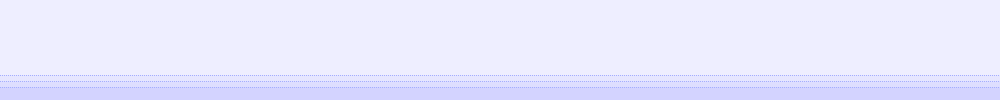【ネムの木】---(掌説2)
縁側で、猫がくるりと丸くなって眠っている。
尾の先が、時折パタン、パタンと動く。シオカラトンボのメスが、耳の先に止まろうとして、何度もチャレンジする。三毛猫の色に似ているから、そこに止まれば見つからないとでも思っているのだろうか。ふわりと止まりそうになると、猫の耳が瞬間、ピクリと震える。トンボは止まり損ねて、また空中に舞い上がる。
こんなことを、何時間見ていたのだろう。風も穏やかで、どこかからかすかに話し声が聞こえてくる。遠くの工事の音が、天井板を伝って規則的にダダダダダッッと空気を震わせる。蛇口をしっかりと閉めなかったのだろう。ポチョン……ポチョンと水の音がする。眠っている猫の姿を見ていると、蛇口を閉めに行く気が起きない。確か昨日までは、家の羽目板にペンキを塗っていた。
一人住まいになって久しい古家の手入れは、年老いた自分が適当にこなしても困ることはない。
有り合わせの色を使ったのでちょっと奇抜な色になったが、近所から文句をいわれる筋合のものでもあるまい。そのほかには何か……。そうか庭の木を伐って束ねたのだった。昨秋から伸び放題だった庭の木を。わずかばかりの木だが、鬱陶しいほどになって居間が暗くなるからと、思い切って枝をおろしたのだった。しっかりしているつもりでも、近頃はとんと忘れっぽくなった。
そうか、それでこんなに眠いんだ。
周三郎は、眠くなった原因を見つけると、安心したように腕枕を直した。猫だってこんなに眠いんだから、年寄りの俺が眠くなってもしようがない。勝手に理屈をつけて、まどろみ始めた。
ゆらゆらと傍らの蚊取り線香が、細い煙をくねらせる。
その煙がふわふわと消え始めるあたりに、うっすらと妻の顔が浮かんで見えた。先に逝かれて、今年で5年目になる。相変わらず寂しいが、仕事で単身赴任したときも、長ければ5年ほど一人暮らしをしたこともある。それを思えば、残りの人生を何とかしのぐことができるだろう。それにこうして、蚊取り線香の煙を利用したりして、会いに来てくれることがある。
妻の優しい顔に見守られるような心地で、眠りの中に落ちていった。
妻の妙は、畑仕事をしていた。単身赴任から帰ると、家を見下ろせる丘の上に立ったころに、妻も自分を見つけてくれる。畦の横に鍬を立てて、麦藁帽子を手に取り、大きく振って合図を送ってくれる。妙の許へ駈け降りたい衝動が突き上げるが、どうにも気恥ずかしい。久しぶりに見る故郷の様子を確かめるように、周囲を見回し、わざとゆっくり足下を踏みしめるように、我が家へ向かった。
ふと顔をあげると、もう妻の姿が見えない。自宅の戸口を開けると、妙の気配がする。だが、どこにいるのかわからない。明るい新緑に慣れた目には、暗い家の中の様子が掴めない。何度かまばたきを繰り返した目に漸く見えたのは、丸く小さな卓袱台の前にちょこんと座って待つ妻の姿である。
煎れたてのお茶が湯気を立て、二人分の昼食が並べられている。もう2時近くなっているのに、食べずに待っていてくれたのだろう。
周三郎がこの家に引っ越してから、何年になるだろう。単身赴任が多い生活から抜け出せそうもないので、少しでも自宅に帰りやすいほうがいいだろうと、都会に居宅を求めたのだ。そして漸く、以前よりも頻繁に帰られるようになった。この家に妻と住んで20年ほどで、周三郎は妻に逝かれてしまったのだった。
眠っているときに見る夢は、いつも妻を探している場面になってしまう。妻の最期に立ち合い、確かに看取ったのだ。それなのに、心の奥ではどうしてもそれが納得できない。どこかで生きているに違いない、それを捜し出してやらねば、という気持ちが、まどろむたびに頭をもたげる。
最近になって、漸く妙の居場所を見つけたのだ。なんとも懐しい田舎の風景の中の、傾きかけた旧居に、一人で住んでいた。庭のツツジの植え込みも、隅を流れる堀の澄んだ水音も、土間の土の匂いも、ひんやりとした涼しさまでもそのままに、妻が立ち、歩いていた。そこに妻が居ることになんの違和感も覚えない自分が、不思議だった。
初めからそこで出会えることがわかっていたかのように、自然に妙の前に座り、昔話に花を咲かせている。自分だけが一所懸命に話しかけるのだが、妻は静かにうなづくだけで、声を聞かせてくれない。少し違和感があるが、周三郎は逢えただけで満足してしまっているようである。不思議な感覚である。
まもなく別れなければならないことは、良くわかっている。でも、なぜ一緒に帰れないのだろう。またここに来れば、いつでも妙に会えることは解っていたことなのだが。
「よくここが分ったわねえ。さあ、入って。」
もともといた自分の家なんだから、分って当然じゃないか。どうしてそんなことを言うんだ? 訝しさを覚えながら、妙の顔を見ようとするが、暗いためか良く見えない。障子を通して射し込む柔らかい光が、20数年前と同じ懐しさで部屋を満たしている。
さらさらと揺れる障子の葉影も、全く変わらない。この前訪ねたときは、もう廃虚のようになっていて、『帰る場所が無くなった』と衝撃を感じたはずなのに、本当はこんなに元のままに残っていたじゃないか。そこに妙まで生活をしていて。
「やっぱり、家はいいなあ。埃を洗い流してくるからな。」
庭に出て、井戸で顔を洗う。井戸も、そこに備えられた桶も、総てそのまま残っている。妻の最期を看取ったのは、間違いがない。しかし、その後の記憶が、現在は朧になっている。
『変な病院に連れていかれたと思ったが、そうか、助かっていたのか。療養でもしていたのだな。田舎に戻っていたのなら、連絡をくれれば良いのに。』
妻がどこに行ってしまったのか、いつも胸にひっかかっていたものが、少し溶けたような気持ちだ。
『少し元気さが物足りないが、ここに居てくれさえすれば、寂しいときにまた話しに来られる。』
顔を洗い、ふと顔を挙げると、そこには明るい田園風景が広がっている。そのすぐそばを、線路が走っている。鉄路のコーン、コーンという音が次第にゴトン、ゴトン、ガタン、ガタンと大きくなり、汽車の吐き出す煙がみるみる近づいてくる。
『あれに乗って、帰らなくては。』
妙に別れのあいさつをしたいが、乗り遅れそうでその暇はない。慌てて駅に走り、列車に跳び乗った。これが後ろ髪を引かれるということなのだろう。古い我が家が遠ざかり、視界の中で小さくなるにつれて、未練が大きく膨んでいく。いつまた会えるのだろう、という不安も、心の隅をよぎる。なぜこんなに慌てて帰らなければならないのか、意味は良く分らない。でも、この列車に乗り遅れると大変だ、ということだけが分っている。
周三郎は、人の気配を感じて目を開いた。縁側の猫は、大きく伸びをしている。トンボは、揺れる蔓草の先でバランスをとりながら、時折目玉をクルリと動かして、羽虫を探している。一瞬で、妻の元から現実の世界に移ってしまった。人の気配は、息子の嫁だった。『気楽なほうが良いから』と同居を断わったために、近所に住んでいつも世話をしに来てくれているのである。今日も、周三郎がそのままにしていた食器を、洗ってくれている。
「あらあら、おじいちゃん、起こしちゃいましたか。御免なさい。」
「あ、寝過ごした。お早う。俺のほうこそ、来てもらったのも知らずに眠っていて……。年寄りは眠るのも仕事のうちだから、勘弁してもらうよ。」
こんな生活が、3年も続いているだろうか。最近では、自分でもいつ起きているのか、いつ眠っているのか、区別がつかないようなときがある。
「今日はずいぶん早く来てくれたんだね。」
「あら、もうお昼ですよ。康平が幼稚園から帰って来たので、一緒にお昼御飯でもどうかと思って、寄ってみたんです。」
「おお、そうか。朝、早起きしたもんで、また寝直して、つい今まで寝ちまったようだな。」
「おじいちゃん、それじゃ起きてないじゃないか。寝ぼ助だなあ。」
幼い康平が、生意気な口調で周三郎の手を引いて起こしてくれる。この間は、まだ暗いうちに来て、どうしたのかと思ったら、『夕方で暗くなったから、雨戸を閉めて帰りますから』と言われたことがあった。その日は、昼寝のつもりが、ついそのまま寝入ってしまったようだった。確か『こんな日は早めに寝るに限る』
と思って、そのまま布団に潜り込んで眠ってしまったはずだった。
自分は、何のために家の補修や庭の手入れをしているのだろう。世間体が気になるからだろうか。あと何年生きるのか判らないが、この調子では起きている時間は僅かなものだろう。
孫は、本物を見たこともない汽車を、畳の上で走らせている。
「先ほどからの工事の音が、近くなって来ましたね。うるさくありませんでしたか。」
『そうか、さっき慌てて跳び乗った汽車の音は、あれか。』
そう思いながらも、周三郎には先ほどの出来事が現実で、現在が夢のようにも感じられる。[夢と現実]、もうそれがどちらでも、気にもならなくなっていた。現在あることも夢、夢もまた夢。
チーッ、チーッという細く甲高い蝉の声が、周三郎の夢の中に突き刺さった。庭のネムの木が、水引細工のような、淡いピンクの花を咲かせている。
© Rakuten Group, Inc.