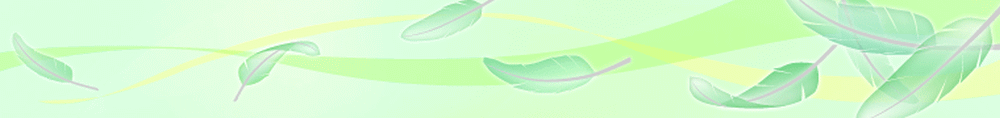白
(2000/08/31)
(夢の話です)
人が住んでいるマチから遠く離れた山の中。
木も生えていない、崖のようなその山肌に、自然に開いた洞穴の奥に、そのヤシロはある。
そこに行けば、今まであったどんなに辛いことも忘れられるという。
どんなに苦しいことも、悲しいことも忘れ、生まれたままの綺麗な心で暮らせるようになるという。
だから、マチに住んでいる者は、苦しいこと、悲しいことがあったら、そのヤシロに向かう。
……存在が確認されていないヤシロに向かっていって、帰ってきた者はいない。
だからこそ、ますます言い伝えは信憑性を持つ。
マチでの暮らしを忘れるほどに、いいところなのだ、と。
僕は、着の身着のまま、マチを飛び出して、言い伝えにしか伝わっていない、そのヤシロを求めて一週間もさまよった。
本当に運が良かったと思う。
森に落ちていた木の実や、川で捕まえた魚を食べて飢えをしのぐ生活も、とっくに限界。
真っ暗なその洞窟の入り口を見つけたときは、空腹と、疲労が見せた幻覚なんじゃないかと思った。
明かりもない鍾乳洞のようなその洞窟の中を更にさまよい、まったく僕は奇跡のようにここにたどり着いた。
ここは天国と勘違いするほどに、綺麗なところだ。
毎日がいい天気で、雨を気にすることもない。川や池には、魚がたくさんいるし、林の方に行けば、動物たちもいっぱい住んでいる。
ヤシロの前は、花畑のように、いろんな色の花が咲き乱れている。
水は澄んでいて、風は柔らかで、緑が目にも優しい。
だから僕も、あのコトを忘れられたんだ。
僕は、白。
名前なんてもう、どうでもいいけれど、ここに来てからは、髪の色と同じ、その名前で呼ばれている。
マチから出てきたときに着ていた、薄汚れた服の代わりに、と言って渡された服も、上下とも真っ白なものだった。
だから僕は、清らかなこのヤシロの中で、上から下まで真っ白な格好で暮らしている。
何ヶ月かすると、ここでの暮らし方がだいたい分かってきた。
言ってみれば、ここは「裏の仕事」をしている。つまりは、人を秘密に殺したり、誘拐したり、奴隷として売っちゃったり。
マチから、救いを求めてここにたどり着く人たちは少ない。
けど、「選ばれた」彼らはここで教育を受けて、そういう仕事ができるようになる。
今までの暮らしを、全部忘れて。
ここに咲いている花には、そういう幻覚作用を及ぼす花粉を出すものがあるらしい。
みんな、マチでの辛いことを全部忘れて、殺人人形のようになって、裏の仕事に手を染める。
どこからそういう依頼が来るのか、とか、そんな難しいことは僕みたいな下っ端には分からない。
けれど、こんな天国のような場所が、実はそういったマチの「黒い」部分を請け負っていると聞いても、不思議と何も感じなかった。
きっと、これも花粉から来る幻覚作用の影響なんだと思う。
最近、僕には感情の起伏がなくなっている。
当然、裏稼業だから、僕たちが「仕事」してる様子はマチの人たちの目には触れないってわけ。
よくできた都市伝説だよね。
僕も、つい最近まで忘れていた。
彼女に身分違いの恋をして、それに絶望してこんな所にやってきた、なんてコトは。
彼女がここの近くにやってきたのは、つい最近のことだ。
洞窟の近くにも、ヤシロの前と同じようなきれいな花畑が何カ所かある。
ちょうど花が真っ盛りに咲いているときで、そこだけヤシロの外なのに、別世界のような光景が広がっていた。
彼女は、ピクニックかなにかでこの近くまでやって来たのだろう。花畑で、たった一人で花を摘んでいるところだった。
「ラン♪ラン♪……ランラン♪ララン……♪」
鼻歌混じりに、花を摘む彼女の姿を、僕は遠目に見た。
周りには、彼女以外の人間の気配はしなかった。僕は、暗殺の仕事を専門にするように訓練されていたから、そういうことが分かる。
その時、僕はもちろん彼女のことを覚えていなかった。
けれど、半ば花に埋もれながら不器用に花を摘むその姿を見て、練習中だったのに、近くに寄っていった。
「花が、好きなの?」
声をかけると、彼女はようやくそれで僕の存在に気付いたようだった。
太陽を背にして近づいた僕を見上げ、まぶしそうに目を細めた。
「ここの花は、きれい。マチでは見たことがないわ」
「そう。僕が、たくさん取ってあげる」
ピンク、青、黄色、白、赤……。一面に咲いている花を、僕は次々と折って、彼女に手渡した。
「あなたは、真っ白なのね。私、白い花が好き」
「そう。じゃ、白い花束がいいね」
僕がそれからは白い花ばかりを摘んで、彼女に渡したので、彼女が持っていた花束は、真っ白い中に、点々と他の色が混ざっている、というものになった。
両手で抱えるようにしてその花束を持って、彼女は帰っていった。
「白い花、きれいね。あなたの髪の色も、同じ。綺麗よ」
「ありがとう」
彼女と交わした会話は、それだけだった。
僕にとっては、久しぶりに(記憶をなくしているので、初めてとも言える)外の人間と話をした体験だった。
© Rakuten Group, Inc.