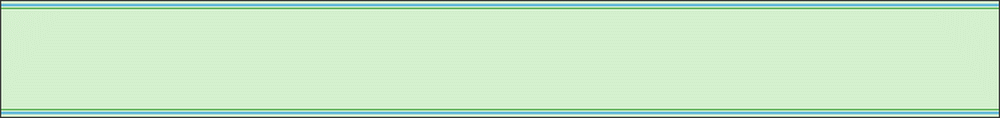テーマ: ★つ・ぶ・や・き★(566028)
カテゴリ: カテゴリ未分類
蚊取り線香の歴史
家庭では蚊を追い払うために、電気式の蚊取り器や、うず巻き型の蚊取り線香を使っていることでしょう。なかでも蚊取り線香は、夏が来たことを実感させてくれる、今でも日本の夏に欠かせないアイテムです。
蚊取り線香の歴史をひもとくと、江戸時代の資料には、「蚊遣り火(かやりび)」と呼ばれるものを利用していたことが書かれています。これは、様々な草木を燃やして煙をたき、蚊を追いやる方法でした。
その後、「除虫菊」という殺虫成分のある花がアメリカから伝わり、1890年(明治23年)に蚊取り線香が誕生しました。当時の形は、長さ30センチ程度の仏壇(ぶつだん)の線香のような縦型で、今と違って運んでいる間に折れやすい上に、長時間はもたず、効き目が弱いものだったのです。
そこで、1895年(明治28年)にこれらの欠点を改善すべく開発されたのが、うず巻き型です。現在のような形は、考案者の奥さんが出したアイデアがヒントになりました。うず巻き型は、縦型のものに比べて、太く、長くなったため折れにくく、持続時間も長く、効き目も良いものになりました。
驚くべき事に、現在使われているうず巻き型は、100年以上前から変わらず、長い間人々に親しまれ、使い続けられているのです。
蚊取り線香のひみつ
蚊取り線香は、電気式の蚊取り器が出回っても、いまだに多くの家庭で利用されています。あの独特の香り、色や形は風情があり、日本の夏の風景には欠かせないものですね。しかし蚊取り線香には、風情があるだけではなく、よく考えられた仕掛けがあるのです。
蚊取り線香一巻きの直径はたった10センチ程度ですが、そのうずをほどいて伸ばせば、なんと全長は約75センチにもなり、この一巻が全て燃え尽きるのにかかる時間は、一晩にあたる約7時間におよびます。ぐるぐるとうずを巻くあのおなじみの形には、長い時間使えるような工夫がほどこされているのです。
また、蚊に効くのは煙だと思っているかもしれませんが、殺虫成分を空気中に散らすために燃やした結果、煙が出るのであって、煙自体は、たき火の時に出るものと同じで、殺虫成分は含みません。殺虫成分は、除虫菊に含まれる殺虫成分を化学合成した「ピレスロイド」と呼ばれるもので、蚊取り線香の、火のついている所から出てきます。
このように、1世紀以上も日本の夏の景色に欠かせないものとして、長い間人々に使われ続けているのには、昔の人のうず巻き型のアイデアと、より効果の高いものを作ろうという努力があったからでしょう。
日本の夏の風物詩だった蚊取り線香は、今ではアジアや南米、中南米など高温多湿の地域にも輸出され、日本だけでなく海外の人々にも必需品となっています。
家庭では蚊を追い払うために、電気式の蚊取り器や、うず巻き型の蚊取り線香を使っていることでしょう。なかでも蚊取り線香は、夏が来たことを実感させてくれる、今でも日本の夏に欠かせないアイテムです。
蚊取り線香の歴史をひもとくと、江戸時代の資料には、「蚊遣り火(かやりび)」と呼ばれるものを利用していたことが書かれています。これは、様々な草木を燃やして煙をたき、蚊を追いやる方法でした。
その後、「除虫菊」という殺虫成分のある花がアメリカから伝わり、1890年(明治23年)に蚊取り線香が誕生しました。当時の形は、長さ30センチ程度の仏壇(ぶつだん)の線香のような縦型で、今と違って運んでいる間に折れやすい上に、長時間はもたず、効き目が弱いものだったのです。
そこで、1895年(明治28年)にこれらの欠点を改善すべく開発されたのが、うず巻き型です。現在のような形は、考案者の奥さんが出したアイデアがヒントになりました。うず巻き型は、縦型のものに比べて、太く、長くなったため折れにくく、持続時間も長く、効き目も良いものになりました。
驚くべき事に、現在使われているうず巻き型は、100年以上前から変わらず、長い間人々に親しまれ、使い続けられているのです。
蚊取り線香のひみつ
蚊取り線香は、電気式の蚊取り器が出回っても、いまだに多くの家庭で利用されています。あの独特の香り、色や形は風情があり、日本の夏の風景には欠かせないものですね。しかし蚊取り線香には、風情があるだけではなく、よく考えられた仕掛けがあるのです。
蚊取り線香一巻きの直径はたった10センチ程度ですが、そのうずをほどいて伸ばせば、なんと全長は約75センチにもなり、この一巻が全て燃え尽きるのにかかる時間は、一晩にあたる約7時間におよびます。ぐるぐるとうずを巻くあのおなじみの形には、長い時間使えるような工夫がほどこされているのです。
また、蚊に効くのは煙だと思っているかもしれませんが、殺虫成分を空気中に散らすために燃やした結果、煙が出るのであって、煙自体は、たき火の時に出るものと同じで、殺虫成分は含みません。殺虫成分は、除虫菊に含まれる殺虫成分を化学合成した「ピレスロイド」と呼ばれるもので、蚊取り線香の、火のついている所から出てきます。
このように、1世紀以上も日本の夏の景色に欠かせないものとして、長い間人々に使われ続けているのには、昔の人のうず巻き型のアイデアと、より効果の高いものを作ろうという努力があったからでしょう。
日本の夏の風物詩だった蚊取り線香は、今ではアジアや南米、中南米など高温多湿の地域にも輸出され、日本だけでなく海外の人々にも必需品となっています。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2010.06.24 13:31:14
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.