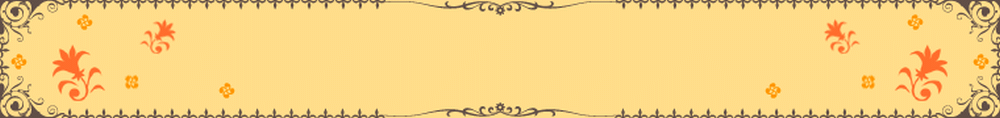PR
X
Calendar
Freepage List
人名索引(旧監督リスト)

監督/外国名/ア~コ

監督/外国名/サ~ト

監督/外国名/ナ~モ

監督/外国名/ヤ~ン

監督/日本字/あ~こ

監督/日本字/さ~の

監督/日本字/は~ん

スタッフ/外国名/ア~コ

スタッフ/外国名/サ~ト

スタッフ/外国名/ナ~モ

スタッフ/外国名/ヤ~ン

スタッフ/日本字/あ~こ

スタッフ/日本字/さ~の

スタッフ/日本字/は~ん

出演/外国名/ア~コ

出演/外国名/サ~ト

出演/外国名/ナ~モ

出演/外国名/ヤ~ン

出演/日本字/あ~こ

出演/日本字/さ~の

出演/日本字/は~ん

テスト(工事中)
映画雑文リスト
作品名(ア行、カ行)

(サ行~ナ行)

(ハ行~英数字)
Comments
Keyword Search
▼キーワード検索
テーマ: 映画レビュー(894)
カテゴリ: キェシロフスキ監督
TROIS COULEURS: ROUGE
Krzysztof Kieslowski
96min
(所有VHS)
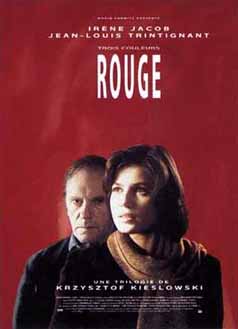
以下は 昨日のページ からの続きです。 『赤の愛』その1 から先にお読み下さい。

(以下たぶんネタバレ)
かつて法学生だったジョゼフは、2才年長の金髪の女性と恋愛関係にあった。たまたま劇場で休憩時間に2階席から持っていた法学書の一冊を下に落とした。拾いに行って、開いているページをなんとなく読む。するとそれが司法試験で出題され、彼はめでたく合格した。恋人も喜んでくれ、万年筆を贈ってくれた(その万年筆は今も使っている)。しかしある日彼が彼女の部屋を訪れたとき、入り口の鏡の中に見たのは、恋人がベッドで別の男と激しく燃えている様子だった。失意と屈辱の中、彼はスイスからフランスを越え、ドーバー海峡を渡ってイギリスへと、恋人とユーゴー・ヘルブリングという男を追った。そしてある日恋人は事故で亡くなった。彼は判事となり、そして恐らく有能で高位の判事となった。しかし心は人間不信になり、それを癒してくれる真実の愛を持った女性に出会うこともなく、法廷では人々の自分勝手なエゴを思い知らされるばかり。真犯人に無罪の判決を下すという間違いも犯した。ある裁判でユーゴー・ヘルブリングの業務上重過失致死の裁判を担当することになり、彼はヘルブリング、かつて恋人を持てる金による贅沢で奪った恋敵に(もちろん正当な判断であったが)「有罪」の判決を下した。この裁判を期に彼は定年前に判事職を辞した。レマン湖(舞台はジュネーブ)の畔の丘の上の静かな高級住宅街にある家に引き蘢った生活を始める。伴侶は雌のシェパードのリタ。その犬を助けたことについてヴァランティーヌに問うように、人というのは結局は自分のためだけに生きているということを確信するためであるかのように、近隣の電話を盗聴していた。プライベートな電話の会話は法廷でより人間の真実がよく見えた。自分の人生を狂わせた恋人の裏切り、それが人間の性であると確認するのが慰めだったのかも知れない。

判事の名前はジョゼフだが、街のカフェ「親愛なるジョゼフ」(Cher Joseph)の2階にはヴァランティーヌが部屋を借りていた。その近くに法学生オーギュストが犬と暮らしていた。彼の2才年長の金髪の恋人カリンはジョゼフの家の近くの高級マンションに住んでいて、その電話もジョゼフは盗聴していた。オーギュストは持っていた本を道で落とし、たまたま開いたページを読んだ。それは司法試験に出題され、彼は合格して判事となる。お祝にカリン(カランと書かれることが多いがカリンとロリは発音していた)は万年筆をプレゼントしてくれた。しかしその後、電話で私設天気情報をやっているカリンなのに、電話には出なくなるし、オーギュストに電話をかけてこなくなる。思い余って彼女のマンションの部屋を窓から覗くと、そこには別の男とベッドで燃えている彼女の姿があった。彼が街に彼女を探すと、彼女は金持ちの男とレストランにいた。二人はヨットでのクルージングの計画を楽しそうに話していた。彼がガラス張りのレストランの窓を万年筆で叩くと彼女はオーギュストに気付く。店を出て「オーギュスト!」と彼の名を呼びながら追ってくるカランだったが、隠れてその声を聞くだけで、オーギュストはそれ以上彼女を追いかけなかった。落胆の彼は飼っていた犬を捨てるために湖畔のポールに縛り車で去る。そして傷心の旅だろうか、フランスを横断してカレーに行き、そこからフェリーでイギリスに渡る。胸には捨てたはずの犬を抱いていた。

このオーギュストの物語は、主人公ヴァランティーヌの物語と平行して描かれる。ジュネーブ大学の学生であり、モデルのバイトもしているヴァランティーヌには、今はロンドンに住む恋人のミッシェルがいた。彼はしばしばヴァランティーヌに電話をしてきたが、それは愛からであるよりも、彼女が貞節であるかどうかを確認するためのようだ。彼女がミッシェルに「愛してる Je t'aime?」と言っても「ボクもだ Moi aussi.」と言うだけで、決して自分から「Je t'aime.」とは言わない。「私を愛してる?」と彼女がきいても「そう思うよ Je crois que oui.」だ。そして近くに肌を感じることも出来ない。たまたまある日、休憩時間に外に出たという偶然が、ヴァランティーヌとミッシェルを出会わせ、二人は恋人になった。真実の愛を見つけたいというヴァランティーヌなのだけれど、この偶然、あるいは選択、それはあるべき運命に収斂されるものではない、間違ったものなのかも知れない。そして彼女に言い寄る写真家ジャンも決して彼女の求める真の愛の人ではない。

ある夜ヴァランティーヌは1匹の犬を撥ねてしまい、首輪にあった住所にリタというその犬を連れて行く。怪我をした犬に無関心な飼い主(J=L・トランティニャン、後で退官した判事とわかる)の様子に怒りを覚えた彼女は、その犬リタを自分で獣医に連れていく。幸いリタの怪我は大したことはなかったが、そこで知らされたのはリタが新しい生命を宿していることだった。彼女はリタを連れて帰って面倒をみ始める。ある日カフェ Cher Joseph で新聞を買うと、そこには麻薬で補導された彼女の弟マルクの写真が載っていた。中に入ってスロットのレバーを引くと、見事チェリーが3つ揃ってコインがじゃらじゃらと出てくる。「悪い予兆か?」と問うカフェの主人に「ええ、理由はわかっている」と答えた。気を紛らすためでもあるかのようにヴァランティーヌは傷も良くなったリタを公園に連れて出る。しかし逃げないと思ってヒモを解くと、リタはいきなり走り去った。しかし見つけることは出来ず、やむなく彼女は飼い主の家を訪ねる。呼鈴を鳴らすとリタが走り出てきた。遅れて出てきた飼い主。ここでのリタがらみでの彼女の笑顔は美しい。飼い主は送った治療費の精算のため小銭を家の中に入ったまま出て来ない。

ヴァランティーヌが家に入ると何やら電話の会話らしきがスピーカーから流れていた。この第2回目のヴァランティーヌと老判事の接見は、神である老判事がヴァランティーヌに試練を与えるという体のものだ。人に善意のあることを信じようとするヴァランティーヌを挫こうというのだ。リタを助けた彼女の動機も、後悔したくないとか、夢で犬に化けて出られて苦しむのが嫌だからとか、結局は自分のためではないか、と問いかける。妻子がありながらホモの愛人を持つ夫、このいずれは起こるであろう家庭崩壊に一体他人は何をすることができるか。ここで前回紹介したのとは別のもう一つのキェシロフスキの親子観も語られる。盗聴した電話での、心臓発作と偽って娘を5度も来させようとした母親のエピソードだ。キェシロフスキが自伝で言うには、親は子供をいつまでも自分が保護したいものとして支配しようとする。しかし子供はそれから逃れようとし、それは子供の当然の権利なのだ。だから親子の関係というのは常に不公正であると言う。なぜ不公正かというのをボク的に敷衍すれば、親はそれが当然の権利だとして子供を支配しようとするが、本来子供の権利であるはず独立をしようとするとき、子供はそこに罪意識を持たされてしまうということだ。そして重要なのは、キェシロフスキが続けて言っているように、そのことを理性で知ることなのである。人の善意、ちょっと言い換えれば隣人愛、ようするには「友愛」、それを信じたいヴァランティーヌは、それの出来ない老判事を「あわれだ」と言い残して去る。

まえがき に書いたので省略する。また 三部作『トリコロール』蛇足 に続く。)

三部作『トリコロール』まえがき
『トリコロール 青の愛』
『トリコロール 白の愛』
監督別作品リストはここから
アイウエオ順作品リストはここから
映画に関する雑文リストはここから
Krzysztof Kieslowski
96min
(所有VHS)
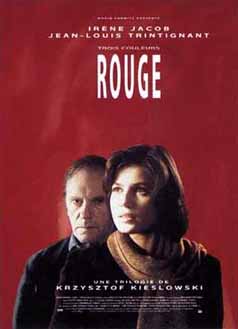
以下は 昨日のページ からの続きです。 『赤の愛』その1 から先にお読み下さい。

(以下たぶんネタバレ)
かつて法学生だったジョゼフは、2才年長の金髪の女性と恋愛関係にあった。たまたま劇場で休憩時間に2階席から持っていた法学書の一冊を下に落とした。拾いに行って、開いているページをなんとなく読む。するとそれが司法試験で出題され、彼はめでたく合格した。恋人も喜んでくれ、万年筆を贈ってくれた(その万年筆は今も使っている)。しかしある日彼が彼女の部屋を訪れたとき、入り口の鏡の中に見たのは、恋人がベッドで別の男と激しく燃えている様子だった。失意と屈辱の中、彼はスイスからフランスを越え、ドーバー海峡を渡ってイギリスへと、恋人とユーゴー・ヘルブリングという男を追った。そしてある日恋人は事故で亡くなった。彼は判事となり、そして恐らく有能で高位の判事となった。しかし心は人間不信になり、それを癒してくれる真実の愛を持った女性に出会うこともなく、法廷では人々の自分勝手なエゴを思い知らされるばかり。真犯人に無罪の判決を下すという間違いも犯した。ある裁判でユーゴー・ヘルブリングの業務上重過失致死の裁判を担当することになり、彼はヘルブリング、かつて恋人を持てる金による贅沢で奪った恋敵に(もちろん正当な判断であったが)「有罪」の判決を下した。この裁判を期に彼は定年前に判事職を辞した。レマン湖(舞台はジュネーブ)の畔の丘の上の静かな高級住宅街にある家に引き蘢った生活を始める。伴侶は雌のシェパードのリタ。その犬を助けたことについてヴァランティーヌに問うように、人というのは結局は自分のためだけに生きているということを確信するためであるかのように、近隣の電話を盗聴していた。プライベートな電話の会話は法廷でより人間の真実がよく見えた。自分の人生を狂わせた恋人の裏切り、それが人間の性であると確認するのが慰めだったのかも知れない。

判事の名前はジョゼフだが、街のカフェ「親愛なるジョゼフ」(Cher Joseph)の2階にはヴァランティーヌが部屋を借りていた。その近くに法学生オーギュストが犬と暮らしていた。彼の2才年長の金髪の恋人カリンはジョゼフの家の近くの高級マンションに住んでいて、その電話もジョゼフは盗聴していた。オーギュストは持っていた本を道で落とし、たまたま開いたページを読んだ。それは司法試験に出題され、彼は合格して判事となる。お祝にカリン(カランと書かれることが多いがカリンとロリは発音していた)は万年筆をプレゼントしてくれた。しかしその後、電話で私設天気情報をやっているカリンなのに、電話には出なくなるし、オーギュストに電話をかけてこなくなる。思い余って彼女のマンションの部屋を窓から覗くと、そこには別の男とベッドで燃えている彼女の姿があった。彼が街に彼女を探すと、彼女は金持ちの男とレストランにいた。二人はヨットでのクルージングの計画を楽しそうに話していた。彼がガラス張りのレストランの窓を万年筆で叩くと彼女はオーギュストに気付く。店を出て「オーギュスト!」と彼の名を呼びながら追ってくるカランだったが、隠れてその声を聞くだけで、オーギュストはそれ以上彼女を追いかけなかった。落胆の彼は飼っていた犬を捨てるために湖畔のポールに縛り車で去る。そして傷心の旅だろうか、フランスを横断してカレーに行き、そこからフェリーでイギリスに渡る。胸には捨てたはずの犬を抱いていた。

このオーギュストの物語は、主人公ヴァランティーヌの物語と平行して描かれる。ジュネーブ大学の学生であり、モデルのバイトもしているヴァランティーヌには、今はロンドンに住む恋人のミッシェルがいた。彼はしばしばヴァランティーヌに電話をしてきたが、それは愛からであるよりも、彼女が貞節であるかどうかを確認するためのようだ。彼女がミッシェルに「愛してる Je t'aime?」と言っても「ボクもだ Moi aussi.」と言うだけで、決して自分から「Je t'aime.」とは言わない。「私を愛してる?」と彼女がきいても「そう思うよ Je crois que oui.」だ。そして近くに肌を感じることも出来ない。たまたまある日、休憩時間に外に出たという偶然が、ヴァランティーヌとミッシェルを出会わせ、二人は恋人になった。真実の愛を見つけたいというヴァランティーヌなのだけれど、この偶然、あるいは選択、それはあるべき運命に収斂されるものではない、間違ったものなのかも知れない。そして彼女に言い寄る写真家ジャンも決して彼女の求める真の愛の人ではない。

ある夜ヴァランティーヌは1匹の犬を撥ねてしまい、首輪にあった住所にリタというその犬を連れて行く。怪我をした犬に無関心な飼い主(J=L・トランティニャン、後で退官した判事とわかる)の様子に怒りを覚えた彼女は、その犬リタを自分で獣医に連れていく。幸いリタの怪我は大したことはなかったが、そこで知らされたのはリタが新しい生命を宿していることだった。彼女はリタを連れて帰って面倒をみ始める。ある日カフェ Cher Joseph で新聞を買うと、そこには麻薬で補導された彼女の弟マルクの写真が載っていた。中に入ってスロットのレバーを引くと、見事チェリーが3つ揃ってコインがじゃらじゃらと出てくる。「悪い予兆か?」と問うカフェの主人に「ええ、理由はわかっている」と答えた。気を紛らすためでもあるかのようにヴァランティーヌは傷も良くなったリタを公園に連れて出る。しかし逃げないと思ってヒモを解くと、リタはいきなり走り去った。しかし見つけることは出来ず、やむなく彼女は飼い主の家を訪ねる。呼鈴を鳴らすとリタが走り出てきた。遅れて出てきた飼い主。ここでのリタがらみでの彼女の笑顔は美しい。飼い主は送った治療費の精算のため小銭を家の中に入ったまま出て来ない。

ヴァランティーヌが家に入ると何やら電話の会話らしきがスピーカーから流れていた。この第2回目のヴァランティーヌと老判事の接見は、神である老判事がヴァランティーヌに試練を与えるという体のものだ。人に善意のあることを信じようとするヴァランティーヌを挫こうというのだ。リタを助けた彼女の動機も、後悔したくないとか、夢で犬に化けて出られて苦しむのが嫌だからとか、結局は自分のためではないか、と問いかける。妻子がありながらホモの愛人を持つ夫、このいずれは起こるであろう家庭崩壊に一体他人は何をすることができるか。ここで前回紹介したのとは別のもう一つのキェシロフスキの親子観も語られる。盗聴した電話での、心臓発作と偽って娘を5度も来させようとした母親のエピソードだ。キェシロフスキが自伝で言うには、親は子供をいつまでも自分が保護したいものとして支配しようとする。しかし子供はそれから逃れようとし、それは子供の当然の権利なのだ。だから親子の関係というのは常に不公正であると言う。なぜ不公正かというのをボク的に敷衍すれば、親はそれが当然の権利だとして子供を支配しようとするが、本来子供の権利であるはず独立をしようとするとき、子供はそこに罪意識を持たされてしまうということだ。そして重要なのは、キェシロフスキが続けて言っているように、そのことを理性で知ることなのである。人の善意、ちょっと言い換えれば隣人愛、ようするには「友愛」、それを信じたいヴァランティーヌは、それの出来ない老判事を「あわれだ」と言い残して去る。

まえがき に書いたので省略する。また 三部作『トリコロール』蛇足 に続く。)

三部作『トリコロール』まえがき
『トリコロール 青の愛』
『トリコロール 白の愛』
監督別作品リストはここから
アイウエオ順作品リストはここから
映画に関する雑文リストはここから
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[キェシロフスキ監督] カテゴリの最新記事
-
キェシロフスキ監督の編集/『トリコロー… 2008.10.10 コメント(2)
-
クシシュトフ・キェシロフスキ監督『トリ… 2008.05.13 コメント(4)
-
『トリコロール 赤の愛』クシシュトフ・キ… 2008.05.11
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.