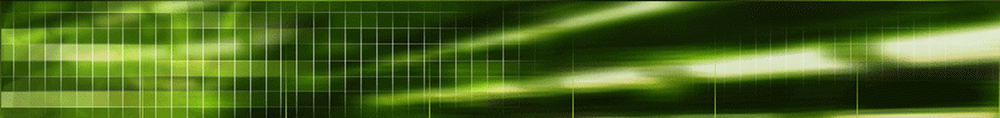OYOZRE 【MORIHIKICO】
噂は、所詮噂。
在りもしない噂。
では、在りもしない噂は何故生まれる?
それは、本当に噂か?
噂に、真実は無いのか?
噂は発展すると伝説化する。
根拠は無いものがほとんどだろうが
決して、OYOZREだと、決め付けること無かれ
【MORIHIKICO】
「キモい」
「汚い」
「ウザイ」
「死ね」
僕が毎日のようにクラスの皆から言われている単語だ。
僕は笠井健吾。11歳の小学5年生。
僕はイジメを受けてるんだと最近になって思い始めた。
別に特別鈍感なわけではない、ただ僕自身が認めたくなかっただけなのかも知れない。
もう言われ慣れてしまったけど、それでもクラスの皆は僕を生ゴミ扱いする。
この日は一日中雨だった。
当然僕の傘も僕の靴も無い。いつも隠される。
僕はゴミ箱の中から自分の靴を見つけたが、傘はどこにも見当たらなかったので、僕は濡れながらも走って帰る。
周りの子が僕を見て笑ってる。笑い声が耳の中に入ってくる。
僕は気にせず家に向かって走った。こんなのもう慣れたもんだ、いつもと変わらないんだ。
僕は走り疲れて雨が降る中、息を整えながら歩いていた。
すると突然、僕の体に雨が落ちてこなくなった。誰かが後ろから僕に傘を差してくれている。
僕は思わず振り返ると、白いコートを着たおじさんが立っていた。
顔は銀色の髪の毛で隠れて良く見えないけど、薄っすらと微笑んでいるようにも見える。
大きくて結構重そうな白い木箱を背負って、おじさんは僕に話しかけた。
「今日は、一日中雨です。傘を持たない君は、雨に濡れるのが、好きなのですか?」
僕は咄嗟に「違います!」と言いそうになったが、喉まで出かかった言葉を飲み込んだ。
言ってしまえば、僕の事を聞いてくる・・・この一日中雨の中、傘も差さずに登下校する変な子供として。
僕はこの事を他人でさえも知られたくない。家族にだって勿論知られたくない。
自分がイジメられているなんて、知られたくない・・・
僕はおじさんを無視して歩き出した。
でもおじさんは僕の後を付けて来る。僕は気にせず走り出そうとしたが、僕の手におじさんがソッと何かを掴ませた。
僕の手の中にはおじさんの傘が有った。
「私は意地悪なもので、からかって申し訳ありません。その傘は、差し上げます。」
僕は慌てておじさんに傘を返そうとした。このままではおじさんが濡れてしまうから。
けれどおじさんは「私は、ここらに用があるんです。」と言い、去っていってしまった。
僕は腑に落ちないまま帰路に着いた。
家に帰ると母さんが僕を出迎える。父さんは居ない、僕が5歳の時に事故で死んでしまった。
だからいつも晩御飯は母さんと二人で食べる。母さんは今日学校はどうだったかいつも聞いてくる。
僕は本当の事が言えない、母さんに本当の事なんか言えないから
いつも「楽しかったよ」などの嘘を言う。でも、母さんはあのおじさんから貰った傘を見つけた。
「この傘・・・健吾のじゃないわよねぇ・・・誰の傘なの?」
僕は本当の事が言えなかった。だから「失くしちゃって、走って帰ってたらおじさんが傘をくれたんだ」と言った。
僕は傘を失くした事と、知らない人から傘を譲ってもらった事で叱られた。
翌日、天気予報では今日も一日中雨だった。
最近異常なまでに雨が続いている・・・僕は自分の傘は隠されてしまったのでおじさんの傘を差して登校する。
今日は昨日と比べて、外は薄暗く、雨も強めに振っていた。
僕は早足で学校へ向かった。すると、正面から誰かが僕の横を通り過ぎた。
傘は差していない、びしょ濡れで髪は足まで伸びている女の子だった。
白いワンピースを着ているが、僕はそれよりも女の子の腕や足が痣だらけなのがとても気になった。
足が悪いのだろうか、右足を引き摺って歩いている。しかも女の子は靴を履いていない。
女の子は足を引き摺りながらもどんどん歩いていく、僕は振り返り、もう一度確かめようとしたが
「また、会いましたね。」
僕の後ろで誰かの声がした。僕はゆっくり振り返ると、傘を差した昨日のおじさんが目の前に立っていた。
そして僕は慌てて女の子の方へもう一度振り返ると、女の子はもう居なくなっていた。
「見た、のですね?」
おじさんが静かに言った。僕は何を見たのかあまりよく分からなかったが
「あの、女の子の事ですか?」
と聞き返した。おじさんは髪を顔から避けて、僕を見た。
髪で隠れて良く分からなかったおじさんの顔は、僕が思っていたよりずっと若そうであった。
「君には、見えたのですか・・・それだけ聞ければ十分です。では、私はこれで。」
そう言って頭を下げ、おじさんは女の子が歩いていった方向へと去っていった。
僕が学校に辿りつくと、クラスの皆は僕を白い目で見る。
毎度の事なのだが、僕の机の上には、登校してくると必ず花瓶が置いてある。
置く奴はもう分かってる。クラスのイジメのリーダーでもある【立石亮平】だ。
でも、今日は僕の机の上に花瓶は置かれていなかった。
立石の奴も来ていない・・・立石の机の上に
花瓶が置いてある。
担任の先生が教室に入ってきて、悲しい顔をしながら立石の事を話している。
クラスメイトは誰一人気にする様子すら無い。
休み時間に職員室を通り過ぎると、「今朝、立石君が路上で全身打撲で亡くなっていた。」と先生達が話し合っている。
僕も立石の事は気にはしなかった。あいつも多分クラスでは要らない存在だったのだろうか。
僕は今日も沢山の奴らに罵倒された。
でもこれもいつもの事なんだ、だから、何も気にしなくて良いんだ。
「おまえなんで生きてんの?さっさと死ねよ、ゴミ」
クラスメイトの【金井正人】が僕の耳元で言う。
これも、これも、いつもの事だから。
そして昨日と同じ、下校しようとすると靴を隠され、傘も・・・・・有る・・・・
おじさんに貰った傘は、誰にも隠されずに傘立てにソッと置かれている。
僕は隠された靴を発見し、土砂降りの雨の中、おじさんの傘を差してゆっくりと歩いて帰る。
帰り道では沢山のお巡りさんが見回りをしている。
立石が死んでいた場所は黄色いテープが貼られているが、今でも沢山の人が群がっていた。
僕はその場所を見た後、無意識に早足で家に帰った。
僕は、何故か薄っすらと笑っていたのだ。
母さんと晩御飯も食べ終わって、午後8時を過ぎようとしている時だった。
母さんは僕に「近くの自販機で飲み物を買ってきて」と頼んだ。
近くとは行っても家からは200mくらい離れている。
僕は家から出るのがとても怖かったが、渋々行く事にした。
暗い夜道を雨の中、傘を差しながら独りで歩く、ここら辺は電灯も少なく、非常に視界が悪い。
僕は少しビクビクしながら、自販機を目指した。
無事自販機に付き、缶ジュースを3本買った後、僕は「ふぅ・・・」と溜め息を付いた。
一気に気が抜けた感じだった。元々暗い場所は怖いけれど、僕の頭の中は何故か【立石亮平】の事でいっぱいになっていた。
何故今になってこんな事を思い始めるのだろう。
でも、立石に起こった事が僕に起こらないとは限らないと思い始めてから
僕はずっと、この夜道を歩く間は、小刻みに震えていたんだろう。
僕は傘を持ち直し、缶ジュースを3本抱えて、元来た道を戻ろうとした。
僕の前方から何かがゆっくりと近づいてくる。
ずり・・・ずり・・・ずり・・・
この引き摺るような音は何だろう・・・電灯が無い場所から聞こえてくるので姿がよく分からない。
徐々に電灯の有る場所へ【何か】が近づく。
電灯の光で、【何か】の姿が僕の目に映った。
今朝見たあの女の子だった。
僕は少し気が落ち着いた。女の子の姿を見れば、少し顔は強張ってしまうが
人であっただけで、僕は物凄く安心したのだ。
女の子は右手に何か持っているようで、さっきの音はソレを引き摺る音だったんだ。
僕は気にしながらもなるべく早足で家に帰ろうとしたが
電灯の光が女の子の引き摺っていたモノを照らした。
全身傷だらけで仰向けのまま白目を剥いているクラスメイトの【金井正人】だった。
僕は抱えていた缶ジュースを全て落としてしまった。
僕の体が無意識に震える。震えが止まらない。
足に力が入らない。今にも座り込んでしまいそうだ。
金井の右足を掴んで引き摺っていく女の子。金井の服や体はボロボロになっておりまだ金井かどうかは確信がなかった。
だが、Tシャツから取れかかっている名札で確信した・・・僕のクラスメイトの金井正人だということが。
女の子は僕に見向きもせず、どんどん前に進んで行く。僕は早くその場から逃げ出したかったので
缶ジュースも拾わず走り出そうとした瞬間。
金井が呻き声を上げながら僕に向かって手を伸ばしている。
白目を剥いたままで言葉にならない呻き声を上げ、引き摺られる事に抵抗しようと必死にもがいている。
「う゛あ゛あ゛・・・あ゛あ゛あ゛・・・」
僕は耳を塞いだ。金井の呻き声を聞きたくは無かった。
「あれが、噂。君の知り合いは、殺されてしまいますね。」
いつの間にか、僕のすぐ側に、あのおじさんが立っていた。
手には分厚い本を広げていて、女の子を見つめながら呟いたのだ。
「さて、君の知り合いはこのままだと殺され、今朝の亡くなった少年と同じようになる・・・いかがです?」
そう言うと、おじさんは今度は僕を見た。おじさんの目は真剣だった。
僕は意を決して聞いてみた。
「あの女の子は・・・何なんですか?・・・」
「噂です。ひきこさんというのは、ご存知ありませんか?」
「・・・知りません・・・」
「そうですか・・・まぁ無理もないですね。基本的にマイナーな噂ですから。私も、ここに来るまでは見た事がありませんでした。」
おじさんはペンを右手に持ち、サラサラと本に文字を書いていく。
「ここには、この噂を知る者が多い。ここに来て良かったです、本当に。」
おじさんは満面の笑みでペンを走らせている。
そして、一旦ペンを止めて背負っている白い箱を降ろすと、箱の中から手鏡を取り出し、僕にこう言った。
「君の知り合いをこのままにしておくも良し、助けるもまた良し、君は、選ぶならどちらを選びますか?」
おじさんの言葉に、僕は物凄く迷っていた、何故こんなにも迷っているのだろう。
人が殺されるのに、何故助けようと思わないのだろう。
だって、僕は、こいつが嫌いだから。
でも
僕は無意識に自分の意思とは無関係に、こう呟いた。
「どうすれば良いんですか・・・?」
おじさんは目をさらに細め、手に持っていた手鏡を僕に手渡した。
「それで、噂の顔を映すのです。あの噂は、いじめに遭い、虐待に遭った【森 妃姫子】だと言いますが、それも全ては噂でしかありません。」
僕は一瞬、恐怖を感じなくなった。足の震えが止まった。
さっきまで足がすくんで動けなかった僕が、嘘のように体が軽くなった。
おじさんはさらに話を続ける。
「噂の一番嫌いな自身の顔、いじめで傷つき、虐待で傷つき、化け物の様になってしまった自身の顔を、その鏡で映すのです。」
おじさんが言い終わると同時に、僕は傘を放り出して、走って女の子の前に回りこんだ。
それでも女の子は止まる気配も無く、金井を引き摺りながら進んでくる。
僕は女の子の顔に鏡を向けた。
黒髪が前も後ろも足の膝まである長い髪から、鏡にだけ映る顔。
痣に切り傷、そして腫れた目からは途切れない涙。
僕の持つ手鏡だけ、その顔は映った。
そして、僕は、気を失った。
目が覚めると、自分の部屋のベッドの中だった。
外は久しぶりの晴天。眩しい太陽の光が、部屋の窓から差し込み、僕の姿を照らす。
あの出来事は・・・夢だろうか
ただ、夢ではない鮮明な記憶ではあるが、途中でプッツリと途切れてしまっている記憶。
夢だろうか・・・夢ではないのだろうか・・・
ふと、僕は右手に何かを持っている事に気付いた。
おじさんが僕に渡した、手鏡だった。
良く見ると手鏡には大きな亀裂が入っていて、僕が手鏡を持ち上げると、鏡の部分が落ち、バラバラに割れてしまった。
落ちた場所は布団の上なのだけど、鏡は見事に粉々になっていた。
昨日の夜の出来事は、夢なんかじゃない。
そして僕の頭には、金井の事が浮かんできた。
あいつはどうなったんだろう・・・
走って学校に向かった僕は、金井の机に花瓶が置かれてない事を確認した。
担任の先生の話では、金井は病院に入院しているようだ。
詳しくは分からないけど、僕はとても安心したんだ。
それから僕は、イジメられなくなった。
イジメのリーダーでもあった立石が居なくなって、金井も僕にちょっかいをかける事は無くなった。
そして今、僕には沢山の友達が居る。
僕は、毎日がとても楽しくて、とても幸せだった。
そして数日経った雨の日
僕は、おじさんと再会した。
「おや、君は・・・随分と、顔色が宜しくなりましたね。」
「久しぶりです、おじさん。」
「おじさん・・・ですか、私は、まだ、二十になったばかりですけどねぇ」
「あ、ごめんなさい・・・」
「まぁ、小父さんとは、大人の男性を意味しますし、私も二十を超えているので、間違いじゃぁないかも知れませんねぇ。」
そう言うとおじさんは薄っすらと微笑んだ。
僕も薄っすらと微笑み返し、おじさんにこう言った。
「おじさんは・・・こうなる事を、全部分かってた?」
「いいえ、正確には、上手く事が運んだ・・・と、言った所でしょうか。」
「でも、金井を助けれたのは、おじさんのおかげだし・・・」
「私は、本を書き上げたくて、君を利用しただけですよ。まぁ、まだ書き終えては居ないので、もう少しこの地に滞在しようかと。」
「そうなんだ・・・じゃぁまた会えるよね?」
「・・・・会えると良いですね。では、私は用が有るのでこれにて。」
雨の中、笑顔で君は私に「さようなら!」と言った。
私はまだ書き終えていない本を手に、雨の中、傘を差しながら歩く。
傘か・・・まだ、私のあの傘を持っていた・・・また会えるのだろうか。
グシャっという音が、私の後方から聞こえてきた。
私は振り返った。活き活きとしていた君が居ない。
さっきまで君が居た場所は、鮮血に染まっている。
私の傘が、持ち主が居たすぐ側に落ちている。
「いじめられている子供は襲わない・・・いじめられなくなった君にとって、これが、幸せだろうか・・・」
私は手に持っていた本を広げ、残りのページを全て書き終えた。
「本は、書き上がりました。この傘は、返してもらいますね。」
私は傘を拾い上げ、開いている傘を閉じた。
「すみません。もう、会えそうに、ありませんね。」
まだ意識がある僕は
イツマデヒキズラレルノ?
END
© Rakuten Group, Inc.