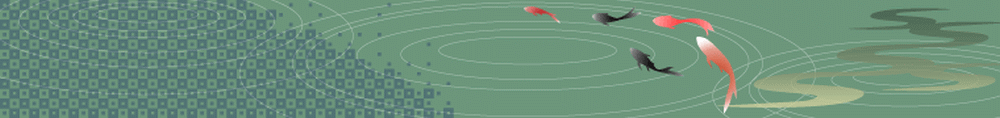考古学・歴史日記02年後半
今日の夕方も講演だった。今日の日記のタイトルの通り、今月初めに略奪および破壊されたイラクの博物館とその収蔵品についての講演だった。講師はミュンスター大学のウルリケ・レーヴ氏。ドイツ・イラク協会の会長を務めるうちの大学のS教授はイラクの状況を視察するために今バグダードに行っているそうで、講演の前の挨拶は僕の先生がした。
講演の前半はイラクの文化財の重要性について、後半は略奪・破壊の現状についての報告だった(彼女はこの間イラクに行ったわけではないので伝聞だったが)。
講演で強調されていたのは、イラクの地に眠るメソポタミア文明が「我々西洋世界の文明の源」であるということだった。これは僕の先生も言っていたのだが(「メソポタミア文明なくして我々の文明はあり得なかった」)、そういう言い方をされると東アジアから来た僕らはどういう反応をすればいいのか困ってしまう。まあここはドイツだから良しとするか。
メソポタミア文明に起源をもつものは数え上げればきりが無い。文字、数学、天文学(暦なども)、都市、灌漑、宗教、文学、法律、ビールなどなどなど形而上的なもの形而下的なもの取り混ぜて、こんにちのほとんど全ての人類が当たり前のように接しているものが、今のイラクの地に起源を持っている。
こんにちのイラクの地はメソポタミア文明の舞台であり、あちこちに遺跡がある。ドイツはその中でももっとも重要なウルク(最古の都市の1つ)、バビロン(「ハンムラビ法典」や「バベルの塔」などで有名)、アッシュル(アッシリア帝国の古都)での発掘を手がけている(昨日のペルガモン同様、バビロンのもっとも華麗な「イシュタル門」はベルリンに運ばれて博物館の中に復元されている)。
もっとも、こうしたメソポタミア文明の重要性はフセイン政権も熟知していた。フセイン大統領は自分をハンムラビ王(紀元前18世紀のバビロニア王。「ハンムラビ法典」で有名)やネブカドネザル2世(紀元前6世紀はじめのバビロニア王。ユダ王国を滅ぼしてユダヤ人をバビロンに連れ去ったいわゆる「バビロン捕囚」で知られる)に擬することを好んでいたというし、遺跡や考古学を国威発揚の道具に使っていた。そのためフセイン政権は、湾岸戦争までは文化財行政に比較的熱心であった(もっともバアス党政権の官僚主義などのために、研究が自由に行えるとはとても言えない状況ではあったが)。
湾岸戦争(1991年)の頃から、イラク政府が文化財行政にまで手を回せなくなったために、イラクからの文化財の不法な流出や盗掘が横行することになった。そして、こんどの戦争である。
略奪の状況はまだよく分からないが、一部にはあきらかに特定の遺物を狙った組織的な犯行もあったという。とにかく、バグダードのイラク国立博物館の遺物の8割が略奪・破壊され、所蔵品目録は床に撒き散らされて出土品の照会はほとんど不可能になった。
考古学では、出てきた遺物そのものも重要だが、その出てきた周囲の状況を記録することが極めて重要である(その盲点をついたのが日本で起きた「石器ねつ造事件」だったのだが)。例えばたくさんの金製品が副葬された王の墓が見つかった場合、盗掘されたら「骨と金とが一緒に出てきた」ということが分かるのみで、それが王の墓であるかどうかも分からなくなってしまう。考古学者が発掘した場合でさえも、出土状況の記録があいまいだと資料的価値を大きく損なってしまう。今回のイラク博物館の状況は、その所蔵品の考古学的価値をほとんどゼロにしてしまったといっていいだろう。
またイラクの博物館には未解読の粘土板文書が多く所蔵されていた。そこに書かれていた古代の叡智は、永遠に失われてしまったに等しい。
戦場で命をかけている兵士や、貧困に苦しむイラクの人々、そして自分が世界の秩序を守っていると信じているアメリカ政府の人々には、朽ちてなくなっていてもおかしくない古代の遺物など、とるにたらないのは分からないでもない。しかしこの度の出来事はおそらく人類が続く限り、汚点として語り継がれることになるだろう。特にヨーロッパは海外から文化財を略奪した前科があるし、自らも文化財の略奪をヨーロッパ内でお互いにし合ってきたので(ドイツはこの2点とも人後に落ちない)、この問題にはアメリカよりも敏感なようである。
ともあれ、失われたものは戻ってこない。こればかりは日本政府がいくら金を出しても取り返しがつかないのである。正直なところ、がっくりとして言葉も無い(大英博物館やルーヴル美術館が略奪されて空っぽになった状況を想像してみるといい)。そして、文化というのは何と無力なことだろう。
まだ状況が混沌としているが(第一イラクでの戦争集結もまだ宣言されていない)、僕もいずれ及ばずながら力になれないだろうかと思っている。
2003/05/04(日) ローマ兵士の暮らし (日記というか備忘録)
先々週くらいの日記でこんにちのアメリカ帝国と2000年前のローマ帝国を比べるような日記というか備忘録を書いたが、この週末も暇をみてはローマ帝国についての本を読んでしまった。マンハイムの博物館で買った少年向けの本である。そのタイトルがなんと「私達のなかのローマ人」(Frank Kolb,「Die Roemer bei uns」)。ドイツとローマ帝国のかかわり(ドイツ国内のローマ遺跡やゲルマン人とのかかわり)や、ローマ人の日常生活などが分かりやすく書かれている。
その中で、ついローマの軍事について目が行ってしまった。今のアメリカ帝国はなんといっても軍事で世界に覇権を唱えているからである。では、ローマ帝国を支えたローマ兵士の実態はどうだったのだろう。
ローマ帝国はその最盛時(1~3世紀)に35万人の兵士をもっていた。これだけの常備軍を持っていた国は当時の世界ではローマと中国以外にはないだろう(ちなみに数だけでいえば、現代のアメリカ帝国よりも中国のほうが兵士数は多い)。機動軍はおよそ30個の軍団(Legion、一個軍団は最大6000人)に編成され、最前線の国境地帯に配置され、東方のペルシアや北方のゲルマン人の侵入に備えたり、内乱に対処したりしていた(時々軍そのものが叛乱を起こして皇帝の首をすげ替えたりしたが)。
驚きはローマ軍の兵役の長さである。兵役は普通20年、「ローマ人」以外の異民族では25年であった。18歳から26歳までの間に役所の兵士募集に応じて志願した。職業軍人ならまあこれくらいの兵役は驚くことも無いが、今の北朝鮮では徴兵義務の兵役が最大12年あるという(最近10年に短縮されたというが。北朝鮮のような小国(人口2200万人)が120万もの大軍隊を維持するにはそれくらいの兵役は必要なのだろう)。
兵士になる理由は様々にあるが、非ローマ人の場合、兵役を終えるとローマ市民権を得られるのが大きかった。ゲルマン人やトラキア人といった異民族は、ローマ軍に投じてその武勇を発揮し、年季を終えると晴れて「ローマ人」となった。フランスの外人部隊に比較することも出来るが、やはりこんにちのアメリカ軍と似ているといえるだろう。今やアメリカ軍の何割かは、こうした兵役後のアメリカ国籍目当ての「異民族」(ヒスパニックや中国系)が占めているという(もっともローマ軍同様、彼ら異民族の役目はあくまで「補助」であるが)。僕は見なかったが、最近の映画「ギャング・オブ・ニューヨーク」の冒頭シーンは、アイルランド移民がニューヨークに着くや、入国許可と引き換えに、当時の南北戦争に兵士として参加することを強制させられるシーンだったという。19世紀にはもうそうだったのか。
入営した兵士は4ヶ月の訓練期間を受ける。なかでも行軍訓練がもっとも苦痛で、40キロ近い荷物(食器や毛布、三日分の食料、工具など)を担ぎ、10キロある鎧兜を着け、5時間で36キロを歩かなければならなかった。訓練期間後、各部隊に配置される。軍隊の仕事は戦争がもちろんだが、普段は訓練とパトロール、そして屯田や建設事業といったさまざまな任務を与えられていた。北朝鮮や中国では軍隊が独自に資金を稼いでいるが、それに近いのだろうか。
1世紀頃の場合、兵士の月給は225デナリウス(銀貨)。これに対してケントゥリオ(100人隊長、中堅士官)は3750デナリウス、上級士官は7500デナリウスだった。もちろん異民族兵士はより安い賃金であった。ちなみに1デナリウスは8アス(銅貨)で、10アスでおよそ5キロの小麦もしくは1リットルのオリーブ油が、60アスで長い服一着が買えたという。食費・住居費などの諸経費は給料から天引きされ、さらに重労働を避けるために上官に袖の下を渡すことも必要だったらしい。給料は年に3回支給され、基本給とは別にボーナスや支度金、退職金もあった。
兵士たちは日常8人部屋の狭い兵舎に住んでいた。兵士の結婚は法的には許されなかったが、実際には兵舎の外に妻子をもち、退役後正式に結婚するものが多かった。軍隊では食料が豊富に支給された。食べ物の恨みは恐ろしいというか、兵士の待遇への不満は反乱に繋がるとして(実際たびたび反乱が起きている)、危険視されたためである。飢饉でも食料が優先的に供給される北朝鮮軍みたいではある。
ケントゥリオは兵士からたたき上げのヴェテランが就任したが(兵士とケントゥリオの間には150の階級があり、細かく給料や役職が規定されていた)、参謀将校は経験を無視して家柄が問われ、その中から軍団指揮官が選ばれた。そこはしっかり身分制なのである。
ローマ軍はもともと文民統制の原理で動いていたが(カエサルも文民として軍隊の上に立っていた)、3世紀には軍人皇帝という武力を背景に権力を奪取する皇帝を輩出するに至り、やがて皇帝権力や帝国の構造そのものが変質し、軍隊における異民族(特にゲルマン人)の割合が増加していった。それはローマ帝国の衰亡の始まりでもあった。
国連という一応の国際秩序を無視して動き出したアメリカ帝国だが、その行く末が非常に見物である。本質的にアメリカ帝国とローマ帝国は違うのかもしれないが、つい比べずにはいられない。軍隊で見る限り、アメリカ帝国にとっての「ゲルマン人」はヒスパニックになるのだろうか?(かつては国内の黒人がその位置にあった)。それとも違った衰亡プロセスを辿るのだろうか。
2003/05/05(月) イラク問題
夕方は講演会を聴きに行く。昨日イラクから帰ったばかりのゾンマーフェルト教授(ドイツ・イラク協会会長)の体験談である。いつになく早口で興奮したように話していた。
アメリカ軍はあれほど戦闘に関しては入念な計画を立てていたのに、イラクの民生についてはほとんど考慮していなかった(日本やドイツのように占領出来ると思っていたのだろうか)。バグダード市民は困窮している。ガソリン一缶得るのに5時間行列しなくてはならない。電気は一日(?)2時間、電話はまったく通じないので衛星携帯電話のみである。さらには無法状態がまだ続いており、時々銃撃戦も起きている。子供たちは爆撃の恐怖から、ちょっとした物音にもびくっとする。戦争が終わってしまうとマスコミは途端に報道量を減らしたようだが、イラク市民の困窮はむしろ今のほうがひどくなっているらしい。そんな中、市民同士の互助活動もささやかながら行われているという。
教授は略奪されたイラク博物館の視察目的でイラクに行ったわけだが、あの略奪も、貧乏な一般市民の大群とは別に、明らかに奪うべき文化財を熟知した目的化・組織化・システム化された略奪団が居たという。同じ事は政府庁舎への略奪もそうで、一般市民には手に入れにくいガソリンや可燃物を撒いてわざわざ建物や書類を灰にした組織化された一団が混じっているという。その背景は分からない。
さらに教授はイラクの今後についての見通しを語ったが、イラクにアメリカ流の「民主主義」が根付くことはないだろうとの予測を述べた。イラクが三つほどの国家に分裂する可能性もあるという。また多数派であるシーア派は徹底して反アメリカで、イランのようなイスラーム国家の樹立を目的としているというし、アメリカが連れてきた反政府活動家・チャラビ氏の手下は銀行強盗をしたり豪邸の住人を追い出して自分の家にするようなことをしているといい、フセイン政権と変わることのない政治手法を取らざるを得ないのではないかと見られている。つまりは、アメリカにとっては1990年までのフセイン政権と同じである。
司会の政治学の教授は「世界の人口の4%にすぎないアメリカ人が、世界の石油産出量の26%を使っている」と述べ、あの戦争がやはり石油目的の戦争ではないかという見方をしていた。会場には教授の姿もあれば(僕の先生も来ていた)、平和活動家のような人もいた。
さてゾンマーフェルト教授は、イラクの中でもイスラーム教シーア派の聖地であるカルバラとナジャフでは略奪行為は一切無かった、と言った。そこでは政府がなくなっても住民が見事に組織化され治安を維持していたという。
この話を聞いて思い出したのが、北アフリカ出身のアラブの歴史家イブン・ハルドゥーン(1332~1406年)の「歴史序説」である。彼は北アフリカを主な考察対象として、政治権力の変遷を、粗野だが連帯意識(血族意識)の強い活力溢れた「田舎(バドウ)」と、洗練されているが連帯意識を喪失した「都会(ハダル)」(技術・文化装置による社会的結合原理)との循環的交代で説明した。衰えた「都会」の文明を「田舎」が征服するが、権力の座に着いた元「田舎」の人々は「都会」化していき(大体3世代くらいかかる)、別の「田舎」に征服されるというわけである。
王朝が交代するとき、社会にカタストロフィーが起きると思いがちだが、実際にはそうはならなかった。それはこの地域にはイスラームという普遍宗教が存在し、「国家」に対する「社会」の優位、「政治」や「経済」に対する「文化」の優位が確保されいるためだ、とハルドゥーンは考えていた。
さて、今回のイラクである。おそらくこの種の政権崩壊後の社会的混乱や無法状態は、長い中近東の歴史ではほとんど無かったことではないだろうか。それはフセイン大統領のバアス党がイスラームを否定して世俗主義を取った1958年以来の統治の結果かもしれないし(彼は政権の末期にはイスラームにすがる姿勢を見せ、演説や国旗にイスラーム色を出していたが)、「征服者」がムスリムではなくアメリカ軍というあまりに異質な文明により、突然といっていい速さで行われたことがあるだろうか。こうした中で、カルバラやナジャフの平穏ぶりはむしろ伝統的なものと言っていいのかもしれない。
もしイラクに「民主的」選挙を行うと、アルジェリアのように原理主義政党が勝ってしまい、イランのようなイスラーム国家ができてしまうだろう(アルジェリアの場合、原理主義化を危惧した軍部が選挙を無効にして戒厳令を敷いた。またイランでは制限付き(聖職者しか大統領になれない)とはいえ、トルコやイスラエルと並んで「民主的」な選挙制度が定着している国である)。そうして出来た政府はアメリカと手を切りたがるだろうし、宗教的理由による制限を国民に強いるだろう。それではアメリカにとって得るものは何も無いのである。
2003/04/20(日) Pax RomanaとPax Americana
ドイツに戻って早速だが、マインツMainzに行ってきた。博物館の特別展を見に行くためである。
ラインラント・プファルツ州立博物館では今、「ローマ人とその遺産」という展覧会をやっている(5月25日まで)。その目的・内容を要約した一文を訳してみよう。
「ローマ人は先見的な発明によってこんにちのヨーロッパの発達に決定的に影響を及ぼしました。ローマ人がライン河やドナウ河沿岸までその帝国を拡張したとき、その地に住んでいたケルト人やゲルマン人は様々な新しいものごと、たとえば街道の整備、地中海伝来の料理、貨幣による支払い、暦や石造建築、そして彫刻などを学びました。
地中海の調味料やワイン、オリーヴ油や容器が交易により南フランスやイタリアからもたらされ、ローマの「ユーロ」(=デナリウス金貨)はローマだけでなくロンドン、ウィーンやマインツでも通用しました。文盲だったケルト人やゲルマン人はローマ人から読み書きを学びました。またローマの暦の一部はこんにちも使われています。
ローマの国家制度や能力の優越性はケルト人やゲルマン人をも政治的・社会的に融合させました。それには原住民へのローマ市民権の施行や宗教的寛容さが背景にありました。
この展覧会は、マインツを始めとする博物館の所蔵品を通して、ローマ時代の生活を分かりやすく紹介します。」
常々見ていて思うのだが、ローマ文明というのはたしかにすごい。博物館の展示だけとっても、鉄の道具はつい最近のものとほとんど変わらないし、優美なガラス容器や立ち並ぶ石の墓碑(弱者であるはずの奴隷の墓碑まであったりする)とかをみていると、視覚的にもローマ文明の偉大さに圧倒される。とても二千年近く以前のものとは思えない。中世ヨーロッパや同時代の他地域のものと比べると、その素晴らしさは歴然としていて、逆に(現代のものとたいして変わらないので)面白みに欠けるほどだ。
さて、今日の日記の表題である。ローマ帝国は紀元前1世紀には地中海沿岸を統一し、「ローマの平和」をつくりあげた。ローマ帝国という圧倒的な文明、そして軍事力を誇る帝国による広域支配の完成である。もちろん実態は、たびたび内乱や東方のペルシアとの抗争、そして最大の不安要因であるゲルマン人問題を抱えていたのだが、ともかくローマは圧倒的であった。特にいわゆる五賢帝の時代(2世紀)はイギリスの歴史家ギボンをして「人類がもっとも幸福だった時代のひとつ」とまで言わしめている(こういうヨーロッパ以外の地域を無視した視野狭窄的な物言いは僕は好きではないのだが)。
そして、世界史上の覇権国はかならずローマ帝国と比較される。パックス・イスラミカ(イスラームの平和)、パックス・タタリカ(モンゴルの平和)、パックス・ブリタニカ(イギリスの平和)、そしてパックス・アメリカーナ(アメリカの平和)・・・・。僕としてはローマ帝国以前に複合文明からなる巨大帝国を作り上げたアケメネス朝ペルシア(紀元前550~330年)を忘れて欲しくないのだが(パックス・ぺルシカ)、まあここでは擱く。
ここで問題にしたいのはやはり「最後の帝国」アメリカである。確かにアメリカは今も軍事力で圧倒的な力を見せつけている(まあアメリカの軍事費は2位から20位までの諸国の軍事費を集めたものより多いというから、無理はないか)。しかし、いわゆる「アメリカ的なるもの」に対する各国の意識は、むしろ最近悪化しているようにも思える(特にヨーロッパで)。アメリカは軍事力と「グローバリゼーション」で「アメリカの平和」の完成と維持を目指しているようだが、これからどうなっていくのかは僕にも全く予測がつかない。
ただ、将来博物館とかを作るときに、世界を支配(席巻というべきか)した「アメリカ帝国」の遺物として僕らは何を展示すればいいのだろうか。コーラの瓶?コンピュータ?原爆?トマホーク・ミサイル?T型フォード?それともアメリカ独立宣言の草稿だろうか?ローマ帝国を研究している現代の考古学者に比べて、未来の考古学者は頭を悩ますかもしれない。
このマインツでの特別展では、博物館付属の喫茶で、ローマ時代の料理を再現したものを食べさせてくれる。もし将来「アメリカ帝国の遺産展」を開くとき、そこで出す再現料理はやはりマクドナルドのハンバーガー・セット(\390だっけ)しか考えられないだろう。
今日はローマ・ゲルマン中央博物館にも行った。この博物館はいわゆる「西洋史」の古代から初期中世までの遺物を概観することが出来る(ただし展示物の多くはレプリカ)。歴史を鳥瞰するのが好きな人にはお勧めの博物館である(ただし解説はドイツ語しかないが)。
マインツは元々ローマ帝国の最前線駐屯地(第14軍団・第22軍団)から出発した町だけに、ローマ帝国漬けの一日になった。
2003/02/18(火) Qatna
今日は夕方フランクフルト大学に講演を聞きに行った。タイトルの1つ、カトナの発掘調査についてである。
カトナは昔の名前で、現在の遺跡名はテル・ミショルフェといい、シリア西部の町ホムスの郊外にある遺跡である。紀元前19世紀頃に都市国家として成立し、前14世紀中頃に滅びるまで交易都市国家として栄え、東西1km、南北1kmという大規模な城壁に囲まれ、中東で最大規模の宮殿をもっていた。この遺跡についてはこの日記で去年の12月くらいに触れたことがあった。
昨年ドイツの調査隊はこの遺跡で大量の粘土板文書(当時は紙が無かったので、粘土板に字を書いて保存していた)と、ギリシャ風の亀などを描いた壁画の破片、そして未盗掘の王墓が発見され話題を呼んだ。今日の講演は、その粘土板文書の解読に関するものである。講演者は意外に専門的な話をしたうえ、考古学的な話題が少なかったので後半は退屈してしまった。
当時カトナは東西交易(ギリシャとイランの間)の中継基地として栄えていた。もっとも、政治的には小さな都市国家だったので微弱だった。南方の大国エジプト(有名なツタンカーメン王の少し前の時代である)、イラク・シリア北部の強国ミタンニ、そして北方の軍事大国ヒッタイト(今のトルコにあった)という勢力に囲まれ、カトナは従属と離反を繰り返して難局を乗り切っていた。一部に根強い人気の漫画「王家の紋章」は多分この時代を舞台にしているんではないだろうか(僕はまだ読んだ事が無い)。
カトナは言語的にはフルリ語という言葉を話しており、ミタンニに近い。しかし文書は当時の共通語であった(今の英語のようなものか)アッカド語(アラビア語・ヘブライ語に近い)で書かれていた。話し言葉はフルリ語、書き言葉はアッカド語で、古代の日本みたいだったと思えば良い(日本でもかつて公文書は全て漢文だった)。
やがて紀元前14世紀に入り、ヒッタイト帝国がミタンニを押しのけてシリアに勢力を伸ばして来た。今までの通説では、カトナは紀元前1350年頃、イダンダ王のときに、ヒッタイトから離反しようとしたためにヒッタイト軍によって滅ぼされたと考えられていた。
ところが今回の新発見文書で、イダンダは実際にはヒッタイトに従属を続けており、イダンダを倒した敵はヒッタイト以外の可能性が強くなったという。内乱、もしくは遊牧民の侵入が考えられるという。イダンダがレンガ4万個を作って城壁を修理し、銅剣1万8千本を製造して軍を武装させ、また数千台の戦車を準備する命令を出した文書が見つかっている。これらの文書は、文書庫に収められる前に町自体が攻撃され、文書がほったらかしになった状態で見つかった。
またカトナはイダンダ王のときに滅んだのではなく、アキツィなる者がその次の王で、こちらはヒッタイトから離反しエジプトに与した為にヒッタイト軍に何度か攻撃されたらしい(当時のエジプトはアケナテン王の時代。対外宥和政策をとったためにヒッタイト帝国にシリアを席巻された)。ともかく、カトナは滅んで小村になり、20世紀のはじめにフランス人に発掘されるまでその存在は忘れられていた。
小国が大国の思惑に翻弄されるさまは、現在我々は目の前に見ている。時代が変わって国連が出来ようが、こればかりは無くなることがなさそうだ。
2003/02/06(木) ナチス時代のマールブルク
夕方、博士論文口頭試問を聞いて、そしてプールに行った後、K君S君とナチス時代のマールブルクに関する講演を聴きに行った。講師は第2次世界大戦に兵士として参加した経験もある老人だった。ただしこの人がマールブルクに住み始めたのは終戦直後である。
大学町であるマールブルクはドイツ帝国の時代から、右翼的な学生団(ブルシェンシャフト)の活動が活発な地域だった。日本ではインテリは左翼と相場が決まっているが、ドイツではそうではなかったらしい。ナチスが受け入れられる素地は十分あった。1927年の大学創設400年の記念行事も、アナクロな帝政時代を感じさせるものだった。
ワイマール共和国時代の選挙で、ナチスはマールブルクでは高い得票率があった。1933年1月の選挙の場合、ドイツ全体でのナチスの得票率は49%だったが、マールブルク市では53%、近郊を含めたマールブルク地区では60%にのぼった。
そして、ナチスの時代が始まる。ユダヤ人の選別と迫害、左翼的な新聞の廃刊、ゲシュタポ(秘密国家警察)の設置・・・。こういうのはドラマや歴史の本でよく見るので、頭ではよく分かっているつもりだったが、実際のマールブルクの当時の写真を見せられると、実感がまるで違う。
マールブルクは戦災にほとんど遭っていないので(今日の講演でもあったが、鉄道の周辺がアメリカ軍に爆撃されたくらいである)、たかだか70年前の写真を見せられてもすぐにどこだか分かる。旧市街のシュタインヴェグを行進する親衛隊。旧市街のキリアン・カペレにあったゲシュタポ本部。僕らの研究所もあるビーゲン通りには、ナチス関連の書店(「ゲッペルス語録」)があった。フランクフルト通りに兵舎があり、そこを一糸乱れず行進する突撃隊、親衛隊、ヒトラー・ユーゲント・・・。旧市庁舎の地下は監獄として利用され、社会主義者が禁錮された。1938年11月9日(「水晶の夜」)、放火され炎上する大学通りのシナゴーグ。どれもこれも、今僕がこうして日常を送る街で現実にあったことである。映画の一シーンではない。
講演者はスライドの最後に、ある諷刺画を掲げた。「昔語り」と題された絵の中で、老人が子供に語っていう。
「1933年に宇宙から残酷な生き物がやってきて、しばらく殺戮をほしいままにした。1945年、それらは消えて、地上からいなくなった」
もちろんこれは強烈な皮肉である。ドイツ政府の公式見解である「悪いのはナチスで、ドイツ人は利用されたのだ」という言い訳は通用しない。「残酷な生き物」を受け入れ、支持し、また徹底した組織で社会を支配するのに協力したのは、紛れも無く大部分の「普通のドイツ人」だった。ドイツ人もそれはよく分かっている。
会場は狭いホールだったが、立ち見が出るほどの盛況だった。聴衆の半分以上は若者だった。少なくとも、ドイツにナチスが復活する恐れは、アメリカにおいてよりは比べようも無く少ないといっていいだろう。
2003/01/31(金) 「スターリングラード」から60年
今日は第2次世界大戦のスターリングラードでのドイツ軍の敗戦からちょうど60年にあたる。この週末は、この戦いを特集した番組が放映されるらしい。一方、今日ドイツのシュレーダー首相はスターリングラードでの戦死者に対して哀悼の意を表明した。また比較的良好な現在のドイツ・ロシア関係について、その重要性を説いている。
スターリングラードの戦いは太平洋戦争(1941~1945)でいえばミッドウェイ海戦かガダルカナルの戦いにあたる、転機となった戦いだった。その規模と凄惨さで、この戦いにおよぶものは沖縄戦くらいだろう。
フランスやイタリア(!)の町ではこの戦いを記念した「スターリングラード通り」というのをよく見かける。この戦いはたびたび映画化され、昨年もジュード・ロウ主演で「The Duell: Enemy at the Gate(邦題:「スターリングラード」、珍しく横文字そのままではないが、意訳のしすぎだなあ。直訳すると「対決」)」が公開されている。
第2次世界大戦中の1942年夏、ソヴィエト連邦と交戦中のドイツのヒトラー総統は石油資源のあるコーカサス方面の占領を目的とした「青」作戦を開始した。
スターリングラードは人口40万の工業都市、ドイツ軍からすればコーカサスへの入り口の脇にあたる。ただ、ヒトラーにはこの都市の名前が気に食わなかった。憎きソ連の独裁者・スターリンの名が冠されているからである(ロシア革命後の内戦時に、共産党軍がツァーリツィンといわれたこの街で勝利を収めたのを記念して、この名に改められていた。スターリンの死後、ヴォルゴグラードと改名、現在に至る)。作戦上第一目標ではなかったこの都市に、ヒトラーは第6軍を差し向け、空軍による猛烈な無差別爆撃を加えた。
第6軍の司令官はフリードリッヒ・パウルス大将。ヘッセン州の役人の息子だったこの人は、事務方の経歴しかない地味な軍人だったが、ヒトラーによって将軍に取りたてられた。しかし彼は、前線指揮は初めてだった。前年冬にドイツ軍がモスクワを目前にしながら攻略に失敗したのに腹を立てたヒトラーが、前線司令官を多く更迭したために、パウルスに第6軍司令官のお鉢が回ってきたのである。
ドイツ第6軍及びハンガリー、ルーマニア、イタリアなどの枢軸軍はスターリングラードを攻撃し、9月には廃墟と化した市街地の大部分を占領した。しかし、ソ連軍は頑強に抵抗し、ドイツ軍はそれまで経験したことの無い市街戦に引きずり込まれていく。建物1つ、瓦礫の山1つを取り合う泥沼の戦いになった。数メートル前進するのに数日もかかり、多くの兵士が死んでいく。守るソ連側も新兵を次々に送り込んだ。ソ連兵の背後にはNKVD(KGBの前身)要員がおり、命令に服従しない者や逃げようとする兵士を容赦無く射殺した。
11月、新たにソ連軍の司令官となったゲオルギ・ジューコフ(1939年のノモンハン事件で日本軍を壊滅させた将軍)は反攻作戦を開始、枢軸軍の側面の弱点だったルーマニア軍を攻撃して敗走させる。前方のスターリングラード占領に気を取られていた枢軸軍はこの事態に対応できず、逆に枢軸軍20余万人がスターリングラードでソ連軍に包囲されることになった。
補給を絶たれ孤立した枢軸軍は次第にスターリングラードの廃墟の中で追い詰められていく。圧倒的多数のソ連兵の襲撃、厳しいロシアの冬、欠乏する食料に武器弾薬。やがてドイツ兵の一日の食事はパン一切れという有様になった。
パウルスはヒトラーに降伏許可を求めたが、ヒトラーは、ドイツの将来のために死ぬまで戦え、君たちの名は永遠に顕彰されるだろう、と答えるのみだった。コーカサスからの撤退に手一杯のドイツ軍に、もはや反攻する余裕はなかった。
年が明けた1943年1月31日、前日ヒトラーによって元帥に昇格されたパウルスはソ連軍に降伏、残るドイツ兵の抵抗も2月2日には止んだ。この戦いでの戦死者は少なく見積もっても両軍あわせて30万人に及ぶという。爆撃等による一般市民の死者も数万人に及ぶ。
捕虜になったドイツ兵は9万1千人。ソ連の捕虜収容所で餓死・凍死するものが相次いだため、1953年に生きて故国に帰った者はそのうちのたったの6000人だった。パウルス元帥は釈放されて東ドイツに戻り、1957年に病死した。
以上すらすらと「死者何人」と書いたが、その実際に想像がつかない。
今ロシアにとってドイツはもっとも頼りになる国になっている(奇しくも昨日ロシア人・ドイツ人と飲んだなあ)。日米関係もそうだが、歴史の流れというのはすごいものだと感心してしまう。
2002/12/23(月) 天皇誕生日など
今日は天皇誕生日だった。ドイツにいると生活にあまり関係無いのだが。
話が飛ぶが、僕がいつも見ているホームページの1つに「戦国浪漫」というのがあって、タイトルの通り戦国時代の人物を取り扱っている。メインは戦国武将だが、文化人や女性など幅広く扱い、史料や実地調査などもする好ページである。
このページでのトップは日替わりで「今日は何の日」という感じで戦国時代のその日の出来事を羅列しているのだが、それによると、第105代・後奈良天皇も12月23日(ただし旧暦)の生まれであるとあった。ちなみに今の明仁天皇の誕生日は1933年12月23日である。
後奈良天皇は1496年12月23日、後柏原天皇の皇子として生まれた。当時は戦国時代の真っ只中、天皇などといった古く無力な権威に目をくれるものなどほとんど居らず、京都の御所は応仁の乱以降の戦乱で荒れ放題、貴族は和歌などを短冊に書いて武士や商人に与え、その見返りで糊口をしのぐといった境遇だった(こういった貴族の境遇は基本的に明治時代になるまで変わらなかった。貴族が重視されるようになるのは明治維新以降、ドイツ式中央主権国家や王室を目指した結果である)。さらには自分の娘を地方の有力大名に与え(血統の箔をつけるために地方豪族はそれを喜んだ)、それを頼って都落ちする貴族も多かった。
1527年、父の後柏原天皇が崩御して即位したが、即位の儀式(大嘗祭)を行う資金さえなく、各地の戦国大名に資金を無心せねばならないありさまだった。今でも日本各地に後奈良天皇の御真簡なるものが伝えられているが、やっていたことは貧乏貴族連中と変わらなかったのかもしれない。1557年、62歳で崩御した。
うちの母方の伯母はおととし亡くなったのだが、その嫁ぎ先は「後奈良天皇の子孫」を自称していた。なんでも、後奈良天皇の手がついた女性を備中の豪族・三村家親がひきとり、生まれた子供を自分の子として育てたというのである(記録上は後奈良天皇には5人の配偶者がおり、子供もかなりいたようである)。生まれた子は勝法師丸と名づけられた。
そこの家の伝承では家親ではなくその子の元親ということになっているが、元親では年代的に矛盾が生じるので(既にこの時点で怪しい話だが)、ここでは家親ということにしておく。三村家は勤皇の志があり、乱世でも皇室を敬ったということになっている。同じような地方豪族の例として、丹波の波多野氏や織田信長の父・信秀などがある。これら成りあがりの大名は、使者を遣わして皇室に献金したりした。
毛利氏の傘下で勢力を拡大した家親は1566年に暗殺され、次男の元親が継いだ。元親は次第に落魄し、1575年ついに毛利氏によって滅ぼされるにいたる。居城である備中松山城が落ちるとき、元親は子もしくは弟の勝法師丸を脱出させ自害した。毛利側の記録や軍記物語では勝法師は元親の実子ということになっている。勝法師丸はしかし毛利方に捕らえられ、10歳の子供にしては堂々とした振る舞いだったために、末恐ろしく思った毛利軍の将・小早川隆景の命で斬られたことになっている。しかし、この時勝法師丸が本当に10歳だとすると、後奈良天皇の落胤というのは物理的に無理である(ますます怪しい)。
ところが、その僕の縁戚の家伝では、勝法師丸は無事に落ち延びて土着し、Iと名乗って代を重ね、現代に至っているという。後奈良天皇が勝法師丸の母に与えたという宝剣も家宝として保存されている。小早川隆景に斬られた利発な子は替え玉ということだろうか。それとも、本当は後奈良天皇ではなくその次の正親町天皇とごっちゃにしているのか、単に三村氏の子孫ということなのだろうか。
この話の真偽はどうでもよい(親戚のこととはいえ、僕にはやはり疑わしいのだが)。ただ、こういった伝承は日本中にあるし、源氏も平家も元を辿れば天皇家につらなる。徳川家みたいに系図を偽作してまで源氏につらなったりした例も含めれば、日本人の半分以上は天皇家から分かれたことになるし、縁戚も含めれば日本人すべてが何らかの形で天皇家に連なっていることになる。どんな乱世になって落魄しても日本人の「総本家」として天皇家が生き残り、現存する世界最古といわれる王朝が続いているのも、その辺に理由がありそうだ(二番目はたしかデンマーク王家だと思う)。
織田信長(1534~1582)は古い権威を否定して坊主を殺したり足利将軍を追放したりしたが、ひとり皇室は自分の権威付けに利用した。皇室も実際の政治に容喙することなく、権威(象徴)にとどまった。同様の路線を徳川幕府も踏襲した。歴代天皇は相変わらず貧しい暮らし(良くいえば清貧)を強いられた。明治以降の天皇像や天皇個人崇拝がむしろそれまでの「伝統」に逆らうものだとといえる。
今の皇室のありかたは、江戸時代までと近代の折衷みたいなものか。「天皇誕生日」は西洋化を目指した近代の名残といえる。
2002/12/14(土) 「討ち入り」から300年
今日は有名な「赤穂浪士の吉良邸討ち入り」からちょうど300年である(ただし、これは旧暦なので正確に今日が300周年というわけではないが)。歌舞伎の題材になったり、映画になったり、何度もTVドラマ化されているので結構知名度は高いだろう。僕も日本に居るときはたいてい見ていたし、田舎が赤穂に近いせいもあって関心はあった。
この事件は元禄15年(1703年)12月15日の未明、赤穂藩元筆頭家老・大石内蔵助良雄(おおいしくらのすけよしたか)率いる、赤穂城主・浅野内匠頭長矩(あさのたくみのかみながのり)の旧臣47人が幕府の高家(儀典官)である吉良上野介義央(きらこうづけのすけよしなか)の私邸に乱入し、2時間の乱闘の末、吉良を殺害した事件である。この乱闘で吉良方は16人が死亡、20名あまりが負傷したが、あらかじめ武装していた赤穂方は数名が負傷しただけだった。浪士たちは事件後、幕府に自訴した。
今ふうにいえば、徒党を組んだ武装集団によるテロ行為に違いないのだが(たとえば潰れた会社の元社員が、潰した原因を作った会社社長や役人宅に殴り込みをかけるような)、当時の日本政府である徳川幕府は忠孝を尊ぶ儒教を信奉している。亡き主君のために仇を討った赤穂浪士たちへの同情は大きく、また何より江戸の町民達は彼らをヒーロー扱いした。結局浪士たちは翌年切腹という「名誉の死」を賜った。まあ現代の法の精神を彼らに適用するのは実は酷というもので、武士というのは戦うのが本職だから、実力行使には復讐しかありえないのだが。
この事件の背景はいろいろ論じられていて、関連本は枚挙に暇がない。また脚色や俗説が入り乱れている。だから僕なりの解釈を書いていく。
「討ち入り」の原因となったのは、江戸城内で浅野が吉良に斬りつけ、浅野が即日切腹・お家断絶という不平等な判決であるという。浅野は吉良に斬りつける際「遺恨覚えたか」と叫んだということで、何らかの怨恨が刃傷の原因であるという。賄賂(もしくは「あいさつ」)をケチった浅野に対して吉良が嫌がらせをしたというのが定説になっている。
浅野の三年前に吉良の儀典指導を受けた津和野城主・亀井茲親は同じように吉良に恨みをもち、斬りつけようとしたが、家老の多胡某が吉良に賄賂を贈って態度を改めさせたので事無きをを得た、という話もある。とすれば、浅野家の江戸家老である安井彦右衛門が気が利かないためにこの悲劇になった、といえなくもない(安井は討ち入りに参加していない)。だが実際のところ内匠頭はケチで癇癪持ちだったという話もある。
TVなどでは内匠頭は美男で名君のように描かれているが、実際どうだったのだろうか。9歳で家督を継いだ彼は、財政建て直しのために常に倹約を強いられた。浅野家は5万3千石だが、内匠頭の祖父の長直が不相応に立派な城(赤穂城)を建てたうえ、幕府による皇居修理などに借り出されて財政が逼迫していた。塩田開発で持ちなおしたとはいえ(赤穂と吉良の塩の市場競争が両者の衝突につながったという経済的解釈もある)、やはりきつかっただろう。吉良への謝礼(賄賂)をケチったのも、事件の背景となった勅使饗応の予算を削って吉良の不興を買ったのも、そこに原因がありそうだ。さらに、武士はともかく、赤穂の領民は浅野家取り潰しと聞いて赤飯を炊いたというから、かなり厳しい税の取りたてがあったことは想像に難くない。
ともかく、内匠頭の一時の癇癪で、赤穂藩の270人の士分、790人の足軽・中間(雑用人)が失業し、その家族が路頭に迷うことになった。今でいえば中堅企業の倒産である。赤穂城を幕府に引き渡す際に、「昼行灯」と陰口を叩かれていた筆頭家老の大石が水際立った働きを見せた。大石家は三代続いて浅野家の筆頭家老の家柄、養子のやりとりなどで主家との結びつきも強かったので、浅野家に殉じる覚悟だったが、他の家臣たち(大野九郎兵衛など)は主君の振る舞いに呆れて、赤穂城を開け渡すやさっさと退散したのかもしれない。大石が幕府に浅野家再興を願い出た連判状には120人しか参加していない。また討ち入り組は大石に近い人脈(大石派)で固められていたようである。自らの才覚でのし上がった一代家老である大野らと、門閥の大石には確執があったようである。
実際のところ、討ち入りに参加したのはたったの47人、多くは中級か下級武士で(寺坂吉右衛門のような足軽もいた)、もはや武士としての再就職(他の藩への仕官)のあてのない人々が多かった。今と違って失業保険もなく、生活は途端に苦しくなっただろう。個人的に内匠頭に近かった大石や片岡源五右衛門を除けば、忠義からではなく、いわば破れかぶれで参加した者もいただろう。これはまさにテロリストと同じ精神状況である。赤穂の遺臣の中でも、「はねかえり」というべきグループである。
まあ最近の「テロリスト」のような、関係無い人を巻き込む卑劣なところは毛頭無いが。
理詰め・法的に考えれば吉良は被害者でしかないのだが、そうはならないのが日本というものだろう。浅野家に厳しい裁定を下してこの事件を招いた幕府にして、浪士に名誉の死を賜り、室町時代に三河守護も務めた名門・吉良家を取り潰し、浅野家を小さいながらも再興させた。さらに平和で退屈な日常にあきあきしていた江戸庶民の力によって、吉良は悪者になり、浅野は名君、浪士たちは戦前戦後も変わらぬ永遠のヒーローとなった。僕も時々訪れる赤穂は浪士詣での聖地となった。そしてこの普遍性・冷静さを欠いた判断は、現在でも全く変わっていないように思う。
© Rakuten Group, Inc.