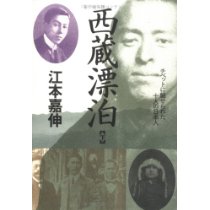
「西蔵漂泊(下)」
チベットに魅せられた十人の日本人
江本嘉伸 1994/04 山と渓谷社 単行本 p305
Vol.2 No.273 ★★★★☆
チベット、と聞くと心がさわぐ。
なぜだろう。
ヒマラヤの北、平均標高4千メートルのこの地の、どこにこれほどひきつけられるのだろう。
その思いとともに、19世紀末から太平洋戦争週末の時代までの半世紀、チベットに向かった10人の日本人を追って、長い旅をしてきた。
p294
この文章、このまんまいただきたい。「チベット、と聞くと心がさわぐ。なぜだろう」。当ブログの根底は、この言葉が形づくっているかもしれない。
それぞれの旅人が残した著書、報告書、日記、書簡、写真、そして外国人の書いた本を含めてチベットに関かわる記録を読み、その人、その家族、知人を訪ね歩いて、話を聞いた。そのなかから、ひとりひとりの旅が浮かびあがってきた。
p295
精度はまったく違うが、当ブログもまた図書館から借りてきた資料をめくりながら、チベットのイメージを追っかけている。そういう意味では著者の視点とそれほど変わらない。しかし、この著者は、資料を深く読んだ上に、さらに、知人を訪ね歩いたり、チベットの地を踏むことによって、読者が知りたいと思っていることを、さらに膨らませて教えてくれる。
日本人のチベット観は、河口の書によってかたちづくられた、と言ってもいい。
しかし、河口と同時代、そしてその後、チベットに向けて真摯な旅をし、貴重な記録を残した九人の旅人がいたのだ。動機、旅のスタイルを異にした彼らのさまざまな視点に立った報告から、チベットの多様な姿がとらえられる。
p302
私もまた、30年ほど前に河口慧海の 「チベット旅行記」 を読んだきり、長いこと、同時代のチベット旅行者の姿を追いかけることはなかった。しかし、本書を読んであらためて、いかに多くの日本人がチベットの地を踏んでいたのか認識した。
チベットをめざした日本人をその行動の時期で分けるとしたら、能海寛、寺本婉雅、成田安輝を第1グループ、矢島保治郎、青木文教、多田等観、再入蔵の河口慧海を第2グループとすることができる。
そして、次の”世代”、太平洋戦争の直前にチベット入りした野元甚蔵、日本の劣勢とそれに次ぐ敗戦を知らずに、モンゴルからチベットへと歩き続けた西川十三と木村肥佐生は、第3グループと呼んでいいだろう。
旅と聞いて、先日読んでいた白洲正子の 「白洲正子と歩く京都」 のときに、「旅なら旅として、私流儀の旅がある」などと捨て台詞を吐いていた当ブログではあるが、さて、こちらの本のタイトルにあるほど、本当に「漂泊」できるか、となると、まったく心もとない。口ほどでもない自分が恥ずかしい。
第16章の「『大正の玉手箱事件』-----大蔵経をめぐる青木と河口の対決」は、面白かった。青木文教がチベットから持ち帰った「大蔵経」に河口慧海が新聞紙上の公開質問状でいっちゃもんをつけたエピソードだ。当時では、大きなスキャンダルとして三面記事をにぎわせたことだろう。いずれが正しいかは不明だが、なにか秘境チベットまで旅したご両人の「さとり」がリトマス試験紙にかけられているような、ドタバタ劇とも見える。
あちこちで飼犬、野犬に吠えられ追われながら、矢島はひたすら歩いた。青木からもらった洋傘が、野犬の襲撃から身を守るのに役立ち、通りがかりの人に対しては、「オムマニペメフン」の真言とともにした数珠がチベット人とみせかけるのに役立った。
オム
マ
ニ
ペ
メ
フン
-
仏教が好き! 2008.10.23
-
男一代菩薩道 インド仏教の頂点に立つ日… 2008.10.23 コメント(4)
-
21世紀のブディストマガジン「ジッポウ」 2008.10.22
PR
Freepage List
Category
目次
(6)22番目のカテゴリー
(49)バック・ヤード
(108)osho@spiritual.earth
(108)mandala-integral
(108)agarta-david
(108)スピノザ
(108)環境心理学
(108)アンソロポロジー
(108)スピリット・オブ・エクスタシー
(108)マーケットプレイス
(108)OSHOmmp/gnu/agarta0.0.2
(108)チェロキー
(108)シンギュラリタリアン
(108)レムリア
(108)2nd ライフ
(108)ブッダ達の心理学1.0
(108)マルチチュード
(108)シンギュラリティ
(108)アガルタ
(108)ネットワーク社会と未来
(108)地球人スピリット
(108)ブログ・ジャーナリズム
(108)Comments




