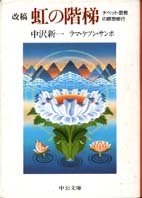
「改稿 虹の階梯」
<4>チベット密教の瞑想修行
中沢新一 /ケツン・サンポ 1993/05 中央公論新社 文庫 633p
★★★★☆
チベット仏教ニンマ派のラマ僧が弟子である中沢新一におこなった、密教修行の階梯の詳細な解説である。チベット高原で熟成した密教の叡智を伝え、真実の心の自由を探究する密教入門の書。原著に倍する枚数の書き下ろしを加えた完全版 裏表紙
1993年の5月という時間的区切りは、個人的にとてつもなく大きな意味を持っている。家族の成長もあり、仕事の流れもあり、自分自身の年齢的な変化もあった。その他、いろいろな因縁が重なり、この時期から私は本を読まなくなった。もともと多読ではなかったが、書店めぐりくらいはしていた。その後95年頃からはインターネット一本槍になったので、さらに精神世界の本は避けるようになっていた。
だから、この1993年の5月に出た「改稿」本にはほとんど手が出なかった。もともと 「初版」本 を持っていたので、ようやく文庫本化されたか、という程度にしか受け取っていなかったのだろう。今回、縁あって、こうして手に取ってみると、まさに「原著に倍する枚数の書き下ろしを加えた」というところは、なるほどと思うが、「完全版」というところは、相変わらず、首をかしげてしまう。
この本がでた時期に、当時の環境の中で、つまりあの忌まわしい事件がおきる前の、まだ世の中バブルの残り香の漂う、そしてまだ肉体的にも若さがあった自分の身体でこの本を味わったら、この本から受けるイメージはまた違ったものになっていたかもしれない。しかし、歴史に、もしも、はない。それはそうだったに過ぎない。少なくとも、今回、こうしてこの改稿本を手にできたことだけでも感謝しよう。
資料的には面白い部分がたくさんある。しかし、当時より耳年増になってしまっている私には、この本で知る前に、他のどこかで聞いてしまったエピソードなどが多く含まれており、冗漫な部分がやたらと気になることになった。なぜに「原著に倍する」書き下ろしを加える必要があったのか、が依然として理解できない。むしろこれだけ書きなおすのであれば、まったく別途な新刊としてでるべきではなかったのではないだろうか。
それと、誰が誰に書いているのかわからない点が、あやうさを倍増している。「クンサンラマの教え」の翻訳なのか、ケツン・サンポが中沢に教えた内容なのか、修行僧・中沢が、「ラマ」として日本の「一般読者」に語りかけているのか、渾然として、意味不明になっているところが多い。つまり、一読者として、私はその辺のことを細かく読みとれなかった、ということなのだが・・・・。
利他心という菩薩の心がまえが欠けていれば、どんなに教えを聞いてそれを修行したとしても、あなたのしていることは修行のまねごとにすぎない。瞑想の時も、真言を口ずさむ時も、五体投地をおこなう時も、仏塔を右まわりに回る時も、マニ車を回して「オーム・マニ・ペーメ・フーム」という観世音菩薩の真言を唱える時も、あなたはたえず自分の行為を、利他の菩薩の心がまえに、しっかりと結びつけていることが大切である。 p58
なにはともあれ、ここからがスタートだ。
仏教の教えには無数の入口がある。しかし、それらすべてが、菩提心の実現と、空性の理解と、慈悲の心の獲得とに、目標を定めているのだ。もしもすばらしい宝物のような慈悲が、しっかり根づいていなければ、どんなに心を澄ませて瞑想にふけったとしても、心に真実の仏性が宿ることはない。密教における「生起次第(キェーリム)」と「究竟次第(ゾクリム)」の瞑想技法なども、そこに菩提心が結びついていれば、この肉体をもった生のうちに、仏性を獲得することも可能になる。ところが、そこに菩提心が結びついていなければ、そんなものは仏教の修行とは言えないものに、なりさがってしまう。
そして、結局はここがゴールだ。スタート地点がゴールである。それこそがゾクチェンの教えであり、円環さえしていない究極の法だ。
-
悟りへの階梯 2008.10.27
-
ツォンカパ チベットの密教ヨーガ 2008.10.26
-
聖ツォンカパ伝<2> 2008.10.25
PR
Freepage List
Category
目次
(6)22番目のカテゴリー
(49)バック・ヤード
(108)osho@spiritual.earth
(108)mandala-integral
(108)agarta-david
(108)スピノザ
(108)環境心理学
(108)アンソロポロジー
(108)スピリット・オブ・エクスタシー
(108)マーケットプレイス
(108)OSHOmmp/gnu/agarta0.0.2
(108)チェロキー
(108)シンギュラリタリアン
(108)レムリア
(108)2nd ライフ
(108)ブッダ達の心理学1.0
(108)マルチチュード
(108)シンギュラリティ
(108)アガルタ
(108)ネットワーク社会と未来
(108)地球人スピリット
(108)ブログ・ジャーナリズム
(108)Comments




