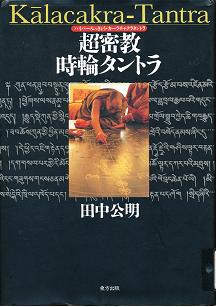
「超密教 時輪タントラ」
田中 公明 1994/11 東方出版 単行本 242p
Vol.2 No.365 ★★★★★
正式には「ハイパー密教 カーラチャクラ・タントラ」と読む。 「曼荼羅イコノロジー」 、 「曼荼羅グラフィックス」 、 など、著者の本にはITを連想させるようなネーミングが多い。時輪タントラについての関心はあるが、それをトータルに紹介している本はすくない。
1994/11 「チベット密教の本」 は、時輪タントラに言及しているが、本の性格上、必ずしも万全ではない。1995/12 「ダライ・ラマの密教入門」 は「秘密の時輪タントラ潅頂を公開する」という触れ込みで、その資料的価値は高いが、総合的に、ベストとは言いがたい。
このような状況にあって、この二書に先立つこと、田中公明の「超密教 時輪タントラ」が出たのは、時期を得た快挙と言っていいだろう。上の二書とあわせて読んだとすればさらに相乗的に理解がすすむだろう。
チベット仏教とくに密教では、師匠から受けた教えを疑うことなく信受し、全身全霊で実践することが無上の美徳とされている。このような伝統から、科学的批判精神が出てこないのも致し方ないことであろう。
また欧米では、このようなブームを承けて、アカデミックな学界でも「時輪タントラ」への関心が高まってきた。筆者も1992年の国際チベット学会の席上いくつかの発表を聴いたが、残念ながら「群盲象を撫でる」といった状態で、この未知の密教体系の全容を明らかにするにはほど遠いものがあった。
p8
状況は日本と欧米にもそう違いはなく、ひょっとすると、当時から10数年経過した現在においても、チベット密教のおびただしい情報の氾濫の中にあっても、この「時輪タントラ」についての情報は、そう変化がないのかもしれない。 そういう状況を考えれば、この本が一冊にまとめられていることは、読者としてはかなり幸運なことだと思う。
インドの仏教は、イスラム教徒の攻撃を受けて、13世紀初頭に滅亡するが、「自輪タントラ」は時代的に最も遅れて現れた仏教であったばかりでなく、これまでのインド仏教史を総括する役割を担っていたのである。したがって「時輪タントラ」成立の謎を解明することは、とりも直さずインドの大地で繰り広げられた、1700年の仏教史を再構成することにつながるのである。 p11
精神世界に関心を持ち、仏教とめぐりあい、さまざまな流れに触れ、経典や行法、歴史を学びながら、やがてはその世界が深化していくなかで、密教と出会い、ついには時輪タントラの存在に気づいていく。そのプロセスは長い長いものである。 しかし、「時輪タントラ」を挟む両サイドから考えれば、ことは大きくことなる。
カーラチャクラは密教のなかではめずらしく、イニシエーションを受けるものに対して制限を設けていないのです。そのため、私は世界じゅうをまわってこのカーラチャクラのイニシエーションを授けてきました。会場には何万もの人々が集い、聴衆のなかには非仏教徒すら数多く交じっています。 「ダライ・ラマの密教入門 」 p4
つまり「時輪タントラ」のイニシエーションを受けるのは、かなりお手軽モードでいいのである。仏教徒じゃなくても、仏教を知らなくたって、イニシエーションを受けることができる。まるで、野外コンサートにでもでかけていくような気持ちで、スタートしてもかまわないのだ。
「時輪タントラ」の教説の一つとして有名なものに、シャンバラ伝説がある。者バラは、近代に入って西洋の精神思想家から注目されたので、欧米で大変有名になったが、それだけに「時輪タントラ」の本来の教説に基づかない、後世後付会の解説が流布している。そこで、本章では、「時輪タントラ」や「ヴィマラプラバー」などの原典に基づいて、「時輪タントラ」に説かれるシャンバラ伝説の姿を、明らかにしてゆきたい。 p68
当ブログの初期においては、むしろこの「後世付会」的シャンバラ=アガルタを 積極的に追いかけてみた経緯 がある。チベット密教学者ならぬ、ましてや多少のトンデモ世界はものともしない当ブログにあっては、かならずしも「後世付会」的情報を一概に間違いと決めつけてしまうことは好みではない。しかし、説得力のある経典にもとづく、説得力ある研究者の論説に耳を傾けることは、おおいに歓迎したいところである。自らの前非をあらためることをためらうことはないだろう。
近代に入ると、シャンバラ伝説は欧米でブームを巻き起こし、本家であるヒンドゥー教ヴィシュヌ派のカルキ伝説以上に知られるようになった。しかし西洋に知られたシャンバラ伝説のいくつかは、はるか後代に成立したチベット人の空想の産物だったのである。 p87
「空想の産物」と決めつけられてしまえば、反発の声が聞こえてきそうだが、精神世界において、「空想の産物」とは必ずしも「蔑称」ではない。また、無価値と決めつけられたものでもない。そのようにわきまえて、そこからさらに理解を深化させていけばよいのだから。
「秘密集会」系の密教は大いに発展し、「父タントラ」と呼ばれる聖典群が成立するが、9世紀ごろからは「母タントラ」と呼ばれる聖典群が形成されはじめた。
母タントラは生理学的に強い関心を示し、身体論を発展させたが、母タントラの代表者ともいうべき「サンヴァローダヤ・タントラ」には、胎児論が展開されている。
p111
この「サンヴァーロ・タントラ」から チャクラサンヴァラ などへとつながっていく。
著者はダライ・ラマ14世が、1981年、西洋で初めてアメリカ、ウィスコンシン州マディソンで行った「時輪タントラ」の大潅頂のテキストを入手したが、それを分析すると、世間の七潅頂のみの次第で、後期密教の出世間潅頂には、ほとんど触れられていないことがわかる。 p135
秘されているものは秘されているのである。時輪タントラの潅頂を受ける方は、かなりお手軽モードであっても、授けるほうは、むしろ軽々にことを進めることができない。そのスケールといい、準備といい、ものごとは容易ではなさそうだ。
今日でもチベット人は、自分のイダム(守護尊)がどの尊格かを、容易には口外しないといわれる。これは自己のイダムを他人に知られれば、呪詛を受けた時に危険になるからだといわれる。チベット人の古代からの風習を伝えるものといえるだろう。 p169
これほどおおげさなことではないが、当ブログにおいても、同化しようとする尊格についての、こまかな個的な経緯は暈していくことも一考だろう。
サンヴァラ系の母タントラでは、比較的初期に属する「サンヴァローダヤ」所説のサンヴァラ三面六臂像が、「秘密集会」と同じ三面の配置を示している。これに対して、主尊の面の色を曼荼羅の塗り分けと一致させるのは、より発達したチャクラサンヴァラの四面十二臂像に、はじめて現れる傾向である。 p182
当ブログとしては、前後して現れる「ヘーヴァジュラ」経典についても、別途フォーカシングが必要となろう。
現代欧米の後期密教研究は、チベット最大の宗派ゲルク派の密教解釈に、多くを負っている。ツォンカパが確立したゲルク派の密教体系は、「秘密集会」の解釈学派である「聖者流」の「五次第」の体系を基礎とし、「時輪」を除く他のタントラの「究竟次第」を、これとパラレルに解釈するものである。「秘密集会」と相違が激しい「時輪」の「究竟次第」のみは、これを別に扱うが、内容に関しては「五次第」との間に浅深の別はないとしている。 p199
著者の文章は淡々とした均質的は一貫性のなかに書かれているが、あちこちに新たなるテーマを散らばめている。
「生命倫理」のような応用科学に入る前に、文献に基づく基礎研究が、まずなされなければならないように思われる。
p200
当ブログでも直観的に感じていることではあるが、説得力のある立場の説得力ある論旨には素直にうなづかなくてあならない。
我々研究者が、チベット系の情報に多くを依存していることは素直に認めなければならないが、こと「時輪タントラ」に関しては、ゲルク派の解釈には宗派的傾向があり、インド密教の流れをそのまま継承するものではないことは念頭に入れるべきであろう。 p222
著者は、最後に「時輪タントラ」研究の意義と、今後の展望について考えている。
「時輪タントラ」は、我々が経験する世界の総てを、六大によて説明する画期的な理論を提唱したばかりか、これを詳細に図示する曼荼羅をも創りあげた。「時輪」の自然科学は、それがたとえ「壮大な流産」であったとしても、現代の思想界に貴重な示唆を与えているように思われてならない。 p233
著者はこの本を 「曼荼羅イコノロジー」 、「詳細河口慧海コレクション--チベット・ネパール仏教美術--」とともに、三部作にするというプランであったようだが、その構想はここで閉じられることはなく、発展的に 「チベット密教」 などへと増殖している。
-
トランスパーソナル心理療法入門 <2> … 2009.01.14
-
エスリンとアメリカの覚醒<6> ラジニー… 2009.01.13 コメント(2)
-
「維摩経」 長尾雅人訳 <1> 2009.01.12
PR
Freepage List
Category
目次
(6)22番目のカテゴリー
(49)バック・ヤード
(108)osho@spiritual.earth
(108)mandala-integral
(108)agarta-david
(108)スピノザ
(108)環境心理学
(108)アンソロポロジー
(108)スピリット・オブ・エクスタシー
(108)マーケットプレイス
(108)OSHOmmp/gnu/agarta0.0.2
(108)チェロキー
(108)シンギュラリタリアン
(108)レムリア
(108)2nd ライフ
(108)ブッダ達の心理学1.0
(108)マルチチュード
(108)シンギュラリティ
(108)アガルタ
(108)ネットワーク社会と未来
(108)地球人スピリット
(108)ブログ・ジャーナリズム
(108)Comments




