PR
Calendar
Category
カテゴリ未分類
(16)歴史
(47)経済
(47)政治
(45)社会
(44)哲学・思想・文学・科学
(44)サブカル・小説・映画
(43)音楽・文化
(20)スポーツ・ゲーム
(13) GKenさん
GKenさん─ 灼熱 ─ HEAT1836さん
余多歩き くれどさん
tabaccosen breton005さん
ミョウの魅 stadanさん
ぶらぶらブラジル日記 Gaobrazilさん
沖縄でよんなよんな sinarsinarさん
りゅうちゃんミスト… りゅうちゃんミストラルさん
再出発日記 KUMA0504さん
Comments
Oct , 2025
Sep , 2025
Aug , 2025
Jul , 2025
May , 2025
Apr , 2025
Mar , 2025
Feb , 2025
Freepage List
Keyword Search
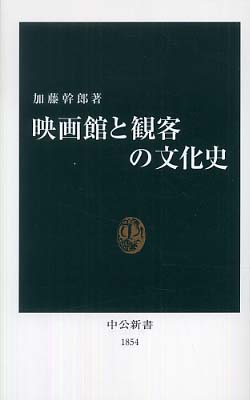
▼ 本来面白い「はず」なのにも関わらず、なぜ、こんなにつまらないのだろう…
▼ 世の中、こんな首をひねるような現象が訪れることは、少なくない。さしずめ、今回とりあげる本書は、私にとって、そんな代表的な本であるといえるかもしれない。もちろん、折角の力作について、「つまらない」という、ある種不合理な批判を受ける当人にとっては、たまったもんではあるまいが。
▼ 内容を簡潔にまとめておこう。
▼ 映画史は、「作品と作家」の歴史として描かれてきた。写真と映画は違い、むしろ演劇との親和性が高い。映画が立ち現れる場所、映画館を訪ねる以外、映画には「起源」がない。どのような環境で上演され、観客はどのような態度で観覧したのか。媒体と場所が違えば、体験はまったく異なるのだから………このような視点から、アメリカと日本、2つのフィールドを軸に、映画館と観客の歴史を追体験していこうと試みる。
▼ 映画の前史には、360度ぐるっと絵が描かれた、パノラマ館という視覚装置があるらしい。 「映画の観客の不動性」は、映画史初期から古典期への移行過程でえられた、歴史的産物にすぎない 。1895年、映画上映は、仏のリュミエール兄弟に始まるものの、1905年頃までは、劇場などで他の出し物と一緒に上映される存在にすぎなかったという。アメリカでは、「ヴォードヴィル劇場」という、ダンス・コントなどのライブ・パフォーマンスをおこなう劇場でおこなわれ、 音楽の伴奏とともに映画の上演 がおこなわれた。19世紀前半までの男性中心主義的な公共圏とは違い、ヴォードヴィル劇場は、20世紀「映画館」と同様の、女性・年齢・階級に関わりない空間であったという。 ライブ・パフォーマンス性が映画館から駆逐されるのは 「張り出し舞台のない映画館」で究極の静寂と機械音の支配する、 1980年代のシネ・コン出現まで待つ必要がある とのこと。
貸店舗などの小規模映画館は、「スライド」や「サイレント映画」が、ピアノ伴奏による歌手・観客の大合唱で埋められながら上演される祝祭空間であった 。1905年~13年「ニッケル・オディオン」は、新移民を中心とする観客たちによって爆発的に流行、それに併せて、制作=配給=興行の分業、安価な商品(映画)を配給元から取りよせるスタイルが普及する。 ニッケル・オディオンは、異郷の地で映画を通して、そこで生きるに相応しいアイデンティティの獲得を行わせる公共圏的機能 を果たしていた。ハリウッドは、1880年代のロシアのポグロムによる、200万人ものユダヤ人のアメリカ移住が遠因として―――ユニーヴァーサル、フォックス、パラマウント、MGM、ワーナー・ブラザーズなどの創始者は皆、ロシア・東欧・中欧からの移民ユダヤ人―――ユダヤ人娯楽産業として出発する。 館内合唱は映画の長大化がすすむ古典期になると衰退して「静粛化」が進むが、それは大衆音楽の需要構造の「楽譜からレコード」への変容と軌を一に しているという。
宮殿のような映画館は、テーマパークと同様、非日常の空間
に他ならない。もはや「ニッケル・オディオン」期のような、外国語が話されたり、黒人・低所得層によって分化しているような、多様な空間ではない。とはいえ 観客は、人種的、階級的、イデオロギー的に均質化されてしまうものの、「序曲」「行進曲(ニュース映画)」「本編」などにはオーケストラが伴奏でつくなど、音楽会と見まごうような多様な音楽が奏でられた
という。ところが、トーキーの登場と世界恐慌に、このピクチュアル・パレスは対応できなかった。1930年代以降、 中規模サイズのトーキー映画館経営に転換していく中で、音楽会的興行プログラムは変容するものの、生演奏自体は続いた
。いったんは静粛になった映画館は、途中入退館と観客が自分で座席を探す(以前はボーイが案内)ため、再びうるさくなったという。
▼ なによりも、1933年ニュージャーシー州に誕生した、「ドライブ・イン・シアター」なるものには、日本人ならば、驚く他はない。広大な駐車場で、車を降りることなく、巨大スクリーンと駐車場脇にある音源によって、映画と楽しんでいたんだとか。排ガスで曇るし見えにくいという欠点があるものの、赤ん坊が泣いても、周囲に迷惑をかけない、プライバシー空間であった。 「ドライブ・イン・シアター」は、喫煙、うたた寝、ダンス、飲酒、SEXなどがおこなわれた空間であり、「テレビと居間」や、今でいえばDVDプレイヤー・モニターを車に乗せる行為の先取り
をしていたという。1957年頃、この「ドライブ・イン・シアター」は最盛期をむかえ、普通の映画館よりも観客動員は多かったらしい。ただし、それは、映画のテレビ化プロセスと重なっており、テレビ保有率が8割に達したときだったという。夜、映画をみる以外には、昼には、教会の屋外説教にも使われた。「ドライブ・イン・シアター」が衰退して、その跡地に建てられたのが、ショッピング・モールであり、シネマ・コンプレックスなのだとか。
▼ 1980年代以降、ショッピング・モール内に展開する シネマ・コンプレックスの登場とは、テレビの多チャンネル化に完全に敗北した証拠であるが、その「社交的交際」の性格ゆえに、今もなおテレビと競争することが可能になっている、
のだという。一本の映画の製作と宣伝に可能な限り予算を投入して、可能な限り高収益をねらう、1970年代登場したスタイル、「ブロック・バスター映画」。「ブロックバスター映画」は、「収容能力の異なる複数の劇場をもつ映画館」にとっては、ヒットの大小にあわせて収容能力の違う劇場を自在に変更できることから、たいへん都合がいい。そのため、 シネコンによる全国同時放映のスタイルが生まれてしまい、「2番館」「3番館」制度はビデオ・レンタルやDVD販売によって無意味化
、「映画等級付け」制度の崩壊を招いてしまったらしい。「ブロック・バスター映画」の興隆は、万人受けする内容でなければならないので、ハイコスト・ハイテク・ハイスピードの世俗的均質の坩堝のような映画の横行、ならびにアート・シアターの廃館と外国映画上映の機会を剥奪をもたらしてしまう。その結果、 「外国映画の再映画権の売買」なる、価値の高い外国映画がしばしばハリウッド映画として再映画化されて世界のシネコンに輸出するビジネスが生まれた
というのだから、驚く他はない。
(続きはこちら
応援お願いします 長すぎて1日では終わらなかった…
)
価格: ¥ 903 (税込)
![]() ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
-
★ 軽やかなロシア社会論 米原万里 『… Jun 21, 2007
-
★ 河口俊彦 『大山康晴の晩節』 新潮文… May 16, 2007 コメント(2)
-
★ 醍醐寺三宝院への旅 Apr 9, 2007 コメント(1)









