PR
X
Calendar
Category
カテゴリ未分類
(16)歴史
(47)経済
(47)政治
(45)社会
(44)哲学・思想・文学・科学
(44)サブカル・小説・映画
(43)音楽・文化
(20)スポーツ・ゲーム
(13) キハ20、DF50、キハ…
 GKenさん
GKenさん
─ 灼熱 ─ HEAT1836さん
余多歩き くれどさん
tabaccosen breton005さん
ミョウの魅 stadanさん
ぶらぶらブラジル日記 Gaobrazilさん
沖縄でよんなよんな sinarsinarさん
りゅうちゃんミスト… りゅうちゃんミストラルさん
再出発日記 KUMA0504さん
 GKenさん
GKenさん─ 灼熱 ─ HEAT1836さん
余多歩き くれどさん
tabaccosen breton005さん
ミョウの魅 stadanさん
ぶらぶらブラジル日記 Gaobrazilさん
沖縄でよんなよんな sinarsinarさん
りゅうちゃんミスト… りゅうちゃんミストラルさん
再出発日記 KUMA0504さん
Comments
日本刀ファン@ Re:★ NHKはウソだ! 『その時歴史が動いた 鉄は国家なり ~技術立国 日本のあけぼの~』について (旧・建設予定地) 接触編(02/21)
とにかく歴史的古代日本で生み出された…
Nov , 2025
Oct , 2025
Sep , 2025
Aug , 2025
Jul , 2025
Oct , 2025
Sep , 2025
Aug , 2025
Jul , 2025
Jun , 2025
May , 2025
Apr , 2025
Mar , 2025
Feb , 2025
May , 2025
Apr , 2025
Mar , 2025
Feb , 2025
Freepage List
Keyword Search
▼キーワード検索
テーマ: 社会関係の書籍のレビュー(95)
カテゴリ: 政治
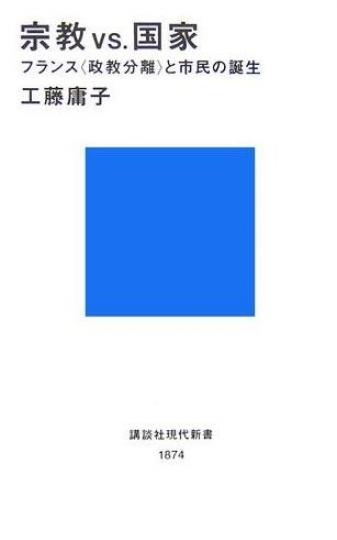
▼ すばらしい。
▼ 「つまらない本しか出さない講談社現代新書」、という私の偏見を吹き飛ばしてしまう快著である。 このブログを読んでいる人は、ぜひとも本屋で購入して欲しい。
▼ マザー・テレサが人権のシンボルであることは、日本人にとって自然でも、欧米人にとって奇異 であるのは何故なのか。 なぜイスラム女性は、フランスの学校で、「スカーフ」を着用してはならないのか。 そもそも、アメリカ・ドイツ・イギリスでは、宗教教育が盛んなのに、どうしてフランスではかくも厳しいのか? その淵源について、文学作品を使いながらたどってくれる、すばらしい19世紀フランス社会史になっているのだ。
▼ 目次は以下のとおり。
第1章 ヴィクトル・ユゴーを読みながら
第3章 「共和政」を体現した男
第4章 カトリック教会は共和国の敵か
▼ 第1章は、『レ・ミゼラブル』である。 ジャン・バルジャンの魂を買った、大司教ミリエル。 ジャン・バルジャンは、終油の秘蹟をこばみ、大司教ミリエルからもらった銀の燭台の光に照らされ、心安らかに臨終の床につく。 売春と奴隷と子供たちの悲惨をもたらす「無知」という名の暴君の絶滅をねがい、友愛と調和と黎明の共和国に賛成票を投じた、かつての国民公会議員医師Gは、ミリエルの薦めを拒絶して、無限の存在の自我こそを神(=理神論者)とする立場を捨てず、ジャンと同様、終油の秘蹟をこばんで死ぬ。 フランス革命の時代、カトリック教会は、憲法への忠誠と引き換えに、「国教会」的な形で護持 され、国家の援助が与えられていたという。 カトリック教会は、プロテスタント・ユダヤ教徒・嬰児・自殺者の墓地への埋葬をこばむので、政府は衛生上共同墓地を造らざるをえない。 今や雑多な宗教でごった返すパリ最大のペール・ラシェーズ墓地だが、創立当初はライシテ(=政教分離)精神の発露どころか、忌避すべき埋葬場所だったという。 ジャン・バルジャンは、死をもって市民権を贖い、ラシェーズ墓地に埋葬される。 市民であることとは、カトリック信徒であることと対立
▼ 第2章は、国家が宗教を管理しようとするナポレオン流のコンコルダートと、宗教を私的領域に囲いこむライシテ原則とは、対極にあることを強調する。 王政復古期は、カトリック教会や修道会が復興した。 「王殺し=無神論者=市民(シトワイヤン)」という概念が生まれる一方、 修道会は、ボランティア活動を通して住民の福祉を支えた 。 驚く無かれ。 われわれの 出生証書、婚姻証書、死亡証書は、元はといえば、カトリック教会教区司祭管轄下の洗礼証書・婚姻証書・埋葬証書に由来 するという。 19世紀、修道会は、職業をもたぬ女性に社会的活躍の場と生きがいを提供し、 カトリック教会は女性化 してゆく。 女性は、男性に比べて、強力な宗教の囲いこみを受けていた。 修道会は、フランスの中等教育において役割を高め、「家族に奉仕する性」である女性にボランティア活動を通してかけがえのないソシアビリテをあたえ、純潔を徳目とした女性教育をおこなった。 フロベールの小説に描かれる、濃厚な「宗教感情」と陶酔をさそう女子修道会寄宿学校の雰囲気は、ミッション・スクールのパロディである「マリ見て」の非ではない。
▼ 第3章は、第3共和制である。 王党派が優勢を占めたにも関わらず、ブルボン派とオルレアン派に分裂していたため、1879年、上下両院で共和派に逆転されてしまう。 フランスのアイデンティティは、「カトリック教会の長女」なのか、「革命の理想を受け継ぐ現代フランス」なのか 。 プロテスタントとユダヤ教徒、ならびに普遍的友愛の世界共和国をめざすフリー・メイソンは、後者に合流。 ジュール・フェリーは、宗教の代替物として「道徳と公民教育」、安息日の労働解禁をおこない、共和国の父、とよばれるようになる。 しかし、良家の子女は、えたいの知れぬ下流階級のかよう公立ではなく、私立のミッションスクールに通わせるのが普通だったという。 「自由・平等・友愛」の標語も、当初からあったのではない。 「責務・絆・調和・共同体」的な「友愛」の定着は、その語のもつキリスト教的イメージ(兄弟、友愛の人キリスト)もあって、「権利、状態、契約、個人」的な語彙である自由・平等より遅れたという。 「友愛」は、キリスト教信仰にかわるものとして、世俗的道徳のカナメとして、非キリスト的な「連帯」「尊厳」の概念が発見される中で、浮上してゆく 。 第三共和制で女性に参政権がなかったのは 、左派において女性は、「カトリック教会に取りこまれた存在」、右派においては「家族に奉仕する性」という、 左右の共犯関係によるもの らしい。大統領令(1944年、ドゴール)で与えられるまで、棚ざらしにされていたらしい。
▼ かくて第4章は、ライシテの総仕上げとなる。 共和派の勝利は、フランス共和国国民の創設の必要性を生む。 かくて、構造的に要請されることになった反教権主義は、コングレガシオン(修道会)にフランス公教育から緩やかに撤退を強いることになる。 反教権主義は、決して輸出されることはなく、 コングレガシオンは、かわりに「文明化の使命」をおびて、植民地教育に進出 したらしい。 ドレフュス事件がおきた理由は、社会主義的な労働者陣営、カトリック主義陣営、ブルジョア自由主義に不満をもつ陣営… 様々な利害のちがう集団を糾合しうる紐帯が、「反ユダヤ主義」しかなかったことが原因
▼ とにかく、フランスに対する、通俗的な認識の変更をよぎなくされる書物であることは、まちがいない。 第三共和制の大臣の6割がフリー・メイソン。 マッチョな植民地帝国である第3共和制。 そこでは、急進党・社会党・共産党の左派勢力とちがって、カトリック教会という支柱、名望家ネットワークを持つ右派勢力は、明確な政党を結成しなかったという。 政教分離法以後も、修道会系の学校は、自由学校に形をかえ、修道会メンバーが世俗の形でなら、教育に携わることが認められていたらしい。 また 政教分離法当時、フランスの政策推進者たちにとって、宗教と国家の共存できる理想的状態とは、アメリカ合衆国だった ……… 現在、キリスト教原理主義に牛耳られるアメリカに対する、最大の皮肉としか言いようがない。
▼ 「不可分の非宗教的な共和国」という国是をもつ、フランス。 そこでは、 公教育の現場からは、軍や警察まで動員して、十字架が撤去された。 この史実こそ、イスラム女性のスカーフを公教育から追放する動きが、フランス人の間であまねく是認される、最大の原因 であるという。 アメリカのフィルターを通しがちな日本では、フランス理解も偏見にまみれがちである。 この状況に風穴をあける入門書、といってよいのではないだろうか。 「ライシテ」とは、単なる政教分離、非宗教性ではない。 「ライシテ」とは、フランス市民社会の基本原則に加え、制度的「決断」を含意するものなのだ、という。 また、筆者は2分法に陥ることもない。 カトリック教会は、アソシアシオンの一つとして、フランス社会において女性を組織化し続け、隠然たる勢力を持ち続けた。 パンテオンでおこなわれた ヴィクトル・ユゴーの国葬こそ、靖国神社の方向性とは正反対の、パンテオンの脱宗教化の完成である という議論は、国立追悼施設に無宗教はありえない、という議論に一石を投じるのではないだろうか。 とにもかくにも、興味深い話でいっぱいなのだ。
▼ とはいえ、これは過剰な批判なのかもしれない。 最近読んだ新書では、ピカイチの面白さだったからだ。 講談社現代新書は100冊以上読んでいるはずだが、こんな面白い本は、本書がはじめてである。 皆さんにはぜひ、お勧めしておきたい。
評価: ★★★★☆
価格: ¥ 756 (税込)
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[政治] カテゴリの最新記事
-
★ 民主党はなぜ戦わない?! 小沢代表秘… Mar 7, 2009 コメント(3)
-
★ 世界一の新聞社と主筆、読売新聞と渡辺… Nov 9, 2007 コメント(3)
-
★ 鉄道政治・社会学へのいざない 原武… Jun 13, 2007 コメント(1)
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.









