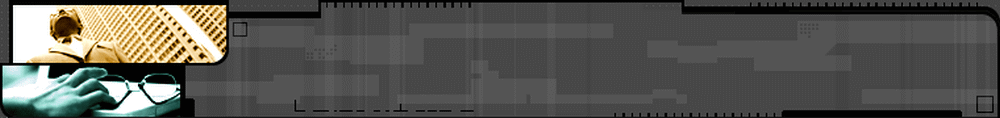PR
X
カレンダー
カテゴリ
カテゴリ未分類
(0)米ドル/ユーロ・円
(129)NZドル/豪ドル・円
(106)バーチャルFX情報
(4)FX奮闘記
(6)アフィリエイト奮闘記
(12)日記
(2)グッピー
(4)キーワードサーチ
▼キーワード検索
フリーページ
カテゴリ: FX奮闘記
世界恐慌(せかいきょうこう)とか100年に一度とか
100年に一度って事は、以前にも同じような事が
起こってる訳で、歴史から未来を予測するのも
自然な流れなのかも知れません。
今日は以前に起こった「世界恐慌」の背景や
行方を個人的にメモすることにします。
参照資料(Wikipedia)、他
世界恐慌
1929年10月24日にニューヨーク証券取引所で株価が大暴落したことがきっかけ。
ヨーロッパ輸出用(食料)⇒農業の機械化による過剰生産⇒各国の購買力追いつかず
↓
アメリカ国内生産過剰
ヨーロッパの復興、相次ぐ異常気象から農業恐慌が発生。また、第一次世界大戦の荒廃から回復していない各国の購買力も追いつかず、社会主義化によるソ連の世界市場からの離脱などによりアメリカ国内の他の生産も過剰になっていった。
また、農業不況に加えて鉄道や石炭産業部門も不振になっていたにもかかわらず投機熱があおられ、適切な抑制措置をとらなかった。アメリカの株式市場は1924年中頃から投機を中心とした資金の流入によって長期上昇トレンドに入る。
株式で儲けを得た話を聞いて好景気⇒だぶついた資金が市場に流入
さらに投機熱は高まり⇒ダウ平均株価は5年間で5倍に高騰
1929年9月3日にはダウ平均株価381ドル17セントという最高価格を記録
調整局面⇒続く1ヶ月間で17%下落したのち、次の1週間で下落分の半分強ほど持ち直し、その直後にまた上昇分が下落するという神経質な動き(それでも投機熱は収まらず)
1929年10月24日10時25分、ゼネラルモーターズの株価が80セント下落
株価は大暴落した。この日だけで1289万4650株が売りに出されてしまった。
翌25日金曜の13時、ウォール街の大手株仲買人と銀行家たちが協議し、
買い支えを行うことで合意。
効果は一時的
週末に全米の新聞が暴落を大々的に報じる。
28日には921万2800株の出来高でダウ平均が一日で13%下がる暴落。
投資家はパニックに陥り、株の損失を埋めるため様々な地域・分野から資金を引き上げ始めていった。
この日は火曜日だったため、後にこの日は「悲劇の火曜日(Tragedy Tuesday)」と呼ばれるようになった。
そしてアメリカ経済への依存を深めていた 脆弱な各国経済(日本も含む) も連鎖的に破綻することになる。
まとめ
産業革命以後、工業国では10年に1度のペースで恐慌が発生していた。しかし1930年代における恐慌(世界恐慌)は規模と影響範囲が絶大で、自律的な回復の目処が立たないほど困難であった。
バーナンキをはじめとする経済学者は異なる見解を示している。
↑今回の経済危機もアメリカ発といっても過言では無いので、彼の発言は無視します。
一つだけメモするとしたら、不況が大恐慌に繋がったのは、その後銀行倒産の連続による金融システムの停止に、FRB(アメリカ連邦準備制度理事会)の金融政策の誤りが重なったためと語っている部分かな?
恐慌に資本主義先進国は例外なくダメージを受けることになった。植民地を持っている国(アメリカ・イギリス・フランス)は様々な政策を採りダメージの軽減に努めたが、持っていない国(日本・ドイツ・イタリア)はそれができず国によっては全体主義の台頭を招くことになる。第一次世界大戦後、世界恐慌まで続いていた国際協調の路線は一気に崩れ、第二次世界大戦への大きな一歩を踏み出すこととなった。
日本
大戦後の恐慌、関東大震災、昭和金融恐慌(昭和恐慌)によって弱体化していた日本経済は世界恐慌発生とほぼ同時に行った金解禁と生糸などの輸出の落ち込みにより危機的状況に陥る。株の暴落により都市部では多くの会社が倒産し就職難の者(学歴難民)や失業者があふれた(『大学は出たけれど』)。農作物は売れ行きが落ち価格が低下、冷害・凶作のために疲弊した農村では娘を売る身売りや欠食児童が急増して社会問題化。生活できなくなり大陸へ渡る人々も増えた。
ブロック経済 政策をとる欧米諸国との貿易摩擦が起こった。この間にも財閥は産業界を支配し、利権を求めて政治や軍に対する影響力を強めた。その後も目白押しの大規模プロジェクトなどで経済的成長が図られたが、資源配分転換と国際協調を背景にした軍縮への軍部の抵抗を止められず太平洋戦争へと向かうことになる。
ブロック経済 とは
自国と友好国を「ブロック」として、関税障壁を張り巡らし、他のブロックへ需要が漏れ出さないようにした状態の経済体制。
自前の植民地経済圏を保持していた大国が採った有効な対応策の一つ。
植民地獲得競争で後れを取っていたドイツ・イタリア・日本の対外拡張主義暴発を即した
要因となる。
以下主観-----------------------------------------------------
どうもこれ読んでると貿易がすごく引き金になってますね。
外需依存型経済の脆弱(ぜいじゃく)性を改めて浮き彫りにした。などと
いう記事も当たり前のようになってきました。
結果として、1月の経常収支は、前年同月の1兆1637億円の黒字から
1728億円の赤字に転落。最大の赤字だった96年1月の赤字額256億円を
大きく上回る規模となった。
上記のような記事が発表されました。
確かに赤字恐るべしなのかも知れませんが、よく見ると・・・
96年の赤字を上回る規模の赤字って書いてありますね、
てことは・・・
その間ずっと黒字だった訳で、その蓄えがものすごいってのも
日本ではないかと思います。
そして、サブプライムや世界大恐慌の影響を日本は運よく回避できている
という記事も目にしました。
たまたま、銀行が再建の為に資金を自由に使える幅が小さかったので、
アメリカ発のイベントに乗り遅れたのが幸いしたような話。
こんな時だからこそ逆の発想で行くと良いかもね・・
メディアの慎重な対応とか
(騒ぎすぎない、前向きな記事)
最先端の商品開発とか
世界への商品PRを強化とか
国内の労働力を食料へ(世界一安全な食料の生産に向けて)
農地の拡大、効率化、機械化、農業人口の増加に力を入れ、
まずは日本の食糧需給率を向上させるとか
米百俵政策w
大恐慌で受けた人的被害(派遣切、就職難)を
もっと高い労働力へと向上させる教育をする事に税金を
投入する。
※労働人口を余らせておく程もったいないものは無いので、
この機会に国が赤字になっても教育に力を入れることが得策かと
「百俵の米も、食えばたちまちなくなるが、教育にあてれば明日の一万、百万俵となる」
まじめな日本の武器は
・安全な食料
・最先端の商品開発
・優れた労働力(教育)
・高い生産力
それを更に生かす事こそ、明日の一万、百万俵になるのではないのでしょうか。
100年に一度って事は、以前にも同じような事が
起こってる訳で、歴史から未来を予測するのも
自然な流れなのかも知れません。
今日は以前に起こった「世界恐慌」の背景や
行方を個人的にメモすることにします。
参照資料(Wikipedia)、他
世界恐慌
1929年10月24日にニューヨーク証券取引所で株価が大暴落したことがきっかけ。
ヨーロッパ輸出用(食料)⇒農業の機械化による過剰生産⇒各国の購買力追いつかず
↓
アメリカ国内生産過剰
ヨーロッパの復興、相次ぐ異常気象から農業恐慌が発生。また、第一次世界大戦の荒廃から回復していない各国の購買力も追いつかず、社会主義化によるソ連の世界市場からの離脱などによりアメリカ国内の他の生産も過剰になっていった。
また、農業不況に加えて鉄道や石炭産業部門も不振になっていたにもかかわらず投機熱があおられ、適切な抑制措置をとらなかった。アメリカの株式市場は1924年中頃から投機を中心とした資金の流入によって長期上昇トレンドに入る。
株式で儲けを得た話を聞いて好景気⇒だぶついた資金が市場に流入
さらに投機熱は高まり⇒ダウ平均株価は5年間で5倍に高騰
1929年9月3日にはダウ平均株価381ドル17セントという最高価格を記録
調整局面⇒続く1ヶ月間で17%下落したのち、次の1週間で下落分の半分強ほど持ち直し、その直後にまた上昇分が下落するという神経質な動き(それでも投機熱は収まらず)
1929年10月24日10時25分、ゼネラルモーターズの株価が80セント下落
株価は大暴落した。この日だけで1289万4650株が売りに出されてしまった。
翌25日金曜の13時、ウォール街の大手株仲買人と銀行家たちが協議し、
買い支えを行うことで合意。
効果は一時的
週末に全米の新聞が暴落を大々的に報じる。
28日には921万2800株の出来高でダウ平均が一日で13%下がる暴落。
投資家はパニックに陥り、株の損失を埋めるため様々な地域・分野から資金を引き上げ始めていった。
この日は火曜日だったため、後にこの日は「悲劇の火曜日(Tragedy Tuesday)」と呼ばれるようになった。
そしてアメリカ経済への依存を深めていた 脆弱な各国経済(日本も含む) も連鎖的に破綻することになる。
まとめ
産業革命以後、工業国では10年に1度のペースで恐慌が発生していた。しかし1930年代における恐慌(世界恐慌)は規模と影響範囲が絶大で、自律的な回復の目処が立たないほど困難であった。
バーナンキをはじめとする経済学者は異なる見解を示している。
↑今回の経済危機もアメリカ発といっても過言では無いので、彼の発言は無視します。
一つだけメモするとしたら、不況が大恐慌に繋がったのは、その後銀行倒産の連続による金融システムの停止に、FRB(アメリカ連邦準備制度理事会)の金融政策の誤りが重なったためと語っている部分かな?
恐慌に資本主義先進国は例外なくダメージを受けることになった。植民地を持っている国(アメリカ・イギリス・フランス)は様々な政策を採りダメージの軽減に努めたが、持っていない国(日本・ドイツ・イタリア)はそれができず国によっては全体主義の台頭を招くことになる。第一次世界大戦後、世界恐慌まで続いていた国際協調の路線は一気に崩れ、第二次世界大戦への大きな一歩を踏み出すこととなった。
日本
大戦後の恐慌、関東大震災、昭和金融恐慌(昭和恐慌)によって弱体化していた日本経済は世界恐慌発生とほぼ同時に行った金解禁と生糸などの輸出の落ち込みにより危機的状況に陥る。株の暴落により都市部では多くの会社が倒産し就職難の者(学歴難民)や失業者があふれた(『大学は出たけれど』)。農作物は売れ行きが落ち価格が低下、冷害・凶作のために疲弊した農村では娘を売る身売りや欠食児童が急増して社会問題化。生活できなくなり大陸へ渡る人々も増えた。
ブロック経済 政策をとる欧米諸国との貿易摩擦が起こった。この間にも財閥は産業界を支配し、利権を求めて政治や軍に対する影響力を強めた。その後も目白押しの大規模プロジェクトなどで経済的成長が図られたが、資源配分転換と国際協調を背景にした軍縮への軍部の抵抗を止められず太平洋戦争へと向かうことになる。
ブロック経済 とは
自国と友好国を「ブロック」として、関税障壁を張り巡らし、他のブロックへ需要が漏れ出さないようにした状態の経済体制。
自前の植民地経済圏を保持していた大国が採った有効な対応策の一つ。
植民地獲得競争で後れを取っていたドイツ・イタリア・日本の対外拡張主義暴発を即した
要因となる。
以下主観-----------------------------------------------------
どうもこれ読んでると貿易がすごく引き金になってますね。
外需依存型経済の脆弱(ぜいじゃく)性を改めて浮き彫りにした。などと
いう記事も当たり前のようになってきました。
結果として、1月の経常収支は、前年同月の1兆1637億円の黒字から
1728億円の赤字に転落。最大の赤字だった96年1月の赤字額256億円を
大きく上回る規模となった。
上記のような記事が発表されました。
確かに赤字恐るべしなのかも知れませんが、よく見ると・・・
96年の赤字を上回る規模の赤字って書いてありますね、
てことは・・・
その間ずっと黒字だった訳で、その蓄えがものすごいってのも
日本ではないかと思います。
そして、サブプライムや世界大恐慌の影響を日本は運よく回避できている
という記事も目にしました。
たまたま、銀行が再建の為に資金を自由に使える幅が小さかったので、
アメリカ発のイベントに乗り遅れたのが幸いしたような話。
こんな時だからこそ逆の発想で行くと良いかもね・・
メディアの慎重な対応とか
(騒ぎすぎない、前向きな記事)
最先端の商品開発とか
世界への商品PRを強化とか
国内の労働力を食料へ(世界一安全な食料の生産に向けて)
農地の拡大、効率化、機械化、農業人口の増加に力を入れ、
まずは日本の食糧需給率を向上させるとか
米百俵政策w
大恐慌で受けた人的被害(派遣切、就職難)を
もっと高い労働力へと向上させる教育をする事に税金を
投入する。
※労働人口を余らせておく程もったいないものは無いので、
この機会に国が赤字になっても教育に力を入れることが得策かと
「百俵の米も、食えばたちまちなくなるが、教育にあてれば明日の一万、百万俵となる」
まじめな日本の武器は
・安全な食料
・最先端の商品開発
・優れた労働力(教育)
・高い生産力
それを更に生かす事こそ、明日の一万、百万俵になるのではないのでしょうか。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[FX奮闘記] カテゴリの最新記事
-
損切り 2008.02.26
-
ランキング若干下落!! 2008.02.22
-
ランキング上昇中!! 2008.02.19
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.