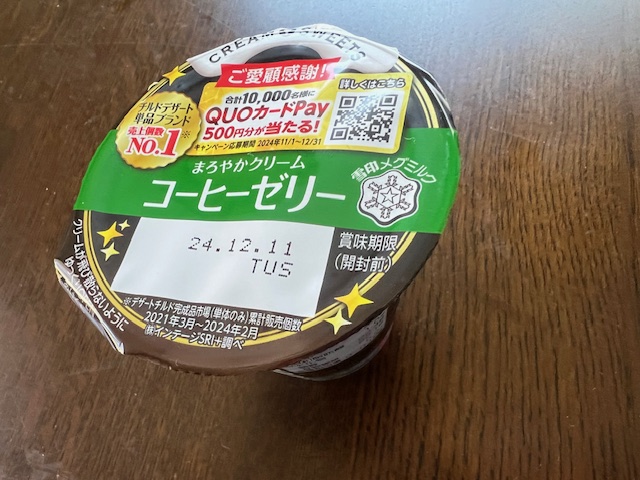(6)
前章と重なるが、ここではモンタージュ理論と呼ばれる考えを基に編集を考えていく。
エイゼンシュテインの映画「戦艦ポチョムキン」(1925年ロシア)はモンタージュ理論を実践した映画として名高い。ショットを積み重ねることで全体像を思い描かせつつ、より心理的な映像としてシーンを組み立てることに初めて挑んだ作品と言える。特に有名なのが乳母車が階段落ちていくシーン(「オデッサの階段」と呼ばれている)で、多くの映画監督がそのシーンの再現、パロディ化に情熱を燃やしている。近年では「アンタッチャブル」でのまさに乳母車が階段を落ちていく駅のシーンは「ポチョムキン」を再現したと言っていい出来になっている。緊迫した空気を最大限に活かし、さらに複数の人物の心理的な動きを捉えている。反対に「スピード」ではそんな時代ではない、という意味を込めて一蹴している。
モンタージュ理論というもの自体、よく耳にするもののその実態が掴めない言葉だ。更にエイゼンシュテインが映像を作りつつ、理論を組み立てていた頃と今とでは映像の作り方、見方に大きな変化がある。彼の理論で物を考えるのは、現在の映像制作を考える時にはそう重要ではないと考える。しかし、汲むべきものはある。
通常のシーン作りではその場に居合わせた一人の人物を仮想することで映像の編集が行なわれる。その人は初めてその場に居合わせるわけだから、通常、全体が判るロングショットから始まる。しかし、必ずしも人はロングショットから物を見ない場合がある。タイトショットから改めてロングショットに入る。物をどういう順番に見たか、という行為の再構築だ。ある別の人物に従って行くとしたら、その人物の背中をフォローするショットがあり、目的の場所に来たところで周囲を眺めるパンショットが入るだろう。仮想の人物からの視点=撮影者の視点として捉えた考え方であり、もっともオーソドックスなカメラワークについての考え方である。全体を空間または時間をもとに一つの視線として考え、構築していくのだ。
モンタージュ理論の成果と言われている「ポチョムキン」の階段シーンでの構成は違っている。映画なので、その現場の空間はすでに判っているものとした上で、タイトショットが続いていく。しかし、カメラの位置はそれぞれまったく別の場所で一連の時間を描いていく。それは複数の視線であり、そのほとんどがタイトショットで出来上がっているため、様々な視線に対応する人の心理状況を描き出していくことに成功し、更に衝撃的な事件としてのまとまりも持たせている。それはまさしくカットを編集することによって生まれる力だ。この力を意図的に使うことで大きな主張を表現することが出来る。それがモンタージュ理論の根幹である。シーンの流れを追ってみよう。オデッサの港へ続く長い石段では戦艦ポチョムキンの反乱の成功を祝う人々で混雑している。その歓喜の中で事件が起きていく。
1) 髪振り乱す女性のアップ数カット
2) 混乱する人々
3) 足のない障害者が両手を使いつつ階段を降りている
4) 白い日傘がカメラに向かって飛び込んでくる。
5) 階段の上、銃を構えた兵士の隊列が見える。(ここで混乱の意味が判る。)
6) 群衆は階段を駆け降りていく。
7) 兵士たちは群衆を追い落とし、殺戮を始める。
8) 殺戮がエスカレートしていく。人々は逃げ惑う。
9) 少年が撃たれ、倒れる。
10)倒れた少年を踏みつけて行く靴。(群衆の弱さの表現が明確にされる。)
11)少年の母親が少年を抱き上げ階段を上っていく。
12)女教師が呼びかけ、群衆が母親に続いて動き出す。
13)兵士の攻撃の手は止まない。
14)美しい母親が赤ん坊を乗せた乳母車を押して逃げている。
15)階段の踊り場に到達する兵士たち。
16)母親は赤ん坊を自分お体で庇う。が、撃たれ、倒れる。
17)乳母車が階段を転げ始める。加速していく。
18)乳母車が倒れる。(群衆の弱さが象徴的に表される。)
19)ものすごい形相のコサック兵のアップ。
20)サーベルを振るう。
21)女教師が切り付けられ、片目から血が噴き出す。(群衆の弱さが明示される。)
エイゼンシュテイン自身はこう語っている。
「モンタージュとは異なった画面と画面を積み重ねて思想を説明するのではなく、異なった画面と画面を衝突させて思想を生み出させるものである。モンタージュの細胞たる画面の中に、すでに相克を呼ぶ矛盾が、すなわち潜在的モンタージュが存在しているのだ」
しかし当時、1920年代のロシアの社会情勢(革命に継ぐ革命の時代)から、エイゼンシュテインの理論は「映像はプロパガンダに使える」という狭い理解にしか行き届かなかったかに思える。また、この映画自体も様々な検閲を受け、国によって全く違った映画になってしまっている。1925年に作られたものの、完全な姿での公開が行なわれたのは1976年になる。世界中のポジ・プリントから再び作り出すのに擁した時間が半世紀に及んだ。そしてその上映機会はなかなかない。(この文章を書いている当人もスチールでしか見た経験がない。)
全く別な世界のショットをつなぐ場合、様々な解釈が生まれる。時にそれは多様なイメージの温床となり、歓迎される。ミュージック・クリップではそうしたカクテルされた画像が複雑なイメージを振りまいている。支離滅裂な映像としか言えない映像も今では充分に存在が求められている。そしてそれすら人々に何かを喚起するものとなっている。
こうした映像作りというのはエイゼンシュテインが活躍していた当時思いもよらなかったことだろう。そこからひとつの思想なり確実な意味なりを読み取ることはできない。ひとつの嗜好としか言いようのない映像の固まりになっている。現在の映像の状況から見るとエイゼンシュテインのモンタージュの根本にある「画面と画面の衝突」は意味が残っているものの、それ以外は数段大きな自由を得てしまっているのだ。
しかし、全体を通してひとつの主張、伝えたいことがある場合、こうした編集は慎重にならざるを得ない。「画面と画面の衝突」は思いがけない方向に意味を運ぶこともあるが、予想以上の効果を上げることもあるからだ。まして、タイトショットが連続する事態はその順番が大きな意味を生んでしまうことが明らかだ。
「ポチョムキン」では反乱に転向する群衆(ポチョムキンの反乱に賛同している)が兵隊と衝突するその勢いと実力を乳母車に象徴させている。乳母車のか弱さはまさに群衆を表現している。群衆はなんの手だてもなく、ぶつかって倒れるものとして描かれているのだ。そのために乳母車が必要だったのだ。
象徴的なものを扱うことによって、複数の視点を持ったカットの集まりがひとつのシーンとして統合されていく。もちろん、こうして作られた映像だけの話ではない。
あるNHKスペシャルのシーン。
1) 銀座の街の俯瞰ショット。地下鉄の出口からぞくぞくと出てくる人々。
ズームインして一人の背広姿の男性を中心としたショットとなる。
2)同じ男性の歩きを正面からフォロー。ある建物に入っていく。
3)あるオフィスのドア。彼がフレームインしてドアを開け、中へ入る。
カメラも一緒に中へ入っていき、彼をフォローする。
撮影には2日間を使っている。担当ディレクターは明日も同じ背広と同じネクタイをして来て下さい、というお願いだけをしたという。俯瞰のみ次の日に撮影したのだ。
最初のカットにより、彼はどこにでもいる日本の会社勤めの人として充分に認識される。もちろん、映像もコメントも余計なことは一切語ってはいない。次のショットでこの人物を追っていることが明らかになる。人物を紹介し、ここに勤めていることが判る。更に彼の立場に至るまでの説明が次に来る。無駄なく、彼を誰とも置き換えが可能な、しかし、具体的な一人の人物として導いている。
この最初のカットがなかった場合、ここまでの表現を映像は出来なかっただろう。具体例で見よう、という表現しか出来ない。カットを衝突させることで表現出来ることのレベルがひとつ上がってしまうのだ。
このレベルでは何気ない、ということはあり得ない。あるとすれば意図された何気なさであろう。僅かにルーズすぎるショットを使うことで対象との距離感が出る。そうした意図的な部分には何気なさはあるだろう。しかし、ここまで考えたものの場合、そのショットは充分に計算され、必要と思われた状態で編集されている。映像は論理構成だけでなく、象徴的な意味も含めた広い要素で成り立っている。編集はそこまで含めたものとしてそれぞれのショットを扱わねばならない。もちろん、多義的な存在である映像のことだから、制作者の意図を越えた意図が自然に発生する。しかし、何よりもまず制作者が意図的であることが編集の基点となる。モンタージュはそのことを私たちに教えてくれている。
© Rakuten Group, Inc.