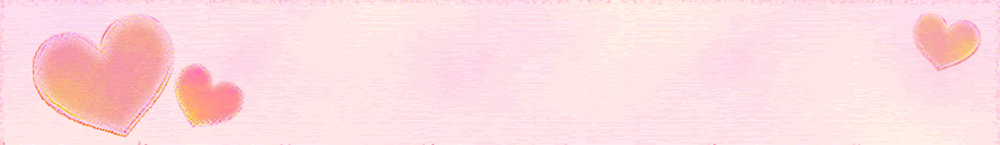老人保健施設の選び方
特別養護老人ホームと違って入居しやすい老人保健施設。預かってもらって安心していたのもつかのま、思わぬ展開が――。あなたの周りでこんなことは起きていませんか?2つの事例をもとに対処法を考えてみましょう。
事例1
介護保険制度がスタートするまで、3年間、自宅で母親の芳子さん(仮名)を介護していたという石島紀子さん(仮名)。
しかし、もともと親子関係がうまくいっていなかったことに加え、体が弱く、介護は精神的にも肉体的にも大きな負担だったといいます。
そのうち、自営業を営む夫が、事業を縮小し人手を減らしたことで、自らも働かねばならなくなりました。
しかたなく、芳子さんは老人保健施設へ。2年半ほどそこで過ごしましたが、やがて退所してほしい、と施設の人に告げられました。そこで別の老人保健施設へ移りましたが、そこでは半年間しか滞在できないそう。
「今、特養に申し込みをしていますが、だめならまた老健に入所するしかありません。あまり転々と居場所を変えると、母にも負担がかかるのでは――。かなり心身が弱っているだけに、不安です」
事例2
80歳を過ぎても出歩き好き。近所でも評判の元気印おばあちゃんだった、大野マツ江さん(仮名)。娘さんの節子さんとは長いこと二人暮しを続けてきました。
しかし突然、大腸ガンを発症し、入院。手術は成功したものの、病室暮らしが長引いたために、足腰は見る影もなく弱ってしまいました。
勤めに出ている節子さんには、退院後、寝たきり状態のマツ江さんを介護することができません。仕方なく老人保健施設へ入所し、リハビリをしてもらうことにしました。
ところが、実際にはリハビリは行われず、マツ江さんはますます寝たきりの状態に。自宅にいたときはどうにか自力でトイレに行っていたのですが、それもできなくなり、おむつをあてられるようになったのです。
1年後、体調を崩した挙句、再び入院。マツ江さんはとうとうそのまま、自宅に戻ることなく亡くなってしまいました。
老人保健施設は、看護、医療的管理下において機能訓練や日常的ケアを行う施設。特別養護老人ホームが終生利用できるのに比べ、あくまで一時的な入所を前提としています。入所期間は通例、3~6ヶ月。厚生労働省の調査では平均229.2日とされています。しかし、利用者の家族側は、もっと長い滞在を希望する場合が多いよう。
「入院が長引いたりすると、その間にお年寄り抜きの生活パターンができあがってしまいがち。例えば、一家の主婦が介護から解放されたというので、パートに出かけたりするわけです。なかなか在宅では世話ができないので、特養が空くまで預かって欲しいと考える家族は少なくないのでは」(ケアマネージャーAさん)。その結果、ひとつの老健を退所すると、今度は別の老健へ移るお年寄りも多く、いわゆる「たらいまわし」現象が起こりがちです。
その一方で、これら特養待ちの利用者のため、長期滞在を容認する老健もあります。こうした施設ではリハビリよりもケアに重点がおかれる傾向が。いずれ在宅介護を、と考えているにも関わらず、あまりリハビリがなされないまま結局、施設に居ついてしまうケースもあります。
その場しのぎ入居は
後々、トラブルの原因に
「短期間の滞在の間にリハビリをしっかりおこなってもらえるのか、それとも長期間の利用が可能なのか。入所する前に、その施設の方針をしっかり確かめておくべきです」と語るのは山梨県にある老人保健施設の職員Bさん。そのときになって困らないためにも、事前に施設側やケアマネージャーさんとしっかり打ち合わせ、短期型か長期型かを見極める必要があります。
そのうえで希望に添った老健かどうかをチェック。いずれ在宅で介護しなくてはならないなら、在宅復帰に向けて生活面でのリハビリをおこなってくれる施設かどうか――たとえば「ユニットケアを導入しているかどうか――などを確かめます。また、退所後、在宅介護することになっても困らないよう、デイケアやショートステイ、リハビリ施設、医療機関など多機能な併設施設がある老健を選ぶ、という手もあります。とにかく、後々困ったケースに陥りがちなのが、その場しのぎ的な入居。一時の都合に惑わされず、長期的な介護計画をたててから施設を決めたいもの。長期入所が可能なら、いつぐらいまで滞在可能なのかもしっかり聞いておき、その後どうするのかについても考えておくようにしたほうが無難です。
もちろん、施設側も家族の困惑をよそに、無理やり退所させることはありません。退所時期については、入所の際にあらかじめはっきりさせておくのが基本ルール。その時期が迫ってくると、医師、看護師、介護福祉士、ケースワーカーたちが会議を開き、本人の心身状態を考慮したうえで在宅介護が可能かどうかを検討します。当然、判定には受け入れ家族の状態も関わることになります。とはいっても、受け入れ家族がいない、介護役は年老いた伴侶のみ――といった、あきらかに在宅介護が難しいケースならいざしらず、微妙な家庭問題まで施設側がうかがい知ろうはずはありません。
「そのほかの理由で在宅介護が難しいのであれば、事前に伝えておく必要があります。日頃、家族会や行事に参加するなど、施設側とコミュニケーションをとっておくようにしてもよいでしょう」(ケアマネージャーAさん)。
突然、病気になったり、痴呆症状があらわれたり――お年寄りの健康状態はいつ一変するかわかりません。ともすれば、すわ、一大事!ということで、あわてて入所先探しをする羽目になりがち。そこはいったん、冷静になって今後のことをよくケアマネージャーさんと相談のうえ、施設選びをしましょう。「うちはまだまだ元気」という場合は、今のうちからしっかり計画を立てておくとよいですよ。
老人保健施設を選ぶ前に・・・
1. 長期的な介護計画を立てる
2. 長期滞在型か短期リハビリ型をしっかりチェック
3. 退所時期を確認
4. リハビリ内容をチェック
5. 複合施設かどうかなどをチェック
6. 家族会や行事などに参加するなど、施設とのコミュニケーションを密に
© Rakuten Group, Inc.