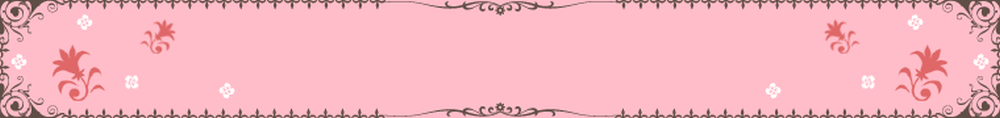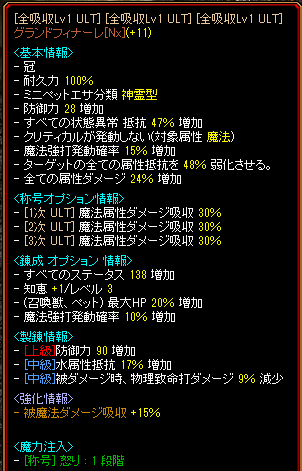第11章微笑みのマッドハンター
「・・・・ヴィンセント・・・」
本当なら、その名を呼ぶ時、ヴォルフリートにためらいなど感じさせないはずだった。吸血鬼の手したが砂のように静かに消えていく。
「久しぶりだね、カイザー」
柔らかな風のような、そんな優しい気持ちが流れていた。
「ベルクウェイン、どうしたのよ」
「うるせえ」
格好悪い。
ヴォルフリートだってさびしいはずだ。泣きたいときだってあるはずだ。
「お前、何している・・・」
かなり走りまわっていたのか、息を乱して顔も蒼白だ。部屋にはラテン語や事件の記録記事やら、難しい哲学やかなりグロテスクなものもあった。
「僕頭がよくないんでまずは足で動いてみようかと」
オカルトや魔術の本まであった。
「・・・営業の本に交渉の本、これは大人が読むものだろう?」
「ルドルフ様と違って僕口達者じゃないし、人付き合いできないから・・」
「一体何の目的でこんなことをしている?」
じろりと青い瞳でヴォルフリートをみる。
「もうすぐカイルやヴィンセントの誕生日だし・・・、彼らの親って難しい学者だったから探ってみようかと」
だがどうも頭脳的なことは苦手なようだ。
「警察に任せろ」
「わかってるくせに・・・」
ぼそりと何か言った。
「え?」
顔を真っ赤にして、ヘレネはプレゼント選びをするアリスの買い物に、その笑顔に付き合っている。
「ごめんね、せっかくのオフの日に」
「いいのよ、予定も入っていないし」
「ありがとう!」
白い花弁が舞う中、アリスがほほ笑む。
ああ、神様、助けてくれ。
努力していたのは知っていた。だが意地やプライドがヴォルフリートという兄を認められなかった。
「本当、彼運動神経ないね」
エルネストの脳裏に、けなげに笑みを浮かべるディートリヒの愛らしい涙が思い浮かぶ。自分は思ったよりはブラコンだったのか。冷たい美貌だと思っている。生意気だと。歯牙にもかけない相手を弟は気にしている。
そう思ったら話しかけていた。
「エルネスト・・」
二階からヴォルフリートが礼儀作法の教師や武術の教師と授業について話していた。使用人も冷たく笑っていた。愛想がいいだけの落ちこぼれ。
「いい加減彼も自分に見切ればいいのに、お父様もそこまで彼に求めてないのにな」
美しい弟にとって自分はライバル、気のいい兄だ。動揺がばれていないだろうか。ああ、くそ、もやもやする。
どうしたんだ?
「確かに・・」
だが彼はいい加減な一方で、努力家でもあった。誰よりも能力が低いのを自覚し、優秀すぎる王子や姉に追いつこうとしていた。
「育ちのせいですかね、あきらめが悪いのは」
氷水のような澄んだ声には一見するとさげすんでいるようにも見える。だが、気のせいか、どこか熱量も静かにあるように思えた。胸の奥がなぜかいたんだ。何だ、イライラする。様子に気づいたのか不思議そうにかわいい顔で、子供っぽい表情で見つめてくる。
・・ドキドキ。
見つめるんじゃない、胸がおかしくなるだろうが。
「ああ、そうだろうね、孤児院でも一番落ちこぼれだったそうだし」
ひやりとした笑みだ。
「以外に意思が強いのかもしれませんね」
「おや、優しいね」
ふいと視線をそらす。
「努力を軽んじないだけですよ」
自分とは毛色が違うし、やることなすこと鈍くてイライラする。外見もそこそこで。
だが、唯一羨ましいと思えるのは。
「本当にお前は馬鹿だな」
惹きつけるものはない。
特別な何かなんて、ないと思っていた。
「やあ」
「へらへらするな」
冷たいジュースを頬に当てると擦り傷に当たった。
「厳しいな、ディートリヒは」
「何でそこまで頑張れる?」
あきらめてしまえばいい、次男何だから適当に過ごせばいい。
「自分の能力以上のことなど母上も姉上も求めていない、お前が頑張る必要はないだろう」
「あれですよ、ホラ、僕も一応男だし」
はぁとため息をついた。
「男の意地か、馬鹿だな」
「君と同じだと思うよ、ディートリヒ。無理して優等生になる必要はないよ」
にこりと笑う。
「僕のどこが」
「僕は期待されないから、時間が有り余っているからわかるよ、いつも目が赤くなるまで剣やフランス語を頑張っているだろ」
「全て、皇帝陛下のために」
ギいいと冷たく重い音が城内で響く。
「皇太子殿下もお変わりなく―」
「ああ」
マニュアル通りの言葉はいつも軽く、重い。
将来を見込んでの、貴族や地位の付いた人間の子供達。機械のような目で紙芝居のようにこびた言葉を向ける。
「聞いてよ、ルドルフ」
その声にほっとする。
「やあ、ギ―ぜラ、珍しいね」
柔らかく皇帝がほほ笑む。それにつられて、ルドルフもほほ笑む。落ち着いた色合いのドレスを切る女官や衛兵が道を譲り、品定めするように自分たちをみる。綺麗で贅沢で美しい、豪華な宮殿に彼らには見えるのだろう。庶民にもここは明るい場所に。
「ルドルフ、どうかしたの」
「いや、何でもない」
鏡を手の中から落した。
「そんなに驚かなくても」
なぜ、姉さんもルドルフ様もそんなに僕が恋愛していたことにこうも驚くんだろうか。
「まさか、ありえん!!」
「ありえないって、ひどいですね」
「お前みたいなデリカシーのない男が、ありえn、いくらだ、どんな手管だ、どんな悪女にだまされた!!」
ありえない、ありえない。
「落ち着いて、ルドルフ様」
というか、それは僕に失礼じゃないか?
「僕という親友がいながら」
声が震えている。視線も下に向いている。
「親友だから、彼女を紹介するんですが」
「そんな・・・」
のらりくらりとふらついている。
「そんなにショックを?」
「・・・ろ」
「え」
「その女と別れろ」
一切、セレスティアは笑顔の可愛い、温厚な天使のような少女は泣かなくなった。
虚ろなその瞳は世界を、人間を拒んでいた。
「どうして、自分のことしか考えない、あさましい人間のために手を貸さなければいけないんですか?」
彼女は、愛しているというセリフを信じた。人と分かりあえると。
冷たく凍えた祖に瞳は世界を憎んだ。
「貴方に笑顔を奪われたのに」
その髪を憎んだ。
「貴方に悲しみを奪われたのに」
その瞳を憎んだ。
「貴方に怒りを奪われたのに」
その優しさを憎んだ。
「貴方に生きる喜びを奪われたのに」
その心の美しさを憎んだ。
「貴方に人生を奪われたのに」
孤独を憎んだ。
「貴方に太陽の下で歩く自由を奪われたのに」
醜さを憎んだ。
「貴方にあの人は殺されたのに、アーディアディト」
神様でもあくまでも何でもいい。
これが夢だといって、妄想だと、現実じゃないと。
ピッピッ
ガラス越しの中で、感情というパーツを魔法武装という形で、異能者に奪われた、存在そのものが平気にされた、金髪の長い髪の、姉がいる。
基本的な部分以外は、抜け落ちていく。
なんでもする、なんでもする。
全て捧げてもいい。どうせ、間違いの命だ。こんな命なくなってもいい。
こんな牙が、爪が何の役に立つ。赤い血のような烙印がひきつる。
涙が流れる。
力を。姉さんに自由を、笑顔を。
「なんでおとうとなのに、ねえさんをたすけてくれないんだよぉぉ、なんでぇぇ」
中にいるトトのせいでゴットヴァルトの中は壊れている。
全て破壊していいから。おねがい。
姉さんをにんげんにもどして。
こんな命なんかいらない。
「あの女はお父様に色目を使ったのよ」
2
アリスは驚いた顔をしていた。シェノルという少年―俺は生まれて初めて見る金髪のかわいい女の子にときめいていた。
「貴方が選んだの?外国の人よね」
「うん、中東のトルコの生まれで身分は中流階級だって」
アリスが恐る恐る指差す。
「ちゃんと生まれとか生活環境とか調べて、よネ。まさか、面白そうで選んでないわよね?」
自分の隣の主人となる少年は楽しそうに笑っている。
・・・何か、とろそうな坊ちゃんだな、こいつが主人で俺大丈夫か?
「イスラム教徒でトルコ語だったから、傍にいたら僕もトルコ語喋れるかなって」
「マジか!!」
思わず、叫んでいた。
「何いきなり叫んでるんだよ、びっくりするな」
「あなたねぇ、いつも物事は順著立てて、感性で選ばないってあれほど」
はぁぁと深くため息をついた。
「それに体格のいい大人に対してのずる賢さや度胸、体重を乗せた鋭いパンチや次の動きの機転のよさや判断力、アームブロックやナイフによる近距離戦、チームワークでの回転率の早さ、体の頑丈さ、傍にいれば姉さんのボディガードもできると思うんだよね」
・・・ああ、ただぼーっと見てたんじゃなくて分析してたんですか。そういえばものすごい速度でメモをとっていましたね。
「だからなぜそういうところばかり目につくの、どう見てもその子目つき悪いし、品性もなさそうじゃないの」
「お前、結構言うな」
「あら、何か言ったかしら?」
じろり。
「姉さんと僕のため何だ、いいよね?」
ヴォルフリートが慣れた手つきで少女の手を握る。
「う・・・」
もぞもぞとするディートリヒに用事から帰ってきたエルネストは気付いた。周囲を気にして挙動不審だ。
・・・具合でも悪いんだろうか。
その時、従者のミカエルが心配そうに駆け寄ってきた。
「先生を読んできました」
「・・・ああ」
「行きましょう」
寄り添うミカエルにああ、とディートリヒは肩を預ける。昨夜は自分にあんなに頼ったのに。
ヴァイオリンを片手に、ジ―クムントはヴォルフリートと向かい合っていた。宮殿の一室で、皇太子の相手をするために呼ばれたのだ。父親は将来のためとか言っていたが、ジ―クムントはルドルフを守る立場の軍人か、政治のサポート役になりたかった。
欲を言えば、親友になりたいのだ。
「ヴァイオリン?」
少しでも上流階級の子息らしくするために、と呼び出されたのだが。どうも生徒役のヴォルフリートは音楽にきょうみがない。
「集中しろ」
紙飛行機を飛ばしたり、走りまわったり。妄想したり。
「こんな呪文みたいな難しいの、僕には無理だよ」
「・・・こいつは」
「つまんない、つまんない」
「足をバタバタさせるな」
服の袖をつかんで座らせる。
「お前は一応俺より年上だろ」
「うん」
ため息をついた。
「幼児じゃないんだから、男らしくヴァイオリンの稽古をしろ」
「こんな楽器覚えなくても、生きていけるよ」
ヴァイオリンを椅子の上に置いた。
「大体、なんで家じゃなくて、宮殿で?」
「俺が知るか、ほら弦を持って」
ヴォルフリートの手に触れるとひんやりしていた。
「お前、手が小さいな」
「そう?」
ジ―クムントは身体を寄せて、ヴァイオリンを弾かせた。
「俺の指の動きに合わせろ」
「ボールで遊ぶ方が面白いのに」
「貴族の子はこんなヴァイオリンやピアノ、詩の暗唱を普通にできるものだぞ、この楽譜も教師に渡されて十秒で誰でも覚えられるぞ」
不満そうなヴォルフリートの顔がジ―クムントの方に振り向く。
「そうなのか?」
「ああ、どの貴族の子でもだ」
ヴォルフリートが楽譜をみる。
「ふうん?」
眉をひそめている。
「ゆっくり教えてよ、僕馬鹿だから」
「ああ」
それはぼけた言動と普段の行動でわかる。
自分の部屋の扉を閉める。
「よかった・・・」
「よくな髪が零れませんでしたね」
メイドのリリーが隣の部屋から出てくる。
「そうだな・・・」
「ぐっしょりしていますね・・・坊ちゃん、シャワーでも浴びられては?」
「だが、私の部屋のは壊れてるだろう」
「それなら、お姉さまのを借りられては」
「・・・そうだな」
今日は付かれた。
アリスは恋をしていた。アロイスとかいう下級貴族の年上の少年と。
僕には手に入れられない、自由な本物の恋。苦しんで傷つけても、まっすぐな彼女は困難に立ち向かっていく。太陽のようにまっすぐで明るい。
正面から相手に立ち向かっていく。僕にはない強さだ。
「ルドルフ様」
「殿下」
「貴方は素晴らしい」
賛美するものやこびる人間が多い。
でもいつだってそれは僕のものではない。ジ―クムントという貴族の少年さえそうだ。
熱意的な視線は臣下のものだ。皇太子という僕を見ているだけだ。
エレオノールのかみにルビーの十字架が絡まったのは、ちょうど、買い物にでて大通りに歩いている時だった。
「あら、ごめんなさい」
「いえ・・・」
シスター時は控えめにしているので、目の前の貴婦人も自分がマフィアの愛人だとは気付かない。馬車の接触事故に大勢の観客があり、従者を連れたエレオノーるの姿もそこにあった。妙齢のはずのエレオノーるは、戸惑ったようにルビーを見ている。
「奥様、大人しくして置いてください、今、外しますので」
「ごめんなさい、人にぶつかって」
「いえ・・・、飛び出した私にも責任がありますから」
従者が劇場に戻るか、とぎょうしゃに聞かれたといってきた。
「いえ、貧血もあるし、ここで帰るわ。貴方は娘に先に帰った、と伝えて」
「はい、奥様」
つ、とエレオノールが声を上げる。
「大丈夫ですか、・・・・私がお医者様を呼んで着ましょうか、何か連絡できるものは」
「それは・・・・」
その時、アリスがエレオノールのもとにやってきた。
・・・・あら、可愛い子。娘さんかしら。
ルビーの悪戯心に火がつきそうだ。
劇場の客席から体を起こし、顔見知りのバレエダンサーに挨拶をした後、ロビーでマリーベルに声をかけられた。
しかも仁王立ちで。
あからさまに挑発的な態度だった。
「・・・・ヴァルベルグラオね、アリスの弟の」
「はい、そうですが」
「・・・この前のことでお礼がしたいんだけど、私についてきてくれる?」
この前?
「今から?」
「着なさい」
強引だ、と思いながら、ヴォルフリートはシェノルと共にマリーベルの後をついていった。ファンの目がきつい・・・。
2
「ヘレネ、ずっと私たち親友よね」
その言葉に胸が痛む。
「もちろんよ」
「よかった」
大好きな笑顔が今はヘレネを突き刺す。
「酷い子たち、セットをめちゃくちゃにして」
「うん、でも、私が傷つけたから」
「それは違うわ、アーディアディト」
貴方が抜きん出た才能を持っているから。
「ヘレネ」
「貴方は悪くないわ」
どこかのバー。
「・・・偉く男前の顔だな」
「煩いよ、ほら、暁の目の情報」
エレクが手を差し出す。
「情報料」
そっけない言い方だ。
「・・・・」
ヴォルフリートはお金を渡した。
嵐の晩、一座の踊り手で案内役だという北欧風の美人姉妹と偶然、暖炉の前で籍を同じする事になった。本当なら使用人部屋に近い客室などは言ってはいけないのだが、遠くからの旅人とと言う事と、普段は屋敷に閉じ込められ、婚約者と使用人、わずかな親友たち、過保護な両親と弟だけの環境で過ごしていたことも影響して、少女らしく話に胸を躍らせていた。
「まあ、ロシアではそんな怖い事件が」
「ええ、王族同士や貴族の争いで領地を取り上げられて・・・」
真っ白な雪のような肌を赤く染めていた。
「怖いわ・・・」
「先導者がいるのよ、いつまでも王族に国を任せるのはおかしいとかいう、行かれた暴力的な」
「ロヴィーサお姉さま、ですが私たち、スウェーデン系の移民で、純粋なロシア国民ではありませんし、確かにロシアの血が色濃く出ていますけど」
「スヴェア」
しゅん、と肩を落とす。
「アルゾノで色素も薄いですし」
「だからこそ、ドイツの親戚の所に生き、私たちで家を復興させようと決めたでしょう」
「・・・・ダイヤモンドの発掘者だったのはご先祖様ですし」
ヴィクトリアの目が輝く。
「まあ、ダイヤモンド」
「ええ、大昔ですけど、領地をもらえるほどの家柄で鉱石関係の仕事もしていて、お叔母様なんかは勲章を国王陛下からもらったことがあると」
「・・・・今はお姉さまだけで」
遠慮がちにヴィクトリアが隣のスヴェアに聞く。
「―私達は会わなければいけない人がいるの」
「・・・・え?」
きょとんとヴィクトリアは首を傾けた。
「命をかけて守らなければいけない、これは私達一族の大昔からの約束事で私達でご先祖様の望みをかなえなければいけないのよ、私達の主よ」
「主?」
「・・・・ええ、今もこの胸にその鼓動を感じるわ」
15歳の少女は確かにそう言った。
3
よっぽど、殿下が好きなのね」
「はぁぁ!?」
ジ―クムントは突然のアリスの言葉に戸惑いを感じる。
「知っていた、アリス、私、ずっとあなたが嫌いだったの」
ショックを受けた表情。
「貴方の優しさや慈しみも、甘さも」
全て。
「ずっと、その上から見た偽善者ブリに吐き気がしていたの」
「しゃ・・・」
うまく言葉が出ない。
アロイス・ツァー・バルツァー侯爵は幼い頃の大病で顔に怪我を追い、高貴な家柄でありながら、女好きで賭け事が好きで金と名誉にしか興味のない凶器の父親とヴィクトリアと同じようにローゼンバルツァー家への憎しみに囚われていた。もう一つ囚われているのは、不公平な扱いを受け、家を持たない異能者の救済だった。彼は、祖母の写真を肌身離さず、持ち歩いている。
ザァァァ・・・・
シャワーを浴びながら、異能者の自分を慕う子供達のことを思う。彼らのためなら、何だってやってきた。
「まさか、本気じゃないんだろう?」
「お前か、リリー・・・・」
「帝国やローゼンバルツァー家のせいでどれだけ犠牲が出ているのか・・・アロイス、お前が一番知っているだろう」
紅の口紅が添えられた唇が妖しく笑う。
「・・・・当たり前だ、だから」
「エレオノール乃娘に近づいたか、本気になったわけじゃないんだろう。エレクやあんたはあの日を忘れたわけじゃない」
ぎり、とアロイスは悔しそうに噛む。
「彼女は何も知らない、俺は・・・傷つけたくない」
「エレクに比べると甘いね、あんたは。アイツは既に自分の手を血で染めているよ」
表情が氷のように引き締まる。
「そんな事、わかっている!!」
壁を力いっぱい叩いた。
4
口からは赤い血液が流れていた。間隔が短くなり、女の毒々しさが現れているように感じた。赤い血のような夕焼けの森の中で、エレオノールの白い傘が揺れた。慈愛のこもった優しい目で彼女はバケモノを見ていた。ただ、静に。背筋が冷たくなった。
姉は素直に彼女が正気となり、喜んでいたが、ヴォルフリートは彼女の母性を、自分に対する異質な目を恐れた。怖かった。
「普通なら、怖いはずじゃないの?お母さん」
「怖くないわ、だって、私は貴方のお母さんだもの」
ヴォルフリートの表情が青くなる。口からは赤い液体が流れていた。
ウィーンの聖母、澄み切った水のような優しさ。確かにその手は暖かい。
赤い毒々しい赤いドレス。白い艶やかな肌、白い首筋。その美しさにぞくりとなる。
獣じみた衝動がヴォルフリートを襲う。
「ヴィヴァリー夫人・・・・」
いやだ、いやだ。傷つけたくない。餌なんかじゃないのに。
「喉が渇くでしょう、貴方の異能者の力は強すぎる。だから他人からエネルギーをもらうことは当たり前なのよ」
「う・・・!!」
青い瞳は優しい目でヴォルフリートを見ていた。
「うぅ・・・・・」
吐き気と吸いたい衝動を喉を押さえて必死で押さえる。何度も、何度も喰らいたい感情と感覚が襲い掛かってくる。
「貴方の乾きは他人しか癒せない」
ヴォルフリートの瞳から涙がボロボロと出てくる。身体がざわつき、身体中の血が一点に上り詰めていく。瞳が鋭くなる。
「ぅぅ・・・・・・や、・・・はぁ、やだ・・・・・よ」
たまらなくて、はきたくて、食べたくて、息が詰まりそうだ。喉に何かが引っかかった感覚。何で、僕がこんな。
「死ぬわけじゃないんだから」
エレオノールがヴォルフリートの手を奪い、夫人の首に当てる。ぞくり・・・、となる。
ざわざわ・・・・。
「いや・・・だ・・・・」
ざわっ。
「いいのよ」
瞳から意識がなくなる。
「―-」
「食べなさい、ヴォルフリート」
意識が途切れた。
激しい苦しみから解放された後、屋敷の中で姉のことで喧嘩するレオンハルトとエレオノールフサイの姿があった。自分の立場を気にするディートリヒの姿も。
・・・・・姉さん。
「貴方は過保護すぎます、家庭教師を三日連続で首なんて」
「アーディアディトを傷つけるものはだれであろうと許さない」
父は、姉を愛していた。家に来たとき、娘よと抱きしめた。外に出る時はついてきたがった。学校をという意見が伯母からあったが大人しい父がその時激怒したのをヴォルフリートは目撃した。
・・・・姉さん、助けて。
「どこにいるの・・・」
この家は、・・・・なんか、怖いよ。怖くてたまらないよ。理由はわからないけど、怖いよ。
「病気なんだ、僕」
最近の自分の体を見ても、そうとしか思えない。
5
馬車に偶然ゴットフリートと一緒になった。ウィーンの町は荒れていた。
「最悪だな、お前のその醜い顔を早朝から見ることになるなんて。庶子生まれのお前がどうして、栄光ある警備隊の隊長についているんだ、しかも騎馬隊の指揮まで」
「・・・・出世したそうだな、おめでとう」
「ああ、ヨハネスおじいさまのおかげだよ、後はわが妻がルドルフ様のお気に入りなんでね、全てが順調だよ」
「・・・妻」
「そう、僕の妻、アーディアディトだよ、あの女清楚な振りして、若い執事を誘惑しやがった。とんだあばずれだよ」
「ゴットフリート・・・・」
空気が変わった。
「・・・そういえば、お前とヴィクトリアが見合いするんだってな、叔父上ならは約手を打つと思っていたが、正義の貴族の家の娘をお前がねぇ」
「家の人間が決めた事だ」
「その見合いの席の狩猟会に、オッドアイの死神が来るぜ」
「・・・・アーディアディトの弟か」
落ち着け、落ち着くんだ。双思いながらも、見つかったという緊張感が体に焦りを生み始める。
「いくらなんでも、すぐにとっちめないわよ。素直にあの人の書斎に忍び込んだ理由を言ってくれれば」
ルビーは気付いた。手袋のしたを脱がすと、見慣れた指輪がある。
「な、何を」
仮面を素早く取ると、澄み切った青い瞳が会った。一度見た、可憐な少女。
「貴方、私と同じなのね」
「え・・・」
「私と同じ、パンドラゲームのプレイヤーね」
「ぱ・・・んどら・・・・」
初めて聞く言葉だった。
6
薄暗い室内、妖しく光るろうそく。
派手な色の貴婦人たち、扇の音。
毎日、毎日。
なぜ、どうして・・・。
なぜ、僕が彼女たちにこんなひどいことをされるのか。痛い、苦しい。
僕は何もしていないのに。
―背中にしるしを上げましょう。
―可愛い駒鳥さん。
「貴方は永遠に私たちのお人形さんよ」
・・・・あ。
「ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああっ」
いやだ、いやだ。
だれか。
「誰か、助けて」
・・・・あ。
「何だ、夢か」
ぎりぎり・・・。
「びっくりした」
「は、はなせ!!」
ヴォルフリートに両手両足を拘束され、関節技をアルフレートはされていた。
「あー、よかった」
「貴様、いいかげんに!!」
「夢でよかった」
場所はプラハ。ヴォルフリートの双子の子供、兄は神となったアリスの作り上げられるまでの世界で、かつてのゲームの参加者が集まる為に利用した時計等に、父と同じ赤毛が混じったダークブラウンンの髪のツインテールの妹と共に、組織との内戦の最中の休息に、訪れていた。蝋燭や洗礼の為のたらい、カップが床に散らばっていた
。
「神の使徒が権力争いか、どこも変わらないな」
民族の衣装を身に纏い、旅芸人か逃亡者でも装っているのだろう。だが、いずれも彼らにはどうでもいい肩書きだった。地が散らばっているが、既に黒ずんでいる。
「お兄様、早く移動しないと、組織からの追っ手が」
眉の一つも、兄と左右対称のオッドアイにも人間らしい感情は欠如していた。まるで精巧なカメラが一枚取るように少女は兄の姿を映す。
「ローゼンバルツァーの尻尾にはかつての力はない。いくらでも時間は稼げるさ」
黒髪の美少年と美少女は今年で14歳を迎えようとしていた。
ルドルフが男爵令嬢と心中事件といわれる歴史的な事件を起こす前の二ヶ月前、ある異能者が事件を起こし、公爵であるリヒャルトと黒髪の美女との間に刺殺事件を古城で起こし、逮捕された。美女は異能者の恋人だったというのに、剣で刺したと言う。
破産し、母の葬式と妻の葬式、妹の葬式を同時に挙げなければならなくなり、金を作ることになったギルバートは裏切られた絶望と怒りで心が揺れていた。悲しみがギルバートの心を包んでいた。
「それではもって行きますね」
「・・・・ああ」
沈痛な声だ。次々と差し押さえられ、親しいものは大嫌いな血だけがつながった父と爵位だけが残ったギルバートから離れていく。
「・・・・・あいつのせいだ」
だが激情を、死を受ける罪人のばつをギルバートは与えられない。
刑務所に行けば、犯人の男と合えて、殺すことが出来るだろう。何故、何故だ、なぜ、こんなひどいことを。
数人の観客と男達に囲まれ、馬車に運ばれていく時、一度たりとも異能者はギルバートを見ようとしなかった。死ぬのだ、自分から幸福を奪った男が。うねりがほんの少し下がる。暗い喜びが湧き上がる。
「だんな様」
古参のメイドが扉を開けて入ってくる。
「何・・?今は放っておいてといったはずだ」
「お客様です」
また、新聞記者だろうか。父親が巻き込まれた理由について聞くのか。
「帰ってもらってくれ、僕は今人と会える精神状態じゃない」
はぁ、とため息をついた。
「・・・・ですが、・・・・その」
「何だ」
「・・・・お客様は・・・・、ヴォルフリート・フォン・ローゼンバルツァーの子息だと」
「!?」
アーディアディトが社交界の席で、パートナーのゴットフリートに連れられて、ディーター・フォン・ビルツバウムとベルノルトから金髪連続殺人の情報を得たのは、昼下がりの事だった。
「そうだよ、見たぜ、犯人がリュービクラル家の屋敷近くで姿を消したのを」
「・・・・気持ち悪いな、ビルつばウム、こんな美しい女性が多くいる席でそんな、血なまぐさい話は止めてくれよ」
僕は繊細なんだ、と目をそらしながらゴットフリートがそういって、持っていた荷物をアリスに乱暴に渡した。
「ちょっと」
「妻だろ、夫の持ち物をちゃんともっておけよ」
馴染みの女性が、ゴットフリートに近づき、冷たい目でゴットフリートは挨拶に行くとアリスに行った。
「~~っ」
扇をきつく握った。
同時刻、夜に差し掛かった時、美しい上流階級の貴族の女性にうっとりと見つめられながら、閣議を終えたルドルフは皇帝であるフランツに追いかけられていた。
「待ちなさい、ルドルフ、もう少し人の気持ちを」
「父上、でしたら、自分に発言をお許し下さい」
「・・・ルドルフ、お前は若すぎるんだ。我々は多くの民族や問題を抱えている。確かにお前の提案はすばらしいものはあるがお前は先進的過ぎる。ちゃんと、周りの違憲も聞く事もお前の役目だぞ」
「皇帝陛下に、ルドルフ皇太子殿下よ、相変わらず美しい親子です事」
「凛々しい横顔、あのお方をエリザベート様が独占なんて」
「まあ、皇帝陛下のお気持ちもわかりますわ、あんなに美しく洗練された方ですもの」
ほお、と貴婦人たちは熱い視線をルドルフに向けると、優しく慈愛のこもった笑みを浮かべる。
「父上、自分はこの国を守りたいのです。伝統を守るのは私の役目ですが、これからのオーストリア・ハプスブルク、二重帝国を国民の幸福を守り、発展させるのも自分の役目です」
美しい容貌の取り巻きはルドルフを崇拝し、守るようにルドルフの後についていく。
「殿下、跡でいつもの時間に」
「ええ、公爵夫人、いつもの宵の刻に」
「楽しみにお待ちしてますわ」
ルドルフは誰が見ても幸せそうな表情で、幸福感に包まれているように、くじけない強さを持っていた。
劇場に帰りに、アリスは弟に写真を取ろうと誘った。
「・・・遠慮したいな、僕、ほら、写真取ると、目をつぶるクセが」
「大丈夫、私がついているから」
卑怯だ、そんな笑顔を向けるなんて。写真は苦手なのに。
「・・・一枚だけだ」
「有難う、ヴォルフリート!!」
目撃者殺せ。不審者は殺せ。裏切り者は殺せ。容赦をするな。
双子の妹は、歯ブラシで歯を磨くように、毎日、教祖や教師にそういわれた。異能者同士は異性以外は敵だ。殺せと。そう、教育された。だまさなければ、だまされる。信用すれば、殺される。愛されると思うなs、殺されるぞ。笑顔の時は、その裏の感情を探れ。利用され、忌むべき敵とされ、駒とナって捨てられるか、それが異能者の運命だ、それ以外の道はないと。悪魔の子供達なのだから、と。
扉が重い音を立てて、ギィィと音を立てる。
「・・・終わった?」
兄は最上階の鐘を撃つ部屋から出てきた。
「完璧主義のお前らしくないな、少し雑だ」
「少し寝不足で苛立ってた、それにこの人間たちが、お父様の写真、私から奪おうとするから」
兄がうなずく。
「それなら、仕方ない」
「うん、仕方ない」
妹もうなづく。
ずぶんと重くなった細い腕を振り下ろす。少女はゆっくりと兄の元に向う。
「服も汚れた、・・・こんな格好じゃ、お父様に会った時に笑われる。・・・どうしよう」
その時、初めて少女は子供じみた表情に変化した。
「・・・恥ずかしい」
兄は一度、妹の困惑した表情を見ると、したいから血で濡れた写真をすくい上げて、誇りを振り払った。
「拭けば、大丈夫だよ。それにお父様は服が汚れたくらいで、笑わない」
「・・・・・」
兄は、妹の赤い手を握った。しかし、一ミリも頬を緩めず、冷たいままだ。
「行こう、ウィーンへ。お父様が待っている」
7
森の中ではパラソルの下で金髪の貴婦人、エレオノ―ルが友人たちとおしゃべりに明け暮れ、ヴォルフリートはアリスに無茶されていた。
「姉さん、だから泳げないんだって」
「12歳のお兄さんでしょう」
川の中で特訓させられていた。
「今度こそあいつとのかけに勝つんだから」
ルドルフ様か。
「かけごとはいいけど、少しはレディーらしい振る舞いを」
「まあ、私にお人形さんみたいに行儀よくしていろというの」
アーディアディトの顔がヴォルフリートの顔に近づく。
「私からおてんばと負けん気取ったら何が残るというの、ヴォルフリート!!」
「姉さん、顔が近い」
吐息が届きそうなほど。
「いいじゃない、血のつながった兄弟何だから」
アリスはにっこりとほほ笑んだ。
「ね?」
微かにヴォルフリートの表情が止まったように見えたがすぐに笑顔を浮かべた。
「そうだね」
廊下を歩きながら、待たせている、中庭へとギルバートは足を伸ばす。
「・・・・確かにアイツは過去に2度結婚しているが、・・・何故、僕の家に?」
「それが私と執事頭で事情を聞きまして、彼には正式な子供はなくなられた現在の妻との間のヨハネスだけだといいましたんですが」
「・・・・外で作った子供というわけか、・・・・年齢は?性別は?」
「・・・・・」
メイドの口は重く硬い。
「言いにくい相手なのか、わかった、君は下がって言い。相手は子供だろう」
「はい」
中庭では、赤い薔薇が咲き誇っていた。季節はずれの薔薇だ。
ギルバートは曇り空の中、ベンチに座る15歳ほどの黒髪の少年と同い年くらいの赤毛が混じったダークブラウンの15歳の少女の姿を見つける。
・・・今、彼は30代だ、・・・・やっぱり、事件を聞いた詐欺師か?
「・・・・君、ちょっと・・・・」
服装を見ると軍服のような服を着ている。
「・・・・・貴方がギルバートですか」
その少年が振り返った瞬間、ぎくりとなった。瞳の色だ。瞳が右が青い瞳で左目が緑色だったからだ。
「・・・・・・君は」
少年と少女は立ち上がる。
「本当は他の兄弟も連れてくるはずでしたが、・・・すみません」
一ミリも少年は表情を崩さず、クールな表情で艶やかな雰囲気を漂わせながら、じっとギルバートを見た。
「・・・その、君は本当にヴォルフリートの」
「はい、息子です。父・・・が捕まったというのは本当ですか?」
「・・・でも、年齢が合わないよ」
「はい、僕と彼女は父も知りませんから。僕が生まれたのは15年前、今まで父の知り合いに育てられました、ギルバート。父が14,15歳の時、僕は、ローゼンバルツァーの手で双子の異能者として父が知らない間、サンプルの父の一部をつかって、人間の恩などもに生ませ、造られたそうです、ウサギや犬が新たな種をニンゲンによって生み出されるように。・・・しかし、今、問うべきは僕の事情ではありません、ニンゲン達から父を救うことです」
「お父様は異能者・・・私たちの家長です。私達全ての異能者を世界から保護する義務があります。滅ぶ世界にお父様が付き合う必要はありません」
「・・・よろしく、ヴォルフリート」
「・・・・姉をお願いします、アロイスさん」
アリスがアロイスを紹介したのは、オペレッタでの会場だった。本当のところは心配だった。アウグスティーンに言われた事はすぐに聞いたが、誤解だといってくれた。いつだって、ヴォルフリートはアリスの味方だった。
「君が認めてくれて、嬉しいよ」
「自分も貴方に会えて、光栄です、アーディアディト姉さんが好きになった人ですから」
穏やかな清涼とした微笑だった。
「僕は二人を応援しますよ、ゴットフリートの方は僕も何とかしますから」
「ヴォルフリート・・・」
「家のための夫婦なんておかしいから、そうでしょう、姉さん?」
「ヴォルフリート!」
アリスが明るい笑顔を浮かべる。包み込むような笑顔を、なぜか方を震えさせながら、ヴォルフリートはアリスに向ける。
翌日、容疑者の一人にローゼンバルツァー馴染みの情報やや交鈔やの友人や妹分、ゲルマン系の医者や看護婦が警察に連れ込まれる事となった。
「昨日はルーマニアにセルビア人、スロバキアにダルマティア人か」
「書類にはんこをお願いします」
「ふう・・・・・」
長いまつげに触れて、切れ長の瞳をルドルフは揺らしていた。
「それと、女官がルドルフ様にお部屋に早く入れてくれるようにと。掃除のものがあのような荒れた部屋を持続させてくれるなと」
「後で行っておく・・・」
「お願いします」
エリアスが書類を持って、部屋を出ようとした時、ああといいかけた。
淡い色の艶やかな髪をかきあげて、紅茶を飲もうとしたルドルフはなんだと答えた。
「そういえば、ヴァルフベルグラオ家のご長男、ルドルフ殿下のご友人、昨日の夕方ドナウ川で作業時間中の終わりですか、エルフリーデ様とデートしてましたけど、あのカイゼルひげの自慢家の部隊、大丈夫なんですか。白いドレスに薔薇の飾りをあたまにつけて、あれ、彼の趣味ですかね」
「え?」
「あのおてんばもあんな女性らしい、艶やかな表情できるんですね、でも、元気はなかったですが」
「へぇ、ギルバートがベルクウェインに。君たち仲悪いんんじゃないっけ?」
趣味の読書とカメラにいそしみながら、ヴォルフリートはディーターの自宅でまどろんでいた。ディーターは足を組んで、イスに腰をかけて、シャツを緩めて、気ままに過ごしていた。わかりやすい明るいイケメンだ。社交家で女性には優しいから、悪い一面も別の印象を与えるようだ。
「やぁだ、ディーターったら」
側には遊び相手のバレエの踊り手がいた。
「アイツ、俺が好きだからな」
「あからさまに嫌いだろ。君のポジティブは君の悪いところだな。ディーター、何故、双思うならいじめを?」
「してねえよ、アイツが勝手に深刻に捕らえて、突っかかるんだよ。まじめで正義ナ奴はこれだから」
ディーターははっと笑う。
「ヴィルフリートも大概だけど、君も底意地、相当だよ。ディーター、君、サド?マゾのどっちなんだ。さすがに腕を折るのはどうかと思うけど、気に入ってるなら君こそ仲良くしたら」
「俺のときは性格悪く・・・いや非道に振舞いながら冷静なんだよ、お前」
「は?」
ディーターはすねたような表情になった。
「なのに、お前、ギルバートには感情的だろう。何と言うか、むかつくじゃん。俺達、友達なのに」
「君がギルバートを苛めるのは賛成してるだろ、僕は君と違って別にアイツの事なんか気に入ってないし。それこそ、自殺でもしろと思ってるよ、ジプシーのくせに大貴族ぶってさ、いいコぶって、薄気味悪いんだよ」
「でも進んで付き合ってるだろ、お前」
「・・・・・まさか、僕が理由という気か?ごめん、それだったらゴメンこうむる」
「わかったよ、いじめねえよ」
「面倒くさい奴だな、君は。・・・・僕だって、あいつとは付き合いたくないさ」
「は?」
「田舎に住んで、ひきこもりたい~」
「それは駄目だ。ほら、いつもの、薬、飲むだろ?」
夜に差し掛かる時、ヨハネスが挨拶に上がり、ヴォルフリートはその後をついていき、今日の予定について、ヨハネスと宮殿内で会っていた。厳しい深い色合いの碧い瞳に深い皺、高貴さと厳格さ、隙もない動作。
誰もがヨハネスの姿を見ると、恐れおののき、敵であるものは一応の敬意を払う。
「しかし、貴様、全然父親に似ておらぬな」
「ローゼンバルツァー公、今はそのような」
「・・・・硬い事を申すな。若者は学ぶ時間が私より多いではないか。どのような事情であれ、お前が皇族とつながりを持っていたこと、私は感謝すべきだな。私はよい孫を持ったようだ、どうだ、あれとは話をしているのか」
「世間並みには」
「・・・ヴォルフ、お前、今も私の約束を覚えておるか」
書類を持つ手が止まる。
「私は宝をお前にやるつもりはないからな、だが、殺しはしない。私は約束を守る男だ」
くっくっ、とヨハネスは笑う。
「方針も変えないと、異能者は罰するべきものだと」
「我が家のしきたりだ、神に愛された帝国に異能者は存在しない」
アリスとルビーは、港で相対することとなった。パンドラゲームを教える、とルビーが一方的に言ってきた。満月に照らされたルビーはどこか世界を拒絶しているように見えた。
「騎士の家柄だから、ロングソード?べたね」
「・・・・」
アリスの表情には警戒心と困惑が浮かんでいる。
「昨日の話しだと決闘なんですよね」
「単純に言えば、そうね。勝者は王の器を与えられ、世界を革命することが出来るそうよ」
からかうような、おどけた口調。それがルビーの喋り方らしい。
「何故、教えてくれるんですか?私は貴方のライバルでしょう、エントリーされてるなら」
空気が変わる。
「そうね・・・」
ひやり、としたアイスのような感覚。
「私が退屈することが怖いから、かしら」
初めて、感情的なニュアンスになった。
「退屈が怖い?」
ルビーはにこりと微笑む。
「貴方の年齢だと、まだわからないわね」
8
幼い頃のルビーは王子様を待っていた。
不公平で、自分を苛める世界から助けてくれる王子様を・
今から考えれば、ありえない話だ。現実に自分の都合のいいように助けてくれる男はいない。最初の一手を、先生をして、アリスに放つ。インドの懐刀を手にして、曲がった刀をアリスの白い首に当てようとする。
「はぁぁぁっ」
何とも、単純で、わかりやすい剣だ。スピード重視だ。
剣に重さがない。鍛錬は重ねているが、自分を陥落させるには、何かが足りない。それは何。
そう考えながら、ダンスのように、相手の動きに合わせて、力量を確認しながら、件を振舞っていると、
「貴方の望みは何なんですか!」
と少女が聞いてきた。
自分の周りにも金髪は多くいるが、ユリウス・ツヴァイリングのウェーブかかった、艶やかなレモン・イエローの髪は太陽に愛された色だった。言動こそ粗暴だが、高貴な振る舞いや仕種、切れ長のクリスマス・グリーンの瞳は普通の容貌を持つ自分にはいらだたしさを感じさせていた。情報屋と同じように、家族や友人を、スロヴァキアで皇帝陛下の命令で失った過去を持つという。何度か、ヴォルフリートと教師によって組まされた殺し合いで戦いあい、引き分けをしあった仲でもある。
相手の力量は経験もスピードも自分よりも優れている。
それがわかるくらいは、アリスは成長していた。このまま長期戦で行けば、恐らく相手のペースに巻き込まれ、自分は相手に一手を放つことも泣く、負けると。だから、ルビーの戦う望みを聞こう、そう思った。
「あら、私が正直に答える女に見えて?」
速いスピードで近距離にアリスに迫る。アリスも反応し、相手から一歩下がる。剣を構え、ルビーと向き合う。
「いいえ・・・」
小指をルビーは唇に添えて、くすくすと笑う。
「ですよね?自分をすぐに相手にさらすような女は、好かれるけど、飽きられるのも早くてよ」
「・・・・」
「でも、コミュニケーションには情報は必要よね」
ルビーが刀を構える。攻撃態勢に入った。
「それなら、交換条件と行きましょう」
「?」
アリスは首を傾けた。
「何ですか」
一息、ついて。
「私が勝ったら、貴方の大切なものを貰いましょう。貴方が勝ったら、そうね、私の命である髪をあげましょう」
「大切なもの?」
「・・・・ルドルフ皇太子よ」
何故、私からルドルフ殿下が・・・いや、今、疑問を持つより。
「私は人を賭け事の道具にしない、間違っていることだもの」
真っ直ぐ、アリスがルビーを見る。
「あら、以外にまじめなのね」
剣をルビーに向ける。
「どこから、そのナを」
「こう見えて、私、交友関係広いのよ」
ルビーはそれだけを言った。
鏡の前で、マリーベルの艶やかで整った髪をルビーがくしで整える。プライドが高く、他人と距離をあがる明るいピンク色を感じさせる髪のマリーベルは、スターの街道を登る新人歌手だ。それゆえに下から上がってくるライバル候補には容赦がない。
「せっかくの美人が台無しよ、マリーベル」
「だって、せっかくアップしたのに、寝癖やクセ下が残ってるなんて」
そうはいっても本というのに、ほんとうにちょっとだ。
「いいじゃない、少しくらい」
マリーベルが大きい声を上げる。
「駄目よ、お客様が私を見に来てくれるのよ」
「マリーは、プロ意識が高いんだったわね」
「当たり前よ、最高の私を見せなくて、いつ、見せるの」
「これから、またリハーサル?今日はオンリーの舞台なんでしょう、海賊衣装のオペレッタ」
「前座よ、でも完璧にして見せるわ」
ふっ、と誇り高くマリーベルが笑う。控え室のp外ではお姉様、と慕う踊り子の姿があった。
ガラス窓がガタガタと揺れていた。
白い足にはぁ、とルビーは舌を滑らせる。
「シスター、君はこのオーストリアをどう思う?」
一生に一度しかない、最高の出会い。本来なら、視線すらかわすことの出来ない人。支配者が、ルビーを支配していた。
・・・・いつか、殿下に会いたい。
ルビーは乾いた日々の中、そう思うようになった。
だから、自由になりたかったのだ。
絶体絶命、アリスが目を閉じた時、氷がルビーの目を突き刺した。
「何、これは・・・・!?」
ルビーが声を荒げ、オーバーアクションをする。
・・・・今だ!
馬車を買えている待ちの間、花売りからアイリスの花を貰った。
「男が花を貰ってもな」
路地裏で、暴漢に包丁を差し出す燃え上がるオレンジ色の髪の少女と小さな少年が視界の隅に入った。服装はぼろきれのようで、使い古しのようだった。男達の怒声が余りに煩い。煩すぎて、頭痛さえする。
「坊ちゃん」
「暇つぶしをしてくる」
全く、子供を苛めるならもっと目立たない所ですればいいのに。
「何だ、てめえは」
「うるさいから」
いきなり、男の顔面を殴り、他の男が殴りかかったので腹を鋭いキックを浴びせた。悲鳴が鳴り響き、残った男は去っていく。
ああ、静かになった。
気絶した男達が静かになり、ヴォルフリートは確認すると、子供達のほうに目もくれずに警察官の下へ、子供達の手を引いて、下いた方向へと歩き出した。
夜中は静かにして欲しい。
剣がルビーの胸に突き刺さる。
獣じみた悲鳴がアリスの耳を突き破った。
勝者、アーディアディト・フォン・ヴァルベルグラオ、と時計ウサギが行った。
どうなる・・・。
アリスはぐっとなった。
「あ・・・ああ・・・」
ルビーの瞳孔が開く。くしゃり、とルビーの身体が捻じ曲がっていく。それは現実にはありえない光景だった。
本当に、偶然に、その時、軍服のヴォルフリートが通りかかった。こちらに気付いて、驚いたようにこちらを見る。
ドン。
「あっ」
「やああああああああああっ」
アリスを突き飛ばし、まるで救いを求めるようにヴォルフリートを目掛けて、ルビーは走り、アリスは追いかける。
あと数センチ。
「ひっ」
「・・・たすけっ」
最後には正気に戻ったように涙をこぼし、頬を緩めて、笑みを浮かべた、袖を掴んだ瞬間、ルビーは消えた。
別荘での地下室の儀式では、ローゼンバルツァーの親族たちが集まっていた。異様な光景に驚いた。人間の敵であるはずの恐ろしい異能者たちが怪物かされ、その肉を人間たちに虐げられ、食われていた。冷たい汗がヴォルフリートの幼い身体を伝う。
いや、それよりも目を奪われたのは。
それは巨大な屍のように見えた。アリスに与えられた立場は異能者からさらに進化した、悪魔を亡ぼす異能者の騎士王。人類の剣。彼女の能力は、神や神獣を操るものだった。天井には、宙吊りになったアリスのためのイスが会った。
「全ては、宇宙の断りのために」
その言葉が何度も繰り返される。
アリスは部屋の中央で奇妙な機械とつながっていた。身体中の地がざわめき、冷たくなっていくのをヴォルフリートは感じていた。機械からギミックが現れ、彼女の首を挟み、何かを注入させた。
周囲の状況も異常だが、何より恐怖させたのは、その異様な姉の姿だった。
・・・・な・・に・・・。
人形のように座る彼女の足元には、服が散らばっていた。
「我らはナイトメア」
黒装束の人間たちの言葉が続いて、発される。青くなり、ふらついたヴォルフリートの身体をラインハルトが支える。
何なんだ、これは。
「・・・・ラインハルト・・叔父様?・・・・これは一体」
言葉が引きつる。機械の頭部部分が意志を持っているように光り輝く。
「・・・よく見ておきなさい、アレはパンドラだ」
足が引きつり、動くなる。体が震えだす。さっきとは違う、恐怖だ。
「ぱ・・・んどら・・?」
「我ら一族の闇だ・・・・」
駄目なんだ、いとおしすぎて。近づきすぎては。
「ん・・・」
ダミアンはヘルミ―ネの唇に指先で触れる。
© Rakuten Group, Inc.