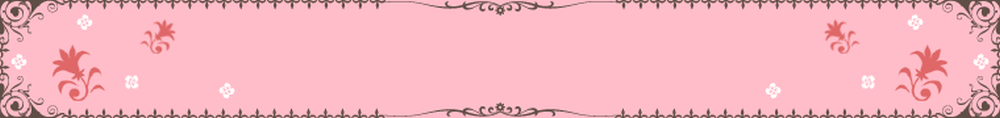第一章
1
なぜ、あなたがアリスなの?
鏡は目の前の人物しか写さない。
アリスはただ夢見る少女。無垢な少女だ。
ヒュウウウー・・・・。
カラ―ル王国、アルトメルデ帝国よりはイシュタルに近い、森林に囲まれた小さな国だが、灰色のオオカミを国の紋章にしているだけに、国ができてから周りのいさかいに干渉されてきた。
昨日の昼ごろ、猟師が確かに空を覆う巨大な水色の光を目撃して、王宮に報告して、調査に来た王宮の関係者は、絶句した。
「これが16年前、あの男を破ったメシアの光か」
「宿命なのだろうな、滅びゆく世界の」
賢者は妙なことを言う。
「パンドラならそうだが、お前たちは」
「神はお前らを生み出した、人間のためではなくな」
帝国主都アルトブルムから、僅かばかり離れたローゼンバルツァーの別邸。そこは勇敢な神フランが降臨された、山や森に囲まれた、湖がいくつかあり、泉や川もあり。わずかなばかりの村がある。都会の喧騒など無縁。
しかし、12歳の少女は利発さはあっても、まだまだ大人の言いつけは破りたくなるものだ。このところ、貴族の令嬢らしく振舞うよう、求めらる事が多くなった。空の色をとかしこんだようなスカイブルーの瞳、腰まで伸びた黄金の長い髪、雪のように白い肌、可憐、愛らしさ、どこからみても美しい少女。
「あれが・・・」
「ええ・・・」
妹のフィネはこういう冒険に付き合わないが、隣の少女に似た、少年は付き合ってくれる。禁じられた、森の奥の奥の古びた洋館、猟をするために作られた小さな洋館。
「行きましょう」
金髪の少女だ。美しい。ドドドドド・・・・ッ。多くの悪魔が、アリスを追いかけてくる。年のころは12あたりか。
「殺しなさい、殺すのです」
追いかけるのは美しい、王冠をかぶったプリンセスラインのドレスを着る、黄金のロッドを持つ女性だ。多くのモンスターを連れて、アリスを追いかける。トランプ兵が怖い顔で叫ぶ。
――あいつを殺してしまえ・・・・ッ。
トランプのカードが散らばる。
次の瞬間、目を覆うほどの鮮やかな虹色の光が。
その時意識が完全に飲み込まれて――。
洋館の地下には、何重もの鎖やらで巻きつけられた細身の剣があった。細かい装飾も施されており、カイザーは触れようとして手を伸ばす。
「私も」
「じゃあいっしょに」
白い、二人の指が其の剣の柄に触れかけた時、突然ぐらりと視界が揺れる。
「地震?」
かなり大きく揺れ、カイザーが思わず剣をつかんだその時、足元に出張った部分があり、足元を滑らせる。
「ひっ?」
壁が割れて、天井からいろんなものが落ちてきて。大きな瓦礫のかけらがカイザーの頭上を。
ごぅぅん。
激しく、頭部を殴られたような衝撃がカイザーを襲う。
「きゃああああああ」
アリスが悲鳴を上げ、次の瞬間、額から血が流れた、それもかなりの量だ。その瞬間、カイザーの体から光が迸り、目が虹色に光り輝き、何か唐突に誰かに乱暴に頭の中をいじられているような、妙になじみがあるような感覚が走り、頭がパンクしかける。そして、意識を次、ロストした。
―五年後、現在。
「これは・・・・」
第4区で、カイザーは占い師からおびえたような声を出された。
「何?」
シャーロットも、アリスリーゼも、ア―ガンスも不思議そうに見ている。
「貴方には不吉な星、死と破壊、混沌、身の破滅が迫っています」
「はぁ?」
「ですが大丈夫、すべてを失っても貴方が持つ巨大な生命力と強運があなたを絶望の淵から救うでしょう、ですが油断せぬように、貴方の振舞い方次第では、貴方ん重大な使命をダメにしてしまうかもしれません」
「何なんだ、シャーロット」
「ええと・・・」
「つまり、お先が真っ暗?」
はっ、と鼻で笑う。
「ありえない」
雲ひとつのない晴天。あまりに穏やかな時間。緑が生い茂り、花々が咲いて。でも金の長い髪、空の色を映しこんだ少女は、丘の上に下りていくモンスターに叫んでいた。
まだ何も言っていない。
本当にほしかったのは、貴方との、何もない。
「待って、行かないで」
光が窓から差し込んでくる。意識が現実に戻る。時計の音が鳴り響く。
「・・・・ア、夢?」
扉が開く。
「姉さん、急に大きい声出して、どうしたの」
茶色の髪が風で揺れる。見慣れたオッドアイ。ああ、夢だったのか。
アーディアディトは心から安どした。
「なんでもないわ」
アルトハイドヴァーデ帝国。
「お母さん、ありがとう」
彫刻に彩られた壮麗な石造りの建物。大通りは大きく開き、華麗な店が並んでいて、街路銃はきちんと整列するように並べられ、黒い街灯が憂いなどないように、学生や恋人たちを迎え入れている。
「いいのよ」
石畳のメインストリートの先には王宮がある。エールリングとも呼ばれていて。市民の心のよりどころである、銀の十字架の守護神エスぺランサの肖像旗額の重要施設に誇らしくはためている。
『残酷なるイシュタル王国を、我らアルトメルデ軍は勇敢に押し返し、危険な最前線にも平等的で人道的な帝国の精神の元、先進的なシステム、アーサーシステムとフォース・ナイツの元、被害も少なく、我らの愛と正義の前にいつかすべての野蛮なイシュタルが屈服する日も近いでしょう、帝国万歳(ハイル・エンパイア)、我らに栄光あれ』
「アルフレート様」
ウルリヒは、ソキアの登場であわてて去っていく。
「来られたのですか」
「もう、自分の奥さんをこんなに待たせて」
ソキアの体がアルフレートに抱きついてくる。
「・・・・・人が見ていますので、それにまだ学生なので」
「むぅぅ、ムードが台無しですわ」
酔狂な奴、下町にいるアルベルトを見て、ディーターは思う。
キルクスや友人たちは珍しく不機嫌になったディーターに不思議そうな顔をする。
「今日は、どこに行く」
「どこでもいいだろ」
町を歩きながら、好みの子がいないか、見渡している時、軽やかな鈴のような声が背後から聞こえてきた。
「偶然ですわね」
「フローラ様・・・」
ディーターはその人物の登場にぎくり、となる。大きい白い帽子に花飾り。純金を溶かしたような長い髪をデイジーの花飾りで飾るゴールド・ライブラの姫君。
2
復讐を誓った人間はどうなるのだろう。
正義を誓った人間はどうなるのだろう。答えは誰にも分からない。失ってはじめて気づくのだ。どれだけ大事だったことを。
復讐を誓ったクリスタルはどう思うだろう。
「忘れたね」
ヒュウウウー、タナトスの城の頂上でクリスタル、アルヴィン、リリーシャに言う。
「サタンの前の人間の時なんて」
ドロップ状の古びた宝石を首から下げた、腰まで伸びた桃色のウェーブヘアの少女はおよそこの世の憂いなど知らないように見えた。
ッァバァイバスラー公爵家。
名門中の名門、彼女は唯一の後継ぎだ。学園では優しく、穏やかな愛らしい少女で知られている。
ひそかに男子生徒のあこがれの的だ。
・・・・いやがらせじゃないか。
すると、大勢の少女たちを連れたアーデルハイトが廊下の窓際にいた自分に気づく。
「ごきげんよう」
「・・・・どうも」
友人の誰かだろうか、ヴォルフリート・フォン・ローゼンバルツァーににらまれる。
「何よ、その態度」
「やめなさい」
「は、はい」
アーデルハイトが笑顔を浮かべる。
「午後のアンドリュー先生の授業は受けられるのでしょう」
「その予定です」
制服とはその人の身分をあらわす。けれど、人々の平穏や幸福を願う人物は、剣や銃。まして、マナを持たない。
遠距離の攻撃が強いスナイパーライフルをまるで習い事をするごく普通の少女のようにシスター服の金髪ロングヘアの天使は黒いスーツケースの中に背負う。
「そのような恐ろしいたくらみを持つ人がいるなんて」
フレーヌは思わず、かたを震えさせた。一見するととろそうな、非戦闘員にも見えるはかなげな少女には銃の使用の持続により、焼けたような跡、かたいものを握り続けたせいでまめができていた。14歳なのに。
「恐れることも囚われることもありません」
「居場所を失い、そういうことでしか己を示せない、哀れなものです」
エルヴィーラの言葉をヘレネは複雑な表情を浮かべて聞いた。
かっての大陸の名を失い、人々は壁の中に住んでいた。戦の女神(モリ―ア)の彫像がアトラスミュールの先にある。
正直言えばだ、カイザーはアルフレートの一番目の兄、ジュライドは苦手だった。人を上から見たような笑顔、スキのない動き、顔を合わす機会も少なく、何でもできる天才型、アルトメルデ軍では指揮官を務め、よくない噂だけを聞く。
深入りすれば、すべて壊されてしまう。ジュライド自身、カイザーのことは嫌いだ。会えば嫌みを言われるか、見下した笑みを向けられるか。
オウル家との家同士のトラブル、後継ぎ問題でこのところ悩んでいたが憂いは少女を話さない。
「あれが・・・」
「ああ・・・」
ゾフィーは双眼鏡でその光景を見ながら、少々うんざりしていた。ここにいる少年達もそうだろう。退屈は油断を生む。男子達の視線がいくつか、無遠慮に向けられる。反対の席に、不似合な軍服の清楚なロングヘアの少女がいる。友人も連れて、わざわざ見に来たのだろうか。それは永遠にあるように見えた。だが誰もが永遠と信じ、安らぎに満ち、そこに不安なんてない。
「・・・・負けたぞ、シエラ嬢が」
大勢の他校の生徒の前で、カイザーと論議の勝負をしていた。
「・・・カイザー」
「今回も俺の勝ちだな」
その観客席にはシエラの兄、カイザーの先輩がいた。
上品な貴族社会や厳粛な掟のあの世界よりもよほど下町にいるほうが、アルフレートの心をなじませた。テオドールをまるで敵のように見る。
「また、貴様か」
「戻るぞ」
アルフレートとしては外に出ていることが多い派手好きで冷酷なジュライドよりも二番目の兄は父にそっくりで、アーネストの方がはるかにプレッシャーを感じる。
「また止めるのか」
「お兄様は厳しすぎます」
淑女の見本というべき二つ上の姉、ルベンティ―ナ。誰でも優しく、女神のように美しい。
それはよく目にする光景で、幼い時は自分がアルフレートをかばっていた。いつの間にか背が追い越されてしまったが。温室育ちのカイザーは意外と庶民の食べ物が好きだ。下町に出て、アルフレートやオルグとともに少々危ないいたずらもしたことがある。
ライトニング・ヴァリアほどではないにしろ、帝国の上流階級の子息令嬢は紅茶を飲む。ただ規則を意外といざという時、簡単に守ることを放棄するのは心配だ。
「シャーロットとアリスリーゼ、どっちが本命なの」
少々辟易していた。もし庶民の息子なら、単純に恋の話にできただろう。
「俺が決めることじゃない」
「そうね、でも少々危なっかしいし、アリスリーゼは誰かが見ていないと」
彼女は学生を続けながら、寮生活をしている。
でも本来、自由に選択できない。軍人でも騎士の家系ではない、歌手や騎士のまねごと、自由奔放だがこのところは度が過ぎている。
「まあ、女性として意識したことないな」
注意もされている。庶民のシャーロットと違い、周りの目もきつい。
だから自分か、オルグかとの話も出てきている。
「お願いです、カイザー様、娘をどうか見逃してください」
帝国首都、第二区。誰もがそれを眉をひそめ、気の毒そうに女性を見る。その光景を見て、なぜか一週間前のことを思い出した。弁論大会で優勝して、全寮制の名門校に通う妹と偶然出会い、馬車の中には騎士のエスターもいて。
場所は劇場の入り口付近で、妙齢の女性が審問官の関係者とアテナの剣の軍人に囲まれていて。
「お兄様・・・」
フリーデリ―ケが襟元をつかむ。冷酷な生きながらの殺人者。
吸血鬼を倒すこと、国を守ることのみに生存を許される卑しき隣人。
「我慢してください、すぐに処理します」
「それはだめだ」
周囲がざわめく。
カイザーは秩序やルールを重んじる優等生タイプだが、いたずら坊主な一面で冒険好きで、けれど周囲を困惑させるのは度を超えた正義感だ。意外と情に流され、熱くなりやすくなる一面もある。女性はまるで死刑宣告でもうけたようにそんなっ、と表情をひきつらせた。オッドアイには、十五歳の少年らしからぬ威厳と誇り、意志の強さが漂っていた。
「あれはクラウド家の」
「パンドラは国のための剣にして、兵器。その存在のあり方は好戦的で冷酷、速やかにアテナの剣へ送らなければならない」
それがこの世界における正義である。法はルールは守らなければいけない。間違いは正す。
「お願いです、次期当主様、娘を立派に育てますから」
胸の奥が痛まないわけではない。アテナの剣ということは女の子供は事実上ここで母親と今生の別れを意味する。アマ―リエの言葉が思い浮かぶ。
「次に正しい子を産めばいい、それだけのことだ」
「そんな」
女性が涙声をあげ、赤ん坊を帝国兵士が連れていく。
「いやああああ、マリー、マリー」
「・・・二ケの儀式?」
飼い猫の相手をしながら、久しぶりに帰省したカイザーにシーザーが初めて、二ケの儀式のことを明かした。
「クラウド家の男が必ずすることになる貴族の男となるための儀式だ」
隣では、フリーデリ―ケの後をエレナが追いかけている。いつも騒がしく落ち着かないがカイザーはかわいがっていた。
「聞いたことはないんだが」
「15になる時初めて知らされるからな、でもある条件の貴族にだけ特別に行う慣習、まあイベントだな、主に剣をささげるというまあ、騎士道のまねごとだな、やってみないか」
そう言われるとカイザーも男だ。アーサー王は好きだし、その、思春期だ、プライド高く見えも払う少年だ。将来、騎士団の人間になりたいという夢を持つ一方で、カイザーはその点は奥手だった。気安く話そうにも、アルフレート以外は、家柄とか才能とか、どうしてもどこかで計算が入る、まあ、それ自体は普通ではあるが。
「まあ、ルールは守るものだからな」
「ラビン叔父上」
「前をよく見るように」
慌てて、セバスチャンがカイザーの体を起こす。
「大丈夫か」
「ああ、相変わらず、すごい迫力だ」
妹のディートリンデがついてきている。
紅茶のにおいを漂わせて、庭で遊ぶ姉妹を見る若い家庭教師は日陰にいてほほ笑んでいる。バーバラすの目の前では見なれた日常が広がっていた。
陽光に輝き、光いっぱい、クラウド家の町屋敷では、犬を追いかけるエレナとフリーデリ―ケの姿があった。
「また、家庭教師をからかったの?」
こめかみを押さえているのは、紺色のストレートロングヘアに鋭い刃のような青い瞳のヘレネだ。玄関ホール前で、癇癪を起す家庭教師を見ながら、その足を少年がいる東の庭へと向ける。
「いつも、すまないな」
成績優秀でスポーツ、乗馬、芸術、あらゆる面でヘレネは優秀。彼女に欠点など存在しないように見えた。
「いいわ、弟みたいなものだもの」
はぁ、とため息をつく。
完全にカイザーは猫はだ。というか、クラウド家は侯爵家の流れだから猫でなくてもいいが。屋敷は猫が自由に歩き回っていた。自由人のシーザーの影響だろう。大真面目にオルグ、シエラ、アルフレート、カイザーは帝国の将来、自分達の輝かしい今後を、庶民との差を、他国との軋轢を語る。
マリアベルは後輩ということもあるが、優雅さ、貴族という少女なので庶民は従わせればいい、そう思っていた。マリアベルは貴族の強気こそ正義、支配者としての意識がカイザーよりあった。勉強もスポーツも常に上位、幼いころから従わせることが得意だった。
「だからさ、アトラスミュールの彼らを」
オルグは朝が苦手だ。年子のヘレネと同じく、完璧人間、将来はまっすぐ国の中枢まで行くとうわさされているが、実は大の動物好きであり、意外だが恋愛ごとには奥手だ。ただ家庭に事情があるのか、あまり自分のことは話さない。
「それは駄目だ」
「そうよ、帝国法でも国の所有物や軍関連のことは禁じられてるわ」
ひやひやさせるなぁ。
セバスチャンはこの時、そう思った。オリバーとセバスチャンは儀式と聞き、正直、不安を隠せなかった。2人は没落貴族の生まれであり、魔術戦争―マギア・ウォー―の敗北者であり、家を失って以来、世界各地を旅一座、あるいは金持ちの護衛など様々なところで過ごし、現在カイザーを守る立場にいる。
「お前たちも大変だな」
また女連れで・・・。アウグストはセバスチャンが嫌いな男だ。
「僕達は別に」
「いつもあいつのおもりで、気苦労察するよ」
オリバーが言葉を発そうとする。
「大丈夫です」
3
「調子に乗るなよ」
カノンが叫ぶ。
「家柄だけで威張っても、今に立場が入れ替わるんだからな」
そう言って、去っていく。
「旧校舎のやつらは乱暴者が多いですね」
「まあ、落ちこぼれの集団ですし」
悪しき風習だ、階級だけで分けるのは。
「俺は気にしていないよ」
「優しいな、お前、あんまりいい奴すぎると今に変な奴に騙されるぞ」
周囲の生徒が、退学となった元伯爵家の少年と妹をみる。
「第3区に移るらしいぜ」
「かわいそうに」
「サファイヤ―」
多くの人々がいきかう、ヴァーヌスで武器やの少女が元気よく、自分に向かって駆け寄ってくる。
「そんな大声出さなくても聞こえている」
白い頬を赤く上気させ、短髪の少女は鼓動が速くなっているのだろう、あわてて追いかけたのか、息も乱れて、汗まみれだ。
セバスチャンはうるうるとさせる。オリバーは心からカイザーを第一の友として、生涯の主として見ている。ローリナから見ると、オリバーが背が高いせいか、二人は兄弟のように見えた。気高く誰にも優しく、友達思いで正義感も強く。間違いや卑劣なことは大嫌い。誰も区別しない。
「少々自分勝手だぞ」
くすり、とローリナは笑う。
「貴方を信頼してるのよ」
ルールや掟を守る優等生かと思えば、時にはあっけにとられる冒険もする。
「ふぇぇ」
セバスチャンはまた、ヴィクターやコーデリアにいたずらの対象とされたようだ。温かな陽光。涼やかな空気や風、森林が広がり、碧がよく生い茂っている。
「兄さん」
やれやれ、世話の焼ける弟だ。
ディアドラは、アリスの元を青い、華やかなドレスのようなミニスカートの制服に身を包みながら、ヘレネとともに向かう。おぼろげな幽玄、あるいは月の間に潜む優美、はかなげ、アンニョイ。もうすぐ、ヴァルベルグラオ家で儀式がおこなわれる。腰まで伸びた長い髪はウェーブかかり、三日月のような飾りを頭につけて。とおくかっての太陽王の国にいるフランシーヌは自分の運命など知らないだろう。
自分とよく似ながら、宿命に従わずに、ただの司祭の娘として生きる彼女には。
―一週間前。
「・・・・意外、貴方にはあらゆる栄光、すべてのものたちからの愛情、幸運がこの先おこるようです」
占い師に歩いている最中、呼び止められ、そう言われた。
「ですが完全に幸運と同時に人間関係のトラブル、争いと破滅が常に背後にありますね、とてつもない幸福と不幸が来るようですが」
「つまり?」
「ですが、落ち込むことはないようです、貴方には常に貴方を助ける方々が現れるようですから」
方々も何も友人はいないのだけど。ヴォルフリートは、できれば目立つ人間より地味に平和に生きたい、日常が日常なだけに。だが占い師は無愛想な自分を見て何を思ったのか。
「大丈夫、貴方は栄光と名声、もしかしたら皇帝陛下のおそばに近い方になれるかもしれません」
それは嫌なことをさせられたうえ、こき使われる未来ということじゃないですか、最悪すぎる。
ピアノの音が聞こえる。シエラが弾いているのだろう。成長にするにつれ、シエラは何となく自分と距離をとっていた。
カイザーは知っている。彼女は本当は音楽家が夢なのだ。感情的なヴィクトリアは趣味は可愛いモノ集め、スイ―ツが大好きで。
だが、家が貴族であることがそれを許さない。
「また、腕を上げたな」
「兄さんには負けますよ」
オリバーやセバスチャンも、カイザーの護衛を名目に、その学園に通っていた。
「オリバーは上流社会より妙に庶民のほうに詳しいな」
セバスチャンははかなげでか弱い、漆黒の闇のウェーブヘアの短髪でどこかミステリアスな雰囲気があり、彼自身もオカルト研究会やミステリー同好会に入っている。オリバーも似た風貌だが背が高く、どこか人を突き放すような、冷たい印象を受ける。一つだけ離れており、オリバーが16歳、セバスチャンが15歳。成績優秀で文系のセバスチャン、スポーツ万能で剣も護身術もこなすオリバー。
「実は遊び人?」
ふと見ていた観客のだれかの会話がカイザーの耳に入った。人付き合いが下手なだけだ。
「お前たち」
その時、ヘレネが通りかかる、腰までの長く整った、夜の闇のようなストレートロングヘアが、整った顔と抜群のスタイル、品格が他のついづいを許さない。目鼻立ちはシエラも似ているが、やはりヘレネは百人中その半分は、見慣れたはずの自分さえみてしまう美人だ。
「いくぞ」
そそくさとその生徒たちは走り去っていく。
三人の少女にライトグレーの少女は壁まで追い詰められていた。表情に乏しい娘だ。「何とかいいなさいよ」
「あんたのせいなんでしょ」
「・・・」
白い頬には頬を売った後がある。
「この泥棒がっ」
ミーシャ・サトォ―ルン。少し離れた場所の木陰から心配そうに見つめるアーンシア・ヴリクとブルゥア・レインポゥの姿もある。
「いいかげんにしないか」
少女たちがはぁ、と声がした方に顔を向ける。
「え、嘘」
「恥ずかしくないのか、寄ってたかって同級生を虐めるなんて」
ミーシャはじっ、とカイザーを見る。
バシャァァァぁ。
「あ・・・」
ミントが思わず、間抜けな声を出した。園芸部に所属しており、一年の一般科の生徒だ。身分は庶民。シャーロットの友人でもあり、かわいいみた目で男子人気は強いがカイザーはなぜか気を抜くことはできない。オレンジかかった明るい金髪のくせ毛がちのゆるふわウェーブ。
「…大丈夫か」
カイザーを守ったのだ。
「すみません」
二階から微妙な顔のジョンの姿がある。
「悪い、オリバー」
「いい、お前を守れるなら」
ア―ガンスが忌々しそうにオリバーの背中のやけどの跡をみる。赤く鋭い瞳、異常にッと乗った顔立ちと自信に満ちた表情。事実、彼は子爵家の後継ぎであり、カイザー同様侯爵家ともつながりがある。生徒会メンバーではあり、フェンシング部副部長。
「身分ない奴にまで親切にして、何の特があるんだ」
ア―ガンスは特に悪意なく、道に困っていた花売りの少女に親切にするカイザーに首を傾けた。
「また、お前は」
ここでは不安なことなど一つもない。明日の心配もする必要もない。
「俺はいつか白の騎士団団長のような人間になりたいんだ」
未来を見つめるカイザーの瞳は輝きに満ちていた。ア―ガンスとオルグは顔を見合わせる。
「弱気を守り、悪をくじくか」
「なんだよ、アルフレート」
カイザーはむっ、となる。
「お前らしいな」
「そっか」
庭先ではフリーデリ―ケが白い犬と遊び、草木が生え、美しい花々が咲いていた。
たたたっ。
「・・・落ち着きがないわね」
家庭教師がカイザーを追いかけていく姿が、マリアベルの眼に入る。
使用人たちもくすくすとほほえましそうに、輝く稲穂のような、金色の髪の少年を見る。
年の頃は十五くらいだろうか。
「オルフェウス兄さんっ」
美しいが意地悪な印象の若い男だ。オルフェウスの姿を見て、頬を紅潮させる。
「それとも、宮殿や軍で何か重要な案件や会議でもあったんですか」
オリバーとセバスチャンは異国の人間だ。もともと、カイザーが留学していたときに王都で見つけてきた。カイザーは二人のたち振る舞いや言葉づかいからして元々は上流社会の出身ではないか。そんな風に思うことがある。セバスチャンは優しい性格で、弟は一つ下、気が弱く手先が器用。もっとも二人とも、オルフェウスが少し苦手のようだが。
「おー、おちつけ」
カイザーの勢いに、オルフェウスは抑え込む。
「すいません、つい、今日はこの後時間は?マリアベルやセバスチャンと買い物に行くのですが」
ぽんと頭をたたく。
「また、今度な」
「はいっ」
学園は、金持ちや貴族がいく、幼等部から大学まである名門校だった。場所は、意外なことに第二区にあった。庶民の生徒も多く、自由な校風であるからだろう。とはいえ、カイザーからしたら普通だが、旧校舎の生徒達からすれば宮殿みたいな校舎だが、疑問に持つこともない。
「お前さ、何で弱いくせに他人の喧嘩に突っ込んでクンの」
興味ではない、不良少年はただカイザーが理解できない。
「あれでしょ、女子にモテたいんだろ」
「正義の味方気取りで大人にほめられたいとか」
少年の仲間は好き勝手に言う。
いつも意見が正反対なのに、何でいるんだ?
威張りやの姉とのんびりで変わり者の妹。風紀委員でもある少女は気に入らないとすぐ、退学よという。悔しそうに、小柄でグラマラスボディーの長い髪の少女が負けたのがよほど悔しいのだろう、縦ロールを揺らして、紫の大きな瞳をカイザーに向ける。
「これくらいで調子に乗らないことね」
「いつでもかかってこい」
にやり、とカイザーは笑う。
おろおろとピンクと白を混ぜたようなふわふわな雰囲気の同じ紫の瞳のたれ目の少女が二人の様子を見ている。
「行くわよ」
「あ。待ってよ」
ずかずかと廊下を歩いていく。
「結局、グラウンドは半分で使うことになったのか」
「はい、先生」
職員室の教師は少しご機嫌な様子のカイザーに眉をひそめた。
「あまり他人のいざこざに口を出すなよな」
あまり生徒人気が低い教師だ。それゆえに居場所をいつもあちこち探している印象がある。
「何でです?」
「親切がそのまま喜ばれると思わないものも中にいるからな、特にお前のように優秀な生徒は特にねたまれやすい」
「そんなことはありません」
「まあ、まだ子供だ、今はそれでいいんだろう、少しは自分の言動や行動がどういう風に見られているか気にかけた方がいいぞ」
「俺は大丈夫ですよ」
「いっていいぞ」
職員室の扉を閉める。
「それはどうかしら」
「え?」
カイザーは突然声をかけてきた少女に顔を上げた。
「貴方の言う平等は他者にとっては本当に平等かしら」
パヴォーネ学園のお騒がせ娘、愛のハンター、ミーハー娘。彼女自身、可愛い。それもアイドル並みに可愛い。新体操部、中等部はダンス部。ミュセル・フォンテーヌ。声もはきはきとしている。
「まあまあ、盛り上がって行こうよ、先輩♪」
「オルグはどうなんだ」
「俺はそういうのは」
「クールだね」
「まあ、光の騎士団―フォース・ナイツならだれでも大人気だろうけど」
ここの生徒は陽気で人がいい人間ばかりだ。
「ヘレネ・・・」
周囲の空気が変わる。
「ガーネット様も」
オルグとヘレネが目を合わせることはない。ナイトハルトはなんだかなと思う。
不愛想な野と無口な野直せばいいのに。
どうにもこういう話はこそばゆい。勿論、貴族は時代にその高貴な血をつながらせるのも役目であるが。
「今のところ、誰に決まりそうなんだ」
「俺は知らない、決まったら教えると言われているだけだ」
「また、こんなところで昼寝してる」
「・・・」
チャイムが鳴る。クラウスが仕方なさそうに、ミリアリアの背後に悪いなというポーズだけとっている。
「悪いな」
「ああ、もう」
「シャーロットは知っているのか?」
「なぜ、ここに彼女が出てくる」
家の考えに従い、優秀な成績を収め、後継ぎとして教育を受け、庶民を守る。それを小さいころから自覚しているカイザーだが、周りが過保護なところがあるせいか、異性、恋愛に関してはどうにも奥手なように見える。女子に騒がれ、軽い甘いせりふをはくことはできても。
「・・・マジで言ってんの」
だからクラスメイトの友人に白い目で見られてもきょとんとするばかり。
「書記さん、ちょっとお願いします」
「ああ、今行く」
「おおおおおおおおおおおおお――っ」
「さっすがは我ら黄金の女神、アリシア―ッ」
「勝利はわれらの手に」
二つの寮が(白い竜)と(赤い竜)がしのぎを競い合う。
グラウンドの真ん中に、生徒会長アリシアと副会長マリアベル、アレクシスが主催した大型のステージが置かれていた。大勢の男子生徒達がステージの下に詰めかけていた。ステージの上にはくせ毛が地の黒髪とそら色の瞳の少女の姿があった。隣には燃えるような赤い髪の少女が恥辱と怒り、先輩へのわずかな尊敬で立っていた。
《みんな、ヤッホーッ、女子高生警官のジュリエットだよ、こんな朝早くからわが名門のラクロス部のために来てくれてありがと――ッ≫
《ヴィクトリアもうれしい――。、って何よ、このセリフ≫
赤いリボンとフリルできらきらでいかにもなアイドルな衣装だ。ジュリエットは警察の制服なのにアリシアはいつもヴィクトリアだけ、こういう衣装を着せる。
「・・・・すげえな」
バサボサ髪のジ―クムントはあきれるのと、幼馴染の意外な姿に微妙な気持ちでいた。
「オリバー、次は負けないからな」
剣道部の衣装に身を包みながら、青い瞳の同級生は歩いていく。
「真面目だな」
はぁぁ、とカイザーはため息をつく。今日のお説教は終わりらしい。生意気だ、生意気だ、根性悪だ、とフレッド・エルドカラレスは射程を連れながら、カイザーをにらんだ後、去って行った。
責任感が強い、頑固者。彼の美点でもあるが同時に最大の欠点だ。どうしてか、女王の国の名門校から転校して以来、似た部分も多い故か、カイザーとは喧嘩になってしまう。
カイザーとしては頑固者をやめて、もう少し融通がきけばいいなと思っている。
「絶対、お前を倒すからな」
試合の後、ライバル視するライルがチームメイトを連れながら、敵チームの頭脳であるカイザーにそういった。
「いいだろう、かかってこい」
観客先では、カイザーファンの後輩が「告白しちゃいなよ」「ええ、でも」とほおを赤くしながら、会話していた。
「俺って、罪深い・・・」
くすくすとした笑い声が聞こえる。
「…笑うなよ、アレクシス」
アレクシス・ヴィルフリート・フォン・フェリクス。同い年で昔からの顔なじみだ。外見よし、家柄よし、性格も運動神経もよし、まあ、自分も似たようなものだ、唯一負けているのは背が低いことだけだ。
成長期だ。俺は未来を悲観しない主義なのだ。
「ごめん、相変わらずすごい人気だなって」
馬鹿にしてるな。
だが、これだけそろうと同級生の馬鹿どもに嫌われそうだがアレクシスは先輩後輩、同級生と慕われている、人格者というものだろう。
アレクシスの緑かかった澄んだ青い瞳が後ろの少女に向かう。その時、観客席から強い視線を感じた。他校から応援に来たのだろう。俺を見ると、アリ―シャ、アレクシスの妹は困ったようにほほ笑みかけてきた。俺も笑みで返す。
だが、アリ―シャが俺にまして他の男子に視線を向けることはない。品行方正の優等生、清楚な彼女の熱い視線はいつだって、一つ上の兄アレクシスに向けられている。
ブラコンという奴だ。
彼女とは対照的に、均整のいい、凹凸の取れた身体の少女がおずおずと出てきた。歩く男子が嫉妬の眼でカイザーを見る。
「ほら、シャルロット」
「・・・・はい」
ぶっきらぼうにシャルロットはカイザーに水筒を渡す。
「おめでとう・・」
「え、ああ」
カイザーもつられて、頬を赤くし、つい目をそらす。幼馴染とはいえ、こういうの、やめてほしいな。
「いちゃつくのは、学園がいだけにしてくれないかしら」
ヒュウウウ―・・。
振り向くと、ヘレネとシエラ姉妹がいた。蒼がかった黒髪ロングヘアの少女たちだ。表情は愛らしい笑顔だが、目が笑ってない。
「こら、シエラ、やめなさい」
「私は間違っていません」
ふぅ、とカイザーはため息をついた。
「相変わらずだな、シエラも少しは素直になったらどうだ」
その時、ふいに風がシエラのスカートを翻した。シャルロットははっとなる。僅かに見えた太もも近くの傷跡。皮膚を引き裂いたような傷跡だ。
「…何かしら」
「何でもないわ」
清涼な、冷え切った目のシエラの瞳に見つめられ、シャルロットは黙りこむ。そして息をつくと、毒を含んだ笑みをシエラは浮かべる。
「あら、幼馴染の女の子や下級生にちやほやされてデレデレするあなたよりはましだと思うけど」
その時だ。
「シエラ、カイザー、助けなさいよ」
駆け足とともに、ジ―クムントと一緒にヴィクトリアがカイザーの元に駆け寄ってくる。
「先輩―」
チームメイトが、アルフレートともにカイザーを呼ぶ。
そんな姿を、アウグストは女性を連れながら、
「滑稽だな」
とつぶやいた。
4
―最初に言おう。
彼ら、勝ち組に勝てると思わない。
彼らの主義や価値観ではどんなものでも価値がある。敗北もすれ違いも退屈な日常も。彼らはいう、自分達は恵まれていない。不幸だ、と。勇気を出せばそこには優しい世界が、角度を変えれば満ち足りた世界が待っていると。中庭では楽しそうにハンドボールする生徒の姿がある。
廊下ではカップルだろうか、楽しげにしゃべっている。明るい校風、気さくな生徒達。「あ、ごめん」
男子生徒は少しばかり目つきの悪い自分にぶつかるが、すぐに向こう側の友人たちの元に向かう。俺の方に向かい、剣道部の赤い髪のポニーテールの少女が手を挙げ、ほほ笑む。
「ごめん、遅れて」
「もういつもじゃない」
友人だという背が高い男子の後に小太りの背が低い生徒がついていく。ギャル風の女子生徒は強気な発言するが、お嬢様達を見ると表情を変え、道を譲る。
おかしいじゃないか、ならばそうでもないものにも何かあるはずだ。青春とは等しく訪れるものだ。なら、何で男女の恋愛に世界は固定するのか。仲間意識をああも体育系はアピールするのか。永遠の友情を歌うのに疑いの目を持つのはなぜか。諦めたのに友達であることを望んだのにぎくしゃくするのはなぜか。
人生とは勝ち負けである。だからこそ、勝者は正義を、愛を友情を語れるのだ。
「だからね、ダヴィデ君、諦めないで」
シャーロットは言う。彼女はクラスの人気者で新体操部で友達も多い。それに美人だ。
「きっとみんなあなたのことよく知らないだけだと思うの」
それはまるで植物に水を注ぐように、飢えた犬に餌を与えるように。
嘘つきだからだ、飾らない優しさ、優しげな視線。真の勝者とは誰かを蔑まない。
あれは幼稚さだ。甘えだ。偽善者とは違う。ゆえに彼らは一人であることを理解しない。きっと彼女の手をとれば世界は明るい、クラスで俺も明るい日常があるだろう。
「ふっざけんな、このアマ――ッ」
「―また、お兄様に頼んだの?」
違う日の昼休み、アリシアにマリアベルは隣を歩きながら、聞いた。マリアベルは、エイルがライバル視する少女だ。プライド高い女王様気質、だが意外と可愛いものに目がないのだ。
「おだてに弱いから、君の最愛のお兄様は」
うっ、となる。
「ぶらこんみたいに聞こえるから止めてください」
男子生徒達が二人にあこがれの視線を向ける。
「で、本当のところ、アレクシスとお兄様はどっちが本命なんだ?」
うりうり、と肩肘を当ててくるのがうっとおしい。
「・・・アレクシスは友達です、それに好きとかそんなんじゃ、プライベートいつも一緒というわけでもありませんし」
「そうだね、そういうのローザならわかるかも」
「それはありえません」
マリアベルははっきり言い切った。
「でも、あの二人、将来・・・」
「ローザリンデは家同士だけで決められるのは嫌いですから」
「まあ、私のところも似たようなものだね、ヴィクター何か、アレクシスと同じ学校が嫌だから、隣国に留学して今は隣の一般校を選んだくらいだ」
「君はまた服装を違反して、生徒指導室まで来給え」
セシルは渡り廊下でげぇ、とした表情になった。
「スカートが短い、装飾品も禁止だ」
「うっせ、教師かよ」
友人らしいの輝崩した少女たちがくすくすと笑っている。
「何を言ってるんだ、規則は守るものだ、大体君はふだんから生活態度が」
「そうよ、そうよ」
エイルが激しくうなずいている。
セシルは大きくため息をついた。
5
「反省文がまだ終わらないのか」
「うるせ、俺は苦手なんだよ」
ついてねぇ、それにしても今日は変なことがあったな。知り合いは友達は少ないが、敵は多いという状況。
イフリート隊は悪いイメージも多いがそれで覚えられてもな。窓が微かに揺れる。教師のシスターも驚いた表情だ。
「なんだ、地震か?」
人が少ない場所、中庭に見慣れた姿を見てアリスはほっとする。
「ヴォルフリート」
友人たちはその姿を見て、じゃあ先に行くねという。
「ブラコンもたいがいにしなさいよ」
頷くと、アリスは一つ下の少年の元に向かう。
「また、さぼり?」
「一日は一回しないのに、授業なんてもったいないから、姉さんもそう思うでしょ」
アリスはヴォルフリートの隣に座る。
「私ね、少し駄目な子なの」
頭をヴォルフリートに預ける。
「そう?」
「うん、でもヴォルフリートの顔見たら、堕ち込むの馬鹿みたいに思えちゃった」
「・・・え、でも」
アリスリーゼは、男女間のそういう意識が薄い。ゆえにフェンシング部のユニフォームのまま、カイザーにしがみついた。
「離れなさい、貴方は女の子、それも貴族の令嬢なのですよ」
「私は幼馴染よね・・・」
マリアベルがアリスリーゼの肩をたたく。
「空気呼んで」
そのまま去っていく。
「カイザーの馬鹿っ」
「そうだ、先生、カイザー・クラウドッて同学年にいますよね」
校門から出る時、教師に尋ねる。
「ああ?」
「今日、昼休みに話しかけられたんですが、どこのクラスなんです、俺クラスに友達がいないので、どういう奴です」
まああれだ、たぶん表になるのだろうが、でもあんな目立つなら男子でも存在気付くよな。
「ダヴィデ、お前・・・」
「うちの生徒にそんな名前の生徒はいないぞ」
「え、なに、そのサイコ的な答え」
ダヴィデは大げさに驚いたような、わざとらしいふるまいをした。
ぞくっ、としたものを感じた。
馬車の中でその美しい屋敷、イヤ城を見た時、奇妙な悪寒に似たものを感じた。
・・何だ?
「どうかしたの」
「あ、いえ・・」
気のせいだ、そうに違いない。そう、今日は最高の日になるはずなんだから。
ガララ。
「―ここが、ヴァルベルグラオの城か」
丘の上に建つなんて、まるで王の城のようだ。
壮麗でいて、威圧感のある、そんな屋敷だ。
「くだらん」
アルフレートはため息をつく。
「お前はまた・・」
カイザーはふっと笑う。
「エレナも連れてこればよかったな」
シーザーが声をかける。
「つくぞ」
屋敷の中はまだ人が少ないようだ。
「あれは貴公子と噂のレーヴェ卿か」
「ふん、家柄だけの男だ」
アルフレートははき捨てるように言う。実力主義の家。カイザーと違い、嫡男といっても、置かれている環境が違う。遊びに連れていくカイザー以外、周囲にいるのは心許せない連中ばかりだ。正義感が強いうえ、言葉を飾らないので女性に人気がある一方、理解できない輩からは疎まれる。優しいんだけどな。
「アルフレートも懲りないな」
肌身離さず、ある写真をロケットに納めている。その謎だけはアルフレート自身からいつか教えてくれる日をカイザーは待つ。はっ、となる。
奇妙な不安のようなものが胸をくすぶる。
何だ?
多くの着飾った客が動きまわり、あるいは談笑している。
その時、シーザーがカイザーたちに声をかけてくる。
「悪い、お前たちは屋敷の中でも探索していてくれ」
「え、いいの?」
カイザーはきょとんとなった。振り返ると少女はもういなかった。貴族階級以外にも多くの客が今日まぬかれているらしいし、気にすることはないか。世間知らずのお坊ちゃまと労働階級特有の偏った考えにあるだけなのだ。深く考えず、カイザーは思考を目の前の華やかに着飾られた会場や廊下を見た。
名だたる豪商や宝石商、親善大使、他国の宮廷の関係者が軒並みそろっていた。
軍国イシュタル。北の大帝国ダヴェーリャ。女王の国ライトニング・ヴァリニア。どれもレミエルで見る有名人だ。
ちなみに東方をソール、西をサートゥン、南をヴェーヌス、北をツヴィトークである。首都を中心に、それぞれ、要塞壁の中で造り、あらゆる主義を認める帝国は移民も民族も受け入れていた。
「すごい顔ぶれだな」
「ローゼンバルツァーですから」
オリバーはははっと笑う。
「人込みは嫌いだ」
カイザーは周囲を見渡す。
「もっと、別のところもみたいな」
「ワインをお飲みになりますか?」
グラスを持ったメイドが近づいてきた。
「悪いな、未成年何だ」
黒髪のメイドの冷たい機械的な視線とぶつかる。隣にいる淡い黄色の華やかなドレスの少女は見目麗しい令嬢達と小鳥のような声で笑い、…ただし瞳は閉じられていた。アリスの視線がこっちに向いてくる。車いすを引いていたらしい。
「そうか、フィネ嬢か、末娘の」
エレオノ―ル夫人の最愛の娘だ。アリスがほほ笑む。なぜかときめくより胸の奥が少し痛んだ。
「・・・?」
セバスチャンが覗き込んでくる。
「うわっ」
「気分でも悪いのか」
「急に前に立つなよ」
「アーロンも着ていたのね」
ユーリアに声をかけられ、眼光が嫌に鋭い長身の男がなれない燕尾服に身を包んでいた。
「旧友に頼まれてな」
「ああ」
ローゼンバルツァーの人間ト笑顔を浮かべてしゃべっている紫の髪のおかっぱの男。
「フィリベルトの遠縁だったかしら」
「ただの田舎の貴族の三流魔術師だよ」
赤い髪の少年が、ラインハルトと話している。
・・・ふぅん、イシュタルのスパイか。
「あの、いいですか」
高い少年の声が後ろで響く。
俺の前のマリアベルと下級生の前では全く違うのだろうか。見栄っ張りというか、皆優しいのだが、誤解されることが多い。
「それでは、カイザー様」
級友たちの間に起こした妹の冷徹な一面。クラウド家の全員に共通するが、なかなか己を曲げない。
「ああ」
欠点ではあるがカイザーはそれがない。お優しい方だといわれる。バルドゥルがいい子ぶる、偽善者という時がある。
守りたいときは自分を見せないと。
シャーロットの言葉が思い出される。俺様な優等生、皆仲良しが主義の友達思いのカイザーは使用人や周囲から少々変わり者扱いされることがある。
意外と人づきあいがうまいセバスチャンはいつの間にか、ユーリアと交渉していた。
「珍しいところなら、そうね」
ユーリアは指差し、中庭をさす。
「少し珍しいものがあるから行ってみたら」
「ありがとう、あとでお礼を言うよ」
いえ、とくすり、と笑う。
まるで世界中の不幸を嘆く天使のような、ただ一つ、自分だけ世界の真実に気付いたような孤独の瞳を宿していた。
「悪い、アリス、席を少しはずす」
「人ごみ苦手だものね」
静寂を求める人だ。こういう派手なものは合わないのだろう。
「すぐ戻る」
「ええ」
アロイスが人ごみを超えて、扉に向かっていく。
「マルティ」
困ったようにアリスは笑う。
「次こそは負けませんから」
大きな栗色の目をくるくると動かす。
・・・騒々しい。
微笑ましい表情でブリジットを思う。
きゃっ。
曲がり角から、突如少女が突進してきた。
「コレット、ごめん、遅れて、あっ、おっと、ごめんなさい、前を見てなくて」
カイザーは笑顔を浮かべ、平気だと答える。
「・・・あれ、どこかで前に会いませんでした」
「アンジュ、相手は貴族さまよ、あるわけないでしょ」
「?そうだっけ、それじゃ、失礼しました、ごめんね待たせて」
14歳の少女はウサ耳のリボンをつけて、金髪の巻き毛を揺らしながら仲間の元へかけていく。
「もう、何をしてるのよ」
「えへへ、ごめんごめん」
マリ―ベルの歌声が会場から聞こえてくる。美しく洗練された声だ。
桃色の長いウェーブ状の青い瞳の大人っぽい雰囲気の少女だ。
カイザーは二階から大勢の客の中、見つめるお伽噺から抜け出てきたような歌姫の少女をみつける。アンニョイ系というか、赤い瞳をマリ―ベルに向けている。
深い沼にのめり込んでいくような・・、少女の吸い込まれるような目を見ながら、ときめきではなく奇妙な不安感に似たものを感じた。
「何だ、セバスチャン」
なぜかセバスチャンはすねた表情をしていた。
「行くぞ」
白い花が地面に一斉に咲き誇っていた。
「すごい・・・」
「なんてところだ」
アルフレートも驚いた顔をしている。
「帰りなさい」
振り返ると仮面で隠した純金の髪の少女がいる。植物のツタを模した模様のダークグリーンの上品な、脚が大きく開いたミニスカートのドレス。まるでおとぎ話の妖精のようだった。高貴さを漂わす青紫の瞳はサやけの色に似ていた。肌は雪のように、血管が通っているかと疑いたくなるくらい白い。腰まで伸びた長い髪がさらりと揺れる。年は16歳くらいだろうか。どこか突き放した印象を与える、そんな少女だ。
「え、・・え?」
つかつかと歩み寄ってくる。カイザーでさえ見惚れていると、美しくも厳しい、彫刻のような顔が近い距離で近づき、心臓の音が高くなったのを感じた。
「いつもの日常に還りたければ、速やかに帰るのです」
アルフレートがカイザーの前に出た。
「無礼だろう、どこの家のものだ」
「・・・・・」
少女は答えない。アルフレートは腰の銃を手に取ろうとする。
「止めろ、相手は女の子だぞ」
「だが」
「アルフレート」
フぃおらが後ろの像に背中を預ける。
その時だ。
「カイザー?」
二階に行き、アリスは弟を呼びに行く。
「また本でも読んでいるのかしら」
「アリス様はヴォルフリート様が本当に大事なんですね」
なじみのメイドがくすっ、と笑う。
「・・・・・う、うん、大事な弟だから」
恥ずかしげに視線を下に向ける。
「―また、どこかへ?」
アリスはドロテアがまた庭園の奥に消えていく。
「いたた・・・」
「大丈夫ですか」
「あ、ああ」
符ぃおらとセバスチャン、カイザーは痛みで頭を押さえ、ゆっくりと目をあける。真っ白な花の咲いた祭壇のような場所。
「これは…遺跡?」
その墓と肖像画を見た瞬間、アリスとカイザーの視界を巨大な黄金の光が覆った。
「アリスッ」
カイザーは爆弾でも仕掛けられたのか、反射的にアリスの身を守った。
「――」
目を開けると、カイザーの目の前に小さい女の子を模したフリルとリボンの人形やぬいぐるみ、古ぼけた新聞やピンクやブルー、緑のインク、童話の本、炎で燃えている木馬の模型、呪いの歌を浮かべるピンク色の大きな口の耳障りな奇妙な小鳥たち。
「貴方は…クラウド家の嫡男よね、これは一体・・」
「アーディアディト、これは・・・」
ぎぃぃぃ、とアリスはその奇妙な音で振り返る。鉄製の目を閉じた女性の天使。その腹が割れ、中からびっしり金属製のとげが見えた。はさみがカイザーの後ろまで接近していた、それもカイザーの背丈ほどもある。
【ぎゃああああああああああああ】
漆黒の闇の空間に、少年と少女の脳裏に焔の中で踊る女性たちの声が鳴り響く。にげても逃げても焔が女性たちに迫る。司祭たちは氷のような目で罪人を見ていた。
「いやっ、止めて」
カイザーはかばうようにアリスを抱きしめ、目を閉じる。
ブツッ。
「・・・・え?」
目を開けると、二人は巨大な十字架の上にいた。黄金の装飾が十字架の先端に取り付けられ、ライオンとユニコーンがよく似た顔の生き物が目の前で衝突しあうという。パイプから連続で音が鳴り響き、どこかから大きくつり下がった斧が三日月状の形となってゆっくり、適度な速度で揺れ落ちていく。
その間にも、着飾った貴族風の飼いならされた怪物が通り過ぎていく。
「何なの、これは・・・」
「何なんだ・・・」
「―よかった、来てくれたのね」
振り返り、あたりを見渡すと、黒髪の少女がいた。真っ白なドレスを着てカイザーたちにほほ笑む。ピンクや白を基調とした、女の子らしい人形が置かれた部屋だ、香水瓶もある。
「私、ずっと待っていたのよ、青の女王と救世主、貴方を」
「君は・・・」
「アリス、あの日の続きよ」
少女は小指を差し出す。
「あの日?」
「黄金の昼下がりよ、いつも来てくれたじゃない、あの人と三人で」
笑う巨大化した魔女、散らばるトランプ。追いかけてくる異形の生き物、白ウサギ。
殺し、アリスを殺しなさい。
あああああああああああああああああ。
―首を切っておしまい。
「いやああああああああああ」
燃え上がる兄弟達、巨大な怪人たち。
捕まってはいけません。鎧の騎士達が、アリスたちの手をつかみ、光がある方へ指をさす。
―にげるのです、貴方達は世界を救うのです。
二人は最後に漆黒の柵の中の灰色のぬのに身を包んだ醜い小鬼―オ―ガの一種?を視界の隅に見る。
―忘れるのです、あれはこの世に災いをもたらす存在してはならない悪魔です。
だが、アリスは手を伸ばす。
「待って、彼もいっしょに」
「アリス?」
柵を掴んで、顔が見えない子供の怪物がこっちを見ている。人型の鬼だ。カイザーたちを食い殺したいのか、怖い目で鋭く見ている。
「だって、あの子はずっと誰かを待っているわ、おいてなんていけない、お願い手を伸ばして、すぐ行くから」
だが、視界は金色の光で覆われて。
幻覚を見ていたのか、それにしてははっきりした、リアリティのある夢だった。アリスと目を合わせる。
「カイザー、貴方も」
「君も?」
「――」
彫刻で構成された庭園で、アリスは茶色のウサギのぬいぐるみを持ちながら、カイザーに笑いかける。
「ヴォルフリートッ」
人ごみの中、カイザーがヴォルフリートに駆け寄る。
「・・・ああ、カイザー様か」
うんざりという顔だ。
「これから儀式なんだって?」
クリストファーがにやにやとカイザーを見てくる。
「お前は誰だ」
「僕の知り合いだよ」
その時だ。
「シーザー叔父さんっ」
だが、気付くとヴォルフリートはいなくなっていった。
「悪いな、カイザー、本当はベルンホルトが来る予定だったんだが」
気遣うような兄弟の従者の視線、自分を気遣ってくれるのは心から嬉しい。だが、いい加減、自分も十六だ、あの時に比べれば大人だ。過去を乗り越えたのだ。
―全てを受け入れ、未来に生きること。
それは誰に教えられるでもなくカイザー自身が考えた信念だ。
「いいよ、シーザーおじさんの方が俺もうれしいし」
「本当なら実の父親が儀式であれを授けるものだが」
「いいよ、おじさんが俺の塔さんみたいなもんだ」
9
「気分でも悪いの?」
また二階に来たかと思うと、ええとうなずく。
「少しね・・・・」
ちら、と見る。
「私ね、ヴォルフリートにアロイスともっと仲良くなってほしい」
「十分仲いいでしょう」
そうじゃない、いいたいことはいつも。
「わかって、私が貴方をどんなに大事に思っているか、貴方がいなければ生きていけないわ」
さすがにヴォルフリートも笑う。
「危ないな、それは血のつながった弟に言うセリフじゃないな、それも彼氏を親に紹介する日に」
「私ね、別にここを出てもいいと思う、でもあなたも来てほしい、いつか約束したよね、家族であの国行くって」
「・・・姉さんの家族を捨てるというの、僕以外にもいるの二、アロイスだって姉さんに無理してほしいわけじゃないと」
「パーティーの後、また・・・」
だから分家の、親戚の父の弟に聞いたことがある。ウルリヒの前にもう一人男子を考えなかったのか。
「お願いです、彼らを兵士から解放を」
「また、あいつら・・・」
うんざりする。ああいう、自分は行動しない、他人に依存し、現実を見ない、戦わない連中は嫌いだ。悪魔崇拝しゃ。
パンドラを人間だという、自由や保護を求める狂信者。
・・・・カイザーが魔法を学べば。
「・・・・」
だがやはり怖い気がした。なぜかはわからないが。
・・・また、パーティーか。
屋敷の二階から、ダークブラウンの髪の少年が下りてくる。
「いつも憂鬱そうだな」
気高く誇りだ格、ある意味貴族の善の部分だけ宿した、15歳の弟。自分の兄が世界を変えようなんて思っていることは夢にも思わない。高貴な、童話の中の白馬の王子様のような。
「ディートリッヒ」
だが慣れろという方がおかしい。それもこんな時に。
「サミュエル・・・」
セラヴィーナアクア・ヴィエルジ・クレ―ネ―ル―モ・フュ・ゴッドカルディア。純粋なハイエルフであり、生まれついてのパンドラである。純粋なエルフの両親から生まれ、二ケの肖像ではそれなりに位の高い剣巫女―ヘレヴイアリィア―でもある。
「宗主様は、あの方をどうなさる気だろう」
サミュエルは黙り込む。預言のことを気にしているのだろう。
「未来はまだ決まってないよ」
「・・・そうね」
ブリジット様の元に向かおう。
「女神の祝福があらんことを」
「しかし、平民は馬鹿騒ぎするの好きですね」
「ええ、今は平和なのになんで革命なんて野蛮なことに夢中になれるのかしら」
「この国は平和なのに」
着飾った客たちにナターリアは眉をひそめた。
「体が弱いのによく来ましたわね」
、ツイツィーリアは褐色の肌の護衛たちを連れて現れる。人間に扮しているが、実際の姿はダークエルフだ。
「土臭い」
ぼそっ、と、ヘレネの一族の当主であるクロイゼルンが神経質そうに口元を押さえる。
「何ですって、この田舎貴族がっ」
「君はまた修行のため、野原を駆け回っていたのか」
「人を屋ザル扱いするのはやめてくださる、わたくしはもう15歳、立派なレディーですわ」
少々、うんざりしていた。アリスやディートリッヒは人がいる場所や騒がしい場所が好きだろう。
こんな時だというのに、よくものんきにしゃべれるものだ。
見慣れた金髪、大きな瞳、きらきらと目を輝かせている。
「酷いぞ、お前、いきなり挨拶もなくいなくなるなんて」
「え?、ああ、着ていたのか」
のんびりしたとぼけた顔でヴォルフリートがカイザーを見る。
さっきもあっただろうに、まあ、こんだけ人がいれば、媚を売る人間も多いことだろう。
「また冗談ばかりだな」
「あまり無理はしないようにね」
「・・・優しいんだ」
つい頬が緩くなってしまう。
「僕が?まさか、カイザー様」
「僕の言葉なんて真実なんてものはないよ」
「え・・・」
「君と違って、僕は薄っぺらいものさ、僕は根が冷たいから他人なんてどうでもいいんだ」
「悩んでいますの?」
ナターリャは今、婚約者候補として会っている一人だ。セアドアが後継ぎではない以上、当然だ。
「どうかな、ただもやもやはしている」
「あまり他人のことに関わりすぎもよくありませんわ」
アニスがクルーエルエッグの少年と遭遇したのは、ご主人様たる大公に連れられた舞踏会だった。とはいえロマンチックなどとい言葉は遠い。
彼らはパンドラでも人間からも、天魔落ち同様恐れられていた。
「連れてくるなんて」
「仕方ないわ、今夜は」
「うふふ」
漆黒のドレスをたっぷりのフリルが幾層にも膨らみ、可愛い花飾りのついたヘッドドレスからつややかな黒髪の長い髪が見えた。
その時だ。
「シャルロット」
柱の陰から見慣れた少女が現れた。
「・・・そのカイザー、儀式の後で会えるかしら」
シャルロットが真剣な表情で聞いてきた。
「なんだ、怖いな」
「大事な、とても大事な話なの、たぶんあなたにとっても」
「わかった、絶対に行く」
「ええ、お願い」
少女は頬を染めている。
「絶対、約束の場所に来て、待ってる・・、いいたいこともあるから」
「これはどういうつもりなの?」
銀髪ツインテールの少女が、銀の十字架と並ぶ黄金の聖十字のお祈り用の衣装を着て、騒ぎの中心、ディーターやエドガーの元に来る。
ソフィアは、貴族出身の魔術師の少女達は唐突な出来事に一瞬何が起きたのかわからなかった。今日は多く、魔術師の塔から数人優秀な生徒だけが出席を許されていた。ケイは、ステンドグラスで覆われた神鏡の間を見まわすと、周囲も同じ反応だった。レーヴェ卿、フェリクス卿、オナシス卿の関係者、騎士達は目を大きく見開いている。
「・・・・え?」
カイザーは天龍球が何の反応も示さないことに、思考が動かなかった。
「そんな・・・」
ダークブラウンのウェーブヘアの少女が驚いたように口元に手を覆っている。
高いマナのしるしは現れているが、何かに拒まれているのか、光を発さない。祝福の洗礼の光が。
白銀の法術師―ブランシルヴァ・マギーナたちも何の音もしない祝福の間に動揺の色を示す。
ブ―ブ―ブ―。
「馬鹿な、なぜ決壊が張られているのにトトの異界のあの扉が現れているのだ」
銀の頂―ケセフ・エクセレンテ―のトップ魔術師があわてて杖を取り出す。
テレ―ジアは目の前で起きる突然の事態に思わず立ち上がろうとした。
「だめよ、テレ―ジア」
「でも、カイザーがっ」
周囲の権力者や貴族、主だったメンバーも驚いている。
「どういうことだ」
「カイザー様に何が・・・」
その時、扉が開き異端審問官とダイアナが入ってくる。
「皆さま、落ち着いてください」
また、ざわと音が大きくなる。馴染みの顔だった。奇妙なのは軍服のような、上品さと硬質さを併せ持ったダイアナの服装だ。それに左腕にあんな狼のようなタツゥーなど入れていただろうか。
「―今日まで、カイザー様は我々と同じ人間でした、ですが私はもう神に愛する帝国に嘘をつきたくないのです」
真剣な、心の隅々まで行きとどくような、暗闇の色と清廉さを宿した声。自分を根底から否定するような異端審問官の一方的な敵意のまなざし。カイザーでなくても戸惑うだろう。
「ダイアナ?」
ローゼマリーもフィランも顔を見合わせている。
「そのものは天魔落ち、人間ではありません」
次の瞬間、聞きなれない言葉に聡明なカイザーの思考は対応が遅れたが、周囲の動揺した声がカイザーを思考の海からすぐに引き戻した。いつも見守ってくれた、おしとやかで親切な、シスター。体中の熱が一気に冷えた。
ダイアナの氷の宮殿のような、凍りつかせる瞳を向けられるまでは。
「・・・な、これは何の余興何だ、ダイアナ、おふざけは」
カイザーはあわてて近寄り、ダイアナを止めようとする。パン、と乱暴に振り払われた。
「触れないで、人間もどきがっ」
そして、冒頭に戻る。
聖なる結界【セイントエリア】によって、客達は一時的に意識を失う。シャーロットもテレ―ジアも床に倒れている。
「貴方の存在そのものです」
ザぁァァァ。水滴がガラスを伝っていく。
「強いて言うなら、カイザー様」
「あなたは幸せすぎた」
「・・・・何を、何を言っているんだ」
茫然と、まだ信じている目でカイザーは戦司祭ダイアナとその部下たちを見る。状況は分かっている。
ザぁぁぁァァァ。
運命の皮肉か、と思った。
あんなに、愛されていた存在が救世主に天魔落ちに祭り上げられる。
数日前が嘘のようだ。
「身柄を拘束されていたのか」
白の騎士団隊長は、カイザーを運ばせながら、多くの死体、燃え盛る炎を見た。副隊長が窺うように隊長を見る。
「このことは陛下に」
「現場は保存しておこう、それに死んだ者たちにもなにかかけるものを」
「了解しました」
10
時計の音がチクタク鳴り始める。
止まっていた時間が息を吹き返し、正常に動き出す。
ツイツィーリアはぞクリとした。
「どうした?」
クロイゼノンが顔を上げる。
それはツイツィーリアにとってなじみの感覚である。
異界が出現、または異界と現実界が接触したことで怒る共振。それは災厄の始まりを意味する。
「ラインハルト、コンラ―ト様」
「どうした」
「危機が迫っています、ここに異界が出現しようとしています」
何をばかな、とおそらく、こちらの関係者だろう高価な服に身にまとった男や華美でこれでもかというくらい、女性というものを現した麗しい貴婦人たち。
―どこに?
ツイツィーリアはあたりを見回す。どこかにワンダーランドの核が形成されているのだ。
ブラックホールという方がわかりやすい。
それは、ローゼンバルツァーのおもだったメンバーや中央フロアにいる賓客の頭上にワンダーランドコアが出現していた。
「避難を」
聖巫女の一人が、ドレスの衣装のまま、ワンダーランドコアに接近していき、異常な現実にただの貴族や金持ち、参加を許された庶民たちはブリジットの指示の元、避難を開始していく。
「これは何なのです?」
「一体・・・」
「いいですから、安全な場所に」
恐怖の場面に会うと逆に冷静になる。戸惑いながらも、彼らは帝国の理念の元、女子供や老人を先に回し、使用人やヴリル達の後についていく。
「ツイツィーリア」
「ええ」
一刻も早くワンダーランドコアを破壊しなければ・・・。
だが、悲鳴が鳴り響く。
「きゃああああっ」
「・・・・あ」
赤い液体が少女の首筋から二つほどの穴から流れ落ちる。
「お逃げください、オルグ様」
きゃあああ、と誰かが悲鳴を上げる。逃げ惑う客達、使用人も事情を知らないものたちからどんどん逃げていく。
「楽しいパーティーは終わりだ」
扉が開き、見事な鍛え抜かれた肉体の男が軍服に身を包み、マントを翻して入ってくる。
「なぜ、お前が」
ヴァルベルグラオ家の当主が、その男の前に出る。
「貴方の存在そのものだ」
いつくしむ女神のような優しい声でシスターはそう言って、頭を押さえこんだ。
ズガぁぁぁ・・・ンッ。
―パンドラの底には希望が残っていた。
でも、その先は何?
顔も覚えていないエプロンドレスの本を持った少女が、未来を約束された少年に優しくほほ笑みかける。
―王になりなさい、全てを守る王に。
少女は赤いあやとりを7歳のころの少年に見せる。
それは幾重にも重なった亡者たちの嘆きであり、憎悪だった。
だが、カイザーがなぜそれが自分に向けられているのかわからないというのは酷であろう。
「死んでください」
悲嘆に満ちていた。
「恨むなら己の無力を我らを恨め」
積もりつもった、叫びだった。
「これは悪ではない、大儀だ」
嘆きだった。
「制裁である」
涙だった。
「我らの苦しみを味わえ」
欺瞞に対する明らかな憎悪だった。
「地獄でお前らが殺した我らの子に土下座して謝れ」
あからさまなカイザーに対する憎悪だった。
秘めていた、祈りだった。
「何を言って、やめろ」
膨れ上がった、裏切られたという絶望と怒りだった。
ズガァァァン。ぎりぎり・・・。
「あの子たちの苦しみはお前達の倍だった」
愛するものを裏切られ、自分に対する憎悪と殺意だった。
装飾が施された短剣の先が向けられ、鎖がカイザーの身を拘束する。身動きできないほどに。
「なんだ、これ」
抵抗するが身動きすらできない。
剣が振り下ろされる。
「神に祝福あれ、我らの悲願を叶えよ」
「やめろぉぉぉ」
銃声が鳴り響く、
「なっ、・・ぐっ」
腹部に鋭い、それでいて熱い鉛が溶かしこまれたような感覚が当主を襲う。黒髪の女性の悲鳴が鳴り響く。当主はひざをつき、その男を見る。軍属とはいえ、当主は穏やかで仲間に優しい男だ。
「すまないな、わが友よ」
ぼやけた視界の中、駆けつけてくるナイトハルトに声を荒げる。
「客をここから非難させろ、お前も逃げるのだっ」
「レオンハルト様」
「速くっ」
ガ―ゴいるたちが客を食い荒らし、よりによって悪夢の魔女―ナイトメア・ウィッチ―の配下が出現してしまう。その姿は当然人間ではない。歯車や巨大な目が膨れ上がった体に巻きつき、細長い数百の手や足が抜き出し、ヒマワリを胸に咲いている。悪魔の中の趣味悪いがらくたなモンスター。
そんな姿だ。ゴォォォ・・・。
「ヴォルフリート様ッ」
ソフィアは会場から出る異国の男に首を傾けながら、魔法杖(ロッド)をふるうが、異臭が漂い、毒の霧が広がるのを止められない。破裂音、奇怪な音や唸り声、体の芯まで凍りつくような冷気に襲われる。
「ソフィア、お前、儀式に参加してたんじゃ」
「抜け出してきたの」
召還、ウォーロック、下級騎士エネルヒア・マジカル。
扉が乱暴に業風とともに開かれ、誰かが驚きの声を上げる。長髪のローゼンバルツァーの子息が大きく目を見開かせる。
ロッドから、人類の敵、ウォーロックの使い魔がその一段とともに会場に足を入れる。エネルヒア・マジカるから火球が会場の中の客人達を襲った。
「悪いな、ヴィクター」
「お前達・・・」
男の仲間は少年がよく知る顔なじみの男だった。
「軍人だったのか?」
次々と、あらかじめ目につけていた戦闘の経験者に男達は剣戟、魔法を仕掛ける。そんな時だ。
「お兄ちゃんっ」
金色のチェーンはエイルの周りをまわり、足元には金色の魔法陣が出現する。
≪物質≫≪輝くもの≫≪秩序≫をつかさどり、エイルはソウルキスを放つ。
空中の一点から金色トオレンジが混ざった風の渦巻きがうなり始め、形作られていく不可視のエイルの弓。甲高い音を上げ、
「いまです、お兄様っ」
「ああっ」
ヴィクターが魔法眼を瞬時に剣へと姿を変える。狂ったように声を上げ、数人がかりで侵入者の戦士だろう男達がヴィクターを切りにかかる。
「ハルトっ」
「ああっ」
「やるぞ」
ショートヘアの少年とサイドテールの少女、ハルトヴィヒで背中を合わせ、にげまどう客達の中、王宮騎士とその部下に立ち向かい、オルグはマジカルと対決する。
「なぜ、自分が守る臣民を恐怖させる、それでも元王宮騎士か」
光の騎士団が抵抗勢力に襲いかかっていく
「フューエル・・・」
その名前が、なぜか激しくジュリアスの胸に切なく、重く、とてつもない悲しみに似た感情とともにジュリアスを襲う。
な・・んだ・・・。
大精霊が少年の手の中で丸紙屑や砂粒のように、原子ごと解体され、物質かとして保てなくなる。
「天魔落ち―サタン―だ・・・・」
すでに息絶える寸前の司祭たちは、侵入者たちが彼らの体が物理法則ではありえない、不自然なほど腕や足が強く捻じ曲げられ、金髪の少年の背中から天使と悪魔の羽が生えていることに気づく。
異界の扉から大砲が、金に装飾された大砲が彼らの頭上に現れ、ラッパの音が鳴り響く。ギャラホルンのラッパ。
「そうか、エレオノ―ル、貴様は・・・」
「なんてものを生みだしたのだ…貴方は」
すべてがすでに終わっていた。カイザーが目を覚ました時、襲いかかってきたゴールドライブラタワーの魔獣は衝撃波によって、天井や壁に貼りつけにされ、骨が噛み砕かれていた。
魔術師たちは着ていた服のみを残し、いなくなっていた。
「・・・・・え?」
ホールでは多くのものが意識を失っていた。
「・・・う・・・」
燕尾服の男が身を起こし、カイザーを見る。
「これは一体・・・」
ドヤドヤと軍人たちが駆け込んでくる。
「天魔落ちだ、奴らにマナは聞かない」
「殺せっ」
あからさまに戦闘態勢、攻撃態勢、素人の自分でも異様に警戒されているのがカイザーは理解する。だが理解できても、なぜ自分がそんな立場に置かれたのか受け入れられるのはよっぽどのものだろう。
「俺が天魔落ち?何を言っているんだ、ま、待て」
兵士たちは、銃口を向けている。グリップをひねれば自分は天国いきだ。
「ごまかすな、この場のもののソウルを吸い取っておいて」
シュテファンが副官を連れて、前に出る。呪文をとらえ、複雑な文様の魔法陣を放つ。多くの死体に、いきなりの現実的じゃない光景。
そうだ、ダイアナは。
「貴様・・・ッ」
背中に剣で切られたような跡がある。かなりの血が流れ、意識を保つのが精いっぱいだろう。
「大丈夫か、一体、だれが」
見えない何かがカイザーの頬を引き裂いた。
「え?」
わずかな血が流れる。
「大人しく、その手の中の剣を収めるんだ、大人しく投降すれば僕は命までは奪わない」
仰々しい長身で細身の銃だ。戦場で人を殺すための専用の銃だ。
「剣?い、いつのまに」
重い剣だ。少なくともカイザーは実戦向きの剣など生まれて初めて持った。何だ、何が起きている?
剣は、赤い血の欠片が散る絨毯の上で転々と転がる。
「・・・投降する、が、俺は天魔落ちではない」
扉が開くと、かんきつ系の香水のにおいが入ってくる。
美しい細身の女性だ。気品と明快さ、二つの反対の要素を宿したような。
「誰だっ」
「お待ちなさい、その代わりモノは私達がその身柄をもらうわ」
三角帽子に舞台役者か?奇妙な格好でずいぶんオレンジのスカート丈が短いがハンドガンを持つ女性はまるでカイザーをハンティングの獲物化のように見る。
「この場は僕に任せてくれ」
軍人が、カイザーを逃がさないように囲み、銃を向ける。
「お前ら、こんなことが許されると思って」
「あんたらの獲物はパンドラがメインでしょう」
だが女は場所を譲り、シュテファンに活躍の場を与える気だ。
「待て、なんだか知らないけど俺はカイザー、カイザー・クラウド、天魔落ちじゃない」
だが軍人は、手の中から、水の剣を生みだし、カイザーに放つ。痛みが襲う、服が水の刃で一気に破けて、かすかな血が白い方からみえていた。
「何のマジックだっ」
よけたが軍人は舌打ちする。
「魔術だ、お前ら害獣から市民を守るための神が与えた手段だ」
軍人は国家と臣民を守るものだ、それが何で暴力的な手段に出ている?それにさっきの水の刃は石があるようにあの若い男の手からいきなり出てきた。
「馬鹿な、魔法なんてあるわけがない」
害獣とは無礼な、後で正式に軍に謝罪を要求してやる。
だが男たちの目は同じ人間、例えば犯罪者でもこんな視線は向けられない。まるで人を人以下の存在であるかのように。
「ノーマナにはそういういしき操作の魔法《ゴスペル》がされるからね、騎士団やパンドラは認知しても君らは疑問を抱かない、魔法はあくまで第三者だと決める」
ドォン。
「きゃああああ」
「いやああああ」
扉が開き、炎が包み込む。
一瞬、背中にすさまじい悪寒がカイザーに走り、あわてて振り向いた。だが目を大きく見開く。
ゴ―ンゴ―ン。
鐘の音が鳴り響く。
「君は・・・」
頭の奥がズキンと痛む。それに何だ。
ひどく胸が苦しく、苦く、切なく、懐かしいような。
ピンク色の唇がつややかに歪み、笑みの形を作る。だが赤い液体が少女の唇の近くについていた。まるでついさっき、血でも吸ってきた吸血鬼のような。
「見つけたわ、青の王アヴァ・キング、…天魔落ち(スレイヤー)にして聖者(セイント)、ナイトにして王、正義にして悪魔」
美しい。
「はぁ?」
・・・・・少し、頭がおかしいのか。
「そうか、これは何かのイベントかおふざけなんだな」
芝居かかったセリフに唐突な展開。後ろの化け物はどう見ても本物の死体のようだが。
「かわいそうな子」
くすり、とほほ笑まれた。
「なっ」
それも美しすぎる絶世の美少女だ。だが笑顔が歪んでいる。悪夢のように。だがそれさえも男をひきつけるものだ。
「・・・・悪い、俺はその手の娯楽に疎くてね、帰らせてもらうぞ」
黒髪のロングヘア、抜群のスタイル、余計な装飾品など彼女の前では無意味、赤い瞳。
「つれないこと言わないでよ、殺し合いましょうよ」
「だから」
別の警察のような格好の少年たちが入ってくる。カイザーに剣や銃を向けてくる。
「お前らもか」
「・・・・お前、赤の女王―レッド・マギーナか」
「多く、血が流れて、みんなばかみたい、おかしいのよ、この私に助けてくれだもの」
少女はドロテアの髪を乱暴につかみ、モノのように扱う。
「一斉射撃、連射するんだ」
ガチャリ、という音が何層も重なり、打つ、撃ち殺す。
「いきなり、なにを、君にげるんだっ」
銃弾の嵐の中――
「いやよ、なんでやっと自由になれたのに逃げなきゃいけないの?」
少女はその選択を後悔したことはない。ティーナ・トゥルケ―ゼノイモントは、アリス達と生きるのみ。
「私こそがアズゥ・カヴァリエ―レだと思ったのに」
訓練された猟犬、シュヴァルツ・パラソルと行動するが、アリスは困っていた。
レーヴェ卿の騎士達がアリスたちと出会った時、すでにあたりは火の中だった。
「ひどい・・・」
こんなの酷いよ・・・。
繰り返される発泡。悲鳴を上げ逃げ惑う人々。こと切れた若い親子。将来を誓い合った恋人達の遺体には指輪がはめられていた。女性の絶叫。
「アーディアディト様、フィネ様達はすでに安全な場所にお連れしています」
血しぶきを上げ倒れていく人々。
「駄目よ、まだ中には多くの人がいるわ、その人達を先に」
それに・・・。
「私はヴォルフリートと一緒でなければ、逃げませんっ、私が探さないと」
少女は博愛主義と行かなくても、争いが苦手な平和主義者で誰にも優しい。
「これはアロイス様も願っていることですよ」
大人しそうで明るく心優しい金髪ロングの少女。
「貴方達は何を言っているの、私が弟を放っておくわけがないでしょう、ずっと前から一緒なんだから」
「お願いです、アーディアディト様・・・」
「いやったら、いや」
その時、シェノルが現れる。
「・・・・いいや、アリス」
シェノルは静かに答える。
「私はここにいますよ」
「なんなんだ、あの女は」
・・・・逃げられた。
「叔父さん達はどこだ」
長い廊下で左腕を押さえながら、血のにおいや煙を吸い込まないよう口を押さえ、オリバー達を探す。
叔父やシャルロットは逃げたのか。
「炎があちらこちらに、何かの事件か、テロか」
受け入れること、それがカイザーにとって信念である以上、魔法も悪魔もいるのだろう。ともかくオリバー達と再会し、早く家に帰りたい。
「シャルロット」
逃げ惑う人々の中にシャルロットがいた。だが呼ばれたシャルロットはなぜか無視して、他の客の子供や老人を連れてカイザーから逃げ出した。声が焔のせいで聞こえなかったのか。
「・・・セバスチャン」
受け入れがたい、研ぎ澄まされた感覚、自分という存在を押しつぶしそうな巨大な何かがカイザーの中で駆け巡った。
「誰だ」
振り向くと、そこにいたのは。
「返せよ」
頭を殴られたカイザーはキッと睨み、振り返る。光る目の少年だ。
「お兄ちゃん・・・」
少女も大きな目が赤く染まっている。
「お前のせいなんだろ、俺の父さんや母さんを返してよ」
涙くみ、皿やインテリアを投げてくる。
「お前ら、パンドラかっ」
カイザーはあわてて銃を構える。
「動くな」
レーヴェ卿の姉、ナターリャが剣を構えてカイザーの前に立つ。
「不埒な天魔落ちが、子供を手に掛ける気か」
「何を言って、おれは」
カイザーは走り出した。
11
「やあああああああ」
「?」
いきなり、角からメイドの少女が剣を振りおろしてきた。
「お前もか」
なんなんだ、今日は。
「サタンめ、死んでしまえ」
爆風で少女のヘッドドレスが吹き飛んで、カイザーはぎょっとなる。折れ曲がった山羊の角のような角が人間の少女の頭に直接生えていたからだ。驚愕よりも先に少女はカイザーに襲いかかる。スご意見筋だ、何と蚊よけるが相手は殺す気らしく緩めない。
「お前さえいなければ、預言は偽物となる」
「何を言っている、俺は悪いことしてないぞ」
少女の顔が赤くなる、怒りだ。
「まだ、あの人を地獄に突き落とす気か、卑怯な悪魔が」
視界の隅でアリスがほかの誰かとともに逃げる場面を見た。
「ハートのジャック様」
「ああ、早く見つかったな」
「軍人か、貴様っ」
銃口を構える。
「どうでもよい、お前は死ぬのだから」
背後から男の部下が襲いかかる。
暴れるカイザーをビリヤード台の上に置く。
「止めろ、何の権限があって俺をこのような態勢で、クラウドが黙っていないぞ」
この国で、オナシス家や侯爵家ほどではないが、それなりに権限がある。次期当主、権威を振りかざすのは好きではないが、こんな理不尽に甘える趣味もない。
歪んだ、馬鹿にした笑みではない。むしろ、小さい子に言い聞かせるように。
「ああ、傍受したとおりだ、少年、お前はカイザーではない」
あらかじめ、用意していたセリフのようだが、軍人はそう答えた。
「はぁ?」
場に合わないが、カイザーは目の前の軍人、いい年した、たぶん軍でもエリートクラスであろう男たちに間が抜けた表情になる。だが哀れむような一笑。誰もがリーダーらしいもの以外、カイザーに目を合わせない。
「俺はカイザー・クラウド、次期当主だ」
まっすぐな目だ。一時、体を拘束から解放されたが、両手を拘束する縄だけは解かれなかった。
「それはおかしい、カイザー・クラウドは隣国の我が国の友人の軍国イシュタルの貴族の人間のはずだ」
「冗談を言うな」
軍人はさっきの奴といい、集団催眠でもかかっているのか、最悪だ、今日はっ。
「本物か偽物か、お前の事などどうでもいい、我ら黒狼(ソンブル・ウルフ)の叡智のものにとっては」
服を引き裂き。
「お前はわれら悲願のため、女神の元へその命を返す、恨むなら薄情なお前の親を恨め」
12
「あなた、どうして・・・・」
だがヴォルフリートは、シャーロットの問いに答えず、軍人たちを斬り込んでいく。
「ぼやぼやするな、来るぞ」
ディートリッヒが客達を連れて、何人か斬ることで、道を作る。
「先に行くぞ、お兄様」
「ああ」
それは舞台のピエロの衣装のようにも、異教の司祭のようにも見えた。大きな部屋だ。華美と言っていい、装飾が施された部屋。ハートオブレクスの騎士が勢ぞろいで彼女の前に並んでいる。
「時が動き出す」
「やっとか」
「助けてくれぇぇ」
誰かが叫ぶが、声が途中で止まる。
でてきたヴォルフリートは、バッハや見慣れた守護者たちを手に掛ける。その間、魔獣に襲われるローゼンバルツァーの親戚たち、炎に焼かれるもの、テロリストに襲われるものがいたが、最初から救う側に入れていない。
「貴様」
少年が怒りでヴォルフリートに迫る。
「そんなに権威が大事か」
「ああ、まだ生き残りがいたか」
ゴォォォォ…。油でも吸っているのか、炎の広がりが早い。ヴォルフリートに迷いはない。セレスティアは、戦うその少年に見惚れていた。ラファエルも。見慣れた者たちが炎に包まれ、いやそれ以外の理由で無残に死んでいる。
勝者は、ヴォルフリートのほうだ。
「行こう」
「おお」
胸に剣が突き刺さる。
「お前・・・・」
ヴリルが驚いたように自分を刺した少年をみる。
「どうして・・・」
どさり、と落ちる。
「・・・あ」
テロリストにでも襲われたのだろう、すでに死の影が女性には見えていた。階段の途中で、金髪の女性は階段の上から下りてくる少年を見る。
「たすけ・・・」
血と炎。惨劇がどこでもあるが、少年は、女性が手を差し出しても、目も向けず、ゆっくりと降りていく。
「・・・お願い、・・・・を・・・して」
ダークブラウンの髪の少年は一度たりとも、その女性に視線を向けることはなかった。
他人を選んだ。
ヴォルフリートはそれが答えだ。
―僕の声は聞こえなかった。
では、自分は何のために今まで。
彼女の血が剣にまだついている。
「・・・」
その時、視界にハートのジャックの姿が目に入る。
なぜ、雀を殺したの?神様。
異界の扉からは軍人を歪ます何かがある。
「行こう、カイザー」
「アリスリーゼ」
「あ、ああ」
剣戟、それも戦闘になれた剣術、そして、ヴァルベルグラオ家の少年の魔術が繰り出される。
「先に行くわ」
「ああ」
ペルソナ、悪魔の力というのは殺傷能力だから。天魔落ちは異界と現実界のバランスを崩す。
「ばかな」
「逃げろ」
暗黒の霧があふれ、感覚を乱し、ラファエルを前衛、防御や工法をヴィルヘルムに任せ、気絶させる。
ハートのキングの至近距離に迫り、悪魔の手で喉を引き裂かれた―死んだという幻覚を誤認させる。
「あぁぁっ」
手下の一人が、アリスリーゼの背中を銃で撃つ。カイザーと手が離れる。
「アリスリーゼッ」
床に倒れ、アリスリーゼは動かなくなる。
敵全員を倒した後、少年はカイザーの方に振り向く。
「行こう、カイザー様」
雨が降っていた。
突然の不幸。だが、ゴットヴァルトはその惨劇よりも多くの死者よりもアリスに殺されそうになったこと、その一点のみで頭がいっぱいだった。
「・・・大丈夫?」
カイザーは混乱していた。目の前で突然多くの死を見せられた。
「お前のせいだ・・・」
友達を他人を大事にするカイザーならこんなことは言わない。だが多くの奪われた命が裏切り者と叫ぶ。
「・・・」
しらーっとしているようにみえた。苛立ちがカイザーの中で一気に走る。
「お前がいたから、おれはっ」
彼からすれば、見当違いもいいところだ。そもそも子息でしかない彼に何ができる。理不尽な殺戮、意味不明な仕打ち。カイザーの常識や世界ではおよそ理解できない出来事。けれど何より、自分だけ助けられて何が嬉しいものかっ。すくう手段があるなら、自分よりも多くのものを助けられたのに。
「ヴォルフリート、お前はすべて知っていたのに救えたのに何で俺を救ったっ」
掴みかかった。彼にはどうしようもない事実だ。今責めるべきは、ヴォルフリートではない。間違いだと知りつつもそうせざるをえなかった。聡明だが世間知らずの学生、それゆえに間違いを起こす。
「―お前が」
「え?」
、何で殺されないといけない、当然だと言わんばかりの、。
「お前さえ生まれてこなければ、死ななかった」
俺は悪くない、世の中を混乱させる、お前らが。
「・・・・カイザー、君は・・・」
そもそも感情が読み取りづらいマイペースな少年だ。珍しくめがみ開き、驚いた表情を浮かべている。痛みを覚えない人間だ、とその時、ヴォルフリートに対して決めつけて。自分はいい、だがお前が多く救えば、いたずらに死ぬ命も存在しなかった。彼らがなにをした、お前らに何を、なぜ苦痛を、無慈悲に殺されるという最悪の悪夢を味わって死ななければならない。
「お前は存在が、生まれたこと自体が間違いなんだっ」
ひきょう者、だがそれでも誰かを責めるしかない。
「出ていけッ、二度と俺の前に顔を出すな」
。
彼からしたら言いがかりもいいところだ。
それも自分の存在を否定されてはどんな奴も怒る。
「さよなら」
表情、眉一つも変えず、カイザーをいくらか意外そうに見た後、そういった。言い返す気もないのか、あきれてものも言えない。
扉を開け、去っていく。
「何なんだ、あいつは」
壁をドンッ、と感情的にたたく。ドタドタ・・・。
足音が、それも一人ではない、近づいてくる。がやがやとうるさい。
「何だ?」
ヴォルフリートが去って行ったあと、大勢の人間がなだれ込んできた。
「投降しろ、ヴォルフリート・フォン・ヴァルベルグラオッ」
鎧と軍服、マントを混ぜたような服装のセカンドの主要ブレイヴが一気にカイザーの周りを囲む。
「はぁ?」
さっきのあいつらといい。
「お前らは誰に武器を向けていると思っている、いいか、間違えるな」
悲鳴をあげそうになった。
「き、きさま・・・」
後方から、背が高い男がニコニコとしながらカイザーの前に進み出た。
槍を喉元につき当てたのだ。軍の関係者か、少し動けばその男は殺すだろうことがカイザーに分かった。
「この槍はね、圧倒的攻撃力と雷の魔法が連続のようだけど、その代わり、おのれのあらゆる罪から逃してくれないんだ」
これはシックスの隊長、鋼の聖人。
「結構辛いから、抵抗するのやめてくれないかな」
「-違う、魔術なんてこの世にない」
「あはは、そうだといいね、じゃあ行こうか」
「この悪魔め、いつか尻尾を出すと思っていたわ」
シャーロットの父、領主が叫ぶ。
「ルイスおじさん・・・」
「嘘つき」
シャーロットが観衆の中、カイザーに投げかける。クラスメイト達の姿もあった。身柄を拘束され、罵声をぶつけられ、卵をぶつけられ、石をぶつけられ。
「痛いっ」
「天魔落ちが」
「無礼な、何をするっ」
「よくも俺達をだましたな」
クラウド家の領民も、家庭教師も。
「化け物」
「嘘つき」
殺せ殺せ殺せ、という言葉が灰色の馬車に特魔に連行される間、カイザーに向けられ。
「・・・ア―ガンス」
その観衆の中には、友人達の姿があった。
「嘘つきの悪魔が」
「え?」
「お前の一族のせいで俺の家はめちゃくちゃになったんだ、よくもだましたな」
涙を浮かべ、憎悪のまなざしを浮かべる。
「俺の・・・、何を」
「裏切り者」
飛行艇で運ばれていく。さも罪人のように。
「でろ」
「俺に銃を向けるな」
「さっさと歩け」
到着したのは古びた石造りの要塞?
巨大な灰色の城だった。
「ここはどこだ・・・」
酷い嵐だ。雷が鳴り響いている。寂ついたにおいが鼻腔をくすぐり、どことなく不安感を感じさせる。
・・・きっと誤解しているだけだ。
石を投げられ、水をかけられ、般若のようだった。蔑み、冷たく笑い、あるいは憎悪や嫌悪をむき出しにする。
自分は何もしていない・・・。
異常な事態だが大丈夫、自分には多くの騎士や家が、ともがいる。波の音が鳴り響く。が、海ではなく、湖の中の孤城のようだった。送られた先は、異端審問官のエモし―オの城だった。
「ここはどこなんだ」
見せしめなのか、街中を歩かされ、その間、悪意や敵意をぶつけられた。あまりにも暴れたせいか、薬を飲まされ、気づいたら飛行艇で、今は悪趣味な城だ。美しい女性だ。服装からして自分と同じ貴族だ。だが傲慢さが其の笑みに張り付いていた。自分と同じ金の髪に緑色の瞳。
「あなたはだれだ」
目を覚ますと、マーガレットが扇を広げ、自分を見ていた。
「これがあの女の救世主様?」
だが、やはり人間として見ていない、冷たくまるで野菜か置物でも見るような目でカイザーを見下ろしている。下の生き物とでも見ているのだろう。
「叔父さんやアルフレートやオリバーやセバスチャンはどうなったんだ、教えてくれ、どうか、どうか」
だが女は声をかける相手でもないというように扉に視線を向ける。扉が見開き、厳しい眼光の黒い髪の少年が入ってくる。
「・・・お前は何者だ」
初対面に失礼な言葉だ。だが、さっきまでの異常な状況が連続していて、すぐに他人に気を許すのは得策ではない。
「甘いな」
「え?」
鋭い目の少年だ。
つかつかと歩み寄ってくる。
「どこの階級のものだ、君は貴族なのか?」
困ったように聞くが、少年は相手にしない。
「疑問を持ったことはないのか?」
ヘンリーはいぶかしげにカイザーに聞いてくる。
「何がだ」
はぁ、とため息をつき、言葉を続ける。
「自分が何でマナを、魔法を使わせてもらえないのか、何で騎士達にかしずかれてきたのか」
勿論、魔術のようなものはあの惨劇の、異常な事態の中、見た。だがうちはただの王家に仕える貴族で軍人で、騎士達も古くからの付き合い、それだけだ。その言い方だと、うちがまるで魔法使いの家のようではないか。
「・・・・お前は何を言ってるんだ?」
隣のイザべラが答える。
「傍に優秀な従者がいたようです、記憶操作の使い手だったようです」
・・・・あのふざけた儀式は父やシーザーも受けていたと聞かされていた。
だが今までの認識がその事実を受け入れるのに邪魔していた。
「馬鹿を言うな、俺にグレイ達がそんな怪しい術をするわけがない、俺は正当な跡継ぎで友達だぞ」
恰好からして、騎士なんだろうか、だがどう見ても学生にしか見えない。俺の家にもおれくらいの騎士はいたが、あんな細い女の子がまさか。
「認識も記憶もか、こざかしいあの侯爵がよく使う手だな、それで深くぼんやりと行かされてきたわけか」
「・・・よろしいので?」
エモし―オが黒い布をかぶった男達を連れて近づいてくる。
「な、何を・・・」
服装や雰囲気よりも何かおかしいことが始まりそうな、何より無言で顔を隠した物に囲まれ、不安を感じずにいれない。
「普通にしてくれ、そうすればすぐに終わる」
どう見ても怪しい、中世の黒魔術の儀式でも出てくるような格好だ。
だが、黒髪の目つきの鋭い少年の顔にようやく、見覚えがある。そう、いつかレミエルでマジシャンの男とともに写っていたチェスクラブの少年だ。
「…そ、そうか、これは悪ふざけなんだな、どこかにおじさんかオリバーでもいるんだな」
ベルトを体に巻き付け、体を固定させていく。
「なあ、お前達、マジシャンか何か何だろう、こんなふざけたことしてないで俺を解放してくれ、妹達も心配するし」
男たちは驚いた顔を見せた後、憐れみの視線を向けた。
「・・・・・気の毒に」
それだけ言って、手下らしい男達は去っていく。
「オリバー、いるのは分かっているぞ、俺は家に帰る、早く出てきてくれ」
だが、だれも答えない。
「構わない、今日までのこいつのすべてを壊す」
短剣で服を引き裂かれた。
「何をする」
睨んでいるが、どちらか上か、すぐにカイザーは理解していた。
「お前にはもう何も残されていない、自由も、名前も、人としての権利も」
「帝国がそんなこと許すモノか」
ズキンと体が痛む。
「禁呪の欠片を流し込んだ、これでうるさいその口も静かになるだろう、俺はヘンリー、ヴォルフリート、お前のいとこだ」
「・・・・俺をあんな魔物と同じにするなッ」
「へえ?お前は魔法など信じない現実主義者なのではないのか」
うっとなる。
「なぜ、お前はクラウド家の誰にも似ていないのに、後継ぎだと思えたんだ、それなら疑問に思ったことはあるだろう」
「・・・違う、そんなこと、俺は母に似て」
「では、そのオッドアイは?お前の家族の中にそんな色の奴はいたか」
「お前は俺を陥れる気か・・・」
だがヘンリーには十分らしく、なおも事実を紡ぐ。
「いいや、お前はヴォルフリート、レオンハルトの次男であり、継承権第二位、お前は今後、ヴァルベルグラオ家の人間と天魔落ちのの両方の顔で生きることになる」
「天魔落ち・・じゃない、大体何なんだ、それは」
「お前は世界を壊す爆弾、黙示録の落とし子、あってはならない神の遺物だ、パンドラよりさらに上の人間ではない怪物だ」
「俺はカイザーだ」
「まずはそのふざけた呪術と術式をはずす」
やれ、と合図をする。
「やめろっ」
ローザンバルツァー家の所有する屋敷の地下でカイザーは暴れまわる。蔭の者たちがカイザーの体を押さえつける。
「あぁぁぁ―――ッ」
ヒュウウウウ。
「いいのですか」
「ああ・・・」
石畳の部屋では、羽根がもがれたように少年が倒れている。
「今は一人にしておけ」
5
7
3
3
」
3
2
4
」
5
3
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- がんばれ!地方競馬♪
- ロージズインメイ産駒 ホウオウルー…
- (2025-11-27 02:13:17)
-
-
-

- 模型やってる人、おいで!
- 連合軍 担架で運ばれる負傷兵 組立…
- (2025-11-27 05:39:58)
-
-
-

- どんな写真を撮ってるの??(*^-^*)
- 高輪ゲートウエイ駅の不思議@@;
- (2025-11-27 07:06:46)
-
© Rakuten Group, Inc.