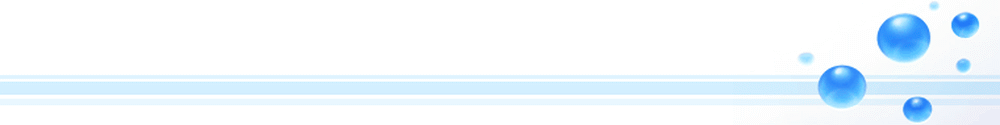兄王・アディス
継いだ。それは、私が国を背負う立場だからだ。
私は父上を尊敬していた。私の考えを理解し、支えてくれ
る存在だった。父上を殺したのは、パルテアとの統一に異議
を唱える者だろう。私は父上を殺した者を、絶対に許すこと
は出来ない。
尊敬すると同時に、私は目標ともしていた。父上がいる限
り、デルクは栄えてゆくだろう。そして、パルテアとの関係
も過去にない形で素晴らしい方法で解決しただろう。父上は
民のため、国のため、そして私たち兄弟のために必死だった
のに。それなのに、どうして父上は殺されてしまったのか。
何故、殺されなければならなかったのか。
私は、父上という尊敬すべき対象と、目標とを同時に。そ
して、永遠に失ったのだ。
父上が亡くなって数日後、パルテアの王子と王女が王都へ
と訪れた。彼らは父の死を悼み、そして私を励ましてくれた
のだ。特に王女であるヴィルヴィーアは私をとても気に掛け
てくれた。その後も彼女は私の元を訪ね、支えてくれた。
私は、ヴィルヴィーアにいつしか心を寄せ愛しいと感じる
ようになった。
彼女は聡明で美しく、優しい女性だった。彼女とともにい
ると私は心が軽くなる
だから、私は願った。このまま、いつまでも彼女とともに
ある自分を。そして、それを彼女に伝えた。
『私は、ラディストを戦争のないひとつの国にしたいと願っ
ている。そして、その時には君に隣にいて欲しいと思う。い
や、その国を作る私を君に見て欲しい。
そんなことを願っては、迷惑だろうか…?』
彼女は驚いた様子だったが、私に優しく微笑み答えてくれ
た。私の願う答えを。
『有り難う。私は貴方の隣で見ているだけではなく、貴方の
手伝いがしたいわ。私もラディストを素敵な良い国にしたい
と願うひとりだから。私と貴方で、それを叶えたいの。』
そして、その答えから7日後。私は彼女をデルクの妃へと
迎え入れることとなった。
それからの日々は、私にとって忙しく幸せなものだった。
私だけでなく、きっとヴィルヴィーアもそうだったのではな
いかと願う。全てのことが、確実に良い方向へと進んでいた。
パルテアとの和平も、デルクの国政も、彼女との日々も。
そう、そんな幸せの中でヴィルヴィーアは私の子供を神か
ら授かったのだ。私はすでに名を考えていた。男ならイデム、
女ならイデア、願い続けたラディストの理想郷に授かった我
が子にと。そう、私が願い考えた名だ。
だが、その日々は長く続きはしなかった。
その日は、久し振りにイディスと食事を摂る予定になって
いた。いつも、互いに忙しく時間が合わないため別々に食事
をしていたのだ。そして、イディスは少し遅くなるので先に
食事をしていて欲しいと言っていた。そして、私に採れたば
かりの実で作られたとシャーベットを渡したのだ。
少し残念な気持ちもしたが、せっかくなので冷たいうちに
食べようとそのシャーベットを口に運んだ。
そして、それは唐突に訪れた。激しい眩暈と嘔吐感を感じ
たかと思うと、いきなり激しい咳に襲われた。まるで、息を
吐き出すように血が溢れて来た。誰かを呼ぼうにも、その音
は血に流されてしまった。
そうしていると、部屋の扉が開きイディスが入って来た。
私は『助かった』と感じたのだが、彼は私の口にしたものを
見て思いもよらない言葉を発したのだ。
『まさか、こんなに簡単に行くとは思いませんでしたよ?』
私は、自分の耳を疑った。そして、彼を見上げるとひどく
冷たい目で微笑んでいた。
『兄上、もう少し人を疑うという行為を知った方が良い。弟
だからという理由だけで、物事を判断するとそうなる。』
未だ、微笑みを残したまま彼は物言えぬ私に告げた。
『兄上、私はずっと兄上が憎かったんですよ。そう、殺した
いと願うほどに。兄上は私の手にすることの出来ぬものを、
いとも簡単に手にしている。そうして、手にした力を使わず
してラディストを統一だなどと。力とは使うためにある。使
わぬ力など、そんなものはないのだから。
しかし、安心して下さい。後は私が上手く使うので。その
力でこの国を誇れる国と変えて行く。あぁ、ヴィルヴィーア
のことも心配しなくて良い。私が全て引き受けるので。
兄上のすることと言えば、そのまま大人しくしていること
だ。父上と同じように…。兄上の誇っていた父上と同じ毒で
死ぬのだから、嬉しいでしょう。気が付かなかったのかも知
ませんが、父上も私が殺したんですよ。』
その言葉を聞き、私は愕然とした。まさか、イディスが父
上を殺したなどと…。確かに、父上を良く思っていない感じ
の所はあったが。私は彼を、それでも良き弟と思っていた。
しかし、イディスは父上と私を手に掛けたのだ。まるで、
小さな動物でも殺すように。微笑みのまま、それをしてしま
うのだ。ショックと不安が私を苛んだ。
私がこのまま死んでしまったら、この国はどうなってしま
うのだろうと。彼のいう力とは、疑うまでもなく武力だろう。
彼はデルクの持つ武力でラディストを統一しようとするのだ。
そして、ヴィルヴィーアをどうするつもりなのか。彼女は私
の子を身篭っている。
私は、その我が子を腕に抱くこともないまま先に逝こうと
している。父上もこんな気持ちを抱いたのだろうか。
だが、私にはその道を逃れる方法を知らない。そして、私
は願う。
ラディストの女神よ…。
どうか、私の分まで彼女らに光を注いで欲しい。
そして、これ以上ラディストを
赤く染めることのないように…。
© Rakuten Group, Inc.