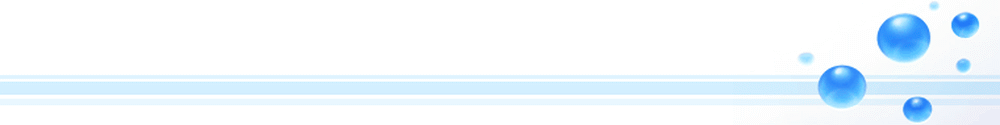戦場の舞姫。
ウーリィは、驚いたように。それでも、嬉しそうに聞きました。
「えぇ、もう5年も前の話だけれど。確か、収穫祭で舞ったのを覚えてるわ。」
エマは、合ってると良いんだけどと思い出すように言葉を紡ぎました。
「ソライです、その国がソライなんです。」
そんなエマを見ながら、ウーリィは嬉しくて泣きそうになりました。
「あ、そういえば、僕も覚えてるかも。」
トトも、そんなエマの話を聞きながら考えるように目を閉じて言いました。
「あら?トトも覚えているの?」
エマは、少しビックリしたように聞きました。
「なんだよー!エマ、僕をバカにしてるだろ?!」
ちょっと怒ったように毛を逆立てたトトは、エマの頬を羽根でつつきました。
「そうじゃないわ。だって、あの国でトトったら迷子になったじゃない?」
クスクスと笑いながら、エマはトトの羽根を摘みました。
「それで、私が見付けたら子供たちに追い駆けられていて…。」
そして、摘んだままトトを自分の膝に下ろしました。
「『こんな国、すぐに忘れてやるー!』って、言ってたのは誰だったかしら?」
膝に下ろしたトトの頭を撫でながら、エマが意地悪な声で聞きました。
「そ、そ、そ、そんな昔の事は、詳しく覚えてないもん!」
撫でられながらも、文句を言うトトはしっかりとその時を思い出しました。
「そんな事があったから、覚えててくれたんですか?」
ウーリィは、笑いを抑えながらエマに聞きました。
「いえ、そうじゃないわ。あの国は、特別よ。」
『そんな事って、失礼じゃんかー!』と怒っているトトを宥めるように。
優しくトトを撫でながら、エマは答えました。
「収穫祭で、白い鳥を放つでしょう?私、どうしてするのか聞いたの。
そうしたら、まだ幼い子供がしっかり教えてくれたのよ。
『どんな色も照らす白い光のように、この国が輝いていますように…。』
『空に国境がないように、いつか大地の境もなくなりますように…。』
まだ小さなお兄ちゃんと妹さんに教えて貰ったのよ。
それで、素敵な行事なんだなって。だから、覚えていたの。」
まるで、懐かしい国を思い出すようにエマは目を閉じて告げました。
「あ、あの、もしかして、その兄妹って…。」
ウーリィは、その話を聞いて何かを思い出すように聞きました。
「お揃いの腕輪をしていませんでしたか?こんな腕輪を…。」
そして、尋ねながらエマに自分の付けている腕輪を見せました。
「そうそう、あの国では流行していたの?」
エマは、その腕輪に見覚えがありました。
あの幼い兄妹がしていたものと同じだったのです。
「いえ、これは僕の両親の形見なんです。」
ウーリィは、自分の腕輪を優しく撫でながら答えました。
「エマさん、その幼い兄は僕なんです。一緒にいたのは、妹です。」
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 本のある暮らし
- Book #0934 ルパンの消息
- (2025-11-20 00:00:13)
-
-
-

- 読書日記
- 書評【ゆるこもりさんのための手帳術…
- (2025-11-20 00:00:13)
-
-
-

- 今日どんな本をよみましたか?
- 近大薬用植物園の花と実・トウガラシ
- (2025-11-20 00:08:53)
-
© Rakuten Group, Inc.