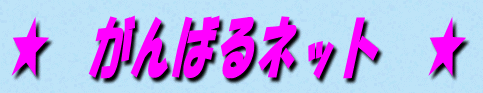糖尿病。慢性腎不全ニュース!
>>Medical Tribune TOPへ
糖尿病の強力なインスリン治療
HbA1Cの急激な低下で網膜症が悪化
〔独ウィースバーデン〕 デュッセルドルフ大学病院内科糖尿病外来の
Ernst Chantelau教授は「コントロール不良な糖尿病患者のHbA1C値を強力なインスリ
ン療法で急激に低下させると,糖尿病網膜症が劇的に悪化することがある」と本紙に
語った。
Early worseningに注意を
糖尿病の後期合併症を防ぐには血糖値の厳密なコントロールが重要であ
る。これは原則的には正しいが,強力な治療により糖尿病網膜症がほどなく急激に悪
化(early worsening)するケースもある。このようなearly worseningの正確な病理
学的機序はまだ解明されていないが,糖尿病治療による網膜症の悪化という逆説的現
象の背景には,虚血性網膜障害が存在するとの仮説が立てられている。
表 Early worseningのリスク患者の疾患・病態
障害を抱えた網膜部位では,網膜において細胞の増殖を促すインスリン
様成長因子(IGF)-Iなどに対する受容体が増加している。HbA1Cが高く維持されてい
る間は,肝臓がIGF-Iの産生量を減らすため,IGF-Iの血中濃度は正常範囲の下限にあ
る。しかし,血糖値が改善されてHbA1Cが急激に低下すると,IGF-Iが上昇し,時には
正常範囲の上限を超えることもある。IGF-Iに比例して網膜に障害が発生し,数週間
のうちに視力が急激に低下するというのだ。
このような好ましくない経過を防ぐには,リスク患者(表)を糖尿病セ
ンターに紹介し,同じ眼科医による眼底検査を 4 週間に 1 回受けさせ,画像で記録
しておくとよい。
事前のレーザー療法も選択肢
場合により,眼科医は血糖値をコントロールする前に,網膜の虚血部位
に対して予防的にレーザー治療を行い,有害なIGF-Iの作用に対する網膜の感受性を
低下させておく。その後,HbA1Cを月間約0.3%のペースで低減させ,慎重に代謝を改
善していく。
急激な血糖値低下により網膜症のearly worseningが生じた場合の唯一
の対処法は,血糖値を一時的に再び上昇させたうえでレーザー治療を行うことであ
る。
しかし,Chantelau教授は,血糖値の急激な低下による網膜症悪化リス
クの存在は,血糖コントロール不良患者をそのまま放置する理由とはならないことを
強調し,「適切な血糖値コントロールの利点は長期的に見て明らかだ」としている。
人工透析患者の2%がC型肝炎感染 医学会など緊急勧告
日本透析医学会と日本透析医会は、人工透析の患者が透析施設でC型肝炎ウ
イルス(HCV)に感染する恐れがあるとして、薬剤の管理の徹底などを求める緊急
勧告を全国約3500カ所の人工透析施設に出した。厚生労働省の研究班(班長=山
崎親雄・同医会会長)の調査では、人工透析を受けた患者の2.2%が院内感染して
いた可能性があるという。
勧告は、「同時集団感染の可能性や、日常的に繰り返す感染の可能性も示唆
される」などとして、国から示されている薬剤の取り扱いを定めたマニュアルを守る
よう求めている。
研究班の調査は、任意に参加した全国の施設が対象。人工透析を受けた患者
約5万2000人のうち、2.2%にあたる約1100人が、01年の1年間でHC
Vの抗体検査の結果が陰性から陽性に転じた。
山崎会長は「何らかの形で人工透析の際に使われた生理食塩水や血液抗凝固
剤などを介してウイルスに感染した可能性がある」と話している。 (04/08 10:08)
血糖値制御の仕組みを解明 岡山大、新薬開発に期待 「1」
記事:共同通信社
提供:共同通信社
【4月7日】
膵臓(すいぞう)の細胞から分泌されるアミノ酸が、血糖値を上げる
ホルモンの分泌を抑える仕組みを森山芳則(もりやま・よしのり)岡山大教授(生化
学)らが6日までに解明し、米国の専門誌に発表した。
日本の糖尿病患者の大半を占めるインスリン非依存型糖尿病に効果的
な新薬の開発につながる成果として注目される。
森山教授らは膵臓の膵島(すいとう)にあるアルファ細胞から、血糖
値を上げるホルモン「グルカゴン」と、神経伝達物質であるアミノ酸「グルタミン
酸」が一緒に分泌されることを解明。その働きを分析していた。
その結果、グルタミン酸はアルファ細胞の表面にある特定のタンパク
質に結合し、グルカゴンの分泌を阻害することが、ラットやヒトの細胞を使った実験
で確認された。
グルカゴンは肝臓に達してグリコーゲンの分解を促し、血糖値を上げ
る。分泌されたグルカゴンが肝臓で働いて血糖値が上がるまでの間に、アルファ細胞
からさらにグルカゴンが分泌され続けると、結果として血糖値が上がりすぎる恐れが
あるため、グルタミン酸がそれを抑える〓フィードバック〓の役目を果たすとみられ
る。
グルタミン酸はコンブのうま味成分として発見されて調味料などに使
われ、記憶や思考にかかわる脳内の神経伝達物質としても知られている。
従来にないタイプの新薬を 「3」
記事:共同通信社
提供:共同通信社
【4月7日】
森山芳則(もりやま・よしのり)岡山大教授の話 従来とまったく異
なるタイプの糖尿病治療薬の開発につながる成果だ。特に血中のグルカゴン濃度が高
い患者にとって有効な薬が期待できる。すでに実用化に向けた研究を始めており、数
年をめどに臨床試験など次のステップに進みたい。今後はより強く反応し、高いグル
カゴン抑制効果を持つ化合物の発見が鍵となる。
提供:Medscape
小児の火傷患者においてインスリンが血糖コントロールとは別に炎症反
応を低減
Yael Waknine
Medscape Medical News
Reviewed by Gary D. Vogin, MD
【4月1日】小児の火傷患者に対してインスリンが、抗炎症媒介物類は顕
著に増大させながらも、前炎症性サイトカインと肝臓の急性期蛋白の濃度を抑えるこ
とで炎症反応を低減させるという後向き試験の結果が、『Annals of Surgery』4月号
に掲載された。
「外傷を受けると、(肝臓の)合成系は肝臓構成蛋白合成から、ヘパト
グロブリン、α2マクログロブリン、α1酸性リポ蛋白、C反応性蛋白(CRP)といった
急性期蛋白の合成に移る」と、レーゲンスブルグ大学(ドイツ)外科病院および衛生
センターのMarc G. Jeschke, MDらが記している。「肝臓の(この)急性期反応の目
的は、恒常性の回復である。しかし、反応が長く過剰に続くと、代謝過剰や異化反応
の増強が起こるので、死亡や病態に至る率が高くなる」。
急性期反応の前炎症性媒介物類には、サイトカインがインターロイキン
1(IL-1β)、インターロイキン6(IL-6)、インターロイキン8(IL-8)、腫瘍壊死
因子(TNF)があるが、中でもインターロイキン10(IL-10)が抗炎症性サイトカイン
である。インスリンの抗炎症作用は、大きな外傷後のこうした細胞媒介物類や肝臓の
急性期反応に対して働くと、著者らは考えている。
重度の火傷を受け、受傷後3日以内の-18歳の小児28例がこの試験の対象
になった。火傷が体表小面積に占める割合は40%を超え、3度火傷が占める割合は20%
を超えており、移植のためのドナー部位が最低でも1カ所必要であった。コホートの
一つは、血糖レベルを120から180 mg/dLの正常範囲に保つのに点滴もしくは単回投与
によるインスリン補充が必要であった小児(n=13)で構成された。もう一つのコ
ホートは、血糖レベルを維持するのにインスリン補充が必要でなかった小児 (n=
15)で構成された。平均して348±170 IUのインスリンが、平均して44±22日間にわ
たって投与された。
全患者において摂取カロリーの量と分布については、Curreriの式で求
め、栄養は経腸で与えた。入院時に比べ試験終了時には体重が、インスリン群は
3.9±1.2%増加したが、コントロール群は.03±1.3%減少した(p<0.05)。
血清アルブミンは毎日測定して、2.0 g/dLの濃度が維持されるように適
切な補充を行った。必要となったアルブミン量は、インスリン群のコントロール群に
比べて有意に少なかった(125±96対271±167 g/m2[火傷面積]、p=0.01)。このこ
とは、受傷から30および40日後の血清プレアルブミン濃度が、インスリン群のほうが
コントロール群よりも有意に(p<0.05)多かったことと関連しており、すなわち、
肝臓の構成蛋白の合成が多かったことを意味している。
インスリンは、受傷直後に遊離脂肪酸が増大することを予防し、15日後
および20日後の濃度をコントロール群よりも低く抑えた (p<0.05)。またインス
リンは、25日後、30日後、40日後の血清トリグリセリド濃度を、コントロール群より
も低く抑えた(p<0.05)。
「遊離脂肪酸の濃度が増えると、肝臓のトリグリセリド蓄積が亢進し、
その結果、肝の脂肪浸潤が起ってやがて肝不全に至り、敗血症や死亡の率が高まる」
と著者らは記述している。インスリンを用いることで、脂肪蓄積の亢進による肝不全
と死亡を予防することが可能であろうと著者らは述べている。
両群とも受傷直後には前炎症性のIL-1βが増大するが、30日後のIL-1β
はインスリン群では有意に低くなり (p<0.05)、コントロール群ではその反対に
若干増大した。受傷30日後のTNF-α濃度の増大についても、インスリン群ではコント
ロール群に比べて抑制されていた(p<0.05)。
こうした抑制と同時に、インスリン群では受傷の30日と40日後のα2マ
クログロブリン濃度が、コントロール群に比べて有意に低かった(p<0.05)。5日
後、10日後、30日後、40日後のCRP濃度も同様にインスリン群が有意に低かった(p
<0.05)。
抗炎症性のIL-10濃度は、両群とも受傷直後には増大し、試験期間を通
じて減少していった。受傷30日後のIL-10濃度は両群とも同じになったが、15日後の
濃度はインスリン群のほうが有意に多かった。
インスリン様成長因子(IGF)1の血清濃度は、両群とも受傷後に3分の1
から4分の1にまで減少し、その主な結合蛋白であるIGFBP3も同様に減少した。しか
し、インスリン群では10日後からIGF-1濃度が3倍に増え、20日および30日後には有意
に増大した (p<0.05)。IGFBP3も20日後に増大したが、コントロール群ではIGF-1
およびIGFBP3は試験期間を通じて低いままであった。
「今回の結果は、インスリンによって前炎症性サイトカイン類と肝臓の
急性期蛋白の濃度が低減することを示している。同時にインスリンは、抗炎症性サイ
トカインであるIL-10を有意に増大させる」と著者らは記述している。「インスリン
治療群とコントロール群の血糖レベルは正常であったことを考えると、インスリンは
血糖濃度の変化を通じた間接的作用ではなく、抗炎症性分子として細胞に直接的に作
用すると考えることができる」。
「インスリンは重度の外傷後の代謝過剰を低減させることが明らかに
なった。インスリンはさまざまな重症状態の死亡や病態を減少させることができると
考えられる」と著者らは記している。
著者らの報告では、利害関係は特にない。
参考文献
Ann Surg. 2004;239:553-560
血液をサラサラにして糖尿病を防ぐ!!
クリスタルカイザーに含まれる『バナジウム』という成分は、
インスリンの感度を高め、血液をサラサラに保つ効果があり、
血糖値を抑え、糖尿病を予防します。
1リットル中にバナジウムを0.055mg含有。
『日経ヘルス』2003年8月号にも掲載されています。
アメリカ・カリフォルニア州につらなるシェラネバダ山脈の、
標高4,000mの山々に降る雪や雨が大自然の中で濾過され
数年掛け1,200mにある環境保全された泉に湧き出るフレ
ッシュな水を源泉でパックした、ミネラルウォーターです。
クリスタルガイザー(Crystal Geyser)は源泉でボトル
詰めし、添加物、防腐剤および人工成分をいっさい加え
ていないピュアでおいしいミネラルウォーターです。
腎移植直後の糖尿病発症で
短期的予後が不良に
〔米ペンシルベニア州ユニバーシティーパーク〕 ペンシルベニア州立大学ミ
ルトン・S・ハーシー医療センター(同州ハーシー)内科のRobert A. Gabbay准教授
らは「腎移植直後に糖尿病(DM)を発症した患者は,移植前からDMを有していた患者
に比べて短期的予後が悪い」とする研究結果を,Transplantation Proceedings
(2003; 35: 2916-2918)に発表した。
移植後のDMでは感染率も高い
ペンシルベニア州立糖尿病センター副所長でもあるGabbay准教授は「DM患者は
その合併症のため,さまざまな医療行為が制限されることが多い。それにもかかわら
ず,移植前からの長期DM患者のほうが,移植後にDMを発症した患者よりも予後がよい
のは驚くべき結果だ。全体的に見て,移植後にDMを発症した患者は拒絶反応,感染,
再入院の可能性が非常に高くなる」としている。
同准教授らは,1999年 1 月~2000年12月にミルトン・S・ハーシー医療セン
ターで腎移植を受けた患者181例の移植前と移植後のデータを検討した。患者は,(1)
腎移植前からのDM患者(88例)(2)移植後DMを発症した患者(21例)(3)移植前も移植
後もDMでない患者(72例)-の 3 群に分けられた。
腎移植前にDMのなかった患者の23%は腎移植後 6 か月以内にDMを発症した。
これらの患者の約57%には感染症が見られたが,移植前からのDM患者では35%,移植
前も移植後もDMにならなかった患者では21%にしか感染症は起こらなかった。また移
植後にDMとなった患者群では,他の 2 群に比べ反復感染する傾向も見られた。
移植後の血糖管理がかぎ
Gabbay准教授は「最近DMを発症した患者では,DMによる合併症をまだ発症しな
いことが期待されるが,今回の調査では,このような患者の腎移植後の予後は不良で
あることが判明した。以前に行われた長期試験は症例数が少ないものの,拒絶反応予
防のために行われる薬物療法によりDMとなることが示された。十分なデータとは言え
ないが,他の研究でも心血管疾患や感染の増加を主因とする死亡や長期入院の発生率
は,移植後のDM発症で高くなることが示唆された」と述べている。
同准教授は「今回の研究は移植後 6 か月に焦点を当てているが,その理由は
移植後の患者では短期間のうちに再入院する大きな問題があるからだ。不良なアウト
カムの発端が早期に始まるのであれば,より早期に治療を開始することで長期的予後
を改善できる。長期的予後の調査にはDMによる他の合併症も含まれるが,短期的なア
ウトカムに焦点を当てた場合,DMによる慢性的合併症の影響を排除でき,グルコース
濃度に的を絞ることができる」としている。
また,「あらゆるDM患者にとり健康状態を維持するには,インスリンを用いた
厳格な血糖コントロールが重要である。腎移植後にDMを発症する患者の予後が悪いと
いうことは,グルコース濃度に関して何かすべきことがあるに違いない。そこで,わ
れわれは次の研究を計画している。早期に治療を開始することにより,患者の長期予
後を改善できればと願っている」と述べている。
Copyright(c) 2004 Medical Tribune Inc. All Rights Reserved.
© Rakuten Group, Inc.