PR
X
Category
カテゴリ未分類
(162)イベント・お祝い
(228)嬉しい贈り物
(366)お買い物
(170)お顔
(72)お散歩
(157)おもちゃ&遊び
(234)お洋服
(15)食べ物
(106)虹の橋
(107)ハンドメイド
(308)病院・健康・お手入れ
(584)プチと大地
(79)プチと大地とメレ
(291)プチと大地とメレとミント
(560)ブログ
(51)モデル・誌面&web掲載
(41)ルチレ
(40)お出かけ:北東北(青森・岩手・秋田県)
(16)お出かけ:宮城県
(7)お出かけ:山形県
(2)お出かけ:福島県
(23)お出かけ:茨城県
(43)お出かけ:栃木県
(102)お出かけ:群馬県
(22)お出かけ:埼玉県
(46)お出かけ:千葉県
(108)お出かけ:東京都(23区)
(97)お出かけ:東京都(23区以外)
(124)お出かけ:神奈川県(横浜市内)
(397)お出かけ:神奈川県(横浜市以外)
(471)お出かけ:新潟県
(2)お出かけ:北陸3県(富山・石川・福井県)
(29)お出かけ:山梨県
(347)お出かけ:長野県
(67)お出かけ:岐阜県
(8)お出かけ:静岡県
(245)お出かけ:愛知県
(7)お出かけ:三重県
(12)お出かけ:滋賀県
(9)お出かけ:京都府
(3)お出かけ:大阪府
(2)お出かけ:兵庫県
(5)お出かけ:奈良県
(1)お出かけ:和歌山県
(8)お出かけ:山陰(鳥取・島根県)
(10)お出かけ:山陽(岡山・広島・山口県)
(12)お出かけ:四国(徳島・香川・愛媛・高知県)
(17)お出かけ:福岡県
(2)お出かけ:その他(1日で複数県)
(11)HITONだけお出かけ
(29)震災・ボランティア関連
(30)Freepage List

ポンタありがとう

わんこにハンドメイド♪

お名前入りニット

雑貨・小物

編みぐるみ

オーダーニット

わんこのおもちゃ

編み物以外のハンドメイド

チャーム

セーター・ワンピなど~2009年~

セーター・ワンピなど~2010年~

セーター・ワンピなど~2011年~

セーター・ワンピなど~2012年~

セーター・ワンピなど~2013年~

セーター・ワンピなど~2014年~

セーター・ワンピなど~2015年~

セーター・ワンピなど~2016年~

セーター・ワンピなど~2017年~

セーター・ワンピなど~2018年~

セーター・ワンピなど~2019年~

セーター・ワンピなど~2020年~

セーター・ワンピなど~2021年~

セーター・ワンピなど~2022年~

セーター・ワンピなど~2023年~

セーター・ワンピなど~2024年~

掲載誌など

【おともだち限定】オーダーについて

オーダー状況

お写真コーナー

☆ソフトクリーム&買い食いリスト☆
Calendar
Keyword Search
▼キーワード検索
カテゴリ: お出かけ:山陽(岡山・広島・山口県)
4/7朝の体重:
プチ4.5kg
大地5.2kg
メレ3.8kg
ミント5.3kg
*******************************************************
写真をクリックすると、フォト蔵で大きくして見られるよ
旅行2日目、
【桜満開の宮島SA】わんこと一緒に広島世界遺産&福岡オフ会の旅 ~ソフトクリームも忘れずに~
の続きです。
リードでわんこ(デッキのみ)

小さかった大鳥居がだんだん近づいて・・・

海から見る厳島神社、素晴らしい

10分ほどで到着

鹿さんと一緒に厳島神社を目指します

さぁ、いよいよ世界文化遺産の 厳島神社 へ
(わんこはキャリー等で)

本社火焼前(ひたさき)より88間の海面にそびえる朱塗りの大鳥居は、奈良の大仏とほぼ同じ高さの16m、重量は約60t。
主柱は樹齢500~600年のクスノキの自然木で作られており、8代目にあたる現在の鳥居を建立するにあたっては、巨木探しに20年近い歳月を要したといいます。
また根元は海底に埋められているわけではなく、松材の杭を打って地盤を強化し、箱型の島木の中に石を詰めて加重するなど、先人の知恵と工夫によって鳥居の重みだけで立っています。

大鳥居
繊細かつ華麗な切妻両流造りで、正面には緑青塗りの引き違いの菱形の格子戸がはめられた本殿には、市杵島姫(いちきしまひめ)・湍津姫(たぎつひめ)・田心姫(たごりひめ)の宗像三女神が祭られています。
屋根に神社の定番とも言える千木と鰹木を持たず、桧皮葺の屋根に瓦を積んだ化粧棟のスタイルを取り入れた寝殿造りならではの様式が特徴です。
現在の本殿は元亀2年(1571年)、毛利元就によって改築されたものです。

本殿
平舞台:寝殿造りの庭にあたる部分で、広さは167.6坪(約553平方メートル)。
安元2年(1176年)、平氏一門が社参して千僧供養が行われた際、社殿の前方に仮廊を設けたという記録があり、こうした仮廊が常設となったものともいわれます。
前方には火焼前(ひたさき)と呼ばれる突き出た箇所があり、管絃祭の出御・還御はここから行われます。
また他の社殿の束柱は木造ですが、この平舞台を支えるのは、毛利元就によって寄進されたと伝えられる赤間石の柱。火焼前分と合わせると239本あります。
高舞台:本社祓殿前にある、黒漆塗りの基壇に朱塗りの高欄をめぐらし前後に階段をつけた舞台で、平清盛が大阪・四天王寺から移したという舞楽がここで演じられます。
舞楽の舞台としては最小のもの。
現在の舞台は天文15年(1546年)、棚守房顕によって作られたもので、当初は組立て式だったものが江戸時代初期に現在のような作り付け構造になったと考えられています。

平舞台&高舞台
国内でも唯一の海に浮かぶ能舞台。
現在、重要文化財に指定されている国内5つの能舞台のうちの1つでもあります。
厳島での演能は、永禄11年(1568年)の観世太夫の来演がその始まりとされ、慶長10年(1605年)には福島正則が常設の能舞台を寄進。
現在の舞台と橋掛及び楽屋が建立されたのは藩主が浅野氏に代わった延宝8年(1680年)のことです。
この能舞台は海上にあるため通常は能舞台の床下に置かれる共鳴用の甕(かめ)がなく、足拍子の響きをよくするため舞台の床が一枚の板のようになっているのが特徴。
春の桃花祭神能がこの舞台で演じられるほか、茶道表千家と裏千家家元が隔年交互に執り行う献茶祭ではここでお茶が点てられ御神前に献じられます。

能舞台
かつては重要な祭事の際、勅使がこの橋を渡って本社内に入ったことから別名・勅使橋(ちょくしばし)とも呼ばれました。
現在の橋は、弘治3年(1557年)に毛利元就・隆元父子によって再建されたもので、擬宝珠の一つに刻銘が残っています。
(以上、全てHPより引用)

反橋
続きます
もしプチ大地メレを気に入っていただけたら、応援クリックよろしくお願いします
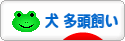
( 別ウィンドウが開ききるまではそのままでお願いしますm(_ _)m )
今までのハンドメイド作品をまとめました

*******************************************************
東日本大震災で被災された方の生活支援を行なっています

*******************************************************



プチ4.5kg
大地5.2kg
メレ3.8kg
ミント5.3kg
*******************************************************
写真をクリックすると、フォト蔵で大きくして見られるよ
旅行2日目、
【桜満開の宮島SA】わんこと一緒に広島世界遺産&福岡オフ会の旅 ~ソフトクリームも忘れずに~
の続きです。
リードでわんこ(デッキのみ)

小さかった大鳥居がだんだん近づいて・・・

海から見る厳島神社、素晴らしい

10分ほどで到着

鹿さんと一緒に厳島神社を目指します

さぁ、いよいよ世界文化遺産の 厳島神社 へ
(わんこはキャリー等で)

本社火焼前(ひたさき)より88間の海面にそびえる朱塗りの大鳥居は、奈良の大仏とほぼ同じ高さの16m、重量は約60t。
主柱は樹齢500~600年のクスノキの自然木で作られており、8代目にあたる現在の鳥居を建立するにあたっては、巨木探しに20年近い歳月を要したといいます。
また根元は海底に埋められているわけではなく、松材の杭を打って地盤を強化し、箱型の島木の中に石を詰めて加重するなど、先人の知恵と工夫によって鳥居の重みだけで立っています。

大鳥居
繊細かつ華麗な切妻両流造りで、正面には緑青塗りの引き違いの菱形の格子戸がはめられた本殿には、市杵島姫(いちきしまひめ)・湍津姫(たぎつひめ)・田心姫(たごりひめ)の宗像三女神が祭られています。
屋根に神社の定番とも言える千木と鰹木を持たず、桧皮葺の屋根に瓦を積んだ化粧棟のスタイルを取り入れた寝殿造りならではの様式が特徴です。
現在の本殿は元亀2年(1571年)、毛利元就によって改築されたものです。

本殿
平舞台:寝殿造りの庭にあたる部分で、広さは167.6坪(約553平方メートル)。
安元2年(1176年)、平氏一門が社参して千僧供養が行われた際、社殿の前方に仮廊を設けたという記録があり、こうした仮廊が常設となったものともいわれます。
前方には火焼前(ひたさき)と呼ばれる突き出た箇所があり、管絃祭の出御・還御はここから行われます。
また他の社殿の束柱は木造ですが、この平舞台を支えるのは、毛利元就によって寄進されたと伝えられる赤間石の柱。火焼前分と合わせると239本あります。
高舞台:本社祓殿前にある、黒漆塗りの基壇に朱塗りの高欄をめぐらし前後に階段をつけた舞台で、平清盛が大阪・四天王寺から移したという舞楽がここで演じられます。
舞楽の舞台としては最小のもの。
現在の舞台は天文15年(1546年)、棚守房顕によって作られたもので、当初は組立て式だったものが江戸時代初期に現在のような作り付け構造になったと考えられています。

平舞台&高舞台
国内でも唯一の海に浮かぶ能舞台。
現在、重要文化財に指定されている国内5つの能舞台のうちの1つでもあります。
厳島での演能は、永禄11年(1568年)の観世太夫の来演がその始まりとされ、慶長10年(1605年)には福島正則が常設の能舞台を寄進。
現在の舞台と橋掛及び楽屋が建立されたのは藩主が浅野氏に代わった延宝8年(1680年)のことです。
この能舞台は海上にあるため通常は能舞台の床下に置かれる共鳴用の甕(かめ)がなく、足拍子の響きをよくするため舞台の床が一枚の板のようになっているのが特徴。
春の桃花祭神能がこの舞台で演じられるほか、茶道表千家と裏千家家元が隔年交互に執り行う献茶祭ではここでお茶が点てられ御神前に献じられます。

能舞台
かつては重要な祭事の際、勅使がこの橋を渡って本社内に入ったことから別名・勅使橋(ちょくしばし)とも呼ばれました。
現在の橋は、弘治3年(1557年)に毛利元就・隆元父子によって再建されたもので、擬宝珠の一つに刻銘が残っています。
(以上、全てHPより引用)

反橋
続きます
もしプチ大地メレを気に入っていただけたら、応援クリックよろしくお願いします
( 別ウィンドウが開ききるまではそのままでお願いしますm(_ _)m )
今までのハンドメイド作品をまとめました

*******************************************************
東日本大震災で被災された方の生活支援を行なっています

*******************************************************



お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[お出かけ:山陽(岡山・広島・山口県)] カテゴリの最新記事
-
【しまなみ海道 大浜PA】瀬戸内&東濃で大… 2017年05月06日
-
【牛窓オリーブ園】瀬戸内&東濃で大地10… 2017年05月05日
-
【牛窓でクルージング】瀬戸内&東濃で大… 2017年05月04日 コメント(2)
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.










