ケニアの旅――貴女とサファリを 4

―― 裏声でひっそりと叫ぶ「ジャンボ」 その1 ――

マサイ・マラ目前の給油所で、再びいつもの4人になり、違う意味での地獄を味わっていた。
フランクは飛ばし屋だ。
すでに舗装された道は途切れていたが、アンボセリへの道中と同じくアクロバチックな運転技術を駆使するフランクなのである。
赤い土が埃を巻き上げ車内に進入してくる。
もうこれ以上、臀部がもたん、というところで車は急停車した。
フランクが外に出るように告げ、涙目のまま外にでると、テレビでよく見かけたことのある牛糞などを塗り固めた家が眼前にあった。
マサイ族の村だ。
マサイ族の村を訪れる―――この、とても俗っぽいオプションツアーを私はすっかり忘れていた。
「ここに来たかったんや!」私は力拳をみせながらMに言う。
「またかいな・・・・・」Mはただ、ただ飽きれるばかりだった。
マサイ村は、藪で作った塀をくぐると円形の広場があり、その広場を囲むようにして牛糞と泥で固めた家が連なっている。
このような集落をニヤッタという。首長中心の大家族集団だ。
マサイ族などナイロ・ハミティック系民族は牛を追って遊牧生活を送るので、一ヶ所に留まらない。だからか、家や集落はとても簡素だ。
槍と盾を手にしてサバンナを素足で駆け巡る男たちは、マンガの世界さながらに、猛獣たちと共存しなければならない運命だ。勇敢な戦死はモランと呼ばれる。
日中、男たちは草を求める牛を追いつづけるので、集落を守るのは老人と女だ。
しかし、今回私たちが訪れた集落の広場には、女子どもばかりか大勢の若い男たちも家の日陰で退屈そうにお天道様を眺めていた。
観光収入に味をしめた堕落してしまったモランたちなのだろうか?
「ジャンボ。ハバリヤコ」藪の門をくぐり、広場に入る私たち4人の姿を見るや否や男たちが寄ってきた。さっそく家のなかを案内してくれるらしい。
英語が達者なマサイの青年に先導され、一軒の家に入る。
この大家族の首長は8人の妻がいるという。つまり、村民みな兄弟だ。
家の中は、もちろん電気も届いていないため薄暗く、よく目を凝らすと3つくらいの部屋に泥壁で仕切られてはいたが、中央の部屋が土間兼寝室といってよい。
しかも、この部屋でさえ3畳足らずの広さだ。
風通しのよい造りとは決していえないが、糞と土づくりのためか、とても涼しく感じる。
逆に夜は糞が熱を貯めるため、暖かくなるだろう。
案内された家の女は不愉快そうな顔を変えることはなかった。
私は早々にサバンナでよく見かけたアリ塚そっくりのこの家を出て、子どもたちと戯れていた。
関西の3人組は広場から奥にある家畜用の広場へ案内されていった。
家畜用の広場は、青空露天市に早変わりしていたのだ。
自給自足が原則のマサイさんたちも、昨今は何かと現金が入用らしい。
この集落をはじめ、マサイの伝統様式も変わりつつあるのかもしれない―――。
アンボセリで、日中プールで過ごしていたら、槍を持ったマサイさんがどこからともなく現れて、小銭をせびりに来たものだった――――。
「ジャンボ!シカモー(年長者に対する挨拶)。俺っちの写真をあんた撮らないかい?」
「いや、いい。昨晩、ピョンピョン飛ぶダンスを観せてもらったときたくさん撮ったから・・・」
「ああ、あいつらは公園内に住む堕落したマサイたちさ」
―じゃあ、あんたは何よ?―
「本物のモランを撮る機会はそうそうないぜ」
―モラン?勇姿がノソノソと、観光客が寝そべるプールサイドに来るかね?―
男はあきらめたようで、プールサイドに平穏が戻った。
Hがこれまた「発見」したキリマンジャロの頂はようやくこのプールサイドからも見ることができた。
分厚い雲が途切れるのを辛抱強く待ちつづけ、雪山が一瞬現れたその瞬間、シャッターを切った。
すると、どこからともなくマサイさんがまたやって来た。
「おい、あんた今、キリマンジャロを撮っただろう?あれは俺たちの神聖な山だ。汚すつもりか?それは大目にみてやるから、チャイをよこしなっ」
あきれ返り、同時に怒った私だが、しだいに笑いがこみあげてきた。
マサイさんもそれにつられて(?)一緒に笑った。
二人の笑い顔にホウオウボクの木に止まっていたツバメのような鳥の一群は一斉に飛び立っていった。
「冗談、冗談・・・」しばらく笑っていたマサイさんだが、急に真顔になり、
「おもしろかったか?じゃあ、チャイをくれ」
「別におもしろくないよっ!それにあんたね~・・・・・さっきからチャイチャイと、私になんのサービスをしたというのよ?」
この人を喰ったような、どこか憎めないマサイさんをたしなめるように告げた。
槍を持ったまま私のそばに佇むマサイさんは、ますます真顔になり、涼しそうに言った。
「プールの監視さ」――――――。
買い物を無視した私にずっとつきまとう担当者(?)の若いマサイの衆に、ある頼みごとをした。
私はケニアの旅を夢みたころから思い描いていた。
――マサイ族の子どもたちに囲まれて一緒に笑顔で「ジャンボー」と叫んでいる写真と撮ってもらう―
「またわざとらしい写真。自然でええやん(笑)」とまたMに笑われそうだ。
いや、実際笑われた。
「キリマンジャロの頂の雪が夕日に染まってほのかに赤くなる。正面に一頭のゾウがいて仁王立ち。
その後をフラミンゴの大群が羽ばたいていく、そんな写真撮りたいねん」
「サバンナの地平線に焼け付くような大きな太陽が沈んでいく、その太陽を二つに割るようにキリンのシルエットが浮かぶ、そんな写真撮りたいねん」
しかし、江戸の仇は長崎で、である。
キリマンジャロの仇はマサイ・マラで、である。
「ねぇ、マサイさん。村中の子どもたちをここに集めてくれないかな~?写真を撮りたいんだけど」
「ああ、写真ね。わかった。ちょっと待ってて」
若い衆は、わずかな軒がある日陰で座り込んで微動だに動かない長老らしき老人にお伺いを立てている様子。
長老は、しばしの時間若い衆の説明を聞き入ったあと、やおらのっそり立ち上がり、私にかすかな微笑みを浮かべた。
年老いたわりに、背が高く背筋もまっすぐな長老は、「あとはお前にまかせた」、というようなそぶりを若い衆にして、また座り込んでもとの「石」に戻った(笑)。
どおやら、交渉は成立したようだ。
というより若い衆よ、子どもを集めてくれたらいいだけじゃん!
なんとももどかしいのは、なぜか、このオプションにパトリックは同行せず、マサイ見学をしないネコちゃんたち1号車に乗ったままマサイ・マラのロッジへ直行していた。
余談になるが、ダチョウのオプションはネコたち1号車4人参加、マサイ族のオプションは私たち4人
が参加。偶然だろうか?
若い衆は何軒かの家に呼びかけ、赤ちゃんからほんとうは学校へ行っていてもいいくらいの年齢まで幅広い層の子どもたちが広場に集った。その数ざっと30人。
もう一声、欲しいところだが、広場をところ狭しと駆け回り、てんで若い衆の言うことを聞かないヤンチャ坊主も数人いるので、「記念撮影」からは除外することにした。
どこの世界にもいるのである。
記念撮影がまた大変である。
小さな子どもたちはカメラを見据えず、私のほうばかり見る。
「ほらほら、お兄さんのほう向いて」
カメラを構える若い衆へ指さすと、子どもたちは私を指さす(笑)。
そのうち、姉の背中におんぶされていた乳児が泣き出す始末で、なんとか若い衆に何枚かのシャッターを切らせた。
が、若い衆はカメラレンズに蓋をしたままの状態だった。
―やれやれ・・・・・また一からやり直しだ―
なんとか無事に「記念撮影会」は終了した。
大勢の子どもに囲まれて私は満足だった。
しかし、今度は私は大勢の「大人」に囲まれる番だった。
まず、撮影終了と同時に、石だった長老が私のもとに歩みよってきた。
背の高い彼の左耳たぶには、なんとフィルムケースが埋められていた。
―おじいさん・・・・・それって、お洒落ですか?―
世話をしてくれた若い衆の目つきも豹変していた。
「まず長老にタバコを1ケース!それから俺たち「キョウダイ」にも分配を!」
渋々、長老にポシェットから封を切っていないマイルドセブン・ライトを1箱渡した。
すると、次々と私に男たちの手がさしだされた――――。
帰国後、現像した「マサイのジャンボ記念撮影」のどの写真も妙に笑っているのは、中央におさまった私ひとりであった―――――。
b> ―― アフリカの水を飲んだ者はアフリカに帰る その1――

「おーい、やっほー、お帰りー」プールサイドで白い肌を余すところなく露出したサングラスをかけた女二人に声をかけられた。
一瞬怯んだが、サングラスをはずして微笑む声の主たちはOと友だちのYだった。
「なんだ、外国人かと思ったよ(笑)」彼女たちの横のデッキチェアーに腰掛ける。
「お久しぶりね。アバーディアはどうでした?」チェアーの白さとほんとうに遜色のない白く締まった肢体のYは、横たわっていた体をねじり私のほうに向き、切れ長の大きな目で語る。
私は目のやり場に困っていたが、そ知らぬ風を決め込む。目線はOにばかり向ける(笑)。
「いや、よかったよー。鍵のかからない部屋での英語劇がムチャ楽しかった」
「英語劇?なにそれ?」
「いやいや(笑)。サイ見れたよ。帰る直前、ヒョウのブザーも鳴ったけど、よくわかんなかった」
「オッ、ヒョウはみられなかったのね?」
「それよかさ、そっちはどうだったの?」
私はMといるときは自然とヘンテコな関西弁で、OやYと過ごすときは、これまた自然にでてくるヘンテコな東京弁だ(笑)。
グレースと話すときは、ぜんぜん自然じゃない(笑)ヘンテコな「英語」だし。
アイデンティティはとっくに崩壊している(笑)。
「まあまぁ、ってとこ。ここのナイトサファリでね、昨晩ヒョウが間近に見れたのよ」
「あっ、すごいじゃないですか(笑)」
「ねぇ、Sくん。なんでYには敬語で、私にはタメ口なのよ。私たち同じ歳だよっ」
「そういうけど、そもそも、僕のほうが年上じゃん(笑)」
「それもそうだけど(笑)」
太陽はほぼ頂点にあり、サバンナが最も焦げ付く時間帯だ。
「たった1週間みないうちに、ずいぶん日焼けしたのね」Yもサングラスをとりびっくりする。
「これでも2回、皮むけたんだよ。ちょっと大人になった(笑)」
「あれからドジ踏んで迷惑かけてない?」
あれから―――――というのは、まだ「カーニヴァル」の遅刻事件や、その原因となった「宝塚追っかけ」のことを根にもっているのだろうか。しつこい、O。
「いや、そんなには、・・・・・あるかな、迷惑(笑)」
実は、最後の最後に大迷惑が待っているのを、もちろん私たち3人は知る由もない―――。
お昼時だからなのか、プールサイドには私たちだけだ。
時折、小鳥たちのさえずりが聞こえてくるぐらいで、小さなプールを囲むホテルのうっそうとした熱帯林により、さえずりがよく木霊する。
木々に遮られ窓のようにわずかにのぞく空にはモクモクと入道雲が立ち上っていた。
アンボセリで私たちは、マサイ・マラでの再会を約束して別れた。
Yはアンボセリではずっと体調不良に悩まされ元気がなかったが、このぶんだと蒸し返す必要もなく大丈夫そうだった。
すこぶる低血圧らしいYは、なにせアンボセリでは一回もサファリをしていないはずだった。
今回の旅発つ直前まで彼女は3日連続の徹夜で仕事をこなしてきたという。
彼女は、アフリカはケニアはもう3回目だと「カーニヴァル」で話していたっけ。
彼女のようリピーターが多いケニアは、人を虜にしてしまう魅力や摩訶不思議な引力があるらしい。
その理由を今回聞いてみた。
「よく諺でいわれてるでしょ(笑)。―一度、アフリカの水を飲んだ者は―」
「赤痢になるっ」
「コレラになるっ」
Yが続けて言おうとしていたところを、私とOは同時に遮って叫んだ。
「違うでしょ、もう(笑)。『アフリカの水を飲んだ者はアフリカに帰る』よ。ローマのトレビの泉にコイン投げるようなものね(笑)」
それなら私も後に―アフリカに帰った―。
しかし、私が「帰ったアフリカ」は、ケニアとは別の国だ―――。
どうして、Yにとって4年の間に3回もケニアだけ、なのだろう。
私は実はYにはもっと核心(コア)になるような部分での説明が欠如しているように思えてならなかったのだが、Yは私たちに構うことなく、読みかけの文庫本に目を落とした。
Yは飄々とした物言いといい、美しい肢体と美貌といい、摩訶不思議な魅力がある。
アフリカのポレポレ精神(ゆっくり)と気質が合うのだろうか。
この旅人には―旅のなかで誰しも抱く、見慣れぬ異国の地での溢れる情熱や感動は、彼女自身がもつ
冷却装置のようなものですべてを異化して、心の奥に仕舞い込んでしまうような技術をもちあわせている―ように思えてならない。
彼女のようなクールな視点を持ち合わせていない、むしろ対極にある私の「意気込む旅」への姿勢は、
すべての「対象」に「感傷的な」旅の「記号」を読み取ってしまうのだ。
きっと、このプールサイドでの光景すら、二人は全く別の世界をつくりあげることだろう。
そう「読み取る」私が、ついつい、「感傷的に」なってしまうのは旅の「終着」が近づいているからにほかならなかった。
ねぇ、このロッジの部屋はどっちでした?」
Yがやおら文庫本から目を離し、私に問うた。
「ロッジって?他になにかあるの?」
今しがたマサイ村からここに到着したばかりの私は、かなり遅めになった昼食を早々に切り上げここにいたのだ。
パトリックの姿がみあたらず、まだチェックインしてないままロッジ内を散策していたので、意味がよく飲み込めなかった。
「コテージとテント式があるのよ。設備は同じだから、断然テント式のほうが風情があってお勧めよ」
「頼んでみたらいいんじゃない?」再び黒いサングラスをかけたOが追従する。
最初、私はOをオバケのQ太郎のフウコとよく似ていると内心思っていたのだが、よく見れば、彼女がもう少しだまっていれば(笑)、Oもなかなかキュートな美人だった。体つきがYとそっくりなところも色白なところも・・・・・。OとYは二卵性の(笑)、双子のようだった。
私はYたちの忠告に従い、レストランへとって返し、パトリックをつかまえ、コテージ式のロッジからテント式に変更が効かないか尋ねてみた。
「変更は効かないが、私はテントのほうなので交換してあげられます」パトリックは喜んで申し出た。
私以外のメンバーはプール近くに部屋があるようだったが、私のロッジはレストランなどがある本館から一番遠い区域にあった。
パトリックが喜ぶはずだ。
マラ川の支流であるクレタ川のほとりに面して建っていた。
テントのジッパーを開けると、ベッド、シャワー室、トイレなどが完備あれており、Yのいう「設備は同じ」が理解できた。テントを囲む木組みの屋根があった。
テントに木枠?
折角のワイルドさが台無しのような気がしたが、夜になるとわかる―――。
夜行性のさまざまな、たとえばサバンナモンキーたちがテントの上を徘徊してうるさいことなんの。
木枠がしているため、まだしも振動は和らいでいたが、それでもテントの布のうえを歩かれたらうるさくて眠れたものではなかった。
パトリックが喜んでいた顔が目に浮かぶ。
まだある。
ここは川の近くである。カバの行動観察にはもってこいだが、夜、カバが鳴き声あげるのを聞いたことがありますか?眠れるひとは尊敬します―――――。
テントの出入り口のジッパーであるが、防虫用のシートと二重になっている。私は外出時にジッパーを最後まで閉めるコツを最後まで覚えきれなかった。
そして、ここも鍵がないことが難点だった。
テントの外には4畳半ほどのスペースに木のテラスがあり、専用のテーブルと椅子がある。
ここでYのように文庫本を取り出して、Yとは違い(笑い)、残り少なくなったウィスキーを傾けるのだ。
これまで、各公園内のロッジはアバーディアの「趣のある部屋」も含めて、概ね快適ライフを過ごすことができた。
夜が深まると、自家発電のロッジ内すべての照明が消え、平原との堺なく闇に染まり、懐中電灯の頼りない光のもとで、シンと静まりかえった部屋に、どこからともなく獣の雄たけびが届く。
夜のロッジもまた、音色のサファリを堪能できるのだ。
カバはもうこりごり、だけど――――。
マサイ・マラでのサファリはMに告げたように、これまでのサファリの総括のような趣であった。
望めば、どんな動物も観察可能なのである。
それよりも私は、1週間、このロッジ生活がいたく気に入っていた。
なんといってもサファリ中は「ちょっと歯ブラシを買いに町へ」、なんてことができないのだから、人口と遮断された、いながらの自然、この「贅沢で優雅なロッジ生活」を満喫しない点はない。
いかに有意義に過ごすかが、サファリの「価値」さえも左右するように思えてならない。
私は日中の暑い盛り、ほとんどプールにいた。もう少し詳しく述べると、「プールサイド」にいた(笑)。
パトリックにはとうていなれないが、Mに言わせると日々、「パトリックに近づいていた」(笑)。
テントでしばらく過ごしたあと、海水パンツに履き替え、再びプールに向かった。
YとOの姿はもうなかった。
一組の白人家族だけが水遊びをしていた。夫婦と小さな女の子二人。
日中はどこのロッジでも、ほとんどひとをみかけなかった。
ケニヤに多く訪れる西欧人は日中もサファリをするらしい。日本人と逆のような気がしておかしかった。
ちょうど、私の娘二人と同じ年頃の女の子たちは、お父さんから悪戯そうに水をかけられ、黄色い歓声をあげていた。
その光景をプールの反対側のチェアーに座り、ビールを飲みながら、微笑ましく眺めていた。
どうしても、遥か数万キロ離れた「異国の地」のことを思い起こさずにはいられない―――。
――みんな元気にしてますか。
パパはアフリカでお仕事がんばっています――
ナイロビで出したあのハガキは、きっと私の帰国後に届くだろう。
それを私から二人に読み聞かせてあげよう。
そうだ、ニエリでだした、もう一枚があった・・・・・・・・・・。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 旅のあれこれ
- 群馬 上毛高原駅近辺散策〜天丸〜猿…
- (2025-02-26 05:38:45)
-
-
-

- フランスあれこれ・・・
- ミッシェルロスタンの灰皿は一度も使…
- (2025-02-25 21:54:13)
-
-
-
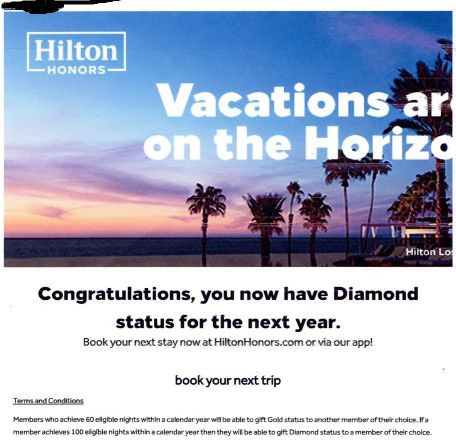
- ラスベガス ロサンゼルス ニューヨ…
- ヒルトン ダイヤモンド会員 2026年3…
- (2025-02-23 06:00:53)
-
© Rakuten Group, Inc.



