さみしい部屋
「じゃあ、」
シンイチは普段と変わらない口ぶりで玄関の扉を開けた。荷物は分けて送っていたから、あとはリュックひとつの身軽な引っ越し姿だ。アパートの玄関は、ついこの間までわたしとシンイチのスニーカーやローファー、サンダルでいっぱいだったのに、今はわたしのものだけで妙にすっきりした感じがした。
「学校で会ったら、どんな顔しちゃうんだろね」
「意外と、こんな感じで普通なんじゃん?」
「そうだといいね」
「じゃ、行くよ」
あっさりとした口調でシンイチは云い、軽く手を挙げると、扉のノブからもう一方の手を放す。
扉の閉まる音。わたしの朝は、終わりから始まった。
急に部屋が静かになった気がした。玄関の扉から目をそらし、ため息をついてみる。その空気の音さえはっきりと聞こえてくる。冷蔵庫の鈍い振動が明瞭に響いてくる。そういえば、この冷蔵庫はシンイチが買ってくれたものだ。その上にある電子レンジは折半で半年前に買った。便利な機能はついていなかったが、ふたりの小遣いでなんとか買えたのはこれだけだった。フローリングの床には薄いカーペットが敷かれていて、その上に木製の座卓が静かに佇んでいる。これは練馬の家具屋でわたしが見つけて来たものだった。昨日まではここでふたりテレビを観ながら食事をしたり、酒を呑んだりして過ごしてきた。そのテーブルの隅に、醤油のシミがこびりついている。こんなに何も置いていないテーブルは久しぶりに見たものだから、シミがついていることなど気づくこともなかった。流しから台布巾を持って来て力を込めて拭いてみる。が、それはもう落ちはしなかった。
シンイチの使っていた部屋は六畳間で、ダイニングと襖一枚で隔てられている。その襖を開けると、なにもない空間だった。開け放されたガラス戸から、生温い風がカーテンを揺らしながら入り込んでくる。シンイチはここで絵を描いていた。絵の具、筆、ペインティングナイフ。ラジカセ。テクノやレゲエのCDが本棚やラックに積み上げられていて、窓際の日が当たるところに、いつもなにかしら描きかけのカンバスがイーゼルに掛けられていた。この部屋に入ると、油絵の具独特の匂いがいつもしていた。どこか生臭い感じのするその匂いを、わたしは好んだ。シンイチは「土の色」と云って茶色を好んだ。空にも、静物にも、植物にも用いてとんでもない色合いの絵を描いた。そのせいか、彼の体からも生臭い匂いが染み付いているような気がして、「土の匂いがする」と一緒に眠る布団のなかでよく思ったものだった。その匂いも、梅雨の終わりの風にまぎれて薄らいでいる。
「この部屋、自由に使えるね」
「持て余してしまうだけだよ」
「カメラの保管室にすればいいよ」
「そんなにレンズも持ってないし」
「じゃあ、暗室にしたら?」
「こんな広いところもったいないよ。それに水とか薬品とか使うし、換気扇ないし」
「いっそのこと部屋移動したら? 手伝うよ」
「いや、いいよ」
彼の部屋を六畳にして、わたしの部屋を四畳半に決めたのはわたし自身だった。九万の借り賃で二部屋、ダイニング付きという物件は、どこも部屋の広さが違っていた。「同棲に二部屋は必要ない」と云う彼に対して、「絵を描くスペースは必ずいるでしょう」とわたしは答えた。「申し訳ないけどありがたいから、遠慮せずにもらうよ」そう云って彼がにっかりと笑ったのを今でも覚えている。四畳半の部屋には天袋があって、カメラの機材の置き場所はそこで充分だったし、なによりシンイチが絵を描く姿を見ていたかった。
その部屋での生活は、今日、二年と二ヶ月で終わった。シンイチは二ヶ月も前からいそいそと引っ越しの準備を始めていた。三ヶ月前に決定的な別れが訪れて、ここまでずるずるとふたりで過ごしてきた。別れることになっても、体の関わりがなくなっただけでなんら変わりのない生活だった。
別れる理由をシンイチは云いださなかった。「そろそろ潮時じゃないかな」と彼が呟いて、「なんで」とわたしが訊いてみて、「そう思っちゃったんだから仕方がない」と答えてきて「もう決まってることなんだね」確認して、彼が頷いて、わたしは黙り込んで、それで決定したことだった。激しい口論も、涙も、暴力も、愛が覚めたという実感もなにもない。だからこれまでずるずるとふたりの時間は延長されていたのだし、それをおかしいと云う気にもなれなかった。
油絵の具の匂いが、湿った風に揺られている。明日には、この匂いもなくなるかもしれない。
ジーンズに履き替えて外に出た。肌に湿気がまとわりついてくる。朝の十時ともなると、通勤姿もほとんど見かけない。シンイチの引っ越し先は私鉄の線路を越えたところにあった。徒歩で十五分かそこらでたどり着く距離だ。引っ越しの手伝いでもしてみようか、と思ってしまうほど、別れた、という感覚がない。しかし、それでももうふたりの何かが交差することはありえないのだ、と、胸の内で呟いて、地下鉄までの遊歩道をゆっくりと歩き出す。空は今にも降り出しそうな様相を呈している。窓を開けっ放しにしていたことを思い出したが、踵を返す気にはなれなかった。ゆったりとしたお昼前の遊歩道だった。じわりと置いて行かれた子供のような気持ちが湧き上がってくる。
「はやく降ればいいのに」
灰色の空を見上げて、大きめの声で呟いてみる。幼い頃のわたしは、なんでもかんでも聞き分けのいい子どもだったらしい。上手な泣き方を知らないのだ。
地下鉄の駅までやってきて、そこから住宅街に続く路地を右に折れた。遅めの洗濯物干しで、ベランダに出ている主婦と目が合ったがすぐに逸らした。
「もうすぐ雨ですよ」
この通りは新旧の家々が交互に続いていて、旧いコンクリ製の家は、くろずんだ壁と、素っ気ないほどに灰色のブロック塀に囲まれており、呼吸のしにくそうな小さな窓が、遠慮がちにいくつか配置してある。夜中に歩いたとき、灯りがついているのを見て、シンイチと「おばけやしきみたいだね」と話したこともあった。そんなかつてはきっとモダンだったコンクリート建築に挟まれるように、小洒落た三階建てのデザイナーズマンションや、きっとこのデザインのために一千万はよけいにお金を遣ったに違いない、というような一軒家を見ることができる。わたしのモルタル製アパートとは雲泥の差だ。その自分のアパートのある小道にでると、昨日から始まった民家の解体工事に出くわした。次に何ができるのかは分からない。しかし、潰される家の悲哀とは逆に、作業員たちは実にはつらつと窓を取り除いたり、埃の飛ばないように幕を張ったりしている。ここ数年で、このあたりはずいぶんと変化した。そしてその変化はまだ続いている。なんでも道路を広くするらしい。旧い家はひとつひとつ、まるで牡丹を摘み取るかのようにゆっくりと、しかし確実なスピードで潰されていく。その代わりに、新しく洗練された家や、マンションが、拡張分のスペースだけを残して建築されている。その最たるものとして、自分の通う大学も、本館から、講堂から、学科棟までつぶされて、汚れも醤油のシミもない、ハイスペックな建物に生まれ変わろうとしていた。今は掘建て小屋がわたしたちの校舎になっている。卒業までに新しい校舎に踏み入れることはできそうもない。街は変わろうとしているが、わたしの生活も変わったのだろうか。そうではない気がする。シンイチは変わったかもしれないけれど、街にも、雨にも、シンイチにも、あの部屋にも、わたしはただ取り残された存在のような気がした。
アルバイトのシフトを増やしてほしい、とチーフに頼むと、彼は一も二もなく快諾してくれた。その後で、「なにかあったの」とさりげなく声をかけてくれる。最高の笑顔で「たいしたことじゃありませんよ」と応えると、「うちは助かるけどね、郡山は学生なんだから卒業できる程度にしとけよ」とだけ云って、また帳簿に目をやった。
着替えを済ませて調理場に入ると、すでにみんな持ち場にスタンバイしている。「今日は金曜だから、忙しくなるわよ」サラダ場兼パティシエのユキノちゃんはチーズの盛り合わせをいくつか用意していた。
「とりあえず、朋美ちゃんはお皿をかたしてくれる?」
すでに多くなっている洗い場の皿を、水を張ったシンクに入れて、ひとつひとつスポンジで洗っていく。水洗いした皿は洗浄機にかけるため、専用の台に詰めてゆき、いっぱいになったところで洗浄機にかける。もう数年来やっている作業だった。洗浄機の内部で勢い良くお湯の噴射される音が、不規則なリズムを作る。それを聞きながら、次の台に水洗いをした皿を詰めていく。調理場の人たちや、ホールの人たちが食べた賄い皿などはプラ製なので、ぽんぽんと勢い良く洗うことができる。わたしはなにも考えずに皿をぽん、コップをぽん、ぽぽんと台に詰めていく。
五時開店と同時に老夫婦の来客があって、それから徐々にお客は増えていった。銀座の七丁目にあるこの店は、生でカンツオーネやオペラを聴かせることが売りで、お客さんもそれが目的の人が多かった。泥酔して駅前で騒ぐような学生たちが、来ることなどほとんどない。その日は盛況で、トイレに入る暇もないほど働いた。チーズの盛り合わせ 生春巻き スモークサーモン お好みピンチョス じゃこと大根のサラダ シーフードサラダ はなまるサラダ 湯剥きトマトとズワイガニのサラダ 抹茶の五つ星アイスクリームに本日のシャーベット。その合間を縫って、明日の仕込みをする。大根やキュウリを短冊状に切ったり、ユキノちゃんが切ったオニオンスライスを水にさらしたりした。始め、包丁はアパートで使っているものよりも大きく、切れ味もよくて、すこし恐怖を覚えたけれど、慣れてしまえばこんなに使い勝手のよいものはない。まな板のうえで、野菜はもとの形をなくし、人間の食べやすい形に変化していく。忙しさにまかせて、ひたすらにまな板を叩く。誰かの、急ぎ足にも聞こえてくる。手を動かすあいだは何も考えずにすむからちょうどいい。
「バイトシフト増やしてほしいって、なにかあったの?」
ユキノちゃんはすこしいたずらな、期待の瞳でそう訊ねて来た。ラストオーダーまで一時間、オーダーの連続が途絶えて、掃除に取りかかっている最中のことだった。
「聞いてもべつにおもしろいことじゃないよ」
「そうなの? でもいいじゃん、教えてよ」
十九歳で、ここにやってきて、ろくに休みのない彼女にとって、アルバイトのいろんな話はおもしろいらしい。「聴かせてよ」と云いながら水を張ったバケツに液体洗剤を溶かし込む。
「彼氏がね、今日出て行ったのよ」
「なに? けんかしたの?」
「出て行く」という言葉にユキノちゃんの目が輝く。
「三ヶ月前に別れたんだけどさ、ようやく引っ越しの準備が整って、今日出て行ったよ」
「ああ、それで家賃が」
「そう。ひとりで九万を稼ぎださなくては追い出されてしまうというわけ」
「そんなのひどいじゃん」とユキノちゃんは云った。「せめて、慰謝料として家賃の補助くらいしてもらわないとさ」
「それも納得ずみだから」
でも、と彼女は続けたが、「仕方ないよ」と呟くと「ならわたしが行こうか?」と笑っている。「それ、いいね」と答えたけれど、本当にそうする気はまったくなかった。
仕事が終わり、店を出ると、足の方から疲れがにじみ出てきた。いつもはシャワーで済ませているが、今日は湯船に浸かりたい気分だった。仕事上がりにもらったビールが体にしみ込んで、足下が浮いているような感覚を覚える。仕事帰りのスーツ姿が歩道にひしめき合っていて、まっすぐ歩きづらい。占い師たちは終電に間に合うように、てきぱきと店じまいをしていた。
遠くの方、数寄屋橋交差点で、一台の車が立ち往生している。けたたましいクラクション。にっちもさっちもいかない、という感じで、車はちょっと進んでは急に止まり、また進んだりしている。さらにクラクションが鳴る。信号が変わったのか、四方から一斉に人々が交差し始めた。車だけが取り残されて、完全に動けないままだ。誰もその車のために道をあけようとはしない。
エルメスの前を通りかかると、いつものように警備員が直立不動で立っている。この人、これから一晩中直立不動なのかしら、と毎度のことのように思い、何もしない、ということが金になるのだなあと感慨にふけったりする。彼は店頭に置かれた人形だった。交差点で立ち往生した車と同じで、こんなに多くの人が歩いているのに、誰も彼のことを見てくれない。
「いいんですか、これ」
割と高い声がしたと思って、目をやると、警備員と背広姿の男が向かい合い、なにやら会話をしている。
「いいんだよ。あまりものだけど、飲んでよ」
「いや、ほんとすみません」
「じゃあ、がんばってくださいね」
短いやりとりだった。背広は軽く手を振って歩き出した。警備員は深々とお辞儀をして、また直立不動になる。その手には缶コーヒーが握られていて、仰々しい制服姿と妙に合っている気がした。急にくやしい、と思った。疲れた足をずんずんと進ませて行きたくなったけれども、人ごみがそれを許さない。小さな歩幅。交差点の前に出ると立ち往生していた車の形はもうなくなっていて、当たり前に他の車が行き来していた。
丸の内線、週末の電車は普段よりもごった返している。つり革に捕まって、できるだけ足に負担をかけないようにした。目の前に座っている男が急になにかわめき散らし出した。酒に酔っているらしく、男は隣のOL風の女性にがなり声をあげている。「なあ、わかるだろ? あんたもさ、使われる身ぃならさ、この男のさみしさっつうのがさ。どんどん税金は上がるし、女房にゃ役立たず扱いされてよお。あんた、そんな妻になっちゃいけないよ。内助の功っていうもんがあんだ。知ってる? 内助の功だよ。な・い・じょ。女は家にいて、きちんと家事こなさなくちゃいけないんだよ。そんなこともできないで、夜の相手もしやがらねえで、あんた、文句ばっかり云っちゃならんよ。それができないなら仕事なんてしたらいかん。いかんのだよ。わかる? 俺の云ってること。わからねえだろうなあ」女は無言のまま立ち上がり、人の間を縫って隣の車両に消えて行った。男が舌打ちをする。「ちきしょう」と小さく呟き目を閉じる。しばらくすると男の喉元から鼾の低く唸るのが聞こえ始めた。
終点池袋で私鉄に乗り換えるためにホームに出る。男は大股開いて、まだ眠っていた。彼がどこで降りる予定なのかはわからない。誰も彼を起こそうとしない。起こしてやるべきか、とも考えたが、けっきょくそうする気にはなれなかった。
駅を出ると、朝から持ちこたえていた空はしとしとと崩れ始めていた。傘は持っていないが、慌てる気分ではなかった。遠回りをして、有楽町線の駅の方までやってくる。遊歩道の煉瓦道に、小さな雨粒が弾かれていく。その様子は、夜の外灯に照らし出されて、スローモーションのように鮮明に見ることができた。植樹された木々の葉が光と雨にまみれて輝いている。後からやってきた傘をさした人々がわたしを追い越していく。濡れているのは自分だけだった。
歩行者信号機の明滅が雨に滲んでいる。短い横断歩道を小走りで横切った。歩みを緩めると、朝から我慢していた煙草を吸いたくなった。コンビニエンスストアに寄って、六ミリの国産煙草を店員に注文する。たぶん、人生で三箱目の煙草だ。アルバイト店員はショートカットの黒髪からしたたる水滴で、レジのテーブルが濡れるのをちらちら見た。極小の水たまりが白面を歪めてみせる。光は吸い込まれ、より深いところに沈着していくように見えた。
アパートの目の前にあるラーメン屋は夜中だというのに、長い列を作っている。有名ミュージシャンが学生のころ、足しげく通っていたという店は、昨年代替えがあって、無口な親父から若い息子が店主になっていた。「味が変わった」と、最近はこの行列を見ることもなかったが、雨だというのに久しぶりの人ごみで、アパートまでの道路が塞がれている。その人ごみを縫って、アパート前にたどり着く。ふと自分の部屋の窓を見てみると、改めて真っ暗なことに驚いた。
「誰もいないところに帰る」
そういう感慨がじわりと湧いてくる。湧いてきたものは二度と収めることができない。夜が明けるのを、じっと待つしかない、それと同じだ。階段を上って、扉の前にきて、鍵をまわして玄関に入る。静けさがわたしを迎える。灯りをつけると、びん、とかすかな電気の走る音がして、同時に足にたまっていた疲れが肩の方まで競り上がってくるのを感じた。ダイニングにべったりと座り込んで、煙草のセロハンをはがし、一本取り出す。ライターを買うのを忘れたことに気づいて再び立ち上がり、ガスコンロで用を足した。十九の夏に覚えた煙草が、喉元で引かかって三度咳き込んだ。しかしそれに慣れると、体に悪いものが、心に悪いものをぬぐい去るようにスムーズになっていった。前に吸ったのはたぶん、四ヶ月前の花見のときだった。シンイチと口論になって、先に家に戻ったとき買ったものだった。ささいな内容だったと思う。シンイチはその後黙って帰ってきて、それ以上の口論はなかった。けれども、よく考えてみれば、それが別れる原因になったのではないだろうか。タイミングがあまりに合っている。そう思うと、ふと浮かんだ仮定はだんだんと根拠もなしに確定されていった。確定された仮定は、真実そのものになる。しかし、真っ当な理由も述べずに出て行ったシンイチを、心から恨むこともできない。誰が悪いわけでもないのだ、と云い聞かせるしかなかった。
煙草を一本吸い終わるころに、視線は六畳間の襖にあった。あの襖を一人で開けることが、妙に空恐ろしく感じられた。開けて、何もない部屋を見て、「土の匂い」を嗅ぐことは、決定的にここにいる人が自分だけであることを自覚させられるような気がした。「もしかしたら、この部屋は開かずの間になるのかな」そう思った。襖はずっしりと目の前にそびえている。自分の方にじりじりと迫ってくるように見えてくる。重たい鉄の扉であるかのように、襖はわたしを拒否した。また、外に出たい気分に駆られた。体は疲れているのに、寝転がってテレビを見て、そのまま眠ってしまうというありきたりな一日の終わりを想像したら、ひどく自分に腹が立ってきた。何もない部屋のために、よけいな出費を補うだけの一日なんて無駄そのものだ、もっと生産的なことをしなくてはならない。そう思って、カメラを三脚につなぎ、白色懐中電灯に赤いセロハンを張って再び外に出た。
雨は止んでいる。どこに行くというのでもなく、静かな街を歩いていった。数百メートルおきにカメラをセットし、小道を長時間露光で撮影する。おもしろい被写体があると、懐中電灯をあて、広角レンズに取り替えて誇張ぎみに撮ってみたりする。夜の神社は、赤く照らし出すといっそう不気味に見えた。煉瓦道の遊歩道ではカメラを地面に置いたまま撮影する。ときどきすれ違う人々が奇異の目で見ているような気がするものの、それを気にしなければそれなりに夜の撮影はおもしろい。
様変わりしていく夜の街並は、思いのほか静かだ。新築された玄関前の、間接照明が真新しい表札を照らし出している。旧い木造家屋の灯りは虫の息で、しかし、たしかにそこに人がいることを感じさせる。自転車が横切る。暗がりのなかで、その人が同じ大学の学生だと分かったときには、もう自転車は遠くに行ってしまい、外灯に照らし出されたり、消えたりしていくうちに、その後ろ姿は見えなくなった。
歩いていくうちに公園にやってきた。そういえば去年の今頃、シンイチと夜中、涼みにやってきたのを思い出す。いい大人ふたりがビール片手に夜風に吹かれている光景はいかにも「終わった」感があったが、今思い出してみるとなかなかおもしろい絵だったと思う。ほろ酔いになったわたしは、めずらしくスカートだというのに滑り台に何度も乗った。
「パンツ丸見えだよ」
「だれも見やしないよ」
「そういう問題じゃねえだろう」
「というか誰もわたしたちのことは見てくれやしないよ」
何がおかしいかもよくわからないままに大笑いした。
その滑り台を撮影する。魚眼レンズを使ってローアングルで見上げたらおもしろいかもしれない。赤い光を当てるとすこし不気味な感じになった。三脚からカメラをはずして地面に敷いたハンカチの上にカメラを置く。地面は濡れた土だったので、少し躊躇したが、勢いにまかせて寝そべった。瞬間、つめたい感触がうすい胸を圧しつぶすのと同時に、土の匂いが強烈に鼻をついてきた。体が一瞬固くなる。立ち上がることもできなくなって、そのまま顔を俯かせた。呼吸を止める。あごを引いて、目をつぶって、視界は闇になったが、体中が土にまみれて、そのまま大地と同化したように錯覚した。泣いてしまいたい。が、うまく泣くことができない。カメラを持たない左手の肘から流れ込んでくる、勢い凄まじいものが背中を走り抜けて、かかとを刺激し突き抜けていく。それは土から生えてくる鋭利な植物の芽だった。体という土壌を突き破り、天に恨みがましく伸びていく感情だった。わたしはその感情に侵されてしまいそうになる感覚に、ぐっと堪えなくてはならなかった。
しばらくしてようやく顔を上げることができた。土の匂いは慣れたせいか、遠くに消え去っている。ゆっくりとカメラのファインダーを覗いた。滑り台の先がぐっと誇張されて、他の背景が赤く歪んでいる。この状態を保つため、カメラの下に小石を置き、アンバランスながらも角度を安定させる。そろそろとレリーズロックする。あとは、しばらく待つほかない。パンツも丸見えではないし、だれもわたしのことなんか見はしないから、そのまま地面に寝そべって、適度な時間を測った。
「ちょっと、君」
突然背後から声をかけられた。呼吸が一瞬止まって逆流し、激しく咳き込んだ。本当はわたしに向けた声なのかどうかは分からない。分からないが声は確実に自分のすぐ後ろから聞こえてくる。上体を起こし振り返ると、ふたりの警官がすぐ後ろに立っていた。
「こんなとこでなにしてるのかな」
肩をすくめて警官を見ると、中年のいかにも、というような男だった。もう一方はわたしとはそれほど齢の差のない、彫りが深く、ラテン系の顔立ちが印象的な男だった。
「いや、ちょっと」
「ちょっとじゃなくて、あんた学生さん?」
「いや、はあ、バイトの帰りなんです」
「バイトの帰りで、カメラなんか持ってるの」
「いや、キッチンのバイトですけど、カメラ、家にあったので」
自分でもよくわからないこと云ってるな、と思う。丁寧に対応しようとすればするほど、うまくいかない。中年警官は口角を引きつらせてため息をつくと、「さっき連絡があってね、不審な人物がカメラで自分の家を撮っているということだったんだけども、たぶん君のことだと思うんだよね」彼の声にはあまり抑揚がない。事務的に話しているといった感じだ。
「すみません、すぐやめますから」
「いや、そういうことじゃ済まされないんだよね。松岡、交番に連絡入れてくれ」
中年警官は若い警官を一瞥してそう云った。松岡と呼ばれる若いほうは、「はい」と夜中に似合わない、はつらつとした声で返事をし、無線でなにやら交信する。どうやら、わたしは交番に連れて行かれるらしい。これは面倒なことになったと思った瞬間、カメラのレリーズを解いていないことを思い出した。あわてて振り返ってカメラの元に走ると、中年警官が「こら、どこへ行くんか」と叫んだ。かまわずにロックを解く。あわてたもののたぶん写真は色が飛んでしまっているはずだ。
「すみません、もう一枚だけ、いいですか」
わたしも図太いな、と思う。あきれ顔の中年警官の後ろで、ラテン系の若い警官がちょっと吹き出したのをわたしは見逃さなかった。
「戦いの場」は環状七号線沿いの交番に移された。妙に白々しい蛍光灯の灯りの下で、わたしはパイプ椅子に座らされ、中年警官のでかい鼻の穴を見つめなくてはならなかった。
「詳しいことは署で聞こうか」という刑事ドラマお決まりの文句を聞けたなら、今日のことは、それはそれでおもしろい経験だからあきらめようと思ったけれども、待っていたのは執拗な尋問だった。濡れた土に汚れた服もそのままで、鼻の穴の粘っこい声に耐えなくてはならなかった。さすがに後になってくるといらいらしながらも、写真を撮っていたいきさつを完璧に説明できるようになり、しかし、フィルムは証拠品として没収され、身元確認のために学生証のコピーを取らされる。「もう一枚だけ」というのが効いたのか、中年警官は最近の若いやつは常識がない、というようなことをさんざんぶちまけた。ラテン系の男は黙って調書を取っている。彼は、シンイチとはまったく逆の姿形をしていた。体全体の線は細いけれども、健全、という言葉が全身から溢れていて、唇の色素がやたら薄かった。その横顔を見ている間、鼻の穴の男の説教はわたしの上のほうをひたすら通り過ぎていく。
「だいたい、いい女性がひとりぷらぷら夜道を歩いているんじゃないよ。アンタの通う大学の学生、評判よくないよ。駅前で脱いで騒ぐし、屋根には登るし、自転車泥棒捕まえてみれば君んとこの学生だし、ほら、北口のアパートで、松岡、おとといだったけな? あんまり夜の声がうるさいって苦情がきてだな、行ってみたら、やっぱり君んとこの大学のカップルだよ。芸術やってるやつは、みんな非常識なんかね。あんたも、夜中一人写真撮ってたりしないで、ほかにすることあるでしょ? ガキみたいに服汚してないでさあ」
けっこうひどいこと云いやがるな、と思いながらも、さほど腹は立たなかった。たしかにそうだね、とさえ思った。家にいても何もやることがないから外に出たわけで、駅前で酔って騒ぐ仲間もいないし、そんな外にまで聞こえるほどの声を上げることも今やない。「ごもっともです。こちらの不手際です。学生が駅前でうるさいのも、駅の屋根に登るのも、セックスの声がうるさいのも、自転車を盗るのも、シンイチが出て行ったのも、みんなわたしの不徳のいたすところです」そう叫んで机を蹴り上げて、それから深々と頭を下げれば、この鼻の穴の男は許してくれるのだろうか。きっと逆上するに決まっている。どうすればよかったのか分からない。わたしの思考は、坂を転がる石のように混乱していった。
警備員にはコーヒーが与えられた。電車でわめく男だって、はっと目を覚ましたところがとんでもない場所だとしても、電話一本でぶつぶつ文句を云われながら奥さんの迎えが来るに違いない。それなのにわたしには迎えも来なければ、コーヒーもなければ、醤油のしみも取れないし、こんなところで鼻の穴を眺めていなくてはならない。愚痴を云える相手すらもういない。あのとき、どうして別れないで、と云わなかったのだろう。出て行かないでとか、家賃払って、とか、わたしも引っ越すから手伝ってとか、慰謝料請求するからね、とか、むちゃくちゃなわがままを云えばよかったのだ。物わかりがよすぎるのだ。すこしくらい、シンイチを困らせてやっても罰は当たらなかっただろうに。最後までいい子でいて、けっきょく泣くのはわたしだけなのに。わたしには何も来なくなった。もう何ももらえないのだ。
つと、涙が頬を伝っているのを肌で知った。「しまった」と思ったが、もうどうしようもなかった。しだいに声はしゃくりあがり、涙があふれ、しまいには大泣きになった。鼻の穴の警官は気まずそうに「いや、ま、君のせいじゃないんだがね」とちいさく弁解をし、ラテン系は目を丸くしていた。そんなことおかまいなしにわたしは泣き続けた。気持ちよかった。泣くのが苦手だったわたしが、人目も気にせずに、いい子でもいずに、子どもの頃のようなみっともない姿で泣けたのだ。ほんとうにみっともなかった。そのみっともなさを、わたしは一度でもあの男にみせることができていたのだろうか。このくらい大泣きをして、あの男を困らせてやりたかった。
涙が終わると、妙にすっきりした気分になって、「ご迷惑かけました」とさばさばした口調で云った。ラテン系の男がティッシュを箱ごとこちらに寄越した。彫りの深い顔立ちが、わたしの崩れた顔を覗き込む。嫌な気はしない。ティッシュを二枚、抜き取ると丁寧に顔を拭き、それを松岡に返した。
「もういいから、松岡、おまえ、その子、送ってやれ」
環状七号線はいまだ、ひっきりなしに車の往来で騒がしかった。とぼとぼとカメラを抱えて歩く隣を、松岡は自転車押しながら、鼻の穴に云われたとおりについてくる。「もう大丈夫ですから」と云っても「仕事ですから」と答えてついてくる。
「それにしても、すみませんね。巡査長、ちょっとひどすぎましたね」
松岡が、遠慮がちに話しかけてくる。
「警官ってみんなあんなもんなんですか」
「いや、とんでもない。彼、ちょっと最近いらいらしてるんですよ。特別です」
「知りもしない人に当たってほしくないわ」
「ごめんなさい」
松岡は、その健康そうな顔立ちに似合わない、弱々しい声で謝る。
「別に松岡さんが悪いわけじゃないですよ」
そう云うと、「いや、でも、まあ」と曖昧な声を漏らして、また黙り込んだ。沈黙を、亀有方面から来たタクシーが走り過ぎて行く。プラタナスが、車の作った弱い風に揺れ、かすかな音をたてるのを耳にする。
「煙草、いいですか」
沈黙を破り、松岡が云う。横目で見ると、返事を待たずに懐から煙草の箱を取り出し、一本銜えて火を点ける。すぐに葉っぱの匂いがわたしの方まで届いてきて、自分までふらふらしてくる。
「でも、おもしろい人ですね、あなたは」
松岡が云った。
「なぜ、ですか」
「変な格好で服汚しながら写真撮ってたし、急に人目もはばからず泣くし、僕は、おもしろいな、って思いました」
「変な女ってことかしら」
「すてきな、って意味ですよ」
また、風がゆるやかに二人の間をすり抜けていく。家の前のラーメン屋は、もう閉店しており、客は一人もいなかった。ただ、煌煌とした灯りのなかで、後片付けをしている従業員たちが、警官と歩くわたしを何事があったのか、というような目つきで一瞥し、すぐさま作業に戻ったのをわたしは見逃さなかった。
アパートの前にたどり着く。任務を果たし、「じゃあ、おやすみなさい」と松岡が云って自転車にまたがるのを、わたしは引き止めた。
「ちょっと上がっていきませんか」
なぜ、そう云ったのか、自分でも分からなかった。単に部屋に一人で戻るのが億劫だった、というだけではなかった。あの男にやれなかったことをしてみたい、という衝動に駆られていたというのが一番それらしい理由になりそうだった。
「いえ、仕事中ですので」
松岡は確実に動揺している。それがまたおもしろい。
「仕事じゃなければ、入るんですね」
「そういうわけじゃないけれど、さっき知ったばかりの人の家に上がるなんてできませんよ」
「家主がいいって云ってるんですよ」
「いや、しかし、勤務中だし」
「勤務中に煙草吸うんですか」
「それは、それとしてですね」
「わたしの使ってない部屋、土の匂いがするんです。いい匂いですよ」
「土の匂いって、あなたの服じゃなくて?」
松岡は、そのラテン系の顔つきには似合わないほどにそわそわし、自転車に中途半端にまたがったまま、目を白黒させていた。彼が、自分のことをどう思っているのか、そんなことかまわなかった。それほど深く、酩酊していた。どうせ、常識のない大学生なのだ。自分のわがままをこれくらいふりかざしてもかまいはしない。わたしはいまだおどおどしている松岡の顔に近づいて、自分でも信じられないほどの強い口調で云った。
「仕事も常識もなにもかも無視しちゃって、わたしを見て上がりたいのか上がりたくないのか、どっちか選んでくださいよ」
松岡は制服の襟を正すと、六畳間の襖をあけて出て行った。一時間ほどの滞在だった。扉は開かれた。重々しく感じられていた六畳間は、いとも簡単に開き、ふたりが埋もれる空間としてきちんと機能したのだ。彼の足音がひたひたと玄関に向かって行くのを、わたしは畳に横になったまま聞く。冷たい足音だ。「また、来ていいかな」松岡が優しい口調で訊いてくる。わたしは応えずに、両腕を顔に当てたまま、ただひたすら息を抑えていた。革靴の、とんとん地面を蹴る音がして、扉は返事も待たず、予想以上に乱暴に閉じられた。
立ち上がり、灯りをつけてあの男の部屋を見回すと、松岡が吸い残した煙草の煙と、灰皿だけで、あとは本当になにもなかった。変に清々しい気持ちだった。この六畳間を、裏切ってやった気がした。小さく、わたしは笑った。笑い続けた。馬鹿なことをしたものだ、と思った。でも、それでなにかが吹っ切れたのならそれで良かった。松岡はきっと二度とはここに来ないだろう。あの男もここには来ないだろう。そう思うと、ふいに煙草の匂いのすき間から、油絵の具の匂いが強烈に鼻をつき、清々しさを呑み込んでいく。油の腐ったような、体内の表面をべたべたと流れ落ちる匂い。生乾きの土の匂いだ。それはもう、部屋の匂いなのか、自分の体から発せられる匂いなのか、よく分からなかった。部屋の外に逃げ出したい気持ちに駆られた。それでもその部屋を出て行く気にはなれないし、逃げても無駄だという確信が揺るぎようもなく目の前にそびえ立っていた。無意味な、空間。あまりにも広い、六畳間。わたしの酩酊はだんだんと醒めていく。残ったものはひとつの感情だった。この空間は、その感情をあてはめるのにちょうどいい大きさだった。そのために用意された広さだった。根元まで短くなって消えてゆく煙草の煙を一瞥して、ダイニングのテーブルに置いたままのカメラと三脚を持ち出す。つけっぱなしの魚眼レンズを部屋の入口にセットして、灯りを消した。曇りガラスの窓だけが、弱々しい輝きを透過させている。三脚をおもいっきり高くして、シャッターを押した。三十秒の長時間露光。わたしはすぐさま部屋の真ん中に寝転がる。裸のまま、寝転がる。どうあがいても逃げられないならば、土の匂いごと、この部屋に収まってしまいたかった。明日、朝一番で現像しようと思う。寒々しい空間にたゆたう煙草の煙は、時間のなかに歪められ、すっかり消え去っているに違いない。
写真のタイトルには、何か形容詞を当てはめてみるのがいちばんいいかもしれない、そう思ったとき、シャッターの切れる音は無感動に響いた。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-
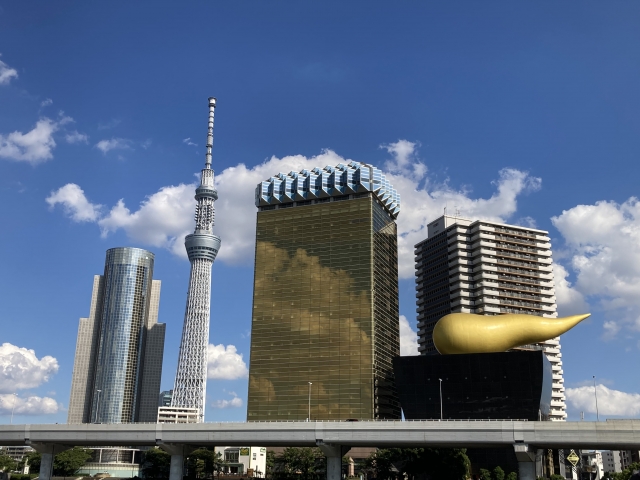
- ◆パチンコ◆スロット◆
- 東京都東大和市 低貸スロット(2.5…
- (2025-11-16 00:00:09)
-
-
-

- 模型やってる人、おいで!
- 客車補足 サンダーバード(その35…
- (2025-11-15 20:52:03)
-
-
-

- 気になる売れ筋おもちゃ・ホビー・ゲ…
- LEGO ‐ Star Wars ‐ | レゴブロック…
- (2025-11-15 21:55:46)
-
© Rakuten Group, Inc.



