猫の恋
「ナアーゴ、ナアアアゴ」と鳴き続けられたんじゃ、ご近所迷惑になるんだってことを分からないのかしら、猫ってやつは。そう云うと、イケザワさんはその横顔をゆっくりと頷かせて、とてもやわらかい声で云った。
「ああ、それ、『猫の恋』」
その日は関東に出てきた者だけでの同窓会で、あのイケザワさんが隣に座った。しばらくぶりで会話は弾んだが、すぐに話題はなくなって、苦し紛れに出したのは近所の猫のことだった。つまらない話を切り出したものだと思ったが、意外と彼女は上機嫌で、「猫の恋」について話し続けた。
「あれは求婚、ていえばいいのかな、とりあえず恋人募集中ですよ、って合図なのよ。俳句の季語にもなっていてさ、『猫の恋声まねをれば切なくなる』なんていう句もあったりして、なんかロマンチックだと思わない?」
「いい迷惑だよ。おかげで毎年この時期は寝不足になるんだから」
「恋は自由でしょう」
「猫が恋するっていうのかい」
「するよお。猫だってカエルだって、恋のために生きてるんだから」
そう云うと彼女はお酒で赤くなっていた顔をいっそう赤くして、残っていたカクテルを一気に空けた。
「野原君も彼女作ったら。仕事だってやる気が違ってくるよ」
「イケザワさんって、初恋っていつだった?」
なによ、薮から棒に、っていう表情で彼女はこちらを見つめたが、「小学五年生のころかな」と答えて「野原君はどうなの」と訊いてきた。
その質問に、少し間を持たせて答える。
「僕は、ちょっと遅くて、中学生のころ、かな」
ええ、誰それ? クラスの子? と彼女は驚いた表情で絡んでくる。その距離の近さにどぎまぎした。
「で、その子とはどうなったの」
「どうもならんよ。ただ教室の隅から眺めていただけさ。そんなもんだろう? 初恋なんて。その点、猫のほうが行動的ってもんだな」
「たしかにそうね」
イケザワさんが小さく笑う。
「野原君も猫のように鳴いたらどう?」
「ただの変態だな」
「でも鳴かなきゃ誰も気づいてくれないじゃん」
「それで猫耳つけたら犯罪だな」
「もう、ごまかさないでさあ、初恋の人って誰よ」
「君がニャーンって鳴いたら教えてやるよ」
調子に乗った言葉を続けながら、「それは君だよ」と冗談めかして云うほうがいいのか、真面目ぶって云ってみたほうが効果的なのか、そんなことをぼんやり考えた。イケザワさんは相変わらずきれいだし、やわらかい物言いがなんだか、昔の想いを思い出させるのだ。できるならば、なんとか今だからこそ云える言葉を伝えたい、そう思った矢先、
「あたしもね、今度結婚するんだ」
返す言葉はなくなった。
幾重にもお祝いの言葉を投げかけながら、お酒をしこたま呑んだ。あのまま「僕の初恋は君だったんだよ」と冗談まぎれに云わないで良かった、としみじみ思いながら、けれど、なんだか急に蚊帳の外に追い出された気分になって、とにかくお酒を呑んだ。「よけいな失恋をしちまったな」などと呟く。体は気持ち悪くて仕方がないのに意識だけははっきりとしていて、幸せそうな彼女の横顔が、なんども浮かんでは消えていった。込み合う終電に乗って、吐き出されるように改札を抜け、やっとのことでアパートの前までたどりつく。猫は今日も外灯の下で鳴いていた。間近で聞いているからか、その鳴き声はひときわ大きくて、よりヒステリックに聞こえた。それともあまりに恋人ができないものだから気が狂ってしまったかもしれない。
「おまえも同窓会に行ったのか?」
猫はこちらに気づいたが、それでも鳴き止まず、ナアゴ、ナアアアゴ、と恋の歌を歌う。美しいとはお世辞にも云えないその声に、ナアゴ、ナアアアゴ、と後に続いて叫んでみる。黒斑の猫はびっくりしたらしく鳴くのを止め、暗闇へ一目散、あたりは静かになってしまった。
部屋の中に入り、押し入れから卒業アルバムを取り出して、顔写真を眺めた。イケザワさんの名前の上に小さく笑う少女の姿があった。ふと小さくナアアゴ、と鳴いてみた。ナアアゴ、ンナアアアゴナアアアゴ。胸の奥からなにかが込み上げてくる。
あわてて閉じられた写真の少女は、まるで失笑しているかのように見えた。
初出『江古田文学』69号
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 寺社仏閣巡りましょ♪
- 11月12日のお出かけ その1 飛木稲…
- (2025-11-14 23:40:04)
-
-
-

- 競馬全般
- (72)京都~エリザベス女王杯予想
- (2025-11-16 07:22:50)
-
-
-
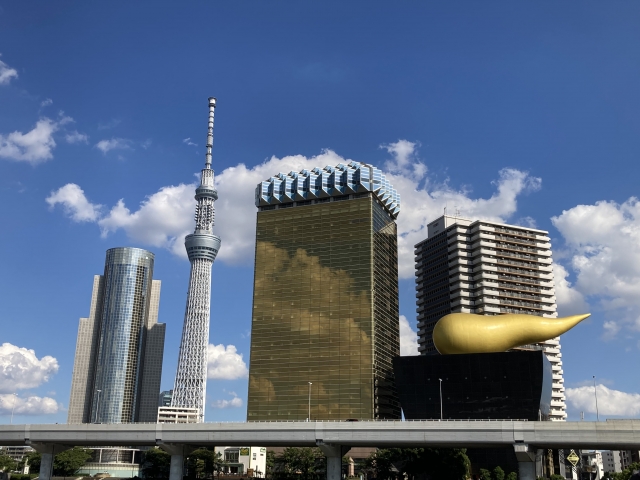
- ◆パチンコ◆スロット◆
- 東京都清瀬市 低貸スロット(2.5円…
- (2025-11-17 00:00:09)
-
© Rakuten Group, Inc.



