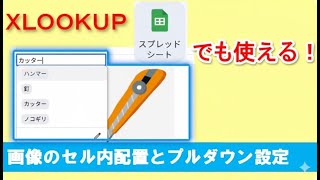日本の習俗vol.6死と生
< 死と生の儀礼の対応 >
何度も書いているが、「死」は霊魂が肉体から離れることであり
あの世で新しい「生」を受け、生き続けるのだとされている。
天理教では死を「でなおし」と呼んだりしている。
少し遺体について枕飯以降のことも書いておこう。
まず湯灌によって丁寧に遺体は清められる(現在は遺体を軽く拭いたりする)。
残った湯は、日のあたらぬところに捨てられ、次いで遺体の身づくろいをして
経帷子を着せ、悪霊退散のための魔除けの刀がすそなどに置かれる。
また、死のケガレがカミに及ばないように神棚に半紙が貼られる。
遺族は遺体と共に喪屋にこもって、別火(べっか)の生活をしたのだ。
そして、これは産湯からはじまる生の儀礼と対応している。
< 葬儀と祖霊化の儀礼 >
通夜以降の儀礼について書き記そう。
遺体から霊魂が取り出され、僧侶がつけた戒名を記した位牌に移される。
↑
霊魂が死体を離れ、あの世で再生したことが象徴的に示される。
土葬の場合は、葬列を組んで墓地へいき、埋葬となるが
先立ち、「へその緒」が棺に入れられる。
これは、母なる大地の胎内にやどって成長するのに必要な滋養を得るためのものだ。
火葬で焼き終えると、遺骨を拾って持ち帰り四十九日の忌明けまで
初七日から七日ごとに家で供養したうえで墓におさめられる。
死者の霊魂は、あの世で毎日の食事にあたる朝夕の仏壇での読経と仏供、
初盆や初正月、百箇日の法要・・・・三十三周忌の弔い上げに至るのだ。
また子供が7歳に至るころまでは特に養育に気を配るとされているように
死者の霊魂も七周忌ぐらいまでは、特に丁寧にまつることが必要とされた。
そうしない死霊は幽霊になり祟ると恐れられたりした。
次回は、 「ふたたび、此の世へ」 ・・・
< ふたたび此の世へ >
死者は、此の世においていく者を気にかけ死んでいくと考えられ
盆や正月には、子孫としばしの時を過ごすと信じられた。
盆 は
7月 7日 墓や家の掃除をして先祖を迎える準備をする。
7月13日 迎え盆には墓に水をかけて先祖の霊を呼び覚まし
*迎え火によって各家の盆棚の位牌に導いてくる。
*先祖は山からとってくる盆花についてきたり、
盆棚に飾ったナスやキュウリの馬に乗ってくるともいわれる。
この後、3日間、子孫と楽しい時を過ごす。
親族やご近所さんは先祖と共食をするために 「中元」 を持って訪れ、
集まった人たちがこれを食べることを
「生見玉(いきみたま)の供養」とも呼んでいる。
僧侶は、帰る家を持たぬ餓鬼が各家の先祖まつりをさまたげるのを防ぎ
さらに餓鬼を成仏させるために、寺で 施餓鬼会(せがきえ) を行う。
また檀家の先祖を供養するために棚経に訪れ、
村人も盆踊りを行って餓鬼を鎮めている。
15日には 送り火 をたいて先祖を墓や山に送るのである。
正月、とくにかつては成人の日とされた
1月15日の小正月も先祖を迎える日であった。
この本来の正月の小正月は1月7日の 七草粥 に始まり、
成人式や農耕の予祝をした。
以前取り上げた、ナマハゲも、これの一種である。
一方
1月1日の大正月は、12月13日の頃の 「煤(すす)はらい」 に始まり
28日の松迎えの時に山からとってくる門松用の松、
31日夜に山上でたかれる火などについて年神が各家を訪れる。
各家では、戸主や長男がつとめる年男が若水を汲んで年神を祀り
その水で 「雑煮」 をつくる。
お年玉 は、先祖から新しい玉をもらって、年をとることを意味している。
年神は1月4日の松おろしの時に、山に帰るとされていて、それまでは
先祖と子孫が楽しく過ごす期間なのである。
もっとも正月は年の初めで神事と受け止められたこともあって
大正月の場合は12月20日・1月4日、小正月の時は
1月16日を仏の正月と呼んで、この日に墓参りなどの仏事がなされている。
ついでに彼岸や追善法要などは、先祖が帰ってくるというよりは
子孫の者が墓に行って先祖を供養するといった行事と考えられよう。
次回は、蘇生(生き返り)と再生(転生)・・・
< 蘇生譚と再生譚 >
祖霊となって帰ってくるとされる日本人だが
蘇生して途中で帰ってきてしまう話や死者が別の人として生まれ変わる話もある。
間近に見た他界の入り口である「三途の川」などの状況を語った話では
美しい花園の間を進むと川があり、その向こうに此の世を去った懐かしい
多くの人がいて、渡り舟で渡ろうとすると、後ろから呼ぶ声がしたので引き返したとか
川があってどうしても渡れないでいたら、息をふきかえしたというものが多々ある。
再生では、平田篤胤が紹介した勝五郎再生。
1810年2月4日、江戸の藤蔵という子供が疱瘡で死んだ。
場所は変わって、中野村の百姓の源蔵の妻から出てきた赤子は勝五郎と名付けられた。
この勝五郎が姉に自分は藤蔵の生まれ変わりだと言って、前世のことを話した。
不思議に思った両親は藤蔵がいたといわれた家にいってみたら
その通りで、勝五郎は藤蔵の生まれ変わりだと確信したという話だ。
勝五郎の話には、死体から出た霊魂が黒衣を着た白髪の翁に導かれ山麓に行き
数日間して、翁の指示で中野村の百姓の妻のお腹に入ったとある。
柳田国男「先祖の話」(1946)には、こうした生まれ変わりは、
霊魂がまだ里近くにいる弔い上げより前に起こる現象で、
本来は同一の氏族または血族の間、特に祖父母の霊が
孫に生まれ変わる例が多いとしている。
これが真実か虚実かは別にして、こういう信仰があったことは
早世した子供を屋敷内に埋めて再生を願ったり
祖父母の名前を孫につける祖名継承もなされている。
山に帰った霊魂が祖神化して、また、
たましいが海や山から新生児に入ってくるという
信仰は生まれ変わりを説明するには面白い背景となろう。
大戦中は「七生報国」というスローガンもあった。
ちなみに再生の回数は頭の巻き目で知ることができるといわれていたようだ。
世界でもこの蘇生・再生の話は存在しており
インド人女性は死亡が確認されて、デリー郊外の墓地に埋葬されることになったが
埋葬される寸前に生き返った、彼女は死亡後~埋葬までを見ていたと証言。
イギリスのショーター青年も、死亡確認後40時間で蘇生、その40時間を見ていた
つまり、もう一人の自分として見ていたと証言している。
イタリアでは、パウレアという女性が胸の病気で死亡、しかし確認後しばらくして生き返り
自分はスペイン人のカルナだと言い張った。
両親は必死にあなたはパウレアだと言っても、彼女はカルナの一点張り。
試しにカルナとは?と語らせてみると、やけに詳しく話すので、医者が
カルナのところに電話をしてみると、4時間前に死んだと応答された。
パウレアは「だから私がカルナなの!」と言うので、電話でカルナの両親と話させてみると
細かいことまで話が合う、これは転生だと思ったという話。
キリストが釈迦の生まれ変わりとする話、三輪明宏は天草四郎の生まれ変わりとする話。
まあ、虚実はわからないが、信仰は日本だけでなく世界でもあったことは間違いない。
ちなみに心霊科学研究家の間では、従来、転生と言われていたのは
A 本人の霊魂が直接、全面的に転生する。
B 本人の霊魂が新しく生まれる者の守護霊となる。
C 前世の人の背後霊が新しく生まれる人の背後霊となる。
D ある人の霊魂がおなじ系統に属する霊魂の統合体に返り、
別な分霊がそこから派遣されて転生する。
と考えられている。あくまで、ちなみにである・・・

クリックをお願いします。
© Rakuten Group, Inc.