PR
カテゴリ
カテゴリ未分類
(108)個別銘柄
(140)業界研究
(10)疑問
(13)投資論
(29)投資に役立つデータ
(8)役に立つ書籍
(29)定性分析
(4)アノマリー・イベント投資法
(1)定点観測
(10)気になるニュース
(16)メモ
(19)斉藤氏逆張りシストレ検証
(11)ROC逆張り投資法検証
(7)雑記
(101)カレンダー
2025.10
2025.09
2025.07
三重県立菰野高校で… 山田真哉さん
運用成績・ポートフ… lodestar2006さん
20周年 bluebonnet7385さん
愛犬こなつのバリュ… konatsu6483さん
コメント新着
キーワードサーチ
先日、100円ショップ業界の運転資金構造分析についての記事を書きました。
その流れというわけではないのですが、個別銘柄分析の第1弾として 2782セリア
を取り上げてみたいと思います。
いろいろ調べても分からないことだらけですので、私の分かっていないところを指摘していただきたいというのも記事を書いている目的です。アドバイス等ありましたらよろしくお願いします。
セリアは キャンドゥ と売上高で業界第2位の座を争っています。1位は言わずもがなのザ・ダイソーの 大創産業 です。
業界としては飽和状態であると言われて久しく、他にも懸念材料には事欠きません。大量発注による低い原価率がビジネスモデルの基本ですので、規模の経済が利きやすい業界です。そういった観点からか、つい先日、業界中堅の 2735ワッツが「シルク」を展開するオースリー(非上場)を買収 し、生き残りを図っています。
以下、セリアについての分析です。定量分析がメインです。というか私の定性分析はあてにならないので鵜呑みには絶対にしないでください。
1.前期までの業績
まずは過去の業績をざっと見てみます。
(1)売上高の推移
売上高は基本的に右肩上がりです(2001年3月期は変則の6ヶ月決算でしたので落ち込んでいます)。ただし、逆に売上高成長率は右肩下がりで、直近5年間は10%台の安定成長で、今期(2007.3月期)は6.3%の成長予想に留まっています。
注)2001.3月期の成長率は売上高を12ヶ月に換算(つまり2倍)してから算出しています。
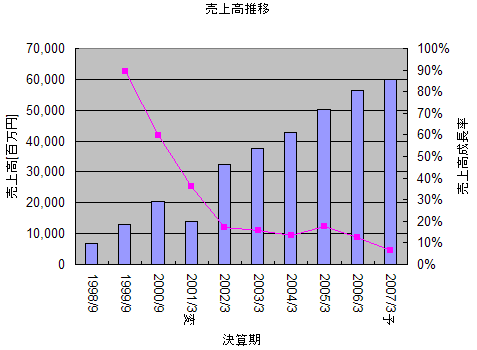
(2)期末店舗数の推移
店舗数は売上高と歩調を合わせるように増えていっています。小売業の場合、事業の拡大を行う場合は店舗を増やすのが基本で、セリアもその路線に乗っていることが分かります。 ただし2006.3月期2Q時点(2005/9)に800店舗を越えてからはあまり店舗は増えておらず、出店ペースを落としていることが分かります。
これだけでは当然、企業の良し悪しは判断できず、1店舗あたりの売上や利益率の推移なども合わせてみる必要があります。
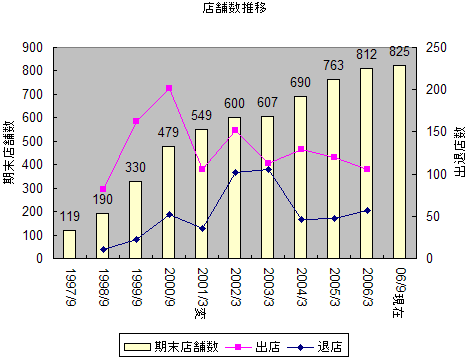
(3)利益の推移
利益額も上昇傾向です。
なぜか2000.9月期に巨額の営業利益を計上していますが、同社の上場は2003年であり、当時どういうことがあったかは分かりませんでした。
2002.3月期に純利益が経常利益に対して異常に少なくなっていますが、貸倒引当金の計上による特別損失の影響が大きいようです。上場前に会計基準を厳格化させたのでしょう。
2006.3月期は売上高の伸びに対して利益の伸びが大きかったようです。この理由については後述する利益率分析で明らかになるでしょう。
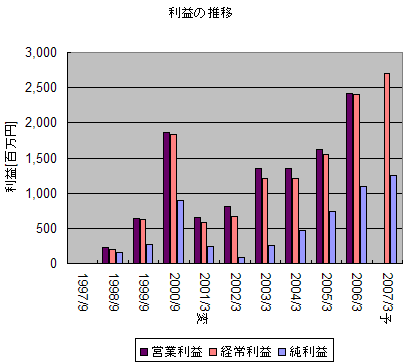
(4)売上高利益率の推移
やはり、2000.9月期になぜだか非常に高い売上高利益率を叩き出してます。何があったかは分かりませんが異常値として参考外にするのが良さそうです。
どうやら売上高で見て300億円を越え、売上高成長率が20%以下に落ち着いた2002.3月期以降で比較するのが良さそうです。2002.3月期以降で見ると利益率は一貫して上昇中で、良い傾向です。
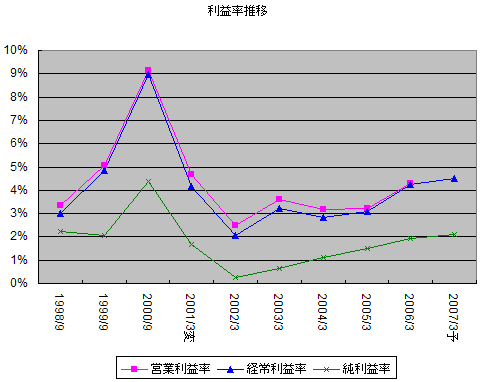
と、ここまで読んで「なるほど」と思った方は、私の15日の記事「 業績予想にも逆張りの視点が必要 」で指摘した 落とし穴にはまっている可能性があります 。
といいますのも、この時点ではまだ、利益率が本当になんらかの理由で上昇しているかどうかは不確定だからです。
良くグラフを見ると、2003.3月期~2005.3月期の3期の間は、営業利益率と経常利益率は3%前後で推移しており、むしろこの3期に限って言えば低下傾向にも見えます。
2002.3月期の利益率が低く、2006.3月期の利益率が高いため、5年を通じてみると上昇しているように見えるのです。本当に上昇しているかどうかは、2006.3月期の利益率上昇が何によるものか、2002.3月期の利益率が低かったのはなぜか、を考える必要があります。
ただし、 あくまでこの時点では確定していないというだけで、2006.3月期の利益率向上は好材料ではあります 。
「この調子なら2007.3月期も利益率は上がるだろう」と安直に思ってしまう危険性があることが、「業績予想にも逆張りの視点が必要」で私が主張したかったことです。
今の時期だと2007.3月期も中間期の業績まで出ていますから、利益率をチェックすることで傾向を確認することができますし、決算書の数字以外の部分を読むこともが必要だと思います。
セリアについて言えば数年前よりPOSシステムを導入していることが経営の効率化に寄与し、利益率アップにつながっているのかもしれません(驚くべきことに100円ショップ業界ではPOSの導入はほとんどされてこなかったようです)。
というわけで、もっと詳しく、営業利益率を構成する粗利益率と販管費率の推移も見てみます。
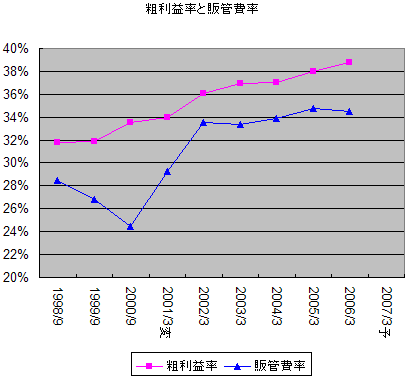
粗利益率の一貫した上昇が目立ちます。規模の拡大によって原価率が下がっているなどの影響が考えられます。
逆に販管費率は、例の儲けまくった2000.9月期は非常に低いですが、わずかに上昇傾向といったところです。基本的には規模が拡大すれば下がってくるべきものと思われますので、これは良くない傾向です。
粗利益率を上げるにも限度があるので、販管費率が下がってきているか、低い値をキープしている企業が個人的にも好みです。ただし、この2つの値は同業他社とも比較し、どのくらいまで上げ下げできる余地があるかを把握しておくことが必要です(まだやってません・・・)。
(5)資本利益率の推移
ROE、ROA、ROICの推移を見てみました。算出方法は以下の通りです。
・ROE=純利益/期中平均株主資本
分母の期中平均株主資本(今は純資産っていうんでしたっけ・・・)は期首株主資本と期末株主資本の平均です。 分子の純利益は、特別損益の影響を受けるのが嫌な場合は経常利益×(1-税率)を使った方がブレがなくて良いかもしれません。税率は40%、41%、42%などいろいろな値が使われているようですが、私は実効税率40.87%に近い41%を使用しています。まあどれでも大差ありません。
・ROA=純利益/期中平均総資産
ROEと同じく、期中平均総資産は期首と期末の平均を用います。この計算式に対しては、分母の総資産には株主に帰属する株主資本と債権者に帰属する有利子負債を含んでいながら、分子の純利益は債権者の取り分である利息を引いた後の額である(株主にのみ帰属する)という不整合が起きているというため、使えない批判がありますが、私は単純にROEと比較することにより財務レバレッジが分かり、自己資本比率も暗算ですぐに出せるため使っています。
・ROIC=営業利益×0.59/((株主資本+有利子負債)の期中平均)
有利子負債は社債+借入金でBSから出してます。
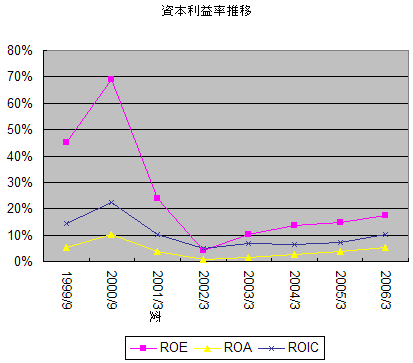
やっぱり2000.9月期が高すぎて他の数字が良く分からないので、2002.3月期以降を下記に抜き出してみます。2000.9月期ごろはROEとROAの乖離も大きく、財務レバレッジがかなり大きかったことが分かります。
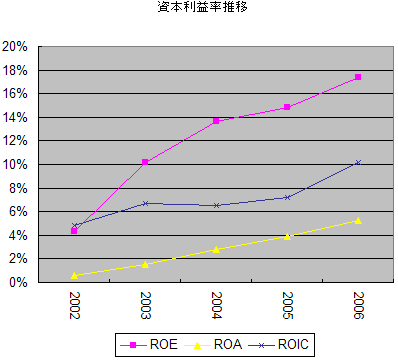
いい感じですね。2006.3月期はROICが10%を越えてきています。WACCが10%を越えるようなリスキーな企業じゃないので、確実にROIC-WACC>0です。つまり投下資本から付加価値を生み出している企業と言えます。
ただし、今後も高い資本利益率が続くことが条件です。その分析は過去の業績分析だけでは不十分で、定性分析の比重が増してきます。業界動向や同業他社比較はもちろん、異業種との比較も必要です。100円ショップ業界はディスカウントショップや食品スーパー、雑貨屋など競合する業態が多く、注意が必要です。
(6)キャッシュフロー分析
企業の価値は将来FCF(フリーキャッシュフロー)の現在価値の合計で決まるというのがバリュエーションの大前提なので、過去のFCFの推移を把握しておくことは大変重要です。
FCFはざっくりと、
営業CF-投資CF
で表すことができます。本当は
営業CF-設備投資額
とした方が厳密なのですが、両者の差は投融資のみなので、いわゆる財テクなどを盛んに行っている会社でなければまあ、誤差は小さいと思われます。
で、このFCF=営業CF-投資CFの推移をグラフにしてみますと(データは直近5期のみ存在)このようになります。
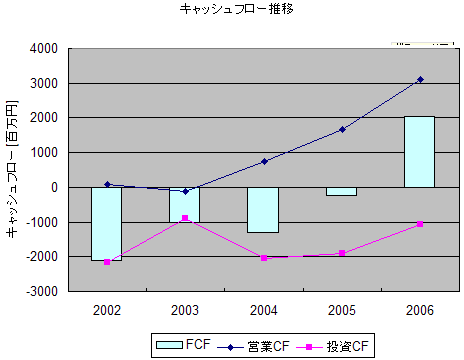
店舗数の増大(=投資)によって事業を拡大してきたので、2005.3月期までFCFはマイナスになってきていますが、マイナス幅は減少傾向で、2006.3月期には出店数をやや減速させたこともあってついにFCFが大幅なプラスとなりました。
拡大期の積極的な投資を回収するフェイズに入ってきたと判断することができます。今期はさらに出店ペースが減速していますので、成長性が期待できない半面、CFの面は期待できそうです。
以上、過去の業績を分析してきました。次回は、現状の分析(今期の詳細な業績分析)を行います。余力があれば今日触れていないB/Sの分析についても書きます。
-
SHOEI:岩手地震の影響なし 2008.06.16 コメント(1)
-
はま寿司はゼンショー傘下だったのか・・・ 2008.05.16
-
隠れたブランド品:DUNLOP FORT 2008.04.22 コメント(1)












