PR
カテゴリ
カテゴリ未分類
(108)個別銘柄
(140)業界研究
(10)疑問
(13)投資論
(29)投資に役立つデータ
(8)役に立つ書籍
(29)定性分析
(4)アノマリー・イベント投資法
(1)定点観測
(10)気になるニュース
(16)メモ
(19)斉藤氏逆張りシストレ検証
(11)ROC逆張り投資法検証
(7)雑記
(101)カレンダー
2025.10
2025.09
2025.07
三重県立菰野高校で… 山田真哉さん
運用成績・ポートフ… lodestar2006さん
20周年 bluebonnet7385さん
愛犬こなつのバリュ… konatsu6483さん
コメント新着
キーワードサーチ
長くなったので適当なところで区切っていきます。
分析(1)でROAを売上高純利益率と総資産回転率に分離しましたが、これをグラフにプロットしていって推移を見てみると面白いです。
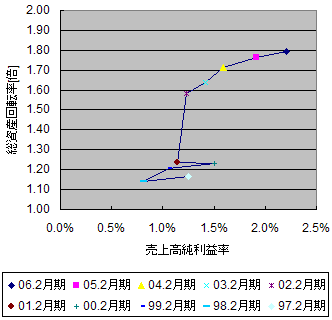
97.2月期から01.2月期までは売上高純利益率も総資産回転率も低く、グラフ上をジグザグに行ったりきたり。
02.2月期に突然総資産回転率が急上昇します。
以降、売上高純利益率も総資産回転率も一貫して上昇。
このグラフでは右上に行けば行くほどいいですから、業績が改善されてきているということがよく分かります。
発生主義ベースである会計上の利益が良くても、キャッシュフローが良くないということはよくあることです。市進の場合は、波はあるものの営業CFは毎年きっちり出しており、かつ営業CFの範囲内で投資を行っていることが、簡易的に計算されるフリーキャッシュフロー(FCF)がプラスであることから分かります。
簡易FCF=営業CF+投資CF (投資を行った場合、投資CFはマイナスになることに注意)
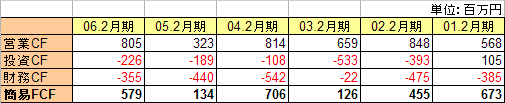
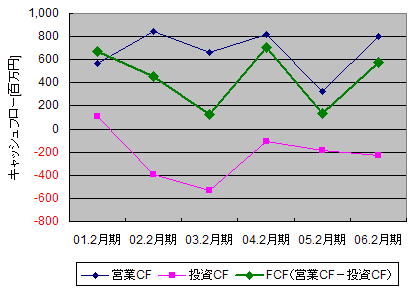
また、市進の場合、財務CFもマイナスとなっており、得た営業CFの中から投資を行い、かつ負債の返済や配当金の支払を行っている、理想的な「+--」の状態になっていることが分かります。
成長はあまり望めませんが、業績には安心感があります。
次はB/Sを使った安全性分析です。
「流動資本キャッシュフロー」とは高田直芳氏の「 ほんとうにわかる株式投資 」で提唱されている安全性に関する指標で、
流動資本CFー=流動資産-流動負債
で定義されています。健全な企業はプラスになります。
「正味運転資本」という呼び方の方がなじみ深いと思われます。
「ほんとうにわかる株式投資」では、これは巧妙に行われたカネボウの粉飾決算でもごまかすことができなかった指標として登場しますが、何のことはない、
流動比率=流動資産/流動負債
と本質的にはあまり変わらないと思います。一般的な健全性の目安である
流動比率>100%
はそのまま流動資本CF>0に対応します。
ただし、引当金等の影響を排除するため、
流動資本CF=流動資産-繰延税金資産-貸倒引当金-流動負債+賞与引当金
が正確な流動資本CFの定義ですので、若干は流動比率とは違う値が出ると思います。
流動比率は私のバイブルとでも言うべき「 できる人の決算書の読み方 」「 企業価値を高めるFCF(フリー・キャッシュフロー)マネジメント 」(ともに著者は池田正明氏)の中で使えない指標として出てきます。
理由はいくつかあるのですが、そのうちの一つは以下のようなものです。
売上債権と棚卸資産(流動資産)が増え、買入債権(流動負債)が減る
⇒ 資金繰りは苦しくなる(運転資金構造分析)
⇒ しかし、流動比率は上がる
と、全く逆の解釈を生むことになるからです。
高田氏の著作はあまり話題に上ることがありませんが、どの本も非常にクオリティが高く、私もかなり勉強させていただきました。しかしこの「流動資本CF」の箇所だけは「??」といった感じです。
市進の場合、流動資本CFは90年代のマイナスから一貫して上昇してプラスに転じてきています(当然、流動比率も改善して100%を超えてきた)。
B/Sの内容をよく見ると、有利子負債をずっと減らしてきていることが、流動負債の減少=流動資本CFの改善に繋がってきていることが分かります。
このような場合は、流動資本CFの改善は信頼できると思われます。
さらに運転資金構造の面からもこれを裏付けてみます。
3つの運転資本回転日数は、10期を通じて常に低位安定しています。資金繰りを犠牲にして流動資本CFや流動比率を高めているわけではないことがこれではっきりしました。
それにしてもこの3つの運転資本回転日数の低さは驚異的です。ほとんど現金で収入があり、在庫を多く持たず、支払も現金払いが多い(割引価格で仕入れができているかもしれない)のではないでしょうか。
SF(セルフファイナンス)日数はマイナスで、資金繰りは超余裕の状態です。
今日はこの辺で終わります。
-
SHOEI:岩手地震の影響なし 2008.06.16 コメント(1)
-
はま寿司はゼンショー傘下だったのか・・・ 2008.05.16
-
隠れたブランド品:DUNLOP FORT 2008.04.22 コメント(1)












