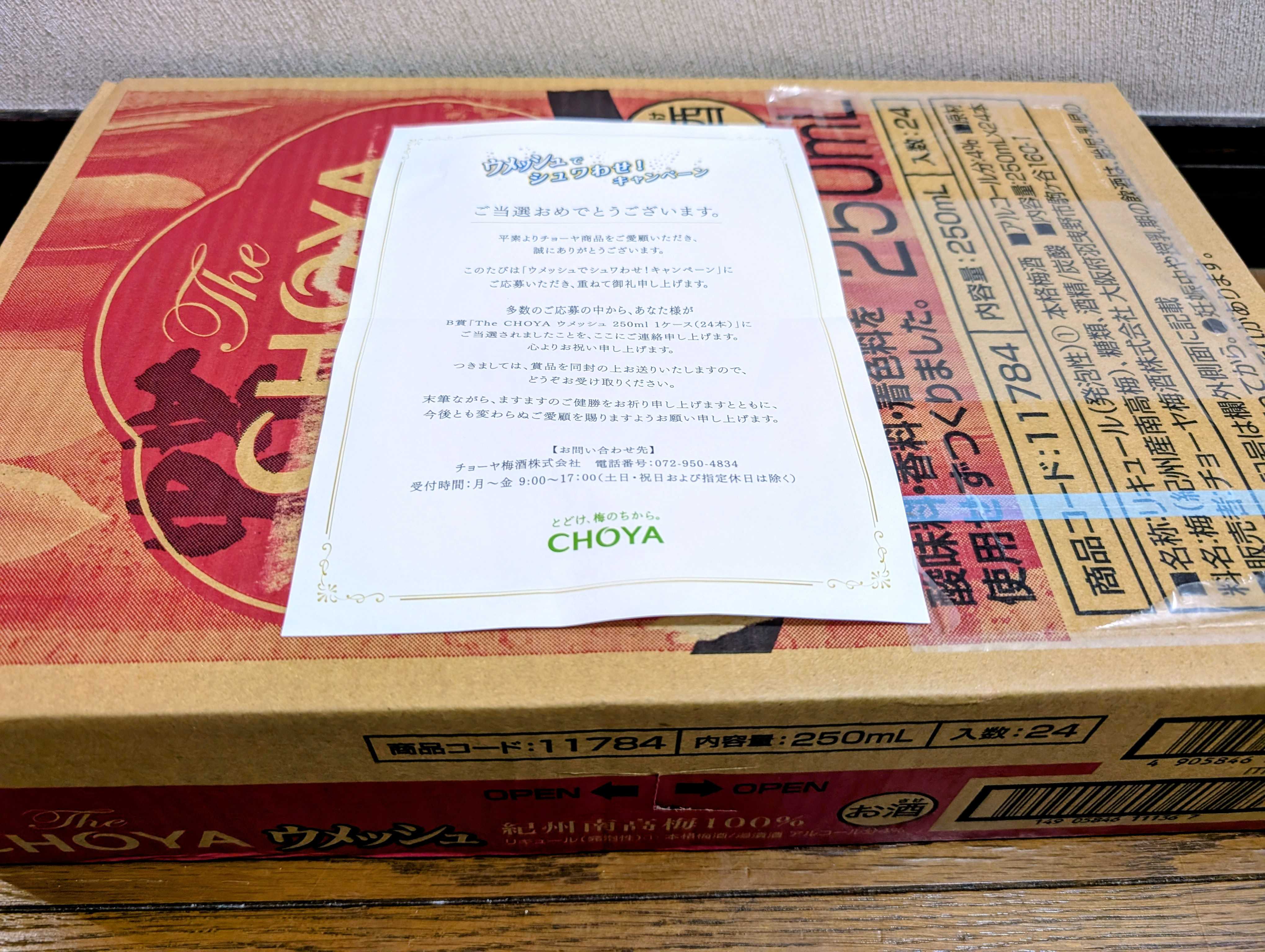第五章 「扇情的レヴュー」
支那服と黒眼鏡の男に、小生が案内されたのは、
廃虚かとみまごうレトロなビルヂングの一室であった。
そこは、ロビィか何かのような広間で、
白い漆喰壁に囲まれた部屋であった。
小生は古風なソファに腰を下ろすようにすすめられた。
「ヘイ、旦那。あっしの役割はここまでで。
そのままお待ちになれば、今に、うんと面白い見せ物がはじまりますぜ。」
にたりにたりと、気色の悪い笑みを浮かべながら口上を述べると、
支那服の黒眼鏡は、部屋を出て行ってしまった。取り残されたのは、
小生ひとり。
部屋中に舞う埃に、たったひとつある高窓から、チリチリ差し込むネオンの
灯りが反射して、部屋の中を赤色に、青色に、紫色に染め変えていた。
どのくらい時間がたったのだろうか。
どこからともなく、甘ったるい香りのする煙りがただよいはじめていた。
うつらうつらと、なんとも心酔いする香りである。
シタールというのだろうか、印度の楽士が奏でる、リズムのない音楽も聞こえはじめる。
一条の光り。
スポットライトを浴びて、この場所には不似合いな道化師が、
極彩色の手風琴を押しながら登場した。薄い紫の煙りの向こう。
これは、うつつの風景ではない。蜃気楼のような幻の風景なのだ。
道化師は、例のフリーズした笑顔のまま、うやうやしく手風琴の
ふたを開けると、中から、ひとつの黒い塊を引立てた。
黒い塊。
なんと魅力的な塊であったろうか。
小生の心の奥底に仕舞いこんだ、悪魔の心を呼び起こす、扇情的な塊。
それは、黒いエナメルの、肌にぴったり吸い付く衣装を着せられた女体だったのだ。
豊満な乳房も、くびれた細い腰も、放物線のようなカーヴを描く尻も、
あますことなく、そのラインを際立たせた塊だったのだ。
それは、道化師に髪の毛をつかまれ、苦し気に立っていた。
顔は秘密めいたアイマスクと西洋猿ぐつわに覆われていて、
定かにはわからない。
ただひとつ、道化師につかまれた髪の毛、亜麻色がかったミディアムロングの髪の毛だけが、彼女の表情だった。
道化師は頭のてっぺんから響くような、不快な金属音のような声で、
口上を述べ始めた。
「ひきいだしましたるこの娘、何の罪とがもございません。
たったひとつ、どこかの誰かのような猟奇の好奇心を持ち合わしましたる故に、
かくも恥ずかしいめにあわねばならぬのでございます。
ご見物の皆様には、どうか最後までお楽しみいただけますよう、
伏して、御願い上げ奉ります。」
道化師は、黒い塊の両手を手錠でからめると、
天井から下がった鎖につないでしまった。
可哀想に、この娘は、背伸びした格好のまま、
最早、身を隠すこともできないのだ。
© Rakuten Group, Inc.