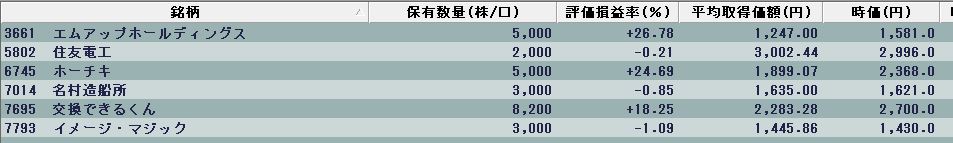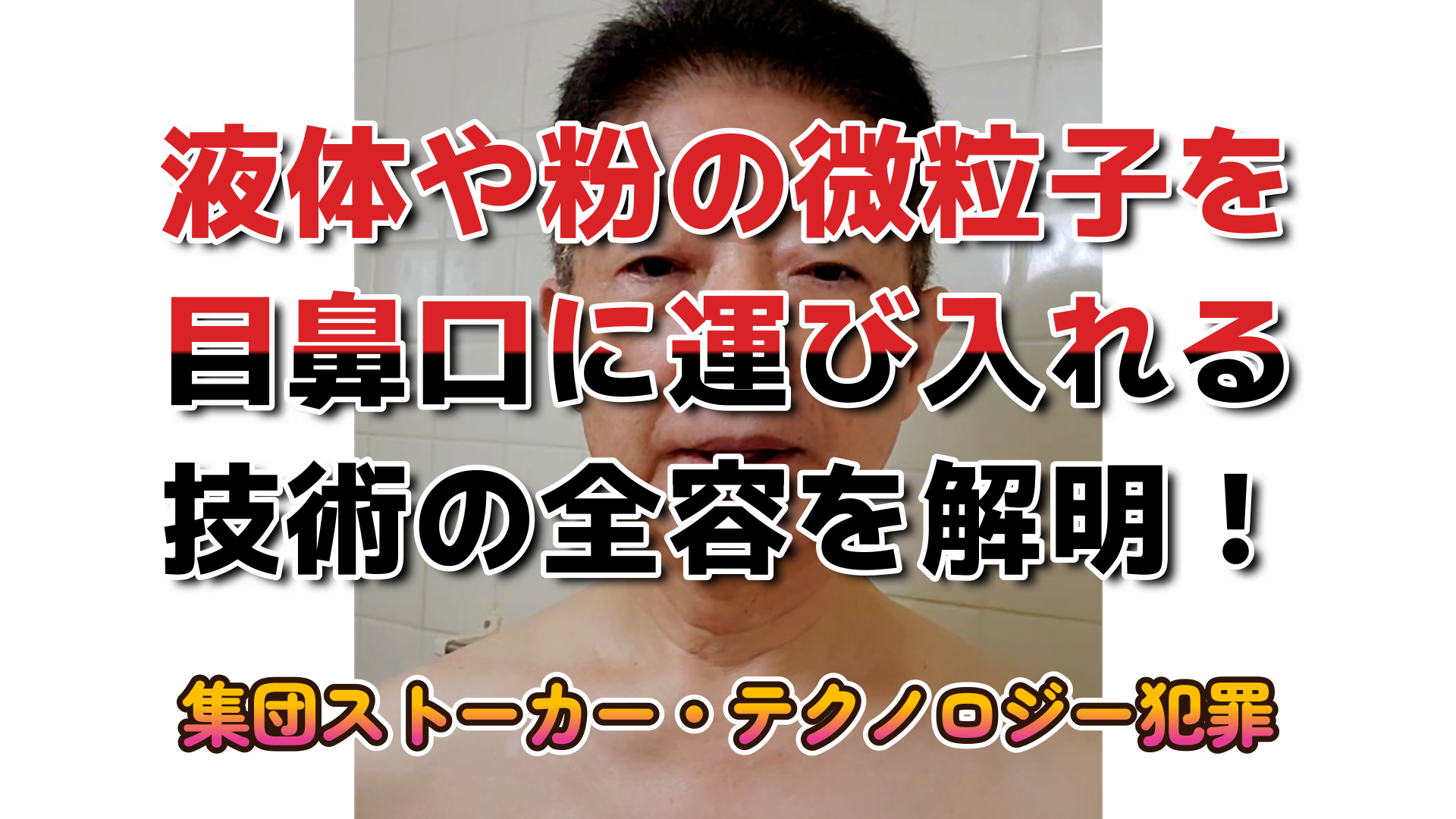[池田先生の学術講演] カテゴリの記事
全21件 (21件中 1-21件目)
1
-
人類の平和と幸福を実現する〝発想の母体〟に
人類の平和と幸福を実現する〝発想の母体〟に第4回入学式 1974年4月18日創造的生命の開花をきょうは講演というより、あいさつという内容で話をさせていただきます。海外訪問から戻ったばかりで、時差による体の変調もまだ残っていますし、そのため話にも飛躍があるかもしれません。また聞きづらい点があるかもしれませんが、ご了承ください。まず最初に、入学試験の難関を見事に突破して、晴れて合格の栄冠を勝ち取られた諸君に対し、私は心よりお祝い申し上げる次第であります。本当におめでとうございました。(拍手)ご承知のとおり「知識」や「学問」そのものには、善悪はありません。皆さんは、子の最高学府において余年間、優れた学問を研鑽した結果、社会へ出ていってからきわめて巧妙なる知能犯にもなれるし、秀でた有益なるインテリゲンチア(知識人)にもなれるのであります。いずれになるかは、皆さん方各人の自由意志の発動次第であります。ですから、この世年間、願わくは全員、良心に基づいた学究生活を送られんことを、切にお祈り申し上げるものであります。私はこの春、新善と文化交流を行うために、三月七日から四月十三日までの約四十日間、北米、中南米に行ってまいりました。創価大学の創立者として、いくつかの大学を訪問し根本的な転換を要求されている現代文明、教育の本質的なあり方について、さまざまに語りあいました。それについての二、三の提案も行い、講演もしてまいりましたので、最初にその報告を、簡単にさせていただきたいと思います。まず、最初に参りましたのは、カルフォルニア大学バークレー校であります。同校には十人のノーベル賞受賞の教授がおられますが、ここでは、ポウカー総長と懇談いたしました。次に音連れたニューオリンズ大学でもヒット総長と「教育国連」構想、さらにはその前段階として、世界の大学を結ぶ「世界大学総長会議」や学生連合である「学生自治会会議」を開催することを話しあい、意見の一致をみました。このことは、カルフォルニア大学ロサンゼルス校のミラー副総長との対話においてもテーマに上り、教育交流を中心にして寄与していくことを、強い共感をもって確認しあったしだいであります。また、同校(ロサンゼルス校)では、「二十一世紀への提言」(=『池田大作全集』第一巻所収)と題して、講演も行ってまいりました。このほか、中南米においてもパナマ国立のパナマ大学、ペルーのサンマルコス大学を訪問し、個々意見を交換しました。とくに、サンマルコス大学のゲバラ総長からは、同大学訪問に寄せてメッセージをいただきました。総腸から創価大学の皆さまにぜひともお伝えただきたいとのことでしたので、そのメッセージを学長にお渡しし、諸君への伝言といたします。(拍手)今回の訪米だけでなく、過日、香港においては中文大学を訪問し、同様に提案を行ってまいりました。昨年はヨーロッパの各大学も訪問しております。今後、いよいよ本格的に世界のさまざまな大学から教授や学生が数多く本学を訪れるであろうし、諸君がどんどん行かなければならないような時代が来るかもしれない。忙しくなると思いますが、またそこには、大きな張り合いがあることを、知っていただきたいと思います。私は、私の信念として、諸君のためには、いかなる苦労も惜しまず、新しき世界への道を開いてまいりたいと思っております。私が、世界の人々のなかを駆けめぐるその胸中には、つねに大切な、そして心より信頼する諸君の存在があることを知っていただきたいと思うのであります(拍手)。どうか、諸君は〝点〟と〝点〟とを〝線〟で結び、さらに、それを壮大な立体とした世界の平和像をつくりあげてほしいのであります。これは、私の諸君に対する遺言と思ってください。お願いします。(拍手)「教育国連」の発想は、国際政治による平和への努力が空転し、行き詰っている現代に在って、それを教育の力で真実の世界平和を勝ち取るための、最後の、そして確かな切り札であると、私は思っているのであります。そのために、「世界大学総長会議」も提案してきたし、学生諸君が平和へ立ちあがるために「学生自治会会議」の提案も行ってきたわけであります。これらは私一人ではとうていできないし、やがての時代、諸君たちがその実現に努力してほしいのであります。 学生こそ大学の主役 ともあれ、世界はますます、この〝発想の母体〟である創価大学に、注目してくるでありましょう。創価大学の諸君こそ、それにふさわしい世界的偉材と育っていかなければなりません。そして、人間と人間のスクラムによって、脈動しゆく世界交流、信頼関係への樹立へ向かって、いかなる波動をおこしていかなければならない、と私は諸君に期待をかけるものであります。私がサンマルコス大学を訪問したさい、総長との会談の席に同席した二十数人の教授の方々から、各人のモットーを贈られました。この教授の方々のすべては、ペルーにおいては第一級の矜持と承っております。その一つに「教授も学生も大衆とともに歩み、人類と幸福と平和と英知という目標に到達するまでは、一切の困難を乗り越えるべきである」という言葉がありました。現代知識人の悪しき習慣は、この〝困難〟をいつも避けているところにあります。私は避けない。民衆の真っただ中にあって、いかなる困難をも乗り越え、人類の崇高な目的に立ち向かっていく精神こそ、大学の存在理由であり、古くまた新しい大学の使命であると、私は生命の底から叫びたいと思いますけれども、諸君、どうでしょうか。(拍手)わが創価大学をはじめ、世界の各大学が、そしてすべての教師と学生が大衆とともにこの共同作業に取り組むならば、必ずや人類平和の目標は達せられるに違いありません。私が今回の大学訪問を通して、数々の提案をしてきた意義も、ここに帰されるのであり、本大学の学風建設の当事者たる諸君に、その英知事業を託したい気持ちでいっぱいであります。 若き創立者との自覚で昨年の第三回入学式の折、少しばかり大学の発祥について、歴史をさかのぼって考察を加えていきました。そのとき、大学というものが制度や建物からではなく、新しい知識と学問を求めようする若者の情熱と意欲から起こったものであることを、述べておきました。すなわち、真理をこよなく自らのものにしたいという若者の情熱がまずあって、それが学問的職業人、つまり教師を生み出し、そしてこの教師と学生との人間的共同体が、今日の大学の淵源となっていったのであります。つまり、もともと大学というというものは、学問を求め真理を愛する学生たちの熱性から始まったということなのであります。これこそ、大学の始原であると同時に、奇数であると、私は思うのであります。学生不在の大学となれば、もはや目的の手段化であり、大学の生命はない、と言いたい。残念なことに、今日の大学には、方向喪失と停滞がつきまとっています。ゆえに、今こそ、大学の原点に立ち返る必要があると考えます。そこで、本日、めでたく入学された諸君に、心の底から要望したいことは、諸君こそ私と同じく、若き大学の創立者であり、創造者であるという一点を、決して忘れないで欲しい、ということなのであります。在学中のみでなく、生涯、創価大学を皆の手で建設し、守っていただきたいというのが、私のお願いなのであります。(拍手)教授と学生の断絶の問題について、サンマルコス大学の副総長と話あったさい、副総長は、次の二点を述べておりました。その第一点は、対話が絶えず行わなければならないこと、第二点として、学生が責任をもって大学諸行事に参画できうる体制を講ずべきである、というのであります。私は、この対談で、苦難のなかにも新しい大学の方向を真剣になって模索しているところは、学生をいかにして大学の主役にするかという点に、新たなる、また時代の流れとして、問題の解決を見いだそうとしている、と感じとったのであります。そこで私は、諸君たちは大学から与えられるのを待っている、という姿勢ではなく、能動的に、かつ情熱的に〝これこそ、大学の新しい希望の灯である〟といえる、誇りに満ちた勇気ある建設作業に、取り組んでもらいたいと思うのであります。とくに対話という問題でありますが、価値ある対話というものは、それぞれの責任感と、信頼感から生まれるものであって、無責任な討論ではないのであります。すなわち、自分たちの大学であるとの強い自覚に基づく責任と、創価大学を人類文化の跳躍台としていくのである、という目的観に結ばれた相互の信頼関係が、必ずや実りある対話をもたらすことでありましょう。そして、本大学に見事な人間共同体を創出していっていただきたいことを、私は強くお願いするものであります。これに関連して、私立大学の特質についてふれておきたい。言うまでもなく、私立大学の存在意義というものは、国家権力からの制約を受けることなく、自主的に見学の信念を貫きとおすところにあります。こうした大学の教育にあっては、広く人類の未来に思いを馳せ、世界的視野に立って有為な人材を、自由に伸び伸びと育成することができるわけであります。狭い国家意識や、民族意識のワクにとらわれることなく、世界のひのき舞台に雄飛すべきスケールの大きな視野の青年たちを、荒れ狂う社会の変革のために送り出すところに、私立大学の特色の一つを、見いだしたいのであります。 学問と文化の精華を守る砦次に、あらゆる大学の使命の一つである学問の研究の場にあっても、私立大学には学閥的閉鎖性の陰りがない。自由な、それでいて活力に満ちた気風がみなぎっていなければならない、と思います。思想の自由、発表の自由、といった学問研究における絶対条件を満たしうるもの、私立大学に課せられた特色である、と私は考えます。このような、みずからの信条に基づいて築きあげた学問の場こそ、独創的な研究成果を生み、個性豊かな研究者を育てていく母体となり、土壌となるにちがいない。また、泡沫のような時流にとらわれることなく、長大な展望に立っての息の長い研究に取り組めるのも、私立大学に課せられた役割であります。私が私立大学のもちうる特色として挙げた教育の研究の在り方こそが、人類歴史の流転の中で産声を上げた、大学という制度のもともとの目標であり、使命であった。これに対して、国立、公立の大学にも種々の長所があり、特色があることも認めなければなりませんが、国立、公立の大学は、なんといっても国家からの要請、制約を無視できないという条件を背負っております。私立大学には、一国家、一民族の要請を受け入れつつも、さらに遠大な視野に立っての教育と研究を、自由に行いうるという最大の長所が備わっている。また、国家権力のあくどい介入に対抗して、真実の学問と文化の精華を守りぬく砦は、私立大学にこそ見いだしうると、考えたいのであります。現在、我が国の習性は、明治以来の流れとして、国立、公立の大学に、青年たちの教育と文化交流の源泉を求めがちであります。いわば、国立、公立の大学を主流とみなしてきたのが、教育者をはじめとする多くの人々の固定観念でもありました。しかし、私は日本と世界の将来を思うにつけても、大学精神を人類社会の中に生き生きと通わせるには、私立大学こそが主流となるべきではないかと、主張しておきたいのであります。諸君、どうでありましょうか。(拍手)私立大学に学び、その自由闊達な精神を骨髄にきざみこみ、毒性的な知恵を培った俊逸たちが、海を越え、大地を踏みしめて、この地球上のあらゆる民衆の真っただ中に入りゆくとき、初めて人間と人間、民族と民族、庶民と庶民の生命交流が可能となり、異なった文化の見事なゆうごと昇華が成し遂げられるものと、確信するからであります。陸続と続く友の輪の広がりから、民衆と民衆をつなぐ強固な交流の懸け橋が築かれ、新たなる地球文化、人類文化の胎動を告げる鼓動が、やがて人々の心を揺り動かすにいたるでありましょう。ともかく、諸君は、民衆間に架けられるべき平和と文化の橋をつくりあげる使節であり、建設者であり、担い手であります。同時に私は、未来の世界に響き渡る地球新文化誕生を告げる暁鐘を、諸君の手で、打ち鳴らしていってほしいのであります。そして、諸君の連打する暁鐘の音には、幾多の無名の人間庶民の切実な祈りにも似た願望が込められていることも、決して忘れないでいただきたい。 新たなる〝生〟を創り出す弛みなき錬磨を 「力」を使いこなす「知恵」を開発するところで最近、世界的に有名な社会学者の著した書に『力と知恵』(中岡哲郎・竹内成明訳、人文書院)という本があります。諸君のなかにもすでに読んで知っている方もあるかもしれませんが、その学者とはジョルジュ・フリードマンというフランス労働社会学の長老であります。この「力と知恵」の意味するものは〝力〟とは人間が技術の開発、発展によって得てきた環境支配の力であります。〝知恵〟とは、この〝力〟を使いこなし、人間の幸福のために価値判断していく英知を指しております。今、私はフリードマンの著書の内容を、諸君に説明するつもりはありません。ただ、この〝力〟と〝知恵〟という立て分け方雨を用いて、訴えおきたいことがある。それは、明治から戦前までの日本の教育、なかんずく大学教育の目標を振り返ってみるとき、あまりにも〝力〟に偏った至高性があったのではないかということであります。知識を吸収し、技術を身につける、そして、〝力〟の面で一日も早く世界的レベルに追いつかなければならない。これが、日本の教育が追求してきた最大の課題であったと思うのであります。もちろん、その背景には、長い鎖国によって、科学技術の分野において欧米諸国から立ち遅れていたこと、もし一日も早く〝力〟をつけなければ、欧米の諸国によって植民地化され、蹂躙される恐れがあったことは否定できません。そして、この所謂富国強兵政策によって、事実、ほかのアジア諸国が次々と自由と独立を奪われていったなかにあって、日本は独立を維持することができたのであります。しかしながら、こうした〝力〟を崇拝し、富国強兵を追求し続けた結果が、日本が未曽有の敗戦という事態におとしいれたことも、歴史の尊い教訓の一つとして、とくに諸君たちは胸に刻んでいていただきたい。また〝力〟の追求のための道具とされた教育が、本来、教育の生命である。ここの人間の尊重、人間の尊厳の樹立という一点を失って、国家や企業にとって価値ある人間、すなわち国家、企業という組織のなかの歯車のような部品に甘んずる人間をつくりだしてきた。教育がその手段となってきたということも、忘れてはならない重大な問題であります。〝力〟の追求も大事だが、それは同時に〝力〟を使いこなせるだけの〝知恵〟の開発をともなわなければなりません。〝知恵〟とは、人間主体に根ざしたものであり、ソクラテスがいみじくも喝破したごとく「汝自身を知る」ことから発するのであります。ここにこそ、人間を機械の部品に堕落させない、人間を他のいかなるものとも交換しえないものとする、尊厳性樹立の起点があるわけであります。真実の学問とは、戦ずるところ、この自己への〝知〟にある。創価大学が目指す学問、教育の理想も、ここにあるといってよい。〝力〟への学問においては、優れた大学や研究機関が世界に数えきれないほどあるでありましょう。だが、それらは人間に何をもたらしたか。それは、惨たんたる現代文明の虚像ではなかったかとも、見えるのであります。諸君の使命は、あらゆる〝力〟を人間の幸福と平和のために使いこなす〝知恵〟を、身につけることにあると言いたいのであります。それは「汝自身」を知り、それに結びついた形で、学問を究めることであります。それが自分に、すなわち人間にとってどういう関係にあるか――すべてをここに引きもどして知恵、技術、芸術の再編成をするとともに、新たな人類の蘇生を、もたらしていただきたいのであります。その着実な作業の積み重ねの中に、人類文化の偉大なるルネサンスがあることを確信し、諸君の成長を、心より祈ってやまないものであります。フランスの著名な文化人であり、歴史家であるルネ・ユイグ氏も、過日東京大学での講演で、次のように述べられていります。このユイグ博士とは、あす夕刻、お会いする予定になっておりますが(=後に両者は対談集『闇は暁を求めて』〈『池田大作全集』第5巻収録〉を出版)、その講演「自然と芸術における形態と力」というテーマの中で一部を要約しますと、「現在の危機は文明の危機である。人間の文化の欠点は、それがそれぞれの分野に分けられてしまい、全体というものを見失っている。私は人類の文かは唯一不可分のものと考える。また、知識人は自己の力と知識のすべてを挙げて、文明のために尽くさなければいけないと考える。今日の危機は社会的危機、政治的危機よりも根本的な文明の危機というべきものである」という意味の警告の論調を展開しておられました。ここで、二十一世紀にはばたきゆく諸君に、私の友愛の情を込めつつ、若干、付言しておきたい。私は同じく昨年、本大学において、〝創造的人間を目指すように〟ということを、要望してまいりました。そのことに関連して「創造的生命」という点に、言及したいのであります。私は何も、むずかしい哲学の解説をするつもりはありません。そしてまた、一般的定義つけをしようという考えも、毛頭ありません。ただ私は、諸君に、この長い尊い人生にあって、敗北の陰のある、暗い人生の旅行者になってもらいたくないのであります。私自身の体験のうえから、〝諸君の前途に栄光あれ〟と願いつつ、一つの示唆として、お話するわけであります。 逆境への挑戦の中に「人間革命」が私の胸に触れてやまぬ〝創造〟という言葉の実感とは、自己の全存在をかけて、悔いなき仕事を続けたときの自己拡大の生命の勝どきであり、汗と涙の結晶作業以外のなにものでもありません。〝創造的生命〟とは、そうした人生行動のたゆみなき錬磨の中に浮かび上がる、生命のダイナミズムであろうかと、思うのであります。そこには嵐もあろう、雨も強かろう、一時的な敗北の姿があるかもしれません。しかし〝創造的生命〟は、それで敗北し去ることは決してない。やがて己の胸中にかかるであろう、さわやかな虹を知っているからであります。甘えや安逸には創造はありえません。愚痴や逃避は脆弱な一念の反映であり、生命本然の創造の方向を腐食させてしまうだけであります。創造の戦いを断念した生命の落ちゆく先は、万物の〝生〟を破壊し尽くす奈落の底にほけなりません。諸君は、断じて新たなる〝生〟を建設する行為を、一瞬たりともとどめてはならない。創造はきしむような重い生命の扉を開く、もっとも峻烈なる戦いそのものであり、最も至難な作業であるかもしれません。極言すれば、宇宙の神秘な扉を開くよりも「汝自身の生命の門戸」を開くことの方が、より困難な作業、活動であります。しかし、そこに人間としての証があります。否、生あるものとしての真実の生きがいがあり、生き方があります。〝生〟を創造する歓喜を知らぬ人生ほどさびしく、はかないものはありません。生物学的に直立し、理性と知性を発現えたことのみが、人間であることのゆえんであると思いますけれども、諸君、どうでありましょうか。(拍手)あらたなる〝生〟を創りだす激闘のなかにこそ、初めて理性を導く輝ける英知も、宇宙まで貫きとおす直観智の光も、襲い来る邪悪に挑戦する強靭な正義と意志力も、悩める者の痛みを引き受ける限りない心情も、そして宇宙本源の生命から湧き出す慈愛のエネルギーと融和して、人々の生命の歓喜のリズムに染めなしつつ、脈打ってやまないものがあるからです。逆境への挑戦をとおして開かれた、ありとあらゆる生命の宝を磨きぬくにつれて、人間は初めて真の人間至高の道を歩みぬくことができると、私は確信するのであります。ゆえに、現代から未来にかけて〝創造的生命〟の持ち主こそが、歴史の流れの先端に立つことは疑いない、と私は思います。この〝創造的生命〟の開花を、私はヒューマン・レボリューション、すなわち「人間革命」と呼びたい。これこそ諸君の今日の、そして生涯かけての課題なのであります。最期に私は、十九世紀後半のフランスの作家であり、詩人であるペギー(一八七四年―一九一四年)が「教育の危機は教育の危機ならず。そは生命の危機なり」(『半月手帖』平野威馬雄訳、昭森社)と叫んだ言葉を思いおこすのであります。現代の危機は、まさに学問、教育の内部まで入り込んでいるところに、その深刻さがあるといってよいでしょう。ゆえにまた、このことは教育こそ未来への突破口があることを物語るものであります。創価大学に私がかけているところのものも、そのためであります。それでは諸君、どうか楽しく有意義な四年間でありますよう――。そして教授の諸先生方、本年入学された〝未来の宝〟をよろしく、と心よりお願い申し上げて、私の話を終わらせていただきます。 【池田先生の創価大学での講演に学ぶ】創価新報2022.12.21
April 8, 2024
コメント(0)
-
スコラ哲学と現代文明
第2回滝山祭1973年7月13日スコラ哲学と現代文明 新しく時代を創造しゆく萌芽がここに!このところ、大学が近くなったのか、私は先月の十三日にもおじゃまし、ヨーロッパの旅の報告などをいたしました。今日の十三日は、第二回滝山祭ということで、ご招待に喜んでまいったわけであります。本当におめでとうございます。(大拍手)皆さんの元気な顔を拝見するだけで、私は充分なわけでありますが、それでは、あまりにも味もそっけもないことになりますので、また、平素考えてきたことを、お話いたします。なお、本日は、諸君の学園の弟、妹達がたくさんみえております。兄さん姉さんとしてよく交流し、あたたかく見守ってあげていただきたい。(拍手)四月九日の入学式の折、少しばかり大学というものの発祥についてお話いたしましたが、その中で、近代文明をもたらしたルネッサンスの精神に触れました。そして、そのルネサンスの驚異的な開花も、突然変異によって生まれたものではなく、それ以前の長い期間、人々の目立たぬ絶え間ない工場的努力と、時代の潮の必然性とのうえに生まれたものであること、また、その萌芽をたどっていけば〝暗黒時代〟と言われている中世の冬の季節に、すでに始まっていたことをお話いたしました。今、この大学の周辺の木々は青葉に輝いておりますが、青葉の発芽は春になって急に始まったのではない。すでに、厳寒の冬のさなかに、その準備を着々と整えていたのであります。人生もまた同じであります。今、この大学の草創期にあたって、現在、私たち一人一人が日々行っているところの、目立たない様々な努力も、あるいは多くの試行錯誤も、やがては華やかに大きく開花するであろう、未来の世界文明の発芽の準備をせっせとしているのだという確信を、私は疑いたくないのであります。今日の話も、この発芽を確認する意味において、およそ時代には縁のないと思われているスコラ哲学にわざわざ光を当て、スコラ哲学の中にすら、時代の文明を促した強靭な発芽があったことを、明らかにしたいと思うのであります。誠に、歴史の生々流転してきたところの実相を、しかととらえることは、未来の歴史を開くカギになるからであります。 大学をつくるのは「人」であり「理念」 時代の谷間に生まれた思想言うまでもなく、スコラ哲学とは、十二世紀から十四世紀を頂点として栄えた、中世ヨーロッパの哲学の総称であります。スコラとは当時の教会、修道院に付属する学校を言い、今日、学校を意味する「スクール(School)」という語の淵源であることは、周知の事実であります。スコラ哲学は、一般に、「神学の婢」と言われ、キリスト教神学を権威たらしめるために存在した、いわゆる〝御用哲学〟にすぎないと考えられてきた。たしかに、スコラ学者の名でよばれる当時の哲学者、思想家のなそうとしたことは、聖書の教える信仰を、いかに正当化するかということであった。これは疑い余地はない。その意味において、このスコラ哲学を含めて、中世ヨーロッパ哲学は、輝かしい古代ギリシャ、ローマの巨峰と、同じく栄光に満ちた近世ルネサンスの連峰との間に挟まれた暗黒の谷間にあるといった見方がされてきたのであります。近代の合理主義思想家達によって強調されたこの評価は、果たして正しいと言えるかどうか、近代、合理主義の行き詰まりから、新しい時代に入ろうとしている時代からみたとき、スコラ哲学は、どのように評価されるべきか――これが、私の論じたい主題であります。まず、それには、スコラ哲学と言われるものが、いかなる時代状況と、社会的状況のもとで生まれ、発展したかを考えなければならない。ヨーロッパの哲学史上、中世哲学は大きく二つの段階に分けることができる。一つは、キリスト教の発生した一世紀から八、九世紀に至る時代であり、この時代の哲学を「教父哲学」と呼んでおります。教父とは、キリスト教の教会に属して、教会の公認した教義に基づいて著作した人々のことであります。この時代は、キリスト教はローマ帝国の全体に広がり、更に、ローマ帝国の崩壊後、歴史の舞台に登場してきたゲルマン諸属の政界にも浸透していった、いわば不況時代にあたっております。この布教の中核であった教父達が、まずしなければならなかった任務は、キリスト教の教義を体系化することであり、ローマ人、あるいはゲルマン人社会の伝統的思考法の中に、いかに適合せしむるかであった。従って、この段階で何よりも強調されていることは、一貫して〝信仰〟の確立であったということができましょう。いわゆる教父哲学の代表者として、ユスティヌス、テルトゥリアヌス、オリゲネス、テルトゥリアヌス、オリゲネス、そして、その総合的な思想家として有名なアウグスティヌスの名が挙げられます。テルトゥリアヌスの思想を要約した言葉として有名な「不合理なるが故にわれ信ず」は、信仰を絶対化したものとして、この教父哲学の一つの結晶と考えます。更に、アウグスティヌスは、『神の国』という本を著して、〝地の国〟の代表というべきローマの崩壊後も、〝神の国〟のこの世における顕現である教会は、永久に続いていくと教え、カトリシズムの教会支配体制に理念的基盤を打ち立てたのであります。この教父哲学の時代が終わり――ということは、ヨーロッパ全土のキリスト教化が安定して――次の九世紀から、十四世紀ルネサンスに至るまでの時代が、スコラ哲学の時代であります。その発祥の契機は、さまざまな角度から分析しなければなりませんが、カール大帝、つまり、シャルマーニュ帝によるゲルマン社会の統一と、イスラム勢力の撤退、そして今日カロリング朝ルネサンスと呼ばれる学芸興隆が、大きい要素として考えられる。先に述べたスコラ、すなわち教会や修道院に設けられた学校の起源は、このカール大帝の奨励によるものであります。さて、一応、布教、発展の時期を過ぎて安定の段階に入ると、学芸興隆の気運とあいまって、教育の真価と形式的整備が要請されるようになった。基本的な協議についてはアウグスティヌスなどによって既に完成されているので、問題は、その教義をいかに証明し、相互に秩序付け、体系化するからであったわけである。中世ヨーロッパが、ギリシャ、ローマから引き継いだ学問的遺産として、文法、修辞法、弁証法、算術、幾何、天文学、音楽の七学課があったが、これらは、自由学課と呼ばれ、これを神学とを、どのように関連づけるかが問題となってきたわけであります。特に、イスラム社会との接触を通じて、アリストテレス哲学は大きい影響を及ぼすようになり、単に個別科学のみならず、人間と理性と聖書の啓示の関係、知識と信仰、哲学と神学という、根本問題に触れざるを得なくなってきたわけであります。 信仰と理性の関係性を探求スコラ哲学を代表する人々としては、旧跡のスコトゥス・エルウゲナ、十一世紀のアンセルムス、アベルトゥス・マグヌス、十二世紀まつから十三世紀に入って、アルベルトゥス・マグヌス、トマス・アクィナス、ド ゥンス・コストゥスと続き、末期においては、近代自然哲学の先駆者ともいわれるロジャー・ベーコンが出ている。いま私は、時間がありませんし、この四世紀の間にわたる思想の歴史を一つ一つたどるつもりはありません。ただ、そこに含まれる基本的な問題のいくつかを抽出し、現代の視点から、そこに考察を加え、概略の流れのみを見ていきたいと思うのであります。最初のエルウゲナは、アイルランドで生まれ、パリで活躍し、「スコラ哲学の第一の父」とも「スコラ哲学のカール大帝」とも称された人であります。スコラ哲学のカール大帝と言われたゆえんは、政治の面では、カール大帝によってヨーロッパ中世世界の基礎が樹立されたように、哲学のうえでは、このエリウゲナによってヨーロッパ中世哲学、すなわちスコラ哲学の基盤が打ち立てられたであります。その基盤とは――「新の宗教とは真の哲学でもあり、またその逆も真である」。したがって「宗教に対するあらゆる懐疑は同時に哲学によって反芻される」――という命題であります。宗教と哲学、信仰と理性の一致を確認し、それを証明しようという、スコラ哲学の基本的課題が、彼の思考に明確にあらわれているのであります。(シュテーリヒ『世界の思想史』上、草薙正夫・提彪・長井和雄・山田潤二・工藤喜作・神川正彦・草薙茅雅子訳、白水社)初めにも述べたように、スコラ哲学はその出発点からして、キリスト教信仰を知識、理性によって裏付けの制約を強く負っていたことを、認めざるを得ません。そして、それは「知らんがためにわれ信ず」(同前)といった、次のアンセルムスにおいても、また、トマス・アクィナスにおいても、ドゥンス・コストゥスにおいても、およそスコラ哲学者と言われる人々においては、信仰の絶対性は共通の大前提だったのであります。ただし、時代の変化とともに、そこには微妙なニュアンスの移り変わりが確かめられる。例えば、トマス・アクィナスは〝理性によって把握される範囲では、神学と一致するはずである。しかし、信仰の内容が全て理性によって認識できるとはいえない。ゆえに、理性の及ばぬところでは、ただ信仰によって真理を把握する以外にない〟と言っている。ここに、信仰と理性の一致を信じ、これを実証しようとして出発したスコラ哲学が、その当初の目標から微妙に揺らいでいることを知るのであります。つまり、キリスト教へのかすかな会議の一歩と、一面では言えないことはありません。更に、ドゥンス・コストゥスにいたると、〝神の意志は何ものにも拘束されず、自由である。それは理性以上のものであるから、理性によって認識し、基礎づけることはできない。神学は合理的なものである〟と言い、ついに知識、理性と信仰との分離となっていくのである。この過程は、スコラ哲学者達にとっては、何ら信仰の動揺をもたらすものではなかったが、理性に対して、信仰や神学の教義に縛られない独自の立場を与えることにはなった。この独立の位置を与えられた理性によって、やがて近世の哲学が発展し、学問の花が咲き、その学問の成果によって教会の競技は、次々とその矛盾を暴露し揺らいでいくのであります。その意味で近世、近代の萌芽は実にスコラ哲学の中に、徐々にその姿を現しはじめていたということができるのでありましょう。 独自の文化を築いた中世ヨーロッパこのように、スコラ哲学は、たんなる神学の婢、中世暗黒時代の象徴などではなく、近世、近代の出発点としてとらえ直しわけでありますが、さらに深く考えると、それ自体においても、一つの文化の大きく輝いた栄光の時代であったと、みなければならない。はじめにも述べたように、ヨーロッパの中世を、古代と近代の中間にはさまれた〝暗黒〟の時代とする考え方は、近代合理主義思想家の言ったことである。だが、本当はそうではなく、中世文化は中世文化として、古代や近代のそれに劣らない。独自の文化を現出したものであり、むしろ近世、近代に通ずる萌芽を、私はそこに見るのであります。そして、もし、この考え方に力点をおくならば、現代文明は、中世キリスト教文明が凋落して果てようとする、末期的な混乱と、人間性喪失の時代であるということにもなるのではないかと思うのであります。本来の意味から、暗黒時代というならば、ヨーロッパにおいては、ローマ帝国の没落期から九世紀あるいは十世紀に至る時代が、まさに暗黒時代であります。ゲルマン諸族の大移動が行われ、社会の法と秩序は崩壊し、交易は絶えた。そして、たえず略奪や殺戮に怯えなければならなかった時代――それは、暗黒時代としかいいようのない時代だったでありましょう。しかし、九世紀から十世紀に至って、人々は生産にいそしみ、その中から新しい文化創造の気運が高まり始めてきた。こうして迎えたのが、スコラ哲学の時代なのであります。今日もなお、ヨーロッパの諸都市の象徴としてそびえている由緒ある教会、寺院のほとんどは、このスコラ哲学の時代に建設、あるいは着工されている。パリのノートル・ダム寺院、シャルトルの寺院、さらに、ドイツではケルンの大寺院等々のゴシック建築は、権力によるのでなく、いわゆるその時代の信仰の結集によって中世社会の持っていた技術と富をもって建てられた。中世ヨーロッパ文明の一大記念碑ということができるのであります。しかも、これらが今日もなお、ヨーロッパの都市を象徴し、ヨーロッパ文明を象徴し続けている。例えば、パリを例にとってきた場合、ノートル・ダム寺院に負けない建造物は、ルーブル宮(現在は美術館)にせよ、凱旋門にせよ、エッフェル塔にせよ、いくらでも挙げられる。しかし、それらは王侯や特権者の栄華の残滓でしかなく、民衆全体の心に支えられた文化的結晶という観点からすると、ノートル・ダムには、はるかに及ばないと言わざるを得ません。このように、空高くそびえ立つゴシック建築が物質的に中世ヨーロッパ文化の興隆を象徴しているのに並んで、精神世界で中世の高まりを表しているのが、まさにスコラ哲学なのであります。学問の興隆は、パリをはじめ、ボローニャ、オックスフォード、ケンブリッジと、多くの学問の中心地を生み、そこに集う学生と教師とによって、大学が形成されていった。現代の大学は、いわばスコラ哲学の時代の遺産にほかならないともいえる。スコラ哲学が探求したもの――それは、とりもなおさず、これら八世紀の大学が教えたということになるが、もちろん、そこには、今日の学問的見地からすれば、幾多の稚拙さや誤りもあった。例えば、彼らにとっての知識とは、事実の観察によって得られたものではなく、プラトンやアリストテレスあるいはユークリッド等の古代哲学者によって書かれたものであった等である。そして、この知識を体系化し、神学の教えを証明し、組織化するために、煩瑣な論証を行い、それゆえに、スコラ哲学はハンさ哲学とアダ名されたことは、よく知られているとおりであります。しかし、そうした欠陥は欠陥として認めた上で、なおかつ、より基本的な次元で、スコラ哲学の果たした重要な役割に、我々は気づかなければならない。 人間の生き方に明確な指針を示すその一つは――それは、何よりも人間としての生き方に明確な指針を示したことである。一つの完結した世界観のもとに、人間がいかに生くべきかを、それなりに認識せしめたからである。スペインの哲学者オルテガ・イ・ガセットはその著である『大学の使命』という本で、この点について非常に興味深い論及をしている。「今日『一般教養』と呼んでいるものは、中世におけるそれとは異なっている。中世のそれは、決して精神の装飾品でも、品性の訓練でもなかった。そうではなくて、当時の人間が所有したところの、世界と人類に関する諸理念の体系であった。従ってそれは、彼らの生存を実際に導くところの確信のレパートリーであった」――そして「今日なお現存している残留物は、当時の高等教育を、全面的かつ本来的に構成していたものの、あわれな生き残りなのだ」(井上正訳、桂書房)と。これは、大学教育における一般教養課程について述べた一節ですが、単に大学での強化というのみにとどまらず、人間一般として持つべき教養の根本問題に触れた、刮目すべき発言であると、私は思うのであります。今日いわれる教養は、極めて内容が漠然としており、オルテガの言うごとく「精神の装飾品」となり、あるいは、せいぜい「品性の訓練」ぐらいにしか考えられていない現状であります。だが、真の意味の教養とは、そのような、表面を繕うために苦労しなければならないようなものではない。現実の人生を生きるため、内面から、自らを導く「世界と人類(=あるいは人間の存在)に関する諸理念の体系」なのであります。更に、オルテガの言葉を引いてみたい。「生は混沌であり、密林であり、墳丘である。人間はその中で迷う。しかし人間の精神は、この難儀、喪失の思いに対抗して、密林の中に『通路』を、『道』を見出そうと努力する。すなわち、宇宙に関する明瞭にして確固たる理念を、事物と世界の本質に関する積極的な確信を見出そうと努力する。その諸理念の総体、ないし体系こそが、言葉の真の意味における教養〔文化〕la culturaである。だからそれは装飾品とは全く反対のものである。教養とは、生の難破を防ぐもの、無意味に悲劇に陥ることなく、過度に品格を落とすことなく、生きていくようにさせるところのものである」(同前)こうした教養、文化の源泉となったのが、中世においては、スコラ哲学であったと言えましょう。私は、先に、スコラ哲学の意義を、日膣は近世、近代の学問的発展のための準備を整える役目をしたと申し上げた。しかし、それだけでなく、スコラ哲学自体が、中世という一つの文明の頂点を示すものであったと述べたのは、このためにほかならない。なぜなら、一つの文化の役目は、それが次の時代の文明のために、どのように貢献していくかということだけでなく――もちろん、それも大事な役目の一つではありますが、それ以上に大事なことは、その時代の人間のため、人間的向上のために、いかに役立ったかということにあると信ずるからであります。もとより、スコラ哲学が、意図的にこうした人間性の確立とか、向上という問題を目指したわけではありません。最初に述べたように、本来は、信仰の理性によって裏打ちすることで、神学のもとに諸学問を統合すること、それによって、キリスト教信仰と教会の教義を権威あらしめようとしたものであった。だが、それが結果的に、へプライズムとヘレニズムとの融合という、ヨーロッパが古代世界から別々に受け継いだ遺産を統合し、自らの内に肉化して、真実のヨーロッパ、またヨーロッパ的人間像の形成をもたらすに至ったのであります。 人間復興の哲学と教養を樹立 次代を建設する宗教の確立が肝要次にもう一面、文明史的にこれをみると、スコラ哲学の果たしたもう一つの役割は、〝地中海文明〟の時代から〝ヨーロッパ文明〟の時代への移行に、決定的なエポックを隠したということである。もちろん、そのための政治的、経済的、社会的な条件は、それ以前から、着々と整えられていました。しかるに、文明のもっとも確信ともいうべき精神的、知的側面で、ヨーロッパが、地中海文明への依存から哲学においてであったといえるのであります。キリスト教は、その発祥以来、八世紀あるいは九世紀に至るまで、古代世界の地中海周辺を、その主たる舞台としていた。いわゆる原始キリスト教、初期キリスト教時代の中心地は、今のエジプトのアレクサンドリアであり、トルコのカパドシア、イタリアのローマ島であった。この時代の最大の教父と言われる、前にも述べたアウグスティヌスは、北アフリカのヌミディアで生まれ、現在のアルジェリアにあたるヒッポという地で活動したのであります。この地中海文明に終止符を打ったのが、七世紀から八世紀にかけてのイスラム圏の拡大でありました。これによって、地中海の制海権はイスラム教徒に奪われ、キリスト教はヨーロッパ内陸部に閉じこもることになる。そしてやがて、カール大帝の出現によってゲルマン世界の統一が行われていったのであります。その後、この統一は政治的に分裂したものの、文化的には、一つのヨーロッパを思考して統合化が進んでいったのであります。このヨーロッパ文明が、ルネサンス、宗教改革、ナショナリズムの勃興等々、幾多の変遷を重ねつつも、発展と世界的伝播を成し遂げ、いわゆる現代文明となってきたといってよい。その実質的感性が、十二世紀から十四世紀のスコラ哲学の時代に当たるのであり、スコラ哲学は精神的内容において、現代に至るヨーロッパ文明の基本的原型であったとみることができる。そして、このスコラ哲学の中心合ったおありやオックスフォード、ケンブリッジ島の諸大額が、現在もなお、世界の学問の源泉地として尊男材質つけていることは、このスコラ哲画に始まる精神の潮流が、今なお流れていることの象徴といえましょう。今日、このスコラ哲学の時代に始まった一連の文化発展の長い歴史は、肥大化し形骸化した醜い姿の中に、悲劇的な週末を迎えようとしております。人間性の喪失、公害に象徴される文明のゆがみは、もはや誰人の目にも明らかであり、文化的創造の源のはずであった大学もまた、深刻な崩壊の危機に直面している。学問の場としても、人間育成の場としても、伝統的な大学は、その指導的地位を失おうとしているといっても過言ではない。この終わろうとしている一つの時代から、次の新しい時代の開幕のためには、新しい大学が必要でありましょう。否、大学という〝形〟は副次的なものかもしれない。大事なのは、新しい哲学であり、現代の、いい意味でのスコラ哲学の興隆であります。真実の宗教を基盤とし、真実の信仰の核として、そこにあらゆる学問も、理性、感情、欲望、衝動等も統合し、正しく位置づけた、新しい人間復興の哲学が要請される。宇宙生命の中に人間の地位を明確にし、生の混沌の密林の中に生きるべき道を切り開く、真実の〝教養〟が打ち立てられねばならない。この哲学を探求し教養を実践する人間と人間の集いが、真の意味の大学を形成するのであります。大学をつくるものは、建物や施設ではなく、理念なのであります。混沌の人生に対処する、力ある真実の哲学を持った人々の集うところ――それこそ、時代を動かし、文明を創造する源泉地としての、真の意味の大学であると思いますが、諸君はどうでしょうか。(大拍手)今日、スコラ哲学の全くの風化は、その基盤とする宗教のまったくの無緑化によるものといえましょう。してみれば、現代ほど宗教を喪失してしまった時代もなく、それゆえに救済のない時代もない。――この現実のうえに私たちは生きつづけているのであります。このように認識するとき、最大の緊急時というべきものは、時代に耐え、現代を導くに足るだけの哲学樹立であり、その基盤をなす信の宗教の確率であります。未来を担う大学の誇りにかけても、その使命とする道は何であるか――その答は、皆さんの胸の中に既にあることを私はかたく信じて、今日の話を終わりたいと思います。(大拍手) 【池田先生の創価大学での講演に学ぶ】創価新報2022.11.16
March 11, 2024
コメント(0)
-
新たな歴史を開く人類の希望の塔に
新たな歴史を開く人類の希望の塔に第3回入学式1973年4月9日 創造的人間たれ創価大学に入学された皆さん、本当におめでとうございます。ともに、この二年間、創価大学の葬送の建設に全魂を打ち込んでくださった教授陣の先生方、職員の皆さま、そして学生の皆さん方、さらには、それをあたたかく見守り、育んでくださった父母ならびに関係者の方々、本当にご苦労さまでした。私は、創立者として、皆さまに心より御礼を申し上げる次第であります。言うまでもなく、創価大学は、皆さんの大学であります。同時に、それは、社会から隔離された象牙の塔ではなく、新しい歴史を開く、限りない未来性をはらんだ、人類の希望の塔でなくてはならない。ここに立脚して、人類のために、社会のために、無名の庶民の幸福のために、何をすべきか。何をすることができるのかという、この一点に対する施策、努力だけでは、永久に忘れてはならないということを、申し残させていただきます。そこできょうは、まず第一に、私は、大学というものが、社会にいかなる影響を与えるかを、歴史的に論じさせていただきます。といっても、難解な、抽象的な大学論を展開しようというのではない。私にはその資格もないし、また、その必要もないと思う。歴史にみられる若干の事例を挙げて、大学が、あるいは広く学問というものが、いかに歴史を動かし形成する潮流となってきたかを、探りたいのであります。ルネサンスでは、十四、五世紀ごろ、ヨーロッパに起こった文藝の大復興運動であることは、皆さんもよくご存じのとおりであります。絵画、彫刻等々の芸術、あるいは文学の分野において、それまで眠っていた人間主義すなわちヒューマニズムという魂を吹き込み、人間謳歌の生き生きとした作品が、次々に世に出たわけであります。これをもって、ヨーロッパは、新しい時代の夜明けを迎えるにいたったといっても過言ではない。この瑠奈さん鋤の作品の数々を見るとき、人間の歓喜というべきものの結晶を感じるのは、決して私一人ではないと思う。このように、ルネサンスは、ヨーロッパ文明の大きなエポック(画期的な時代)であったことは確かであります。しかし、このルネサンスは、どうしておこったのか。たんに、文学、芸術の広場で、偶然におこった変革であったとは考えられない。その前段階として、より深い地盤からの胎動が、それよりもいち早くおこっていたことに気づくべきであります。それは、学問の大復興であります。この学問における大復興は、中世から始まっております。いわゆる芸術の大復興運動としてのルネサンスほどには知られてはおりませんけれども、重要さにおいては、それと匹敵するものをもっており、心ある歴史家たちは、この学問におけるルネサンスを「十二世紀のルネサンス」と呼んであります。大学が発生したのは、じつに、この十二世紀におけるルネサンスにおいてであります。中世初期においては、人間が習得すべき知識の内容は、ラテン語の文法、修辞学、論理学、および算術、天文、幾何、音楽の七自由学に限定されており、それは、聖書を読み、神の自然法を理解することと、王権維持のために、慣習法を運用するために必要とされたものでありました。算術や天文は、教会歴を計算するためのものであり、音楽もまた、教会の祭礼に必要なものとして、学んだわけであります。その他は政治上、慣習法を実務上運営するために学ばれたものもあります。これが、当時の最高教育でした。 社会に新風を送る使命担う 大学とは知的財産の集積所そこへ、スペイン、イタリア等を舞台に、イスラム世界から、教学、哲学、地理、法学などの新しい知識がもたらされてきたのであります。これらには、古代ギリシャ、ローマにおいて既に解明されていたにもかかわらず、中世のヨーロッパでは隠されていたものであり、あるいはイスラム教徒やイタリアの商人たちが、インドなど東方世界から学んだものもあったようです。ともかく、学問における古代の遺産を獲得してから、強い、いかなるものもせきとめることができない勢いで、知識の吸収、蓄積、体系化が行われ始めたのであります。新しい知識を求めようとする若者が、当時あった修道院学校等の束縛を越えて、新たな学問の集積書を求め、それに応ずる学問的職業が生まれたわけであります。すなわち、それが教師であり、教師と学生の共同体が、パリとボローニャに最初に形成されました。それが本格的な大学の出現であります。大学を意味するユニヴァーシティーの語源は、ウニベルシタスで、元来、ギルド(組合)と同義で、多数の人々、または多数の人々の結合を意味するものであります。学生と教師の結びつきが、大学をつくりだしたものともいえます。したがって、大学とは、本来、建物、制度から出発したのではなく、人間的結びつきから発生したものであると考えられるのであります。パリ大学においては、神学の研究、再編成から始まり、ボローニャ大学は、法律学を中心としていました。これらは従来の境界主義に対する反省の芽生えであり、当時発達した商取引の法規運用の実務の学問として、近代的で、合理的な学問の知識が、続々と蓄えられていったのであります。とくに、こうした学問探求の精神的基軸となったのが、人文主義、すなわちヒューマニズムであります。市民層の増加、商取引の活発化に導かれながら、大学を頂点とする知識層に、このようにして人文主義が定着するに及んで、貴族支配の枠外の流れとして、ルネサンスの機は熟していった。人間を見つめ、真理を追究する旺盛な知識欲が、やがては人間謳歌の文芸復興を守り立てていったのであります。もしも、ルネサンスが、底の浅い、たんなる思いつきの文学や芸術のあったならば、歴史の流れを変えるほどの恵みのある変革とはならなかったにちがいありません。その基盤に、旧社会の束縛からの脱却した人間の自我の目覚めがあり、深い学問的確信の裏づけがあったゆえに、あれだけのエポック・メーキングとなったのであります。ルネサンスの巨匠の一人であるレオナルド・ダ・ビンチ(一四五二―一五一九年)7は、絵画の才能だけではなく、数学や医学問うあらゆる分野に優れた業績を残した天才として知られておりますが、ダ・ビンチが、絵画の中で用いた遠近法にしても、幾何学的な裏付けを用いている。また、人体や動物の精緻なスケッチは、彼が自ら解剖したりして得られた医学的知識の裏づけとして、描かれたものがたくさんあります。これらを通してみると、ルネサンスの輝ける作品の数々といっても、その以前から、長い年月をかけて地道に積み上げられていた学問的知識の基盤があって、初めて生まれ出たものであったことに気づくのであります。私がここで皆さんに申し上げたいのは、歴史を動かす要因は、自由なる人間の思索であり、生命の潮流であるということであります。一つの文明が興隆していくには、深い思想的遺産を、その基底部にもっていかなければなりません。天才といえども、この時代的、この時代的、思想的基盤なくしては生まれえないし、仮に生まれたとしても、何らその能力を発揮することはできない。さらにまた、力の論理のみで築き上げられた社会機構は、真実に人々の生活に影響を与え、歴史に光を残す存在とはなりえないと思うからであります。人々は、ともすれば、表面にあらわれ、残された歴史の成果だけを把握しようとします。そして、その形式だけをまね、伝統だけを重んじて、自らの行動原理としてしまう傾向が強すぎるのであります。それらの業績を推し進め、達成させた、より深層部の原因に目を向けようとしない。そこに、過去のさまざまな変革の失敗があったことも、私はみたいのであります。目前の成果に目を奪われ、その達成の身に明け暮れる行動は、所詮、徒労に終わらざるをえないでありましょう。大学は、知的財産の集積所であります。そこにおいて、いかに意義ある研究・教育が行われるかによって、国家あるいは社会の、ひいては文明そのものの消長が決まるのではないでしょうか。学問の勃興するところ、必ず民族の勃興あるといわれるゆえんであります。古代文明の数々も、つねにその背後に、学問の繁栄をもっておりました。イスラム世界においても、学問の集会場のような存在があったことは明らかでありますし、インドにおいては、仏教の興隆とともに、学問は強い支持のもとに発展したのであります。有名なインドのナーランダーには、その期限を千数百年前にさかのぼることができる、きわめて古い歴史をもつ大学(当時は仏教を求めて額装らが集まった寺院)がありました。紀元五世紀から七世紀ごろにかけてもっとも隆盛を極め、数十平方キロもの広さをもっていたといわれています。規模の大きさでは、現在の大学をさえしのぐほどのものであり、ヨーロッパの大学にくらべて、はるか以前から、整備された大学として、インド、さらには東洋全域にわたる精神的淵源地となっていたのであります。中国などからも留学生がたくさん来ていたことが知られております。近年の発掘によって、研究室や寄宿舎、教室の跡が発見され、学僧数千から一万人もが、大丈夫教の研究にいそしんでいたことが明らかにされております。玄奘が『大唐西域記』において、みずから訪れた印象等を述べていりますが、はからずも、それが事実であったことが立証されたといえます。後年、イスラム教徒により破壊されるまでの数百年間、このナーランダーは、営々と大乗仏教の理念を築き上げ、流布していったであります。この大学の源流として、東洋の精神文化、特に、インド方中国、日本へと渡った仏教文化の偉大な潮流をたどることができるのであります。万にも及ぶ額装が、真摯に仏教と取り組み、論議を交わし、やがては自らの持ち場で、その実践へとおもむいたのであろうその壮挙を想像するならば、世界に誇る東洋の精神文化の淵源がここにあるといえましょう。皆さんは、学問がその根底的な部分で深められ、展開されていくならば、それは、やがては偉大な文化の源流となるであろうことを信じていただきたい。表面的な華やかな波浪よりも、改定を流れる潮流の方が、いかに尊く、力強いかを、確信していただきたいのであります。さらに言うならば、その学問も、あくまでも人間を基調にしていかなければならないということであります。ヨーロッパにおいて、中世以来、大学で培われてきた人文主義が、ルネサンスの根源力となったことは、すでに申し述べましたが、これは、古代の、また大学と呼べないような学校においても言えることであります。 師弟の徹底した対話がある教育の要古代における最高学府の代表的なものとして、プラトンが創立したアカデミアが有名であります。プラトンの時代において、アテネでは、修辞学をもって立つソフィストが少なからぬ影響を与えていました。彼らは、現実の社会に名をなすための必要な種々の学問を教える職業的教師であったわけであります。それに対して、真理探究の理想を掲げて立ちあがったのがソクラテスなのであります。ソクラテスは、斜陽のギリシャ世界を直視しながら、現実主義的な、また体制依存的な哲学者たちと対立し、人間性の本質のうえに立って、アテネの変革をめざすとともに、永遠に残るべきものとしての学問に一身を賭しておりました。ソクラテスは、みずからの信条を青年たちに伝えるため、あらゆる場を利用したのであります。市場で、ある時は街頭で、宴会場で、およそ人間の集まるところならば、どこでも出かけていって、彼は対話をとおして教育していったのであります。堕落せる学問と戦ったのであります。そこには、徹底的な対話と訓練があり、まさに校舎なき人間大学の観を呈していたといえましょう。ソクラテスのその本質を受け継ぎながら、プラトンはアカメディアを創立するわけでありますが、校舎をもち、固定した教育の場を設定しながら、どこで行われた教育は、極めて人間的なものでありました。ギリシャにおいて、食事をと野にしながら会話をするのは、市民の生活様式としてはごく普通のものでありました。プラトンの学校においても、この方式を最大限に活用したといわれる。食事の際でも、また散歩の才でも、プラトンは学生と活気にあふれた会話を気軽に交わし、そこで哲学的な、あるいは人間的な課題を取り上げて、討議したことが想像されているのであります。こうした師弟間の対話は、そのまま心理追及の態度にもあらわれていきます。師弟が相たずさえて共同研究し、一つの心理をつかもうと努力する姿が、アカメディアの誇りでもありました。入学の資格は厳しく、一種の貴族主義的なところもあったようでありますけれども、その底に流れるのは、自由の息吹であり、哲学による社会の改善でありました。したがって、当然のこととして男女共学であり、また、世俗的な権力からの学問の自由を守ることに関しても、極めて真剣であったようであります。このプラトンのアカメディアは、紀元前四百年ごろ創設され、以後、ローマ皇帝によって閉鎖させられるまでの約九百年間、ヨーロッパの精神的源流となっております。徹底した対話、師弟の共同研究という人間的な原点が、これだけ永続させ、また、歴史に多大な影響を与えていったのであろうと、解釈されるのであります。 精神の自由に豊かな発想がプラトンよりさらに歴史をさかのぼり、古代インドにあらわれた釈尊の教育法も、徹底した対話であったことは、明らかであります。宇宙・人生の根本法則を悟達した釈尊にとって、その覚りの内容を伝えるのは、問答を通してでありました。経典のほとんどが問答形式となっているのは、それを裏付けております。人間の具体的、現実的な悩みにぶつかり、そこでの対話をとおして、みずからの悟りを伝えようとしたわけであります。後年、厖大な協議が体系づけられておりますけれども、あくまでもその源流となるものは、人間的なふれあいであり、そこから惰性の錬磨と、真理探究の歩みが開始されているということを、忘れてはならないと思うのであります。プラトンの学校が、ヨーロッパの歴史のいたるところに影響をあたえたことは、後年、ルネサンスがおこったときも、そのめざしたものが〝ギリシャに還る〟ことであったことからもわかりますし、釈尊の人間教育も、東洋の歴史のすべてにと言っていいほど、大きな影を残している。その原因ともいうべきものは、真理の探究にあって、人間を基調にし、その本題を解明し、徳政を啓発することに最大の目標をおいたからであると、考えられるのであります。人間的なものに根をもたない学問や心理の研究というものは、抽象的で空虚なるものとなるか、軽薄で底の浅いものになるか、いずれかにならざるをえないと、思うのであります。原題はまた、人間の本質を見失う危機にさらされております。どうか皆さんは、こうした前提を踏まえ、歴史に進路を示し、かつ、切り開いていくものとしての学問の果たす役割に誇りをもち、人間らしく、真実の人間の復興を勝ちとるべく、学問の道を、真理探究の王道を歩んでいただきたいのであります。そこで、さらに私は、こうした大学の本来の使命を認識したうえで、皆さん方に次のことを要望したいのであります。それは「創造的人間であれ」ということであります。わが創価大学の「創価」とは、価値創造ということであります。すなわち、社会に必要な価値を想像し、健全な価値を提供し、あるいは還元していくというのが、創価大学の本来目指す者でなければならない。したがって、創価大学に学ぶ皆さん方は、創造的な能力を培い、社会になんらかの意味で、未来性豊かに貢献していく人となっていただきたいのであります。「創造」ということは、たんなるアイデアとは違うのであります。しかし、一つのアイデアを生むことさえも、それには基礎からの十分な積み重ねが要求されます。学問における創造は、それとは比較にならないほど基礎的な力量が要求されるのは言うまでもありません。想像の仕事は高い山のようなものであり、それだけの高さに達するには、広い裾野と、堅固な地盤を必要とするものであります。幅広い学問的知識と深みのある施策の基盤のうえに、初めて実りのある想像の仕事ができるわけであります。その意味からすれば、大学こそ、その基盤を築くにもっともふさわしい場であります。ところが、現在の大学の一般的傾向は、こうした条件に恵まれているのにもかかわらず、創造性への意欲は乏しいとも言えるのではないでしょうか。とくに、創造的人格を形成していく場となっていません。わが創価大学は、他の大学にはない創造性あふれる、みずみずしい大学として、社会に新風を送っていただきたい。これが私の念願であります。創造性を養うには、精神的な土壌が豊潤であることが必要であります。そして、それは精神の自由度という言葉で表せるのではないかと思います。精神が抑圧され、あるいは歪曲されているところに、自由な発想も、独創的な仕事もなされる道理がない。精神が解放され、広い視野をもっているとき、そこには汲めども尽きない豊かな発想が出てくるものであります。すでに述べた過去のいくつかの学校の例は、そういって意味で、精神の放縦ということとは違うのであります。一方、自由な、伸び伸びとした精神活動を要求しているのも事実ではあります。さらに、それにとどまるのではなく、高い自己規律に基づいた精神の開発をも意味していると考えるべきであります。勝手に考え、自由に振る舞うのが精神の自由ということではない。発想し、対話し、研磨し合うことによって、みずからの視野を拡大し、より広い、より高い視野に立ってものごとを洞察していくことこそ、精神の自由を真に拡大する道ではなかろうかと、私は思うのであります。プラトンの学校においても、また、ナーランダーの仏教大学においても、自由の気風のみにとどまらず、そこには、峻厳な心理との対決があった。創造的発想があった。それゆえにこそ、多くの精神的遺産を構築することができたのではないかと思うのであります。したがって、精神の自由度を増すということは、ある意味においては、厳格な訓練を必要とする場合もあるということであります。イギリスにおけるオックスフォード大学や、ケンブリッジ大学は、私立大学であります。これらの名門校は、数多くの学問的成果を生み、また学者、偉人を輩出しておりますが、そこでは厳格な教育法が、現在でも中世さながらにたもたれております。しかし、学生の持つ精神の自由度は高く、自己の精神を拡大して、社会へ貢献する跳躍台としているのであります。では、精神の自由度を増し、自己を拡大させていくエネルギーをどこに見いだすか。この点になると、どうしてもまた「人間とは何か」という問題になり、人間学にもどってこなければならない。人間の持つ潜在的な可能性を引き出し、開発し、アウフヘーベン(=矛盾するものをさらに高い段階で統一し解決すること)させる哲学の問題となってきてしまうのであります。 学問の道を貫き人間の復興を 文明開化の鍵は生命の開発に私がすでに挙げた大学の例においては、この哲学・思想のバックボーンがあったことを想起していただきたいのであります。生命・人間を直視し、その開発をめざしたところに、学問の自由な発達があり、ひいては、文明の絢爛たる開花があった。創造性の鍵は、まさにこの一点にあると私は思う。創価大学は、この人間学の完成をめざし、その厳然たる基盤のうえに、学問の精華をちりばめていただきたい。そして、地道な人間関係をふまえた学問の推進、真理探究の歩みが、大きくは社会変革の原動力になっていくことを確信していただきたいのであります。こうした点から、また、創価大学という名にふさわしく「創造的人間であれ」ということを、皆さんはもとより、創価大学の永遠のモットー、特色、学風にしていってはどうかというのが、私の提案したいことなのであります。この気風が、創価大学の輝ける伝統に高められていくならば、現代日本の指標を模索しつつある大学界に新風を送るものとして、貴重な存在になるということは疑いないと、私は確信するものであります。話は変わりますが、昨年、私がヨーロッパを訪れましたときに、イギリスの有名な歴史学者であるアーノルド・J・トインビー博士と種々懇談いたしました。歴史に限らず、哲学、芸術、科学、教育等、あらゆる分野にわたって熱心に議論を交わし、有意義な法門でありましたが、最初に博士夫妻にあってあいさつを交わしたとき、そのあいさつに驚かされたのであります。私はイギリスへは、オックスフォード、ケンブリッジ両大学の招聘に応じてまいったわけではありますが、博士は開口一番、「わが母校、オックスフォードに来てくださったことを感謝します」と述べられたのであります。そしてトインビー博士の夫人は、次いで「私の母校、ケンブリッジ大学に来てくださったことを感謝します」と述べておられました。博士夫妻から、そのようなあいさつを受けるとは思っておりませんでした。そのあいさつを聞いて、私は、博士がいかに母校に深い誇りと愛情をもっておられるかを、知らされた思いでした。オックスフォードもケンブリッジも、そしてアメリカのハーバード大学も、みな私立大学であります。日本とちがい、海外においては、私立大学の方が、深き伝統をもち、世界的によく知られている場合が多い。そして、それらの大学出身者は、自分の母校に対し、強い誇りと愛着心を持っています。その大学の出身者が、社会的に影響力を持つようになると、進んで寄付などをして大学を守り立てています。大学の経営は、その寄付によって成り立っているといわれるほどであります。といっても、今から、皆さんに早く偉くなって寄付をしてほしいと強制しているわけではありません。(笑い)私立大学というのは、国家権力と全く無関係のところにある。もちろん大学である以上、公的性格をもちますが、根本的には、自主的にみずからの信条の実現のために、社会に有為な人材、学問的成果を送り出すために創設されたものであります。言い換えれば、私立大学は、自主的な大学のことであり、いわば、皆でつくる大学なのであります。そこが、国立、効率の大学と違うところであります。大学の淵源はいずこを見ても、この私立大学から始まっている。大学は、お仕着せによって発足したのではなく、自然発生的におこったものだといってよい。したがって皆さん方は、この創価大学を自分たちでつくり、自分たちで完成していく大学であるという認識をもっていただきたい。在学中においては、もちろんのことであります。たんなる知識習得のためであると思ってほしくない。会社へ就職するためのパスポートであると思ってほしくないということも、もとよりであります。教師陣の先生方とつねに対話し、人間らしい活気のある大学をつくりあげてほしいのであります。創価大学は、発足後間もない新大学であります。学風も伝統もまだ定かにはつくられてはいない。今後、皆さんがつくりあげ、皆さんが積み上げていくべきなのであります。私は、その皆さんの努力を、最大限の応援を込めて、見守っていくつもりであります。さらに、在学中でだけでなく、大学を巣立ってからも、母校を誇りにし、あたたかく応援し、見守っていっていただきたい。新入生の皆さんに対して、卒業してからのことを述べるのは、少々早すぎるかもしれませんが、いかなる地、いかなる場であっても、母校を思い、母校を誇りとし、母校を守り立てていく皆さん方であってほしいというのが、私のお願いであります。トインビー博士のごとく、だれに対しても、母校をほめてもらうのがいちばん誇りとし、また、その母校を喜んでくれる人に対して感謝できる、そのような皆さん方になってほしい。そうなっていただくことが、創立者として、最大の悦びなのであります。 全員が創立者との誉れと自覚でともあれ、現代文明はある意味において、まさに転換点に立っていると言っても過言ではありません。それは、人類が果たして生き延びることができるかという、重大な問題もはらんでおります。戦争兵器がもつ平和への脅威はもちろん、進歩に対する誤った親交が、人類の死への行進を後押ししている現代であります。人類が生き延びるために、われわれはいったい、何をすればよいのか。いったい何ができるのか。先見の明をもつ学者の間では、それが、真剣な討議のテーマになっている。こうした現代にあってこそ、ふたたび新たな人間復興が必要であること、私は叫びたい。それは、人間中心主義、人間万能主義のそれではなく、人間が他のあらゆる生物の仲間として、いかにすれば調和ある生をたもつことができるのかという意味での人間復興であり、人間が機械の手足となるのではなく、機械をふたたび人間の手足とするには、どうすればいいかという意味での人間復興であります。ここで私は、このネオ・ルネサンスとも言うべき人間復興への要請に対して、今こそ、その重要な分野として、哲学・思想・学問におけるネオ・ルネサンスを必要とするのではないかと、考えるのであります。学問への新たな意欲を人類がそそぐならば、そして先見の眼を開くならば、人類が生き延びるための新たな哲学・思想が確立されるにちがいない。そしてそれは、たんに人類が生き延びるためという消極的な目標を超えて、新たな人間賛歌の文明が築かれていくことと信じるのであります。この、これからなさねばならない壮大な人類の戦いの一翼を、創価大学が担うならば、そして、少なからぬ貢献をなしうるならば、創価大学の開学の趣旨も一応、結実したと、私はみたいと思うのであります。大学におけるこの仕事は、決して容易ではないと思われる。また、短時日のうちに結論の出るものでもない。地道な研究の積み重ね、厳密な討論、旺盛な意欲を幾年にもわたって継続することを要するのは明らかであります。なによりも、それは創価大学に現に属する人々、また将来、志を同じくして加わってくるであろう人びとの全員が、一つの生命体となってこそ、その開花をもたらすことが可能となるのであります。どうか一人一人が、創価大学の代表者であるばかりでなく、創立者であるという誉れと自覚をもって、充実した学園生活を送り、さらに豊かな人生への跳躍台としていっていただきたいことをお願いするものであります。最後に、私のこれからの最大の仕事も教育であります。それは、二十一世紀の人類を、いかにしたら幸福と平和の方向へリードしていけるか、この一点しか、私のこころにはないからであります。その心から、私は皆さんに、人類の未来を頼むと申し上げておきたい。また、教授陣の先生方にも、学生を立派に育てていただきたい。衷心よりよろしくお願いいたしますと懇願し、全人類に創価大学ここにあり、との誇りと期待を込めつつ、私のあいさつとさせていただきます。 【池田先生の創価大学での講演に学ぶ】創価新報2022.10.19
February 22, 2024
コメント(0)
-
「人間の美質」の輝きが時代を照らす
進歩・創造 挑戦・開拓 自発・能動「人間の美質」の輝きが時代を照らすスペインアテネ文化・学術協会1995年6月26日21世紀文明の夜明けを―ファウストの苦悩を超えて㊤ 時代背景と講演の意義1914年に創設されたスペインの著名な文化団体であるアテネオ文化・学術会議は、95年6月26日に池田先生に対し、世界平和への貢献を称え「顕彰の盾」を贈呈。その席上、池田先生の講演が発表された。当時の世界は、冷戦が終結したものの、旧ユーゴ―スラビアをはじめ、民族対立や地域紛争の激化、世界各地で頻出する難民問題、悪化の一途をたどる環境問題など、地球的課題が山積していた。講演で池田先生は、21世紀文明は大量生産・消費・廃棄といった近代の産業・科学技術文明の延長線上で考えてはならないと指摘。課題を見極め、文化の軌道修正を行うべく「自律」「共生」「陶冶」の三つの視点から仏教の英知に基づき論及した。まず、文豪ゲーテが描いたファウストの苦悩も、「自立」を求めてついに得られぬ悲劇だったと主張。一方、仏法では外在的な規範ではなく「法」という内在的規範による「自律」を志向していると訴えた。次に、〝自然〟と〝人間〟を相対立させてきた現代文明の基調を、「共生」へと転じゆくのが仏法の「依正不二」のダイナミズムであると論じた。最後に、これまでの産業文明は利便や快適さを追うあまり、内面性の「陶冶」をないがしろにしてきたと強調。「陶冶」なき脆弱な内面世界と、未曽有の大殺戮を演じた20世紀の悲劇的な外面世界とは、深い次元で重なり合っていると考察し、〝人格・内面の錬磨〟――すなわち、「人間革命」の哲学の重要性を主張した。講演を聴講した識者は、『哲学なき時代』の暗雲を払い、人間と普遍的価値に光を当てた新しい地平が開かれました」と語った。 本日は、歴史と経験を誇る、ここアテネオ文化・学術協会において、講演の機会を与えられたことは、私の最大の名誉とするところであります。ご尽力してくださったロペス・ペレス会長をはじめ、関係の諸先生方に深く感謝申し上げる者であります。さて、二十一世紀まで、あと五年半。せかいは、まさにカオス(混沌)一色に塗りつぶされております。コミュニズム(共産主義)の崩壊により、にぎやかに開幕ベルが鳴らされたかに見えた民主の舞台も、数年を経ずして、暗転してしまい、時代は、文字どおり〝世紀末〟の暗雲に覆われております。民族や宗教がらみの争乱はあとを絶たず、本来ならば、人間性に欠かすことのできない彩である文化や文明でさえも、対立・相克の火種になりかねません。冷戦構造の崩壊は、我々の意図と期待とは裏腹に、あたかも〝パンドラの箱〟を開け放ったかの感さえするものであります。こうした時流に掉さしつつ、二十一世紀文明にアプローチしていくには、どのような観点が必要されるでしょうか。目下のところ、最も多く議論されているのは、二十一世紀文明は、近代の産業文明、科学文明の延長線上に考えられてはならないということであります。大量生産・大量消費・大量廃棄といった近代の産業文明のあり方をこのまま推し進めていけば、早晩、人類社会そのものの破局を迎えてしまうことは、明らかであります。三年前のブラジル・リオデジャネイロでの国連環境開発会議は、「持続可能な開発」という選択をしておりましたが、ともかくそれを踏み台にして、格段の英知の結集が迫られているところであります。それと同時に、私は、仏法者の立場から、時代精神の深層、つまり、ヨーロッパ主導の近代文明のエートス(道徳的気風)ともいうべきものにスポットを当ててみることも、重要な課題ではないかと訴えたいのであります。そこまで光を照射しなければ、容易に打開の道が見つからないほど、時代の閉塞状況は深刻であるといえないでしょうか。こうした人類史的課題を前にしたとき、私の脳裏に鮮やか蘇ってくるのは、貴国の卓越した思想家ルイス・ディエス・ダル・コラール博士の洞察であります。コラール博士は、三十年余り前、文化使節として来日され、多くの講演などを通し、我が国に、強い印象と多大なエートスとして見いだしていたのは、なんでありましょうか。それは、フランス革命における政治や法律といった表層の次元ではなく、「人間の尊厳に対する新たな感覚」(『ヨーロッパの略奪――現代の歴史的解明』小島威彦訳、未来社)であり、また「人間本来の力に対する想像を絶した信頼」(同前)であります。そして、「この地上における人間生存に対する有効的確な支配」(同前)なのであります。これは、言ってみれば、かのゲーテが悲劇『ファウスト』に描ききったような、ファウスト的自我の発揚でありましょう。貪欲なまでに認識し、行動し、支配しようとする近代精神の精髄であり、ヨーロッパ近代をして世界を席巻せしめた歴史的原動力でありました。いうまでもなく、それは近代精神、近代文明のエートスの〝光〟の部分でありますが、また、そこには、必ず、〝影〟の部分がつきまとっています。その限界と生き詰まりは、「心根つき果てて苦難の煉獄を横切りつつある」(同前)ファウストに譬えられているとおりであります。私がなぜこのような史観に注目するかといえば、近代文明の位置づけ、捉え方が〝反時代〟的でなく、優れて〝弁証法〟的であるからであります。先進諸国におけるカルト集団の横行が象徴するように、世紀末の闇が深ければ深いほど、人々の目は〝反近代〟〝反時代〟的になりがちであります。なればこそ、大切なことは、近代文明の〝光〟と〝影〟、〝正〟と〝負〟を厳しく選別し、〝光〟と〝正〟の部分を正しく継承しゆく「弁証法」的な史観ではないでしょうか。こうした観点から熟考してみれば、我々が近代文明のエートスから、何を継承していくべきかは、明らかになるはずであります。それは、進歩や創造、朝鮮や開拓、自発や農道などの言葉を関するにふさわしい、いつの時代にも変わらぬ人間性の普遍的な美質であります。日々新たな社会や自然に働きかけ、交流しながら、環境と同時に自分自身をも更新しゆく、人間生命のダイナミックな発現にほかなりません。それはまた、二十一世紀文明のエートス形成にも、枢要な役割を果たしていくに違いありません。その継承作業に当たり不可欠なことは、近代文明の〝影〟と〝負〟の部分を、どう矯め直し、軌道修正していくかであります。私は、悠遠なる仏教の歴史に蓄積されてきた精神的遺産は、そうした二十一世紀文明のはらんでいる課題に、大きく貢献できると信じております。そこで今回は、「自律」「共生」「陶冶」の三つの角度から、私の所見を述べさせていただきたいと思います。近代文明の軌道修正されるべき第一の点は、「自律」ということではないでしょうか。ファウストの苦悩は、自律を求めてついに得られぬ悲劇であります。「おのれの自我を人類の自我にまで押しひろげ、ついには人類そのものと一緒に滅びてみよう」大山定一訳、『ゲーテ全集』2所収、人文書院)と勇往邁進する、不適にして不遜なファウストは、自律を装った自らの傲慢を、結局、盲目と死をもって贖わざるを得ませんでした。ファウストが演じたのは、正真正銘の悲劇でしたが、二十世紀に入り、貴国が誇る世界的詩人・オルテガ・イ・ガセットは、自己を律することができず右往左往している散文的状況へ、鋭い矢を放っております。「われわれの時代はいっさいの事象を征服しながらも(中略)自分自身のありのままの豊かさのなかに自分の姿を見失ってしまったように感じている時代なのである」(『大衆の叛逆』神吉敬三訳、岩波文庫)「戦場において百万の敵に勝つよりも、一人の自己に勝つものこそ、最上の戦勝者である」(中村芳朗『人間性の発見・涅槃経』筑摩書房)こうした言葉は、枚挙に暇がありません。このように、おびただしい仏説の意図するところを一言にしていえば、「自律」の勧めといえますが、それは、他律的な宗教的呪縛に決別しようとした近代文明のエートスとは、いささか異なります。同じように自己の確立を志向しているとはいえ、ファウスト的自己とは、はっきりと一線を画した「自律の構図」ともいうべきものを、仏教では説いているからであります。それは、釈尊が特に晩年に強調していた「自帰依、法帰依」という構図であります。釈尊の最後の説法の一つには、こうあります。「みずからを洲とし、みずからを依りどころとして、他人を依りどころとしてはならない。法を洲とし、法を依りどころとして、他を依りどころとしてはならぬ」(増谷文雄『仏教百話』筑摩書房)すなわち、自己を律するには、自らを依りどころとして、他人や外部の出来事に紛動されぬ不動の自己を水かねばならない。その不動の自己を築くには、独り高しとする我見や傲慢を排し、徹して法を依りどころとする――そこに、真の「自律」も可能になるというのが、「自帰依、法帰依」の構図であります。私は、この「法」が、徹頭徹尾〝内在〟的に説かれているということであります。生命に内在しているがゆえに、「法」の働きは、ついに、人間がそれを自覚できるかどうかにかかっています。仏は〝覚者〟といって、その自覚が最高度に達した人のことであります。そして、慈覚とは、「自律」とほとんど同義語なのであります。従って、仏という偉大な覚者にとって、最大の悩みは、迷い多き人間にこの自覚が可能なのか? 可能であったにしても、人生の荒波の中で、はたして自覚を持ち続けられるのか? という難問でした。だからこそ、釈尊や、日蓮大聖人は、最高の宗教的自覚を得た後、その「法」を民衆に説き及ぶに際し、幾度かの逡巡を重ねているのであります。「法」の内在的自覚ということは、確かに人類史的な難問であります。しかし、この一点を避け、「法」を外在化させてしまえば、すぐさまそれは他律的規範と化し、人類の前には、「自律」の道は、依然として閉ざされてしまうでありましょう。外在化された「法」が、多くの場合、聖職者や権力者に利用され、人間を奴隷的地位にまで貶めてしまうことは、多くの宗教的非寛容性が、たどってきた血塗られた道に明らかであります。ゆえに、貴国の偉大な言語学者のメネンデス・ピダルが、スペイン精神史の美質を次のように描き出すとき、同じく内在的、自律的規範を志向するものとして、心からのエールを送りたいのであります。すなわち、「欠乏に耐えることにおいて人難不抜なスペイン人は、人間をしてあらゆる逆境を超越させる知恵の規範、すなわち『堅忍し節制せよ』(sustine et abstine)を胸中に持している。その内部に本能的な特殊のストイシズム(=禁欲主義)を抱いている。つまり彼は生まれつきセネカ主義者なのである」(『スペイン精神史序説』佐々木孝訳、法政大学出版局)と。 【創造する希望池田先生の大学・学術機関公園に学ぶ】創価新報2022.8.17 「人間革命」の旗を高く掲げ共に前へ21世紀文明の夜明けを―ファウストの苦悩を超えて㊦ 第二に「共生」—共に生きる、という視点を申し上げてみたいと思います。「悲劇」の冒頭、ファウストは、月のように独白します。 「あらゆるものが一個の全体を織りなしている。一つ一つが互いに生きてはたらいでいる」(大山定一訳、『ゲーテ全集』2所収、人文書院)ここには、宇宙の森羅万象が、互いに関連し、依存し合いながら、絶妙なハーモニーを奏で、生々流転しゆく「共生」の生命感覚が脈動しております。大きく息を吸い、大自然や大宇宙と自在に交感しゆく、こうした、おおどかな生命感覚は、現代人から、はるか縁遠くなってしまいました。いうまでもなく、現代文明の基調は、自然を人間と対立させ、人間によって支配・征服されるべき対象として捉えつづけてきたからであります。その結果、人間自身の孤立と自己疎外は、ファウスト的自我の悪魔的側面が招き寄せた帰結といってよいでしょう。多くの識者が指摘するように、二十一世紀の地平を拓くためには、こうした自然観、右中間の軌道修正こそ急務であります。ここ数年、「共生」が未来世紀へのキー・ワードとして、にわかに脚光を浴びているゆえんも、ここにあります。その点、仏教では、人間と、それを取り巻く人間社会や自然、宇宙などの環境と不可分なものとして捉える視点を、一貫してもってきました。 その一つに、「依正不二」という原理があります。手みじかに言えば、「正報」とは我々の自己自身を、「依報」とは我々を取り巻く環境を意味しております。そして、我々自身と環境とは、常に一体にして不二であり、互いに影響し合い、相互浸透し合いながら調和をたもっていくというのが、仏教の基本的な考えであります。こうした知見が、ポスト・モダンの知のパラダイム(範型)として大きく注目を集めてきていることは、皆さま方、ご存じのことであります。仏法の捉え方によれば、「人間」と「自然」が織り成すハーモニーは、決して静的なイメージではありません。それは、創造的生命がダイナミックに脈動しゆく、活気にあふれた世界であります。そのダイナミズムは、先に近代文明の継承すべきエートスと申し上げた「進歩」や「創造」、「挑戦」や「開拓」などの能動的なエネルギーを、余すところなく接する広がりを有しております。そうした「正法」と「依報」とのダイナミックな関係を、仏典では簡潔に「正報なくば依報なし・又正報をば依報をもつて此れをつくる」(全1140・新1550)としているのであります。まず、前半部分の「正報なくば依報はし」でありますが、例えば、我々が死んだところで、人類は存続していきますし、極端に言えば、人類が滅亡しても、それが、宇宙の終りを意味するわけでもありません。にもかかわらず、「依報」の存在そのものを「正報」のなかに包み込み、「正報なくば依報なし」と断ずるのは、もはや、人間と環境とが不可分であることの客観描写というよりも、宗教的確信に基づく主体的決断であります。その決断の根拠を、仏教では「一念」と呼んでおります。「正報なくば依報なし」とは、その「一念」の地平をば、時間と空間の限界を超えた、宇宙大の「大我」にまで拡大せよ、との促しであり、更に言えば、その決断にふさわしい生き方、大乗仏教で菩薩道と呼んでいる、「小我」を去って「大我」にのっとった生き方をも要請しているのであります、とはいえ、主体的決断だけで終わっていたのでは、独我論や唯心論、或はファウスト的独尊にさえ陥りかねません。そこで、仏典の後半部分では「正報をば依報をもって此れをつくる」と、最新のエコロジー(生態学)的視点を先取りしたかのような補足がなされ、「依正」の絶妙なバランスがとられているのであります。この環境への温かい眼差しによって、「正報なくば依報なし」との断固たる意志は、ほどよく融和され、人間と環境とのダイナミックに相互浸透しゆく、真の「共生」の在り方へと止揚されているのであります。さて、皆さまは、こうした仏教の「依正不二」論が、オルテガ哲学の精髄である「私は、私の環境である。そしてもしこの環境を救わないなら、私をも救えない」(『ドン・キホーテに関する思索』A・マタイス・佐々木孝共訳、現代思潮社)との命題に、驚くほど親近しているお気づきだと思います。「私は、私と私との環境である」という言葉は、「正報なくば依報なし」と同じように、自我の「大我」への広がりを志向していないでしょう。「環境を救わないなら、私をも救えない」という言葉からは、「正報をば依報もつて此れをつくる」と同じような、共生へのベクトルが感じ取れないでしょうか。従って、オルテガの「文明とは、何よりもまず、共存への意志である」(『大衆の反逆』神吉敬三訳、角川文庫)との言葉に、また、大思想家ウナムーノの「強者は、根源的に強い人は、エゴイストになることはできない。十分に力を有している人は、自らの力を他に与えるものなのだ」(「生粋主義をめぐって」佐々木孝訳、『ウナムーノ著作集1 スペインの本質』所収、法政大学出版局)との言葉に接するとき、私はそこに、大航海時代以来、数百年の時の試練を経て、貴国の精神水脈を流れ続けてきた「共生」のエートスの一端を垣間見る思いがします。それはまた、大乗仏教の精髄である菩薩道とも、深く通底しているのであります。 第三に「陶冶」という点に触れてみたい。ここにも近代文明が亡失してきた盲点があると思うからであります。近代の産業文明は、利便や効率、快適さなどの追求を旗印に、数百年間をまっしぐらに走り抜いてきました。その結果、空前の富の蓄積がなされ、物質的な側面では、先進国の一般市民は、往昔の王侯貴族も及ばぬ生活が可能となりました。しかし、その代償として、いわゆる産業社会のトリレンマ(三者択一の窮境)と呼ばれるもの―すなわち、➀増え続ける人口を養う経済発展②枯渇する資源・エネルギー③環境破壊の三者が、互いに規制し相矛盾し合うという複雑な連鎖構造など、多くの難題を抱え込んでいることは、周知の事実であります。しかも、より深刻なことは、産業文明の伸展が生命力の衰弱というか、内面世界の劣化現象を引き起こしてしまっているという事実ではないでしょうか。利便や快適さを追うあまり、困難を避け、できるだけ安きに就こうとする安易さから、「陶冶」が、二の次、三の次にされてきたのが、近代、とくに二十世紀であります。内面性の陶冶を怠ったことへの「しっぺ返し」を、最も痛切な形で受けているのが、旧社会主義国でありましょう。私は現在、ゴルバチョフ元ソ連大統領と、雑誌で対談を進めておりますが、氏は、急進主義の誤りというかたちで、繰り返し、そのことに触れております。「過激主義というのは、ものごとを単純に決めつけてしまうことへの誘惑と同じく、しぶといものです。二十世紀において、性急な決定や、すべての困難を一挙に解決できる摩訶不思議な解決法がある、という単純な思い込みのために、人々は、どれほど辛酸をなめたことでしょう」また「〝もっとも急進的な、革命的なものが、変革と進歩をゆるぎないものにする〟という、十九世紀、二十世紀の考えは誤りです」(『二十世紀の精神の教訓』潮出版社)—と。私も、全く同感であります。フランス革命の動向に厳しい眼を注ぎ続けたゲーテの「内面的訓練の過程を与えずして、単に我々の精神だけを介抱するような種類のものは、ことごとく有害である」(ディエス・デル・コラール『ヨーロッパの略奪―現代の歴史的解明』小島威彦訳、未来社)との警句を、今、私は思い起こしております。「内面的訓練の過程」—これ、すなわち、内面性の陶冶であります。これをおろそかにし、制度の件閣のみ先行することへの危惧は、フランス革命に対しバーク(イギリスの思想家)が、アメリカ革命に対しトクヴィル(フランスの歴史家)が、ロシア革命に対しガンジーが、中国革命に対し孫文が、ニュアンスの違いこそあれ、一様に表明しているところであります。そして現在、社会主義国に限らず、自由主義国も含め、世紀末の人類社会に横行する物質主義、拝金主義、倫理の崩壊は、彼らの危惧が、決して杞憂には終わらなかったことの証左であります。オルテガが、徳十年以上も前に憂慮していた「慢心しきったお坊っちゃん」(前掲『大衆の反逆』)の時代とは、さながら今日のことのようであります。 古来、仏教では「忍辱」ということを修行の柱としてきました。また、釈尊の臨終の言葉が、「怠ることなく修行を完成なさい」『ブッダ最後の旅』中村元訳、岩波文庫)であったように、内面の陶冶や鍛えを、第一主義的課題として重視してきております。この点に関する日蓮大聖人の訓戒を、幾つか挙げてみましょう。「鉄(くろがね)は炎(きたい)打てば剣となる」(全958・新1288)「闇鏡も磨きぬれば玉と見ゆるが如し、只今も一念無明の迷心は磨かざる鏡なり是を磨かば必ず法性真如の明鏡と成るべし、深く信心を起こして日夜朝暮に又懷(おこた)らず磨くべし」(全384・新317)「いまだこりず候法華経は種の如く仏はうへての如く衆生は田の如くなり」(全1056・新1435)子のように、内面世界の陶冶や鍛えの勧めが、いずれも〝剣〟〝鏡〟〝田と作物〟などの具体的例に寄せて述べられている点に、留意していただきたい。これらの農作物や手仕事を特徴づけているのは、活字の世界などと違い、結果を得るまでの過程に少しの手抜きも名許されない、つまり要領やごまかしの通用しない世界であるということであります。例えば、田に育つ稲にしても、収穫に至るまでに、実に八十八段階ともいわれる手順を踏まなければならず、どれ一つ欠けても満足のいる結果は得られません。名刀を鍛え上げるにしても、鏡を磨き上げる場合も、同じ道理であります。にもかかわらず、近代文明の申し子ともいうべき「慢心しきったお坊っちゃん」たちは、この道理に背を向け、楽をしよう、易きにつこう、簡単に結果を手に入れようとするあまり、オルテガの言う「真の貴族に負わされているヘラクレス的な事業」(前掲『大衆の反逆』)などとは、縁なき衆生と化してしまった感さえあります。その結果、旧社会主義国はもとより、〝勝利〟したはずの自由主義国家にあっても、シニシズム(冷笑主義)や拝金主義の横行する「哲学の大空の時代」を招き寄せてしまいました。その陶冶何脆弱な内面世界など、未曽有の大殺戮を演じた二十世紀の悲劇多岐な外面世界とは、深い次元で重なり合っているように思えてなりません。ゆえに、私どもは、人格の陶冶の異名ともいうべき「人間革命」の旗を高く掲げ、新たな人間性期の夜明けを目指し、航海を続けているのであります。以上、私は、二十一世紀文明構築のための要件と思われるものを「自律」「共生」「陶冶」の三点に絞って申し上げてみました。それらが、煉獄のファウストの苦悩にとって、希望の曙光たりうるかどうかは、歴史の審判にゆだねる以外はないでしょう。しかし、一歩を踏み出さずして、一歩も千歩もありません。私は一仏法者として、試練の歴史を生きる同時代人として、諸先生方とともに、全力をあげて、この未聞の開拓作業に汗を流してまいる決意であります。最後に、貴国の偉大な精神的遺産である『ドン・キホーテ』の一節を申し上げ、私の話を終わらせていただきます。「遍歴の騎士は世界の隅々へ分け入れるがよい、およそこみいった迷路へ踏みいれるがよい、一歩ごとに不可能なことに敢然と立ち向かう通い、人住まぬ荒れ地の真夏の日の灼くがごとき炎熱に堪え、冬は風雪の厳しい寒さに堪えるがよい」(『セルバンデスⅡ』会田由訳、『世界古典文学全集』40所収、筑摩書房)ご清聴、ありがとうございました。 【創造する希望池田先生の大学・学術機関講演に学ぶ】創価新報2022.9.21
February 2, 2024
コメント(0)
-
グローバルな視野と人類益の発想を
グローバルな視野と人類益の発想をアルゼンチン ブエノスアイレス大学1990年「融合の地」に響く地球主義の鼓動 時代背景と講演の意義1990年(平成2年)3月1日、アルゼンチン最高峰の学府、ブエノスアイレス大学は、池田大作先生に対し、日本人初となる名誉博士号を贈った。同大学での授与式の席上、池田先生の講演が発表された。講演の約4カ月前の89年(同元年)11月に東西冷戦の象徴だったベルリンの壁が崩壊。同年12月に、東西冷戦が盛んに。さらに、環境破壊、資源枯渇、エネルギー機器、人口爆発など〝地球的問題群〟が山積していた。池田先生は講演で、世界の相互依存が緊密化しており、いかねる国家・態勢も排他的な孤立は不可能になると世界情勢を分析。21世紀の課題はナショナリズムと地球主義(グローバリズム)の融合であると指摘した。そして、その問題解決の糸口はアルゼンチンの国民性にあると主張。同国に脈打つ「個の自立」と「世界性」が調和する「コスモポリタン(世界市民)的人間像」こそ時代の先駆であると訴えた。続いて、「第三世代の人権」(平和・環境・発展などのグローバルな連帯)に焦点を当て、人権問題に言及。「第一次世代の人権」第一世代の人権」(自由権的基本権)、「第二世代の人権」(生存権的基本権」と異なり、「第三世代の人権」は国家の枠を超えた地球的規模での対応が必要という特徴があるため、「グローバルな視野と人類益の発想に立つ」世界市民が求められると語った。同大学のシェベロフ総長は、「(池田先生は)わが大学の再興栄誉である名誉博士号を受けられたのですから、大学の扉はいつでも開かれています」と敬愛の念を込めて語った。 伝統ある、また南米屈指の最高学府であるブエノスアイレス大学において、このような挨拶の機会をいただき、シェベロフ総長閣下をはじめ、教職員の諸先生方、並びに学生の皆様に心より感謝いたします。また、ただいまは光栄にも、貴大学の名誉学位を賜り、重ねて厚く御礼申し上げます。今、世界は、あらゆる局面でボーダーレス(国境なき)時代を迎えております。昨年末、東西冷戦という文壇の象徴であった〝ベルリンの壁〟が崩壊しました。私自身、かつてそこを訪れた一人として、誠に感慨深く、この歴史の開店を見つめたものであります。政治であれ、経済であれ、世界の相互子損は一層緊密化しており、いかなる国家も態勢も排他的な孤立は不可能になっております。現代は巨視的に見れば、二度の世界大戦をはじめ「対立と分断」の悲劇におおわれてきた歴史の歯車が、新しい「共存と調和」の秩序を模索し、音を立てて動き始めた「大いなる過渡期」といってよい。この巨大なうねりを思わせる時流――その前途には幾多のアポリア(難問)が濃霧のように垂れこめ、混沌としております。そうしたなかにあって、二十位世紀へ向けての最大の課題は何か。ナショナリズムとグローバリズムを志向しつつ、どうナショナリズムの新しい秩序付けを行うか、という問題であると思います。それは例えば、ソ連や東欧諸国における民族運動の沸騰や、ドイツ統一、一九九二年に予定される欧州統合の問題などにも、〝ポスト・ヤルタ〟の世界が直面する最大の試練として、すでに先鋭的に表れております。もし、対応を誤れば、収拾のつかない混乱を招くことは必至であり、はるか地平線上に顔をのぞかせたグローバリズムの太陽も、たちまち黒い霧に覆われてしまうでありましょう。いま、私の脳裏には、この一月にした四苦会談した貴国のデ・ラ・グァルディア駐日大使の一言が鮮やかに蘇ってまいります。それは、私がアルゼンチンの国民性についてうかがった折のことでした。大使は「一口で言うのは難しいが」と断られながら、その特質を「融合の地」と表現されておりました。まことに素晴らしい洞察であり、特質であると思います。私が申し上げるまでもなく、貴国は、その地勢自体、国内にいて世界中の風景を楽しめるといわれるほど多様であり、また国民も多様な諸民族の融合によって構成されております。私は、この「融合の地」という溶鉱炉から、未来に向かって限りない可能性がたぎる音を聴きとる思いがするのであります。つまり、融合が生むカオス(混沌)は星雲を生成しゆく創造的な渦であり、いわばカオスの噴流の中でこそ人間の創造的生命のダイナミックな躍動である。これは、諸民族の「融合の地」アルゼンチンの姿にも通じていると思います。なるほど、そのエネルギーは沸騰点への過程にあるかもしれません。しかし、貴国を愛したフランスの社会学者E・モランがヨーロッパを表した言葉「生成的混沌」(『ヨーロッパを考える』林勝一訳、法政大学出版局)という言葉は、このまま貴国の特質と二重写しになってはきてはないでしょうか。そこに、私が貴国に新たなグローバリズムの先駆を見る理由があるのであります。さて、こうしたボーダーレス時代は、それにふさわしい新しい「人間像」を求めております。その点でも、南米独立の先駆けとして、誇り高き「自由」と「自治」の精神に裏打ちされた個人主義が根をおろしている貴国の伝統は刮目に値します。さらに「融合の地」が育んだコスモポリタン(世界市民)的な雰囲気もある。このいわば「個の自立」のベクトルと「世界性」のベクトルの調和に、私は注目したい。貴国の代表的な詩人ボルヘスは、想像力の翼の赴くままに時間と空間を超越した迷宮に分け入り、「ただひとりの不死の人――それが全ての人間である」(『不死の人』篠田一士訳、『世界の文学』9所収、集英社)と、一人が万人を包含し、万人が一人に極まる不思議に迫っております。すなわち、一個の人間の内奥を「タテ」に掘り下げて「普遍」と出会うのであります。更にボルヘスは「アルゼンチン人は市民である前に一人間であるというのが真相なのだ』(『翼端審問』中村健二訳、晶文社)とも言っている。つまりこれは、「ヨコ」に国家という人為枠組みを突破して「人間」という「普遍」を見るのであります。こうしてボルヘスのこの「タテ」と「ヨコ」からの凝視が焦点を結ぶ地点に立ち現れてくるもの――それが「個の自立」と「世界性」を併せ持った「コスモポリタン的人間愛」のイメージであります。広大なパンパで生きぬくガウチョ(牧童)の姿を描いた貴国の文化史上の傑作『マルティン・フィエロ』(ホセ・エルナンデス)。今なお人々に愛誦されているといわれるこの名叙事詩の最後で、主人公のフィエロがこう謳っております。「俺のすべての兄弟たちの幸せ不幸せは、俺の幸せ不幸せ、兄弟達は俺の生き方を誇りをもって心の中にとどめ、同胞達はいつまでも 俺のことを想い出してくれるだろう」だれびとの庇護も求めない独立不羈の生き方の象徴であり、いささかアウトロー的でさえあるガウチョ的な人間像のなかに、こうした「同胞(パイサーノ)」への限りない共感の念が脈打っていることに私は心ひかれます。自立した個人がその胸中に呼びかける「同胞」という言葉が「人間」と同義になる時代こそ、新しい世紀であると思うのであります。 さて、このようなコスモポリタン的個人が世界に貢献し得る最大の課題として、今後、世界的に急浮上してくるであろうものは人権問題であります。皆さまもご存じのように、近年「第三世代の人権」がクローズアップされ、心ある人々の注目を集めております。それは自由権的基本権としての「第一世代の人権」、生存権的基本権としての「第二世代の人権」に対して、発展・環境・平和などを内容としています。第一、第二の人権が〝国家からの自由〟の保障や、国家に要求する性質の権利だったとすれば、「第三世代の人権」は、もはや国家の枠を超えた地球的規模での対応なしには真の解決を望めない性質のものである点に際立った特徴があります。例えば、「環境問題に対する権利」を取り上げてみても、汚染されない空気や水とともに生きる権利を確保するには、国境や国益にとらわれていては解決できず、グローバルな視野と人類益の発想に立つほかない。まさにボーダーレス時代こそ、コスモポリタン的個人の出番であると、私は信じてやまないのであります。ともあれ、あらゆる閉鎖的な考え方が変更を迫られ、崩壊していくのが、ボーターレス時代の潮流であります。個人においても、自分を超えて人類全体と関わっていることを自覚できるような生き方が求められているといってよい。そのような価値体系の取り組みを挙げたい。そして貴国の国民性のなかに、とりわけ若い世代の皆さまに、その旗手としての大いなる可能性を見いだすのであります。最後に、本日が、歴史ある貴大学と、はるか日本の若い大学である創価大学との、学術・教育交流の第一歩となれば、これ以上の喜びはありません。貴国並びに貴大学のますますのご発展を心より念願しつつ、私のささやかな挨拶といたします。 【創造する希望池田先生の大学・学術機関講演に学ぶ】創価新報2022.7.20
December 13, 2023
コメント(0)
-
人と人を結ぶ以外に平和の橋は築けない
人と人を結ぶ以外に平和の橋は築けないキューバ ハバナ大学1996年6月25日新世紀へ 大いなる精神の架橋を 時代背景と講演の意義キューバ共和国の最古の歴史を誇る最高学府・ハバナ大学は1996年(平成8年)6gs津25日、池田大作先生に日本人初となる「名誉文学博士号」を授与した。同大学で行われた授与式の席上、池田先生は記念講演を行った。当時、キューバは冷戦終焉の混乱のあおりを受け、困難に直面していた。ソ連崩壊(91年)によって貿易の85%を占めていたソ連・東欧との輸出入が途絶え、経済的な援助も停止していた。加えて、96年2月にはキューバ領空に入った米民間機をキューバ軍が撃墜し、米の経済封鎖が強化されるなど、人々の生活は厳しさを増していた。そうした中、池田先生は〝キューバ精神の父〟ホセ・マルティの民衆愛に貫かれた思想を通して講演。まず、マルティの「人間の尊厳と相いれないものは、全て滅びる運命にある」との信念を紹介。21世紀に始まる新たな千年には、「人間の尊厳」を基盤とした「希望と調和の文明」を築いていきたいと力説した。そこで、仏典に説かれる「小宇宙たる人間」と「大宇宙」の関係性を挙げ、人間と社会、そして宇宙を結ぶ『詩心』の力に言及。また、平和創出の力として、人と人を結ぶ人間像として〝菩薩〟の心と振る舞いを紹介。人間をつくる教育こそが未来を開く架橋であると結んだ。講演終了後、同国のノベージ高等教育大臣(当時)は、感動の面持ちで語った。「まさに、私たちの進むべき未来への進路をも示す講演であったといえるでしょう」 ブエナス・タルデス!(スペイン語で「こんにちは」)尊敬するハルト文化大臣。尊敬するヴェーラ総長。尊敬するマルティ副大臣。またアジア外交団の車先生方はじめ、ご臨席の皆さま。そして、英知の顔輝く、若き学生の皆さま。ただ今、キューバ共和国の誉れある「フェリックス・パレラ最高勲章(文化功労の最高勲章)」、また二百七十年に及ぶ伝統のハバナ大学から「名誉文学博士号」を賜り、これほどの栄光はありません。心より御礼申し上げます。私は、この栄誉を、私の恩師である戸田第二代会長に、捧げたいと思うのであります。貴国の偉大なる精神の父であり、共和国の威雄であるホセ・マルティは、「民主が疲れても、決してあきらめない人間」(Obras Compltetans de Jose Marti,Editorial Nacional de Cuba)に、歴史変革の光明を求めております。わが恩師は、まぎれもなく、そうした有者の一人でありました。一国をあげて、アジアへの侵略戦争に暴走しゆくなか、恩師は、先師牧口初代会長とともに、日本の軍部ファシズムに抵抗し、投獄されました。しかし、二年間の獄中闘争を完全と勝ち越え、獄死した牧口の平和への遺志を受け継ぎ、五十一年前、敗戦の焼け野原に一人立ったのであります。その出獄の日が、間もなく巡りくる七月三日であります。「人間の尊厳と相いれないものは、全て滅びる運命にある」というホセ・マルティの信念は、そのまま恩師の歴史観でもありました。ゆえに恩師は、「人間の尊厳」なかんずく「生命の尊厳」に一切の焦点を当てました。民衆一人一人が、尊極なる「生命」の価値に目覚め、生活に、人生に、社会に価値を創造していく――この〝内面の変革〟を基熟とする「人間革命」という大道を、恩師は踏み出したのであります。⚔冷戦が激化するなかで、厳然と「地球民族主義」の理念を提唱いたしました。その志向する所は、現代的に言えば、「トランス・ナショナル」、すなわち、偏狭な民族中心主義を克服し、人類の共通の課題に挑みゆくことにあります。ここに、仏法の人間主義を基調として、世界の民衆を結びゆく、私どもの「平和」と「文化」と「教育」の運動の原典があります。二十一世紀に始まる新しい千年には、「人間の尊厳」を基盤とした、〝希望〟と〝調和〟の文明を、断固として築いてまいりたい。その深き願いを込め、本日は、「新世紀へ 大いなる精神の架橋を」と題して、ホセ・マルティの思想と対話を交わしながら、若干の考察を加えさせていただきたいと思うのであります。私が注目したいのは、ホセ・マルティが不可欠とした「詩心」による〝個と全体の架橋〟であります。人間の心の律動を、大宇宙、大自然のリズムと和合させながら、悠久なる時空の中で、幸福へ、平和へと高め、開いていく――それが、「詩心」といってよいでありましょう。古来、〝人間〟と〝社会〟と〝宇宙〟を結ぶ架橋の役割を担ってきたのが、生命に躍動する「詩心」でありました。現代社会から、「詩心」の喪失が指摘されて久しくなりますが、それは、現代人が、〝断片〟と化し、閉ざされた空間で呻吟している証左といわざるを得ません。だからこそ、「詩で教育せよ!」というホセ・マルティの呼びかけが、強く迫ってくるものがあります。〝人間の目が、かつて見たこともないほど美しい〟とたたえられるカリブの島に、人情味あふれる人生模様を織りなすキューバ。その街角で、浜辺で、そして何気ない会話の中で、多くの詩が自然に語り合われている――なんと心豊かな光景でありましょうか。貴国の人々は、ホセ・マルティがいう「魂の叫びである詩の翼」を育んでおられるように思えてなりません。それは、世界的に文学の衰退が憂慮されるなか、貴国をはじめラテン・アメリカ文学が、ひときわ活況を呈し、旺盛な生命力を称えている事実からも、うかがわれるのであります。ホセ・マルティの名が、その第一ページに記されている、文学史上に不滅の「モデルニスモ(近代主義)」運動しかり、詩人のギリェンに象徴される「ネグリスモ(黒人芸術)」の運動も、またしかりであります。これらの精神的営為は、とりもなおさず、自らが何者であるかを真摯に模索し、みずみずしい「生の全体性」を回復せんとする運動であった、といってもよいのではないでしょうか。ホセ・マルティが、同じく詩人であったホイットマンに託して述べた次の言葉は、そのまま自身の心からの感慨であったに違いありません。「彼(=ホイットマン)にとって無縁なものは何もありません。彼はあらゆるものに気を配っています。枝をはうかたつむり、不思議なまなざしで彼を見つめる牛」「人間は両腕を広げて、自分の胸にすべてのものを抱擁しなければなりません」(高橋勝之監修『キューバ革命思想の基礎』神代修訳、理論社)と。響きあう「詩心」は、生き生きと、宇宙すべてに、自己との関連性を見いだしていこう、とするものであります。⚔仏典では、人間の生命と宇宙の活動との〝相応性〟を、具体的に、次のように説いております。「鼻の息の出入りは山沢渓谷の中の風に法とり口の息の出入りは虚空の中の風に法とり目は日月に法とり髪は星辰に法り眉は北斗に法とり脈波江河に法とり骨は玉石に法とり皮肉は地土に法とり毛は叢林に法とり」(全567・新718)と。このよに、仏教は、人間の内なる「小宇宙」と、外なる「大宇宙」との密接不可分な関係性を、精妙に説いているのであります。それは、大宇宙のリズムに調和し、共鳴しゆく、人間の「生の全体性」であります。宇宙の森羅万象は、〝一念〟、すなわち、人間の「心」に包括される。と同時に、その〝一念〟は、森羅万象に脈動し展開していくのであります。個の法理は、「人間は統一された宇宙」(前掲 Obras Comppletas de Jose Marti)というホセ・マルティの洞察とも呼応しております。わが〝一念〟の変革は、「詩心」の勲発とも連動しております。この〝一念〟の拡大が、他者と共鳴し、周囲への貢献を広げつつ、生命の内奥から、智慧と慈悲の太陽を輝かせていくものであります。これこそ、万人に平等に開かれた、「人間の尊厳」また「生命の尊厳」の光彩でありましょう。この内なる太陽を昇らせゆく「人間革命」こそが、〝人間〟の連帯を強め、〝社会〟の繁栄をもたらす。そして、〝世界〟の平和を創出する基点となるにちがいありません。波乱万丈の人生にあって、ホセ・マルティは悠然と、「いかなる場所であろうとも、人間がしっかり立ち上がれば、太陽はそこで輝いている」(同前)と語っておりました。ホセ・マルティが、ラテン・アメリカが抱える問題を掘り下げたエッセーを「根源へ」(前掲『キューバ革命思想の基礎』と題した時、まさに、人間の内面を根源的な変革を志向していたのではないでしょうか。ホセ・マルティは、徹して弱者の側に立ち、人々の苦悩と同苦しゆく勇者でありました。「人間にとって、真実勝唯一の栄光とは、他者への奉仕である」(前掲 Obras Comppletas de Jose Marti)と断言しております。自他ともに「人間革命」を探求しゆく〝人格〟を、仏教では「菩薩」と呼びます。「菩薩」は、四つの汲めども尽きぬ無量の心で、他者とかかわることによって、小さな自我のカラを打ち破っていくのであります。それは、第一に、民衆の苦しみを抜こうとする心。第二に、民衆に楽しみを与えようとする心。第三に、民衆の幸福をともに喜ぶ心。第四に、民衆を平等に愛する公平な心であります。まさに、ホセ・マルティの生涯は、こうした〝菩薩〟の無量の心に溢れていたと、私は見たいのであります。⚔ともあれ、すべてが「人間」で決まります人間」をつくり、「人間」を結ぶ以外に、崩れざる人類の平和の橋は築けません。もとより、それは、地道な作業であり、長い目で見れば、成果は望めないかもしれない。しかし、私たちは、ホセ・マルティが愛する妹に書き送った手紙に励まされるのであります。それは、「木を見てごらん。太い枝に、黄金色のミカンや赤いザクロが実るには、どんなに時間がかかるか、わかるだろう。人生を極めていくと、あらゆるものが同じプロセスをたどることがわかるのだ」(同前)と。ここには、斬新的な歩みに徹する忍耐がうかがえてなりません。これこそ、「人間の尊厳」に則った、内発的な変革を可能ならしめる力でありましょう。その意味において、私は、教育に力を入れて、世界に燦たる知性を誇る貴国のたゆみない努力に、心から敬意を表したいのであります。教育こそが、未来への希望の架橋である、と私は考える一人であるからであります。今、私の胸には、ホセ・マルティの有名な言葉が、響きわたっております。「それぞれの人間文明の真価は、その中でどのような種類の男性と女性が生まれるかによって知ることができる」(「二つのアメリカ」橋本芳雄訳、加茂雄三編『キューバ革命』所収、平凡社)と。貴大学の宝ともいうべき、マルティ資料の保管所は、〝鉄を熱する炉〟すなわち〝人間を錬成する場所〟という意義の「フラグワ」という名前を冠しているとうかがっております。まさに、貴大学が、二十一世紀の「新しき人間像」を鍛え、世界の舞台へ陸続と輩出しゆく、熱き「フラグワ」となりゆくことを、私は確信してやまないのであります。結びに、諸先生方のますますのご健勝と、新世紀のキューバを担いゆく青年たちの栄光の前途に思いを馳せつつ、私の好きな貴国の詩人ギリェンの詩の一節を捧げ、私の講演を終わらせていただきます。「汝の魂を光で満たしはるか山頂を見ざしたまえ!汝の杖を大胆にも妨げる障害があれば汝はより果敢な翼を広げたまえ!」(Obra poetica/,Editorial Letras Cubanas)ムーチャス・グラシアス!(スペイン語で「どうもありがとうございました」) 【創造する希望池田先生の大学・学術機関講演に学ぶ】創価新報2022.6.15
October 30, 2023
コメント(0)
-
教育が開く世界精神のコスモス
教育が開く世界精神のコスモスマカオ東亜大学(現・マカオ大学)1991年1月30日新しき人類意識を求めて 時代背景と講演の意義1991年1月30日、マカオ東亜大学(現・マカオ大学)から、池田先生に同大学初となる名誉教授の称号が授与。それに続き、先生の講演が行われた。89年にベルリンの壁が崩壊。東西冷戦が終結し一時、世界に平和の曙光が差したかに見えた。しかし、講演直前の91年1月17日に中東で湾岸戦争が勃発。世界に再び暗雲が立ち込め、〝ポスト冷戦〟の新たな国際秩序が模索され始めた。そうした中、池田先生は講演で、民族主義による世界の混沌から新しき秩序を生み出すためには、人間の無意識僧に根差す「民族意識」を、教育や哲学、宗教などによって陶冶し、「人類意識」へと鍛え上げるべきだと訴えた。さらに、中国文明の基底部にある〝自律〟の個人主義・自由主義の思想には、西欧型の極端な個人主義と異なり、「他者」と関わっていく視点が存在すると論及。池田先生はそれを「中国伝統の優れて現実的なコスモス感覚」と表現し、現代の行き詰まりを打破しゆく突破口があると主張した。同大学からはその後、池田先生に「日本研究センター名誉所長(93年)」「名誉社会科学博士(95年)」「報戸軽・アジア研究センター名誉所長(99年)」との栄誉が贈られている。それらに対して周学長(99年当時)は「未曽有の功績を象徴するもの」と賞賛している。 本日、栄えある東亜大学の、初の名誉教授という最大の栄誉を賜り、まことにありがとうございました。ランジェル博士、薛寿生学長をはじめ、すべての関係者の皆様に心より御礼申し上げます。また、このように大勢の若き英知の方々の前で記念講演をさせていただくことは、大変にうれしいことであり、重ねて深謝申し上げます。さて、ここマカオは、十六世紀以来、ポルトガルの東洋貿易の拠点となり、東西を結ぶ交流の要衝となってまいりました。日本との関わりも深く、日中貿易の中継地として重要な役割を担い、いわば日本にとっては、西洋文明の新風を送ってくれた大切な〝窓〟であったといえましょう。今回、私は初めてマカオを訪れました。中国の昔をしのばせるたたずまいポルトガルの文化の雰囲気を伝える多くの建築物が見事に調和し、マカオ独自の景観をつくりだしていることに、深い感銘をおぼえております。それは東洋と西洋の異なる文明・文化が共存し、調和できることを明確に示しております。昨年四月、ランジェル博士も、創価大学での記念講演で述べられておりますとおり、まさにマカオは、四百五十年間にわたって、〝東西文化の融合が可能である〟ことを世界に証明するという〝文明史的意義〟を担ってきたのであります。国際文化を迎えた今、このマカオの存在は、異なる文明・文化の共存は、ひいては人類の調和を考える貴重な先例として、ますます大きな光彩を放っていると思えてなりません。そのマカオ唯一の総合大学として、間もなく開学十周年を迎える貴大学の特色も、豊かな国際性にあるとうかがっております。教授陣も、中国、イギリス、ポルトガル、フランス、アメリカ、カナダ、ドイツ、オーストラリア、ニュージーランド、日本から招聘されており、さらに私ども創価大学も学術交流協定を結ばせていただいておりますが、世界各地の大学、研究機関と積極的な交流を推進しておられる。また、貴大学設立の式典には、世界二十六の学長が出席していることも、国際化時代を担いゆかれる大学関係者の貴い熱意の賜物であり、同時に貴大学への世界の諸大学の大いなる期待の表れでありましょう。東亜大学こそ、東洋におけるボーダーレス時代の担い手にふさわしい大学であり、その前途に思いをはせるとき、二十世紀の世界を照らす希望の旭日が、このマカオの地から昇りゆくのを仰ぎ見る日のことが待望されてなりません。◇ご承知のとおり、世今、湾岸戦争という重大な事態に直面しております。これまでの米ソ二極体制に代わって人類融合の道を開く新たなコスモス(秩序)は未だ形成されず、秩序感覚の失われたカオス(混沌)の時代の様相を呈しているといっても過言ではありません。それは、イデオロギーが終焉を告げたあと、世界各地で噴出している民族主義に象徴されております。確かに民族というものは、人間が人間であろうとするとき、立ち返るべき一つの原典ではありますが、それが、そのままグローバルな秩序形成に繋がっていくとはとうてい言えない。昨年亡くなった私の友人、アメリカのノーマン・カズンズ教授は、人間に「部族意識」ではなく「人類意識」を教えることこそ、教育の要諦であると力説されておりました(『世界市民の対話』毎日新聞社。『池田大作全集』第14巻収録)。すなわち、半ば人間の無意識僧に根差している民族意識を、教育や哲学、宗教などによって陶冶し、より開放的にして普遍的な人類意識へと鍛え上げていかねば、新たな世界秩序など、とうてい望むことはできないと私は思います。こうした課題を前にして、私は、中国三千年の文明を地下水脈のように流れている伝統のコスモス感覚ともいうべきものに、注目せざるを得ません。おそらく、それは仁・義・礼・智・信の「五常」をモットーに掲げた東亜大学の建学の精神にも通じていくであろう、と私は思っております。最近、日本や、韓国、台湾、香港などNIES(ニーズ=新興工業経済地域)諸国のめざましい経済発展に触発されてか、中国を含むそれらの地域を〝アジア文化圏〟〝漢字文化圏〟等と括る試みだがしばしばなされているようですが、確かにこの問題は、経済次元を超えて、文明史的意義をはらんでいるといってよい。ところで、アメリカ中国学会の重鎮であるコロンビア大学のウイリアム・T・ドバリー教授は、十年近く前、香港の中文大学で、一連の記念講演を行い、それを『朱子学と自由の伝統』(山口和久訳、平凡社)と題して上梓いたしております。その中でドバリー教授は、「為己之学(いこしがく)〈自分自身のための学問〉、「克己復礼(こっきふくれい)」〈自己の抑制と礼節への復帰〉、「自任」〈自らに道徳責任を負うこと〉、「自得」〈自分の力で何かを得ること〉などのキー・ワードを分析しながら、封建主義イデオロギーの典型とされてきた朱子学のなかにも、よく検討すれば、ヨーロッパの近代思想にも相通ずるような自由主義、個人主義の脈絡がたどれる、としております。詳細は略させていただきますが、お気づきのように、そこには「自」という言葉が頻出しております。「自」とは「自由」に通じ、また、「自分」や「自己」をも形成する言葉です。その基調をなすトーンは、個人の自律性といってよい。更に「為己之学」とは、学問は科挙のための受験勉強のように、他から言われてやるようなものではなく、まず自分自身に立ち返ること、つまり自己認識、自己理解を第一義としており、きわめて内向的、内省的なトーンに貫かれております。先ほどのランジェル博士のスピーチにもあったとおりであります。ドバリー教授は触れておりませんが、一見して明らかなように、この内省的個人の自律性という概念は、極めてデカルト的といってよい。かのデカルトも、中世スコラ哲学の崩壊の寄る辺なき混沌のなかにあって、徹底した自己省察を行い、ついに、有名な〝コギト〟(我思う、故に我あり)にたどりつき、そこを足場にして、一切の哲学的営為を成し遂げました。自らを律しつつ、独り、さっそうと我が道を征く彼の雄姿は、まことにヨーロッパ近代哲学の父の名にふさわしいものでした。と同時に、デカルト哲学にあっては、徹底した個の自律性の貫徹はあっても「他者」というものが、ほとんどといってよいほど顔を出していない。そこが、中国思想にはらまれている自由主義や個人主義と徹底的に異なるところです。先に触れた「克己復礼」に見るごとく、そこでは、内省的自己が、転じて「礼」という社会の約束事を通じて「他者」と関わっていくという視点が、明確に打ち出されております。自由主義や個人主義といっても、中国のそれは、現実の一個の人間が、生き、活動している有機的な〝場〟としての社会が常に想定されている点において、ヨーロッパ思想と明確な一線を画している。私は、そこに中国伝統の優れて現実的なコスモス感覚、更に言えば人間及び社会がどうあるべきかという点への責任感覚、義務感覚といったものを見いだす一人であります。そうした点を踏まえ、ドバリー教授は〝ここには極端な個人主義は排除され、それに代わって、他者と最も親密に交わっているときの自己の姿こそ、真正の自己であるとする人格主義がその場所を占めている〟ことに論及しております。ここに言う「極端な個人主義」とは、いうまでもなく、社会の進展とともにその歪みを露に拡大してきたヨーロッパ個人主義をさしております。ちなみにこの点は、北東アジアの興隆に関心を寄せる欧米の識者たちが、等しく着目するところのようであります。『アジア文化圏の時代』を著した、フランスの中国学会の碩学L・ヴァンデルメールシュ博士も「西欧社会の超個人主義の含んでいる有害な偏向を摘発することにより、西欧人の自覚と反省を求めることを目的としています」(福鎌忠恕訳、大修館書店)と、著述の意図を語っております。もとより、ヨーロッパ的個人主義が、大きな歴史的意義をもち、相応の成果をあげてきたと言う流れは、決して否定されたり過小評価されてはならない。人権という極めて今日的な課題ひとつ取り上げてみても、二百年前のフランスの人権宣言以来、強大な国家権力からいかに個人の尊厳を守るかという人権思想と、それを支える個人主義なくして考えられないのでありマシ。こと、こうした人権感覚という点に関しては、日本人などは、欧米の人々に比べて、まだ遅れていることを認めざるを得ません。そのうえで、ヨーロッパ的個人主義のデメリットの側面に目をやれば「極端な個人主義」や「超個人主義」の欠陥は、国家と裸形の個人を対置し、個人の権利を強調するあまり、人間が生き、活動する有機的な〝場〟を、非常に不安定なものにしてしまう点にあります。フランス革命に典型的にみられるように、国家と個人との際立ちすぎる対置は、その中間の小規模、中規模の共同体を抹消する方向に作用する。国家権力の中央集権化と肥大化につれ、事実、社会はそのような経過をたどってきました。しかし、実際の生活にあっては、国家と個人が直に向き合う、いわゆる〝大状況〟などごくわずかであり、大部分の時間は家庭や職場、地域共同体などの〝小状況〟で営まれているわけです。他者の顔が見え、本当の交わりが成り立つのは、そうした〝小状況〟であり、従って、そこにあってこそ、我々は生きる喜びや実感を、心底味わっている本当の自分を発見できるのであります。その肝心の足場がぐらついているなかで、国家と対峙させられた個人は、ある場合は無力感でアノミー現象に陥ったり、ある場合はその反動で、全体主義のアジテーションの格好の餌食になってしまう。このことは、今世紀、我々が何度も目にしてきたことであります。◇中国の小伝説的名君・堯帝にまつわる〝鼓腹撃壌〟の故事は、おそらく現代の政治状況とは正反対のものであります。皆さま方がよくご存じのように、〝鼓腹〟とは腹をうつこと、〝撃壌〟とは木ごま遊びをすることであり、この世の楽しみ、謳歌する様を言う。自らの為政がうまくいっているかどうか不安になった堯帝が、ある日おしのびで町へ出、町の外れに来ると、白髪の老農婦が、〝鼓腹撃壌〟しながら歌っていた。 日出でて作(はたら)き日入りて息う井を鑿(ほ)りて田を耕して食う帝力我に何かあらんや!(後藤基巳・駒田信二・常石茂編『中国孤児物語』河出書房新社) 権力者の力など、私になんの関係があろうか——。何と健康でおおらかな現実肯定でありましょうか。私には、この素朴な言い伝えが、くだって欧米の真摯な知性が発掘した、優れて中国的な自由主義、個人主義を育んだ原基であるように思えてならない。もとよりそれは、文字どおり掘り起こされたもので、現実には、歴史の流れに埋没してきました。多くのリベラルな要因をはらんでいた思想が、なぜ開花しなかったのは、別角度からの解明を要する課題でありましょう。とはいえ、思想的遺産はあくまで遺産であります。中国三千年の歴史を貫くコスモス感覚、精神の位階秩序を形成しつつ、世界精神へと昇華しゆく原感覚ともいうべきものは、中国仏教や日本の大乗仏教に見られる円教的側面、つまり〝大いなる肯定〟にも通じるものであります。わたしはそこに、ドバリー教授やヴァンデルメールシュ博士が示唆するように、ヨーロッパ主導型文明の行き詰まりを打破しゆく、貴重な突破口が見いだせると信じております。かつて、マカオで青年時代の一時期を送った孫文は「民族と国家の永遠の地位を維持するとなると、道徳の問題になってくる。よい道徳があってこそ、国家は永遠におさまるのである」(『三民主義』上、安藤彦太郎訳、岩波文庫)と述べました。いうところの道徳とは、中国文明の「儀礼」的、「教礼」的側面ではなく、より深い原感覚に掉さしてこそ、可能となるでありましょう。同じように、貴大学の掲げる「五常」すなわち仁・義・礼・智・信のモットーもまた、こうした良き伝統の光が当てられたとき、二十一世紀への新たな指標として、更に装いもみずみずしく蘇ってくるのではないでしょうか。なお、この「五常」については、仏法のうえからも種々、意義づけております。そうした伝統に立って、僭越ではありますが、「五常」の現代的意味を考えるならば、まず「仁」とは、ヒューマニズム・人道への目覚めであり、広くは人類愛への目覚めといってもいいでしょう。「義」とは、エゴイズムの克服であります。世界は、互いの主権を尊重しつつも、自国中心主義を乗り越えて、「人類益」「人類主権」を指向していかねばならない転換期を迎えている。その意味で、世界市民の条件は、まさにこのエゴイズムの克服にある。また「礼」とは、他者の存在を認め、敬意を払うことであります。世界はさまざまな民族・国家の集合体であり、それぞれが独自の文化を保ち、アイデンティティーの核を形成している。それを認め、異なる文化を理解し、尊重することは平和共存の基本であります。そして「智」。知恵こそ想像の泉といってもいい。今、世界には国際紛争が多発し、環境問題等の地球的問題群が山積しています。その解決には硬直化した発想を打開し、柔軟で見ず三栖椎知恵を湧現し、それを結集していく以外にない。最後に「真」すなわち、〝誠実さ〟であります。不信を信へ、反目を理解へ、憎悪を慈愛へと転じていく根本は、〝誠実さ〟であることは論をまたない。策や方法では、信頼という友誼の大地を耕すことはできない。世界が互いに心を開きあうためには「信」こそ絶対の要請となるのであります。唐突のように思われるかもしれませんが、この「五常」という目徳を、巧まずして体現していた人物として、私は周恩来総理を思い起こします。私は、宗総理とは逝去の一年前、一九七四年十二月、第二次訪中の折にお会いし、また夫人の鄧穎超女史とは今に至るまで深い友誼を結んでおりますが、宗総理の振る舞い、言動は、自らを厳しく律する精神の風格に満ちておりました。当時、周総理は、病気療養されていたため、北京市内の病院での会見でありましたが、病気にもかかわらず、わざわざ玄関まで出迎え、帰りには見送ってくださった。私はその礼節に心打たれたことを今でも鮮明に覚えております。会見の部屋も質素でした。また「いまの中国は経済的に豊かではありません」と率直に心情を吐露されながら、平等互恵にして世々代々にわたる人民の有効を展望されていた。私は、そこに和を重んじ、自らを抑制する謙虚の美と、信念に徹する強靭な意志力を垣間見た思いでした。その思いを込めて、創価大学には「周桜」と「周夫婦さくら」を植え、亡き総理を偲んでおります。さて、皆さまもよくご存じのように、中国南宋の宰相・文天祥は、このマカオに広がる海を詠った、有名な『零丁洋を過ぐ』の詩を残しております。文天祥は、科挙の首席合格者であり、知勇兼備の若き闘将であった。彼は侵攻してきたモンゴル王朝の元と果敢に戦い、最後まで抵抗するが、ついに捉えられる。元は、その力量、人柄を評価し、懐柔し帰順を迫る。そのとき彼が詠んだのがこの詩であります。 皇恐灘頭 皇恐を説き、零丁洋裏 零丁を歎ず。人生 古より 誰か死無からん、丹心を留取して 汗青を照さん。 ――あの江西の皇恐灘の急流のあたりで元軍に敗れたときは、あわて恐れたことを語るばかりで、この零丁洋にあっては、一人おちぶれ、捕らわれの身となったことを嘆くばかりである。しかし、人生にあって昔から死なない者があるだろうか。どうせ死ぬのであれば、せめて赤誠の真心を、この世にとどめて、歴史に輝かせていきたい――。(盧田孝昭『中国詩集』4、社会思想社、引用・参照)文天祥はこの詩をもって、死を覚悟で懐柔の誘いを断り、やがて、刑場の露と消えていきます。しかし、最後まで、節を曲げることなく、真偽に生きた文天祥の名は、英雄として今なおひときわ歴史に輝きを放っております。このエピソードが、今日なお私たちの胸を打つのは、立場を超えて、その人間としての心情が普遍であるからであります。文天祥がその魂をとして我が道を生きることを歌った大海を望み、若き孫文が封建中国の改革のための運動に身を投じたこのマカオは、大いなる理想に向かう青年の立志の天地にふさわしい地であります。最後に、東亜大学に学ぶ皆さまが、この新しき英知の港から、新しき世界精神、人類意識の開道者として、二十一世紀の平和の大海原へ船出されゆく姿を思い描きつつ、私の記念講演とさせていただきます。ありがとうございました。 【創造する希望池田先生の大学・学術機関講演に学ぶ】創価新報2022.5.18
September 27, 2023
コメント(0)
-
世界市民の連帯で人類史の夜明けを
世界市民の連帯で人類史の夜明けを中国・復旦大学1984年6月9日人間こそ歴史創出の主役私は数日前、北京大学において、「平和の王道――私の一考察」と題して、講演を行ってまいりました。引き続き、この八十年近くの伝統ある復旦大学においても、このような機会を与えられたことは、誠に光栄であり、名誉学長の蘇歩青先生、また学長の謝希徳先生はアメリカを訪問されているとうかがっておりますが、ご列席の諸先生方、学生の皆様に心から感謝申し上げるものであります。北京大学での講演では、中国文明の〝尚文〟の伝統が、戦争や武力の行使に走りがちな傾向を抑制する力をもたらす伝統的な思考様式を加えさせていただきました。そこで今回はテーマをしぼり、私が最も注目しながら、北京大学ではほとんど触れることのできなかった歴史館の問題、人間の生き方にいかなる意味を持つのかという点について、若干申し上げたいと思います。◇さて、歴史に対する関心の深さという点では、中国は、世界に冠たる存在であります。同じ東洋でありながら、例えばインドなどの歴史への無関心とは、あまりにも対照的であります。古来、中国の人々は執拗なまでの関心と努力を払って、歴史上の出来事を文物に書きとどめていきました。書物の多いことをさして「汗牛充棟」――重さは牛が引いても汗をかくほどで、かさは棟につかえる――という言葉がありますが、中国の史書の類はまさに「汗牛充棟」そのものであります。また、中国にあっては「温故知新」――故(ふる)きを温(たず)ねて新しきを知る、あるいは「借庫説今」――古を借りていまを説く、などの諺が、長年、尊重されてきました。それらは、歴史というものが、現在を映しだす鏡として、また、現代を照らし出す光源として受け止められてきた証左と考えられるのであります。新中国における歴史観については、私は詳しく知りません。たしかに革命後の中国で、あらゆる分野で、人民大衆が原点に据えられており、故・毛沢東住席が話された「人民、ただ人民だけが、世界の歴史を創造する原動力である」(毛沢東選集刊行会編訳『毛沢東選集』7、三一書房)という歴史観のうえに立って、大衆に奉仕する〝民衆史観〟ともいうべき構造をとっているように思えてなりません。その点、堯帝や舜帝の神話時代を最高の範とする、いわば〝帝王史観〟が主流をなしてきた、儒家流の伝統的な歴史館とは、明確なる一線を画していることと思われます。とともに、歴史意識の深層に、数千年間にわたって蓄えられてきた伝統は、良い意味でも悪い意味でも、そう簡単に変わるとは思われません。だからこそ、その真相を凝視した魯迅は、人間が人間を食う――〝食人〟という着想から、人間変革の困難さと重要性の訴えたのでありました。私の着眼からするならば、歴史を尊び、歴史的経験を鏡とも光源としても、現在を生き未来を方向づけていくという、良い意味での伝統的な歴史意識は、数千年という長きにわたって、今なお脈々と息づいているように思えてならないのであります。貴国の文物や人々のスピーチには、しばしば古典からの的を射た引用がなされていて、いつも私は感心させられますが、それは、歴史がある種の教訓性をはらみつつ、現在に生きていることを物語っていると思えてならないのであります。◇ところで、そのような歴史の捉え方は、十八世紀以降のヨーロッパ、とくに十九世紀の歴史主義の潮流の中では、はっきりとした輪郭を与えられた歴史観や歴史意識とは明らかに異質なものであります。たしかに歴史主義の潮流は、実証性や客観性という点で、一定の成果を収めてきたと思われます。しかし、そこで何よりも重視されたのは、歴史を客体化して、自然と同じように客観的考察の対象とする、学としての整合性でありました。その結果、歴史そのものが、ある種の法則性を帯び、人間との生き生きとした関係を断って、独り歩きを始めたわけであります。ヨーロッパ近代文明の危機を鋭く予見した、かのドイツのニーチェは「われわれは歴史を生と行動のために使用するのであって、生と行動からの安易な離反のために使用するのではなく、また我欲的生と怯懦な卑劣な行動を曲飾するために使用するのでは全然ない」(『反時代的考察』小倉志祥訳、『ニーチェ全集』4所収、思想社)と言っております。ニーチェの言う「生」とは「人間」と置き換えることができると思います。歴史観のみが独り歩きし「生」や「人間」が、それを生みだした主役でありながら、かえってわき役に追いやられている主客転動こそ、ニーチェの攻撃してやまないものでありました。歴史がよりよき現在と未来のための、つまり「生」と「人間」のための糧とされてきた中国の歴史意識は、そうしたニーチェの攻撃とは、無縁の次元に位置していると思います。司馬遷に象徴されるように、中国の歴史への関心のあり方は、冷たい客観的な法則性を追うのではなく、人間がいかにしていくべきかという激しい主体的、倫理的問いかけを、常にはらんでいたのであります。『史記』の中の有名な一節を取り上げてみたいと思います。これを読むと私は、常に勇気と感動にあふれるのであります。「周の文王が殷の紂のため捕らわれの身となったとき『周易』を著わし、孔子がわが道のおこなわれざることを知って『春秋』を作り、屈原が楚王に追放せられて『離騒の詩』をうたいあげ、左丘が盲目となって『国語』を製し、孫子が脚切りの刑にかかって兵法を編集し、呂不韋が蜀に流されてから『呂氏春秋』を伝え、韓非子は秦始皇に囚えられてから『説難』『孤憤』を書いた。美しい『詩』の三百篇すら、聖人賢者が時勢に概してうたったものが大部分を占めているのではないか」(貝塚茂樹『史記』中央公論社)とあります。つまり、苦難や迫害こそ、すぐれた史書、文物を生み出す母体であったということであります。だからこそ歴史は、人々の幸福と不幸、喜びと悲しみ、善と悪――総じて人間の運命への肺腑を突くような問いかけとなったわけであります。それはまた、大著『史記』を著す司馬遷のモチーフでもあったわけであります。歴史が人間の運命への問いかけであるということは、歴史的記述といえども人間の外にあるのではなく、常に内面にあるということと考えられます。極論すれば、歴史は即自分史であるといえると思うのであります。そこには、一切の運命をわが身に受け止め、毅然としてたじろがぬ一個の自立した人間像が浮かび上がってきます。仏法に「八万四千の法蔵は我身一人の日記文書なり」(全五六三・新七一三)という言葉があります。八万四千とは、具体的な数ではなく、多数を意味し、「八万四千の法蔵」とは、釈尊が一生の間に説いたすべての法門をさします。その膨大な法門の一切が「我身一人の日記文書」、すなわち、一個の人間生命の働きとして考えられているのであります。次元は違いますが、ここでもまた、毀誉褒貶にながされるのではなく、雄々しく運命に立ち向かいゆく、自立の人間観、世界観の確立が促されているのであります。ともあれ、歴史の流れは、一刻もとどまってはいません。貴国の大詩人・李白の言葉を借りれば、「天地は万物の逆旅にして光陰は百代の過客」であります。人間とりわけ民衆が、脇役に甘んじてきた歴史に、一日も早く終止符を打たなければなりません。それには〝タテ〟に自立の人間像を掘り下げ、確立するとともに、〝ヨコ〟には、そうした人間と人間とを結ぶ世界市民の連帯の波を、千差万別と広げていかなければなりません。時代の急速な流れは、〝宇宙船地球号〟の時代を迎え、世界はあらゆる意味で緊密な一体化を強めつつあります。中国の歴史であれ、日本の歴史であれ、世界史の運命と切り離しては考えられないのが現代の状況であります。明暗のめまぐるしく交差する歴史の流れを、希望あふれる世紀へと切り開いていくには、人間こそ主役であるという歴史観の確立が必要であります。それとともに、宇宙船地球号という世界市民の連帯が必要になってきたことを、お互いに確認する時代に入ったことを強く自覚していかねばならないと思うのであります。最後に、今までも、またこれからも、中国そして世界の逸材を八十年近く生み出してこられた復旦大学のますますの大興隆を、切に切にお祈り申し上げ、私のつたない話とさせていただきます。 【創造する希望「池田先生の大学・学術機関講演に学ぶ」】創価新報2022.4.20
August 28, 2023
コメント(0)
-
心と心の回路の開放が平和を構築
心と心の回路の開放が平和を構築グアダラハラ大学1981年3月5日 メキシコの詩心を思うこと私は創価大学の創立者として、また真の仏法を基調とした平和、文化、教育を推進しゆく創価学会インターナショナル会長という立場で、多くの国々を回っております。このたび私は十六年ぶりで帰国を訪問いたしました。約一週間の日程ではありましたが、ロペス・ポルティ―ヨ大統領閣下をはじめ、ソル・ファナ最高学術院長のアリア・ピラール・ガリンド・ロペス・ポルチーヨ・デ・コルデロ女史、セラーノ・メキシコ国立自治大学総長などとの対話を通し、文化、教育、平和の日墨(日本・メキシコ)交流の意義を、ささやかではありますがとどめることができました。また民衆次元での日墨合同の文化祭を開催することもできました。本日が貴国訪問の最終日であります。この忘れ得ぬ日に、貴大学において、講演できます機会をお与えくださったエンリケ・サンブラーノ・バイゼ早朝に感謝するとともに、聴講してくださる教授、学生諸君に敬意を表するものであります。私は今までに、北京大学において「新たな民衆増を求めて」という題で、モスクワ大学では「東西文化交流の新しい道」、カルフォルニア大学ロスアンゼルス校では「二十一世紀への提言」という題で講演をいたしました。本日は、メキシコと日本との古くからの友好の歴史を振り返りながら「メキシコの詩心に思うこと」、付随して「メキシコ文化の指標」とも言うべき論題で話をさせていただきます。更に、急速なる国際化の時代に入って、共々に平和を希求し、志向するという視点も含めながら、概観的に約一時間にわたって述べさせていただきます。ご存じとは思いますが、メキシコの国と日本の国との関係は、決して新しいものではありません。その関係は、すでに十七世紀の初め、伊達政宗が、家臣・支倉常長らをローマに派遣した際、当時はスペイン統治下であった貴国メキシコを経由して統治に向かったことは歴史的事実であります。最近日本で、著名な作家が支倉常長をモデルにした『侍』という小説を著し、大きな話題を呼びました。私も早速手にして、当時の貴国のありようをしのんだものです。また一八八八年、日本が貴国と結んだ日墨条約が、近代日本が外国と最初に結んだ対等の条約であることも、ご存じのとおりであります。特に第二次世界大戦以後は、政治、経済、教育、文化の側面で、両国の関係は著しく深まってまいりました。そのこと自体は大変に喜ばしいことですが、それによって国家関係の基盤である民衆と民衆との相互の理解がどれだけ深まったかというと、まだまだ緒についたばかりといっても差し支えない。したがって私は、両国をつなぐ心と心の架橋作業に、平和、文化、教育という次元で、これからも全力を挙げていく決心であります。❑さて、昨年末、日本の横浜で、アジア平和研究国際会議が開かれました。これにはアジアをはじめ世界の各地から多くの識者が参加されましたが、その中にイヴァン・イリッチ氏がおりました。皆さまがとご存じとことと思いますが、イリッチ氏は現在、メキシコ国際文化資料センターの所長をされています。氏の思想については、賛否両論、多くの議論がなされており、私も、いわゆる『脱学校の社会』などに盛られた論旨には、ラジカルすぎてそのまま賛同しかねる面もあるのですが、イリッチ氏が日本の新聞紙上で語っていた言葉には、非常に強い印象を受けました。すなわちイリッチ氏は〝私の関心事は、人々が詩的になり、冗談を言い、笑えるようになることだ〟というのです。さりげない表現ですが、教育や文化、平和を考える際、一つの重要なポイントではないかと私は思います。詩心(スピリット・オブ・ポエム)そして笑顔――。それは何よりも、心と心の回路の開放を意味しております。平和といい文化交流といっても、肝心の心の回路が開かれていなければ、絵に描いた餅に等しい。有名なユネスコ憲章の「戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心の中に平和のとりでを築かなければならない」との一節も、そのことを意味していえるといえましょう。ところでこのウイーン生まれの学者イヴァン・イリッチ氏は、なぜこのように詩心や笑顔ということを強調するのか。そこには多くの要因が挙げられるでしょう。これはあくまで私の推測でしかありませんが、その要因の重要な一つとして、イリッチ氏が1960年に当地に移住して以来のメキシコ体験が挙げられるのではないかと思うのであります。それというのも、メキシコの歴史や文化について、私のささやかな見聞を通して鮮やかに浮かび上がってくることは、メキシコの人々の詩心や笑顔に通ずる陽気さというか、一種独特の心の豊かさであるあるからであります。〝太陽と情熱の国〟メキシコのイメージは、ともかく陽性であります。私は、それが単なるイメージだとは思っておりません。祭りが好きで人生何事につけても楽しんでいこうという志向の強いメキシコの人々は、どんな厳しい試練に直面しても、心根の部分では、優しさや明るさ、あるいはそれに裏付けられた勇気を手放すことがなかったのではないでしょうか。私は、アメリカのジャーナリスト、ジョン・リードがメキシコ革命を活写した優れたルポルタージュ『反乱するメキシコ』(野田隆・草間秀三郎・野村建朗訳、筑摩書房)の中で紹介している一つのエピソードが思い出されてなりません。一九一三年、メキシコは政府軍と革命軍が入り乱れて、混乱の極みにありました。そのようなさなかにあって、リードは危険を冒してメキシコ入りをする。ちょうどアメリカとの国境線近くで、戦火を逃れてアメリカへ避難してくる多くの難民と出会う。国境には、武器を所持していないかどうかを調べるための監視人が置かれていた。「男女を問わず、必要もないのに念入りで残酷な身体検査が行われた。私も立っていると」――とリードは述べています――「一人の女がスカートを平気で桃のあたりまで繰り上げながら浅瀬を渡って来た。女は分厚いショールをまとっていたが、それは中に何か隠してあるかのように前の方がふくらんでいた。『こら、待て!』税官吏がどなった。『ショールの下に何をかくしているんだ。』女はゆっくりと着物の前をあけ、落ち着き払って答えた。『セニョール、私にも分かりませんわ。女の子かもしれないし、男のかもしれませんわ。』」(爆笑)修羅場に臨んでこのような巧まざるユーモアや冗談を口にできるということは、男も顔負けの胆力というか、まことに見事な対応と言わざるを得ません。もう一つ、私の心に残っている、メキシコ革命にまつわるエピソードを挙げさせていただきます。それは、革命の英雄として、今なおメキシコの人々に愛され、親しまれているパンチョ・ヴィリャに関するものであります。一九一三年三月、要衝トレオンをめぐる攻防の際、ヴィリャの率いる革命軍は、トレオン北西のイェルモに到着。早速、「攻撃の準備が整えられた。ところが、かんじんのパンチョ(=ヴィリャ)のすがたが見えない。指揮官たちはイライラして彼を待った」。四日後、ようやくヴィリャが「泥まみれのすがたで突然現れた。彼は、進軍の途中でだれにも言わず、友人の結婚式に出席するため横道にそれて、メキシコ式の祝宴で夜も昼も踊り狂っていた」というのであります(増田義郎『メキシコ革命』中央公論社、引用・参照)。今は時代が違うし、理由もなく学業をさぼったりしたら、総長にしかられますよ。(爆笑)私はある本でこのエピソードを読み、思わず微笑せずにはいられませんでした。軍律という枠に組み込むことのできない人間性の横溢、陽気でロマンチックで勇猛果敢なヴェリャの人となりが、彷彿と踊っております。たしかにヴェリャその人のキャラクターもあったでしょうが、同時に、先に申し上げたアメリカ国境での、一夫人の振る舞いとも深いところでつながっている〝メキシコなるもの〟が、私には感じられてなりません。誠につたない表現で恐縮ですが、『詩心や笑顔に通ずる陽気さというか、一種独特の心の豊かさ」と申し上げたのも、その意味なのであります。それはいかなる、意味においても感傷的なものではありません。多くの革命と同様、メキシコ革命も、文字通り民衆の血みどろの死闘によって戦い取られたものであります。多くの婦人達でさえ、銃を取り戦闘に立ったことが、記されております。その戦いの過程で引き起こされた悲劇的な出来事も、枚挙に暇がないでありましょう。そうした中にあって、なおかつ失われなかった詩心や笑顔、ユーモアであっただけに、私はこれらのエピソードが、大地にしっかりと根をおろして、ことのほか尊いものに感じられてならないのであります。おそらく、そのような人間性に対するみずみずしい感受性は、自由や平等、独立といった優れた近代的な人権感覚へと昇華されゆく豊かな可能性の宝庫であったと、私は信じております。(拍手)話しは飛躍するようですが、一九六七年に「中南米比較地域条約」(ラテンアメリカにおける核兵器の禁止に関する条約)が結ばれました。その条約を履行するための国際機構であるOPANAL(ラテンアメリカ核兵器禁止機構)の本部はメキシコシティーに置かれており、これら一連の措置は、メキシコの人々の強いイニシアチブによって成ったと聞いております。私はこのメキシコの選択を、米ソ両大国が主導する核拡散防止条約への対応といった、政治次元でのみ論じてはならないと思っております。もっと深く、メキシコの人々の自主的、主体的な選択に関わるものではないでしょうか。言うまでもなく、核兵器は史上かつてない残虐な兵器であります。これほどの人間性への冒涜はなく、核兵器の使用が人類の絶滅を招きかねないゆえ、私も折あるごとに、その禁止と廃絶を訴えてまいりました。三年前に開かれた、第一回国連軍縮特別総会の際にも、ワルトハイム総会議長あてに書簡を送り、核軍縮及び廃絶への幾つかの提言をしてまいりました。その中に、国連のイニシアチブによる非核ゾーンの設置、拡大という項目を含めておいたのですが、その意味からも、メキシコの人々がラテンアメリカ地域の非核化に努力を続けられていることに、深く敬意を表するものであります。なぜそうした努力を自主的、主体的な選択と申し上げるかといえば、どれだけ明確に意識化されているかは人間が人間らしく生きるための骨格ともいうべき、自由、平等、独立などに対するメキシコの人々の鋭い人権感覚が投影されていると思うからであります。その人権感覚は、ファシズムと戦うスペイン人民戦線に、最後まで温かい支援を送り続けた連帯意識と、決して異質なものではないはずであります。たしかに自由といい、平等、独立といっても、それを完全に実現することは至難の業であります。近代メキシコの歴史も、多くの曲折をたどった試行錯誤の過程であったといってもよいかもしれません。政治、経済面をはじめ、課題は数多く残されており、挙げて皆さま方の今後の努力と建設作業にかかっているわけであります。しかし私は、三百年にわたるスペイン統治下の凍てついた大地のもとでしぶとく生き続け、独立や革命を経て鍛え上げられてきたメキシコの人々のアルマ(魂)は、将来にわたって、必ずや見事な実を結ぶであろうことを信じてやみません。それは、貴国と日本はもとより、ラテンアメリカをはじめとする第三世界、ひいては人類社会へと、巨大な貢献をなしゆくでありましょう。あたかも、メキシコ・ルネサンスの旗手であったリベラやオロスコ、シケイロス、タマヨ等の芸術が、世界的な衝撃波を呼んだように――。貴国をよく知る日本の画家によると、客を迎える時のメキシコ流のあいさつに「この家は、また、あなたのお住まいでもあります」というのがあるそうです。誠に人情味あふれたやりとりであり、お国ぶりがよくうかがえるような気がいたします。仏典にも〝二つの蘆束〟と題する同じような比喩が説かれております。蘆とはイネに似て細かく長い茎をもつ植物で、蘆束はそれを数本束ねたものです。釈尊の門下でも、智慧にかけては並ぶもののないといわれた舎利弗という人が、その譬えを使ったと伝えられているのです。「例えば、二つの蘆束があるとしよう。それらの蘆束は、相依っている時には立っていることができる。同様に、これがあることによって、かれがあり、かれがあるから、これがあるのである。もし、二つの蘆束のうちの一つを取り去れば、他の蘆束も倒れるであろう。同じく、これがなければ、かれもなく、かれがなければ、これもないのである」と。(相応部経典)この譬喩は、人間が独りで生きることはできず、互いに依存し助け合って生きていくことの大切さを教えているのであります。「この家は、また、あなたのお住まいでもあります」との、招待の際の貴国のあいさつにも、同じような深い生活の知恵が含まれていると思うのであります。ともあれ国際化時代を迎えて、メキシコと日本に限らず、世界各国の交流は、今後、一案と活発化していくことでありましょう。国と国、民族と民族との間に平等互恵が徹底されなければならず、それには民族相互の心の交流が不可欠なときを迎えております。今回の私どもの気候訪問が、そのためのささやかな一石にともなればと念願いたします。最後に、きょうおあつまりくださった二十一世紀に立ち向かいゆく、知性と情熱に燃えた学生の皆さん方が、メキシコ国家の柱となるとともに、一人一人が使命と責任あるリーダーとなって、存分に寄与されんことを祈り願って、私の講演を終わりとします。(大拍手) 【創造する希望池田先生の大学・学術機関講演に学ぶ】創価新報2022.3.16
July 9, 2023
コメント(0)
-
平和と人間のための安全保障㊤
平和と人間のための安全保障㊤ ハワイ 東西センター 199年1月26日 内なる変革こそ人類の未来を開く王道本日、まことに輝かしき伝統と傑出した業績を誇る、この東西センターにおきまして、講演の機会をいただきましたことは、私のこの上ない光栄と思っております。ご尽力くださったオクセンバーク理事長並びにマツナガ平和研究所のグアソン所長をはじめ、御関係者の方々に深く感謝申し上げるものであります。ありがとうございました。また、このたびの阪神・淡路大震災に対し、諸先生方から真心こもる、お見舞いの励ましをいただきました。この席をお借りいたしまして、謹んで御礼申し上げます。万人を魅了してやまない、ここハワイの天地には、「人間」と「自然」との抱擁があり、「東」と「西」との握手があります。「文化の多様性」の調和があり、「伝統」と「近代化」との融合があります。私は、ハワイこそ、「平和」と「人間」という人類の根本課題を探求する格好の舞台であると信ずる一人であります。私自身、世界への旅を、ハワイより開始いたしました。一九六〇年——奇しくも、貴センターが創設された、その年のことであります。日本の軍国主義によって、太平洋の回線という悲劇が刻まれた、このハワイから、人類の平和の旭日を輝かせていきたい——これが、青春の日より、私が抱いてきた熱願でもあります。 翻って、眺望すれば、二十世紀は、一言でいって、あまりに人間が人間を殺しすぎました。「戦争と革命の世紀」と形容されるように、二度にわたる世界大戦や相次いだ革命など、今世紀は、かつてない血なまぐさい激動の連続であったといってよいでしょう。科学技術の発展が、兵器の殺傷能力を飛躍的に高めたこともあって、両度の世界大戦など死者は約一億人にも及び、その後の礼賛かから現在に至るまで、地域紛争等による犠牲者も、二千万人以上にのぼるといわれております。とともに、「南」と「北」の貧富の差は拡大し続け、約八億人もの人々が飢えており、幾万の幼き尊い命が、日々、栄養不良や病で失われております。この構造的暴力から、決して目をそらすことはできません。さらに多くの識者が危惧するように、東西を問わず蔓延する〝精神の飢餓〟は、物質的な繁栄の空虚さを物語っております。こうした計り知れない人柱をもって、二十世紀の人類が贖ってきたものは、一体何だったのか——世紀末を迎え、一段と混迷の度を加えつつある現状を前に、だれしも痛恨の上を抑えることができないでしょう。私の胸には、大乗仏教の真髄たる「法華経」の一文字が迫ってくるのであります。「三界は安きこと無し 猶火宅の如し 衆苦は充満して 甚だ畏怖す可し」(『妙法蓮華経』創価学会版191㌻)——この現実世界は、安心できるところではない。ちょうど燃えている家のごとくである。多くの苦が充満しており、はなはだ恐るべきである——と。苦悩と恐怖の苦脳に焼かれる民衆への限りなき同苦であります。この悲惨な絵巻を直視しつつ、「法華経」には、こう宣言されております。「応に其の苦難を抜き、無量無辺の仏の智慧の楽を与え、其をして遊戯せしむべし」(同173㌻)——まさに、人々の苦しみを抜き取り、無量無辺の「仏の智慧」の楽しみを与えて、遊戯できるようしてあげたい——と。ここに、仏法の出発点があります。そして、それは、この現実社会の真っただ中に、安穏なる楽土を断固として築かんとする、ダイナミックな行動へと脈動していくのであります。その基軸は、あくまでも、民衆一人一人の生命の変革による「生活」と「人生」の蘇生であります。私の恩師である戸田城聖先生創価学会第二代会長は、これを「人間革命」と宣言したしました。思えば、十九世紀の進歩主義思想に酔いしれた人類は、社会及び国家の外的条件を整えることのみ狂奔し、それをもって幸福への直道であるかのごとき錯覚に陥ってしまったのであります。しかし、「人間」それ自身の変革という根本の一点を避けてしまえば、せっかくの平和と幸福への努力も、かえって逆効果となってしまう場合さえある。ここに、二十世紀の最大の教訓があったとはいえないでありましょうか。大変、威を強くしたのは、安全保障問題の権威者でもあられるオクセンバーグ理事長も、私と同じような感触を持っておられるということであります。昨年秋、東京でお会いした際、理事長は、こう述べておられました。「——精神が空洞化すると、人々は『不安』をもちます。『安定』できない。一人一人が『安心』を感じない。これでは、国家は人々の真の『安全』を保障できません。——真の安全保障は、国家だけでなく、分化そして個人まで、その視野に入れなければなりません」と。私も、全く同感であります。 いかなる困難、悪条件にも揺るがない確たる内面世界、すなわち不動の〝汝自身〟を築き上げていく。その内なる生命の変革——すなわち「人間革命」から、社会の変革を志向していくことこそ、「恒久平和」の道を開き、「人間のための安全保障」を可能ならしむる王道であると、私は思うのであります。 「知識」を正しく使う「智慧」の開発が重要いかなる困難にも揺るがぬ〝汝自身〟を築け差異を乗り越える哲学が時代の要請 こうした観点に立って、私は、二十一世紀へ向け不可避と思われる発想の転換を、第一に「知識から智慧へ」、第二に「一様性から多様性へ」、そして第三に「国家主権から人間主導へ」という三点にわたって、提案してみたいと思います。まず第一は、「知識から智慧へ」という命題であります。私の恩師戸田会長は、「知識を智慧と錯覚しているのが、現代人の最大の迷妄である」と鋭く見破っていりました。確かに、現代人の知識量・情報量は五十年前、百年前に比べて飛躍的に増大しておりますが、それがそのまま幸福をもたらす智慧につながっているとは、とうてい言えません。むしろ「知識」と「智慧」のはなはだしいアンバランスが不幸をもたらす場合があまりにも多い。それは、近代科学の粋が核兵器に直結していることや、先ほど申し上げた「南北の格差」の広がりなどに、如実に表れております。空前の高度情報化社会を迎えた今、膨大な知識や情報を使いこなしていく「智慧の開発」は、いよいよ重大な眼目となっているのではないでしょうか。例えば、発達した通信技術は、民衆の「恐怖」と「憎悪」を煽るために悪用される場合もある。その一方で、教育の機会を世界に拡充するために活用することもできます。それを分かつのは、人間の「智慧」と「慈愛」の深さなのであります。仏法は、一貫して、人間生命の慈悲に基づく「智慧」に焦点を当ててきました。私どもの信奉する仏法に、こういう一節があります。「仏教を習ふといえども心性を観ぜざれば全く生死を離るる事なきなり、若し心外に道を求めて万行万善を修せんは譬えば貧窮の人日夜に隣の財を計へたれども半銭の得分もなきが如し」(御書383㌻)——仏教を習ったとしても、自分自身の心の本性(仏性)を内観しなければ、全く、障子の苦しみから離れることはできない。もし、心の外に道を求めて、万行万善を修めたとしても、それは、例えば貧窮している人が、日夜にわたって、隣の人の財産を数えたとしても半銭の得もないようなものである——と。仏教をはじめとして、総じて東洋的思考の特徴は、一切の知的営為が、「自己とは何か?」「人間いかに行くべきか?」と言った実存的、主体的な問いかけと緊密に結びついて展開されて点にあります。この一文も、その象徴的事例といえましょう。最近、水などの資源を巡る地域紛争が憂慮されておりますが、それに関連して、私が思い起こすのは、故郷での水争いに対して示した釈尊の智慧であります。——釈尊が、布教のため、故郷の一帯を遍歴していた折のことである。旱魃のため、二つの部族の間を流れる川の水量が乏しくなり、争いが起こった。彼らは、互いに一歩も譲らず、武器を手に、流血も辞さないという事態となった。まさに、そのとき、釈尊は、自ら分け入って、こう呼びかけたのであります。「殺そうと闘争する人々を見よ。武器を執って打とうとしたことから恐怖が生じたのである」(『ブッダのことば』中村元訳、岩波文庫)武器をもつからこそ、恐怖が生ずる――この明快なる言葉には、皆の目を覚まさせる響きがあった。人々は武器を捨て、敵、味方ともに一緒になって、その場に腰をおろした。やがて釈尊は、目先の〝いさかい〟よりも、さらに根源的な恐怖である「生死」について語り始めた。だれびとも避け得ぬ「死」という最大の脅威を、いかに打開し、安穏の人生を生きゆくかー—人々の心に染み入るように、釈尊は訴えいったというものであります。 「小我」を打ち破り「大我」へ——生命尊厳の仏法の英知にその源泉が 確かに、現代の複雑な葛藤と比較すれば、素朴にすぎるエピソードであるかもしれません。旧ユーゴスラビアを巡る紛争にしても、そのルーツをたどると、二千年近くもさかのぼってしまう。その間、東西キリスト教会の分裂もあり、オスマン・トルコによる征服あり、今世紀には、ファシズムやコミュズム(共産主義)による蹂躙ありで、民族や宗教がらみを敵意は、想像を絶する根の深さ、すさまじさであります。少し、その経緯をたどっただけでも、それぞれの勢力が、歴史的な見地から差異を強調し合い、自己の正統性を言い立てていれば、とても収集がつきません。しかし、だからこそ、釈尊の勇気ある対話が垂範するごとく、人間を分断するのではなくして、人間としての共通の地平を見いだそうとする智慧、すなわち、思い切った精神の跳躍が要請されているのではないかと思うのであります。そして、仏教は、そのための無限の宝庫でありうるでありましょう。仏典には、平和の英知の言句は、枚挙に暇がありません。例えば、日蓮大聖人の一文には、平和や安全の危機と、人間生命の内的な要因との連関について、こう洞察されていります。「三毒がうじようなる一国いかでか安穏なるべき(中略)飢渇は大貧よりをこり・やくびようは・ぐちよりをこり・合戦は瞋恚よりをこる」(御書1064㌻)——貪り、瞋り、癡かさという三毒の生命の毒が強盛な国が、どうして安穏でいられようか。……飢饉は、激しい貪りの心から起こり、疫病は癡かさから起こり、戦争は瞋りの心から起こる——と。こうした欲望や憎悪にとらわれた、個人的自我としての「小我」を打ち破り、民族の心の深層をも越えて、宇宙的・普遍的自我である「大我」へと生命を開き、充溢させていく——その根源こそ、仏法が明かして智慧なのであります。この智慧は、どこか遠くにあるのではない。「足下を掘れ! そこに泉あり」というごとく汝自身の胸奥に開かれゆく「小宇宙」そのものに厳然と備わっているのであります。そして、その智慧は、人間のため、未来のため、勇猛なる慈悲の行動に徹しゆくなかに、限りなく湧きいずるものであります。この「菩薩道」を通して勲発される智慧をもって、エゴイズムの鉄鎖を断ち切っていく――。そのとき、もろもろの知識もまた、地球人類の栄光の方向へ、生き生きと、バランスよく回転始めるのではないかと私は考えるのであります。 【創造する希望「池田先生の大学・学術機関講演に学ぶ」】創価新報2021.12.15
April 9, 2023
コメント(0)
-
「ヒューマニズム」の世紀へ㊦
「ヒューマニズム」の世紀へ㊦インド ラジブ・ガンジー現代問題研究所1997年10月21日しかし、一口に「ヒューマニズム」と言っても、中身は一様ではありません。ヒューマニズムの変遷については、さまざまに分析できますが、近代市民社会のエートス(基本精神)となったのは、ルネサンスと宗教改革を経て、西欧を中心に形成された「個人主義的ヒューマニズム」であると言えましょう。十九世紀後半に、その矛盾と脆弱さが露呈するにつれて、施行されたのが、「社会主義的ヒューマニズム」の試みであります。これらの近代ヒューマニズムは、確かに、中世的な〝絶対者の楔〟から、人間を開放するもであったかもしれない。ところが、解放さてれはずの人間は、 今度は、自らの偏狭なエゴイズム、いわば〝小我〟に隷属していったのであります。欲望に振り回される「欲望の奴隷」になってしまった。その弊害は、社会の退廃と環境破壊、貧富の拡大という人類的課題として噴出してしまったのであります。さらに、さまざまな原理主義の台頭に象徴されるように、〝ポスト・イデオロギー〟の人類史は、未曽有の試練に立たされているといっても決して過言ではありません。この局面を、どう打開するか。はつらつたる、平和な「地球文明」の創造へ、どう踏み出していくか。そのための原動力は、何か。私は、行き詰った近代ヒューマニズムを超えて、〝コスモロジー(宇宙観)〟に立脚したヒューマニズムを提唱したいのであります。なぜなら、イデオロギーというものは、「二元対立的」であり、どうしても他者を「差別」し「排除」しがちです。これに対して、コスモロジーは、より深い次元から、「包括的」に、あらゆる他者を受用する「寛容」の特徴をもつからであります。その好例がアショーカ大王の「ダルマというヒューマニズムの治世」であります。それは大王の根本原則に、端的に表れております。その第一は「不殺生」です。その第二は「互いに敬え」です。不殺生については、人間以外の生物にも拡大して論ずるべきでありますが、私は少なくとも、「人間は人間を絶対に殺してはいけない」ということを、二十一世紀の〝人間憲章〟の冒頭に掲げるべきであると主張したいのであります。これまで、そして今も、「正義」の名のもとに、どれほど多くの血が流されたことでありましょうか。近代ヒューマニズムの象徴であったフランス革命では、多くの無辜の人々が断頭台に消えました。また社会主義的ヒューマニズムが、実験の過程で、当初の志に反して、何千万という人々を死に至らしめました。これも今世紀の厳然たる史実であります。この悲劇を断じて繰り返してはならない。今、求められる「ニュー・ヒューマニズム」の第一項目は絶対に、「殺すなかれ」の黄金律でなければなりません。「殺」と暴力を伴う〝正義〟は、いかなる論理で装うとも、全部、にせものの正義であります。タゴールが一生涯、叫び続けたように、「いけにえ」を求める神は、偽りの神なのであります。 では、これまでの「ヒューマニズム」の脆弱さは、どこに由来するのでありましょうか。精緻な分析をする席ではありませんので略させていただきますが、その根本は「人間への不信感」ではないでしょうか。「人間への不信」は、自己に向けられれば対話の拒否となり、暴力となるからであります。不信は不信を生み、憎悪は憎悪を生む。限りなき流転に歯止めをかけるものは、一体、何か。それこそ「一人の人間生命は、大宇宙と一体の広がりをもち、最高に尊貴なものである」と見る「宇宙的ヒューマニズム」であると思うのであります。その思想は、貴国のウパニシャッドの賢人や釈尊の教えに結実しております。釈尊の教えの最高峰である「法華経」は。その真髄と言えましょう。法華経は人々に、「差異へのこだわり」を捨てて、共通の「生命の大地」を知ることを教えました。その大地に立てば、「差異」は対立をもたらすものではなく、豊かさをもたらすものとなります。「法華経」の薬草喩品では、多種多様な草木が、同じ雨によって潤わされ、土井膣の大地に生い茂る譬えを説いております。しかし、ただ「ニュー・ヒューマニズム」を叫び、「宇宙的ヒューマニズム」を論じるだけであれば、それは観念論でありましょう。その「生命尊重」の思潮を現実に広げる方途を求めなければならない。その重大な柱が、私は「教育」であると思うのであります。宗教やイデオロギーだけで、「教育」がなければ、どうしても「独善」となるからであります。時代の趨勢として、宗教は個々人の自由という方向に向かうのでありましょうが、宗教を独善に陥らせることなく、正しい方向へ、平和の方向へ持っていく翼は、「教育」であります。タゴールが、彼の深き宗教性に、西洋人をも理解させる「普遍性」を与えたカギは、彼の教育であり、知性でありました。彼は自分のみならず、大学の設立をはじめとして、生涯、教育による人間開発へ努力したのであります。要するに、教育こそが人間を自由にするのであります。知性こそが、人類がそこで語り合える普遍的舞台であります。教育は人を偏見から解放します。暴力的熱狂から心を解放させます。宇宙の法則への無知から解放してくれるのは教育であります。また教育によってこそ、我々は無力感から解放され、自分自身への不信感から解放されます。自分の中に眠っていた能力を解放させ、「完全なるものに到達しよう」という魂の意欲を、思う存分に伸ばしていく。これが教育です。これは、なんと素晴らしい体験でありましょうか。自分への不信感から解放された個人は、他者を潜在する可能性を持信じるに違いありません。「彼は、今の見かけの姿が真の姿ではない。内に、もっと素晴らしい宝をもっているのだ」と信じ始めるのであります。表面の際にとらわれず、共通の「生命の大地」「生命の大海」を見抜く眼を与えるもの。それは教育であります。 「教育なき宗教」は独善に 釈尊の実践もまた、一面から見れば、教育活動であったとも言えます。法華経に「開示悟入」とあります。一人の人間の本来もつ智慧を「開かせ」「示し」「悟らせ」、その智慧に「入らせる」ことが、仏教の究極の目的なのであります」(法華経121㌻、趣意)。これは「教育」と完全に軌を一にします。『仏教』は裏を返せば人間教育であり、一方、「教育」は、人間信頼という精神性に裏打ちされてこそ価値がある。「人格を形成」し、「平和への知性」を与え、「社会への貢献」を教える「人間愛の教育」こそが最も必要なのであります。私どもSGIの源流は「創価教育学会」であります。戸田第二代会長も教育者でありました。そして〝教育の目的は、生徒を幸福にすることにある〟(『牧口常三郎全集』5、参照)という信念から、その幸福の中身を追求し、仏教の生命哲学に至ったのであります。マハトマ・ガンジーやネルー首相が、反植民地主義の闘争を展開したのと同時代の日本で、戸田は、牧口初代会長とともに、反軍国主義を貫き通しました。牧口が七十三歳で獄死した悲嘆を乗り越え、弟子である戸田は、閉ざされた独房にあって、「法華経」等に依拠しつつ、「宇宙的ヒューマニズム」の原点を己心に覚知したのであります。戦後、私は、この恩師と出会いました。奇しくも五十年前、貴国の独立前夜の八月十四日であります。あの制憲会議の席上、ネルー初代首相は、〝すべての人々の目から涙をぬぐい去ることがわが国の目的である〟(「ネルー演説集」坂本徳松・大類純訳、『世界大思想全集』22所収、河出書房新社、参照)とガンジーの「夢」を引いて叫ばれました。まさに、その日でありました。ともあれ、教育が開く「英知の世界」がなければ、宗教の信仰も〝盲信〟になる危険があります。反対に、「教育」による英知の光源をもてば、宗教による「精神性」も、より光を放つことでしょう。ゆえに私は初代・二代会長が、真の「教育」の探求の延長線上に、民衆の中での「仏法」の実践に至ったことを、最も道理にかなった道と思っております。今度は、その「仏法」を基調にして、私どもは、世界のあらゆる人々、民族、国々の中へ、「教育」と「文化」と「平和」の普遍的な連帯を広げているのであります。 一九七四年には、私は、相前後して中国とソ連を訪問いたしました。この年、中国には、二度行きました。当時は、中ソ紛争たけなわのころでありました。しかし両国首脳に、一民間人として、率直に関係改善を訴えたのであります。とりわけ、ソ連訪問の際は、なぜ宗教否定のイデオロギーの国へ行くのかと、何回となく批判されました。私は、そのつど、「そこに人間がいるから行くのです」と明言いたしました。昨年(一九九六年)は、アメリカとともに、キューバを初訪問し、カストロ議長とも友情の絆を固めてまいりました。国家間の険悪な関係でさえ、一歩高い「人間」の次元から見るならば、決して乗り越えられない壁ではないと、私は信ずるのであります。今、私の胸には、ラジブ首相のあの凛とした声が蘇ります。いわく、「世界文明に対するインド最大の貢献は、多様性と民族の独自性が決して対立しないことを証明している点である。我々は、五千年の生きた経験を通して、我々の多様性のなかの統一が、生き生きとした現実であることを、世界に示してきた」と。二十一世紀の地球が直面しているのは、この〝多様性の統一〟を、どう実現するのかの一点であります。人類は、今こそ、貴国の尊い歴史と智慧から真摯に学ぶ時が来ていると、私たちは思うのであります。貴国は今年(一九九七年)、栄光の独立五十周年を迎えられました。歴史上、「非暴力から生まれた最初の国」であると同時に、「最も新しき国」が貴国であります。人類の進歩の最前線の国が貴国なのであります。その壮大な実験は、インドを超えて世界に深い精神の啓発を与えております。マーチン・ルーサー・キング師によるアメリカの人種差別への反対闘争も然り、あの八九年の東欧革命も、またしかりであります。「源遠ければ、流れ長し」という言葉があります。未来への「平和の大河」を求めるならば、その源は、最も深き人間精神の源流に求めていかなければならない。揺るぎなき平和を求めるならば、揺るぎなき土台を求めていかなければならない。それこそ私は、アショーカ大王を一例として、貴国が二十一世紀へ、二十二世紀へと発信している「平和のメッセージ」でもあると思うのであります。 あるいは、こういう見方は、あまりにも楽観的に聞こえるかもしれません。しかし、私は「人間への信頼」を絶対手放したくないのであります。私は、人間性への大いなる信仰をもっているのであります。あの日、ラジブ首相と私は、東京で語り合いました。「人類の『心の壁』を取り払いましょう!」と。壁を取り払ったあとには、広々とした「共生の大地」が広がっていることでありましょう。その大地の上に、平和の大河が流れ、分化の大樹が天に向かって伸びていくことでありましょう。事実、私と首相とは、あの時、一切の違いを超えて、互いの胸中の「平和の調べ」で結ばれたのであります。ラジブ首相は、掲げた「夢」に向かって、突き進みました。勇者は敢然と、人間の中へ、民衆の中へ、飛び込みました。「夢」に殉じ、「ヒューマニズム」に殉じました。今も燦然と輝いておられます。その荘厳な「生」と「死」をもって、新世紀の人類の行く手を大きく照らしてくださっております。樹財団は、ラジブ首相の「正心の後継者」として、首相のあの崇高な「夢」を、具体的に追求しておられる。その「夢の追求」には、インドはもちろん、世界の心ある人々が、こぞって参画するでありましょう。「人類よ、ラジブ首相に続け! その先に『平和』はある」と、私は申し上げたいのであります。終わりに、青年時代より愛読したタゴールの「最後のうた」の一節を朗読して、スピーチの結びとさせていただきます。 おお 大いなる人間がやって来る——あたりいちめん地上では 草という草が顫(ふる)える。天上には ほら貝が鳴り響き、地上には 勝利の太鼓がとどろく——大いなる生誕の喜びの瞬間(とき)が来たのだ。今日 暗き夜の要塞の門がこなごなに 打ち破られた。日の出の山頂に 新しい生命への希望をいだいて恐れるな 恐れるなと、呼ばわる声がする。人間の出現に勝利あれかしと、広大な空に 勝利の賛歌がこだまする。(「最後のうた」森本達雄訳、『タゴール著作集』2所収、第三文明社) サンキュー・ベリーマッチ。ダンニャワード!(「ヒンディー語でありがとうございました」)) 【創造する希望「池田先生の大学・学術機関講演に学ぶ」】創価新報2021.10.20
January 28, 2023
コメント(0)
-
「ニュー・ヒューマニズム」の世紀へ㊤
「ニュー・ヒューマニズム」の世紀へ㊤インド ラジブ・ガンジー現代研究所1997年10月21日時代背景と講演の意義池田先生は、1997年10月21日、インドのラジブ・ガンジー現代問題研究所の招聘を受け、講演を行った。当時、世界は核兵器をはじめとする大量破壊兵器の脅威、民族紛争の激化、地球温暖化やオゾン層破壊などの環境問題、経済面での南北格差の拡大等、幾多の課題に直面していた。また、エイズや麻薬の蔓延なども深刻化していた。こうした暴力的な世界を癒すものとは——先生は「『ニュー・ヒューマニズム』の世紀へ」と題し、来るべき21世紀を展望し、論じた。冒頭、20世紀は科学技術の発達に伴い「空間的距離」が消滅した一方で、大量殺戮の世紀だったという事実に言及し、「心の距離」は少しも消滅していないと指摘。「新しい現実」に応じた「新しい哲学」が必要だと主張した。その上で、21世紀はアメリカ・中国・インドの三国が主軸となる可能性が高いとし、とりわけ世界の安定のためにもインドの興隆を期待。アショーカ大王やマハトマ・ガンジーが実践した、インドに脈打つ「非暴力」の精神こそ、世界をリードする思想であると強調した。そして、「宇宙的ヒューマニズム」の確立を訴え、それを実現するものは「教育」の力であると述べた。講演を聞いた同研究所のフセイン副議長は語った。「〝アジアの光〟である釈尊は、確かにこのインドに生まれました。しかし、そのまばゆい光は日本に受け継がれ、池田博士がそれを一段と燦たる大光へと輝かせたのであります。 本日は、大変に懐かしい、尊敬してやまぬラジブ・ガンジーもと首相ゆかりの財団から、呉正平を受け、かくも多くの傑出した先生方の前で、講演に機会を与えられましたことは、私の最大の名誉であります。ソニア・フセイン副議長をはじめ、心より御礼申し上げます。十二年前、来日されたらジブ首相と知り合った、あの秋の一日は、今なお私の胸に鮮やかに輝き続けております。ラジブ首相は、あの涼やかな瞳で、まっすぐに二十一世紀を見つめておられた。「私は若い。私には夢がある。私は、こんなインドを夢見る。強く、独立し、だれにも頼らず、そして世界の国々の先頭に立って『人類に奉仕する』インドを夢見る」と。新世紀を目指すラジブ首相は、「時代遅れ」を憎んでおられた。それは単に「物質文明の立ち遅れ」を意味したのではありません。その反対であります。科学技術を言うなら、それは、飛躍的に発達しました。事実、私は、日本を出発して、その日に貴国に到着いたしました。昔ならば、何カ月あるいは何年もかかったかもしれない。私が対談したトインビー博士も、現代の特徴を「距離の消滅」(『二十一世紀の対話』。『池田大作全集』第3巻収録)と表現しておられた。今世紀、世界は見る見る狭くなりました。通信技術の発達は、まさに瞬時に世界を結んでおります。にもかかわらず、今世紀ほど「人類が人類を殺した」世紀はないのであります。◇人類の「心の距離」は、少しも解消していない。新しい現実に、人間が対応し切れていないのです。これをラジブ首相は、「時代遅れ」と呼んだのであります。貧困と飢餓を克服するだけの力を、人類は十分に持っている。しかし、その力を人類は、大量殺戮の核兵器をはじめ、巨大な資源の浪費に使っております。これまた「時代遅れ」であります。要するに、人類は行き詰っている。「新しい現実」はあるのに、「新しい人間」がいない。めまぐるしいスピードで世界は変化しているのに、それに対応できる「新しい生き方」「新しい哲学」そして「新しい人間関係」が広がっていない。ここに現代の根本的課題があります。それは、いわば「二十一世紀からの要請」であります。この「未来からの呼び声」に鋭く応えようとしたのが、ラジブ首相でありました。本日は、先覚者であるラジブ首相を偲びつつ、所感の一端を「『ニュー・ヒューマニズム』の世紀へ」と題し、述べさせていただきたいと思います。 暴力は現実を悪化させるだけ非暴力が「最も現実的な」選択 今、未来は、あまりにも渾沌としております。しかし、一つの巨視眼から見れば、二十一世紀はアメリカ、中国、インドの三国が主軸となる可能性が高いと、私は思っている一人であります。鼎という三本脚の器がありますが、二本足では安定しません。三本脚であってこそ安定できます。中国の古典に『三国志』という書があります。二つの大国が対立するなか、三つ目の国を興して、その均衡による平和を追求していったのであります。それを拡大してみれば、世界も二国が中心だと、どうしても対立の方向に行ってしまう。三国があってこそ、常に話し合い、連携をとりながら、平和の方向へと全体の軌道をもっていける。そういう構図が、世界平和の理想と考えられます。さらには、そこに「世界連邦」的な方向へ行く可能性を見いだせるのではないでしょうか。ゆえに、世界を安定させる要因として、貴国インドの興隆が、極めて大きな意義をもっていると思うのであります。その意味で、貴国が今、市場経済や高度科学技術を活用しつつ、二十一世紀へ雄大に飛翔しようとしている姿は、まことに注目すべき事であります。今、再びの絢爛たる「インド・ルネサンス」を私は期待してやみません。人類が、それを願っております。しかも、貴国のもつ「非暴力のメッセージ」は、今後の人類にとって、決定的な意味をもっていると私は信じております。いわば「世界の明日」を、すでに先取りしている国が、貴国であります。∮さて、二十世紀を一言でいえば、「悔恨の世紀」であると言った人がおりました。人類の進歩を信じて、颯爽と歩み始めた今世紀も、ふり返ってみれば、かつてない「メガ・デス(大量殺戮)」と「環境破壊」、恥ずべき「貧富の格差の拡大」という荒野が広がっている。一体、どこで人類は道を間違ってしまったのでありましょうか……。世紀末の人類の心象風景を思うとき、浮かんでくるのは、貴国の偉大なる王、アショーカ大王であります。数限りない世界の王のなかで、ひときわ抜きんでた「王の中の王」。トインビー博士も、また、「EU(欧州連合)」の源流を作ったクーデンホーフ=カレルギー伯も、私に対し、大王をほめたたえておりました。アンドレ・マルロー氏、ポーリング博士、キッシンジャー博士とも、大王について私は語り合いました。アショーカ大王の法勅の中に、こういう一節が刻まれています。〝これは、わが深き悔恨である〟(塚本啓祥『アショーカ碑文』第三文明社、参照)と。何を大王は後悔したのでありましょうか? 全インドを統一した強大な王の〝悔恨〟とは何であったのか?それは、ご承知の通り、カリンが王国を、大王は侵略した。勝ちました。圧倒的勝利であります。征服は成功しました。しかし、戦争の犠牲は、あまりにも大きかった。カリンが王国では、十万人が捕虜となりました。さらに、その何倍の人が、この戦争で命を落としたといいます。国を捨てて流浪せざるをえなくなった難民も多かったことでしょう。親と子が、夫と妻が、友と友が、師匠と弟子が——痛ましい離別が数限りなく繰り返されました。嘆きの声が大地をおおいました。この地獄図を前にして、アショーカ大王は痛切なる悔恨にさいなまれたのであります。(『中村元選集(決定版)』6、春秋社、参照)「何のために、こんな征服をやったのか?何のために、私は領土を拡大したのか?何のために私は『力』を行使したのか?幸せたるべき人生ではないか。それらを破壊する戦争とはいったい、何か? なぜ人が人を殺さなければならないのか?」わたしには、大王の「魂の叫び」が、時のへだたりを超えて、胸に迫ってくる気がいたします。そして、今世紀は、世界中で、この何百倍、何千倍もの悲劇が生じたのです。ゆえに今こそ、人類は、アショーカ大王の「回心」に学ばなければならない。私は、強く、そう思っております。∮「人間主義こそ」混迷を打ち破る究極の思想アショーカ大王の悔恨は徹底的でありました。容赦なく自分を責めました。そして大王は豁然として知ったのであります。「力による勝利」は、真実の勝利ではない。むしろ人間としての敗北にすぎない。むなしく、何の価値も生まない。「力による征服」ではなく、「ダルマ(法)による征服こそ真の征服である」(前掲『アショーカ王碑文』、参照)と、大王は悟りました。この「力」とは軍事力だけではなく、経済力も含めてよいでしょう。また「ダルマ」とは、正義、説くなどの意味をもち、多義的な言葉でもありますが、貴国の詩聖タゴールは、「ダルマ」とは、「文明」という言葉に最も近い言葉であると言っております。また国父ガンジーは、「文明」の本義を、故郷の言葉(グジャラート語)での「よき行為」としております。それらをふまえて、私は「ダルマ」とは、真の「文明」であり、「人道」であり、「ヒューマニズム」と言ってよいと思うのであります。アショーカ大王の「心の革命」によって、「軍鼓の響き」は「ダルマというヒューマニズムの交響曲」に変わっていきました。私の生涯のテーマは、「一人の人間における偉大な宿命の転換をも成し遂げ、更に全人類の宿命の転換をも可能にする」であります。その歴史上の一例が大王であります。大王は、夢想家ではありませんでした。行動の人でありました。行動なきヒューマニズムなど、言葉の矛盾でしかありません。大王は、まったく新しい哲学と、まったく新しいビジョンによる「実験」を開始しました。大王は、国内にあっては福祉政策に力を入れました。「生命以上に尊いものはない」との精神の具現化であります。人間のための病院だけでなく、動物のための病院も建設しました。薬草の栽培や、街路樹の植樹など「環境保護」も実施。井戸を掘り、各所に休憩所を設置しました。女性の要求に応じるために「女性のための奉仕者」と呼ばれるポストもつくりました。また自らは仏教に帰依しながら、あらゆる宗教の精神性を尊重しました。いわば「信教の自由」の保障です。古代ではきわめてまれなことであります。こういう「ヒューマニズムの政治」を実現するには、言うまでもなく、経済力が必要となってまいります。大王は、経済基盤の拡充のために、交通網を整備し、ギリシャ、中東方面へと貿易を広げました。それとともに、釈尊の示した経済倫理である「すべての人への分配の原則」を実践し、経済格差の是正に努めたのであります。「力」を何に使うかという「知恵」を持った大王に、もはや迷いはありませんでした。大王はまた、他の国々と文化の交流を積極的に行いました。シリアやエジプト、マケドニアなど西方にも「平和の使節」を派遣し、平和外交を展開しました。使節たちは、訪問した各地で、言語や風俗などの差異を超えて、慈悲の行動に徹したと言われております。ある学者は、その活躍を「古代の平和部隊」と呼んでいます。大王のヒューマニズムが世界を結んだのであります。これは、厳然たる事実の歴史であります。ラジブ首相が平和外交を展開し、インドの首相として、中国へ三十四年ぶりに訪問、またパキスタンとの友好に尽くしたことは、大変に有名であります。私は、ソ連のゴルバチョフ大統領と何回となく語り合い、対談集も発刊いたしました。ゴルバチョフ氏は、ラジブ・ガンジー首相と共同で発表した「デリー宣言(核兵器と暴力のない世界の諸原則に関する宣言。一九八六年十一月)」について、私に、こう述べられておられました。宣言後の共同記者会見で、「われわれは無条件にテロリズムに反対する者だ」と語ったことを回想し、「ガンジー首相は、私の崇高な親友でした」と語っておられました。(『二十世紀の精神の教訓』。『池田大作全集』第105巻収録)ゴルバチョフ氏はまた「インドは、私も深い尊敬の念を人々には、他者の痛みに対する深い同情があり、『平和』と『自由』と『正義』への強い意志があります」とも言っておられた。(同前)私は、この石を現実政治に生かそうとしたのが、アショーカ大王であり、マハトマ・ガンジーであり、ネルー首相であり、ラジブ首相であったと見ております。それは「非暴力という理想を現実に適応する」ということではなかったと思うのであります。むしろ「暴力は現実の課題を何も解決しない。悪化させるだけである。非暴力こそが、もっとも現実的な方針である」との確信ではなかったでしょうか。長いスパン(機関)で見れば、「人間の社会」であるゆえに、人間主義(ヒューマニズム)こそが究極の「力」なのであります。 【創造する希望「池田先生の大学・学術機関講演に学ぶ】創価新報2021.9.15
December 11, 2022
コメント(0)
-
21世紀への提言——ヒューマニティーの世紀に㊦
21世紀への提言——ヒューマニティーの世紀に㊦カルフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)1974年4月1日「小我」を乗り越え「大我」に生きよ!仏教の真髄は、煩悩を断ち執着を離れることを説いたものでは決してない。無常を悟って、諦めを説いた消極的、虚無的なものではなく、煩悩や執着の生命の働きを生み出す究極的な生命の本体や、無常の現実の奥にあり、それらを統合、律動させている常住不変の法のあることを教えたのが、仏法の真髄なのであります。すなわち、無常の現象に目を奪われ、煩悩に責められているのは「小我」にとらわれているのであり、その奥にある普遍的真理を悟り、その上に立って無常の現象を包み込んでいく生き方にこそ「大我」に生きるといえましょう。この「大我」とは、宇宙の根本的な原理であり、またそれは同時に、私達の生命の様々な動きを発展させていく、根本的な本体をとらえた「法」であります。トインビー博士は、此の本体を哲学用語で「宇宙の究極の精神的実在」と呼ばれておりましたが、それを人格的なものとしてとらえるより、仏教のごとく「法」としてとらえるのが正しいと思うといっておられました。この「小我」でなく「大我」に生きるということは、決して「小我」を捨てるということではない。むしろ「大我」があって「小我」が生かされるということなのであります。文明の発達というのは、人々に執着があり、煩悩があるからこそあるものともいえます。もしと身への執着がなければ経済の発達はないし、厳しい冬を克服していこうという意思がなければ、自然科学の発達もない。恋人を愛するという煩悩がなければ、文学の重要な部分は張ったつぃな買ったでありましょう。(笑い)仏教の一部では初期においても、煩悩をなくそうという考えはあり、そのために、肉体をも焼き尽くす試みさえ行われた。しかし、煩悩というものは、生命が本来持っている根源的な本体から発現してくるものであり、なくすことはできない。というより、行動の原動力さえあります。ゆえに、個の煩悩にとらわれた「小我」を正しく方向づけることが、不可欠であります。真実の仏教はいま、その根本の「大我」を発見した。「小我」をなくそうとするのではなく、逆に「小我」にとらわれるものではない。「小我」をコントロールし、方向づける「大我」のうえに立ってこそ、文明は正しい発達を告げるといいたいのであります。(大拍手)したがって、仏教が無常を説き、死を見つめることを教えたのは、逆に常住不変の法の実在することを教えるためであったわけであります。つまり仏とは諦めを教える人ではなく、常住の法を悟った人をいうのであります。死を恐れずに見つめ、無常を明らかに悟ったのは、その奥に常住不変の法があり、わが生命もその法則のうえに立って運動する尊き存在であることを、知っていたからこそであるといえましょう。死は私たちの肉体を、必ず包み込む。それは、避けることができない。しかし、それを超えて、永遠に生起し、展転しゆく不滅の生命の裏付けられていることを仏法は教えている。その絶対の確信のうえに立って、死を、無常を見つめることを指し示したのであります。 内なる生命を見つめ〝人間謳歌の文明〟つくる 仏法では「生死不二」と説きます。生も死も、永久不変に流れゆく生命の二つの現れ方であって、どちらかに他方が従属するものでもない。時間、空間の認識の枠を超えた「空」の次元でこそ、この生死をつかさどる永遠の究極的生命がとらえられているといってよい。トインビー博士と、その永遠性の問題は繰り返し論議いたしましたが、博士も「究極の精神的実在」は、仏法で説く「空」の状態でしか捉えられないと言っておられました。この「空」ということを、短い時間で説明しきることは困難ですが、一般的に考えられている「無」ということでは絶対にありません。「有」や「無」は時間、空間という私達の通常の認識尺度で判別しうるものでありますが、「空」はその奥にある本源の世界を問題にしていけるわけであります。私達は、生まれて成人に達するまで、肉体的には大変化を行っている。幼い時の肉体とは、別人のごとくであるといってもよい。これからの人生の長い道程にあっても、数知れない変化を行っていくうえでありましょう。精神的にも大きな変化が見られるのは当然であります。しかし、その中に一貫して変わらぬ自分というものがある。それは単に記憶の問題にとどまらず、一個の生ある個体としての、本源的な「我」の問題であります。子の本源的な「我」は、肉体や精神のうえに顕れてきているけれども、そのもの自体を認識することは困難であります。肉体や精神をつかさどり「有」や「無」の世界の奥にある本体であると言わざるを得ない。仏法は子の本源的な「我」が、宇宙大の生命に通じていると説くのであります。更に、この「我」は、永遠に不滅の働きをなし、ある時は「生」に、ある時は「死」の姿をとる。これが生死不二という考え方であります。私達は、その「大我」を、わが生命のうちに持っている。そして宇宙生命とともに呼吸しながら、無常の世の中に生きて行くのであります。 翻って、現代文明を見るとき、私達の文明はまさしくこの「小我」に翻弄され、その最大限に暴れさせた文明であったことは悲しい。人間の欲の権化が環境を汚染し、石油資源を掘り尽くして、巨大な科学文明を作りだした。巨大なビル、高速の交通機関、さまざまな人口食料、そして最も忌まわしい兵器——それらのすべてが、人間の執着、煩悩の現象であります。それらのなすがままにまかせ、人間を従属させていくならば、必ずや人類を自滅に陥れるに違いありません。世界的な主張として、今、現代文明の暴走への反省から、「人間」に目を向けるようになってきたのは、ようやく人間が人間であろうとしている兆しであるといえましょう。欲望に支配され、無常の現象の世界ばかり追い回すのであれば、そこにいかに知性が発揮されるといっても、本源的には、本能に生きる動物と変わるところがない。現象の奥にある、目には見えぬ実在に目を向けてこそ、人間は人間たる価値を表すのではないでしょうか。(拍手)トインビー博士は、自らのエゴにとらわれた欲望を「魔性の欲望」と認識され、それに対し「大我」に融合する欲望を「愛に向かう欲望」と名づけられました。そして「魔性の欲望」をコントロールするためには、人間一人一人が内なる自己を見つめ、制御することが必要不可欠であると、二十一世紀への警鐘として述べられたのであります。きたるべき二十一世紀の文明は「小我」に支配されてきた文明を打ち破る、「大我」を踏まえ、無常の奥にある常住の実在をつかんだうえに立っての円満な発達が要請されるべきであります。それでこそ、初めて人間は、自らが人間として自立し、文明は人間の文明になるのであります。そのような意味から、私は、二十一世紀を「生命の世紀」でなければならないと訴える次第であります。(大拍手)私達の人生は、また宇宙のあらゆる現象は車輪が回るがごとく、展転きわまりないものであります。しかし、煩悩、欲望の泥沼の上をあえぎながら走るか、確固とした「大我」を悟った生命の大地の上を走りゆくかによって、その回転は変わってくる。その時、初めて文明は確かな足どりを持って動き始めるといえるでありましょう。二十一世紀が夢に見た人間謳歌の文明になるかどうかは、一にかかって、人間そのものに目を向け、常住不変、不動の力強い不変の生命を発見しうるかどうかにかかっている。そしていまは、まさにその分起点にあることを、本日、私は皆さんに訴えたいのであります。二十世紀後半から二十一世紀にかけての現代は、まさしく人間が真に人間となるか否かの転換期であると、私は考える。これまでは、極論かも知れませんが、人間は知性を持った動物の域を出なかった。私の信奉する七百年前の日蓮大聖人の経典の中に「才能ある畜生」(御書215㌻)という表現がありますが、現代において、この言葉の持つ意味が極めて明確になりつつあります。人間は知性的に人間であるだけでなく、精神的、更に生命的にも、人間として跳躍を遂げなければならないと信ずるものであります。その課題は、今日の誰人にも課せられております。まず、自ら人間としての自立の道を模索すべきだと思います。私は仏法によって、その「生命の旅」を開始いたしました。皆さんも、一人一人が未曽有の転換期に立つ若き建設者、開拓者として、それぞれの「人間自立の道」を考えていただきたい。私は本日、そのための参考として仏法の英知の一端をお話いたしました。この講演が、皆さん一人一人にとって何らかの指標となれば幸いであります。(大拍手) 【創造する希望[池田先生の大学・学術機関講演に学ぶ]】創価新報2021.8.18
October 19, 2022
コメント(0)
-
「21世紀の提言-ヒューマニティーの世紀に」㊤
「21世紀の提言-ヒューマニティーの世紀に」㊤カルフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)1974年4月1日時代背景と講演の意義1974年4月1日、池田先生は、海外大学・学術機関で初となる講演を、全米屈指の名門学府・カルフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)で行った。当時の世界情勢は、アメリカとソ連の両大国を盟主とした東西陣営の対立に加え、社会主義国同士である中国とソ連の関係も険悪となり、複雑な様相を呈していた。一方、その当のアメリカは、60年代の後半から70年代初頭にかけて、人種差別問題やベトナム戦争の泥沼化で社会の分断が深まり、講演の前年に起こった繁栄を支えてきた技術革新と大量生産・大量消費の文明が揺らいでいた。講演の冒頭、池田先生は72年と73年に行われたトインビー博士との対談を紹介しながら、仏法の中道主義こそ、物質主義と精神主義を止揚する第三の「生命の道」であると語った。そして、生命を手段化する「テクノロジーの文化」を超えて、生命尊厳の「ヒューマニティーの文明」へと発展するため、欲望に振り回される「小我」の生き方から、大宇宙の根本法に則った「大我」の生き方への転換が必要と強調。21世紀を「生命の世紀」にするには、「我々に新鮮な勇気と感動を与える歴史的な講義」(ノーマン・ミラー副総長)、「人類の未来開拓へ、根本的な道標を示した、重要な意義をもつもの」(ネイサン・サビラ教授)など称賛が寄せられた。生命尊厳の思想を基盤とした文明築く 本日はUCLA(カルフォルニア大学ロサンゼルス校)のヤング総長、またミラー副総長の御招待をいただき、アメリカの知性を代表するキャンパスで講演できることを、心の底から喜んでおります(拍手)。これからのアメリカを、否、二十一世紀の世界を担う皆さんへの満腔の期待と敬意をこめつつ、格子としてというよりも、むしろ、共に未来を語り合う友人として話をさせていただきます(大拍手)。一昨年(一九七二年)及び昨年(七三年)の五月、イギリスの歴史学者であり哲学者でもあるトインビー博士の招待を受け、十日間にわたって真摯な討議をいたしました。私は人間対人間の中に、相互の触発があると信ずる一人である。ゆえに、対話を最も重んずるのであります。ご存じの通り、トインビー博士は現代が誇る最高の知性の一人であり、人類の巨大な財産であります。八十五歳でありながら、なお、かくしゃくとして創造的な仕事を続けておられる。トインビー夫妻は、いつも六時四十五分に起床しておられるようであります。この時間は、諸君はまだ睡眠中かもしれないし(笑い)お手洗いに行って、もう一度寝床に入る時間かも知れない(笑い)。起きられるとすぐに、お二人でベッドを片づけ、朝の食事を作るそうであります。そして九時になると博士は、用事があってもなくても、ご自身の机に向かうそうであります。私はこの姿を拝見して。美しく老いたいものだと思った。諸君のように、若さという美しさもあるが、老いた美しさには、尊さをはらんだ美しさがただよっているように思えてならない。さて、諸君も、お父さん、お母さんが、美しく老いていかれるよう、落第したり落胆させるようなことをしないよう、切望するものであります。(笑い、拍手)トインビー博士との対話の際、座右の銘をうかがったことがあります。博士は「ラボレムス」というラテン語を挙げられた。「さあ、仕事を続けよう」という意味であります。ローマ帝国のセウェルス皇帝が西暦二一一年、イングランド北部の厳冬の地で、遠征の途にある時、重病に倒れて死期が迫った。しかし、指揮者として、仕事を続けた皇帝は、まさに死なんとするその日「さあ、仕事を続けよう」と、全軍にモットーを与えたのだとうかがいました。私は、博士が老いて益々若々しく、精力的に仕事が続けたれる秘密を知った思いがしました。そして生涯〝思想の苦闘〟を続ける人間の究極の美しさを、ここにみたのであります。 〝中道〟こそ人類の歩むべき軌道文明論、生命路、学問・教育論、文学・芸術論、自然科学論から国際問題、社会問題、人生論、女性論など幅広く話し合いました。二十一世紀の未来を展望しつつ、対話は果てしなく続き、延べ四十時間を超えるものとなった。私も日本へ帰ってからも。所感による討論は、幾度となく繰り返されたのであります。私が博士にお会いして、対談のあいさつをした時「さあ、やりましょう! 二十一世紀の人類のために、語り継ぎましょう」と、一瞬、厳しい表情となり、決意を込めた強い語調で言われた。自らの死の中にある未来の世界に強い関心を寄せ、若き私どもに、知性のメッセージを贈ろうとされる博士の心に打たれながら、私は対話を続けたのであります。本日、私は、博士に決して劣ることのない決意と誠意をもって、皆さんに語り継ぎたい(大拍手) トインビー博士との対話の締めくくりとして、二十一世紀の人類への提言は何か、と問うた時、博士は、「二十一世紀において、人類はテクノロジーの力に酔いしれてきた。しかし、それは環境を毒し、人類の自滅を招くものである。人類は自己を見つめ、制御する知恵を獲得しなければならない。そのためには、極端な放縦と極端な禁欲を戒め、中道を歩まねばならない。それが、二十一世紀の人類の進むべき道だと思う」という意味のことを述べられておられた。私もまったく同感であり、特に「中道」という言葉にひかれた。というのは〝東洋の心〟を流れる大乗仏法は、中道主義を貫徹しているからであります。この言葉はアウフヘーベン(止揚)に近い言葉と考えていただきたい。すなわち、物質主義と精神主義を止揚する第三の「生命の道」のあることを、私は確信しております。現代文明の蹉跌を矯正する方途として、具体的な方法論を論じ合いました。しかし、技術的な方法論は、それのみにとどまっては、根本的な解決をもたらさない。そこで、どうしても「人間とは何か」「生きるということはどういうことか」等々、もう一度原点に踏み込む必要を、共々に痛感したものでした。いきおい博士との対談は、人間論、生命論といった、根本的なものに重点が置かれていったのであります。特に印象的であったものの一つに、生命論に対する対話があります。これは、人間が人間を知るための基本的な論議であり、人間の生命活動こそ、文明を形成する根本の要因があるからであります。トインビー博士は二度の世界大戦を体験され、戦争が妥協のあり得ない最も悪い制度であると叫んでおられる。また最愛の子息を亡くされ、いいようのない精神的苦痛を味わられた。それらは、博士の関心の大きな部分を、人間の生死、ひいては生命の奥深くに向けさせているようでした。私自身、兄を戦争でなくしている。戦争ほど悲惨で、残酷なものはないというのが、私の実感であります。それは生涯、変わることがないでありましょう。生命をこのうえなく尊厳とする思想を、全人類が等しく分かち持つことが急務であると、トインビー博士と私は、強い共感と祈りをもって、確認し合ったのであります。私はきたるべき二十一世紀は、結論として言うならば、生命というものの本源に、光が当てられる世紀であると思っております。否、そうあらねばならないと信じています。そうあってこそ、文明は真実の意味でテクノロジーの文明から、ヒューマニティーの文明へと発展するであろうと思うからであります。トインビー博士との生命論に関する対話では、精神と肉体の関係についての問題、生命の永遠性についての問題、死刑論、安楽死の問題、エゴイズムの問題等々、多岐にわたるテーマが取り上げられたわけでありますが、本日、この講演の場においても、生命路を総括的に取り上げ、皆さんとともに、人類の行く末を見つめていきたいのであります。 ご存じの方も多いかと思いますが、仏法の第一歩においては、人類を苦の集積であると説いております。生まれ出る苦しみ、病気の苦しみ、老いる苦しみ、死ぬ苦しみに代表されますが、愛するものといつかは別れなければならない苦しみ、求めても得られぬ苦しみ等々、人生には苦しみが充満していると説くのであります。楽しい時間というものは早く去り、そして必ず壊れていく。それを失う悲しみが加わって、苦しみを感ずる時間は長い。社会に広がっている貧富の差、人類、風俗の差は、人に楽しみを与えるよりも、苦しみを実感させるように私は思える。ではなぜ、人は人生に苦しみを感ずるのか。それは「無上」ということを知らないからであると、仏法では教える。無上とは、あらゆる宇宙、人生の現象で、常住不変のものはないということであります。その原理を知らないところから、苦しみが起こるというわけであります。若き者は必ず老い、形あるものは必ず滅ぶ。健やかであっても病むときが来、生あるもの必ず死す。ギリシャの哲人ヘラクレイトスは「万物は流転する」と言ったといわれておりますが、神羅万象すべての川の流れのごとく、一瞬としてとどまることなく変化しゆくものなのであります。この机やマイクや建物すべて、頑丈にできていることを疑うわけではありませんが、それすらも十分な時間さえあれば、いつかは破壊され、私は講演しなくてもすむようになる(笑い)。もっともそれまで待てるほど、私の体が頑丈だとは思っておりませんが……。(笑い)。ところで、このような「無常」の原理を忘れ、それを常住だと思って執着するところに、魂の苦しみが生ずる原因があると、仏法は説くのであります。もし皆さんに、美しい恋人がおられるとしても、最初からその恋人の三十年後、四十年後の姿を思い浮かべつつ、交際しておられる方は少ないと思います(爆笑)。やはり現在の美しさ、若さがいつまでも続くことを願うのが、人情というものであります。また、いかに膨大な富でも、死んだ後まで持っていけるものだと信じて、そのために一生懸命働こうという方も、あまりおられないはずです。ともかく、得た富を少しでも長く自身に留めておこうとして働くのであります。これらは、決して誤った考えとはいえない。むしろ、自然な人間の感情である。しかし、この感情があるがゆえに、苦しみがあることも事実であります。恋人をいつまでもわが手にと思うがゆえに、種々の葛藤があり、愛するものと別れなければならない時、最も大きな魂の苦痛を感ずる。冨を確保しようとするあまり、その富に執着し、隣人と争い、味わわなければならないのであります。「死」という問題も同じである。私達が今、こうして生きているのは事実であり、常に死ぬことを考えて生きているわけにはいかない。いつの間にか、自らの生が、いつまでも続くと無意識のうちに考え、その生を保とうとして様々な努力をする。しかし、その強い執着が、人間にあらゆる苦しみを与えていることも疑いない事実である。死ぬことを恐れるからこそ、老いにおびえ、病に苦しみ、生を貪ろうとして果てしなき煩悩の泥沼にもがいているのが、私達の人生であるともいえるのでありましょう。仏法は、これら常識の変転を明らかに見つめよと説く。むしろ偉大なる勇気をもってこの事実を受け入れなければならない、と主張しているのであります。事実から目をそむけ、変化する無常の現象を追いかけるのではなく、冷静にその事実を受け止めるところから、真実の覚りへの道は開けるといえるのであります。人生は無常であり、そのゆえに苦の集積であり、さらにこの現実の肉体を持つ自己自身も、必ず死ななければならない。その死を恐れずに見つめ、その奥にあるものを捉えることを、仏法は教えております。先ほども申し上げたとおり、無常の現象にとらわれ、煩悩のとりこになるのは、決して、愚かな行為と片付けることはできない。というより、人間の生ある限り、生命の存在がある限り、生に執着し、愛を大切にし、利を求めるのは、自然な感情だからであります。従来、仏法は、煩悩を断ち、欲を離れることを教えるものとしてとらえられ、文明の発展の対極にあるもの、それを阻害するものとさえ考えられてきた。こうしたことは、無常を強調する一側面が浮き彫りにあれたものであり、これだけが仏法のすべてであると考えるとしたら、仏教の一面的な評価にすぎないと言わざるを得ません。 【創造する希望[池田先生の大学・学術機関講演に学ぶ]】創価新報2021.7.21
September 10, 2022
コメント(0)
-
「教育の道 文化の橋——私の一考察」
「教育の道 文化の橋——私の一考察」北京大学1990年5月28日時代背景と講演の意義1990年5月28日、池田先生は中国第一の〝知性の府〟北京大学で3度目となる講演を行った。当時の中国は、78年から開始された改革開放政策によって近代化に取り組み、市場経済に移行、国際社会への復帰が進められていた。しかし、89年6月に起きた第2次天安門事件により、世界各国から強い非難を浴び、孤立していた。そのような状況の中で、池田先生は約300人の大交流団を率いて中国を訪問し、同大学での講演に臨んだ。先生は講演で、国際化の時代を迎えている現代において、教育こそ「地球の未来を開く大業」と語り、中国における教育思想に言及。深き人間洞察に基づいた中国文明の〝人間教育〟の伝統が、新たなる世界像の形成の多大な貢献をなしゆくと展望した。また、日中の交流について「両国の間に如何なる紆余曲折が生じようと、私たちは断じて友好の纜から手を離してはならない」と訴え、より永遠なる友好を支えるのは民衆と民衆を結ぶ〝心の絆〟であると強調した。講演に出席した学生たちからは、「池田先生の話された平和の展望は、まさに私たちの国の民衆の展望です」「池田先生の教育に関するお考えと中国文化に対する情熱に感動いたしました」など称賛の声が多数寄せられた。 本日は、北京大学を訪問し、多くの教員や学生の皆さま方にお会いでき、大変うれしく思います。また、ここに、北京大学初の「教育貢献賞」を賜り、まことに光栄に存じます。王学珍校務委員会主任、呉樹青学長はじめ、さらには私の著作の刊行にご尽力くださった北京大学出版社の麻子英社長、またここにお集まりの学生の皆さまに、衷心より感謝申し上げます。大変にありがとうございました。なお、創価大学の教職員、学生一同も「くれぐれもよろしくお伝えください」と申しておりましたので、お伝えいたします。(拍手)ご存じのように、創価大学は、貴大学との間に学術交流を結んだ、日本で最初の大学であります。協定の調印以来、本年ではや十年の歳月を刻むに至りました。これもひとえに、貴国並びに貴大学の友誼の賜物にほかなりません。この席をお借りいらしまして、謹んで御礼を申し上げます。既に私は、貴大学より名誉教授の称号のほか、日本研究センターでは顧問として栄誉をいただいております。また、これまでに六回にわたって、貴大学を訪問するたびに、皆さま方は何時も変わらぬ友誼の笑顔で温かく迎えてくださいました。いわば〝北京大学の一員〟として遇してくださる皆さまの心に包まれ、私も懐かしき〝わが母校〟の恩に報いるためにも、私は貴大学のより一層の発展のために今後、更に力を尽くしてまいる決心であります。さて、本日は「教育貢献賞」受賞の記念講演を、ということになっておおりますが、大学での講演は、いつもつくづく難しいものだと思っています。それは、話が長くなれば飽きられてしまいますし、短くては、学問的蓄積がないのではと笑われてしまう(笑い)。また、あまりにやさしすぎては最高学府の大学には、ふさわしくないと言われ、難解すぎると、あまり咀嚼しないで話をしているのではないかと非難される(笑い)。まことに大学での講演は難しい(爆笑)。しかし、本日は、講演者の宿命的ともいえるこの課題に挑戦しながら、少々、お時間をいただき、「教育の道 文化の橋——私の一考察」と題し、お話させていただきたいと思います。(拍手)以前より私は、教育こそ〝我が人生の総仕上げの事業〟と心に決めておりました。未来を開き、未来を育むといっても、その主体は「人間」にあるといってよい。「人間」をつくりあげる事業こそ、すなわち教育にほかなりません。「人間」の内なる無限の可能性を開き鍛え、そのエネルギーを開き鍛え、そのエネルギーを価値の創造へと導くものこそ教育です。いわば教育は、社会を築き、時代を決する〝根源の力〟であります。とりわけ現代は、高度に細分化された「知識」が氾濫している。他方、それらを統合しうる人間の「知恵」の力、深き人格の力が求められる時代ともなってきた。また、史上かつて見ない「国際化」の時代を迎えていることから、教育は今後、一国のみならず、地球の未来を開く大業として、ますます重要度を増すでありましょう。 では、教育の未来を考えていくうえで、拠るべき〝礎石〟は何か——。それを思うとき、私の脳裏には、中国における教育思想の光機に満ちた伝統が浮かんできてやみません。私はそこに、「人間」の完成への向けられた滔々たる〝情熱の大河〟を見る思いするからであります。人間教育に関する英知において、古代ギリシャ人と中国人は双璧をなしたといっても過言ではありません。事実、人間性の完成、人格の陶冶を目指す教育の「理念」、「カリキュラム」をめぐっては、両者とも、まことに精緻・深遠を尽くしたといえましょう。一例をあげれば、古代ギリシャ人にとって教育の眼目の一つは、個性の開発にあった。すなわち、一方的に〝教えること〟ではなく、一人一人が秘めている可能性を〝引き出す〟点にありました。いわばこうした「学習者の自発能動性」の重視は、かのプラトンが自ら主宰するアカデメイア(学園)で、学習者相互の啓発と個性の発現をもたらす「対話」を重んじたところにも表れております。同じく東洋においても、人間教育の思想がここ中国に芽吹き、大きく開花いたしました。例えば諸国を遊説し、政治に希望を失ってなお、後進の人材育成に心血を注いだ貴国の先達は、「教」つまり「教える」人ではなく、「育」、「育てる」人として述べております。「啓発」という言葉のもととなった「悱ぜざれは啓さず、緋せざれば発せず」(学び苦しむ熱情がなければ、何事も変わらない)と。また「一隅をあげて三隅を以て反さざれば、即ち復びせざるなり」(四角いものの一つの角を教えて、他の三つの角を悟らないものには、何を教えてもむだである)など、ほとばしらんばかりの学びの意欲と自立を厳しく求めた指導法。「学問」、すなわち学ぶことと問うことの双方に同じ比重を置いたうえでの対話の勧奨など、いずれも深き人間洞察から発する卓見であり、中国文明に宿る人間教育の〝祖型〟の光を、私は強く感ぜざるを得ないのです。近年、こうした東洋の教育思想の光源に世界の識者も改めて注目するようになってまいりました。その一人、アメリカ・コロンビア大学のウィリアム・T・ドバリー教授は『朱子学と自由の伝統』(山口久和訳、平凡社)と題する著書の中で、中国思想の底流にある〝自由主義〟の系譜をたどるとともに、たとえば、互いが持論を交換し合う「講学」という教育の在り方を通して培われた、学問の場における相互扶助・相互啓発の精神を論じております。こうした古代ギリシャや中国の教育思想で、私が感嘆してやまないのは、ギリシャ神話にあっては、神々のために人間が血を流しあったのではなく、人間のために神々が戦ったのであったし、また、貴国においても先哲が「怪力乱神を語らず」と、超越的なものを拒否したことは、申すまでもありません。第二に、人間の内面的陶冶が第一義とされているものの、そこにはとどまらず、すぐさま経世済民への実践へと転じゆく、強い倫理性を帯びていたということであります。 〝人間教育〟が新たな世界像の形成に貢献 古代ギリシャにあっては、例えば、もっぱら魂の位階秩序を整えんとするかのようなプラトンの主著は、何よりも「国家」論として構想されたものでありますし、プラトン自身、晩年にいたるまで燃えるような政治的関心と情熱を抱き続けました。中国の伝統にあっても、有名な『大学』八条目のうちの前半部分——すなわち「格物」「致知」「誠意」「正心」は、後半部分の「修身」「斉家」「治国」「平天下」の条目に示されているのは、いわば〝平和への王道〟を歩むための、欠かすことのできない前提とされてきました。ここに留意すべきは、私があえて「古代ギリシャ」と言わざるを得ないように、プラトンやアリストテレスの思想は、ギリシャ社会のなかでの歴史的継承という点では明らかに断絶があり、主として文明的・知的遺産として受け継がれてきた。それに比べて中国にあっては、あのような巨大な版図圏のエートス(道徳的気風)として、しかも三千年の長きにわたって、断絶することなく生き続けているという事実であります。その人間教育への情熱は、単に儒教的なるものに限らず、広い意味での教育という人間的営為を通して、カオス(混沌)のなかからコスモス(秩序)を作り出そうとする、たゆまざる意志と言い換えることもできましょう。その大河のような流れのなかには、文化の発展と社会の安定の基盤は「民衆」にこそ求められねばならぬとする王陽明の民衆教育論、あるいは明末清初の激動期に『明夷待訪禄』を顕して学校における自治や実力本位の人材登用の必要を説いた黄宗義の学校論など、今なお刮目すべき所論が少なくありません。もとよりそれが、常に全うに実現できたわけではない。教育の振興は、一面、試験地獄ともいうべき「科挙」の制度をも産み落とした。しかも、その儒教的教養は、もっぱら支配者層にのみ独占され、秦に民衆のものにはならなかった。そうした点を考慮に入れつつも、人間の自己完成に即してコスモスの形成しゆかんとする中国の人々の秩序感覚、歴史感覚、さらに言えば宇宙感覚は、例えば、マルクス主義導入に当たっての永久革命の思想に見られるように、今もなお脈打っていると思います。のみならず、それは、フランスの中国学の第一人者として知られるL・ヴァンデルメールシュ教授が「西欧文明に匹敵する一文明形態の出現が準備されつつある」(『アジア文化圏の時代』福鎌忠恕訳、大修館書店)とした「新漢字文化圏」形成のための地下水脈となっていくに違いない。ある先哲は、中世的世界観を打ち砕いたコペルニクス革命のもたらしたものは、新たな世界像ではなく、世界像なき時代である、と述べております。そうした世界像なき時代が、ようやく黄昏時を迎えようとしている現代、教育思想に集約的に表れている中国の伝統正心は、普遍的ヒューマニズムを不可欠の機軸とするであろう新たなる世界像の形成に、多大な貢献をなしゆくであろうことを、私は信じてやみません。 さて、時流は今、日中の交流に新たなる章節を求めております。それは同時に、中国に対する日本の姿勢を、根本から問い直すことにも通じましょう。申すまでもなく、日本は貴国より教育思想はじめ文化全般において大恩をこうむってまいりました。その恩に、どう報いていくべきなのか——。日中交流においては、この一事が日本に問われていると思われてなりません。人はもとより国もまた、今日のグローバルな時代には、孤立して生きることはできない。この世界に生きる限り、無数の人々、国々から恩恵をこうむっていかねばならない。「恩」とは、いわば人間と社会の営みを相互に支え育んでいくべき精神性の発露であり、人間性の精髄と申せましょう。草創期の北京大学に奉職した魯迅は、かつての日本留学時代における恩師の思い出を、名作『藤野先生』に綴っております。一度こうむった恩は、それが如何なるものであれ、終生消えはしない。恩とは本質的に、授ける側より設ける側の〝心の問題〟であります。文豪の心に宿った、死への恩愛の念——私はそこに、人間の高貴なる精神が奏でる内なる調べを聞かずにはおられません。恩を「感じ」、恩を「報ずる」ことは、まさしく人間の「正道」であります。それゆえ〝文化の恩人〟である中国の発展と幸福のために、誠心誠意、努力を傾けていくことが、日本人にいやまして求められている、と確信してやみません。特に日中両国は、地理的に近い。古来、「一衣帯水の国」とも呼びならわせてまいりました。こうした両国の深き絆を思えばこそ、共に活力ある真の平和と安定へと力を合わせていくことが、両国のみならず、アジア、さらに世界の平和実現にも大きく貢献していくことになる、と私は強く信じているものであります。民衆という「大海」の上に交流の「船」は進む友情は、貫いてこそ〝真実の友情〟へと高められます。日中の友好も、貫いてこそ〝真金の友好〟となるでしょう。両国の間にいかなる紆余曲折が生じようと、私たちは断じて友好の纜から手を離してはならない。今、私たちにとって何より大切なことは、日中友好の「金の橋」を将来にわたっていかに盤石にしていくか、永続ならしめていくか、という現実の課題であると思います。政治や経済における往来も重要であることは、論をまちません。しかし、より永遠なる友好交流を支えるのは、何より民衆と民衆を結ぶ〝心の絆〟でありましょう。民衆次元の信頼関係を書いては、政治・経済上のいかなる結びつきも砂上の楼閣になってしまう恐れがあります。民衆という「大海」の上にこそ、政治・経済の「船」は浮かび、進むのです。民衆と民衆の心の絆は、目には見えない。しかし、見えないがゆえに強い。無形であるがゆえに、普遍的・恒久的な紐帯である。それを形成しゆくのは、人間の精神に〝永遠〟〝普遍〟への飛翔の翼を与えてくれる「文化」の光彩であります。なかんずく「教育」は、人間の持つ無限の可能性を開き、人と人とのうちに〝平等性〟〝共感〟の絆を育む。そうした「文化」「教育」の交流こそが、日中の民衆の絆を永遠ならしめる根本の力となりましょう。その意味で、私はここで再び申し上げたい。より一層の「文化」「教育」の交流で、日中友好の「金の橋」に第二期の往来を——と。北京大学は、あと八年で創立百周年の佳節を迎えます。新たなる〝第二世紀〟へ向かって、東洋有数の伝統を誇る貴大学の世界へ果たす役割は、いやまして大きくなりましょう。貴大学のモットーに私どもの「創価」の理想とも相通ずる「創新」(新しきものの創造)の一項目があります。貴大学の「創新」の光り輝く壮大な未来を心に描きながら、私もさらに力を尽くしてまいる所存であります。(拍手)最後に、長時間にわたり、拙い講演にご清聴くださいました、北京大学の諸戦線型、またご来賓の皆さま、新世紀を担って立ちゆく若き偉大なる指導者であられる学生の皆さま方に、栄光あれ、ご多幸あれとお祈り申し上げ、私の話とさせていただきます。 【創造する希望=池田先生の大学・学術機関講演に学ぶ=】創価新報2021.6.16
July 31, 2022
コメント(0)
-
人間文明の希望の朝を
人間文明の希望の朝を*************時代背景と講演の意義冷戦の終結から3年後の1993年2月12日、池田先生は南米最高の知性の殿堂・ブラジル文学アカデミーで講演した、当時、既存のイデオロギーが崩れ、西欧の科学技術文明が推し進めるグローバル化の一方で、その反作用とも言うべき民族・地域紛争——旧ユーゴ紛争と民族浄化、米ロス騒動、欧州でのネオナチの台頭等——が激化していた。カオス化する世界にあって、新しい調和をどう創り出すのか——この問いをめぐり、池田先生は「閉じた箱」「開いた箱」という観点から論及。「閉じた箱」すなわち人間が陥りやすい独善と偏見は、植民地政策等をもたらした自民族中心主義、環境破壊を招いた人間中心主義と通底しており、近代科学および、それを土台とした文明もまた普遍性を担保しえない。ゆえに、閉じた箱から締め出された「他人の痛みへの感受性や思いやり」「異文化・異民族への理解や寛容」等の人間性の回復を強調。分断された人と人、人と自然を調和させるため、人間・生命の全領域を豊かに蘇生させる「大いなる普遍」への視座を持つべきだと提唱した。同アカデミーのアダイテ元総裁は、「講演は、人類が人類であるための気高い意思をよみがえらせ、一国の民衆のみならず、全民衆の精神を高め、志を大きく広げてくれました」と称賛を寄せた。************ セニョーラス・エ・セニョーレス・ポーア・ノイテ(皆さま、こんばんは)。オージ・エスト・ムイト・へリース(本日は、お会いできて、とてもうれしいです)!(大拍手)尊敬するアダイテ総裁はじめ、ブラジル文学アカデミーの諸先生方、その光栄にもフランコ大統領閣下の名代としてご臨席くださったオアイス文化大臣、またリオ州を代表してご臨席くださったくれ頓法務長官はじめ、すべての御来賓の皆さま。本日、偉大なる伝統を誇る知性の殿堂ブラジル文学アカデミーより「災害会員」の一席を賜りましたことは、私の最大の名誉であり、衷心より御礼を申し上げます。ここリオが生んだ卓越した雄弁家モンタウぺルネの名を冠するこの席にスペンサー(イギリスの思想家)、ヒノット(フランスの社会学者)、マルチネンチェ(フランスの文学者)、ピダル(スペインの文学史家)、そして創立者アシス初代総裁の翻訳で知られるグロスマン(アメリカの翻訳家)という光輝満つる方々に続いて、東洋人として初めて就任する栄誉に浴しましたことを深く感謝申し上げるものでございます。さらに重ねて、栄えあるアシス褒章を授与いただき、これほどの喜びはございません。本当にありがとうございました。(拍手)さて、ブラジル近代文学の栄光の父である初代アシス総裁が述べているように、十九世紀末、貴アカデミーは、フランス学士院に範をとりつつ、青年たちが集い、新しい理想を掲げて誕生されました。実は、私は四年前そのフランス学士院に招かれて、「東西における芸術と精神性」と題して講演したことがあります。その末尾を次のような自作の一節で結びました。「今 芸術は/その手もて 魂を誘う/天かける 想像力の花園へ/いと高き 英知の台(つてな)へ/そして/地球文明の はるかな地平へ」と。科学技術の発達によって、否応なく地球が一つになりつつある現在、それに対する精神面からの対応、すなわち地球文明というべきものを志向しなければ、二十一世紀の希望の朝(あした)はあり得ない、との私の信念からであります。とはいえ、イデオロギー崩壊後の世界はよくいえば多様化、悪く言えばエントロピー増大の法則さながらにカオス化の様相を一段と強めつつあります。そうした流れにあって、多様性のなかに調和、統一を求め、地球文明の地平を切り拓いていくために、ブラジル文明のもっている重みは、計り知れないものがある、と私は思う一人であります。世界に冠たる人種デモクラシーにしても、近年のアメリカのロサンゼルス暴動、ヨーロッパにおけるネオ・ナチスの台頭などを考えてみれば、どれほどかけがえのない人類史的財産であるかは、あまりにも明らかであります。そうしたブラジル人の国民性を作家オランダの古典的著作は、「率直な態度、新設、手厚くもてなそうとする気持ち、寛大な心など(中略)ブラジルを訪れる外国人がこぞってほめそやすこれらの美徳はブラジル人の国民性としてこれからも消えることのない特徴と為ろう」(S・B・デ・オランダ『ブラジル人とは何か』マウリシオ・クレスポ訳、新世界社)としております。確かにブラジル日系人の知己たちが、異口同音に口にする言葉は、ブラジルは住みやすい国だ、ということであります。 私は数年前、ブラジル移住八十年の歴史をもつ日系一世の児玉良一氏と対談集(『太陽と大地 開拓の曲』第三文明社。『池田大作全集』第61巻収録)を編みましたが、氏はその中で、「ブラジルの自然はなんでも好きです。本当にブラジルが好きなので、今度この国に生まれたいかといえば、ブラジルです」(趣意)と、にこやかに語っておりました。多くの人を、否、万人を魅了してやまぬ、そのようなブラジルの国民性、精神的土壌の奥底に横たわっているものは何か——貴国の生んだ偉大な作家であり、誉れ高きアカデミーの会員であったローザの名作、『大いなる奥地』に擬して、私はそれを「大いなる普遍」と申し上げておきたいと思います。近代史の数百年を通じて、ある種の普遍主義を標榜しながら世界を席巻してきたのは、いうまでもなくヨーロッパの科学技術文明であります。それは、効率主義と拡大主義という有無を言わせぬ駆動力によって、強引に世界をその影響下に置いてきました。二十年前に私と対談したトインビー博士が、優れた小冊子を『世界と西欧』と名付けたように、世界の他の地域は、科学技術を軸にした西欧文明をどう受け入れ、どのようなスタンスをとるかで、それぞれ自国の進路を模索せざるをえませんでした。それは貴国の鋭敏な知性たちが、一九二〇年代以降、「近代主義」あるいは「地方主義」といった形で、熱烈に問いかけ続けたテーマでもあるはずです。ところで、こうした科学技術文明の標榜する普遍主義が真に普遍の名に値するかといえば、明らかに否、であります。確かに、価値や意味の世界から切り離され、自己完結的世界にあっては、普遍的な広がりや整合性を持つかもしれないが、それは例えば、果物の表皮のようなものであります。果物それ自体、すなわち人間生活の全領域から見れば、ごく限られた一部でしかない。普通というよりも、むしろ個別・特殊的な一領域にすぎないのであります。その点、イギリス・ケンブリッジ大学の天文学の権威、ホイル博士は、「閉じた箱」「開いた箱」というユニークな問題提起をしております。これは、博士の愛弟子であるスリランカ出身のウィックラマシンゲ博士と私が、昨年秋に上梓した対談集(「『宇宙』と「人間」のロマンを語る」毎日新聞社。『池田大作全集』第103巻収録)に寄せてくださった序文で述べられたものです。博士によれば、近代科学は、西暦五〇〇年ごろに形成された地球中心主義のドグマ、つまり「閉じた箱」的発想に立っている。すなわち、「何事もこの地球上で起こることは、地球の外側の宇宙で起こる出来事といかなる関係もありえない。ただし、ありがたい太陽熱だけはもちろん別である」という見解であります。しかし、「閉じた箱」の中で解決できる問題はごくわずかであり、特に宇宙や生命へのアプローチは、もっと「開いた箱」的発想に立たなければならない。その点、共にアジア人であり、仏教という文化土壌を共有している、私とウィックラマシンゲ博士との対話に、大きな期待を寄せてくださっているのであります。それはさておき、心すべきは「閉じた箱」的発想は、それが人間の習慣に基づくものである限り、科学にとどまらず死生観全般に及んでくるということであります。「閉じた箱」とは、平易に言えば、外部に目をふさぎ、自らを独りよしとするドグマや偏見といえましょう。それゆえ、近代科学がそれと意識せず陥っていた地球中心主義は、近代文明総体に色濃く影を落としている、人間中心主義、民族中心主義等と通底しており、同じ「閉じた箱」から生まれた、一卵性双生児といっても過言ではありません。本論の文脈に即して言えば、アジアやラテン・アメリカ、アフリカ等に猛威を振るった植民地主義も、その淵源をたどれば、その「閉じた箱」的発想に行き当たると思います。それがいかに強く近代文明を呪縛し続けてきたかは、皆さま方に申し上げることもないでしょう。 しかも、多くの科学者が善意の人であったように、植民地政策を推進した民族中心主義が罪の意識や後ろめたさをともなくことなく、むしろある種の使命感にさえ支えられ、まかり通ってきたことに、問題の根の深さがあります。それを典型的に浮き彫りにしているのが、ポーランド生まれの英国作家コンラッドの中編『闇の奥』であります。彼自身も象牙採集船の船員として、コンゴ川をさかのぼり、白人の黒人に対する搾取をつぶさに実見してきているだけに、描写の迫真性は、おそらく類を見ないと思われます。 新たなるコスモス形成の基盤に その中に、〝この地上の征服とは何か〟について語られる一節があります。すなわち征服について、「単に皮膚の色の異なった人間」たちから、無理やり勝利を奪い取ることにほかならないとしつつ、次のように記されております。「よく見れば汚いことに決まっている。だが、それを償ってあまりあるものは、ただ観念だけだ。征服の背後にある一つの観念。感傷的な見栄、いいや、そんなもんじゃない、一つの観念なんだ。己を滅して、観念を信じこむことなんだ、——われわれがそれを仰ぎ、その前に平伏し、進んで犠牲を捧げる、そうしたある観念なんだ」(中野好夫訳、岩波文庫)植民地主義の野蛮な情熱と表裏をなしている、一種の透明で非人称的な普遍主義の響きをコンラッドの文章はよく伝えております。彼の言う「観念」とは、まぎれもなく「閉じた箱」の産物であります。こうした「観念」は、確かに「閉じた箱」の果かでは独りゆく〝気概〟たり得ても、一度「開いた箱」に移されるや鼻持ちならぬ〝臭気〟を発し始めます。それは、コンラッドの作品の「観念」の使途を待ち受けていた、恐るべき人間性の荒廃をあげれば十分でありましょう。植民地主義に限らず、近代文明は、総じて「閉じた箱」の内部で展開されていきました。そこから締め出されてきたのは、他人への痛みの感受性や思いやりであり、異文化・異民族への理解や寛容であります。また理性と感性とのバランス、自然や宇宙との共感であり、偉大なるものに対する敬虔さ等であります。そして、すべてとはいわないまでも、それらの多くが、先ほど申し上げた作家のオランダが簡潔に要約しているブラジル人の美徳に符合しているのではないでしょうか。いたずらに貴国を美化するつもりはありません。確かに詩人アンドラ―デが、嘆息まじりに「かくも堂々たる、かくも果てしなき、かくも途方もなき彼女」(J・フランコ『ラテン・アメリカ』吉田秀太郎訳、新世界社)と形容したように、ブラジルの精神性における光と闇のめくるめく交錯は、安易な要約など拒絶しているかもしれません。しかし、私は、たとえ地中に埋もれた磨かれざる原石のような状態にあったにしても、その精神性の土壌に、近代文明の表層的な普遍主義にとって代わる「大いなる普遍」への可能性の回路を見たいのであります。 昨年五月、貴国での「地球サミット」の一環として皆さま方の多大なご尽力を賜り、私どもSGI(創価学会インターナショナル)が「環境と開発展」を開催させていただいた折、シンポジウムの席上、尊敬するアダイテ総裁は次のように語られました。ここ文学アカデミー新館講堂のこの席でのスピーチであります。すなわち「ブラジル国民は偉大な国民であり、希望の源泉である。新世紀の幾多の困難を克服していくためには、この「希望のブラジル国民」こそ頼みとすべきでありましょう」と——。芸術の世界にしても、かつてイギリスのエリオットが「荒地」と言い、フランスのヴァレリーが「枯渇の泉」と言った如く、先進諸国の芸術が押しなべて生命力を衰退させていくなかで、ブラジルに限らずラテン・アメリカの文学が、際立ってコスミックな危機意識を体現し、新たなコスモス形成への強烈なバイタリティーを放射しているのも、決してゆえなきことではないと思うのであります。その意味からも近代ヨーロッパの序幕と終幕を激しく生き、普遍的な精神性の価値を模索し続けた、代表的なコスモポリタンであるモンテーニュとツヴァイクが、共にブラジルの天地の厚い思いを寄せているのは、興味深い。もとより、モンテーニュが十年余りの現地体験をもつ使用人から聴取したのは、いまだブラジルの名さえなかったインディオ社会の風習ですし、ナチスに追われたツヴァイクが亡命の地としたのは、人種デモクラシーの著しく進んだ二十世紀中葉のブラジルであり、同列に論じることはできないでありましょう。しかし、死を間近にしたツヴァイクが、ブラジルの血でモンテーニュを読みふけっていた事実に象徴されるように、稀有なコスモポリタン的資質の持ち主であった二人のこのゆくりなき符号は、私には何か示唆的な出来事のように思えてならないのであります。モンテーニュの『エセー』は、私の若いころからの愛読書でありますが、人間学の宝庫ともいうべきこの大冊の中でも、ブラジルの風習について語られた部分は、ひときわ異彩を放っております。「新大陸の国民について私が聞いたところによると、そこには野蛮なものは何もないように思う。もっとも、誰でも自分の習慣にないものを野蛮と呼ぶなら、話は別である。まったく、われわれは自分たちが住んでいる国の考え方や習慣の実例と観念以外には真理と理性の尺度をもたないように思われる」(「モンテーニュ」1、原二郎訳、『世界古典文学全集』37所収、筑摩書房)こう静かに開始される考察は、インディオ社会の風習に対する、当時の常識から見て驚くほど大胆で勇気ある評価であります。その曇りなき眼、平衡感覚は、〝野蛮の発見〟といわれる二十世紀の文化人類学の成果である文化相対主義を、四百年前にして、優に先取りしております。モンテーニュが濃密に体現していたように、自己本位の「閉じた箱」的発想でなく、常に相手の立場に立って物事を見ようとする複眼の視座こそ、コスモポリタンの不可欠の要件であり、一方的、画一的なものの見方は、普遍主義の値に値しないのであります。故郷を追われ、「私がほとんど半世紀を通じて、コスモポリタン的に「世界の市民」として鼓動するように私の心臓をしつけたことも、その甲斐はなかった」(『昨日の世界』Ⅱ、原田義人訳、『ツヴァイク全集』20所収、みすず書房)と、失意と傷心の淵に沈むツヴァイクの魂を温かく包み、癒したのもブラジルの天地でありました。回想録『昨日の世界』に付せられた彼の「遺書」の一節ほど〝ブラジル的なるもの〟の包容性を語っているものも少ないと思います。「日一日といやます思いで、私はこの国を愛するようになった。私自身のことばを話す世界が、私にとっては消滅したも同然であり、私の精神的な故郷であるヨーロッパが、自ら否定し去ったあとで、私の人生を根本から新しく建てなおすのに、この国ほどに好ましいところはなかったとおもうのである」(同前)両度にわたる世界大戦、なかんずくナチスの暴虐は、近代文明の自殺行為にほかならなかった。文明の高みから野蛮を見下してきた彼らこそ、実は野蛮以上に野蛮な本性をもつことが白日の下にさらされてしまった。私は、モンテーニュがインディオを評して、「われわれのほうこそあらゆる野蛮さにおいて彼らを超えている」(原二郎訳、前掲書)と語るのを、ツヴァイクは深く深く首肯していたであろうと想像されてなりません。ところで私は貴国についてイギリスのラテン・アメリカ額の草分けであるジーン・フランコ女史の『ラテン・アメリカ』から多くのことを学びました。女史は、その中で、二十一世紀のブラジル文化の特徴を、「根源を求めようとする動きとの間の緊張」、更に「地方的または地域的な特徴を強調しようとする人々と、ブラジルを世界文化の先端に位置づけようとする人びととの間」の「緊張」としております。(吉田秀太郎訳、前掲書)まことに簡潔にして要を得た指摘と言ってよく、「大いなる普遍」飲み法雄置き果実もまた、そうした「緊張」関係の中でしか得られないと、私は信じております。「個別」と切り離された「普遍」はコンラッドの「観念」のように一人歩きする危険性をはらんでおります。これは民族や階級といった「観念」が猛威を振るった二十世紀が、多大な代償を払って手にすることのできたかけがえのない教訓であります。そうではなく、真実の「普遍」は「個別」に即して求められねばならず、両者の絶えざる緊張関係の中で、個別的なものに普遍的な意義づけを与えていくものこそ、芸術の有する真骨頂ともいうべき想像力の働きであると思うのであります。ちなみに、こうしたアプローチの仕方は、大乗仏教にも極めて親しいものであります。「八万四千の法蔵は我身一人の日記文書なり」(御書563㌻)——釈尊一代の説法は、我が身一人の日記の文書である——「一人を手本として一切衆生平等」(同564㌻)と。——この法門は、一人を手本にすることによって一切衆生に皆平等に当てはまる——すなわち、普遍的な理論や理念は、それ自体として意味を持つものではない。あくまでも具体的な一個の人間に即して展開されているのであります。さて、国民性の美質を探るには、優れた作家の手腕を借りるのが一番いいと思います。貴国の文学の日本語への翻訳は、残念ながら、まだまだ緒についたばかりでありますが、その中で土俗性と近代性、個別性と普遍性の問題を、最も鋭く提起しているのは、ローザの『大いなる奥地』ではないかと私は思います。実際、ブラジル北東部の奥地で熾烈な戦いを繰り広げる若き野盗リオバルドの口から、やや唐突に「私は宗教に基づいた都市を作りたいと思う」(中川敏訳、『筑摩世界文学大系』83所収、筑摩書房)という骨太の、コスミックな響きを帯びたセリフ聞いたときの不思議な感動が私は忘れなれません。今の世界のどこかで、宗教がこのようにみずみずしい生命力を讃えて語られているでしょうか。世紀末の今の宗教事情といえば、限りない世俗化の流れに洗われて形骸化するか、個人の内面的支持としてみすぼらしく逼塞させられるか、オカルトまがいの淫祠邪教が、つかのまの盛衰を繰り返すか、あるいは、間欠泉の用にエネルギーを沸騰させ流血抗争の引き金を引くかが、ほとんどといってよいでしょう。いずれにしてもマイナス・イメージばかりであり、宗教が期待を込めて肯定的に語られるケースは稀であります。確かに、リオバルドの資質は、宗教を語るにも足るものであった。一見野性的で荒々しく見えの彼の情熱は、その実、神や悪魔との契約についても思い悩み、愛とは何か、信頼とは、自由とは、勇気とは……と人生を問い続ける類まれな繊細さに裏打ちされていた。「大いなる普遍」への目覚めが調和を生むだからこそ、奥地をめぐる覇権は、単なる覇権争いではなく、目指すは正義の実現であり、彼らなりの使命感に基づく覚醒への一撃であった。転戦のおもむくところ、戦いが「内なる戦い」の様相を強めてくるのも当然の帰結しょう。「わたしたちは奥地(セルタン)を目覚めさせなくてはならない! ただし、奥地を目覚めさせる方法はただひとつ内部から目覚めさせるのでなくてはならない」「奥地——それは人の心の中にある」(同前)「奥地」という個別性から「内なる奥地」という普遍性への深化、昇華であり、「宗教に基づく都市」とは、そうした内面化を経ながら日常性を脱し、宗教学で言う〝聖なるもの〟の現れとして彫琢されているシンボルなのであります。そこに遠望されているのは近代の退化した宗教ではもとよりありません。それは、「人間」と「自然」と「宇宙」とを包み込んで、その勇気的結合の要となり、コスモロジー再興へのエネルギー源たりうる、優れて統合の力を有する宗教といってよい。リオバルドの言葉が「大いなる普遍」と呼ぶにふさわしい内実、リアリティーをもつゆえんであります。しかも、そのリアリティーは、個別へのあくなき執念によって保障されている。野盗という原始的世界の素材をとっている点といい、博物学や地理学にも精通した著者ならではの微細を究めた奥地の自然描写といい、ふんだんにちりばめられた民間伝承といい、私はそれらが『モナ・リザ』の〝ジョコンダの微笑〟をひきたたせているそのバック——すなわち、空気遠近法を駆使して描かれた峨々たる岩山と、同様に効果を演じているように思えてなりません。留意すべきは、その宗教間であります。「私が固く信じ、断言し、説明しようとしているのは、全世界が狂っているということである。そう、お客人、あなたも、私も、私たちが、万人が、狂っている。そこで、狂気から脱して正気を取り戻すためには宗教が必要となる。いつも、狂気を治すのは祈りなのだ。祈は魂を救済する」(同前)時代の病を癒すために、宗教的祈りを必須としつつ、しまも、その宗教観からは、宗教的ドグマが慎重に斥けられ、普遍的なるものが強く志向されている点に注目したい。ドグマは癒しどころか、むしろ狂気・狂信を増進させるものでしかないからであります。そうではなく宗教は、人間の精神性を陶冶し、善きものへと高めながら、新たなコスモス形成の基盤となっていかなくてはならない。ローザの希望していたそうした宗教的世界こそ、「大いなる普遍」の理念型であり、二十一世紀の地球文明のバックボーンとなっていくであろうことを、私は信じてやみません。私も微力ながら、そのような普遍的な精神性の土壌の開拓にいやまして挺身してまいる決意であります。最後にブラジルの限りない未来に思いをはせながら、偉大なる自由の詩人アルベスの詩を皆さまと分かち合い、私の講演とさせていただきます。「然り!/指の隙間から/時の砂がこぼれ/やがてひとつの世紀が/尽きんとするとき/ある国に/偉大なる人物の名が/数多見出される/掌におさまらぬほどに/おお! 英雄たちよ!/荘厳なる杉の大樹が/幾世紀を超えてなお/崩れざる堅固さをもって/そびえ立つが如く/貴方たちこそが歴史(ドイツ)の大樹である/そして/ブラジルが憩いゆく」(Poesias Completas de Castro Alves,Editora Tecnoprint)ムイト オブリガード(どうも ありがとうございました)。 【創造する希望 池田先生の大学・学術機関講演に学ぶ】創価新報2021.5.19
July 4, 2022
コメント(0)
-
人間主義の最高峰を仰ぎて——現代に生きる釈尊
人間主義の最高峰を仰ぎて——現代に生きる釈尊(トリブバン大学1995年11月2日) 時代背景と講演の意義第2次世界大戦終結から50年目の節目を迎えた1995年11月2日、池田先生はネパール随一の最高学府・国立トリブバン大学で講演を行った。当時、世界では絶え間ない民族対立や地域紛争の激化、悪化の一途をたどる環境問題、大量難民流出など、地球的課題が山積。日本にあっても、「阪神・淡路大震災」や「地下鉄サリン事件」など、悲惨な災害や事件が相次いで起こっていた。こうした故動く社会の中で、池田先生は「知恵」と「慈悲」の二つの角度から釈尊の「不滅の精神」に迫り、それが現代の平和建設にどう生かされるかを語った。講演の前半は、釈尊が放つ「智慧の大光」が照らし出す三つのメッセージ、①「生命の宝塔を輝かせよ」②「民の心に聴く」③「〝智慧〟よく〝知識〟を活かす」に論及。後半は、釈尊の「慈悲の大海」の姿に、①人類の宇宙的使命は慈悲にある」②「ヒマラヤのごとく悠然と」③「自他供の幸福を目指せ」との三つのメッセージが示されていると主張した。そして、自他供の幸福を願う人間主義の地球規模の連帯こそが、それぞれの国に個性豊かな繁栄を築き、人類全体の栄光を開く光源になると訴えた。講演終了後、K・K・ジョン同大学副総長(当時)は、「すばらしい講演でした。釈尊を語る人がいても、釈尊を実践する人はいません。SGI会長は、平和と人間主義という釈尊のメッセージを、今、この場で学生たちに教えてくださいました」と称賛した。 ヒマラヤのごとく悠然たる不動の自己をナマスカール(尊敬する皆さま、こんにちは)。尊敬するジョン総長代行並びに副総長はじめ諸先生方。そして卒業生の皆さま。本日は、釈尊生誕の地であり、あこがれのネパール・トリブバン大学の卒業式で講演の機会を与えてくださり、私は大いに喜び、名誉に思っております。心より御礼申し上げなす。ありがとうございました。アジアを代表する最高峰の貴学府より、かくも晴れ晴れと学位記を授与されました皆さまに、私は最大に祝福を申し上げます。授記に際して、まことに厳粛な宣誓がなされる光景に、私は心から感動いたしました。この気高き誓願を抱く、二十一世紀の若きリーダーの前途に思いをはせるとき、私の胸は希望に高鳴るのであります。本日は「人間主義の最高峰を仰ぎて——現代に生きる釈尊」と題して、皆さまともどもに、この偉大なる〝人類の教師〟が残した精神的遺産を、「智慧の大光」「慈悲の大海」という二つの角度から、考察したいと思います。荒れ狂う怒涛のなか、〝海図なき航海〟を余儀なくされている現代人の姿を目にするとき、私は、貴国の偉大な詩人パーラクリシュナ・サマの詩の一節を思い起こすのであります。 無知の少年がするような言い争いは避けよう不和を解消し 繁栄を享受し盲信を捨て去ろう人間主義を信奉し 自他ともに生き抜くのだ真理の探究と 善行の決心を競い合おうではないかおお世界よ私が息を引き取る前に核兵器の脅威を取り除いておくれ永遠の平和の歌声で戦争の二字を消しておくれ(「さらば、おお世界よ、さらば!」) 戦乱の世紀にあって、砂漠で水を欲するように、痛切なまでの平和の希求であります。それは、ネパールの人々の美しき心情そのものでありましょう。そして、その水源のありかを探し求めようとするとき、巨大な姿を現してくれるのが、人々に平和と安穏をもたらそうと肝胆を砕き続けた、かの釈尊の「人間主義の最高峰」ともいうべき「智慧」と「慈悲」ではないかと思うのであります。 釈尊が放つ「智慧の大光」の第一は、「生命の宝塔を輝かせよう」とのメッセージであります。近代の幕開けから二十世紀末の今日にいたるまで、人間社会の営みは、科学技術の発展、産業・経済の成長など、量的な拡大を主眼とする「進歩主義」への強力な信仰に支えられてきたといってもよいでありましょう。しかし、そこには、思わぬ落とし穴が待ち構えておりました。人々が、酒に酔っているように「進歩主義」の夢を追い続けているうちに、「青写真」のために「現実」が、「未来」のために「現在」が「成長」のために「環境」が、「理論」のために「人間」が、ないがしろにされてしまったという事実であります。ここに、今世紀の悲劇がもたらされたのであります。こうした人類の現状に対して、釈尊の智慧は、人間の「生命それ自体」に立ち還っていくことこそが最も重要であると、提起しております。釈尊の教え精髄とされる「法華経」には、壮大にして荘厳なる宝塔が登場いたします。それは、まさしく、人間の内奥に広がる宇宙大の生命を象徴しております。小宇宙ともいうべき芳醇な「生命」の開拓こそが、釈尊の生涯をかけた主題であったと思うのであります。 近年、「人間開発」という指標が強調されている趨勢を見るにつけて、この釈尊の先見は、いやまして光っております。私が十年以上前に対談集を編んだ、ローマ・クラブの創立者ペッチェイ博士は、遺言のごとく、こう述べておりました。「これまで探索されたことすらない未開発で未使用な能力という、莫大な富がわれわれ自身の内部にある」「これこそまさに驚くべき資源であり、再生も拡大も可能な資源」(『二十一世紀への警鐘』読売新聞社。『池田大作全集』第4巻収録)である、と。博士と私は、この「生命」の開発を、「人間革命」と意義づけたのであります。その開発のカギこそ「教育」であり、貴国は、模範の取り組みを続けておられます。それはまた、未来世紀への責任を自覚した「持続可能な開発」への大いなる運動になっていくことは間違いありません。仏典には「過去の因を知らんと欲せば其の現在の果を見よ未来の果を知らんと欲せば其の現在の因を見よ」(御書231㌻)とあります。いたずらに過去にこだわらず、また未来への不安や過度の期待に引きずられることなく、〝今、現在〟の自己の充実と確立こそ第一義であることを啓発しているのであります。いわば、「刹那に永劫を生きよ」「足下を掘れ、そこに泉あり」という凝結した生き方の提示であります。まさに釈尊は、〝今この瞬間〟に「生命の宝塔」を光輝あらしめ、そこから、人類の未来を照らしゆく「真実の進歩」を切り開いていきなさい、としました。これが魂の巨人である大勝利者の言葉であります。第二のメッセージは、「民の心に聴く」ということであります。仏法では、少々、難しい言葉ですが、「不変真如の理」にも増して、「隨縁真如の智」を重んじております。つまり、時代や状況によっても変わらない真理に基づいたうえで、刻々と変転する現実に応じて、自在に智慧を発揮していくことが大切であると教えているのであります。そうした行き詰まりのない智慧の源泉は、釈尊の「民の心に聴く」という姿勢にあったと、私は考える一人であります。「心に問おうと欲することは、何でも問え」(『ブッダのことば』中村元訳、岩波文庫)——釈尊はしばしば人々にこう語りかけております。まことに、釈尊こそ、ソクラテスと並ぶ「対話の名人」であり、民衆との対話の海の中で、人々を導いていきました。釈尊こそ、比類なき、「人間教育の大家」であったと思うのであります。例えば、最愛のわが子を失い、悲嘆にくれる母に、釈尊はその子を救う〝薬〟として、芥子の種子を探すように語りかけます。ただし、その種は、まだ「死人を出したことのない家」から、もらってくるようにと指導するのであります。その母は、必死になって、一軒一軒、訪ねて回った。だが「死人を出したことのない家」など、どこにもなかった。次第に母は、自分だけではなく、どの家も、家族を亡くした苦しみを抱えていることに気づき始める。そして、自身の悲哀を乗り越え、「生老病死」という根本の課題の探求に目覚めていったというのであります。釈尊が、どれほど民衆の心を見つめ、人々の境涯の向上のために慈悲と智慧を注いでいたか、多くの説話を読みながら胸に迫ってくるのであります。 菩薩の行動こそ人類の連帯築く希望の源泉 「法華経」には、持経者の理想的な姿として、あらゆる民衆の声を聞くという徳性をあげております。すなわち、「彼の人は、無数の人々の声を聞いてよく理解し、天の声、妙なる歌声を聞き、男女の声、幼い子どもたちの声を聞く。山や川、険しい谷の中の鳥の声までも聞く。地獄の諸の苦しみの声や、飢えたる人々の飲食を求める声を聞く。下は阿鼻地獄から上は有頂天に至るまで、あらゆる音声を聞いて、しかも耳根は壊れることがない」(法師功徳品、趣意)。これは、単に宗教的実践の指標であるだけではなく、政治・経済・文化・教育の万般にわたる大指導者論であると、私は思っております。私どもの「創価(価値創造)教育学」の創始者は、第二次大戦中、日本の軍国主義と戦い、七十三歳で獄死しました。その名は牧口常三郎と申し、創価学会の初代会長でありました。牧口会長は小学校の校長でしたが、相手がいとけない小学生であろうと、過酷な取り調べの堅持や看守であろうと、その人の人格を尊重し、常に「対話」を貫き通しました。「生涯教育」や「環境教育」の提唱、また「母たちの声」を反映させた学校教育など、牧口初代会長の先駆的な智慧も、「民の心に聴く」という徹した「対話」から生まれたといってよいのであります。第三に申し上げたい「智慧」のメッセージは、「〝智慧〟よく〝知識〟を活かす」という価値創造の道であります。貴大学で、最先端の学問を習得なされた皆様の姿に、私は、カピラバットゥの城で、学びに学んだ釈尊の青春を想起するのであります。若き王子たる釈尊は、天文学・医学・法律学・財政学・文学・芸術等々、あらゆる学問に取り組みました。〝「他人を苦しめるような呪法」ではなく、「すべての民」のためになる知識を学べ〟(立川武蔵訳、『ブウダチャリタ』、『原始仏典』10所収、講談社。引用・参照)——これが、釈迦族の帝王学だったのであります。私が感嘆するのは、人々の苦悩を救いゆく釈尊の一生にあって、青年時代までの学問が、ことごとく生かされているという事実であります。だからこそ釈尊は、王にも、農民にも、当時、勃興しつつあった商人層にも、「随宜説法(機根にしたがって法を説く)」「応病与薬(病気に応じて薬を与える)というように、それぞれにふさわしい譬喩や道理を駆使しながら、法を説くことができたと思うのであります。「核」と「遺伝子」に象徴される現代の科学知識の発展は、それを人類全体の幸福のために使うか、それとも個人や民族や国家のエゴのために使うかを、今、厳しく問われております。いまだに、核抑止論という自らつくった〝恐怖の均衡〟政策から脱却もできない世界の現状は、残念ながら、エゴを克服できないまま、暴力、武力等に屈服している哀れな、悲しい姿といわざるをえません。釈尊の遺誡に、「心の詩とはなるとも心を師とせざれ」(御書1025㌻)とあります。心に渦巻く煩悩(暴力性や貪欲性)に左右されず、支配されず、またそれを無理やり消滅させるのでもない。自らが「心の師」となって、煩悩をも価値創造の方向へリードしていきなさい、との教えであります。その「心の師」となるのが、人間生命の内奥より勲発されゆく「智慧」なのであります。そして、この「智慧」は、人間のために、民衆のためにという「慈悲」の泉があって初めて、限りない作用があることを知らなければなりません。 次に、釈尊の人格を構成するもう一つの柱は「慈悲の大海」の姿であります。慈悲の第一のメッセージは、「人類の宇宙的使命は慈悲にある」という使命論であります。釈尊にとって、まさに「宇宙は慈悲の当体」であり、自らの振る舞いは、その慈悲の体現でありました。宇宙の神羅万象は、一切が「縁起」、すなわち、縁りて起こっている。お互いに支え合っているがゆえに、何一つ無駄なものがない。また意味がないものはあり得ないというのであります。その相互依存の「糸」を活用して、宇宙は生命を育み、この地球上には、人類をも誕生させたわけであります。仏法では、現代天文学の知見とも一致して、この大宇宙の他の天体にも、知的生命が活躍していると論じております。まさしく、宇宙それ自体が生命体であり、貴い慈悲の顕在化であると見ることができるのであります。釈尊は、生まれ故郷である貴国を目指していたとも推察される〝最後の旅〟の途上、訪れた町で豊かに生い茂る木々を見つめながら、繰り返し、「楽しい」「楽しい」、「美しい」「美しい」との感慨をもらしておりました。生涯、広大な大地を歩きに歩き、民衆救済の平和旅を貫いた釈尊の慈悲が、宇宙生命の永遠なる慈悲の律動と共鳴していた姿であると私は信ずるのであります。翻って、近代が直面している一番大きな課題は、「生きる意味の喪失」であります。何のために生きるのか。人間とは、一体、何か、人間は何のために生きるのか——。生きる「意味」を見失った現代人は、「意味への渇望」に身を焼きながら、社会からも、自然や宇宙からも独立し、疎外感のなかを、さまよい続けております。仏法の慈悲論は、この地球上に誕生した人類の使命は、宇宙の慈悲の営みに参画し、その創造のダイナミズムを高めつつ生き抜くことにあると明示しております。つまり、万物を育み、繁栄と幸福に導く慈悲の行動こそ、宇宙より人類に託された使命であり、この使命の自覚と達成にこそ、「生きる意味」があると釈尊は呼びかけているのであります。このような慈悲論は、今日において、一人一人の人間を尊重しゆく、「共生の文化」を養い、地球環境と共栄しゆく「自然観」を培っていくことでありましょう。そして、さらには、「分断」から、「融和」へ、「対立」から「融和」へ、そして、「戦争」から「平和」へと人類史を軌道修正させゆく、菩薩道の行動を促してやまないのであります。釈尊の慈悲が贈る第二のメッセージは「ヒマラヤのごとく悠然と」であります。すなわち、確立された「不動の自己」こそが、大慈悲の基盤となるからであります。一切衆生を潤す釈尊の慈悲の大境涯は、まさしく、嵐があろうと厳然として微動だにもしない、ふるさと「ヒマラヤ」の秀峰をほうふつさせております。「善き人たちは、雪の山(=ヒマラヤ)のように、遠くから輝かせる。だが、悪しき者たちはここにあっても見られない。夜放たれたもろもろ矢のように」(宮坂宥勝『真理の花たば・法句経』筑摩書房)と述べているように、釈尊が目指した理想の人間像とは、白雪をいただきながら、いつも悠然とそびえ立つヒマラヤの不動の姿がイメージされていたにちがいありません。多くの識者が指摘するように、自由や平等が主張されると、良い意味でも悪い意味でも社会は変動常なき状態に置かれます。そうであればあるほど「不動の自己」が確立されないと、他人と比較することばかりに気をとられ、知らずしらず嫉妬や怨嫉という情念に支配されてしまうのであります。ゆえに、こうした縁に粉動されぬ、「不動の自己」は、いつの時代にあっても、社会に安逸をもたらす原点であります。そして、現代ほど、その原点の要請が重要なときはないと感じるのは私一人ではないと思うのであります。だからこそ、「自らを依処とし、法を依処すべし」という釈尊の弟子への遺訓は、そのまま、宇宙究極の法と一体化した「不動の自己」(大我)へと導く、人類への遺訓であるといえないでしょうか。最後に、第三の慈悲のメッセージは、「自他供の幸福を目指せ」という行動論であります。近代人権思想の勝ち取ってきた最大の遺産が「個」の尊厳であることは論を待ちません。しかし、この問題は、制度的な保障だけですむものではない。それどころか、現代人は、自らの主張にのみ専念するあまり、他者の存在を見失い、その結果、肝心の自分自身のよって立つ基盤さえぐらついてしまうのであります。他者と自身の関係性を、釈尊は次のような言葉で表現しております。 人はおのれより愛しいものを見出すことはできない。それとおなじく他の人々にも、自己はこのうえもなく愛しいさればおのれのこよなく愛しいことを知るものは自愛のために、他のものを害してはならない(増谷文雄『仏陀のことば』角川書店)人間、「自分」ほど大切なものはない。ゆえに、「我が身に引き当て」、「他者」を大切にすべきである——まことに無理のない自然な語り口のなかで、相互に「他者」の存在、相手の立場に立ち、共感することこそ慈悲の第一歩であると釈尊は説いているのであります。孤独な現代人の心の病を癒す「良薬」は、ここに求め津以外にないと思うのは私だけではないでありましょう。釈尊は、成道してから、その法を人々に説こうか、説くまいか、大いに躊躇し、葛藤しております。解けば必ず、無理解な批判や迫害が沸き起こるであろう。敢えて人に語らず、自分一人で、静かに法悦を味わってもよいのではないか……。皆さま方の方がよくご存じとと思いますが、仏伝によれば、この逡巡する釈尊の前に、梵天(ブラフマン)が現れ、「前進か後退か」「幸福か不幸か」「栄光か悲惨か」、そうした分岐点に立たされている人々のために、是非とも、教えを説くように懇願したといわれております。この「梵天の勧請」が、釈尊の「自己」のなかに「他者」を復活させ、自他供の崩れざる幸福へと進みゆく、真の「仏」の誕生の契機となったとされているのであります。「一切衆生の病むがゆえに我病む」釈尊の心中には、常に、生老病死の苦悩に喘ぐ民衆の呻き声が響いておりました。時を超え、国を超え、釈尊は、こう呼びかけているのであります。「汝の心のうちに『他者』を復活に、自他ともの幸福を満喫せよ」と。ゆえに十三世紀の日本の日蓮も、「法華経」を解釈しつつ、「自他共に知恵と慈悲と有るを喜とは云うなり」(御書761㌻)——自他ともに、智慧と慈悲をもっているのが本当の「喜び」である——と応えているのであります。それは「第三世代の人権」、すなわち「平和な国際秩序」と「健全な地球環境」を創設しゆく「連帯権」にも通じていると、私は思うのであります。こうした人間主義の連帯こそが、それぞれの国に個性豊かな繁栄を築きながら、人類全体の栄光を開きゆく光源となるでありましょう。使命深き皆さま方が、大鵬のごとく、智慧と慈悲の翼を広げ、「平和と生命の尊厳の二十一世紀」へ飛翔されゆくことを、私は念願し、また確信する次第であります。結びに、皆さま方のこれからの人生が、「希望」と「健康」と「幸福」に包まれゆくことを心から祈りつつ、私の大好きな貴国の詩人ミギレの雄渾なる「青年よ」の一節を申し上げ、私の祝福のスピーチを終わらせていただきます。 夜明けの光が 雪の山頂をてらし清新な活力が英雄の腕(かいな)に沸き出ずるおお 青年よその朝日の光の矢を たぐり寄せ君が触れることによって新しい波を起こし給えそして 君の指で世界を覚醒させたまえ新たな躍動の世界へと ご清聴、ありがとうございました。ダンニャバード(ありがとうごいざいます)。 【創造する希望 池田先生の大学・学術機関講演に学ぶ】創価新報2021.4.21
May 14, 2022
コメント(0)
-
東西における芸術と精神性
東西における芸術と精神性フランス学士院1989年6月14日本日、三百数十年の輝かしい伝統と格式をもつフランス学士院において「東西における芸術と精神性」と題し、公園の機会をいただきましたことは、私の最大の栄誉とするところであります。芸術アカデミーのアンドレ・ジャックマン会長に深い敬意を表するとともに、マルセル・ランドフスキー事務総長をはじめ、関係者の方々に心よりお礼を申し上げます。また、ご多忙のところ、ご出席くださった諸先生方に熱く感謝申し上げるものであります。さて、この由緒ある演壇に身を置いて、私の胸に一辺の思想がこみあげてまいります。 幽遠なる海底には 深く 深く吹き上ぐる大いなる泉あり それは湖よりもなお広く青く清冽なる水脈滾々と溢れ 溢れそこには妙なる琴の音が 静かに また静かに 漂い響く この太鼓よの初めより 尽きせぬ真清水に人もし触るれば永遠なる生命の力は洗われ出で人もし汲めば自在無礙なる創造の力を養う内なる宇宙をひたしゆくこの泉は大いなる生命の海へと流れゆくおお 根源なる大宇宙の神秘のこの泉よその底知れぬ深淵より生命の大海はうねり歴史は迸る ほとりなる琴の音が奏でる聖なるその荘厳なる調べは人間の内なる律動にして人類の普遍の言語なるかひとは聴かずや波間にたゆとう玲瓏たるこの聖なる交響をひとは見ずやこの魂の奥深く湧き出づる音律を大いなる深淵なる 不可思議な創造の泉を—— 古来、芸術とは、人間の精神性のやむにやまれぬ発露であり、様々な具体的な〝かたち〟として結晶しつつ、そこに巧まずして、一個の「全一なるもの」を表象するものでありました。確かに、個々の芸術活動は、限られた空間内での営みであります。しかし、芸術に参画する人々の魂には、自らの活動という回路を通じて、宇宙的生命ともいうべき、一体化せんとする希求が脈打っておりました。つまり、自分と宇井ミクロの世界が、宇宙というマクロな世界と融合しつつつくり出すダイナミックな一つのいのち——。そこに生きた芸術がある。人間には、肉体的に〝パン〟を欲するように、精神面においては、そうした「全一なるもの」にひたり、それを呼吸し、そこから蘇生の活力を引き出すことを、生き方の基軸としてまいりました。〝パン〟が肉体の新陳代謝に不可欠であるのと同様、芸術もまた、その効用は、「心の新陳代謝」になくてはならぬものであったわけで張ります。アリストテレスがいみじくもカタルシス(浄化)と詠んだのも、芸術のこの働きであったと思われます。では、なぜ、芸術が、人間とってかくも本然的な営みであり続けたのか。私は、その最大の要因を、芸術のもつ「結合の力」に求めることができると思うのであります。ゲーテの『ファウスト』の独白には、「あらゆるものが一個の全体を織りなしている。/一つ一つがたがいに生きてはたらいている」(大山定一訳、『世界古典文学全集』50所収、筑摩書房)とあります。これが生きとし生けるものの実相であるならば、人間と人間、人間と自然、人間と宇宙をも結び合わせ、「全一なるもの」を志向しゆくところに、芸術の優れて芸術たるゆえんがあるといえましょう。詩歌であれ、絵画であれ、音楽であれ、われわれが珠玉の芸術作品に触れたときの、あの感動を一言にしていえば、あたかもわが胸中の泉に共感の波動が幾重にも広がり、精妙なリズムの促すまま、はるか天空へ飛翔しゆくがごとき生命の充足感であり、これこそ自己拡大の確かなる実感であります。有限なるものは無限なるものへと、また体験の個別性は、「意味論的宇宙」ともいうべき普遍性の世界へと開示されていく、そこに芸術特有の「結合の力」の生き生きとした発動があると私は見たいのであります。ところで、その普遍性の世界は、往古の演劇が宗教的祭儀とは不可分の関係にあったことに象徴されるように、常に宗教の世界と相即不離の関係にありました。J・E・ハリソン女史も言うように「その初めにおいては同じ一つの衝動が人を教会に向かわせ劇場に向かわせる」(『古代美術と祭式』佐々木理訳、筑摩書房)ものであったわけであります。こんなエピソードがあります。かなり以前のことですが、日本の有名な歌舞伎俳優がヨーロッパに遊び、ルーブル美術館で西洋美術の名品の数々を鑑賞した。そのあと語った感想が「みんな耶蘇(キリスト)ではないのか」のひと言であったというのであります。やや率直すぎる評言ではありますが、西洋美術が、いかにキリスト教の伝統から生命の水を得てきたかという表現を、素朴に示しております。東洋からの旅人が、西洋美術の中に身をもって感じ取った「全一なるもの」とは、とは、「耶蘇」の一言に凝縮されているとでもいえましょうか。確かに、貴国のノートルダムやシャルトルのカテドラルは、まさに西欧中世のゴシック建築の精華であるとともに、中世キリスト教の世界観を具現した〝芸術的統合〟であったということは、いうまでもありません。つまり芸術は宗教であり、宗教は芸術であり、二つながら、よく生きんとする人間の情熱のおのずから志向するところでありました。それでは東洋にあってはどうか。かつてはポール・クローデルが、また近年には私の知友であり、日本で対談集を出版した故アンドレ・マルロー氏が、並々ならぬ関心を示した日本人の美意識も、色濃く宗教性を帯びたものであります。日本の宗教的伝統は、キリスト教のような厳格な一神教とは異なり、あいまいな部分が多いのですが、それにもかかわらず、マルロー氏が、西洋と異なる日本人の伝統的美意識を「内的実相」と呼ぶとき、そこには、宇宙や自然との声明的な共感ないし一体感に基づく宗教的背景をはっきり感じ取っていたはずであります。かつて、クローデルが、西洋と対比して「自然を服従させるというよりも、自らがその一員となること」(『朝日のなかの黒い鳥』内藤高訳、講談社)と位置づけていた、東洋的もしくは日本的美意識は、数十年の歳月を経て、マルロー氏の網膜に映じたものと深く根を通じております。「全一なるもの」への志向性は、それと意識されないにせよ、日本の文化においても、独自の彩りを添えてきたのであります。そこで問題は、古今東西を問わず、こうして芸術や宗教を通して発現されてきた「結合の力」が、社会の近代化にともない、とみに衰微してきているという現実であります。私は十九世紀末葉以来、鋭敏な精神が予感し警告し続けてきたことを、ここであえて繰り返すつもりはありません。しかし、自然や宇宙から切断されつつある人間は、いまや人間同士の絆さえ立たれがちであり、その結果、孤独はもはや孤独として、すなわち病としてすら意識されなくなっておりました。いうまでもなく、私たちを取り巻く芸術環境も、近代の流れとともに次第に大きく変わってきました。一例を挙げれば、原稿用紙やタプロー(画布)に一人向かう孤独な芸術家と、他方、匿名の読者であり鑑賞者である大衆といった、あまりに近代的な芸術環境にあって、「結合の力」がどこまで十全に発揮されうるのか、そこには大きな困難があります。個々の努力や才能によって、それなりの成果が期待できるにしても、何よりそこには、「結合の力」を発現させるための有機的、共同体的な〝場〟が欠落しております。それは、例えば古代ギリシャにおいて、半円劇場に集い来った観客たちも俳優たちと同様に、ときには俳優以上に演劇に参加することができた芸術環境とは、よほど違うはずであります。失われゆく原始の生命力を求めて、ある人は、はるか古代人の骨太の闊達さに思いをはせ、ある人は、近代的に汚染されぬ天地のたくましいエネルギーに承継の目を向けるなど、様々な格闘がなされてきました。逆説的になりますが、私には、十九世紀末から今世紀にかけて、きら星のごとく輝き現れた巨匠たちの饗宴は、あたかも、こうした時代の不幸の深刻さに濾過されて生まれた結晶とさえ思えてくるのであります。現代においては、自由かつ多様な芸術的試みが可能になった半面、見えるものを超えて、より遠く突き進んでいく力も、故郷を喪失したおのれの魂の分裂の復旧を痛切に願う求心性も、弱まり薄められているように思えてなりません。 さて、ここで私は、東洋の仏教の説く「縁」という概念を用いて「結合の力」を「結縁の力」と置き換えてみたいと思います。そのほうが、本日のテーマに即して、問題の所在を、よりはっきりと浮き彫りにできるからであります。「縁」を「結」ぶということの「縁」とは、仏法の「縁起」説の概念に由っております。ご存じのように「縁起」説は、釈尊以来、仏教の長遠な歴史を貫く骨格ともいうべき歴史を貫く骨格ともいうべき考え方でありました。すなわち、仏教では、社会現象であれ自然現象であれ、何らかの「縁」によって「起」こってくるのであり、それ自体のみで存在するものは何もない、と説いております。これは一言にしていえば、「すべての事実は関係性のなかに生ずる」と言い換えてもよいのでありますが、ただ関係性というと、空間的なイメージが強くなってしまう。それに対し、仏教の「縁起」とは、時間の要素も加わった、多次元的な捉え方となるのであります。クローデルやマルローを魅了した、自然と共感、共生している日本人の美意識の根底には、原始的なアニミズムの要因もありますが、より深く、仏教的伝統に因をもつ「縁起」観も見逃してはならないと私は思っております。ちなみに日本の伝統的芸術である茶や生花、庭、ふすま絵、屏風などは、それ自体として価値や意味をもつというよりも、ふさわしい生活空間の〝場〟の中に位置づけられることによって、初めて、その本来の光を発揮する——すなわち〝場〟に「結縁」することによって価値や意味を生じてきたのであります。連歌や俳諧なども本来、多人数が寄り合う〝場〟なくしては、成り立たない芸術であったことも付言しておき来たいと思います。さて、こうした「結縁」によって生起する一切の事象の実相を、大乗仏教では「空」と説いております。この「空」の概念を「無」と同一視する傾向はいまだ払拭されたことはいえないようであります。この点に関しては、仏教側の責任もあり、特に、世俗的価値や欲望を否定し去ったところに悟りの境位を求めた、いわゆる小乗仏教は、ニヒリズムと著しく近接する要素をもっております。しかし、大乗仏教で説かれる「空」の概念は、ニヒリスティックでスタティック(静的)な小乗的概念とは、百八十度様相を異にし、刻々と変化し生々躍動しゆくダイナミックな生命の動きそのものなのであります。皆さま方に近しい人の言葉を借りるならば、一切の事象を「永遠の相の下」でではなく「持続の相の下」で捉えようとしたベルクソンの生の哲学のほうが、よほど大乗的な「空」の概念に親密であるといってよい。私は、この大乗仏教の「空」が内包しているところの、生々脈動してやまぬダイナミズムを、「創造的生命」と名付けておきたいと思います。その生命は、時間的、空間的な限界を常に乗り越え、乗り越え、小さな自己から大きな自己への超克作業に余念がありません。すなわち、宇宙本源のリズムとの共鳴和音に耳を傾けながら、日々新たな飛躍と自己革新を目指しゆくところに、その面目があるからであります。私が、アカデミー・フランセーズのルネ・ユイグ氏と対談集『闇は暁を求めて』(講談社。『池田大作全集』第5巻収録)を上梓したのは、十年ほど前になります。その中でユイグ氏は、この大乗仏教の核心部分を、適切にも「精神的生命」と位置づけ「宇宙が目標として向かって歩んでいる未来の創造的行動に私たちを結びつけます」と、深い理解と共感を示してくださいました。このことについて、日本の高名な仏教学者は感嘆の思いで評価しておりました。この創造的生命のダイナミズムについて、大乗仏教の精髄である法華経では、多角的にして総合的な解明がなされておりますが、本論に即し、その点を少々考えてみたいと思います。まず法華経では、時間的にも空間的にも、無限、無辺の生命の広がりが開示されるとともに、しかもその広がりは、一個の生命の「いま」の一瞬に包摂されゆくという生命の自在性を説き明かしております。法華経の前半では、神羅万象(諸法)は、根源の一法(実相)に帰一し、その法との合一を果たすことにより神羅万象が自己の一念に収まり、また自己の一念は全宇宙に遍満しゆくことを明かしております。さらに後半では、無始無終の久遠の仏を説くことによって、生命の永遠性を示すのであります。なおかつ過去も未来も、現在の一瞬に凝縮されてくる。全体を通して、法華経では空間的な「合一」と、時間的な「凝縮」とが、〝無障礙〟という創造的生命のダイナミズムを形成しているとするのであります。また創造的生命を、私どもの〝生き方〟からいえば、自己完成への限りなき能動的実践として現れるともいえましょう。すなわち法華経の諸経中でも際立った特徴は、その「菩薩道」の実践の場を、荒れ狂う厳しき人間社会の中に会えて求め、そこでこそ自信の生命が磨かれ、「小我」を超えた「大我」の確立へといたることを説いている点に見いだせるのであります。更に私は、法華経の描写にまことに劇的、文学的、絵画的、彫刻的イメージが横溢していることにも触れておきたいと思います。法華経の説法の中心部分は「虚空会」と呼ばれる空中での儀式でありますが、そこでは、金、銀、瑠璃、真珠など七つの財で飾られた巨大な宝塔が大空に浮かび上がります。その大宇宙にそびえ立つ「宝塔」とは、実は生命の壮大、荘厳さを象徴しているのであります。寿量品という経文が描く安穏なる世界の姿——天人が満ち、庭園の林も堂閣も宝も飾られ、花咲き果実たわわに、人皆遊び楽しみ、空には天鼓鳴り、美しい花が雨のごとく降り注ぐ——と。これはおとぎの世界をほうふつさせるような、生命の詩と音楽と絵画の競演といってよい。宗教史にあっては、宗教と芸術が対立・相克するケースもしばしばみられますが、法華経における創造力の縦横なる駆使は、両者の相補い、融和しゆく環境を、よく示しております。以上、こうした点からも明らかなように、法華経における創造的生命のダイナミックな展開には、人間の営みのさまざまな次元が、すべて包摂されているのであります。それらが混然一体となって宇宙的流動ともいうべきダイナミズムを形成し、淘汰作用と昇華作用を重ねていったはてに、どのようなイメージが浮き彫りにされるのでありましょうか。あたかも多くの色彩をほどこされたコマが、回転の速度を速めるにつれ、限りなく美しい一色に近づいていくように——。私はここで、法華経の精髄をまことに簡明にした言葉を思い起こすのであります。それは「迦葉尊者にあらずとも・まいをも・まいぬべし、舎利弗にあらねども・立っておどりぬべし、上行菩薩の大地よりいで給いしには・をどりてこそいで給いしか」(御書1300㌻)と。迦葉や舎利弗とは、釈尊の高弟であり、いわば知性の代表の存在であります。彼らが「舞」や「踊り」になぞらえられているのは、法華経の説法を聞いたときの、彼らの歓喜の高揚を意味しております。つまり、宇宙の深奥の真理と人生の最高の価値とを知り得た生命の喜びを描写したものといってよいでしょう。上行菩薩とは、法華経の説法の座で、釈尊が滅後の弘法を託すために、大地の底より呼びだしたとされる無数の菩薩の代表であります。その仏法上の意義はさておき、それらの菩薩が大地より涌出する態様が「舞を舞う」「踊りてこそ出づ」と、力強く、生気に満ちた芸術的イメージで表象されていることに、私は深い感動をおぼえるのであります。そこには、生々脈動しゆく創造的生命のダイナミズムが、見事に表象されているといってよい。私は「表象」という言葉を使いながら、貴国の輝かしい文学的伝統である〝象徴主義〟を思い浮かべております。確かに、法華経自体が、一個の生命の回転のドラマとして説かれているのでありますから、「踊りてこそ出づ」等の表現も、事実の客観描写というよりも、創造的生命の優れて象徴的な描出と捉えることもできます。菩薩の躍動しつつ出現する態様は、一言でいえば歓喜を象徴しております。それは単なる歓喜ではなく、宇宙の本源の法則にのっとった人生の深い探求と、社会への限りなき貢献を通しての「歓喜の中の大歓喜」であります。 その象徴性の純度というものを考えるとき、私は、ポール・ヴァレリーの薫り高い対話篇『魂と舞踊』の中で、ソクラテスが踊る女人の姿を凝結して語る美しい一節を、想起するのであります。——「生命のあの高揚と振動、あの緊張の支配、得られるかぎり敏捷な自分自身のなかで、あの恍惚状態は炎の功徳と力を持ち、恥や患い愚かさなど、生活の単調な糧はそのなかに酔焼き尽くされて、女人のなかにある神のように尊いものを、われわれの目にかがやかせてくれるではないか」(伊吹武彦訳、『ヴァレリー全集』3所収、菊間書房)と。もとより、両者を同次元で論ずることはできないかもしれないと思います。しかし、動くものの究極に、言語というかたちを与えようと象徴性の純度を高めていくとき、期せずして創造力が〝踊り〟のイメージを象る連想作用に誘われるということは、大変興味深いことであるとはいえないでしょうか。 ともあれ現代は、人類史上、空前とも言うべき試練と変動の時代を迎えております。そうしたなかにあって、多くの人々の目が、内面へと向けられていることも明らかであります。晩年のヴァレリーは、不気味な軍靴の音を聞きながら「精神連盟」のために奔走しました。マルロー氏も、私との対話で、未来世紀の「精神革命」の予兆に耳をそばだてていられました。本日のテーマに即して言えば、創造的生命の開花、発言の運動は、人間の内面的変革を通し、必ずやそうした「精神連盟」「精神革命」に、大きく道を開いていくではありましょう。それはまた、芸術をはじめ、人間の全ての営みを活性化させゆく源泉たりうるであろうことを、私は信じております。おわりに、私の拙い〝芸術頌〟を詠み上げさせていただきたい。 おお 芸術!おお 芸術よ!汝は永遠の光彩文明と文明の消えざる碑銘 おお 芸術!おお 芸術よ!汝は生命の凱歌「自由」と「創造」と「歓喜」との おお 芸術!おお 芸術よ!汝は深き祈り根源なるものへの聖なる合体 おお 芸術!おお 芸術よ!汝は友愛の広場万人が相集い 握手し笑みを交わす かつて 西の文人は謳った「東は東、西は西——だが両巨人の相見えん時東西も、国境、出自もありえぬ」と時を同じくして 東の詩人も 謳った「東洋も西洋も人類の祭壇の前に婚せよ」と 今 芸術はその手もて 魂を誘う心なごむ 癒しの森へ天かける 想像力の花園へいと高き 英知の台(うてな)へそして地球文明の はるかなる地平へ—— と謡い上げ、また祈りつつ、本日の記念のスピーチを終わります。 【創造する希望[池田先生の大学・学術機関講演に学ぶ]】創価新報2021.3.17
April 14, 2022
コメント(0)
-
牧口常三郎——人道と正義の生涯㊦
牧口常三郎——人道と正義の生涯㊦アメリカ サイモン・ウィーゼンセンター1996年6月4日 一九三九年、牧口は、創価教育学会の第一回総会を開催いたしました。この年、第二次世界大戦が勃発。ドイツはポーランドへ侵攻し、日本の軍隊も暴走を増し、中国や韓・朝鮮半島で蛮行を重ねていきます。このような時流を危惧し、牧口は軍部ファシズムと全面的に対決の姿勢を示します。日本の宗教界の多くが、戦争遂行の精神的支柱たる国家神道に翼賛していくなか、示相・信教の自由の縦覧に憤然と反対し、平和実現への宗教的信念を断固として曲げなかったのであります。また日本がアジア諸国に神道の信仰を強制した非道に対し、牧口は「日本民族の思い上がりも甚だしい」と烈火のごとく怒り、憤慨してやみませんでした。牧口の峻厳さは、他の民族の文化や宗教に対する寛容と、深く通底していたのであります。一九四一年の十二月、日本は、ハワイの真珠湾を奇襲し、太平洋戦争に突入します。その五か月後には、創価教育学会の機関誌「価値創造」が、治安当局の指示で廃刊とさせられました。「言論の自由」を奪うことなど、「信教の自由」「良心の自由」を踏みにじる軍部にとって、いともたやすいことでありました。権力は、これらの「基本的な人権」を封じ込めることによって、国民に沈黙の〝羊〟の体場に甘んじさせておこうとした。牧口は、これに対して、「羊千匹よりも、獅子一匹たれ! 臆病の仙人よりも、勇気ある一人がいなければ、大事を成就することができる」と訴えております。不正や悪に、真っ向から立ち向かう牧口の言説は、権力の側にとっては、危険思想以外の何物でもありませんでした。†善いことをしないのは悪いことをするのと同じ牧口は、思想犯として、徹底した特高(特別高等警察)刑事の監視にさらされるのであります。しかし、牧口は、民衆の中に常に飛び込んで、間断なく対話を続けております。後の起訴状には、牧口は、戦時下の二年間に二百四十余回の「座談会」を開催したと記されております。舌鋒鋭く軍部への批判に及んで、「発言そこまで!」と刑事に制止されることも、一度や二度ではありませんでした。軍部権力による神札の礼拝の厳命には、同信であったはずの僧侶までも、ことごとく屈従しましたが。牧口は、最後まで、きっぱりと拒絶しております。一九四三年七月、遂に、牧口は、戸田とともに、官憲に捕らえられ、投獄されました。容疑は、稀代の悪法である「治安維持法」の違反と「不敬罪」であります。牧口は、一歩も退くことがなかった。独房の中でも、牧口は大きな声を出して、他房の囚人たちに語りかけたといいます。創価学会第二代会長の戸田は小説『人間革命』で綴っています。「皆さん、こう黙っていては退屈するから、一つ問題を出しましょう。善いことをしないのと、悪いことをするのとは、同じでしょうか。違うでしょうか」(『戸田城聖全集』8)どこまでも、また誰とでも、牧口は心を開き、平等な立場で対話をしていく、闊達な人間教育者でありました。取り調べの堅持や看守にさえも、諄々と仏法の法理などを説き聞かせております。「世間的な毀誉褒貶等に気兼ねして悪くはないが、善もない」という生き方は、結局仏法に反する——現存する尋問調書には、こうした牧口の見解も明確に記されております。(『牧口常三郎全集』10、第三文明社)仏典には「人のために火を灯せば、自分の前も明るくなる」(御書一五九八㌻、趣意)という譬喩があります。まさに、牧口は、自他ともに希望を輝かせゆく、積極的な「貢献の人生」を最後まで垂範してやまなかったのであります。また尋問調書から分かるように、牧口は、中国への侵略や土井東亜戦争などは、根本的に、日本国家による誤った精神的指導に起因する「国難」であると、断言しておりました。日本の侵略戦争が「聖戦」と美化され、言論界も、競って賛美する時代において、こうした牧口の発言は、稀有の勇気と覚悟を表したものであります。家族に送った獄中の書簡も残されております。「老人は当分ここで修養します」「本が読めるから、楽であり、何の不足はない。心配しないで、留守を守って下さい」「独房で思索も出来て、却ってよい」等々、思いやりに満ち、しかも一種の楽観主義さえ感じさせる、悠然たる筆致であります。「心一つで地獄にも楽しみがあります」——これは、検閲で削られた書簡の一節であります。(前掲『牧口常三郎全集』10)地獄——狭い独房の四璧の中では、息がつまり、暑さや寒さは、容赦なく老齢の身を痛めつけていったに違いありません。しかし、わびしさはなく、彼の胸中には、常に赫々たる信念の太陽が昇っていました。牧口は、人権を無視した国家権力とは、「正義の怒り」をもって戦いましたが、その「怒り」を「憎悪」へと変質させることはなかったのであります。やがて、老衰と栄養失調で重体になり、ついに病監へ移ることに同意いたします。衣服を改め、羽織を嫡子、頭髪を調え、看守の手を借りず、衰弱した足で、病監へ歩いていきました。そして、その翌日、一九四四年の十一月一八日、奇しくも「創価学会の創立の日」に、眠るがごとく逝去したのであります。死の恐怖さえも、牧口をとらえ、屈服させることはできませんでした。一般に、人間は死を恐れ、忌み嫌う存在といえましょう。死への恐怖こそが、人間に内在する、他者への攻撃本能の基底をなしている、という見方さえあります。しかしながら、仏法では、「生死」は「不二」であるとし、「生」と「死」の永遠なる連続性を説いております。正義の信念を貫き、生死の本質を通観していく者にとっては、生も歓喜であり、死もまた歓喜となる、と教えております。大いなる人道の理想に生き抜く時、恐怖も、後悔も、そして憎しみさえもなく、死を迎えることができるという確かな証を、牧口は冷たい牢獄の中で、厳然と残したのであります。†牧口は、誰にも看取られず、心によって偉大であった、また行動によって偉大であった生涯を終えました。その静かな逝去は、新生の旅立ちとなりました。すなわち、直弟子の戸田が、同じく獄中にあったのであります。二カ月後に、「牧口は死んだよ」と、判事から聞いた悲嘆、憤怒……。戸田は涙も涸れ、獄中で一人懊悩したといいます。しかし、実は、その「絶望」の果てから「希望」の回転が始まったのです。「死して獄門」を出た牧口の代わり、戸田は「生きて獄門」を出ました。師匠の命を奪った権力の魔性への怒りを、新たな平和運動の創出への決然たる誓いとしたのであります。かつて牧口は、『創価教育学体系』において、「悪人は自己防衛の本能から忽ち他と協同する」「(=結託し)強くなって益々善良を迫害する悪人に対し、善人はいつまでも孤立して弱くなって居る」(同全集6)と慨嘆しておりました。「さしあたり、善良者それ自体が結束していく以上に方法はない」(同前、参照)——これが、牧口の痛切な、そして痛恨の心情だったのであります。ゆえに、その不二の弟子として、戸田は、草の根の対話の広場である「座談会」運動を軸に、「善なる民衆の連帯」を、戦後の荒野に築き始めました。それは、仏法の「生命尊厳の哲理」を基調として、民衆の一人一人が賢くなり、強くなって、「人道」と「正義」が尊重される政界を創りゆく運動であります。また、牧口は、『価値論』において、「人を救う」という「善の価値」にこそ、「宗教の社会的存立の意義」があるとしておりました。(同全集5、参照)。すなわち、「宗教」のために「人間」があるのではない。「人間」のために「宗教」があるという人間主義であります。牧口の精神を創立の魂とする「創価大学」のキャンパスに、この四月、一本の桜の木が植樹されました。それは、中東和平に命を捧げられた、故ラビン首相の記念の桜であります。記念の植樹は、創価大学と学術・教育交流を結んだ、ヘブライ大学のアラド副学長御一行をお迎えして、盛大に行われました。かつて、ラビン首相は、叫ばれました。「平和の勝利に優る勝利はないからです。戦争には商社と被征服者がありますが、平和においては皆が勝者になるのです」(早良哲夫監修『ラビン回想録』竹田純子訳、ミルトス)と。春がめぐり来るごとに「ラビン桜」が、美しい万朶の花を大空に向かって大きく咲かせていくことでありましょう。また、その志を継承する青年が、陸続と育ちゆくことを、私は信じてやみません。「教育」は、「新たな生」への希望の光であります。牧口は、権力と真正面から戦い、微動だにしませんでした。その勇気と英知の提唱は、時代を超えて、人々の良心を揺さぶり、覚醒していくことでありましょう。牧口は、いかに高邁な理想であっても、そこに民衆に根ざした連帯の行動がなければ、実現できないことを見抜いておりました。私どもが、SGI(創価学会インタナショナル)憲章に制定したように、他の宗教とも、「人類の基本的問題」について対話し、その解決に協力していくのも、この精神からであります。牧口の魂は、創価学会、そしてSGIの運動に脈打っております。私どもは、いかなる権力にも断じて屈しません。永遠に牧口の信念を受け継いでまいります。始祖日蓮が予見したごとく、はるか「万年」の先を目指して、民衆の「平和」と「文化」と「教育」の連帯を広げていく決意であります。私自身、皆が勝者となりゆく「平和の二十一世紀」へ、尊敬する諸先生方と手を携えて、命の限り、勇気ある行動を貫いていく決心であります。本日の貴センターにおける講演を、私は、牧口常三郎初代会長、ならびに「人道」と「正義」のために殉じた、すべての方々に、そして、深き「決意」をもって未来に生きゆく若き人々に捧げます。 偉大なる思想をもった人間と、そして民族が偉大なる信仰をもった人々がそしてまた嵐の中で壮大なる理想と現実に生き抜いた人間と民族のみが限りなき迫害を受け、耐え抜いた人間と民族のみが永遠にわたる歓喜と栄光と勝利の太陽を浴びゆくことを信じて、私の講演を終わらせていただきます。トダー・ラバー!(ヘブライ語で「どうもありがとうございました」) 【創造する希望「池田先生の大学・学術機関講演に学ぶ】創価新報2021.2.17
March 25, 2022
コメント(0)
-
牧口常三郎——人道と正義の生涯①
牧口常三郎——人道と正義の生涯①アメリカ サイモン・ヴィーゼル・センター1996年6月4日 時代背景と講義の意義1996年6月4日、池田先生はアメリカの著名な人権団体「サイモン・ヴィ―ぜル・センター」で講義を行った。当時は、東西冷戦の終結から6年半。冷戦構造の崩壊により、ルワンダや旧ユーゴースラビアなど各地で、民族紛争や内戦が勃発し、その影響を受けて、世界で大量の難民と避難民が生まれていた。国家や民族、宗教の違いによる差別や憎悪が原因で、生命と人権が脅かされるという深刻な問題が人類を取り巻く中、池田先生は正義の人権闘争を貫いた初代会長・牧口常三郎先生の足跡を紹介。「国権よりも人権を」「国家主義よりも民衆主義を」との信念に言及した。そして、その遺志は「世界の禅の人を結束させる」という創価学会の平和運動に継承され、発展していると述べた。講演会の冒頭、同センターの創立者であるハイヤー会長は語った。「昨年(95年)の冬、日本のある主要な雑誌が、死の収容初・アウシュヴィッツのガス室で大量殺人を否定する記事を掲載し、ユダヤ人社会は衝撃をもって受け止めました。(中略)その意味で、本日、日本にもユダヤ人の大切な友人がいると紹介させていただけることは大きな名誉であります。池田SGI会長と、会長の創立された大楽——創価大学は、寛容の橋を架ける作業を、ただ語るだけでなく、実践してこられました」 国家主義ではなく民衆主義 人間主義をシャローム!(ヘブライ語で「平和を」)尊敬するハイヤー会長ならびに令夫人、尊敬する気センター理事会ならびに来賓の諸先生方、私は、貴センターの「寛容の博物館」を、三年前の一月、オープンの直前に見学させていただきました。ホロコーストの歴史は、人間の人間に対する「非寛容」を示す、究極の惨劇であります。私は、貴博物館を見学し「感動」しました。いな、それ以上に「激怒」しました。否、それ以上に「このような悲劇を、いかなる国、いかなる時代においても、断じて繰り返してはならない」と、未来への深い「決意」をいたしました。そして、「人々が忘れなければ希望は続く」という、ウィーゼンタール博士の言葉を抱きつつ、わが創価大学は、ただ今、会長のお話にありましたように、貴センターの全面的な協力を経て、一九九四年五月から、日本各地で「勇気の証言——アンネ・フランクとホロコースト」展を共催したのであります。東京都庁舎での東京展の開幕式には、クーパー副会長をはじめ、貴センターの御一行が参加してくださり、アメリカのモンデー駐日大使など二十カ国の大使館関係者も出席されております。戦後五十年に当たる昨年(一九九五年)の八月十五日には、ハイヤー会長をはじめ、多くの御来賓をお迎えし、広島での開催となりました。さらに、沖縄など全国十九都市に巡回され、今も継続されております。直接、同展を訪れた人々は、一日平均で約五千の市民、合わせて約百万人に及んでいることを、謹んでご報告いたします。なかでも、けなげな乙女アンネと同じく十代の青少年が数多く訪れ、憤激に紅涙をしぼっております。親子づれでの見学も絶えません。当に、「正義」を教える最高の「教育」の場となり、「啓発」の場となっているのであります。開催にあたって、私は、胸中で、牧口常三郎初代会長の愛弟子であり、私の恩師である戸田城聖第二代会長の遺訓を反芻しておりました。それは、「ユダヤの人々の不屈の精神に学べ!」という言葉であります。幾世紀から幾世期を重ねた迫害の悲劇に、ユダヤの人々は決して屈しなかった。その偉大な強さと勇気から、学ぶべきことは、あまりにも多いと、私は思ってきた一人であります。ユダヤの民は、迫害への挑戦のなかから、不滅の教訓を刻み、そしてそうお英知と精神と強さを、後世の子孫に厳然と残してこられました。「忘れない勇気」とは、同時に「教えていく慈愛」でありましょう。「憎悪」が植えつけられるものであるからこそ、「寛容」を植えつけていかねばなりません。 いかなる困難にも価値を創造する人格を育む仏法では、「怒りは善悪に通ずる」と教えております。いうまでもなく、利己的な感情や欲望にとらわれた怒りは、「悪の怒り」であります。それは、人々の心を憎しみで支配し、社会を不調和へ、対立へと向かわせてしまうものであります。しかし、人間を冒涜し、生命を踏みにじる大悪に対する怒りは、「大善の怒り」であります。それは、社会を変革し、人道と平和を開きゆく力となります。まさに、「勇気の証言」展が触発するものこそ、この「正義の怒り」にほかならないのであります。冷戦後の世界における重大な課題は、異なる「民族」や「文化」や「宗教」の間に横たわる無理解と憎悪を、いかに乗り越えていくかということでありましょう。 ⚔私には、昨年十一月、「国連寛容年」の掉尾を飾る第五十回国連総会でのウィーゼンタール博士の演説が、強く胸に響いて離れません。すなわち、「寛容こそ、この地球上のあらゆる人々が平和に共存するための必要条件であり、人類に対する恐ろしい犯罪に至った憎悪に代わる、唯一の選択肢であります。憎悪こそ、寛容とは対極の悪であります」と。ここで確認したいことは、「怒り」に積極と消極の両面がはらまれるように、「寛容」にも、消極的な寛容と積極的な寛容があるということであります。ともすれば、現在の社会一般の通念となっている、他者への無関心や傍観は、その消極的な寛容の一例といえるかもしれません。日本においては、無原則の妥協を「寛容」とはき違える精神風土が、軍国主義の温床になってしまった痛恨の歴史があります。真の「寛容」は、人間の尊厳を脅かす暴力や不正を断じて許さぬ心と、表裏一体であります。「積極的な寛容」とは、他者の立場に立ち、他者の眼を通じて世界を見つめ、共鳴しゆく生き方にあります。すなわち、貴センターが範を示しておられるように、異なる文化と進んで対話し、学び合い、相互理解を深めていく。そして、人類の共感を結びゆく「行動の勇者」こそ、まことの「寛容の人」なのであります。この崇高なる「人権と平和の城」である貴センターにおきまして、わが先師である牧口常三郎初代会長について講演の機会をいただきましたことは、私にとりまして、無常の光栄であります。本日は、「正義の怒り」、そして「積極的な寛容」という二つの点を踏まえつつ、牧口が生涯、貫いた信念、その思想と行動について、簡潔にご紹介させていただきたいと思うのであります。日本の軍国主義の時代にあって、牧口は、「悪を排斥することと、全を抱擁することは同一の両面である」(『牧口常三郎全集』9、第三文明社、参照)、「悪人の敵になりうる勇者でなければ善人の友とはなりえぬ」(同全集6)、「消極的な善良に甘んぜず、進んで積極的な善行を敢然となし得る気概の勇者でなければならない」(同前、参照)等と強く主張しております。そして、「戦争」に反対し、「信教の自由」を奪った軍国主義に敢然と抵抗して、投獄されました。過酷な弾圧を受け、七十三歳で獄死したのであります。牧口常三郎は、一八七一年、日本海の一寒村であった新潟県の荒浜に生まれました。この六月六日で、生誕満百二十五年を迎えます。牧口は、自身のことを「貧しい寒村出身の一庶民」であると、誇りをもって言い続けておりました。小学校を卒業後、苦しい家計を助けるために進学を断念。やがて単身、北海道にわたり、働きながら、時間を見つけては、本を読み、学び続けております。その才能を惜しんだ上司の援助もあり、独学で師範学校に入学し、二十二歳の春、卒業しました。牧口は、若き情熱を教育に燃やし、恵まれぬ子らのために、教育の機会を大きく広げていくのであります。教え子たちからの感謝を込めた追想は、枚挙にいとまがありません。⚔時代は、国を挙げて「富国強兵」を推し進め、軍国主義の道を歩み始めた時であり、教育においても、盲目的な愛国心が鼓舞されていきました。しかし、牧口は「そもそも、国民教育の目的とは何か。面倒な解釈をするよりも、汝の膝元に預かる、その可憐な児童を『どうすれば、将来、最も幸福な生涯を送らせることができるか』という問題から出発すべきである」(同全集4、参照)と論じたのであります。牧口の焦点は、「国家」ではなく、どこまでも、「民衆」であり、そして一人の「人間」であったのであります。それは「国権の優位」がことさらに強調されるなかで、「個人の権利と自由は、神聖侵すべからざるものである」(同全集2、参照)と言い切って憚らなかった。彼の人権意識は、あまりにも深く、強かったのであります。一九〇三年、一千ページに及ぶ大著『人生地理学』を、三十二歳で出版しました。発刊は、日露戦争の前夜であり、東京帝国大学の教授ら、高名な七人の博士が、そろって、「対ロシアの強硬策」を建議したことも、開戦論を高めました。そうした時勢にあって、無名の学究者牧口は、足元の「郷土」に根ざして、しかも「狭隘な国家主義」に偏らず、「世界市民」の意識を育むことを提唱したのであります。その後、四十二歳で、東京の小学校の校長となり、以後二十年にわたり各校を歴任し、東京屈指の名門校も育て上げております。牧口は、アメリカの哲学者であるデューイ博士らの教育理念に学びながら、日本の教育改革を進めました。しかし、権力の露骨な介入である「視学制度」の廃止などを直言する牧口には、常に圧迫が加えられたのであります。地元の有力者の子弟を特別扱いせよという指図を拒否したために、政治家の策謀によって、追放されたこともあります。この折、生徒も、教師も、父母も、皆、こぞって牧口校長を慕い、留任を求めて同盟休校までしました、後に、転任校でも、同様の干渉を受けましたが、牧口は、自分の辞任と引き換えに、子どもたちが伸び伸びと遊べるように、運動場の整備を実現させ、他校へ移っていったというのであります。こうした歩みは、ほぼ同時代のホロコーストのなかで、命をかけて、子どもを守る奮闘を続けた、ポーランドの偉大なユダヤ人教育者コルチャック先生の人間愛とも相通ずるのではないかと思う一人であります。一九二八年、牧口は、仏法に巡りあいます。すべての人間生命に内在する、尊極の智慧を開発しようとする仏法は、それ自体が、社会に開かれた民衆教育の哲理であると信ずるのであります。教育を通しての社会の変革を強く志向してきた牧口は、この仏法との出会いによって、理想の実現への確かな手応えを実感していったようであります。時に五十七歳。人生の総仕上げの刮目すべき展開が始まります。二年後、弟子の戸田とともに、『創価教育学体系』第一巻を出版。この発刊の日、一九三〇年十一月十八日を、私ども創価学会の創立の日としております。「創価」とは、「価値の創造」の意義であります。その「価値」の中心は、何か。牧口の思想は明快でありました。それは「生命」であります。デューイらの実用主義の検地を踏まえつつ、牧口は、「価値と呼ぶことのできる唯一の価値とは、生命である。その他の価値は、何らかの生命と交渉する限りにおいてのみ成立する」(同全集5、参照)と洞察しました。人間の生命、また生存にとって、プラスになるか、そうか。この一点を根本の基準としたのであります。「生命」の尊厳を守る「平和」という「大善」に向かって、挑戦を続け、いかなる困難にあっても、価値の創造をやめない——そうした「人格」の育成にこそ、「創価教育」の眼目があります。 掲載範囲のポイント大悪に対する怒りは「大善の怒り」「行動の勇者」こそ、まことの「寛容の人」軍国主義に対峙し世界市民の育成を提唱 【創造する希望[池田先生の大学・学術機関講演に学ぶ]】創価新報2021.1.20
February 15, 2022
コメント(0)
-
平和への王道—私の一考察
平和への王道—私の一考察中国・北京大学1984年6月5日中国に脈打つ〝尚文〟の気風私はこの北京大学に、今日で六度目の訪問となりました。本日は四年前に続き、再び講演をさせていただく機会を与えてくださった尊敬しる丁石孫学長先生、尊敬する諸先生方、親愛なる学生の皆さま、およびご列席の皆さまに敬意を表するとともに、深く感謝申し上げるものであります。今日という日は「新たな民衆像を求めて」と題して、中国民衆の現像を、私なりに考えてみましたが、今回は「平和柄の王道—私の一考察」ということをテーマに、日頃から私が信じ実行している恒久平和建設への展望を、一民間人の立場から、少々述べさせていただきます。本日の私のつたない話が、日中両国の平和友好への一席にもなれば、と念願しております。さて、個人同士の些細なケンカにおいても、国家間の戦争の場合でも、争いというものは自己抑制の力が働かなくなった時に生ずるといえましょう。とりわけ国家の次元においては、一度戦争という方向に走り始めると、有名なプラトンやイギリスの哲学者ホップスが、国家を人間離れした「怪獣」に例えているように、この自己抑制力を働かせることは、至難の業のようであります。「強大な軍費をもち、完全な守備体制をととのえ、しかも最後まで守備体制だけを堅持した国家は、遺憾ながら、まだ見たためしがない」(『ゲーテ格言集』大山定一訳、『ゲーテ全集』11所収、人文書院)とのゲーテの嘆きは、その困難さを物語って余りあります。軍備をもたなければ一番よいのですが、一挙にそうしようとしても現実的ではない。事実、今日ほど平和が叫ばれている時代はありませんが、軍縮は、一向に進展する兆しが見えないようです。ゆえに、遠い道のりではあっても地道な平和への努力を積み上げていく以外にない。それには、文化や文明の〝文〟の力をもって、軍備つまり〝武〟をコントロールしていくことこそ急務でありましょう。それを私は「国家の自己抑制力」と申し上げたいのであります。こうした観点から見る時、中国三千年の歴史は、極めて示唆するところが多いと思うのであります。なぜなら、中国史を巨視的に俯瞰してみると、〝尚武〟というより〝尚文〟の国であるという印象を強くするからであります。もとよりこれは比較相対のことであって、純然たる〝尚武〟の国がないのと同様、純然たる〝尚文〟の国もありません。要は、どちらが主流をなしているかであって、中国においては、ごく例外的な時期を除いて〝尚文〟の気風が、歴史を動かす大きな力になってきたように私は思えてなりません。 武力侵略を抑制する文を尊ぶ伝統の精神たしかに中国も、漢帝国の成立時や蒙古族の支配する元の時代は、武力を表に立てた膨張主義であったし、万里の長城に象徴されるように、辺境では絶えず攻防戦の歴史でありました。また国内では治乱攻防の歴史を繰り返し、戦火の規模も、日本のような島国から見れば文字通りのケタ違いというほかありません。また、文字を尊ぶ精神が〝尚武〟ならぬ〝文弱〟に堕し、時代精神の敗退を招き、各王朝末期の騒乱状態へと推移していった事実も私はよく知っているつもりであります。その上で申し上げたいのですが、文明史に栄枯盛衰の姿を減じてきた数々の強大な帝国に比べ、中国史においては、武力のみに頼ったあからさまな武断主義というものは、どちらかといえば影が薄いように思われます。一時的に武断主義がまかり通ったとしても、やがて文化や文明の大海のような力の中に吸収されて行ってしまう。中国には「世界一の歴史の国」と言われていますが、そのおびただしい史書のいくつかをひもといてみても、そこには、常に強烈な倫理性、倫理感覚が満ちております。そこが〝尚文〟の国たるゆえんであり、力に任せた武力侵略を抑制する力も、そこから生まれてくるものと思われます。外征が道に反し、特にも採るという考えが中国に芽生えたのは、隋・唐のころだと言われております。世界に冠たる大文明が絢爛と花咲いた時代に、こうした考え方が生まれたということは、文化や文明の力をはかるうえでこれは大変に示唆的であります。確かに、隋の煬帝の高句麗遠征が、民衆に過酷な犠牲をしいていたころには「—遼東に向いて浪に死ぬなかれ」という反戦歌が大流行しております。また玄宗晩年の無益な国境経営に、莫大な国費を人命が費やされているころの、杜甫の有名な詩「兵車行」などからは、単なる沿線というよりも、外征そのものを不徳とする響きさえ聞こえてきます。 衣を牽(ひ)き足を頓(とん)し道を攔(さえぎ)りて哭(こく)し哭声は直ぐに上りて雲霄を干す道旁に過ぐる者の行人に問えば行人は但だ云う「点行頻りなり」と或は十五より北のかた河に防ぎ便(すなわ)ち四十に至るも西のかた田を営む去(ゆ)きし時には里正の与(ため)に頭を裹(つつ)みくれしに帰り来たりて頭白き還(な)お辺を戍(まも)る辺庭の流血は海水を成せど武皇 辺を開く 意は未だ巳(や)まず君聞かずや 漢家山東の二百州千村万落 荊杞を生ずるを (『杜甫』黒川洋一注、『新修 中国詩人選集』3、岩波書店) 出征兵士に代わって、無益な侵略戦争を告発した名詩であります。こうした機運の中から、外征を非道、不徳とする考え方、時代精神が培われていったに違いありません。ちなみに、遣隋使、遣唐使など、日本と中国との直接的な外交関係が開始されたのも、この時期であります。こうした考え方は中国の外交姿勢にも表れており、とりわけ朝貢外交、朝貢貿易に端的に示されていると思われます。言うまでもなく中国は、一部を除いて、従属国の宗主権を求めるだけで、あえて征服しようとはしませんでした。朝貢とは、中国を宗主国と認める国が、臣下の礼をとる証しとして、貢物を携えて来朝する。それに対し、中国皇帝は、返礼として中国の文化的な工芸品等を下賜するという外交、交易のあり方であります。この朝貢貿易の前提となったものは、文明、文化によって周辺国を心服せしめゆくという考え方ととらえられる。すなわち〝尚文〟の思想と誇りが根底にあったといえましょう。注目すべきは、この朝貢外交が、必ずしも宗主国である中国の利益にならなかったということであります。使者や随行員の滞在費などの費用は、宗主国側の負担であった。しかも、皇帝からの下賜品は、常に貢物の額を上回っており、一度入貢すると、臣下の礼をとることを代償に、従属国は五倍から六倍の利益をあげていたそうであります。明の太祖・洪武帝の海禁政策の背景には、中国側がこうした負担に耐え切れなくなった、という事情も挙げられております。大帝国の余裕といえばそれまでですが、誠におおらかな秩序感覚であります。ここ数年、私は東欧諸国を何回か旅して、そこに残されたオスマン帝国残忍なまでの搾取の爪痕に、旋律を禁じ得ませんでした。それだけに、朝貢貿易に見られるような中国の対外姿勢のおおらかさと、〝尚文〟の姿が、際立って強く印象に残るのであります。のみならず、こうした秩序感覚は、近代ヨーロッパのナショナリズムと、それが生み出した支配、被支配の意識構造とも、著しく様相を異にしていたと思うのであります。 果敢な行動と勇気の対話が時代を動かす 常に「人間」を座標軸に据える中国の思想かの〝五・四運動〟の沸騰するような雰囲気の中、北京大学を訪れたバートランド・ラッセルは、中国の印象を「『誇りを抱くから戦う気ならない』国があるとすれば、その国はまさに中国である。ごく自然な中国人の態度は、寛容と友好の態度であった、相手に礼節を示し相手からも礼節をもって遇せられたい、と願う態度である」(『中国の問題』牧野力訳、理想社)と述べております。ご存じのように、このラッセルの中国評価は、封建遺制のマイナス面に目を向けていないとして、魯迅などの厳しい反発を招きましたが、異なる文明の美質が描き出されていることも事実であります。そこに私は、人間あるいは国家の、むき出しの本能や獣性をコントロールしゆく文明の〝力〟—すなわち自制力、抑制力を見いだすのであります。こうした力を豊かに蓄えていく以外に、軍備をコントロールし、やがて廃絶へと導きゆく平和の道は、考えられないと申し上げたいのであります。今から十六年前、まだまだ我が国で中国の脅威が盛んに言われていたころ、私が、日中国交正常化の提言を行い、その中で、中国が「直接に武力をもって侵略戦争を始めることはとうてい考えられない」と訴えたのも、一に、こうした歴史と伝統を踏まえてのことでありました。その後、日中両国の国交は回復され、国連に復帰した貴国は、「大国主義にはならない」と、しばしば明言しております。私は、多少なりとも貴国の歴史を知るがゆえに、その主張が、戦略的な駆け引きなどとは無縁の発言であることを信じてやみません。さて、中国においてそうした自制力や抑制力が生み出される背景を、もう少し掘り下げてみると、物の見方、考え方の原点に、常に「人間」が据えられていることに私は気づくのであります。中国思想に詳しい、わが国の気鋭の学者は述べております。「中国の哲学はひたすら人生の目的を追求してきた。哲学者たちの思索は、ついに人間という関心領域をはずれることがなかった。自然にかんする思索といえども、人間にかんする思索の自然主義的立場からの基礎づけとして展開された。いいかえれば、哲学はなによりもまず人間だったのである」(山田慶児『混沌の海の中へ 中国的思考の構造』朝日新聞社)と。「人間という関心領域をはずれることがなかった」ということは、人間が原点であったということであります。哲学に限らず、私は、宗教、科学、政治等、人間的営為のあらゆる面で、基調として言えるのではないかと思っております。人間のための哲学、人間のための宗教、人間のための科学、そして人間のための政治ということであります。禍福の織りなす大河のごとき中国の歴史において、人間という座標軸はついに揺らいだことはなかったのではないでしょうか。当たり前のようですが、このことは、口で言うほど簡単ではありません。キリスト教やイスラム教のような一神教の世界、特にヨーロッパの中世社会などにあっては、座標軸は常に「神」によって占められて入りました。人間は神の僕であり、哲学は神学の婢でしかありませんでした。人間的営為のように見えても、その実、神のための哲学であり、神のための宗教、科学、政治であったわけであります。こうした思考の在り方は、神の憑きが落ちた近代以降においても、たやすく改めるものではありません。神に代わって座標軸の中心となったのは〝進歩〟の観念であり、科学技術への信仰であります。この点については、すでに多くのことが言われていますが、近代科学の在り方一つ取り上げてみても、それが「人間という関心領域」を逸脱したがゆえに、知性の自己運動、自己完結の所産となる傾向は否めないのであります。もとより私は、科学技術文明の成果、恩恵を毛頭、否定するつもりはありません。しかし「人間」という基軸が欠落した科学の行き先には、大きな落とし穴が待ち構えていることを、決して忘れてはならないと思います。とりわけ、平和という観点から留意すべきは、近代の国家間の戦争の主たる元凶ともいうべき植民地主義の背景にも、「人間」という基軸を欠落させた思考形態があったという事実であります。すなわち、西欧近代を唯一の基準にして、人間社会を「文明」と「未開」に二分していく思い上がった思考形態こそ、誤った選民意識を生み、植民地主義を陰で支えていたものなのであります。その意味では、ヨーロッパ近代文明は、多くの物質的、精神的所産を残しながらも、全体の傾向性から見れば、人間の野蛮な情熱に対する自生作用、抑制作用というより、その野蛮な情熱をカムフラージュする働きをしてきたともいえるのではないでしょうか。 〝水滴は石をも穿つ〟一人一人の努力が要さて、キリスト教における「神」に当たるものを、強いて中国文明に探すと、「天」がそれといえましょう。この言葉は、宗教や哲学、道徳、科学などの面で、実にしばしば出てまいります。しかし、ごく初期を除いて、キリスト教の神のような超越的な実在ととらえられたことは、絶えてありませんでした。「天」は、ア・プリオリ(先験的)な実在として人間に望み、語りかけてくるのではなく、ア・ポステリオリ(経験的)に人間に即して、人間の側から問われていったのであります。現代の中国で、この「天」という言葉が、どのような語感を持つのか、私はつまびらかではありません。おそらく、さまざまな害毒をもたらした封建道徳の遺物として受け止められている面もあるからでありましょう。しかし、私が注目するのは「天」そのものよりも、その問われ方であります。「天」が常に、人間に即して内在的に、内発的に問われていったということであります。これは、前回の講演でも申しました「個別を通して普遍の見る」行き方ではないかと思うのであります。そこにおいては、人間の側から現実を通して「天」を問いかけ、そして現実を再構成しようとする不断の努力と実践に重きを置かれます。いわば〝静〟よりも〝動〟のイメージが、クローズアップされてくるのであります。それとは逆に、ある一定の固定的観念を基準にして価値判断していく在り方は、それに固執するあまり、観念といえども生々流転してやまぬ人間の営みが生み出したものにすぎないという視点が欠落しがちであります。その結果、「理論信仰」「制度信仰」「効率信仰」をもたらし、生きた人間は、その呪縛のもとに置かれてしまいます。例えば「核抑止力信仰」などは、人間の側からの問いかけが欠落している点で、近代の誤った信仰の最たるものと信じております。なぜなら、その信仰が人間同士の不信と憎悪と恐怖の上に成り立つものであり、それらを除去することなくして、核の廃絶などありえないからであります。この〝動〟のイメージに関して、魯迅の作品『非攻』に言及させていただきます。ご存知のようにこの作品は、戦国時代の行動する平和主義者として有名な墨子を扱ったもので、日本のある訳者は「戦争をやめさせる話」と翻訳しております。(竹内好訳、『故事新編』所収、岩波文庫。以下、同書を参照)魯の人・墨子は、ある時、大国である楚の国が小国である宋の国を攻め滅ぼそうとしているのを耳にする。しかも、そのきっかけは墨子の同郷人である公輪般という人が、雲梯という城攻めの武器を作って楚王に献じたため、王がその気になったのだという。そこで墨子は、戦争をやめさせるために、とるものもとりあえず急ぎ楚の国へ向かった。道々、眺めてみると、宋の国はあまりにも貧しく、楚の国は豊かだ。何のために攻めるのか……。まず墨子は公輪般に会って戦争の愚を説く。だが、もう既に楚王に説いてしまったあとだからだめだ、と。そこで墨子は、公輪般をとおして楚王に面会する。墨子のノベル道理に楚王も納得するが、それでもなお、公輪般が自分のために雲梯を作ってくれた、攻めんわけにはいかん、と楚王は言う。そこで墨子は、楚王の前で、公輪般と図上戦術を行い、ことごとく打ち破った。ついに公輪般は墨子の殺害をほのめかすが、墨子は更に知恵をめぐらし、楚王に言う。〝自分の助言で宋城は鉄壁の守りを固めている〟—と。ついに楚王は、攻撃を思いとどまった、という。要約して言えば、このような筋です。魯迅は、数ある諸子百家の中で墨子を最も尊敬していたと言われますが、確かに、ほのぼのとしたなかにも風刺のきいた、印象深い作品があります。特に楚王が、〝自分のために雲梯を作ってくれた、攻めんわけにはいかん〟というくだりは現代の軍拡論者のひな型を見るようであります。私が、なぜ『非攻』に言及したかといえば、墨子のこの平和行動主義こそ、今もなお、平和への突破口を切り開くカギであると思うからであります。ともかく平和のために働き、語る—そうした〝動〟の触発作業は、たとえ遠回りのように見えたとしても、不信と憎悪と恐怖を、信頼と愛と友情に変えゆく「平和への王道」であり、ここから必ずや心と心を開きゆく回路を見いだしていけることを、私は信じてやまないからであります。先月、東京で開かれた国際ペン大会に、中国ペンセンター会長の巴金氏が参加され、私も、それに先立ってお会いしました。巴金氏はそのあいさつを「文を以って友に会す」という、誠に〝尚文〟の国の人らしい言葉をもって始められ、次のように訴えられました。「水滴は石をも穿つと申しますが、文学作品も長い歳月にわたる伝播によって、人々の心に根を下ろすことができます。ペンを武器にして、真理を顕示し、邪悪を糾弾し、暗黒勢力に打撃を与え、正義の力を結集することができるのです。平和を愛し、正義を主張する世界諸国の人たちが、しっかりと手を取り、自分の運命をその手に握っていきさえすれば、世界大戦も核戦争も、必ず避けることができるでしょう」と。私もそう思います。一人一人の努力が、たとえ水滴のように微力に思えても、やがて石をも穿つ、否、岩をも押し流す大河となっていくでありましょう。それには、果敢なる行動と勇気ある対話を積み重ねていく以外にありません。微力ながら私もそうしていくつもりでありますし、中国の未来を双肩に担っておられる皆さま方もともどもに、その平和への大道を歩みゆかれんことを念願し、私の話とさせていただきます。 【創造する希望「池田先生の大学・学術講演に学ぶ】創価新報2020.12.16
December 23, 2021
コメント(0)
全21件 (21件中 1-21件目)
1