2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2006年05月の記事
全41件 (41件中 1-41件目)
1
-
凶悪犯罪者に対する偏見
今週配信されているマル激には安田好弘弁護士がゲストで出ている。タイトルは「私が重大犯罪の被告を弁護しなければならない理由」となっている。これを聞いて思うことは、我々が凶悪犯罪の報道から、いかにしてその犯罪を犯した人間に対して極悪人という偏見を抱くかということだ。もう少し正確に言うと、犯人であるかどうかがまだ決定していない被疑者に対してでさえ、マスコミの報道から大きな憎しみを抱いてしまうという偏見が育っていく過程というものがもっとも心に残ったものだった。安田弁護士は、山口県光市の事件の弁護を引き受けた際、上告審弁論に欠席したことが、裁判を遅らせる意図だったのではないかということでバッシングを浴びていた。ほとんどのマスコミのニュースがそうだったし、個人のブログでも非難する論調の文章が目立っていた。しかし、冷静になってこの事件を見れば、このような感情的な反応は偏見から生まれるものではないかと考えてみなければならないのではないだろうか。安田弁護士によれば、この事件の鑑定書を詳しく見てみると、検察側が事件の描写をする際に意図的に凶悪性を増すような表現をしているところが見られるという。明らかに鑑定書が語る事実に反するような描写が見られるというのだ。それを具体的に書くのはためらいがあるが、例えば子どもを床にたたきつけたという描写が被告人の残虐性を示すものとして語られている。しかし、そのような行為をしたのなら、鑑定書にはその時の傷がはっきりと書かれていなければならないのに、そのようなことが書かれていないという。もしたたきつけたということが間違いであるのなら、気が動転しておろおろしているうちに落としてしまったということも可能性として考えられる。これは被疑者に対してひいき目に見過ぎているかも知れないが、真理を確定するには、あらゆる可能性を検討しなければならないとしたら、可能性のあることは、もしかしたら無かったかも知れないが、あえて想定してみるという思考法が必要ではないかと思う。安田弁護士の話に説得力を感じるからといって、それだけの理由で安田弁護士が正しいと主張するつもりはないが、検察の言い分や、それを代表するマスコミの報道の方を無批判に信じるのも間違いではないかと思う。どちらも可能性があるものとして、それが確信出来るまでは仮定の話として深い吟味が必要だという意識を持たなければならないのではないかと思う。それを凶悪性を肥大させて、被疑者があたかも凶悪な人間であるかのように思い込み、凶悪な人間が凶悪な犯罪を犯したのだと短絡的に理解するなら、これは一つの偏見になるのではないだろうか。安田弁護士は、鑑定書と検察側の主張の食い違いを精査するには2週間では足りないと判断して、上告審弁論の延期を申し出たということだ。そして、それは普通によくあることで、今までは認められなかったということはなかったそうだ。それが認められなかったので、欠席せざるを得なかったというのが安田さんの説明だった。これは極めて説得力があるものだと僕は思った。光市の事件は、その内容があまりにも衝撃的で、しかも被害者遺族がマスコミの前面に出てその憎しみを率直に語っていた。これに感情的に同化して、被害者遺族の憎しみにまったく同化して被疑者を見てしまうということが起こったように感じる。この事件を冷静に眺めることが出来る人が極めて少ないように思う。これは社会が一つの偏見にとらわれている状況だと思うのだが、このような偏見は判断の間違いをもたらす恐れがあるのではないかと思う。しかし、この事件の場合は、被疑者が被害者を殺してしまったのは確かなことのようなので、その殺したという事実を客観的に受け止めるのはかなり難しいだろうということは感じることが出来る。安田さんが言っていたが、意図的に殺してやろうと思って殺す「殺人」と、殺すつもりはなかったのだが、間違いが積み重なって死に至らしめてしまった「傷害致死」のようなものとは、結果として被害者が亡くなったと言うことでも、その事実の解釈はまったく違ってくると言う。だが、このことを論理的に正しく受け止めるのは、法律の素人にはなかなか難しいだろうと思った。結果的に死んでしまったのだから同じように責任を取れ、というのは暴論だと宮台氏は語っていたが、冷静さを欠いた人間にはそれがなかなか分からないだろう。偏見は冷静さを失わせる。暴論に陥らないためにも、偏見から逃れることが必要だ。そのメカニズムを正しく理解して、偏見から逃れる方法を確立することが誤謬論にとって重要になるだろう。安田さんが語ったことでもう一つ印象的だったのは、俗に和歌山毒カレー事件と呼ばれている事件だ。この事件に関しては、確たる物証が無く、状況証拠だけから犯人らしいとされている林被告が死刑の判決を受けたことに僕も不当性を感じていた。しかしそれは、あくまでも確証がないのに、もっとも重い刑罰である死刑を宣告したことの不当性を感じていただけだった。林被告その人については、真犯人であるかどうかということは分からないという見方だった。もしかしたら犯人であるかも知れないという思いもあった。しかし、安田さんの話を聞いていると、林被告が犯人だとした考えそのものが実は間違っているのではないかという気がしてきた。それこそ偏見によって作られた冤罪ではないかという気がしてきたのだ。もしこれが冤罪だとしたら、偏見は取り返しのつかない恐ろしい結果と結びついてしまうことになる。林被告が、カレーの中にヒ素という毒を混ぜたと言うことが裁判では問われているのだが、なぜそのようなことをしたのかという動機は最後まで解明出来なかったらしい。動機は解明出来ないが、それは、林被告の激高しやすい性格から、感情的な行動としてこの事件が行われたのだと解釈されているらしい。しかし、激高しやすい性格というのは、マスコミが作り上げた偏見に過ぎないのではないかというのを安田弁護士の話からは感じる。何もしていないのに、連日極悪人のようにマスコミには報道され、外にも出られないような監視の下に置かれたら、イライラが募って爆発しそうになるのはある意味では当然だ。これは激高しやすい性格ではなく、理由のある激高として理解出来る。マスコミが林被告を怒らせて、激高させておもしろおかしく報道しようとしただけではないかと僕は感じる。安田さんによれば、林被告というのは、「漁師の娘さんで、肝っ玉母さんのような人」と言うことらしい。凶暴な性格を持った極悪人というイメージは、マスコミが煽ったものなのではないか。そのマスコミが煽ったイメージによって裁判が左右されるとしたら、これは極めて重大な間違いではないかと思う。林被告とその夫とは、保険金詐欺の罪でも裁かれていた。マスコミの報道では、夫を殺して保険金をだまし取ろうとしたと言うことで、さらに林被告が極悪人であるというイメージを増大させることになったものだ。「毒婦」という偏見をあからさまに表現する言葉まで使われた。しかし、これはまったく真相と違うと言うことだ。真相は次のようなことらしい。林被告がかなり多額の遺産相続をしたとき、その財産を夫が使い込んでしまったらしい。それを返すことが出来なかった夫は、それじゃ、保険金で何とか金を作ろうと考えて、自ら毒を飲んで保険金をだまし取ろうとしたらしい。だから、保険金詐欺については夫婦の共犯と言うことで夫も裁かれていた。もし、夫を殺して保険金をだまし取ろうとしていたのなら、夫は被害者であり共犯者にはならないはずだ。この保険金詐欺については、夫も服役しているので、大筋では認めていたのだろうと思う。しかし、この犯罪については「毒婦」と呼ばれるような凶悪なものではないと思う。これはマスコミがあおり立てた偏見以外の何ものでもない。真相というのは、それが本当にあったことであれば、たとえ表面的には不思議に思えても、よくよく考えてみれば納得出来るという解釈に落ち着くことが多い。林被告夫婦が保険金詐欺をしたということも、その背景をよくよく考えてみれば、それは失敗ではあるけれどもその失敗を犯した事情というものを理解出来る。しかし、真相かどうか分からない、ある意味では頭の中で空想的にでっち上げたものは、よくよく考えてみればどうも理屈に合わないということが出てくる。林被告がカレーの中に毒を入れたという想像も、よくよく考えてみればどうも理屈に合わないことがたくさんあるように感じる。神保哲生氏が指摘していたことだが、保険金詐欺の時に保持していたヒ素を持っていた人間が、それを保持していることがすぐに分かってしまうはずなのに、なぜあえてヒ素を使って殺人を犯すことを考えたか、ということに対するつじつまの合わなさだ。どうしても殺人を犯す動機があったのなら、それが露見することを恐れるよりも、殺人の動機の方が高くてその行為に踏み切る恐れはある。しかし、動機がほとんど無いのに、なぜ疑われるかも知れない行為に踏み切るのか、その行動の整合性が理屈に合わないと言うのだ。僕もそう思う。林被告が、近所の人に恨みを抱いていたというような事実があればまだ違うかも知れないが、安田さんによれば、林家の人々というのは、周りの人間たちとあまり関わりなく生きてきたのだそうだ。親身になってつきあうこともない代わりに、さしたるトラブルもなく、ましてや恨みを抱くことなど無かったようだ。またヒ素を混入したと言われるカレーは、自分の子どもたちも口にする可能性のあったもので、子どもたちを巻き込んでまで殺人をするだけの動機がどこにも見あたらない。すべては、林被告が「毒婦」とまで呼ばれる極悪人であるというイメージから導かれたものであるように見える。凶悪犯罪者と呼ばれる人たちのイメージは、いったん確定してしまうと、それ以外の見方は難しくなってしまう。しかしそれは偏見であり、そこから間違った判断が生まれるという意識は、誤謬論にとって欠いてはならないものだと思う。安田さんの話は、このほか耐震構造偽装問題で有名になった小島社長の弁護のことに及んでいた。小島社長に対しても、マスコミの報道によって偏見が増幅されていることを指摘していた。それもなるほどと思った。偏見を偏見として意識することは、より真理に近づくことになるのだなと思った。
2006.05.30
コメント(2)
-
天皇個人に対する偏見
先週のマル激では天皇制について論じていた。ここで僕の関心を引いたのは、議論されていたのが、天皇制という抽象的な制度という対象ではなく、具体的な天皇個人の問題として語られていたことだった。それは現在の明仁天皇を巡る問題だったり、昭和天皇である裕仁天皇を語るものだったりしていた。天皇制という制度を巡っては、理論的には、それがすべての差別の根源であるという主張があったり、戦争における失敗が天皇制軍国主義というものに帰して考えられているところがある。僕もかつては、これらの主張を素朴に信じていた。しかし、マル激の議論を聞いていると、問題はそれほど単純ではないのではないかと感じるところがある。天皇という存在は、無条件の絶対的な聖性を持っていると考えられている。聖なる存在として、無条件の頂点に位置するというその属性から、反対の極にある、もっとも穢れた存在というものを必然的に生み出すという考え方が、理論として差別の根源であるという考え方だろうか。僕も素朴にそう信じていたところがあった。しかし、世の中には聖なる存在だと思えるものが確かに存在するし、低俗だとして批判されるのが当然だというものも存在する。そのいずれもが、なぜ聖なるものなのか、なぜ低俗なのかという理由が見つかる。自分を犠牲にしても他人のために尽くそうとする姿には聖なるものを感じる。映画のヒーローにはそのような属性を持ったものが多い。また私利私欲に走り、公共の利益よりも自らの利益を優先させるような行為に対しては、低俗なものとしての批判が起こっても当然だと思う。その理由や条件が具体的に明確なら、聖なるものとして尊敬するのも、低俗なものとして軽蔑するのも、ともに論理的にはもっともだと思える。この理由や根拠が存在せず、抽象的に、証明抜きで聖なるものとして前提することが論理的な誤りだと指摘出来るものだと僕は考えていた。だが宗教などでは、信仰の対象となるものは証明抜きで聖なるものと前提している。それが論理的な間違いだとしたら、すべての宗教は間違いだということになってしまうのだろうか。これも極論の間違いのような気がする。宗教は暴走すると社会に害悪を与えるが、それが穏健に人々の間の共通感覚として浸透していれば、逆に社会の安定に貢献する。人々が、受け入れがたい不幸に見舞われたときに、それを受け入れ、新たな再生の力を与えてくれるものが社会にとって穏健で有用な宗教ということになるだろう。天皇制も、一つの宗教として、日本社会の安定化に役立つのなら、聖なる存在としての天皇に大きな意義のあるものと捉えられるかも知れない。小室直樹氏の天皇制主義は、そのような方向からの考察なのかも知れない。僕はそれに大きな違和感を感じながら見ていたが、天皇制が日本社会の安定に貢献するという判断をすれば、天皇制主義になったとしても不思議はないかも知れない。僕はまだそのような認識になれないので、依然として天皇制主義にはなれそうにもないが。天皇制を一つの宗教として、その信仰を強制しようとしたのが、天皇制軍国主義の失敗だったのではないかと感じる。信仰は強制して注入することで穏健に育つものにはならなかったのだと思う。戦争をやりたかった人間にとっては、穏健ではなく攻撃的な面が育った天皇制軍国主義は、もしかしたら成功だったのかも知れないが、多くの庶民にとってはその結果を見れば、注入された宗教がいかに社会を破壊するかを経験したのではないだろうか。戦後の日本に象徴天皇制という形で天皇制が残ったのは、これを穏健な宗教として存在させることで、日本社会の安定化に役立たせようとする考えをした者がいたのではないだろうか。戦後の天皇の存在は、聖なる存在という前提があるものの、それが聖なる存在、天皇個人が平和主義者であり・民主主義者であり・誰よりも日本の国と人民のことを思っている、という姿を見せることに努力していたのではないだろうか。この姿に対して、理論的には天皇制は差別の根源であり、かつての戦争の間違いの象徴でもあったということから、その存在は今の天皇にも具体的に現れているはずだと考えて、天皇個人にも差別の属性を無批判に押しつけているとすれば、それは一つの偏った見方「偏見」になるのではないかと今は感じる。抽象的な理論としては、その存在がそのように結論づけられるような感じがするが、その抽象論が現実にも適用出来るには、様々な条件を具体的に吟味しなければならないのではないかと思う。現実の天皇の存在は、象徴天皇制という規定から、象徴としてふさわしい存在になるような努力をしている姿がうかがえるのかもしれないと思った。それは、マル激で指摘していたような、現天皇の明仁天皇の様々な行為の中に、実に尊敬すべき姿勢がうかがえるからだ。一つは、正月の出来事だったが、東京都教育委員の棋士の米長氏が、「日本中の学校で国旗を掲げ、国歌を斉唱させることが私の仕事です」というようなことを語ったとき、明仁天皇は即座に「強制でないことが望ましい」という答をしていたことだ。国旗・国歌に対しての批判は直接にはないが、それを強制するということをすれば、正しい志も間違った結果になるという、正当な指摘がここにうかがえる。いかに正しいことであっても、それを強制してやらせようとすることは間違いだ、ということを即座に言えるのは、民主主義やリベラリズムというものが、本当に自分の中に根付いているから言えるのだろうと思う。また、米国領サイパン島にある太平洋戦争韓国人犠牲者追悼平和塔への訪問についても、明仁天皇の歴史認識の正当さを示すものとして記憶しているものだ。民主主義やリベラリズムに対しての意識の素晴らしさを持ち、さらに歴史認識という科学性においても優れている明仁天皇については、この具体的な姿から尊敬の念がわいてくるのを感じる。天皇だから聖なる存在だということを信仰するのではなく、具体的な姿を見て、それが非常に素晴らしいものだと感じて尊敬の念がわいて来るという感じだ。僕は天皇制主義者ではないが、この明仁天皇の姿には尊敬を感じる。教条主義の間違いは、理論的には正しい帰結が、現実の条件を無視してそのままベタに適用されるところから生じる。現実の具体的存在は、その具体性を十分吟味して判断しなければならないのだが、理論の正しさが疑い得ないとなったら、そのような教条主義に陥る危険が出てくる。真理として充分確からしいからこそ教条主義に陥りやすくなるというのは皮肉なことだが、そのアイロニーを十分理解しなければならない。天皇制というものの考えを、それを天皇個人にそのまま押しつけるのは一つの偏見からくる間違いを生む。これには充分気をつけなければならない。しかしまた、この偏見に気をつけて、明仁天皇という具体的な存在に尊敬感を抱いたからといって、その尊敬感を天皇制という抽象的な対象に無批判に広げてしまい、天皇制そのものも尊敬すべき制度だと考えてしまうのは、もう一つ別の偏見に陥ったことになるだろう。具体性と抽象性は、認識の運動として昇ったり下りたりする過程とともに理解しなければならない。そのどちらにも偏見に陥る可能性があると考えて注意しなければならないだろう。それが誤謬論として大事なことだと思う。天皇制の問題として抽象的に昇ったときの大事な問題としては、マル激を聞いていて次のようなものが浮かんできた。天皇制が穏健な宗教として日本社会の安定に役立ち利益として働いたとしても、その中に安住することは果たして正しいことなのかという問題意識だ。穏健な宗教として存在するということは、様々な判断において、自分で判断するのではなくその宗教に従った判断に従うということを意味する。それは、宗教が穏健なものであればそれほど大きな失敗をすることはない。だから、自分で判断して失敗するよりは、宗教に従って失敗をしない方を選んだ方が安全だ。だが、現在の日本のように複雑化した社会で、果たしてそのような単純な対応でいつも穏健な結果が出るというふうに期待出来るだろうか。象徴天皇制という宗教は、穏健な宗教として存在することが難しくなっていくのではないか。それはある政治勢力から利用され、天皇制軍国主義の失敗を繰り返す可能性がないだろうか。今の明仁天皇の時代においてはそのようなことはないだろうと思える。明仁天皇の具体的な姿は、天皇制軍国主義の中心に座るようなことはほぼ絶対的にないと感じられる。しかし、天皇の世が変われば、どのような資質を持った人間が天皇になるかは分からない。そのようなときのリスクを避けるために、日本国民は、象徴天皇制という宗教を必要としない、自らの判断で民主的でリベラルな道を選択出来るように努力すべきではないかと思う。明仁天皇個人には尊敬感を抱くが、天皇制そのものは、日本国民の成長を妨げるものとして穏健な形として廃止出来る方向が望ましいのではないかというのが今の僕の考えだ。宮台真司氏は、天皇について語るとき「陛下」という敬称を使う。僕は、明仁天皇に対する尊敬感を抱いていても、この言葉を使うことには何か違和感を感じてしまって使えない。このあたりのメンタリティの違いを考えるのも面白いかも知れない。
2006.05.29
コメント(2)
-
もう一つの偏見について
偏見というものが不当性を持つのは、それが社会的弱者に対してであることが多い。偏見とは文字通り「偏った見方」であり、ある一面を捉えて、そこから得た解釈が、対象の全面であるかのごとくに扱って考えることを言う。以前に本多勝一さんが、アメリカの黒人を取材したときに、その差別された現状に同情して善意から黒人へ近づいた人々が、現実の黒人たちに嘘つきや泥棒が多いことに大きなショックを受けるだろうと書いていたことを思い出す。嘘つきや泥棒が黒人に多いことは事実だったから、それと黒人であるという属性とを結びつけて、例えば黒人は道徳的・倫理的に劣っているという見方をすれば、それは偏見というものになる。実際には、黒人だからという理由で嘘つきや泥棒を説明出来るのではなく、その社会的状況などを、一面的にではなく多面的にその影響を考慮に入れて考えなければならない。それが出来ないと偏見という間違ったメガネで対象を眺めてしまうことになるだろう。単なる善意だけで黒人に近づいた人間は、このような現実に接して、かえって激烈な差別主義者となることもあると本多さんは指摘していたように記憶している。僕は差別糾弾運動の不当性を現実に見てきたので、その意味では差別反対運動に対する偏見を持つ可能性はあった。しかし、差別糾弾運動の間違いは現実的な間違いであり、差別反対運動の基礎は抽象的な論理であるから、それを混同してはならないという意識があったので、差別そのものに反対することに偏見を持つことは免れた。しかし、フェミニズムに対しては、現実的な経験がなかったこともあり、これの論理的側面と現実的な批判とを直結してしまって偏見を持ったような感じがする。はてなダイアリーの方にトラックバックをもらった「あえて、反フェミニズムを擁護する」を読んでみると、次の指摘にはなるほどと思えるものもある。「この場合、秀さんが捉えそこなったのか、つい口が滑って違う論点に話がいってしまったのか、定かではないが、「内田センセイ」によるフェミニズム批判は実は結構、簡単なものだ。わりとベタに上野千鶴子が嫌いなだけみたいな感じは否めないのだけれども、それを抜きにして、単純に言うと要するに、「フェミニズムというのは「女として」語るというが、じゃあその「女」って何かね?「女」そのものなんてわしゃ見たことも触ったこともないし、今話してるのは「女」なんてもんじゃなく「あんた」じゃないか。「私たち、女たちは」なんて言い出したところで、「女」なんてそんなに単純にくくれるものではないだろ。」と、いうことであるのだと思う。」これは、具体的なある言説に対する批判なら正しいと僕も感じる。だから、内田さんの正しさは、常に具体的に誰が何を言ったかと言うことに対する批判になっていることにあるのではないかと思う。だが、これをフェミニズム一般に広げてしまえば、論理としては逸脱してしまうのではないかと思う。僕はそのような逸脱をしたというのが自分の判断で、その逸脱の原因は、どうやら「フェミニズム」という言葉への偏見からのものだろうというのが自己分析だった。ただ、これは僕が持っていた偏見に対する批判であって、僕が「フェミニズム」に対して偏見を持っていたからといって、「フェミニズム」が批判を許さない真理だと言ったら、これはもう一つの偏見になってしまうだろう。僕の間違いとフェミニズムの正当性とは一応切り離さなければならないと思う。だから、「どっちかって言ったら、内田樹は嫌いなんだけれど、まあ失礼を承知で言ってしまえば、この「論争」でフェミニズムはが「勝って」、「敗北した」秀さん=「内田センセイ」ということになり、フェミニズムは「内田センセイ」に「勝ち」、その正当性は認められた、というようなことになると拙いなあと思って。それに関してそんな意図はしていない、というような言い方は無しだ。意図していなくても、そういうふうな図式になるのがネットの「論争」というもののであるし、そんなことは分かりきっている筈だから。」と、このトラックバックで語っている心配は、もう一つの偏見として意識しておかなければならないのではないかと感じた。論理的には、僕の論理展開に正当性がなかったということであって、それによって、批判の対象になっていた「フェミニズム」全体の正当性が証明されたということではない。全体性の中には、まだ確実になっていない部分もあるだろうから、その確実性を高めるためにも批判は必要なのではないかと思う。しかし、それは正当な批判によって確実性が高まるのであって、的はずれな批判によっては正当性も高まらないと受け取らなければならないのではないだろうか。しかし、「そういうふうな図式になるのがネットの「論争」というもののである」というのは、なかなか困ったものだと思う。ネットで「論争」と呼ばれているものは、その結果としての勝敗にしか関心がないのだろうか。これでは「悪貨は良貨を駆逐する」という社会法則の正しさを確認するような出来事を経験するだけではないかと思う。自分のことを褒めているようで気が引けるのだが、自ら間違いを認めるというのは、ある程度の誠実さがなければ出来ないことだろうと思う。そうすると、誠実な人間ほど完全な敗北の形を見せると言うことがあるかも知れない。あくまで詭弁を強弁して、間違いを認めなければ、形の上では負けたようには見えないかも知れない。真理を悟ることよりも、気分的な勝利感の方が大事だと言うことがネットの常識であれば、ネットでのまともな議論というのはやはり期待出来ない。ネットで行われるのは、誹謗中傷と詭弁・強弁だけになってしまうのではないかと思う。「そういうふうな図式になるのがネットの「論争」というもののである」ということが、果たして偏見なのか、それとも事実を語ったものなのか、なかなか判断は難しいものだろうと思う。これが事実であると思えるような例はあちこちに見受けることが出来る。しかし、だから論争では負けちゃいけないんだというふうに考えたら、この自縄自縛から逃れることが出来なくなるのではないだろうか。一般論として語れば、三浦つとむさんがその認識論で語ったように、現実の対象は無限(可能無限)に多様で複雑であるにもかかわらず、人間の認識はその一部を制限された形でしか捉えられないと言うことから、認識は誤謬を本質的に伴うと考えなければならない。その一面を全面と勘違いすれば、偏見から逃れることも出来ないと考えなければならない。一般論としてこのように考えれば、論争のどの論点で間違えて、どの論点で正しかったかと言うことを判定することは極めて難しいと言わなければならない。僕が、ディベートというものに対して、その論理の訓練としての効用を疑うのは、正しさの判定が難しい論理というものをあまりにも単純に判定しすぎていると感じてしまうからだ。論争においては、そこに合意点が見つかれば、そこに正しさの可能性を見ることが出来るのではないか。しかし、合意しただけではまだ正しさは確実ではない。さらに確実性を高めるように努力しなければならないだろう。だから、一方がその間違いを認めた論争においては、その間違いという点で、誤謬を正しく捉えた可能性があるというふうにその論争を受け止めた方がいいだろうと思う。双方が自分の間違いを認めず、相手の批判で終わってしまった論争においては、正しさは何も証明されなかったと受け止めなければならないのではないだろうか。論争の当事者は、自分の主張の正しさを疑わないだろうが、それは立場から来る正しさの主張であって客観的なものではないと思った方がいいのではないかと思う。立場から来る正しさは、もう一つの偏見である可能性が高いという自覚を持った方がいいのではないかと思う。立場を越えた、ニュートラルな客観性というものが、果たしてありうるものかは難しいと思う。しかし、それが難しいものであっても僕はそれを求めたいと思う。それを求めることによって、自らの間違いも正しく間違いと受け止められる、本当の誤謬論に到達出来るのではないかと思うからだ。
2006.05.28
コメント(0)
-
方法論としてのフィクショナルな前提
大きな失敗をしたにもかかわらず、出直しの姿勢に暖かい言葉をかけてもらえて感謝の気持ちで一杯だが、その一つ一つの言葉に返事を返す余裕がまだ無いので、折に触れてそれらのコメントに触れることで返事にさせてもらうことをお許しいただきたい。さてそのコメントの中でも非常に心にとまったのが、mojimojiさんの次の記述だ。「「一方的な反批判停止」の中で、「つまり、行動面においては、僕は決してフェミニズム的な批判は受けないと思っている男だ。少しでも、抑圧的・封建的なところがあると指摘されて、その指摘が正しいものであればそれを改めるという柔軟性も持っていると僕は思っている」という部分、お気持ちはよく分かるのですが、これは僕自身の自戒もこめた仲間へのアドヴァイスとして申し上げるのですが、そのように言いたくなる心情こそが、私たちが警戒すべきものです。自分の中の気づかないところに抑圧的なプロトコルが仕組まれているだろう、ということを、方法論的前提として常に忘れないようにするのがよりよい対処法かなと思います。実際、自分の行動の中に抑圧的なものの欠片を発見し、肝を冷やすことは今でもしばしばあります。」(「偏見が生まれてくる前段階について」のコメント…はてなダイアリー)このような記述に関して、以前の僕ならある種の反発を感じて読んでいたかも知れない。しかし、一つの失敗を経た今は、この言葉を冷静に受け止めて、その正しさを理解することが出来る。以前の僕が反発を感じただろう解釈は、mojimojiさんが正しく表現している「方法論的前提」と言うことを読み落として、それをベタに前提として語っていると受け取るというものだ。「自分の中の気づかないところに抑圧的なプロトコルが仕組まれているだろう」という指摘を、「存在が意識を決定する」という言い方を教条主義的に考えるのと同じように、差別する側にいる男は、前提として必ずフェミニズム的な差別意識を持っているのだという指摘としてそれを受け取っただろうと思う。このような前提を正しい出発点として設定し疑わないのは、事実として証明されてもいないことを事実であるかのように設定して進める論理になるのではないかという反発を僕は感じたことだろう。しかしこの言葉を正しく理解するなら、それは男の差別意識をベタに設定して前提とするのではなく、それを見過ごしていないかどうか、方法論として意識せよという主張だと言うことが今なら分かる。方法論をベタに受け取れば誤謬に陥るというのは、あちこちで例として僕も見てきたことだった。方法論というのは、フィクショナルな前提を設定する仮言命題的思考だ。それへの注意を強調してきた僕が、フェミニズムに関してはそれを方法論としては理解出来ていなかったというのは、やはり「構造的無知」に属するものだろう。それは偏見という曇りが晴れなければ理解が難しいことだった。宮台真司氏は、フィージビリティ・スタディという思考の際に、あらゆる実現可能性を考えるという方法論において、日本人はそのような思考を方法論として意識することが困難だという指摘をしていた。旧日本軍の会議などで、日本軍が負けるという可能性を語った時点で、「貴様は神聖なる皇軍を侮辱するのか」と一喝されたという。しかし、負けるかも知れない可能性を語るのは、実は負けないための条件を吟味するという、勝つと言うことの目的のための方法論なのだ。これが出来ないと、負けるかも知れない条件を見落として実際に本当に負けることになる。歴史はそれを証明しているのではないだろうか。負けないという目的を達成するためにこそ、仮定の上では負けると言うことをフィクショナルに設定して考える、という思考法がフィージビリティ・スタディというものになる。方法論というのは、何のために行うかと言うことが意識されて初めて役に立つものになる。mojimojiさんが提出した方法論も、その目的は、気づかないうちに自分が差別と偏見の中に落ち込んでいないかと言うことを避けることだ。この方法論を意識していないと、いつそのような間違いに陥るか分からないから気をつけなくてはいけないという、ある意味では誤謬論につながる方法論にもなっている。「つまり、行動面においては、僕は決してフェミニズム的な批判は受けないと思っている男だ。少しでも、抑圧的・封建的なところがあると指摘されて、その指摘が正しいものであればそれを改めるという柔軟性も持っていると僕は思っている」という意識を、ナイーブにそのまま受け止めるのではなく、たとえ結論としてそうであるということが個々の場合に確認出来たとしても、それが確認出来るまでは、方法論としては、「自分の中の気づかないところに抑圧的なプロトコルが仕組まれているだろう」と言うことをフィクショナルな前提として設定して考えろと言うアドバイスなのだと言うことが今は理解出来る。この方法論をベタに受け取ると、フィクショナルな前提としてではなく、それが事実の指摘のように感じられてしまうのだろう。これは、そう言われる方だけではなく、そのような言い方をする方にも方法論としての自覚が足りなくて失敗をすることが出てくるのではないだろうか。差別意識というものが確かに証明されてもいないのに、方法論的前提が常に事実として正しいものと錯覚すれば、男はみんなフェミニズム的な差別意識の持ち主だという極論が生じてきてしまうのではないかと思う。これをフェミニズムの責任に帰したのは僕の間違いだったが、そのような間違いに陥りそうな人が間違いを避ける方法を誤謬論として考えなければならないのではないかと思う。差別反対の行動の時には、それが不当な糾弾につながるという実際の間違いにつながったと思う。差別意識の問題も、自分への戒めとして、方法論的前提として「存在が意識を決定する」と言うことを仮定として、差別意識を持たないためにこそその前提を設定するという意識が必要だと思う。しかし、その前提を事実として正しいものとしてしまい、そこから差別意識の存在を帰結するようなら論理的な間違いになるのではないかと思う。方法論としてのフィクショナルな前提は、デカルトが提唱した「方法論的懐疑」というものを思い出す。デカルトの懐疑は、真理に到達するために疑うという方法論としての懐疑だった。しかし、それをベタに受け取ると、世の中のすべての現象は疑いうるのだから、何一つ確かなものは無いのだとする「懐疑論」に陥ってしまう。このことからもたらされる間違った結論は、科学といえども完全に確かなことが言えるわけではないので、常に不完全であり、科学も一つの仮説に過ぎないのだという、科学を仮説に解消してしまうような発想だ。このような「懐疑論」は、僕にとっては科学への冒涜のようにも見えたので、怒りすら感じるようなものだった。しかし、デカルトの「方法論的懐疑」はあまりにも有名で、それを「懐疑論」として間違えるのは、間違えた方が悪いということはすぐに分かる。「懐疑論」の間違いは、デカルトが「方法論的懐疑」などということを提唱したからだと、的はずれな考えを持つことはない。実際には、科学というのは、現実への適用の条件さえ正しく捉えていれば100%確実な知識を与えてくれるものになっている。仮説のように、適用して結果を見てみなければそれが正しいかどうか判断出来ないと言うものではないのである。科学が確実な知識でなければロケットをとばすなどという危険は冒すことが出来ないであろう。ロケットを飛ばしてみなければ、どこに行くかは分かりませんという仮説しかなかったら、危なくてロケットなど飛ばすことは出来ない。方法論というのは、現実の物事をベタに受け取るのではなく、一度フィクショナルな前提を通して見てみることになる。このフィクショナルな前提そのものに感情的な反発があるときは、この方法論を自分のものにするのは難しい。旧日本軍が、自らの敗北の可能性を前提として、方法論的に考えることが出来なかったように、自分が信じている事柄と反対の仮定を設定することは難しい。しかしmojimojiさんが正しく指摘するように「そのように言いたくなる心情こそが、私たちが警戒すべきものです」という指摘が正しいのだろうと思う。この心情を乗り越えて、冷静に論理的に、方法論としての前提を設定出来るかどうかも、誤謬論として重要なことではないのかと思った。mojimojiさんの貴重な指摘をありがたいものとして感謝して受け取りたい。
2006.05.26
コメント(0)
-
内田さんのアンチ・フェミニズム言説に対する誤読
僕の偏見にとってもっとも大きな影響は、内田さんのアンチ・フェミニズム言説を誤読したことだろうと今は感じている。誤読のポイントは、内田さんがアイロニーとして語ったことを、アイロニーとして理解せず、ベタにそのまま受け取ったことにある。なぜそのような受け取り方をしたかは、僕の無意識に属することのような気がするので今は分からないが、誤読から偏見への流れを考えてみると、これがもっとも大きなもののように思える。内田さんの真意は、フェミニズムというものが基本的に正しい主張をしているものであるにもかかわらず、現実にフェミニズムという言葉で流通している現象は、その正しさを少しも実現せず、かえって抑圧的な作用をもたらしているという皮肉を指摘したものとして理解しなければならなかった。それはフェミニズムに対する誤読であり間違った判断ではないかということが内田さんの真意ではなかったかと思う。それを、間違ったのはフェミニズムだというふうに、現象を短絡的に理解したことが誤読だったと思う。アイロニーをベタに理解すれば誤読するというのは、僕が他人に対して指摘して回ったことだ。その同じことを自分がしていたというのはまことに恥ずかしい限りだと思う。しかし、それだけにこの誤謬は、注意していなければすぐに落ち込んでしまう誤謬ではないかとも思える。アイロニーというのは非常に難しい。そこに表現されている表面的なこととはまったく正反対の真意をつかまなければならないからだ。内田さんのアンチ・フェミニズム言説に対しても、表面的にはフェミニズムを批判しているように見えながら、その真意は、フェミニズムを誤読している人の滑稽さを指摘しているように読まなければならなかった。アイロニー的表現を使わずに、それがベタに分かるように、形式論理的に表現すれば、少なくとも理屈の間違いはなくなるかも知れない。しかしそうすると表現出来る幅はかなり狭いものになってしまうだろう。現実の複雑な現象というのは、アイロニーでなければその本質が言えないようなものがあるような気がする。アイロニーに対する読解能力というのは、対象の複雑さを本質的に理解するときには絶対に必要なものだろう。それが出来なかったと言うことを告白するのはとてもつらいことだが、そう言わざるを得ないだろう。アイロニー表現というのは、現実の対象がそのような性質を持っているときに、それが的確な表現として成立する。フェミニズムというのは、まさにそのような性質を持っているものだろう。これをアイロニーとして正しく受け取らないと、そこからは偏見が生まれる可能性を感じる。これは、現実の弁証法性が複雑に絡み合っているところで見られるものではないかと思う。フェミニズムというものが、まだ確固たる理論として統一されていないと言うことは、そのアイロニー性が、アイロニーのままで語られていると言うことではないかと思う。同時に背負っている矛盾が、矛盾のままで解消されないところがたくさんあるのではないかと思う。男女の不当な差別を告発することは正しいが、差異に応じて対処することもまた正しい。どこが不当な差別で、どこが正当な差異への対処かは、複雑な現象であり難しい判断だ。この矛盾を背負った弁証法性が、現象としてのアイロニー性をもたらす。正しい判断も、そのバランスを越えて行き過ぎると、直ちに滑稽な逸脱したフェミニズムになってしまう。そのアイロニー性を表現したものとして内田さんのアンチ・フェミニズム言説を受け取らなければならなかったと思う。だから内田さんの言説を誤読をせずに正しく受け取るならば、そのような微妙なバランスをどうやって確保して間違った道にはまりこまないかを考えると言うことにならなければいけないだろう。これを、バランスを崩すのは、そもそもフェミニズムが間違いであり、それが悪いのだと責任をフェミニズムに押しつけたことが偏見だった。難しい現象を正しく理解することは難しいのだと僕は理解していたはずだった。だから、その難しい現象に対して、時に間違った判断をしてもやむを得ないと思っていた。問題は、その誤謬を正しく理解して、誤謬から学ぶことによって正しい道を探すことだという認識を持っていた。フェミニズムが直面している問題は、まさに複雑で難しい問題であるのに、同じように考えられなかったのは「構造的無知」であり、それは偏見から生まれたものだ。内田さんに到達することによって、とりあえず僕の偏見の自己批判も最終点にたどり着いた感じがする。内田さんを誤読していたことはたいへん恥ずかしいことであり、内田さんに申し訳ないと思う。これからは正しい理解を深めていって、思い込みでない、内田さんが優れているという面の客観的な理解をしていきたいと思う。僕の自己批判・自己分析が、同じような誤謬に陥りそうな人にとって参考になれば、僕の失敗も一つの意義を持つのではないかと感じさせてもらえる。そのようなことを願って、とりあえずの自己批判にピリオドを打とうと思う。
2006.05.25
コメント(2)
-
自分の中の教条主義と自らの誤読に対する自己批判
自らの中にある偏見に気づき、「構造的無知」から解放されて自分を冷静に眺めてみると、「地獄への道は善意によって敷き詰められている」という法則を自分が実践していたのを感じる。自らが正しいと信じた行為によって、僕は多くの人を攻撃してしまったことに気がついた。それが正しいと思っていただけに、歯止めが無くエスカレートしていってしまったようにも思う。そのようなことを見抜いていた人からは、僕のような人間は、まったく軽蔑に値すると思われても仕方がないと思っている。何を言われようとも返す言葉がない。しかし、コメント欄に暖かい言葉をかけてくれる人がいるのを見て、このような軽蔑すべき姿をさらしてしまったにもかかわらず、出直そうとする姿を暖かく受け入れてくれる人がいると言うことに、大きな感謝を感じる。人の心の温かさを感じて、ただありがたいと思うだけである。それに勇気を得て、自分にとってはもっともつらい自己批判をする決心がついた。これがどうしてつらいかというと、教条主義と誤読というのは、僕が攻撃して回った事柄なので、自らが激しく怒りを抱いていたことを実は自らが行っていたというアイロニーを認めなければならないからだ。これはひどくつらいことだ。自分で自分を軽蔑しなければならないと言うのは、自己防衛本能をひどく傷つける。僕は内田樹さんの言説を、教条主義的に崇拝していただけだったことに気がついた。自分では客観的に評価をして支持していたつもりだったが、結果的には教条主義的に支持していたに過ぎなかった。それは、内田さんを批判する言説に過剰反応していたと言うことからそれを認めざるを得ない。内田さんは、文章は誤読される権利があると語っていた。この言葉の意味を、誤読せずに正確に受け止めるべきだった。たとえ批判が、誤読から生まれたものであろうとも、批判する権利は誰にでもあるのである。その批判に対して、それが間違いであると感じたなら、批判の内容そのものに対して反批判を返さなければならなかった。しかし、僕はしばしばその反批判が行き過ぎて、その批判を提出している人間への攻撃へと及んでしまった。これは全くの過剰反応だった。批判をすることは誰にでもある権利なのだから、批判をしたことに対して文句を言うべきではなかった。批判そのものの内容にあくまでも絞って反批判をするべきだったのだ。このような過剰反応が起こる原因は、僕が内田さんを教条主義的に崇拝し支持していたことから出てくるような気がする。内田さんが批判されることに対して、僕の中には、自分が神聖だと思っている領域が汚されるというような感情が芽生えてしまったのだ。自分のことを神聖だと思われるのは、内田さんにとっては迷惑なことだったろうが、「構造的無知」にとらわれていた頃はそれに気がつかなかった。しかし、冷静に振り返れば、やはりそう言う面があっただろうと思う。それにもかかわらず、僕は論理を使えるものだから、表面的には相手の欠点を指摘して正しいことを行っているように装うことが出来た。しかし、自分の気に入らないものを叩くというのは、インターネットでの「ネット右翼現象」として語られているのと同じではないかと思う。「ネット右翼現象」では、その感情が前面に出ていて、その攻撃が理不尽であることがすぐに分かるが、僕はなまじ理論武装をしてその現象を難しくしていたので、なお始末が悪かったかも知れない。内田さんを批判する言説を見つけてはそれに反論をし、それが行きすぎて理不尽な叩き方で相手の人間に対する攻撃にまで及んでしまったことがたくさんあっただろうと思う。今は、そのような行為をしてしまった人たちに、ただ申し訳ないと思うだけだ。今さらわびられても、害した気分は回復しないかも知れないが、これもただ恥ずかしいと思うだけである。過剰反応は僕の教条主義から生まれたものだが、これが激烈な攻撃心を生み出すというのは、神聖なものが汚されたという被害感情が生まれてくるからだろうと思う。この被害感情が生まれなければ、その批判を冷静に受け止めて、批判そのものに反批判の目を向けると言うことが出来ただろう。それが出来なかったことを今は悔やむだけだ。誤謬の研究がもし本当に役に立つものなら、自分のこの自己批判が、同じような失敗を二度と繰り返さないと言うものでなければならない。言説の内容を反批判するとも、その反批判が決して人間への攻撃に及ばないように出来なければならない。「罪を憎んで人を憎まず」と言うことが実践出来るようにならねばならないと思う。内田さんへの誤読の中で、フェミニズムに対する僕の偏見を育てたのは、内田さんのアンチ・フェミニズム言説への誤読が最も大きいだろうと思う。これは、項を改めて詳しく自己批判してみたい。僕が偏見を抱き、それを育ててきたことに関しては、内田さんから受けた影響が大きい。これは認めざるを得ないが、それでは内田さんが非難されても仕方がないかといえば、それは間違いだと思う。すべては誤読をした僕に非があるのであって、そこから偏見を抱いたというのは、すべて僕に責任があることだと思っている。表現されたことから影響を受けて失敗したからと言って、その影響を与えた表現には責任はない。責任は、影響を受けて行動した人間の方に全面的にある、というのが僕の考えだ。これには異論がある人がいるかもしれないが、もっと詳しく考えてみたい。今のところは直感的にそう判断しているだけの所があるからだ。実は、僕はフェミニズムを論じることを通じて、この考えを主張したかったのかも知れない。世の中にフェミニズムという名前で流通している表現は多い。その表現の中には正しいものもあれば間違っているものもあるだろう。その影響で間違った行動に陥る人もいるだろうと思う。しかし、間違った行動に陥った人は、表現を正しく受け止められなかったと言うことで、その行動に対する責任はすべて自分が負わなければならないと思う。フェミニズムが、その人に影響を与えたことをもってして、フェミニズムを非難すべきではないと思う。林道義さんが『フェミニズムの害毒』の中で指摘している、多くの批判すべき行動は、実はその行動をした人間の責任を問わなければならなかったのだと思う。それを、表現としてのフェミニズムに責任を押しつけようとしたところに林さんの偏見があり、間違いがあると思う。指摘した事実に対する批判が正しくても、この批判の原因をフェミニズムに押しつけてしまったら、その批判の全体像は間違ってしまう。僕がやっていたことも同じことだったように感じる。表現に責任を押しつけないと言うのは、そのようなことをすると「表現の自由」が制限されるのではないかと感じるからだ。責任は、あくまでも受け取る側の人間にあるのであって、表現は原則的には、何を表現しようと自由だとしなければならない。たとえそれが間違っていたとしても、表現を制限するのではなく、間違いを正しく批判することで間違いが淘汰されなければならないと思う。間違った表現であっても、それが表現されることを妨げてはいけないというのが「表現の自由」の正しい理解であると僕は思う。僕のようなひどい間違いも、表現してもかまわないと言うことは保障されなければならない。しかし、それが間違っているなら、このように批判でもってそれが淘汰されるという方向を取るべきだろう。影響を与えると言うことで、表現に制限を与えるなら、正しいことで大きな影響を与えるような表現まで制限されてしまう。そのようなことがないように、表現の自由は守られるべきだと思う。僕は内田さんの影響によって間違った観念を持ってしまったが、これは影響を与えた内田さんにはまったく責任がない。すべては間違った僕に責任がある。このことは、内田さんの表現と僕との関係では正しいと思う。しかし、一般的にはどのようなときが正しくて、どのようなときに例外的に正しくないことがあるかを検討する必要があるだろう。これもまた項を改めて考えてみたいことだ。僕が内田さんを教条主義的に崇拝していて誤読していたことを自覚することはたいへんつらいことである。それは、まさに神聖だとすら感じていたものを自分自身が汚していたと言うことになるだけにそのつらさを感じる。この教条主義と誤読から、批判を越えて攻撃にまで至った人々に対しては、今さらながらと思われるかも知れないが、ただ謝罪の気持ちを感じるだけだ。罪を憎んでも、人を憎んではならない、と肝に銘じなければならないと思った。
2006.05.25
コメント(0)
-
偏見が生まれてくる前段階について
コメント欄にもいくつかコメントをいただいているが、今は自分にそれに答えるだけの余裕がないので返事が書けないでいる。決して無視しているのではないが、今は冷静に他のものにまで目を向けることが難しいと言うことで理解してもらえればと思う。今は、自分の失敗を見つめることで精一杯で、他のことを冷静に見つめる自信がない。今しばらくは、自らの誤謬をしっかりと見たいと思う。さて、僕が「フェミニズム」というものに偏見を抱く前段階として、あるトラウマ体験が深く関わっているような気がしてならない。以前にもちょっと触れたことがあるが、ある冊子の誤植を巡って追求されるという体験をしたことがある。その当時の僕は、ある組織の事務局長をやっていた。冊子というのは、その組織の大会の記録をまとめたものだった。これにいくつかの誤植があったのだが、当時の僕は事務局長とは言え、この記録冊子の制作には一切関わっていなかった。それは、それを担当するものが他にいて、そこが全面的にその制作を担っていたのだ。これは当然のことで、僕は教員をやりながらその組織の事務局長をしているのであって、その仕事を専門にしているわけではない。だから、具体的な処理の仕事は分業で当たるのが当然だろう。だから誤植について追求されたときに、その追求そのものがひどく不当なものだという憤りを感じた。しかもその誤植については、制作担当者の方から正誤表が提出されていて、それなりの責任を取っていると言うことがあった。誤植はミスには違いないが、そのミスの責任は取っているという認識が僕にはあったので、さらにそれを追及してくると言うことは不当ではないかという感じを抱いていた。しかし追究の本質が、単純な見間違いという誤植の指摘ではなく、その誤植に無意識の差別意識が現れているのではないかというものに及んだとき、僕はさらに不当性が高くなったのを感じてますます憤りの気持ちが高くなった。無意識への追求というのは、本人には分からないのでそれは完全に否定することが出来ない。本人がそれを分かっているなら、無意識ではなく意識的なことになるはずだからだ。だから、無意識というような追求は間違いだと僕は思った。無意識を追求するのではなく、もし差別意識がかいま見えるというのなら、どこからそれが判断出来るかというのを、無意識ではなく具体的な存在として示さなければ納得出来ないと思った。無意識の内容というのは、それが存在することを証明するのも難しいし、それが存在しないことつまり否定することも難しい。そんなあやふやなことを基礎にして議論すべきではないと言うことを感じていた。だがその追求に対して強く否定していたのは僕だけであり、それを応援してくれる声はなかった。これは僕にはトラウマ経験として残った。相手の不当な主張が、民主的には許容されてしまったのかという落胆が僕の中に残った。僕はそれ以来、その組織での活動への意欲を失った。事務局長という職を降りた後は、ほとんど何の協力的な位置には着いていない。これもトラウマ経験から来るものだ。僕が体験したものは、暴論による差別糾弾運動とでも呼べるものだった。不当な差別を告発する行為は正しい行為だ。しかし、それが暴論を元にしたものだったら、正しい行為だったものが不当な行為になる。真理が誤謬に転化するのだと感じた。無意識の中にある差別意識が、ある偶然から表に現れるということはあるだろう。しかし、それはそう言うこともあると言うことであって、すべての事柄に無意識が反映してくるのではない。解釈によっては差別のあらわれであると解釈されることであっても、それが必ず無意識の中の差別意識の現れであると言えるかどうかは、深い分析が必要なのだと思う。誤植した文字を見ただけで、そこに無意識の差別意識が潜んでいるなどと言うのは暴論だ。そのところに僕は強い憤りを感じた。人間の無意識を問題にするのなら、もっとデリケートな深い分析が必要だろうと思ったのだ。人間の無意識には、何らかのうちに不当な差別感が住み込む可能性はある。それが顔を出すこともあるだろう。しかし、それは顔を出したときに意識化して修正することも出来る。むしろ、私には一切の差別意識はありませんというような意識の持ち主は、その修正が出来ないのではないだろうか。差別意識は、小さいうちに修正出来ることが大事で、それをすべて払拭することが出来ると考えてはいけないのではないか。もしすべて払拭しなければならないとなったら、どんなに小さなものでも追求せざるを得なくなるだろう。これは、極端な暴論ではないかと僕には感じられる。社会的な影響の大きなものを教訓として、人々が自らを反省して間違いを訂正していけるように図るべきではないだろうか。無意識の心を追求することには危険な暴論に陥る危険性があると思った。このような危険性が「フェミニズム」にもあると、僕は短絡的に判断してしまったようだ。それが偏見から生まれた間違いであり、偏見そのものと言えるかも知れない。僕が自分の体験にとどまる限りで、そこで体験した誤植の追求というものの不当性を考察していただけなら、僕はその不当性の指摘を間違えることはなかったのではないかと思う。具体的な存在に即した論理は、それが的確に存在を捉えていれば間違いはしない。しかし僕は、自分の体験から、「無意識の心を追求することは論理の暴走を生む」とか、「前提とする正義を絶対的に正しいものとすれば教条主義を生む」とか言うような一般法則を導く論理を展開した。これは、抽象が正しい限りにおいては正しいのだが、それを具体的な存在に適用するときは、抽象の過程を正しく理解して、それが適用出来る条件を十分吟味しなければならない。抽象論の現実の応用にはそう言う難しさがある。それが自然科学的なものであれば僕もかなりの注意が出来た。引力の法則では、重力加速度は質量にかかわらず一定だというものがある。ガリレオの有名なピサの斜塔での実験などはそれを確かめるものだと伝えられている。大きな鉄球と小さな鉄球を同時に落とした場合、二つは同時に地上に達するという実験だ。大きさにかかわらず重力加速度は一定というわけだ。ところが、小さな羽と同じ重さを持った小さな鉄球を同時に落とすと、これは羽の方がゆっくり落ちる。この場合は、その形状が、空気の浮力という抵抗を受けやすいという条件が入ってくる。正しい法則が、そのまま現実と直結しない特別な場合だ。これは「重力加速度は一定」という抽象法則がそのままでは反映しない現実になっている。社会法則の場合も、「無意識の心を追求することは論理の暴走を生む」とか、「前提とする正義を絶対的に正しいものとすれば教条主義を生む」とか言うような一般法則は、現実の対象がこの法則を適用するにふさわしい条件を持っているかを吟味しなければならなかった。「フェミニズム」という対象に関しても、このような条件にふさわしいかの検討を具体的にしなければならなかったのだ。ところが僕はそのようなことをせずに、この法則を短絡的に「フェミニズム」に押しつけてしまった。これがそもそも失敗の始まりだった。なおそれが失敗だと気づかなかった「構造的無知」の中にあった頃は、僕がこの法則を押しつけたのは、本物の「フェミニズム」ではなくて、「暴論を犯すようなフェミニズム」なのだという強弁をしてしまった。これは全くの詭弁で、自分の間違いをさらに間違った方向へと導く論理の転落になる。そもそも「暴論を犯すようなフェミニズム」という規定は、最初から自分の都合のよい結論を出すために設定した対象に過ぎなかったのだ。このような対象を設定出来れば、自分の論理はいつも正しさを獲得出来る。しかしそれは論理としてはナンセンスである。他人がこのようなナンセンスな論理を展開しているときは、それが僕にはよく分かった。こんなご都合主義の論理なんかは少しも証明にはなっていないと言うことがよく分かった。しかし、自分がそれを展開しているのに、それにまったく気がつかなかったというのは、やはり「構造的無知」というのは恐ろしいものだ。事実の解釈から出発して、その視点を意識しつつ、どのような違う視点があるかにも注意しつつ論理を展開すると言うことが弁証法のはずだったのに、僕の「フェミニズム」批判は、事実から出発しなかったことが失敗の大きな原因だろうと思う。それは、事実ではなく自分の頭の中にあった妄想的な「フェミニズム」像から出発してしまった。この妄想を抱いていたのが失敗だったというのはよく分かるのだが、なぜこのような妄想を抱いたかと言うことは、まだ僕の無意識に属することのような気がしてはっきりとは僕に分からない。僕は学校現場にいたので、男女別の出席簿を廃止して男女混合にしたという噂は早い時期から聞いていた。しかしその多くは使いにくくて仕方がないという感想とともに聞いていた。男女混合にすると、男女別にして処理しなければならない仕事には使いにくくて仕方がないのだ。多くの医療的な診断・検診などの場合がそうだし、他にも考えればいくつかあるだろう。このときに、例えば欠席者を確かめたいと言うときに、名簿を見ただけでは対象の生徒がどこに載っているかがわかりにくい。学校現場では、名簿などは使いやすさを最優先させてもいいのではないかと僕は思っている。男女別が、ある種の思想を表しているというのが、ある意味では正しくても、それがひどく使いにくいものであるなら、そのような思想性ゆえに男女別にするのではなく、使用するときの効率性のゆえに男女別にしているのだと考えれば、男女別の名簿が存続する合理的な理由もあるだろうと思った。それを何でもかんでも男女別にしなければ、それは男優位の思想のあらわれだと考えるなら暴論であると思っていた。当時は、これとフェミニズムを直結するような発想はなかったが、どこかでこれをつなげるきっかけがあったのだろうと思う。そのきっかけは今のところ分からない。それが解明出来たら、僕の偏見の解明も一応の終着点を迎えるかも知れない。
2006.05.24
コメント(1)
-
自らの誤謬から学べること
偏見からの「構造的無知」が晴れてみると、自分の論理展開がまったく無理な詭弁であることがよく分かる。まさに構造的無知というのは、その本人にはまったく見えないことが、外にいれば容易に見えてくるという構造を持っている。ばかげた論理を展開したものだと思う。僕は「構造的無知」から、自らの過剰反応に気づかず、むしろ批判する側の方を過剰反応だと思い込んでいた。しかも、その過剰反応は、気に入らない言説を叩くためだけに批判しているのではないかという、被害者意識につながっていた。これも「構造的無知」から来る妄想だ。被害者意識を持ったことが、逆に僕の攻撃性を増す方向へと働いてしまった。向こうが叩いてくるなら、叩き負けないくらいに叩き返さなければならないと言う感情が生まれてしまったのだ。守るために攻撃するというメンタリティは、男に多いものだろうか。とにかく、そのメンタリティによって、誤解からとはいえひどい言葉を投げつけたものだと思う。人格的な非難を浴びても仕方がないとさえ思っている。その時に悪口雑言を浴びせた方には、たいへん申し訳ない思いを感じて、ただ恥じ入るだけだ。僕は日常生活では少しも攻撃的な人間ではないのに、被害者意識を感じたときの攻撃性の強さは、今振り返ってみると自分でも驚くくらいだと感じる。僕は個人であり、幸いなことに瀬戸さんの指摘で目を覚まさせてもらったので、それ以上の被害を生まずにすんで良かったと思う。オウム教団なども、凶悪事件を起こす前は、自分たちが攻撃されているという被害者意識を強く持っていたそうだ。被害者意識が暴発したときに、かえって強い攻撃性につながるというのは、一般的に言えることかも知れない。今の僕には実感としてその怖さが分かる。今さら言葉だけでお詫びをしても、気持ちの埋め合わせにはならないかも知れないが、せめて自分の誤謬を材料にして、誤謬の研究に資することが出来ればと思う。自分のひどい論理展開も、戯画的なサンプルとして展示しておこうと思う。このような誤謬を起こさないための注意をここから教訓として得たいと思う。すべては、事実と論理の確認をせずに、気分的な偏見から結論を出したことが誤謬につながっているのだが、論理の間違いとしてもっとも大きなものは、ある命題の正当性を得るためという目的のために論理を使ったことだろう。論理というのは、現実に存在している正当性を捉えることが出来たときに、論理としても正当性を持つ。しかし、現実に存在しているかどうか分からない正当性に対して、そのつじつまが合うことを目的にして論理を使えば、その正当性が存在しなかった場合は、論理は破綻する。現実の事実をいろいろ総合して、そこから本当に「フェミニズムのうさんくささ」が結論として引き出せるのなら、論理は間違いを犯さず正しいものになる。しかし、この命題が本当は存在しない偏見に過ぎないものであれば、非存在がいつかは論理の破綻を招く。論理は、あくまでも現実に存在するものからの結論という形で引き出さなければならなかった。これは論理を学んできてよく分かっているはずなのに、この問題では、現実に存在しない偏見を出発点にして、演繹的に論理を展開してしまった。相手が数学のような形式論理なら、それでも形式を踏み外さなければ真理に到達出来るが、現実存在を対象にするようなときは、現実存在が少しでも設定した目的と違う面を見せれば、その時点で演繹は破綻する。今から冷静に振り返れば何でもなく分かることがその時にはまったく分からなかった。これが本当の「構造的無知」というものだろう。まったく恐ろしいものだ。僕は瀬戸さんの言葉で「構造的無知」に気づいたが、それに気づくことは大変だろうと思う。何しろ、瀬戸さんと同じように指摘している人は他にもたくさんいたのに、その批判ではまったく目が覚めなかったのだから。これは、敵対している論者とは、互いに攻撃をしているのであって、相手が攻めてきていると言うことしか認識していないからではないかと思う。ところが、瀬戸さんに対しては、僕は大きな信頼感をおいていたので、瀬戸さんが単純に攻撃だけをしてくることは無いという思いがどこかにあった。だから、瀬戸さんに、同じようなとげとげしい攻撃的なエントリーを送った後、何でそんなことをしているのだ、という思いが突然頭に浮かんできたのだった。あのまま瀬戸さんにまでとげとげしい言葉を投げて終わっていたら、僕はばかげた論理を使って沈没する運命をたどっていたことだろう。瀬戸さんのおかげで僕は誤謬から救われたという思いがする。瀬戸さんのような人物がいてくれたことが、偏見の中にはまりこんで抜けられないと言う最悪の状態を免れさせてくれた。偏見の中で沈没しそうな人に、瀬戸さんのように手を差し伸べてくれる人間がいると、その人間はもしかしたら偏見から抜け出せるかも知れない。ひどい言葉を投げかけてお騒がせした本人が言えた義理ではないのだが、偏見を持った人間を批判するだけではなく、そう言った救い出す人物もぜひ増えて欲しいものだと思う。『フェミニズムの害毒』を書いた林道義さんだって、瀬戸さんのような人が近くにいたら、きっと偏見から抜け出せていたのではないかと思う。林さんはそれほど悪い人間じゃないと僕には思えるからだ。林さんも僕も、ごく普通のリベラルな中高年だ。封建的な思想を持っているわけじゃないし、権威主義者でもない。その普通の人間が、なぜ偏見に陥るか、そしてその偏見をどうして強化させていってしまうのか、誤謬論はそこを解決しなければいけないんじゃないかと思う。僕は、僕の身近に、暴論を吐くようなひどい自称フェミニストがいたわけではない。そのような被害を直接受けたわけではないのに、どうしてフェミニズムに対する偏見を持ってしまったのだろう。僕が過剰反応だと受け止めて、それを攻撃だと被害者意識を持ったのは、フェミニストは、そう言う自説にとって気に入らない男は叩いて回るのだと、僕の持っている偏見からそのように考えてしまった。そんなことはまったく事実として確かめたわけでもないのに、僕は無意識のうちにそんな判断をしていたことを感じる。僕の中に、どうしてそのような偏見が生まれてきたのだろうか。僕の特殊な条件がその偏見と結びついているのか。それとも、一般的に僕のような状況は多くあって、そのような偏見に陥る可能性は高いのかどうか。誤謬論として考察する値打ちがあるのではないだろうか。自分のことを棚に上げてこんなことを考えて申し訳ないが。一つ思いつくことがあるので考えてみたい。それはある種のトラウマ経験が偏見につながっているのではないかという仮説だ。それがトラウマであるだけに、心に対する影響が大きかったのではないだろうか。この次に考えてみたいと思う。
2006.05.23
コメント(0)
-
一方的な反批判停止宣言
このようなタイトルでエントリーを立てるとまた反発を呼びそうな感じもするが、自分の偏見に気づいた今となっては、その偏見を指摘される批判に対して反批判を返す意味が無くなった。というよりも、それは正当な指摘であるから、いくら叩かれてもそれを受け入れなければならないと言う感じだろうか。こういうとき、指摘の一つ一つに答えて、その批判を受け入れるかと言うことを答えた方が誠実なのかも知れないが、一つ一つ検討していくと微妙で受け入れに躊躇するものも出てきそうなので、とにかく、反批判はもうしないということで、以前のエントリーは自由に叩いてもらいたいという姿勢だけを表明する。これを無責任だとまた批判されても、今のところはそれに反批判する気はないので、とりあえずフェミニズムに関することには反批判をしないことを一方的に宣言する。そして、最後に、自分の持っている偏見を、偏見として率直に語ることに努力をしたいと思う。理論武装するのではなく、率直な思いとしての偏見を語ることに努力して、以前の失敗の反省をしたい。個人的なことを語るが、僕はいままで男としての地位を利用して女性に圧力をかけるように振る舞ったことはない。妻に対しても、女であるから家事や子育てをするべきだというような考え方で接したことはない。妻は多彩な趣味と才能を持っているので、外で仕事をしながらその趣味の世界でも活躍するという、忙しい毎日を送っているが、その生活スタイルに不満を抱いたこともない。自分の世界を広げ、自己実現のために自分の人生を費やすのは当然の権利であると思っているから、そのことによってこちらへの関心が少々薄れても文句を言ったことはない。妻が自分の欲求に従って活動するのと同じように、僕が自分の欲求でいろいろな活動をすることを同等に認めてもらえばそれでいいと思っている。つまり、行動面においては、僕は決してフェミニズム的な批判は受けないと思っている男だ。少しでも、抑圧的・封建的なところがあると指摘されて、その指摘が正しいものであればそれを改めるという柔軟性も持っていると僕は思っている。しかし、僕はこれまでの人生の中で本当の意味で抑圧的に扱われたという経験がない。自己実現をすることは素晴らしいという経験をしてきたからこそ、妻がそのような活動をしてもそれを支持出来る。だが、自分が抑圧されたことも、他人を抑圧したこともないので、実感として抑圧されることが人間にどのような影響を与えるかが本当には分からない。それは言葉で説明されたものを読んで、頭で想像して理解することは出来るが、肌で実感して受け止めることは出来ない。つまり、僕はフェミニズムが語る、男優位の社会の中で抑圧されてきた女性というものを、頭の中では理解出来るが、心の中で実感として理解が出来ないのだ。これは、そのような経験がないのだから、運命的に難しいと僕は思っている。行動的には非難されるところはないが、心の中は本当の理解が出来ていないという男に対して、フェミニズムはどのような態度を取るだろうかという予想において僕には偏見がある。それは、僕が実際にそのように扱われたという事実ではない。あくまでも予想という想像の中にしかないものだから、これは偏見以外の何ものでもない。僕の偏見は、行動面において非難されることのない男でも、社会に対して、基本的に男優位の構造が女を抑圧していると言うことを理解出来ないものは、厳しく糾弾するのではないかというものだ。これは、まだ厳しく糾弾されたわけではないので、偏見に過ぎないのだが、このような偏見を僕は強く持っている。フェミニズムが、人の心にまで踏み込んでくるのではないかという偏見が僕にはある。それが、僕のフェミニズムに対する「うさんくささ」の正体だ。これは僕の個人的偏見に過ぎないのであるから、それを理論武装して、イデオロギーの持つ暴走性につなげたのは間違いだった。それは短絡的な判断だった。僕が『フェミニズムの害毒』に書かれた林さんの主張に、基本的には間違っているけれども、批判の対象としている「林さんが考えるフェミニズム」に対する批判はその論理に正当性があると共感したのは、林さんも、同じような偏見を持っていると感じたからだろう。偏見という点で、僕と林さんは重なった。この偏見を批判して叩くのは正しいのだが、それでもなおかつ開き直って主張したいのは、これが偏見であると理解しても、この偏見は僕の中からは消えないのだ。これが、可能性として存在し続けることが、僕の中で偏見を維持し続けることの原因になっている。この偏見が消えないので、僕はフェミニズムというものに、本当に深くコミットしていくことは出来ないだろう。それは、いつも第三者的に外から眺めていくことしかできないだろう。これは、やはり「男優位の社会の常識」に毒されていると判断されるのだろうか。しかし、大部分の男はそうではないかというのは、これも僕の偏見だろうか。大部分の男は、本当の意味では、抑圧された女性という社会的な存在を理解出来ないのではないだろうか。そしてまた、僕のような男(具体的には何一つ抑圧的な機能は果たしていないが、本質的な差別の論理は肌では理解出来ない男)は、フェミニズムの側にいる人間には、実感として何を考えているかが分からないのではないだろうか。それは、林さんの『フェミニズムの害毒』が簡単に切って捨てられているように感じるところから感じるところだ。これが簡単に切って捨てられるところに、僕は、僕らのような男の心情は理解されないのだろうなと言うことを感じる。そしてそれがまた偏見を維持させることになる。僕は、フェミニズムに関するエントリーを書く前は、まだ自覚的なアンチ・フェミニズムではなかった。何となく「うさんくさい」という偏見を持っていただけに過ぎなかった。しかし、今では、その偏見が絶望的に僕には身に付いているという自覚をしている。とても努力だけで捨て去ることが出来ない。僕は、封建思想をもっているからという理由でフェミニズムに反対しているのではない。だから、そのような方面で反フェミニズムを主張している人間たちとは連帯出来ない。フェミニズムが主張している、不当な男女差別をなくすということは正しいと思っているからだ。しかし、フェミニズムの陣営とも連帯することは絶望的に難しいとなったら、僕は他人事としてこれを見ていくことしかできないだろうなと思う。僕のような男が多いか少ないかは、検討に値する問題だと思う。男の陣営は、封建的・家父長的な価値を守る反フェミニズムに属するか、フェミニズムに賛同する者たちか、そして僕のようにどっちつかずの偏見を持った男たちか、大きく分けると3つに分かれるのではないだろうか。どの男たちがもっとも多数派を占めるだろうか。僕の最初の問題意識は、このようなものであったはずなのに、理論武装しようとした間違いが論理の破綻を呼んだ。「構造的無知」のなせる技だろう。なまじ論理が使えたから、この無知に陥ってしまった。偏見を叩く批判に対しては、こちらに反批判の余地はないのだから、もう反批判を書くことはない。それは決して無視しているのではなく、反批判出来ないので書かないのだと解釈して欲しい。僕の方に、もし余裕があれば、後日、ああここのところはこう叩かれても仕方がないなと反省するエントリーを書くかも知れないが、余裕がなければそういうものも書けないかも知れない。そこで、chikiさんにもたいへん申し訳ないのだが、視点の違いからの反批判を書く意味が無くなってしまったので、これも一方的に終わりにさせてもらいたい。もちろん、chikiさんが、僕の偏見の部分を正当に批判するのはchikiさんの自由だ。これに対しては、僕はそれを受け入れるだけだ。このエントリーに対してもたぶん不満を感じる人は多いだろうが、その不満は批判として発言してもらいたい。それに対して僕はもう反批判はしないけれど、決して無視しているのではない、と解釈して欲しい。
2006.05.23
コメント(5)
-
瀬戸さんの指摘はほぼ全面的に正しかった
昨日瀬戸さんのトラックバックに対して返事を返したとき、最後に「内田さんによれば、フェミニズムはすでに終わってしまったと感じられている。そうであれば、どこで破綻していったのか、その分かれ目がどこにあるかが僕の次の関心になる。僕は、フェミニズムに対しては、論理的考察の対象以上の何の感情も抱いていないのだ。」と僕は書いた。書いた後で、オレは何をこんなに力んだ書き方をしているんだろうという思いがふと頭をよぎった。そして、よく考えてみたら、瀬戸さんが指摘するように、僕が書いた最初のエントリーの題名が問題だと言うことが急に理解出来た。よく考えてみれば、あのエントリーは、僕が抱いている「フェミニズム」という言葉に対する偏見が基礎になって書かれているものだ。僕はその偏見を偏見として自覚してはいたものの、インテリのイヤらしさから、偏見を理論武装しようとしてしまった。偏見であるなら、偏見として率直に語らなければならなかったことに気づいた。僕に理論武装するだけの能力がなければそんなことをせずにすんだのだろうが、その率直さが無かったことが、偏見を理論武装するという間違いを犯してしまったように感じる。このことが分からなかったので、偏見を指摘する声をすべて過剰反応だとしか受け取れなかった。これは、そもそも僕が「フェミニズム」に抱いていた偏見のせいで、いろいろな現象に過剰反応していたことが、あのエントリーの原因であったのに、自分の過剰反応に気づかなかった僕は、僕のエントリーに対する反応も過剰反応であるという理解しかできていなかったようだ。「構造的無知」というものだろう。その部分だけは、僕の頭からはまったく抜け落ちていた。本当にまったく理解出来なかった。瀬戸さんに対して、何であんなに力んだ言葉を返したのだろうと言うことがきっかけで、ようやくこの「構造的無知」に気がついた。僕のあのエントリーは、全くの偏見から出発したものでありながら、その偏見が生じてくるのを理論的に捉えようとしたことが間違いだった。偏見が正しいことを証明しようとしたのではないが、偏見が生まれることはやむを得ないと言うことを理論的に語ってしまったことが間違いだった。あの偏見は、まったく僕の個人のものとして語らなければならなかったのだ。そのことを自覚したくなかったのだろうな。全くの「構造的無知」だと思う。とりあえず、瀬戸さんに僕の間違いを伝えたいと思い、この短いエントリーを立てる。
2006.05.23
コメント(0)
-
可能性(可能無限)とイズムの暴走性
瀬戸智子さんから「論理学の勉強」というトラックバックをもらった(ライブドアブログで)。コメント欄に書き込もうと思ったのだが長くなりそうな気がしたので一つのエントリーとして立てることにした。「すべての命題は相対的である。」という言葉の意味を解釈すると、これは、すべての命題には真になる場合もあれば偽になる場合もあるということになる。これは、「すべて」という言葉で語っている世界が、どの世界なのかで違ってくる。「すべての命題は相対的である。」という命題は、形式論理の世界では成り立たない。形式論理の世界では、一度真だと決めた命題は、永久に真でなければならない。相対性はないのである。必ず偽になる命題は「矛盾」と呼ばれるが、形式論理の世界では「矛盾」が真になることはない。もしそのようなことが起こったら、形式論理の世界そのものが破綻する。しかしひとたび形式論理の世界を離れて、現実の対象を扱う弁証法論理の世界に入ってくると、「すべての命題は相対的である。」ということが真理になる。これは、現実存在というものが、必ず違う視点を持って眺めることが出来る存在であるという理解から得られる。違う視点から眺めることによって、その命題が真である範囲と偽である範囲が区別される。肯定と否定が両立するという弁証法的「矛盾」の姿がそこにある。だが、現実存在に対して「すべて」を語ると、ここに述べられている「クレタ人のパラドックス」のような論理破綻をもたらす。この「すべて」が自己言及的なものを含む「すべて」であった場合論理は破綻する。それならば、「すべて」は何ものに対しても言えないのか?一つだけそれが言えるものがある。それが可能性(可能無限)だ。現実存在を見る視点というのは、実際の具体的な存在を見てみないと分からない。だが、一面だけを見るのではなく、必ずどこか違う方向から見える可能性があるはずだと考えることが出来る。その可能性がある限りでは、すべてに言及出来る。個々の存在のすべての集合という「実無限」をいっぺんに捉えることは出来ないが、任意の対象に対して、前から見るのと違う視点は必ず可能性として存在していると考えられる。それをすべての対象について確かめ終えると言うことはないけれど、必要ならどれかの対象をつかんで調べることが出来るという可能性がある。この可能無限については、数学的帰納法というものがそのイメージを教えてくれる。自然数の全体をすべて数えきることは出来ない。しかし、何でもいいから自然数を取ってきて、その一つ後というのはいつでも考えることが出来る。どんな自然数でも、任意のものを作り出す可能性が存在するわけだ。そうすると、ある自然数について正しいことが、その一つ後の自然数についても正しいことが確かめられると、任意のどんな自然数を取ってきても、その一つ前、また一つ前と遡って、一番小さい1にたどり着く。その1で正しさが確認出来れば、任意の自然数について正しさを確認出来る可能性を得たことになる。これが、数学的帰納法による、すべての自然数について成立する法則の証明となる。可能性というものに関しては、「すべて」に言及することが許されるのである。「フェミニズムという考え方の暴走性であって、フェミニズムそのものが間違っているという議論ではない。」という命題は、フェミニズムそのものを対象にしたのではなく、「考え方」とも言うべき「イズム」のようなものが、可能性として常に暴走する危険があるということを基礎にして出てくる命題なのである。この場合の「すべて」は可能性に関して語っているので論理的に成立する。だから、フェミニズムにも暴走する可能性があるという意味で上の命題を理解する必要がある。これを実体としての「フェミニズムは暴走する」というふうに解釈してはいけないのだ。それは、個々の現実に存在する「フェミニズム」と呼ばれるものの個性を検討して判断しなければならないのだ。宗教的信条は、可能性として常に暴走する危険を持っている。しかし、現実に暴走したのはオウム教団という具体的な存在だった。実体としての教団というものが持つ宗教が暴走するかどうかは、その宗教の具体的実体を考えなければ結論出来ない。しかし、可能性を語る限りでは、すべての宗教は暴走する可能性をもっていると考えることが出来る。だからこそ暴走する可能性に対して歯止めを作る必要がある。政教分離の思想はその一つだろう。ここまでは論理的な話だ。次に、瀬戸さんが指摘している「フェミニズムのうさんくささ」のタイトルの問題に移ろう。このタイトルが、論理的な考察を妨げて感情的な反発を呼んでいるという指摘だ。しかし、僕はこのタイトルは充分論理的なものだと思っている。「フェミニズム」というものは充分うさんくさいものなのだ。だいたい「フェミニズム」という言葉は、その定義が明確には決まっていない。自分が信じるフェミニズムこそが本物のフェミニズムだという主張をしたいだろうが、それは出来ることなのかどうか。フェミニズムと呼ばれているものに怪しいものまで含まれているというのが現状ではないのか。それが本物ではないと主張するのは自由だ。しかし、それをフェミニズムという範疇からすべて取り除くことは出来ないだろう。ウィキペディアの定義を批判するものもたくさんいたが、では、ウィキペディアの語るフェミニズムは本物ではないからということであそこから排除出来るのかどうか。「フェミニズム」がうさんくさいというのは、僕の感覚であり、しかもそれは事実に基礎を置いた感覚なのである。その「うさんくさい」という言葉を否定しようとしても仕方がないのではないか。先週のマル激では、選挙の頃にインターネットで「うさんくさい」を検索すると、一番に亀井静香さんのページが登場したと語っていた。僕は、亀井さんを死刑廃止論で知ってからは、政治家として尊敬しているが、亀井さんの死刑廃止論のようなパブリックな面を知らない人が、亀井さんは「うさんくさい」と言ってもそれは仕方がないと思っている。おそらくその人は、亀井さんの他の面である保守政治家としての、利益のためにはどんな行動でもするという面は知っていて、その面を捉えて「うさんくさい」と思うのだろうと思う。僕のように尊敬を感じるような評価も、「うさんくさい」と感じる評価も、評価としては両立しうるし、そう感じることは仕方がないのである。フェミニズムに対しても、それが素晴らしいものだと信じて行動する人間もいれば、その「うさんくさい」面に注目する僕のような人間がいても仕方がない、というのが現実なのだ。その現実をなぜ正面から見ようとしないのだろうと思う。「うさんくさい」と感じる人間がいたら、フェミニズムの信用は落ちてしまうほど、自分が信じているフェミニズムは脆弱なものなのか。それが素晴らしいと信じているのなら、ちょっとくらい欠点を突っつかれたくらいでなぜ過剰反応をするのか。そんな欠点などこうやって克服してやるというようなことがなぜ言えないのか。フェミニズムに対しては、それを褒めてくれる仲間内の議論しか目に入らないのか。外からの批判には耳を傾けないのか。考えが暴走する可能性があるのはフェミニズムばかりではないのだから、他との比較も必要だと語った言葉があったので、その比較をしてみて気がついたことが一つある。大きな暴走をして、社会に多大な害悪を与えたマルクス主義やオウム教団に共通していたのは、「無謬性」という言葉で語ることの出来るものだと感じる。「無謬性」こそが暴走のきっかけになるのではないかと思う。旧社会主義国は、国家に対する批判を許さなかった。国家は間違えてはいけないし、常に正しいとされなければならなかった。それは、プロレタリアート独裁の正当性が崩れてしまうからだ。失敗した政府は、当然責任を取って交代しなければならないのが、近代の掟だからだ。資本主義国家が、社会主義国家ほどの大きな暴走を許さなかったのは、失敗した政府を批判するという、失敗に対する対処のメカニズムがあったことが大きかったと思う。毛沢東が、いかに文化大革命で失敗しようと誰も毛沢東を批判出来なかった。それを失敗(誤謬)と認識することが許されなかった。無謬性というものがその考えにあると、間違ったことを正しく判断出来ない。おそらくこれが暴走のきっかけになって、その歯止めがなかった旧社会主義国は完全な破綻の道を歩んだのだろう。無謬性に拍車をかけるものに教条主義というものもある。これがはびこっていると失敗の認識はさらに難しくなる。「うさんくさい」という言葉に過剰反応する心情の中に、無謬性とか教条主義の陰がないかどうか、よく考えて欲しいと思う。これは自分でそれが分かるときは、それを乗り越えることで成長出来るが、他人から見える形で出てきてしまえば、その「イズム」は破綻への道を歩む途中になってしまうのだ。その分かれ目になるのが、誤謬に敏感になると言うことになる。内田さんによれば、フェミニズムはすでに終わってしまったと感じられている。そうであれば、どこで破綻していったのか、その分かれ目がどこにあるかが僕の次の関心になる。僕は、フェミニズムに対しては、論理的考察の対象以上の何の感情も抱いていないのだ。
2006.05.22
コメント(0)
-
「数学屋のメガネさんへの再批判。」に対する反批判 4
さてchikiさんの「数学屋のメガネさんへの再批判。」に対する反批判の続きだが、以前の石原慎太郎氏の言葉を巡るものを、ちょっと補足説明しておいた方がいいと感じた。これを論理の問題とすることに違和感を感じる人がいるかもしれないので、そのあたりのことを説明しておく。とりあえず、その部分の僕の文章を全文引用しておく。「このような極論からの批判は、論理的正当性も伝統も無視したものになる。だから、他の視点を持っている人間からはそれが行き過ぎだと思われてうさんくさい目で見られるようになるだろう。このような極論に対しては、「石原慎太郎東京都知事は、都議会定例会において、「最近、教育の現場をはじめさまざまな場面で、男女の違いを無理やり無視するジェンダーフリー論が跋扈(ばっこ)している」、「男らしさ、女らしさを差別につながるものとして否定したり、ひな祭りやこいのぼりといった伝統文化まで拒否する極端でグロテスクな主張が見受けられる」、「男と女は同等であっても、同質ではあり得ない。男女の区別なくして、人としての規範はもとより、家庭、社会も成り立たないのは自明の理だ」と強調し、ジェンダーフリー教育を公人の立場で公式に批判した。」と、ここに書かれているように、石原氏の批判が正当なものとして論理的には判断出来る。僕は、政治家としての石原氏には批判的だが、極論としてのジェンダーフリーに対するこの批判は正当だと思う。」石原氏の論理の場合前提としているのは、「男女の違いを無理やり無視するジェンダーフリー論が跋扈(ばっこ)している」ということだ。この「ジェンダーフリー論」が、ジェンダーフリーという言葉で十把一絡げに出来るものではないということには同意する。しかし、ここで非難されているような「男らしさ、女らしさを差別につながるものとして否定したり、ひな祭りやこいのぼりといった伝統文化まで拒否する極端でグロテスクな主張」というものが全く存在しないという「事実の否定」までが出来るだろうか。このような事実が全く存在しないのであれば、事実の問題として石原氏の言葉を引いたのは不適切だったと僕も非を認めよう。しかし、このような主張が存在し、その主張によって男女別の出席簿を否定したり、「ひな祭りやこいのぼりといった伝統文化まで拒否」したということがあったのなら、それに対する批判としては石原氏の批判は正当だというのが僕の評価だ。論理の問題というのはここまでである。この主張がジェンダーフリーを代表する主張だと受け取ったらそれは間違いになるだろう。しかし、僕が論じていたのは、逸脱したフェミニズム的発想から生まれるであろう主張の批判だ。この主張は、ジェンダーフリーの主流ではないかもしれないが、逸脱によって生まれる可能性はゼロだろうか。そこのところが論理の問題なのである。あくまでも逸脱したものからの発想という前提があるのだが、読み手によっては、その部分を逸脱したフェミニズム的言説とは読まず、それこそフェミニズムだと誤解するおそれはある。そこのところは、配慮が足りなかったと思う。しかし、chikiさんがここで提出している石原氏の記者会見の言葉「彼らが具体的に提唱している幾つかの事案に関しては、とても常識でいって許容できないものがたくさんあるから。そういう例外的な事例がね、あまり露骨にメディアに持ち上げられて出てくると、ジェンダー・フリーのある正当性を持ったムーブメント(動き、流れ)でもね、私は非常に誤解を受けると思いますよ。」を見ると、ここで謝罪しているのは、そのような事実がなかったにもかかわらずあったと偽ったことを指しているのではない。例外的な事例があったことは否定していないのである。それをジェンダーフリー一般と結びつけたことを謝罪しているように僕には読める。そうではなかったのだろうか。論理の問題としては、このような極論がまともなフェミニズムからも生まれてくるかというのが僕の問題意識だ。そうすると、そんなものはどんな理論だって極論を考えれば生まれてくると主張する人がいるかもしれない。ことさらなぜフェミニズムだけを取り上げるのか、という疑問がその後に続くだろう。まさしく、極論を考えればどんなものでも誤謬に陥るからこそ誤謬を考えることが重要になるのである。そして、どんなものでも誤謬に陥るにもかかわらず、ある存在は誤謬を免れ、ある存在は誤謬にとらわれる。その差はどこにあるかというのが僕の問題意識だ。マルクス主義は、逸脱した誤謬の影響が最も大きかった理論だろう。オウム真理教では、その教義が極論へと流れていった。このような極論への流れは、いかなるメカニズムで起こるのか。そして、その社会的影響はどうとらえたらいいのか。その考察の対象にフェミニズムが選ばれたことに感情的な反発はあるかもしれない。これは、僕のうさんくささの感覚からくるものだ。うさんくさいものの方が誤謬に流れる可能性が大きく、しかも悪影響が大きいと思ったので考察の対象にしている。マルクス主義もそうだったがフェミニズムも、自らが正義の立場にいることに疑いを持たない。絶対的正義を標榜しているように見える。確かに「女性であるだけで差別されている」などということに反対できる男はいない。それが真理であるなら、それは絶対的な正義を持つ。問題は、現象を解釈したときに「女性であるだけで差別されている」などという判断がいつも正しく行えるのかということだ。それはとても難しい判断だ、という自覚があれば、フェミニズムは極論に流れることから免れるだろう。しかし、現象を捉えて短絡的にそう結論しているように見えるときは、フェミニズムは極論に陥る危険性をはらんでいるのではないかと僕は感じる。こういう可能性を論じても、そういうことの事実を見せろという要求をする人間もいるだろうなと思う。「女性であるだけで差別されている」ということを証明することが難しいのと同じくらい、それが間違っているという証明をすることも難しいのだ。だから、本質的には、そのような難しい判断をするときは、いつも間違いに陥っていないかという反省が必要なのだ。それが可能性を論じるということだ。事実を示せという要求は、そのような判断が簡単に行えると主張しているに等しい。それが簡単にできると思っている人間は、極論に陥ってもたぶん気がつかないだろう。僕はそう思う。僕の論理は、そういうことを論じているのである。このエントリーに関して論外に低い水準のトラックバックが来た(これははてなの日記でのこと)。最後にこれに言及しておこう。「あくまでも「仮定」の話ですから」というエントリーでは、仮言命題の「仮定」の話をしているのだが、ここで語られている場合にも、「仮定」には何をもってきてもいいというとんちんかんな論理的理解をしている。仮定に何をもってきてもいいということが、ある条件の下での話だと言うことはきっと何も知らないのだろう。仮言命題での仮定というのは、形式論理で言うと、「AならばB」のAに当たるものを言う。これが形式論理の範囲であれば、Aの位置に置かれた命題はすべて仮定と呼ばれる。確かに、形式論理であれば、それは任意の命題Aを置くことが出来る。しかし、形式論理が、なぜ形式論理と呼ばれているかといえば、それは命題の内容を捨象して、命題の関係の形式にのみ注目して、その形式と真理性との関係を見るから形式論理と呼ばれているのである。「AならばB」のAは確かに仮定ではあるが、この命題だけでは、形式論理は何の意味もないのである。Aが正しいかどうかと言うのは、形式論理では判断出来ないのである。形式論理の仮定に意味が出てくるのは、「AならばB」「BならばC」という二つの仮定を置いたとき、そこから必然的に「AならばC」という形式の命題が導かれると言うときに、仮定に意味が出てくるのである。実際に命題の内容が関わってきて、現実に具体的に仮定が設定されるときは、その仮定と、そこから推論される結論との間に内的な連関がなければならない。何も関係のない、単に命題であるというだけのことでそれを仮定にしても何の意味もないのだ。 「うちの犬はバナナが好き」ならば「昨日のおかずは魚だった」という命題は、形式的には、「うちの犬はバナナが好き」が仮定になっている。だが、それが仮定になっていることで何が言いたいのだろうか。これの形式だけを問題にしたいのなら、「AならばB」と書けば足りるのである。形式論理はそのようにしている。「「数学屋のメガネのkhideakiさんの言うことはすべて間違っている」と仮定してみる。その仮定に基づき「間違ったことを、さも小難しい用語を並び立てて正しいそうに言っている数学屋のメガネのkhideakiさんはバカにちがいない」と判断する。」と語ることで、本人は何か言ったつもりになっているかも知れないが、それは論理に対する無知をさらけ出しているだけのことなのである。皮肉のつもりなのかも知れないが、この程度の水準でアイロニーだなどと考えているとしたら、文学的表現の水準も低いものだと思う。この文章を書いた人間は、専門が理論社会学だそうだが、この程度の論理水準で理論社会学が出来るとは驚きだ。このように論外に低い水準のトラックバックは削除しておく。今回は言及したが、次回からは言及せずに削除することもあるだろう。その時は、「論外に低い水準」だと判断したと思ってもらえばいい。(この削除の基準は、はてなでもライブドアでも同じ。論外に低い水準のものは削除する。)
2006.05.22
コメント(0)
-
「数学屋のメガネさんへの再批判。」に対する反批判 3
さてchikiさんの「数学屋のメガネさんへの再批判。」に対する反批判の続きだが、まずは次のようなものから始めよう。chikiさんは、僕の提起を「極端なフェミニズムの登場→正当なフェミニストが是正しない→誤解の蔓延→自分のような噴きあがりが続出→ムキー」という単純な図式で解釈しているが、もしこのような単純な図式で受け取っているとしたら、「フェミニズム」という言葉が陥っている強い偏見と誤解を払拭するのはかなり厳しいだろう。僕は行き過ぎたフェミニズムをいちいち訂正して回れなどと言うことは一言も言っていないと記憶している。そんな風に受け取れるような記述があれば、僕の文章表現のミスだろうと思う。無意識の中にも、そのような考えはないとかなり自信を持って言える。なぜなら、そんなことをしても少しも偏見の解消にならないと思っているからだ。間違ったフェミニズムは、フェミニストが是正しないから蔓延するのではない。普通の思考がちょっと行き過ぎただけで誤謬に陥るから、誤謬になるような可能性があふれているから、それが蔓延するのである。その蔓延を防ぎたかったら誤謬の研究をして注意を呼びかけるしかない。そのようなことを僕は言いたいのだ。もしフェミニズムの陣営が誤謬に鈍感であれば、その指導的立場にいる人間に決定的な誤謬が生じる恐れがある。マルクス主義の陣営はまさにそうだった。その決定的誤謬は何をもたらしたか。マルクス主義が正しく論じていた部分まですべて失うという、完全なマルクス主義の死をもたらした。ここで内田樹さんを引用するとフェミニズムの陣営としては神経を逆なでされたように感じるかも知れないが、「2006年05月20日 エビちゃん的クライシス」の中で内田さんは、「「フェミニズムはその歴史的使命を終えた」と私が数年前に書いたのは、事実認知的な意味ではなくて、遂行的なメッセージとしてである。「歴史的使命はそろそろ終わって頂いても、ウチダ的にはぜんぜんオッケーなんですけど」ということを言いたくて、いささか先走り的なことを申し上げたのである。戦略的にそう言ってみただけで、まさか、「ほんとうに終わっている」と思っていたわけではない。」と書いている。フェミニズムという言葉自体が死語になってきていることに驚いているのだ。今はマルクス主義は完全に死語になって、それを理解出来る若者は皆無ではないかと思う。それと同じような状況がフェミニズムという言葉にも出てきたと内田さんは感じているらしい。内田さんが語っていることは、内田さんの大学の狭い範囲内での特殊な状況だと解釈することも出来る。しかし、それが一般的な出来事であったりすれば、フェミニズムという言葉が死語になったかも知れないと言うことは、誤謬の分析を通じてもっと深刻に受け止めなければならないことなのではないかと思う。僕が吹き上がってフェミニズムの攻撃をしているという解釈では、まったく深刻には受け止められていないのだなと思う。「このような認識は、メディアやテクストの性質に対してあまりに鈍感であるといわざるを得ません。」という言葉が、僕の言葉の引用とともに語られているのだが、僕には「このような」という代名詞の意味が分からない。「鈍感」という言葉に対しても、どこが鈍感なのかが分からない。「この」はいったい何を指しているのだろう。どんな認識を指しているのだろうか。またメディアやテクストの性質とは、具体的にどのような性質を言っているのだろうか。残念ながら、ここで語られていることは何一つ僕には分からない。ここでは、「言語の「本質」についてご存知である秀さんには釈迦に説法でしょうから説明は省略しますが」と言っているが、どうも僕が考えている言語の本質と、chikiさんが捉えている言語の本質には違いがあるような気がするので、ぜひ「釈迦に説法」してもらいたいものだと思う。と、ちょっと皮肉っぽく書いたが、これはここに感情の揺れを見たので、同じようにちょっと感情的な対応をしてみたくなった。こういう言い方は、議論としてはあまりよくないと僕は思う。批判であればこのような皮肉も、まあ勝手に言ってくれよという受け取り方ですむが、議論の中で使われると、ディベートのテクニックなのかなと感じてしまうだけだ。リベラルの側の人間は、ディベートのテクニックはあまり使わない方がいいと僕は思う。感情を揺さぶられるときもあるだろうが、その感情をそのまま読みとられるような表現を使わない方がいいだろう。論理はあくまでも冷たく突き放して、無関係の第三者のような顔をして語った方が間違いが少ない。「秀さんの色メガネから見た世界」というレッテル貼りも、リベラルの側は使わない方がいいだろう。そう思っていても口に出すのは不利だと思う。このように感じていたら、誰が読んでもそう結論せざるを得ない相手の言葉を引用して、「秀さんの色メガネから見た世界」と表現しなくても、そう読者が感じるような書き方を工夫した方がいいだろう。僕は、相手がどんなにバカだと思えても、直接バカだとは表現しない。その主張がどれくらいばかげたことであるかの論証に最大限の努力を費やす。バカという言葉を使わずにバカという認識を伝えることに努力する。直接的な悪口雑言を吐いてしまったら、言説の説得力を失うだろうと思う。特にリベラルの側はこの点に注意した方がいい。そんなことをしたら、いわゆる「ネットウヨ」の類と同じにしか見られないからだ。このような僕の態度は、自らの悪意を自覚しての行動だ。しかし、悪意を自覚した人間の方が、僕は正しいことが言えると思っている。善意だけの人間が、善意があるから正しいと勘違いしている姿を見ていると、僕の中の悪意は、それに皮肉を投げつけてやりたくなる。それに対して、「「僕が誤解しているんだから、フェミニズムの戦略的失敗だい」という程度の主張でしかない」という解釈をしているのは、かなり甘いのではないかと思う。僕の悪意はその程度ではない。確信犯的な悪意をもって語っているのだから、このままではフェミニズムは本当に死んでしまうと言うことを語っていると受け取って欲しかった。そして、それが死ぬことに対して、僕は守ろうという気持ちは全くないと言うことは内田さんと同じだ。僕の中のそう言う悪意までも受け取って批判してもらいたいと思う。「前回のエントリーでも触れましたが、私はかようなメディアイメージを払拭する努力をしてくれる論者がいれば支持します。しかし一方で、メディアイメージや誤配の問題すらも「フェミニスト」の責任や戦略の問題にして批判してしまうかのような秀さんのスタンスは問題であろうと思います。」という主張もかなり甘さを感じるものだ。メディアが悪いイメージを発信することが偏見の原因なのか。それを改善すればフェミニズムに対するイメージは回復するのか。メディアにそのようなことを期待しているのか。僕は、マスメディアにそんなことを期待しても無駄だと思う。むしろ逆の方に作用するだろう。フェミニズムというのは戯画化すれば笑える対象になってしまうのだ。笑える対象になるものを、マスメディアが笑いの対象にしないことがあると考えるのは、あまりにも正義に対してナイーブすぎるのではないか。笑いものにしようと思えばいくらでも欠点は見つけてくることが出来る。それは2チャンネルを見ればよく分かる。そして、マスメディアは、そのような情報をこそ「売れる情報」として喜ぶのだ。「メディアイメージや誤配の問題すらも「フェミニスト」の責任や戦略の問題にして批判してしまう」というのは大いなる誤解だと僕は感じているが、このような認識にとどまっていたら、あら探しされるような欠点はなくならないという自覚が欲しい。あら探しなどはいくらでも出来るのである。だから、偏見を持ちたい人間はいくらでも偏見を持てる。事実を語って嘘をつくことはいくらでも出来るのである。だからこそ誤謬に敏感になって欲しいという願いなのだが、残念ながらそのような思いはまったく伝わらないようだ。偏見を煽って、攻撃しようと思えば、いくらでももっと過激なことを書ける。その偏見は、偏見を持つ方が悪いという認識にとどまっている限りでは、偏見の払拭は出来ないと僕は思う。特に相手が悪意をもっているときは、「相手が悪い」というのは百も承知で悪いことをしている確信犯だ。フェミニズムは、体制権力を批判する面を含んでいる。そんなものは弾圧されるのが普通だと受け止めておいた方がいい。正義の主張をするだけではフェミニズムを守ることは出来ないだろう。正義なんて、どうせその時の多数派の意見に過ぎないのだから。
2006.05.22
コメント(0)
-
「数学屋のメガネさんへの再批判。」に対する反批判 2
chikiさんからさっそく反応が返ってきたことを感謝したい。幸いなことに、今忙しいそうなので、この間に、「数学屋のメガネさんへの再批判。」の残りの部分に対する反批判を書いてしまいたいと思う。新しいエントリーで、批判の趣旨はさらに深く分かってきたのだが、それでもやはり疑問は解けない。chikiさんは、「「たとえ善意から出発した○○であろうとも、それが極論にまで達すれば論理的には間違える」というのはどんな論理にも当てはまる」と書いている。つまり、僕が語ったことはある意味ではごく当たり前のことなのである。書き方が気に入らないということはあるだろうが、ごく当たり前のことに対してどうして過剰反応が起こるのかが僕には分からない。僕は弁証法の正しさを確信しているが、それも条件を逸脱しない限りでの正しさだという自覚をしている。弁証法だってその適用範囲を逸脱すればいつでも詭弁に転落する。誤謬の可能性はいつでも存在する。それは当たり前のことであって、当たり前だからこそ、誤謬に敏感になって、どこで真理が誤謬に転化するかということを研究しなければならないと思う。誤謬の研究は、宮台真司氏やその師匠の小室直樹氏も重要性を強調していたものだ。敗戦という明らかな失敗に対しても日本ではその失敗(誤謬)を深く研究することが出来なかった。そのような社会は、同じ失敗を繰り返す危険性がある。昨今の国会の状況を見ていると、そのような論理の繰り返しが起きているのではないかとも懸念される。フェミニズムにもこんな所に論理が逸脱する可能性があるという指摘は、それほど非難されるようなことなのだろうか。これによってフェミニズムへの偏見や誤解が助長されると思っているのかなという印象を受けるが、この程度の論説で偏見や誤解が助長されるのであれば、すでにもう偏見や誤解の中にあるのではないか。その偏見や誤解は、世間で流通しているフェミニズムは本当のフェミニズムではない、と切って捨ててすませられるものなのかどうか。むしろどこに誤謬を生むきっかけがあるかを、当事者が論じない限り、誰もその偏見や誤解から抜けることが出来ないのではないだろうか。マルクス主義は完全に死んでしまったし、日本共産党は偏見と誤解の中にある。だが、共産党は自らの誤謬を明らかにして反省したことはない。無謬神話というものがはびこっている。誤謬は、誤謬を正しく認識してこそ真理に到達する。日本共産党が自らの誤謬を真摯に反省しない限り、最初から共産党を支持していない人間でない限り、外から見ている人間は共産党をうさんくさいものだと感じるのではないだろうか。フェミニズムというまとまった陣営はないのだろうが、フェミニズムの側に立っていると自覚している人たちは、むしろフェミニズムが行き過ぎて誤謬に陥ることに対してもっと敏感に研究した方がいいのではないかと思う。そして、このような行き過ぎをすると誤謬に陥るのだから注意をしようと呼びかけた方がいいと思う。僕の指摘が論理的に間違えているということであるならその指摘が欲しかったが、大部分は、僕が論じている「逸脱したフェミニズム」は、あんなものはフェミニズムでは無いという反応だった。これはとても冷たい言い方だと思う。「逸脱したフェミニズム」に陥って間違った行動や発言をしている人たちはたくさんいると思うのだ。それが妄想の中だけにしかいないというのは間違っていると思う。それが妄想だけなら、迷惑だと思って事実を報告する人もいないだろう。この人たちは、まったく本来のフェミニズムとは関係のない人たちだと切って捨てることが出来るだろうか。本来のフェミニズムのある一部に反応して、その一部を肥大させてしまったために誤謬に陥ったのだとは考えられないのだろうか。そう受け止めれば、その人たちの誤謬に陥ったきっかけをもっと深く検討して、正しい道に戻るような援助が出来るのではないだろうか。それとも、間違いの中にいる人は、間違った人間が悪いのだから、切って捨てればそれでいいのだろうか。これは、人間の態度としてかなり冷たいのではないかと感じる。筆坂秀世さんは、軽率な行動で失敗を犯した。それに対して共産党は、ミスを犯した筆坂さんを切って捨てて放り出しただけだった。冷たい組織だなと思う。筆坂さんが、ミスを挽回して頑張る姿を見せられれば、日本共産党に対するイメージもだいぶ変わっただろうにと思うのだが、今回の結果でイメージはさらに落ちただろう。共産党に対してこのように語ることは、政治的には偏見と誤解を助長する言い方になるだろうか。僕はそう言われても仕方がないのではないかと思う。自業自得ではないかと思うのだ。誤謬に対して鈍感な姿勢がこのような結果を招いたのだから、それを指摘されても文句は言えないのではないかと思う。chikiさんは、「「男女の違いを無理やり無視するジェンダーフリー論が跋扈(ばっこ)している」ことが前提になった」ということを問題にしているが、この前提が全くないと言い切れるかどうかにも僕は疑問を持っている。もちろん、そのような「男女の違いを無理やり無視するジェンダーフリー論」は、本物の「ジェンダーフリー論」では無いという批判はここでもあるだろうが、それが本物ではないということを認めた上で、あえてそのようなものが「跋扈している」ということはないと言い切れるだろうか。もしそういうものが跋扈しているのであれば、それに対して不満や非難をする方が当然だと思う。この「男女の違いを無理やり無視するジェンダーフリー論」というのは、非難する人間の頭の中にしかない妄想なのか。それは現状認識としてどうなのか、ということが疑問だ。もちろん、それが本物のジェンダーフリー論ではないということは同意してもいいと思うが、本物ではないということで済ませていいのかというのが僕の疑問だ。「男女の違いを無理やり無視するジェンダーフリー論」は、本物のジェンダーフリー論とはまったく関係のない、間違った人間が悪いだけのことなのか。それは、筆坂さんを切って捨てた共産党の冷たさに通じるものなのではないか。また「デマの拡大解釈などに基づくメディアイメージ自体が疑わしいということが指摘されれば、そのイメージや発言の引用を利用した論理的展開は現実味や説得力を失います」と語っているが、現実にはそれは必ずしも成立しないのではないか。小泉さんの派手なパフォーマンスは、論理的にはひどいデタラメばかりで、メディアイメージも相当疑わしいものとして、笑いの対象になっていたように感じた。しかし、選挙では圧倒的多数に支持されて自民党が圧勝した。小泉さんのイメージ戦略は、少なくとも選挙民に対しては「現実味や説得力」をもったのではないかと思う。これはメディア理論ではどう解釈されるのだろうか。それが嘘であっても説得力を持つ場合があるから恐ろしいのではないかと思う。ナチスドイツの宣伝というものをもっと深く学ぶ必要があるのではないかと思う。僕は論理的に正しいことを求めていろいろなことを考えているが、論理的に正しいからといってその考えが主流派になるとは思っていない。三浦つとむさんのように優れた人でさえマルクス主義の陣営では主流派にはなれなかった。人々が論理的に深くものを考えるのはとても難しい。だから誤謬に陥ったとしてもそれは、対象が難しいものであればあるほど仕方のないものだ。だから、三浦さんは誤謬について深く考えるように勧めていたし、そのセンスを磨くことこそがかえって真理をつかむことになると僕も思っている。決して善意や正義では論理的な正しさは理解することが出来ない。「周りの指摘が過剰なので偏見を強化しちゃいました」という評価は正しくないだろうと僕は感じている。あの程度の言説で強化される偏見などは、最初から強く存在するのだというくらいの自覚が欲しい。そして、過剰に反応することで、それがさらに強化されるのであって、それは差別反対運動の様子などを見ているとよく分かる。僕の指摘に間違いがあるなら、そこを論理的に冷静に指摘すればいいだけの話で、もし、誤謬の指摘に間違いがないと思えれば、その点では確かにそうだから、誤謬には気をつけようというだけですむことではないかと僕は思う。もっとも、あの反応に対して、あれは過剰反応では無いという認識をしているのなら、議論の前提が共有出来ていないので、そこから先は議論にはならないと思うが。「あくまで「論理」の問題としてのみ(というより、自分が読み取って欲しい枠組みでのみ)読み取るべきだとするのは、議論をする者としてあまりに無責任(うさんくさい)です。」という意見に対しては、「議論」というものの認識が違うということで反論させてもらう。僕は、chikiさん以外にはトラックバックを返していない。それは、他のものはまったく前提を共有出来ないだろうと思ったので、議論にはならないと判断したからだ。それは、相手に対する批判であって、それは批判である以上、自分の基準で相手を切るのは当然のことだ。僕もそうしているので、僕はそのこと自体に文句を言うつもりはない。いくらでも自分の基準で僕のことを切ってもらってもけっこうだと思っている。それが批判というものだ。しかし、議論というのは、少なくともそこで論じている前提というものが共有されて、その前提の下ではどのような結論が出てくるかという論理的判断が出来る人間の間でなされなければならないと僕は考えている。前提の共有と論理的判断能力を有するということが議論が成立するための必要条件だ。単に対立したことを語り合っているだけのものは僕は議論とは呼ばない。その論理が正しいかどうか判断出来る人間同士で議論しないと、水掛け論に終わるだけだ。読みとって欲しいなどという願望を僕は持っていない。論理的な正しい判断をしてくれと要求しているだけだ。僕が意図したことでないことを読みとって、それに批判を投げつけるのはかまわない。しかしそれには、必要なら反批判が返ってくるということだ。それは議論ではないのだから、僕も僕の基準で読みとって批判を返すというだけのことだ。それが気に入らないのなら批判をすべきではないと思う。世の中には議論が簡単に成立すると思っている人もいるようだが、日本社会において議論と呼ぶに値するものはほとんど無い。今の国会を見るとその堕落ぶりはひどいものだと思う。僕がもっとも水準が高い議論だと思うのは、神保哲生・宮台真司両氏のマル激での議論だ。あれほどの高いレベルは望まないが、議論と呼ぶのなら、前提の共有と論理的判断の共有くらいはしたいものだと思う。chikiさんのこの言葉に対する反批判は、「議論」という言葉に対する概念が違うということを言っておこう。このあたりでアップして、さらに続きを考えていこうと思う。chikiさんとは、議論の段階で言えば、今は共有出来る前提を探っている段階だと僕は認識している。
2006.05.22
コメント(0)
-
「数学屋のメガネさんへの再批判。」に対する反批判 1
chikiさんからもらった批判(「数学屋のメガネさんへの再批判。」)を読んで驚いた。これは、実に見事な批判だ。と言うと何か敗北宣言をしているようだが、初めてまともな批判をもらったという驚きと、これだけ見事な論理展開を見せてくれたchikiさんに、正直言って非常に尊敬の念を抱いている。しかし、だからなおのこと、納得するまでこれに反批判を送りたいと思う。chikiさんが、途中で嫌気がさすようなら無視していただいてもかまわないが、これだけ見事な論理を語る相手と議論が出来るならば、こんな素晴らしいことはないと思っている。まず納得出来ないことの第一だが、「「フェミニズム」をひとつの統一主体であるかのように論じること&求めることの問題点」と語られている部分だ。僕は、あのエントリーで、冒頭に語ったように、行き過ぎたフェミニズムということを考察して、論理的に逸脱する可能性というものを考察している。だから、「フェミニズム」一般について論じたのではないし、一つの統一主体だなどと主張してもいない。だから、そのように読みとれるなら、どこでそのように読めたのかを教えて欲しい。そこは、もしかしたら、僕の表現が間違えているかも知れない。これだけ見事な論理を展開する人だから、単なる誤読ということはないだろう。だが、それが表現の間違いであれば、訂正してすむことではないだろうか。人間は誤謬から逃れることは出来ない。単純なミスも許さないということでは、何も言えなくなってしまうのではないかと思う。僕の趣旨は、あくまでもフェミニズムの考えが逸脱する可能性の考察にある。もし僕の表現に、現実のフェミニズムを十把一絡げに扱っていると思われる部分があって、誰が読んでも文脈上そう読めてしまうということが理解出来れば、それは僕の間違いだと認めることが出来る。しかし、それがそう納得出来るまでは、やはりその指摘は受け入れることが出来ない。次に納得出来ない部分は、「Wikipediaというものの性質やソースの取り扱いに対してまったく配慮がないというメディアリテラシーの問題」として指摘されている部分だ。僕が語ったことは、フェミニズム一般の批判ではない。あくまでも逸脱する可能性のことを考えたものだ。ウィキペディアに対しては、「基本的な情報」という書き方をしたが、これは、フェミニズムというものに対して、一般の人が求める「基本的な情報」ということで考えたもので、それだからこそ逸脱の可能性を検討出来る対象として選んだものだ。ここに書かれたことがフェミニズムの正しい定義だとして選んだのではない。「論争中の論点に対して機能する政治性の問題」というのは、具体的には何を指すのだろうか。僕が発言することで、政治的な影響があるという判断をしているのだろうか。そこまで買いかぶってくれるなら僕も嬉しいのだがそうでもないようだ。これは、その指摘そのものがよく分からない。僕のブログなど、一日にせいぜい200~300人程度が訪れるだけの所だ。そこのどこに政治性の問題があるのだろうか。それとも、インターネットでの発言はすべて政治性を帯びるということなのだろうか。そのような言い方は、他人の自由な発言に対して、「政治性」という言葉で制限をかけることにはならないのか。「「極論としての○○を批判する~」という議論スタイルそのものが持つ問題」というのは、どこに問題があるのかが実際には僕には分からない。極論を考えるというのは、誤謬論ではごく普通のテクニックに過ぎないと思っているからだ。誤謬は逸脱から生まれる。それだったら意識的に逸脱を起こすのは極論を考えるのが一つの方法だ。この方法論に問題があるということが、僕には今のところ理解出来ない。例えば、僕が現存するフェミニズムそのものの批判を意図して、それが極論に達するところまで想像をふくらませて、フェミニズムそのものの批判としたのなら、それは「「極論としての○○を批判する~」という議論スタイルそのものが持つ問題」と言えるだろう。しかし、僕は、あくまでも誤謬論として極論を設定して、その誤謬可能性を追求しているのだ。その誤謬論のどこに問題があるかを指摘してもらわないと、僕は決して納得しないだろう。「「たとえ善意から出発した○○であろうとも、それが極論にまで達すれば論理的には間違える」というのはどんな論理にも当てはまるにも関わらず、「他の思想と比べてかくも間違えやすい」という論述もないまま」という指摘がなされているが、これは後のエントリーで何回か触れているので、僕は、これを取り上げた理由は述べていると思っている。他の思想と比べてということでいえば、同じように逸脱した思想としてのマルクシズムとの相似性を感じている。虐げられ、不当に抑圧されているというルサンチマンが、逸脱する可能性をはらんでいる。「「フェミニズムのうさんくささ」を証明したつもりになっている」ということは全くの誤読だと僕は感じている。だいたい「うさんくさい」というのは、個人の感情であって証明出来ることではないのだ。それを証明したというふうに受け取るのは過剰反応だ。僕がいくら論理にこだわる人間でも、自分の感覚を証明しようとは思わない。僕がうさんくささを感じるのは、絶対的な正しさをもっているかのように、フェミニズムの前提が作用して、それで現象を切り刻んでいくように見えることに対するうさんくささの感覚だ。それは決して絶対的な正しさを持っているわけではないのに、人々にそのような圧力を与える。これが「イズム」の恐ろしさであり、フェミニズムという「イズム」もそのようなうさんくささを持っているというのが僕の感覚だ。これは、僕の感覚であって、誰もがそのようなものをもっていることを証明したのではない。同じような感覚を持っていると表明してくれるのは歓迎するが、誰もがそのような感覚を持っている、あるいは持つべきだなどという主張は僕にはない。「Wikipediaの例を鵜呑みにしたうえで」という指摘も納得が出来ないものの一つだ。あのような例は、逸脱したフェミニズム思想からは必然的に出てくるものだという主張が、僕の中にあるものだ。もしも、あのような例が、逸脱したフェミニズム思想から生じないのであれば、そのことをこそ証明すべきではないのか。石原慎太郎氏の言葉に対する指摘も納得がいかないものだ。その部分を全文自分のエントリーから引用すると次のようなものになる。「このような極論からの批判は、論理的正当性も伝統も無視したものになる。だから、他の視点を持っている人間からはそれが行き過ぎだと思われてうさんくさい目で見られるようになるだろう。このような極論に対しては、「石原慎太郎東京都知事は、都議会定例会において、「最近、教育の現場をはじめさまざまな場面で、男女の違いを無理やり無視するジェンダーフリー論が跋扈(ばっこ)している」、「男らしさ、女らしさを差別につながるものとして否定したり、ひな祭りやこいのぼりといった伝統文化まで拒否する極端でグロテスクな主張が見受けられる」、「男と女は同等であっても、同質ではあり得ない。男女の区別なくして、人としての規範はもとより、家庭、社会も成り立たないのは自明の理だ」と強調し、ジェンダーフリー教育を公人の立場で公式に批判した。」と、ここに書かれているように、石原氏の批判が正当なものとして論理的には判断出来る。僕は、政治家としての石原氏には批判的だが、極論としてのジェンダーフリーに対するこの批判は正当だと思う。」僕はあくまでも、「このような極論に対しては」「石原氏の批判が正当なものとして論理的には判断出来る」と語っている。この仮定を取り除いて、石原氏の語ったことが事実であるかのように扱っていると批判するのは的はずれではないか。仮言命題というのは、仮定を置いて論理を展開するのである。それが「仮定」の話であるのに、その事実性を云々するのは、論理的な的はずれではないのか。僕のエントリーを読んだ人が、石原氏が語ったことがすべて正しいと受け取って誤読するという指摘だったら、その批判を僕のミスだと認める。仮言命題の扱いに対しては、論理に慣れていない人には難しい。だから、あれは仮定の話だといっても、本当の話だと誤読する人は出てくるかもしれない。そのような指摘だったら僕も納得するが、論理の問題に事実を対置しておかしいではないかという指摘は納得出来ない。論理の批判なら論理に対して行うべきだ。これだけ見事な論理を展開してくれるのだから、そのような批判を期待している。とりあえずはここまででアップする。しつこいと思われるかも知れないが、納得出来るまで反批判を送り続けたいと思う。
2006.05.21
コメント(0)
-
事実としての『フェミニズムの害毒』
僕は、フェミニズムの持つ論理の暴走性というものに注目をし、それに気をつけなければ真理が誤謬に転化するのではないかという、第三者的な視点を提出しているのだが、どうもフェミニズムの側にいる人にはそれがひどく気に入らないようだ。どのトラックバックを見ても、フェミニズムにそのような論理的な暴走性はないということは書かれていない。フェミニズムはそのような主張はしていないとか、実際にフェミニズムが暴走した実例を提出せよというようなことは書かれていた。そこで仕方がないので、林さんの『フェミニズムの害毒』から、林さんが暴走した逸脱したフェミニズムが引き起こした害毒だと受け取っていることを事実として提出してみたが、林さんからの引用というのがまた気に入らなかったようで、これも「フェミニズムではない」という言葉が返ってきたようだ。どうも論理が通じない相手と論理的な会話をするのは難しい。僕が論じているのは、フェミニズムという考え方の暴走性であって、フェミニズムそのものが間違っているという議論ではないのだ。だから、林さんからの引用の事実も、あくまでも、フェミニズムという考えが暴走したら、このように受け取って間違った判断をする人たちが出てこないだろうかと言うことを語っているのである。だから、フェミニズムにそのような暴走性がないというのなら、それはフェミニズムではないということを言うのではなく、フェミニズムの論理からはそのような逸脱が生まれてこないと言うことを説得的に述べなければならないのではないだろうか。逸脱するのではないかと言うことを問題にしているのに、逸脱したものを指して、それはフェミニズムではないと語るのは論理的な反論になっているのだろうか。『フェミニズム』(竹村和子・著、岩波書店)には、フェミニズムについて次のように書かれている。「フェミニズムの意味は、「(両性の平等という理論に基づいた)女の権利の主張」ということに対しては、フェミニズムの側にいる人間たちも同意するのだろうか。この本には、フェミニズムの前提として次の二つもあげられている。「一つは、少なくともフェミニズムが存在している社会においては、女の権利は奪われており、ひるがえって男の権利は守られていること(そう認識されていること)、もう一つは、性的に抑圧されている者(「女」と呼ばれている者)は、「女」という立場を維持したまま、その十全な権利を主張していくということである。」これにも同意するだろうか。同意しなければ仕方がないのだが、もしこのことに同意するのなら、この前提が、論理の逸脱をもたらす可能性というものがあるというのが僕の主張だ。それに対する反論ならば、そのような論理の逸脱はないということをいわなければならないのだが、何故事実を要求するのだろうか。上の前提は、その成立する条件が正しく把握されている限りにおいては正しい。しかし、その条件が正しく把握されていなければ容易に誤謬に陥る。その条件は、簡単に誰も間違わずに判断出来るものだと、フェミニズムの側にいる人間たちは主張するのだろうか。どのような具体的場面でも、「女の権利は奪われており、ひるがえって男の権利は守られている」ということが正しく判断出来るだろうか。それは間違えることはないのか。間違えた場合は、それはフェミニズムではないと切って捨てれば世間は納得するのか。「性的に抑圧されている者(「女」と呼ばれている者)は、「女」という立場を維持したまま、その十全な権利を主張していく」という発想からは、女であるという理由だけを自分が不当に扱われているということの根拠にするという間違いを生じないと、自信を持って言えるのだろうか。僕が問題にするのは、まさにこれらの発想から生じるかも知れない論理の逸脱の方なのだ。林さんの著書から引用するのは、林さんが語る事実というものが、このような発想から生まれた、本当の意味でのフェミニズムに対する誤解から生まれた現象のように見えるからだ。林さんは、それが間違ったフェミニズムだとは思っていないが、その間違ったフェミニズムは、本当のフェミニズムとは完全に無関係なのか、というのが僕の疑問だ。誤謬というのは、真理とまったく違うものとして存在しているのではない。真理の認識において逸脱が生じるからこそ誤謬が生まれるのだ。本当のフェミニズムが正しいものであったとしても、逸脱すれば誤謬になる。現実の逸脱による誤謬から生まれたフェミニズム攻撃は、そんなものはフェミニズムとは関係ないとして無視していればすむ問題なのかということだ。林さんはフェミニズムの変質を論じている。ということは、林さんも、最初の認識では、フェミニズムを男女の本当の平等を目指すものと考えていたわけだ。しかし、フェミニズムは、その理想を目指すのではなく、矮小化された女性の主張を押し通すだけのものになってしまったと考え、それが害毒をもたらしていると主張している。林さんが、矮小化された女性の主張だと考えているものは、フェミニズムからは生じないものなのか。真理の条件を逸脱すれば、そのような矮小化が起こる危険はないのか。そのような発想が全く出てこないフェミニズムは、やはり誤謬に対して鈍感だと思う。無謬思想をもった「イズム」は、かつてのマルクシズムがそうであったように、非常に危険な思想になる。フェミニズムは、もっと誤謬に対して敏感になるべきだ。誤謬というのは、人間の認識にとっては本質的なものである。誤謬から逃れられる人間などいない。だから、誤謬を犯すことは少しも恥ずかしいことでもないし、マイナスの評価をもたらすものでもない。誤謬を誤謬と認識出来ないことが「構造的無知」として大きなダメージになる。「構造的無知」にとらわれた人間は、しばしば戯画化されて描かれる。戯画化されたフェミニストが語られるのは、反動的な悪意ある宣伝ばかりではない。実際に「構造的無知」があるから、そこを捉えられて戯画化されるのである。林さんがこの本で語っている「青い鳥コンプレックス」というものは、フェミニズムの逸脱からは生まれてこない発想だろうか。林さんによれば、これは次のように説明されている。「母親が日常生活には幸せがないと思い込んで、生き甲斐や幸せや「自己実現」などを、家庭の外に探し求めるという心理を指すものである。この心理に取り憑かれると、女性たちは母を捨て妻を捨てて、「生き甲斐」を手に入れたいと思い、外へ外へと駆り出されていく。夫の世話や子どもの世話は価値の低いもの、ばからしいものと感じられ、外の世界の「仕事」や「文化」や「芸術」などがバラ色の素晴らしい世界だと感じられる。」これは、フェミニズムの考え方が逸脱したときに出てくる発想ではないと言えるだろうか。もちろん、人には個性があって、外に出て行くことの方がふさわしいという女性もいるだろう。それが、女性であるから我慢させられるということにつながれば、その不当性は明らかだ。これに反対するフェミニズムは真っ当なフェミニズムである。その能力に応じて社会進出する道が保障されるべきだろう。しかし、その能力を考慮せず、誰もが社会進出するべきだと考えればそれは逸脱した発想だ。自分の個性と能力に応じた希望を持つことを教えることは、決して真のフェミニズムに反することではないだろう。しかし、そう主張したとき、それが男であった場合、フェミニストはそれに我慢出来るだろうか。内田樹さんは、そのような主張を多くしている。だいたいが真っ当な常識的な主張だ。その時に、フェミニストたちは、その真っ当な主張を受け入れられるだろうか。林さんは、この本で、子どもを大切に育てたいという素朴な気持ちを肯定すべきだと提案している。それを、女を家庭に縛り付ける思想だと、逸脱したフェミニズムは考えるのではないだろうか。働いて社会に出ることこそが正しいと一面的に考える発想は、フェミニズムの逸脱からは全く出てこないのか。子育てに自分の個性を見出し、それが幸せだと考える女性がいても、それは当然なのではないだろうか。林さんがこの本を書いた頃は、専業主婦願望が高まった頃だったらしい。それを、林さんは、家庭的な愛情を無視して育てられた世代が抱いた反動的な願望だと解釈している。林さんの教え子の世代は、ちょうどその母親たちが、外で働くことこそが女の開放という考えに染まっていた世代だったらしい。だから、そのために家庭では母親不在の状態が多かったらしい。その反動として、家における母親の重要性や、母親を求める気持ちが子どもの世代に強くなるだろうことは容易に想像出来る。この専業主婦願望の増加に対して、林さんは次のように書いている。「フェミニストたちは、その現象の中にマイナスの意味しか読みとることが出来ない。その典型が、小倉千加子の評論(『読売新聞』1998年4月8日付夕刊)である。彼女は女子大生の専業主婦志向とは、「自分に正直に生きる」ことを捨てて、親の期待通りの「幸せな指導」をするように「妥協」した産物だと断じている。そのような見方の背景にあるのは、女子学生は卒業したら働きたいと思うのが当然であり、「幸せな」結婚をしたいなどというのは親の願望に引きずられた「不正直な」心だという見方である。何と単純で無神経な見方であろうか。」この小倉千加子氏はフェミニストでは無いという批判をしたい人がいるかもしれないが、問題は、「単純で無神経な見方」が、フェミニズムの逸脱として生まれてこないかということだ。問題は逸脱ということなのである。これを誤謬として、逸脱をちゃんと意識出来る人間なら、その誤謬を犯すことから逃れられる。しかし、誤謬をちゃんと認識出来ない人間は、いつかは誤謬にとらわれるだろう。将来の誤謬から逃れるために、逸脱の可能性をちゃんと認識するということが、誤謬の研究の目的なのである。小倉氏が考えるような女子大生もいただろう。しかし、それがすべてであるかどうかは分からない。林氏が解釈するような女子大生がいてもおかしくない。双方が、自分が考える女子学生しかいないと主張していたら、双方が間違っていると言うことになるだろうが、フェミニズムの前提を教条主義的に信奉してしまったら、フェミニズムの方が誤謬に陥る可能性が高いと僕は思う。だからこそ、フェミニズムの陣営は誤謬に敏感でなければならないのだ。
2006.05.21
コメント(1)
-
行き過ぎたフェミニズム批判としての『フェミニズムの害毒』
行き過ぎたフェミニズムなどもはや存在しない。それはもう終わった問題なのだ、というような意見をちらっと目にした。何を今さらそんなことを問題にするのか、というわけだ。しかし、これはずいぶんとおめでたい無防備な考え方だなと思う。そう考える人は、いい人ではあるのだろうが、手練手管に長けた反動側の攻撃にはひとたまりもなく潰されてしまうだろう。実際にはフェミニズムというのは、その論理構造からいって、常に行き過ぎる可能性をはらんでいるのである。だから、行き過ぎに注意していないと、うっかり失敗することが必ずある。反動側の人間はその失敗を見逃さず、いつでもフェミニズムを叩けるというチャンスをうかがっているだろうと思う。誤謬に対して鈍感なフェミニズムは、リベラルの信用も落としてしまうことになるだろう。面白いことに、内田樹さんが『フェミニズムの害毒』の書評を書いているのだがそこにこのような記述がある。「だから、フェミニズムが近代的システムの硬直性や停滞性を批判する対抗イデオロギーであるかぎり、近代文明に対する一種の「野性」の側からの反攻であるかぎり、それは社会の活性化にとって有用であると私は思っている。だが、有用ではありうるが、それは決して支配的なイデオロギーになってはならない質のものである。(ヒッピー・ムーヴメントや毛沢東思想やポルポト主義が支配的なイデオロギーになってはならないのと同じ意味で。)それは「異議申し立て」としてのみ有益であり、公認の、権力的なイデオロギーになったときにきわめて有害なものに転化する、そのようなイデオロギーである。」これは、フェミニズムというイデオロギーが容易に誤謬に転化するものであるということから来る内田さんの直感ではないかと僕は思う。支配的なイデオロギーが誤謬に転化した場合、どのように恐ろしいことが起こるかは、「毛沢東思想やポルポト主義」によって証明されている。『フェミニズムの害毒』は1999年に出された本だ。8月の出版だから、今年の夏で7年になる。だから、ここで語られていることはもう克服されたという人もいるかも知れない。しかし、僕はここで語られているような害毒が簡単に克服されたとは思えない。それは、日常生活のあらゆる場面で出会いそうな現象だからだ。特別な状況で起こるものではないのである。ここで語られていることは本物のフェミニズムではないという意見もあるだろう。誤解されているのだというわけだ。しかし、本当に深刻なのは、フェミニズムを本当には知らない人間は、たいていこのように誤解するということなのだ。誤解しているだけだからフェミニズムには責任がないと簡単に済ませることは運動論的な間違いだと僕は思う。これが誤解であるなら、誤解であることを分かるように示すことこそが大事なことなのだ。誤解する方が悪いという姿勢は、運動論的に運動の弱体化をもたらすだけだ。それは、誤謬に対して鈍感な姿勢なのである。さて、日常的に見られる「フェミニズムの害毒」(これは文脈的に理解するなら、林さんが捉えているフェミニズムということの理解から帰結される害毒、という意味に取らなければならない)は、林さんの本ではまず次のようなものが登場する。林さんの妻が女性だけの研究会に行ったとき、会が終わってから食事に誘われたらしい。その時「夫が待っているから」と断ったことに対して、「あなたは自立していないのねえ」とイヤミを言われたという。このとき、林さんは、「「夫のために早く帰る妻は自立していない」という公式を当然のように信じている女性たちがいると言うこと」に驚いていた。そして、これを「フェミニズムの悪影響のためである」と断じている。これに対して、その女性研究者はフェミニストではないとか、間違ったフェミニズムを基礎にして考えているから誤解するのだといっても、林さんはおそらく納得しないだろう。もちろん、林さんを納得させる必要はないと思っているフェミニストがいたら、ここから先の議論は必要ない。林さんのような保守主義のオヤジなどは、頑固頭の分からず屋だから、そんなオヤジが何を思おうと関係ない、というフェミニストだったら何も議論する必要はない。そう言うフェミニストには、勝手におまえらの運動をしろよ、というだけだ。相手のことを自分たちが理解する必要がないと思っている人間を、こちらから理解してやろうという優しさを見せるほど僕は人間が出来ていない。フェミニストがそう言う姿勢を持っているなら、やはりフェミニズムはうさんくさいものであり、決して社会の主流になってはいけないイデオロギーだという内田さんの主張を支持したい気持ちになるだけだ。もし、林さんのようなオヤジを、分からず屋の頑固オヤジだということで切り捨てるなら、男社会の論理が分からない分からず屋のフェミニストなど切り捨ててしまえという考え方を批判出来ないだろうと思う。林さんのような考え方を切り捨てて、自分たちの主張だけを通そうとするのは、フェミニズムにとっては決定的に矛盾したことになるのではないか。林さんのようなオヤジを受け入れることは、フェミニズムにとっては損なことのように見えるかも知れないが、そうすることによってフェミニズムは確実な真理性を手に入れることが出来るのだ。受け入れるというのは、何も主張に賛成しろということではない。林さんの批判は、対象が「行き過ぎたフェミニズム」に限定される限りでは正しいのである。その正しさを受け入れるべきだということだ。そして、その正しさを受け入れた上で、行き過ぎではない、正しいフェミニズムの主張があるという姿勢を持つべきなのである。行き過ぎを指摘されただけで感情的な反発が起こるようでは、どうやって正しい主張を論理的に説得出来るだろうか。行き過ぎの指摘を認め、そのような誤謬に陥る可能性に注意して、正しい方向を探ることが出来れば、林さんのような人とも連帯が出来るのである。「愛情で結ばれた関係の中では、どちらが支配するとか、どちらが自立しているのかということは問題にならない。愛情という観点を「縛るもの」とか「自立を妨げるもの」と規定したときから、そして『愛という名の支配』などという本が出て、愛はすべて支配の道具であるかのように思う女性たちが増えたときから、フェミニズムは狂い始めたのではないだろうか。」という林さんの問いかけに対して、そんなものは間違って理解している方が悪いといって済ませるのは、運動としてどうなのかということだ。このように間違って受け取られる責任は、フェミニズムの方には一切無いのだといっていられるのだろうか。それは、誤謬に対してあまりにも鈍感なのではないかということだ。このようなことを語ると、おまえが相手の論理的間違いを指摘するのも同じではないかという屁理屈を言ってくる者がいるかもしれない。僕の方は、それが何故論理的に間違えているかをかなり詳しく説明しているつもりなのだが、人によっては切って捨てられているように感じるかも知れない。そう言う屁理屈に対してつまらない議論をしたくないのであらかじめ述べておく。ブログにおける対話は運動ではない。個人的な論説のやりとりに過ぎない。だから、そこで理解が足りなかったり間違えたりするのは、何ら社会的な影響を持つものではない。しかし、フェミニズムが不特定多数の人に呼びかける運動である限りでは、その影響で勘違いをする人間が出てきたら、運動としてその現象を考察しなければならないのだ。僕のように市井の人間が何を語ろうと、その影響力の小ささからいえば、たとえ間違ったことを語っても、実質的な影響力がなければ何ら問題はない。それは言論の自由に属することに過ぎない。しかし、フェミニズムの指導者が語ったことが、たとえそれが誤解されるようなことがあったとしても、その誤解に対してさえ責任が生まれることがある。それは社会的影響の大きさによるのだ。林さんは、「この母親の言葉の背後には、「亭主の世話をするなどは、女性の生き甲斐とすべきことではない」とか「女性の仕事としては程度の低いことだ」という考え方が、透けて見える。こうした心理こそ、まさにフェミニズムが広めているものなのである。」とも語っている。これに対しても、フェミニストたちは誤解だと言って切って捨てたくなるだろう。しかしこのような誤解は切って捨てただけで無くなるのか?フェミニズムは、このような誤解を決して生まない完璧な理論なのか?そう思うのは、あまりに誤謬に対して鈍感なのではないか。僕がフェミニズムに関連したエントリーを書くきっかけになったのは、筆坂秀世さんのセクハラ問題に関連して、ライブドアのコメント欄からたどっていった「2006-04-26 16:13:03 / 時事問題 筆坂さん・・・・・。」という文章を読んだことだった。そこに書かれていた「セクハラ問題にちょっとでも興味ある人なら分かると思うけど、筆坂氏はアウトよ。」という言葉がきっかけだった。この事件については、細かい具体的な事実は何一つ知らされていない。セクハラというデリケートな問題で、事実が分からないのに、それが不当だという判断が簡単に出来るものではない。しかし、このエントリーでは、何故「アウト」なのかは何も語られず、「セクハラ問題にちょっとでも興味ある人なら分かる」と言っているだけだ。これは、セクハラ問題というのは、女性が訴えればそれだけで「アウト」になるということなのだろうか。これは世間に流通している「フェミニズム」の悪影響ではないのだろうか。世間に流通している「フェミニズム」は本物ではないというようなことをいっても仕方がないのではないか。これが「フェミニズムの害毒」であると受け取りたくなるオヤジはたくさんいると思う。筆坂さんは、『日本共産党』(新潮新書)の中で「私は、三人に対し、チークダンスを踊ったこと、デュエットで腰に手を回して歌ったことは事実だと認めた。これ以上でも、これ以下でもないからだ。同席した秘書も、その女性が、私が「帰ろう」と声をかけるまで、大いに楽しんでいたと証言している。それが何故セクハラという訴えになったのか、今もって不可解と言うしかない。」と語っている。これは、筆坂さんの側の主張だから、これが正しいと言うことは直ちには言えない。しかし、同じように、相手の女性の主張が正しいともすぐには言えないだろう。少なくとも、今のところ真相は分からないということが正しい論理的な理解だ。それが何故「アウト」だと即断されてしまうのか。セクハラ論議のおかしさは、フェミニストたちはまったく疑問を感じないのだろうか。セクハラは、それを受けた女性の側に判断の基準があるということに疑問を持たないのであれば、僕はセクハラ論議は、フェミニズムの悪影響を受けていると思うだろう。セクハラという犯罪行為を断罪するのであれば、女性の感覚という観念的な基準ではなく、誰が判断しても納得がいくような客観的な基準が提出されるべきではないか。論理の問題に対して、事実を提出しろというような意見を言う人がよくいるが、論理の問題はまず論理で考えることが大事なことだ。事実の問題で言えば、筆坂さんのセクハラ問題が、筆坂さんが「アウト」だというのなら、何故「アウト」なのか事実を示すべきだろう。これは論理の問題ではなく事実の問題だから、事実なしに「アウト」という判断は出来ないのだ。
2006.05.21
コメント(2)
-
ジェンダーへの疑問
竹村和子さんは『フェミニズム』(岩波書店)の中で、ジェンダーについて語っている。ジェンダーは普通次のように考えられている。「生物学的な所与の性差と考えられている「セックス」と比べ、「ジェンダー」はセックスの差異の上に構築される「社会的・文化的な性差」、いわゆる「男らしさ」や「女らしさ」だと理解されている(この因果関係に対しても、後に疑義が突きつけられる)。」ジェンダーにとっては、社会というものが重要なキーワードになる。このジェンダーに関しては、フェミニストの間でもまだ意見が分かれている部分があるそうだ。それは後ほど見ることにしたいと思うが、僕は、ジェンダーの考え方そのものの中に論理の逸脱の危うさを感じるところがある。竹村さんは「人は女に生まれない、女になる」というシモーヌ・ド・ボーヴォワールの言葉を引用しているが、僕はこの言葉の解釈に、拡大解釈を生みかねない危うさを感じる。女というのが抑圧のシンボルだと思っている人は、社会によって女にされることに不当性を見たくなるだろう。しかし、それは「すべて」不当なことなのか。この言葉は、「すべて」という言葉に通じる論理の逸脱の可能性を感じさせるものだ。人間というのは本能が壊れた生物だといわれている。人間は、そのまま放っておいたのでは人間にならない。人間の間で、社会の中で生活することによって人間となっていく。人間が人間になるためには教育というものが不可欠の要素になる。狼に育てられた人間は、外見は人間のように見えても人間にならない。社会によって女にされることがすべて不当だったら、同じような論理で、社会によって人間になることも不当だということになってしまうだろう。そうすると人間は、本質的には野蛮で動物的になることこそが正しいあり方だということになってしまう。欲望を開放して、自分のやりたいことを勝手にやって、社会のことなど無視して生きるのが人間的だということになってしまう。林道義さんの『フェミニズムの害毒』(草思社)によれば、フェミニズムというのはこのようなエゴイスティックな存在であると断罪されている。社会を無視したエゴイズムこそが正しいと主張するのがフェミニズムだというふうにされている。これは、フェミニズムに対してかなり偏見のある悪意ある見方だとは思う。しかし、逸脱した間違ったフェミニズムであれば、そのように見えても仕方がないかも知れない。林さんの間違いは、この本の題名を『逸脱したフェミニズムの害毒』としなかったことかも知れない。いずれにしろボーヴォワールの言葉を教条的に受け取ったら逸脱する恐れがあるだろう。人間にとっては社会の中で生きていくことは本質的なものである。社会の影響を受けることが人間の本質であれば、それをすべて否定することは出来ない。「すべて」ではなく、どの場合にその影響が不当になるかという細かい検討が必要なのだ。ばかげたジェンダーフリーの主張には、その細かい検討が抜け落ちていると僕は思う。さて、フェミニストの立場から問題にしているジェンダーの側面を、竹内さんの本から拾ってみよう。「そもそもジェンダー規範の問題点は、まず第一に、ジェンダー規範は「男」と「女」という二極化されたカテゴリーを作り出し、そのどちらかに人を当てはめるということ、第二に、このジェンダーの二分法は階層秩序を持つものであり、<二つの差異>ではなく、<一つの差別>を意味しているということだろう。」と竹内さんは語っている。この第二の問題を分かりやすくいえば、男を基準にして「人間」という範疇を作り上げているということだろうか。つまり、男ならば無条件で「人間」の中に入れてもらえるが、女はなかなか「人間」の範疇に入れてもらえなかった歴史があったということだ。これは実際には女だけではなく、社会的に差別される人々は、みな権利の主体としての「人間」の範疇からは除かれていた。だから、社会的に認められていない権利というものが、そのような差別される人々には多く存在したということだ。これは不当なことであり、社会を形成する「市民」であれば誰でも「人間」の範疇に入れなければならないだろう。そして、その「人間」がどのような権利を持っているかという人間観を正当なものとして持たなければならない。この人間観が狂っていると、せっかく人間の範疇に入れてもらっても、かえって不利益を招くということにもなってくる。例えば、今の男社会のひどい雇用状況というものが、人間の労働として仕方がないものと受け取られてしまうと、同じ人間なんだから、女が同等に扱われてひどい雇用状況にいても仕方がないと結論しなければならなくなってくる。これは、雇用状況が本当に人間的かどうかが問われなければならないが、男と女が同等かということの方に目がいってしまうと、的はずれな雇用機会均等法などが出来上がる。女を人間の範疇から排除するのは不当だが、人間の規定そのものが狂っていると、人間の範疇に入れることが誤謬になるという由々しき状況が生まれる。ジェンダーの主張は、人間の規定が狂っていないかという誤謬にも敏感でなければならないだろう。正しい人間規定で、男の状況も改善されるなら、その状況でのジェンダーフリーの主張に反対する男はいなくなるだろう。第一の問題に関連しては、「フェミニズムは、<ジェンダーの廃絶>のために闘うのか、それとも<ジェンダーの平等>のために闘うのか」という問題が提起されている。男女が平等に「人間」の範疇にはいるのなら、生物学的な差異があるのは明確なのだから、それが社会的にもある種の差異として認められても、本質が平等ならそれで良しとするのか。社会的な差異をすべて取り除かなければ、ジェンダーによる差別はなくならないのかという問題だと思う。これは論理的には明らかだと思う。現実存在に対して「すべて」などという硬直化した規定をすれば、それは必ず極論に行き着いて誤謬になる。現実存在は、違う視点から見た判断で、条件によって違う扱いをすることこそが正しい。すべてを一緒くたにすべきではないのだ。<ジェンダーの廃絶>のために闘うフェミニズムはかなりうさんくさいものになるだろう。しかし、気分的にジェンダーが廃絶されないと、差別そのものが解消出来ないと感じるものも存在する。竹内さんの指摘では、性的マイノリティの問題が語られていた。性的マイノリティにとっては、男と女という区別が残る限り、その範疇にも入らない存在として、やはり差別されているという意識が残り続ける。このようなものに対しても、性的マイノリティを「人間」の範疇に含むということが常識化すればいいではないかという考えも出来るが、感情的なしこりが残る可能性はあるかも知れない。これは難しい問題には違いないだろうが、このような問題の解決のために<ジェンダーの廃絶>という戦略の方を選ぶとしたら、フェミニズムの運動は誤謬へ転落するのではないだろうか。<ジェンダーの廃絶>の道は、林さんに批判された道であり、それは正当な批判として僕には読める。現実存在に対して「すべて」という規定をするのは、やはり論理的に間違いなのだと思う。弁証法的に扱わなければ、どこかに間違いが出てきて、その間違いを攻撃されるということになってしまうだろう。フェミニズムが<ジェンダーの廃絶>という道を選ばなかったかどうかは、まだ本の先の部分を読んでいないので分からないが、もし失敗の歴史をもっているのなら、その失敗から深く学ぶことが出来なければならないだろう。<ジェンダーの平等>の道は、人間の規定が正しい限りでは正しいのだから、フェミニズムはその戦略の道を選ぶべきだろうと思う。ジェンダーという社会的な性差別が不当であることを証明するには、「社会」というものの深い理解も必要だろうと思う。社会は、個人が集まれば社会になるのではない。個人においては正しいことが、社会においては正しくなくなることも多い。個人においては、宗教的な信条は、何を信じようと自由だが、国家が一つの宗教に支配されるのは間違いだ。国家という社会的存在には信教の自由はない。個人は目に見えるが社会は目に見えない。だから、<ジェンダーの平等>においても、目に見えない社会のとらえ方を失敗するという誤謬の可能性が存在する。この判断においても、誤謬に対する敏感さを持たなければならないだろう。権力のない側が頼りにするのは、論理的な正しさ以外にはない。それがなかったら、どんなに出発点が正しい運動であろうとも、大衆的な支持を失い、理想を実現することは出来なくなるだろう。
2006.05.21
コメント(0)
-
フェミニズム理論の逸脱する可能性
単語に過剰反応して文脈理解をしない者がいるので、冒頭に一言断っておくが、これから述べることはフェミニズム一般の批判ではない。フェミニズムの理論において、正しい範囲のものが、いかにして誤謬に転化していくかという過程的構造について考察しようと言うものだ。真理と誤謬を対立した二つのものとして、相容れない固定化したものと考える人には、真理が誤謬に転化すると言うことは理解が難しいかも知れない。しかし、真理というものが、ある対象に対する認識において判断として存在することを理解するなら、その対象と認識との関係から、条件を逸脱して誤謬に転化する可能性があることが分かる。それが真理と誤謬との弁証法的関係だ。三浦つとむさんは、人間の認識に誤謬が伴うことを必然的なものとして本質と捉えた。誤謬というのは、頭が悪かったり・能力がなかったりすることで引き起こされるものではない。人間の認識がある種の制限を受けていることから、その制限を逸脱する可能性をもっていて、そこから必然的に生み出されるものなのだ。人間の視覚は、表面に見える部分しか捉えることが出来ない。後ろを見るには、後ろに回り込まなければならない。内部を見るには、表をはがしてそれを壊さなければならない。その制限の下で、見えない部分を見ようとすれば、確かなものの範囲を逸脱して誤謬に陥る可能性をもっている。この誤謬は不利益ばかりをもたらすものではない。人間は、たとえ認識に制限があろうともそれを越える方法を見出していこうとする。直接見えないものに対して、間接的に見ようとする努力をする。原子論などはそのような努力の末に見つけられた真理だ。だから、誤謬はより深い真理へのきっかけをもたらすものでもあるのだ。誤謬に鈍感な人間は、間違いに陥ったときにその間違いに気づかない。間違いに気づかないから、より深い真理に到達することもない。しかし、現実に間違いに陥ったときは、実践的な不合理が出てくる。認識においては間違いに気づくことが出来なくても、実践的に失敗がたくさん出てくるのだ。社会主義国家の誤謬も、マルクス主義という認識においてそれが自覚されることはなかった。だが、国家運営においての様々な失敗が、その誤謬性を明らかにしていった。もっと誤謬に敏感な指導者がたくさんいたら、社会主義国家は、あれほど悲惨な崩壊はしなかっただろう。世間で「フェミニズム」として理解されているものは、『フェミニズムの害毒』(林道義・著、草思社)によれば間違いに満ちたものとして理解されている。フェミニズムに対する悪意に満ちたこの本を取り上げていることに、フェミニズムの陣営は反発をするかも知れないが、悪意をもって理解されていることも、世間では「フェミニズム」だと見られているのだ。間違ったフェミニズムを語っている人間は、頭が悪いわけでもないし、反対の陣営のために悪意をもって語っているのでもない。正しい論理が条件を逸脱して誤謬に転化しているのである。そうであるなら、今正しい論理を語っているフェミニストも、誤謬に対して鈍感であれば、いつ条件を逸脱して誤謬に転化するか分からないと自覚するべきなのだ。逸脱のきっかけになるのは、対象の範囲を無自覚に広げることにある。エンゲルスがボイルの法則について語った相対的誤謬では、気体の体積と圧力の関係において、液化する臨界点においてその法則が誤謬に陥ることが語られていた。気体が液化するとき、その体積は著しく減少する。だから、その臨界点では気体と圧力に関係するボイルの法則が成り立たなくなることが分かる。このとき、この一つの誤謬からボイルの法則そのものを否定するのは、否定の行き過ぎであり、やはり逸脱した誤謬である。正しくは、ボイルの法則は条件付きで成立するという認識を持つことだ。そして、その条件を具体的に正確に求めることが、ボイルの法則に関してより深い真理の認識となる。フェミニズムに対してもそのような姿勢を持つべきだろう。それが正しい理論として通用する条件を正確に求める必要があると思うのだ。フェミニズムの場合、逸脱する可能性は情緒的な面からも考えることが出来る。フェミニズムは、不当に抑圧されてきた女性の解放を目指す運動から生まれてきた。不当に抑圧されてきた人々が、感情的に行きすぎると言うことは、日本における差別反対運動やアメリカの人種差別反対運動が持っていた行きすぎた考え方が発生する事実からも想像出来る。それは感情的な問題として同情出来るものではあるが、同情出来たからと言って容認することは出来ない。これを容認すれば、運動そのものが致命的なダメージを受けるだろうと思う。さてフェミニズムの基本的な理論を学ぶのに僕は、『フェミニズム』(江原由美子・金井淑子・編、新曜社)、『フェミニズム』(竹村和子・著、岩波書店)という本を選んだ。ここに書かれていることは大部分が論理的に正しいと感じたからだ。だから、これを本物のフェミニズムではないとする人がいたら、その人に対しては僕は何も語る言葉を持たないのだが、この本が「フェミニズム」の良心的な部分を代表していると理解している人なら、その良心的な部分が誤謬に転化する可能性があるのではないかという、僕の論理展開を理解して欲しいと思う。これは、良心的な部分に対する批判ではなく、ましてやゆがんだ理解から生まれた悪口ではないのである。竹村さんは、そのまえがきに当たる部分で次のように語っている。「一つは、少なくともフェミニズムが存在している社会においては、女の権利は奪われており、ひるがえって男の権利は守られていること(そう認識されていること)、もう一つは、性的に抑圧されている者(「女」と呼ばれているもの)は、「女」という立場を維持したまま、その十全な権利を主張していくと言うことである。これらの前提から類推される事柄は、社会の成員は「男」と「女」に二分され、この二つの性の間の力学に不均衡が生じていて、フェミニズムは、権利を奪われている女が、権利を過剰に付与されている男に対して意義申し立てをするものだという図式である。フェミニズムを語るものは、たいていの場合女と言うことになり、その女たちは男を「敵」と見て、男の特権に挑戦すると思われている。だからフェミニズムに直面した男は、時に女の舌鋒に驚き、恨み、ある時は女の挑戦を、風車に挑むドン・キホーテのように的はずれなものと見なしてやり過ごす。社会が--少なくとも日本の社会が--フェミニズムに対して抱いているイメージは、個別的な例は別にしても、現在の所は大なり小なりこのようなものだろう。」ここで語られていることは大部分が正しいだろうと思う。だから、条件を逸脱しない範囲において、つまり真理である限りにおいては、正しくものを考える男は反対しない。しかし、すべての社会現象に対して「女の権利は奪われており、ひるがえって男の権利は守られている」と主張されるように感じられたら、「風車に挑むドン・キホーテのように的はずれなものと見なしてやり過ごす」という男の態度が正しいものになってしまう。具体的な現象に対して、「女の権利は奪われており、ひるがえって男の権利は守られている」ということが納得出来る対象であれば、そこに意義申し立てをすることの正当性を認めるのは、男であろうと変わりはない。少なくとも、人権意識を持った男なら奪われた権利に対して意義申し立てをする方が正しいと判断するだろう。ところがこのときに、男は現代社会の構造に毒されていて、人権意識を持った男などはいないというような考え方を提出されると、そんなに信用されないのなら、男は女と関係なく生きていくだけさ、と憎まれ口を聞きたくもなってくる。このような逸脱する可能性が、フェミニズムはないと自信を持って言えるだろうか。また、このように逸脱する人間は、真のフェミニストではないと切り捨てて問題が解決するだろうか。フェミニズムの論理が逸脱して、誤謬に転化したときは、本来連帯して手を取り合える男もフェミニズムに対して反感を持つようになるだろう。鈍感なフェミニストはフェミニズムの信用を傷つける。それでは人権意識に欠けた、男社会の優位性という観念から抜けきれない男たちは、その間違った考えを攻撃してもいいと言えるだろうか。これは運動論的な問題になると思うが、そのような男の支援などは必要ない、そのような男は駆逐するだけだ、と考えるなら徹底的な攻撃をすることが正しくなるだろう。しかし、それは本当に運動として正しいのか。残念なことに、今の社会には自覚した男は少ないと思う。もし、そう言う男を全部駆逐しようとしたら、社会から男はほとんどいなくなってしまうだろう。そして、そのような攻撃的なやり方をすることを間近で見せられたら、リベラルな男たちも、その攻撃性に嫌気がさして女との連帯を放棄することだろうと思う。運動論的な戦略としては、今の大多数を占める封建思想をもった男たちを、何とかして理解者にする努力をする方が正しいだろう。その理解者にする努力は、正しい論理を主張して、間違いを排除していくという努力しかない。少しでも間違える可能性をもった主張をしたら、そこへの攻撃は激烈なものになるだろう。フェミニズムの考え方は基本的には正しい。だから、その反対者たちは、その基本的に正しい部分への攻撃は出来ない。だが、ひとたび間違いを見つければ、その間違いから出発してフェミニズムの全主張を否定しにかかるだろう。これは論理的には間違いだが、封建思想というバイアスがかかった男にとっては、その論理の間違いを理解することは難しい。「構造的無知」にとらわれてしまうからだ。『フェミニズムの害毒』という本は、フェミニズムの陣営からはひどい本のように見えるだろうが、著者の林さんという人は、ひどい封建思想の持ち主のようには見えない。せいぜいが穏健な保守主義と言えるくらいの人だろう。そのような人がフェミニズムの全主張を否定しにかかるということは、フェミニズムの運動の戦略の失敗ではないかと僕は思う。本来なら、林さんのような人でも連帯出来る方向を目指さなければならないのではないかと思う。そうでなければ、日本の大部分の男がフェミニズムに理解を示すということはないだろう。フェミニズムの考えの中の逸脱する可能性の部分と、逸脱した考えを批判して全否定しようとする反対の陣営の考えを理解することは、フェミニズムに対する深い理解をもたらすと僕は信じる。それは、単に知識としての歴史を知るよりも有効性のある知識になるだろう。
2006.05.21
コメント(0)
-
トラックバック先のエントリーに対する雑感
トラックバック先のエントリーでの批判はほとんど的はずれだと感じているのだが、部分的に気になるところを雑感として記録しておこう。まず「こんな主張誰がしてるの?」の中の次の部分だ。「ちなみに、「クラス名簿を男女混合にする」ってのは、あるかもしれない。しかしその真意は、「男女別にする正当性はどこにもない」というところからきているはずだ。もちろん、「男女混合」にもいろいろなものがあるだろう。家がお金持ちの順番とか(笑)、背の高さ順とか、学校から家までの距離が短い順とか。そのどれもが恣意的でしかない。もちろん、「あいうえお順」だって恣意的なのである。しかし、どんな順番も恣意的であるなら、その暴力的な要素が少なく、かつ調べるコストがかからないような順番がよいであろう。「あいうえお順」が最も正しいとは思わない。それに代わってより暴力的でない案があれば、僕はそちらに乗り換えてもいいと思っている。ただ現状ではそれが思いつかないからという理由で、暫定的に「あいうえお順」を支持している。」これは、論理的に極めておかしいのだが、本人にはその自覚はないかも知れない。本当は「男女別にする正当性は考えれば思いつく」のだが、ここでは百歩譲って、その正当性がないと前提しておこう。しかし、この前提を置いたとしても、そこから「男女別の出席簿を否定する」という論理的帰結は出てこないのである。もし、「男女別の出席簿を否定する」という結論を出したいのなら、「男女別の出席簿の不当性」を証明しなければならないだろう。それが論理というものだ。いったいどういう理由から「男女別の出席簿の否定」ということが出てくるのだろうか。それでも、まだ「男女混合の出席簿の方にこそ合理性がある」という主張があれば、それに変えるという理由も納得出来る。しかしそれは、「そのどれもが恣意的でしかない」と言うことを語っている。男女別の出席簿の不当性が言えないのだったら、恣意性という点では両方とも同じではないかと思う。どうして、男女混合の方の恣意性を選ぶのだろうか?「現状ではそれが思いつかないからという理由で」そうしているのなら、男女別の出席簿だって、他にいいものが思いつかないのだったら、どうしてそうしていけないということになるのだろうか。「男女別の出席簿に正当性がない」と主張するのはいいだろう。しかし、その主張から、「男女別の出席簿は駄目だ」という結論を出すのは論理的な間違いだ。それが極論に流れる論理の間違いにつながる。僕の指摘はここにあるのだが、論理のセンスが悪いとそこが分からないだろう。現場の感覚としては、「男女別の出席簿」には合理性があるといえるのだ。一目で分かる差異として男女というのは、視覚的な明確さをもっている。男女別というのは、クラスの生徒の全体の把握には、他の方法よりも感覚的につかみやすいという合理性を持っているのである。もちろん、この合理性は、他の方法でも解決出来る合理性だから、男女別でなければならないというわけではない。男女混合の出席簿でも、便利な方法が見つかればいくらでもそれに変えていけばいいのだと思う。だが、男女別がいけないという理由が、男の差別意識の現れだなどと言われると、僕はそんな理由は噴飯ものだと思うだけだ。いけないというのなら納得するだけの理由が欲しいし、積極的に変えていくのなら、そっちの方がいいという納得する理由も欲しいと思うだけだ。さて「数学屋のメガネさんのエントリー「フェミニズムのうさんくささ」への疑問。」というのは、これが「疑問」というものであれば丁寧に答える必要があるとは思うが、もし「批判」であるとしたらやはり的はずれだろうと思う。とりあえず「疑問」と受け止めて、その部分に答えたいと思う。「フェミニズム一般を否定するのではなく、極論としてのフェミニズムの批判」を始めた後、いつの間にか「行き過ぎた」「極論としての」が抜け落ちた「フェミニズムに対するうさんくささ」を問題化してしまうという、「特称命題を全称命題にして取り違えるという論理的間違いに陥る」手法には問題があると思っています。」という文章が「疑問」なのか「批判」なのか微妙なところだが、ここには、文章読解能力というリテラシーの問題が入っている。「フェミニズム」という言葉に対して常に「行き過ぎた」「極論としての」という修飾語をつけなければ、そのような意味としては受け取れないと言うことであれば、あそこの全文に対して、抜け落ちているところのすべてをそう解釈して欲しいということを言っておこう。しかし、本来なら、文章というのは、単語で理解するのではなく「文脈」で理解しなければならないものだ。一つの文章の中で同じ単語が使われていても、その両者がまったく違う意味を持っている文章というのも存在する。そんなとき、いちいち修飾語をつけて表現するときもあるが、これくらいは文脈から読みとってくれと思いたくなるときもある。だいたい言語というのは、本質的には概念を表現するものであるから、現実存在をそのまま表現することは出来ないのである。その概念を頼りに、現実存在との関係から意味をたぐり、概念には盛り込めない具体的な意味を読みとることが言語の理解と言うことだ。もしインターネットで文章を読む人間の大部分が文脈を読むことが出来ないとしたら、すべての単語にたくさん形容詞をつけて書かなければならなくなるだろうが、それはかなり煩わしい文体になるだろうと思う。僕は、極力代名詞を使わないように、具体的な名詞を使って何を指すかがはっきり分かるようにと言う配慮をした文体にしているが、それでもかなり煩わしい文体になっていると感じている。これ以上煩わしい文体になるのなら、非常にやりきれない気分になってくる。そして、「「特称命題を全称命題にして取り違えるという論理的間違いに陥る」手法には問題があると思っています。」という、批判として読める部分に関しては、批判としては甘いし、論理的に明確でないと僕は感じている。僕が論じていた特称命題というのは「様々」という修飾語がついている言葉で、この言葉は、意味から言って「すべて」を指しているのではないから「特称命題」であることが明確なものだ。それに対して、「様々」で言及していた対象を、いつの間にか「すべて」にしてしまったら、「特称命題を全称命題にして取り違えるという論理的間違いに陥る」だろうと言うのが僕の主張だ。もし僕が使っている「フェミニズム」という言葉が、このような論理的間違いに陥っていると批判するなら、どの部分で使われている「フェミニズム」が「特称命題」であり、どの部分で使われている「フェミニズム」が「全称命題」になっているかを具体的に指摘すべきだろう。同じカタカナで書いているからと言うことでは論理的な指摘にはならない。文脈からそれを指摘して、その解釈が妥当であるということが証明されなければ、それは論理的な批判としては弱いのである。それから、最後の部分では、言論の立ち位置について言及した部分があるが、これは読みようによっては言論封殺につながる発想を持っている。立ち位置を表明しなければものを語ってはイケナイというような意味にも読みとれる恐れがある。それは、言論の自由の否定ではないのか。言論の自由というのは、何か資格があって、その資格をクリアしなければ持てない権利なのか。それは、フェミニズムの発想に反するのではないだろうか?僕の立ち位置には何ら陰謀的なものは無い。論理的に真っ当なものを求めたいと言うだけのことだ。だから、論理的に真っ当でないと思えば批判するだけのことであって、その批判が何か目的があってするようなものではない。逆に言うと、何か目的がなければ批判することは許されないのか、という疑問を提出したい。「フェミニズム」という言葉の周辺で語られる言説にうさんくささを感じ、論理的に真っ当でないと感じたからこそあのような批判を提出した。それだけのことだ。僕は直接「フェミニズム」の運動に関わっている人間ではないから、そこに間違いがあると思っていても、それを是正しようなどという意志は持たない。それは、そこにいる人間が努力すればいいことだと思っている。ただ、外から見るとこんな風に見えるよ、という提言は、まったく役に立たないいらないものなのだろうか。それが役に立たないと思うのなら聞き捨てておけばいいのだと思う。しかし、そのような発言を許さないという姿勢は、言論の封殺ではないかと思う。もしそのようなメンタリティをもっている人間がいたら、思想・信条・表現の自由、それから言論の自由というものの権利についてもう一度よく考えた方がいいだろうと思う。これらは基本的人権に属するものだ。だから、この権利を行使する条件は、その主体が人間であればいいと言うことになる。その他の資格はいらない。ある言論に対しては、それが間違っていると思えば批判すればよいのだし、批判するまでもないことなら聞き捨てておけばいい。ただし、批判に対しては反批判が返ってくることは覚悟しなければならないだろう。その批判が本質的なものであれば、おそらく自分の「構造的無知」を気づかせてくれるだろう。それはかなり痛い経験になると思うが、成長することは確かだ。
2006.05.20
コメント(1)
-
告発のための告発
ブログになる前の楽天広場では、かつて著作権法の違反を摘発することが流行っていた頃があった。当時はまだインターネットも大衆的な開放がされたばかりの頃で、よく知らなかったり慣れていなかったりする人たちが、著作権のある映像を無自覚に自分の日記に貼り付けていたりしていた。それに対して、啓蒙する意味で親切に教えているのなら、この著作権法違反の摘発も、僕はそれほど違和感を感じなかったと思うが、どうもそれは啓蒙的ではなく、むしろ摘発して告発すること自体が目的ではないかと思えるようなものが多かった。他人の欠点を指摘して、自分がそれを諭すような立場に立ったときに快感を覚えるという種類の人間がいるのだなとその時僕は思った。そのような快感を感じる人間にとっては、著作権法というのはまったく便利な法律だという感じがした。何しろ違反かどうかは極めて分かりやすい。だからその指摘は簡単に出来るし、何しろ法律だから、自分の方に絶対的な正しさがあることが証明出来る。安心して他人を叩けるとなったら、叩くことに快感を感じる人間にとっては、毎日叩く材料を探すのが面白くて仕方がなくなるだろう。そういうものに快感を感じない人間としては、叩かれる材料の提供だけはしないようにしようと気をつけたものだった。僕はそれまでは歌詞の全文を掲載したりもしていたが、引用だけにしたものだった。引用であれば著作権を侵害することはないからだ。著作権法違反を告発する人たちは、自分たちが正義を実現していると思っているから、自らの善意を疑うことがなかっただろう。だから、告発を楽しんでいるのだと言われると腹が立つかも知れない。しかし、それは自覚がないだけで、著作権法の本質を理解していれば、単純な摘発だけをして、何かいいことをしたなどと思えるはずがない。著作権というのは、創作者の知的所有権というものを守るために作られたというのが本質的なものだ。創作物によっては、単なるコピーであっても大きな利益をもたらすものが存在する。そのようなものを、最初に作り出した人間を無視して、利益の方だけをかすめ取ることが横行したら、創作意欲そのものが衰えてしまう。優れた創作を期待するには、そのような創作者を守る必要があるという発想から生まれたものが著作権法であり、本質はそこにある。だから、本質的な判断としては、創作者の知的所有権を侵していない、そのプライオリティーを尊重していると言うことがあれば、本質的には著作権侵害ではないはずなのである。それを、単純に著作権があるものを使ったと言うだけで、犯罪を犯したという指摘をするのは、啓蒙的な意味では間違いだと思う。もっと他の方法で指摘するべきだし、明らかな著作権侵害を象徴的に告発すると言うことが必要だったと思う。実際には、著作権法違反摘発の流行は、その著作権を管理している巨大企業に利益を生むことにしかつながらなかったと思う。その善意は、巨大企業の利益を高めることにしか役に立たなかった。それが本当に創作者を守ることにつながっていたかどうかは極めて疑わしい。今はCDがかなり売れなくなってきているそうだ。著作権を守るために様々な制限を課したものだから、そのような面倒なものに対する関心が薄れたのだろうと思う。流行のCDは、特に優れた創作者が作り出したものとは限らないから、人々の関心がなくなれば、ぜひ手に入れたいという意欲はなくなるのだろう。機械的な著作権法の適用は、かえって著作物の衰退を招くと言うことがこれからも出てくるのではないだろうか。告発のための告発に対して、大衆的な気分がどのように反応するかと言えば、そのような面倒なものには関わりたくないと言うことになるだろうと思う。著作権法違反を摘発されるようなら、著作権が存在するものには一切手を出さないとした方が安全だ。それを味わって楽しむと言うことは関心の外になるだろう。芸術の衰退にもつながるのではないかと思う。告発のための告発が、このように、本来の目的ではない結果を招くと言うことは、それは論理的必然ではないかと思える。かつての差別糾弾運動にもそのような面が見えた。差別糾弾運動は、差別反対運動の一つで、その運動によって差別というものをなくすことを目指したものだった。しかし、それは本当に効果があっただろうか。差別というものの現象の中にある本質的な不当性というものに、人々が目覚めて、差別反対運動を支持する人が増えただろうか。僕は、まったく効果がなかったと思う。それどころか、差別反対運動に対する反感をすら生んだのではないかと感じている。僕が実際に関わった問題でも、ある印刷物の誤植が、差別意識の現れだと追求されたことがある。そういう追求をする人間は、人間には間違いがあるということが分かっていないのかと思う。三浦つとむさんは、誤謬というのは、心がけが悪かったり、頭が悪かったりして起こるのではなく、人間の認識というものが制限されているところから必然的に生じるのだと論じていた。誤謬が人間の本質的なものであるなら、誤植に関しても、短絡的に差別意識の現れだと追求するのではなく、何故誤植が起こったのかという具体的な検討が必要だろう。教員の仕事の傍ら、忙しい中で印刷物の処理をしなければならなくなったとき、それに専念して仕事をしているわけではないのだから、そこに単純なチェックミスがあったとしても仕方がないと普通は思うだろう。しかし、社会生活の中で、教員という地位にいることが差別の体系の中で必然的に差別意識をもたらすのだというような、教条的な思い込みがあったら、単純なミスによる誤植も、そうでない解釈がされてしまう。古いソビエトの映画では、ある誤植を訂正するために、徹夜で訂正処理をするシーンがあったというのを聞いたことがある。それは、その誤植が、共産主義に対する忠誠心を疑わせるものになっていたからだったと記憶している。このように、人々の心の中まで支配するような恐怖政治というものも、ソビエトを始めとする社会主義国家の崩壊の原因だろうと思う。人間の心まで支配するような国家は、いつかはこのように強烈なしっぺ返しを受けるのだと思う。告発のための告発も、最後は人間の心を告発するところに行き着く。著作権法違反をする人間も、差別をする人間も、その心がけが、元々そのようなものだったのだという告発だ。このようなやり方は、崩壊した社会主義国のやり方であり、最近批判が強くなった共謀罪と同じやり方だ。それは、人の心を問題にして、思想・信条・表現の自由を侵すものになる。フェミニズムによる告発も、似たような面がないかどうかは気をつけておいた方がいいのではないかと思う。フェミニズムを提唱する人間は、共謀罪に対して反対する人間が多いと思うが、もし告発のための告発が行われているとしたら、構造的には共謀罪と同じことをしているのだという自覚が必要だ。また前回取り上げた「フェミニズムを知らなければ批判はできない」というエントリーの次の文章「とりあえず、フェミニズムの歴史もなんにも知らないことが分かる文章だ。」は、本人は自覚がないかも知れないが、言論封殺を意図した言い方になっている。これは、「知らないことには何も言うな」と言っているに等しい文章だ。これが、思想・信条・表現の自由に反するものであることは、フェミニズムの運動をする人間は、特に気をつけておいた方がいいだろう。知識のあるなしにかかわらず、何を言おうとも自由なのだ。間違っていれば訂正すればいいだけの話である。もし、知識がないことで発言を制限するなら、女性にとって知識や能力が不足している分野へは、何も語ってはいけないと言うことにならないだろうか。フェミニズムというのは、そういうものに反対していたのではないのだろうか。言うこととやっていることとが違うというのは、このようなときに指摘されることだろう。自分たちの気に入らない言論はそれをしゃべらせることもしたくないと言うのは、いわゆる「ネットウヨ」と呼ばれる人たちの心性だと思ったのだが、リベラルの側にもあるようなら、その運動は破綻するだろう。リベラルは、権力を持たないのだから、あくまでも言説の正しさという論理で主張しなければ、それを支持する人々は出てこないと思うのだ。もし感性だけでつながっている情緒的な運動だったら、似たような人たちだけでやってちょうだいね、というだけだ。僕は、そのような似たような人たちが、圧倒的少数派であることを願うだけだ。それならば害はない。
2006.05.20
コメント(2)
-
フェミニズムの主流派はどこにいるのか
極論としてのフェミニズム批判をしたところ、いくつかのトラックバックをもらったが、僕がよく訪れる瀬戸智子さんのブログを除いては、それが過剰反応としか思えないトラックバックだったので少々驚いている。過剰反応は、いわゆる「ネットウヨ」と呼ばれる集団の特性かと思っていたのだが、フェミニズムを論じる人間にもそのような過剰反応があるようだ。この反応で、僕はフェミニズムというものにますますうさんくささを感じるようになった。過剰反応というのは、容易に反対の極に振れる可能性があるからだ。もし自分の主張がまともなフェミニズムだと思うのなら、僕の批判などは、極論としてのフェミニズムを批判したものなのだから、それと自分とは違うと言ってしまえばそれですむのではないかと思う。それをどうして、極論の批判に対してまで、フェミニズム一般への批判だと受け取るのだろうか。自分の理論の中に、僕の批判に相当するものが入っていたのだろうか。僕が師と仰ぐ三浦つとむさんはマルクス主義者だった。今ではマルクス主義は完全に死んだと言ってもいい状態になっている。ソビエトの崩壊によって、マルクス主義を基礎としていた国家がその理論の誤りを証明したからだ。マルクス主義はソビエトが崩壊する前から様々な人に批判されていた。反共的な極端なものから、三浦つとむさんのように同じ陣営からの批判もあった。異なる立場からの真っ当な批判としては、ソビエトの崩壊を予見していた小室直樹氏がいるそうだ。反対の極の反共主義からの批判は、かなり間違いも多く、批判そのものも甘いものが多い。僕は三浦さんのように完全にマルクス主義者だとは自己規定出来なかったが、マルクスやエンゲルスが語ることは正しいと感じていた。しかし、現実の主流派のマルクス主義が批判されても痛くも痒くもなかった。僕は三浦さんを通じて主流である「官許マルクス主義」は間違いだと思っていたからだ。だから、そんなものはいくら批判されても、自分は違うと思っていればよかったし、むしろ批判が甘いんじゃないかと思っていたくらいだ。だから、僕が極論としてのフェミニズムを批判したとしても、まともなフェミニズム論者だったら、そんなものは自分とは違うと思うだろうと思ったし、むしろ僕の批判が甘いという指摘が来るのではないかと思っていた。それがどういうわけか、論理的な指摘ではなく、的はずれな少々感情的な反批判になっていたので、僕が批判するマトモでないフェミニズムもフェミニズムの主流なのかと疑ってしまう。「官許マルクス主義」はマルクス主義の主流派だった。三浦さんのようなマルクス主義は、全くの少数派であり非主流派だった。これは、それを信奉している人間が、圧倒的に「官許マルクス主義」の方に多かったと言うことが、当時それが主流だったということの判断の根拠だ。そして、間違った理論である「官許マルクス主義」が主流だったことが、後の社会主義国家の崩壊を招き、マルクス主義という理論が完全に死んでしまう原因となった。当時「官許マルクス主義」に反対する人々の中で、それは「真のマルクス主義」ではないから、自分たちの正しいマルクス主義はまだ死んではいないと主張する人もいた。しかし、これは多くの人の賛同を得られなかった。主流であったマルクス主義が死んだとき、やはりマルクス主義そのものは死んだのだと僕は思う。僕はマルクス主義は死んで良かったと思っている。「官許マルクス主義」という間違った理論を信奉していた人々は、能力が低いために間違えた人々ではないからだ。彼らは、少なくとも社会主義の体制の中では最高の能力を備えた人々だった。能力という点では、資本主義国家の人たちと遜色はなかっただろう。しかし、彼らが最後まで間違いから抜け出せなかったのは、内田さんが語る「構造的無知」にとらわれていたからだろうと思う。僕は、この「構造的無知」を支えたのは「善意」だったと思っている。まさに「地獄への道は善意によって敷き詰められて」いたのだ。論理的判断よりも善意による判断の方が優位に立ってしまったことが「構造的無知」の原因だと思う。マルクス主義を揶揄する小話としてこのようなものがあるそうだ。ある時、大部の地域の歴史を編纂するという難しい仕事が課されたという。例えば1000ページほどの地域史を作るとき、マルクス主義的な考え方で、1000人の労働者が1ページずつ担当して、みんなが力を合わせればすぐに出来るという結論が出てくる。これはまったくばかげた発想なのだが、その1000人の労働者の善意は確かなものだ。その善意を疑う人間は、人民の力を信じない反動的なブルジョア思想の持ち主ということにされてしまう。この小話がばかげた内容を含んでいると言うことは、仕事というのは、機械的に振り分けたからと言って成功するものではないということが論理的に理解出来る人にはすぐ分かるだろう。しかし、労働者は力を合わせれば何でも出来るという善意が一番大事なものになってしまうと、そのような論理的な理解は排除される。機械的に振り分けた仕事が、いかに仕事の能率を下げ、社会主義国家の国力を衰えさせたかは、崩壊後によく分かった事実だ。難しい複雑な仕事であればあるほど、その仕事をマネージする優れた指導者が必要になる。資本主義社会であればごく当たり前のことが、社会主義国家では間違った「官許マルクス主義」によって発想もされなかったのではないかと思う。ばかげた発想というのは、頭がよければ避けられるというものではない。論理に優先する何かがあった場合は、その優先するものが邪魔をして「構造的無知」に陥るのである。フェミニズムが論理に優先してもっている何かというのを、僕は、すべてにおいて問題を「男性優位の社会構造から生じ、または家父長制が無意識に前提視されていることから生じている」と考えているところにあると感じている。これが、「すべて」ではなく、具体的な検討を経て、そうである場合とそうでない場合を区別していれば、そのようなフェミニズムは極論に流れることを避けられる。さて的はずれの批判だと思われるトラックバックの中で、もっとも的はずれだと思うものに言及しておこう。「フェミニズムを知らなければ批判はできない」というエントリーでは、冒頭に次のように語られている。「とりあえず、フェミニズムの歴史もなんにも知らないことが分かる文章だ。」これに対しては、皮肉を込めて、「とりあえず、論理についての何たるかについて何にも知らないことが分かる文章だ。」と感想を言っておこう。論理というのは、対象を選ばない。相手にだけ適用出来るものではないのだ。それは自分にも返ってくることを知らなければならないだろう。僕はフェミニズムのうさんくささを、一面を固定した視点で見るという形而上学的な論理が極論として出やすい所に見ていた。だから、それに対して論理的な反論をするのなら、フェミニズムには、そのような固定した視点は生じないのだという反論をする必要があるだろう。それが論理というものだ。それが納得いくものであれば、僕のうさんくささも解消されてフェミニズムに対する評価も変わってくると言うものだ。しかし、それを「知らなければ批判はできない」などという紋切り型で語るなら、論理の何たるかを知らないだけだろうと思うだけだ。僕はフェミニズムの定義をしたのではない。歴史を語ったのでもない。論理的側面を語っただけだ。それに対して何を知らなければ批判出来ないというのだろうか。論理というのは、その展開の構造を見るものなのである。個別的な知識について何か言及するのではない。僕の論理展開について、知らなければならない知識がどういうものであるか何も語らずに、「知らなければ批判はできない」という言葉を対置するだけで批判したつもりになっているとすれば、論理を知らないのだろうと思うだけだ。僕は、フェミニズムを語る人間は、もっと論理的に正当性のあることを語るべきだと思う。すべての根拠を男性優位の社会構造に還元すべきではないと思う。セクシャルハラスメントについても、どのようなときに不当な行為であるかという判断を、もっと論理的に正当性をもって論じるべきだと思う。現状では、女性が訴えれば「セクハラ」になるという風潮になっている。しかし、同じように見える行為でも、それが不当なものと、偶然の事故のようなものとの違いがあるはずだ。あるいは女性の側の全くの誤解だってあるだろう。それを一緒くたにするとしたら、それは論理的に正しくないと僕は思う。機械的に表面的な事柄だけで判断をするから僕はそれをうさんくさいものと感じてしまう。僕がウィキペディアで見つけた「ジェンダーフリーの実践例等」についても、あんなものはフェミニストは主張していないということが言われていた。それでは、フェミニストは、あそこで語られている事柄には何一つ賛成はしないのだろうか。フェミニストが、あそこに書かれていた事柄すべてに反対するのなら、フェミニストはそんなことを言わないということを僕も信じよう。しかし、そうではなく、一つでも賛成するものがあったら、どのような根拠でそれに賛成するかを知りたいものだと思う。また、あそこで書かれていたものの反対のことが現実には行われている。それに対してフェミニストは何一つ反対はしないのだろうか。例えば、クラス名簿が男女別になっていることには反対しないのだろうか。どれ一つとして反対しないのだということであれば、あそこで提出されている事柄が、フェミニズムに通じているという解釈は撤回しよう。しかし本当のところはどうなのだろうか。もし一つでも、現在行われている事柄に反対なら、その反対の根拠も聞いてみたいものだ。その根拠が論理的に真っ当なものであれば、フェミニズムも真っ当なものだと僕は思うだろう。しかし、フェミニズムが語られるとき、その主張の根拠が「男性優位の社会構造から生じ、または家父長制が無意識に前提視されていることから生じている」ということしか語られないなら、僕はフェミニズムをやはりうさんくさいものだと思う。どこかで正当な理由が語られているのだろうか。
2006.05.19
コメント(3)
-
フェミニズムのうさんくささ
弁証法の論理には「両極端は一致する」という法則がある。極端というのは、一般論的に考えると、現実に存在する物事をある一面からしか見ないということになる。本来なら多様な面を持っていて、多様だからこそ、視点を変えれば矛盾した結論も導かれてしまう現実存在を、一面からしか見ないのであるから、これは他面を無視した誤りに導かれる。両極端からの主張というのは、それが誤りに導かれるという点で共通しているが、この誤りが論理的には一致する結論にまで到達するというのが、弁証法でいう「両極端は一致する」ということだ。これは面白い法則だと思う。極論を主張する人間は、それが極論であることによって、実は否定したい対象を肯定してしまうという誤りに陥ってしまう。この極論による誤りは、視点を固定してしまう面があるので、形而上学的誤謬とも呼ばれている。これは、批判の出発点の正しさを持っている考察が陥りやすい誤謬なので、良心的な人々は十分注意しておかなければならないだろう。善意だけでは論理の正しさはもたらされない。その善意が確かなときは、論理的な誤謬があっても善意の正当性でそれが無視される場合もある。「地獄への道は善意によって敷き詰められている」という現象がその時に起こるだろう。このような誤謬は、マルクス主義を主張するときにもよく現れたもので、三浦さんはそれを「官許マルクス主義」と呼んで批判していた。マルクス主義は、虐げられていた人々に対する善意の救済というものにあふれていた。しかし、それが善意であればあるほど、現状の否定が行き過ぎる極端に振れる恐れがある。それが「官許マルクス主義」と呼ばれる論理的誤謬につながったと僕は感じている。フェミニズムというものも、現象として虐げられた女性・差別された存在としての女性というものから出発することによる極論の可能性をはらんでいる。その不当性を主張することは批判の出発点として正しい。しかし、不当性を否定することは正しくても、それが行き過ぎて、すべての現象が否定されるものであるかのように主張されると、これは極論としてのうさんくささが出てくる。たとえ善意から出発したフェミニズムであろうとも、それが極論にまで達すれば論理的には間違えるというところに僕はうさんくささを見る。フェミニズム一般を否定するのではなく、極論としてのフェミニズムの批判を考察してみたいと思う。それは間違った論理であるにもかかわらず、現状に不満を持っている人には受け入れやすい論理になるだろう。そのようなメンタリティは、心情的には理解出来ても、誤った論理は結果的にはフェミニズムの信用を落とすことになる。極論としてのフェミニズムは、本来連帯出来るはずの男と女の連帯を破壊する。だから、これは批判する価値のある批判ではないかと思う。「フェミニズム 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』」には、フェミニズムに関する基本的な情報が書かれている。ここには、「多くのフェミニストは、女性に関する様々な社会問題が、男性優位の社会構造から生じ、または家父長制が無意識に前提視されていることから生じていると主張している。また、女性間の差異を考慮に入れれば、例えば「黒人」「女性」というように、二重、三重に抑圧されていると捉えることができるため、フェミニズムを複合的な抑圧の集成理論として、また相互に影響する多くの解放運動の流れの一つとして捉えることもできる。」というフェミニストの主張が書かれているが、これは基本的には正しいと僕も思う。しかし、これを極端にすれば容易に誤謬に陥る。「様々な社会問題」は、あくまでも「様々」なものであって、「すべて」ではない。しかし、これを「すべて」と考えれば、特称命題を全称命題にして取り違えるという論理的間違いに陥る。現在主流となっているフェミニズムが、この極論の間違いに陥っていないかどうかは検討されるべき価値があると思う。「ジェンダーフリー 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』」という項目は、「フェミニストのすべてがジェンダーフリー推進派ではなく、フェミニストではないジェンダーフリー支持者もいる」という但し書きがついているが、極論としてのフェミニズムが到達する可能性のある誤謬の例がいくつか挙げられている。それは、「ジェンダーフリーの実践例等」としてあげられている次のようなものだ。「・クラス名簿を男女混合にする。 ・男女の呼称を「さん」に統一する。 ・「男女」の名詞を「女男」に変える。 ・スカートは最も「女らしい」服装なので、制服からスカートを廃止しようとした ・女子の体操着のブルマー廃止と同時に、男子の短パンも廃止し、男女兼用のハーフパンツとする。 ・運動会の競技を男女混合にする。 ・ロッカーや下駄箱の男女別の禁止。 ・小学校教科書の記述を「点検」。「男の子はズボンに女の子はスカートに髪かざり」、「おじいさんは反物売り、おばあさんは家で」、「およめに来て・・・・およめに行く」、「小さなお母さんになってお昼を作る」などの表現をジェンダーフリーに反するものとする。 ・男女別学の公立高校を共学にする。 ・高校入試の合格者数を、男女同数にするよう要求する。 ・黒や赤などのランドセルの色を家庭が選択することを禁止し、「女男ともに黄色いランドセル」といった、統一色を要求する。」これは、差異があることを、その現象だけで不当な差別だと考える一面的な論理的誤りだ。差異が存在することに正当な理由のあるものも、視点を変えれば理解出来るはずだ。しかし、差異があるのは、すべて男性優位の思想の表現であるという極論を持っていると、差異があるだけでそれを否定してしまうという論理が生ずるだろうと思われる。このような極論からの批判は、論理的正当性も伝統も無視したものになる。だから、他の視点を持っている人間からはそれが行き過ぎだと思われてうさんくさい目で見られるようになるだろう。このような極論に対しては、「石原慎太郎東京都知事は、都議会定例会において、「最近、教育の現場をはじめさまざまな場面で、男女の違いを無理やり無視するジェンダーフリー論が跋扈(ばっこ)している」、「男らしさ、女らしさを差別につながるものとして否定したり、ひな祭りやこいのぼりといった伝統文化まで拒否する極端でグロテスクな主張が見受けられる」、「男と女は同等であっても、同質ではあり得ない。男女の区別なくして、人としての規範はもとより、家庭、社会も成り立たないのは自明の理だ」と強調し、ジェンダーフリー教育を公人の立場で公式に批判した。」と、ここに書かれているように、石原氏の批判が正当なものとして論理的には判断出来る。僕は、政治家としての石原氏には批判的だが、極論としてのジェンダーフリーに対するこの批判は正当だと思う。内田樹さんも、行き過ぎたフェミニズムに対しては、その行き過ぎを的確に批判してきた人だ。「1999年12月21日の日記」では、「上野千鶴子の造語」と語る「アカデミック・ハラスメント」を「はた迷惑なことを思いつく」といって批判している。これが行き過ぎだということは、何を基準にしてこれを判断するかが明確に出来ないことから結論している。「どう考えても「アカハラ」認定は恣意的であることをまぬかれない」と語っている。僕もそう思う。ある現象を「アカハラ」だと受け止める人がいれば、それは「アカハラ」だということになってしまいかねない。「セクハラ」の規定に似ているところがある。しかし、内田さんが語るように、感情的にそう受け止めたくなる人がいても、視点を変えれば、「しかし説教をかますのは教育的指導のためである。「よちよち、いいこでちゅね」と甘やかしているだけでは、ぜんぜん教育にならないことは誰にでも分かる。 ろくでもない論文を書いてきたら、こんなものでは学位はだせんと言うだろうし、仕事がほしいといってきても、人に教えるのは十年はやいと回し蹴りをくらわすこともあるやもしれない。 それを相手が女性だからだというので「アカハラ」といわれたのでは私の立つ瀬がない。」という解釈も出来る。どちらが正しいかは、具体的な現象を具体的に分析してみなければ分からない。その具体性を飛ばして、一般論としての「アカハラ」の規定を押しつけるとしたら、これは極論としての誤謬だろう。現実存在というのは、一般論で切り捨てられるほど単純なものではないのである。理論と応用との違いを考えなければならない。内田さんは、最後で「どのような愚劣な理説であれ、それを開陳する資格は誰にでもある。私はただ、自分のまわりに女性であることが「自分の研究が不当に低く評価されていること」の主要な理由だと主張する女性研究者がいたら「あ、すげー頭の悪いひとなんだ」と心の奥で思うだけである。」と語っている。まったくその通りだと僕も思う。ただ、極論の誤謬に陥っている人は、自分の頭が悪いという論理的な帰結は受け入れがたいものになるだろう。受け入れがたい考えは、無意識のうちに無視されるという「構造的無知」に陥るに違いない。だから、このように語る内田さんは、極論が正しいと思い込んでいる人たちからは嫌われることになるだろう。しかし、内田さんの論理が正しいと受け止めている僕は、内田さんは率直にものを語る人なんだなという尊敬の念が生まれてくる。内田さんのこのような物言いに対して、感情的な反発ではなく、論理的な反駁が語られるなら、フェミニズムに対するうさんくささも少しは解消されると思う。
2006.05.19
コメント(3)
-
しごきの有効性について
ちょっと前に戸塚ヨットスクール事件で服役していた戸塚宏氏が刑期を終えて出てきたというニュースがあった。そして、その後にアイ・メンタルスクール(NPO法人)事件というものが起きて、これも何か戸塚ヨットスクール事件に似たような印象を人々に持たせたようだ。両方の事件に共通しているのは、引きこもりや家庭内暴力といった問題を抱えた青年を教育するという目的を持っていたことだ。これらの問題には、残念ながら有効な解決手段がなく、当事者として困り果てていた親にとっては、戸塚氏などが救世主のように見えていたというのも共通している。これらの教育が、一定の効果を持つ場合もあっただけに、その評価というものが難しい面を持っている。戸塚氏の持論である「体罰も教育だ」というものは、東京都知事の石原慎太郎氏でさえも支持しているというのを聞いたことがある。アイ・メンタルスクール(NPO法人)で、同じような事件が起こってしまったというのは、未だにこのような問題には有効な解決法がなく、少々乱暴であっても有効性を持っている方法に頼ってしまうと言うことになってしまうのだろうかという残念な思いが残る。戸塚ヨットスクールやアイ・メンタルスクール(NPO法人)で行われていた行為は「しごき」という言葉で表現することが出来る。そして、「しごき」は一定の効果があることは、スポーツにおける指導で証明されている。しかし、それが批判されていることも確かだ。その批判が、本質を突いたものになっていないために、「しごき」はなかなかなくならない。そして、結果的に効果があったということで「しごき」に手を出す指導者は後を絶たない。「しごき」は、その本質を分かっていない指導者には、常に行き過ぎる危険性をはらんでいる。成長・発達を促す「しごき」ではなく、精神・身体を破壊する「しごき」になりかねない。「しごき」の本当の有効性を発揮させるためには、指導者に確かな目がなければならないのだが、安易に表面的な効果に目を奪われていると、その行き過ぎを見過ごしてしまう。この「しごき」について見事な論理展開をしていたのは、『武道の理論』(三一新書)を書いた南郷継正さんだった。南郷さんは、この本の193ページから198ページまでにかけて、実に見事な「しごき」論を展開している。「しごき」の有効性を認めながらもその欠点を指摘し、どのような場合に「しごき」が、見事な教育法から単なる暴力に堕落するかを論じている。まずは有効性の方からその指摘を見てみよう。「武道とかスポーツとかに否応なしについて回る「しごき」なるものは、本質的な意味においては絶対的に必要なものであり、非常に大事なことなのである。何故かならば、体力の限界状況において、その状態に打ち勝つ精神というものは、放っておいて出来上がるということは、ほとんどあり得ないと言ってよい。特に、実力の接近した戦いほど、強烈な精神を持つものの方が有利になってっくるものであれば尚更のことである。 これらの精神というものは、それらが必要であると自覚しているだけでは駄目なのであって、技と同じように自ら創り上げなければならないものなのである。」「しごき」というのは、極限状況を作り上げる鍛錬において必要なものであるという指摘はまったく正当なもののように感じる。練習においては名選手であっても、いざ試合になると実力を発揮出来ないものは、この極限状況において平常心を保つことが出来ないことが多いだろうと思う。その克服のためには、「しごき」は有効性を発揮するだろうことは予想出来る。練習の時に試合と同じような極限状況を経験するには、「しごき」という手段は有効性を持っているだろう。これは学問においては三浦つとむさんが「真剣勝負」と語ったような、失敗するかも知れない難しい問題に果敢に取り組むというような、失敗を恐れない気持ちに通じるものかも知れない。安全な答があることがはっきりしている問題を解くのではなく、答があるかどうかも分からない問題に取り組んで、学者生命をかけて問題に取り組むことを三浦さんは「真剣勝負」と呼んでいたようだ。この「しごき」が有効であるには一定の条件が必要だ。すべての場合に「しごき」が役に立つというわけではない。その一つの条件は、上にも書かれているように、「しごき」を受ける人間がその必要性を自覚して、自らの技を創り上げるためにそれを受け入れるという意志を持っていることだ。この条件がないと、次のようになってしまうと南郷さんは指摘する。「しかしながら、自己の目的とするものに疑問を感じ始めると、それに積極的に耐え抜こうとする心がなくなる結果、当たり前の「しごき」にも耐えきれなくなって、体よりも心が先に参ってしまい、結果的に死亡するという事態を招きやすくなることになりかねない。この場合、指導者が、耐え抜こうとする意志のあるものと、逃げ出そうとする心を持っているものとの区別を見抜くことが出来ないと、前者の場合成功した「しごき」が、後者の場合は失敗して、世論の糾弾に遇うということにもなるのである。」二つの事件における「しごき」は、しごかれる本人の意志によってそれに耐えようとしていたのではない。無理やり耐えさせようとしていたものだ。まず「しごき」の有効性の一つの条件がまったく考慮されていない状況での「しごき」だったと考えられる。このような状況だったから、意志の違いによる区別という発想もおそらくなかっただろうと思う。この区別がない発想だとどういうことになるか。大部分の体育会系の「しごき」がそうなると思うが、逃げ出そうとする人間は根性がないという受け取り方をするだろうと思う。これは、根性がないという判断が正しいかも知れないが、根性がないということは、「しごき」に耐える意志を持たないことであるから、その時点で「しごき」をやめなければならない。ところが、根性がないことは駄目であるという発想があると、さらに「しごき」を強める傾向が、日本的な精神主義には存在する。これが、「しごき」による死亡事故を招くだろうことは容易に想像出来る。アメリカの映画などでも、スポーツや軍隊の鍛錬の場面では、「しごき」によく似た場面が出てくる。しかし、指導者が感情的に根性を鍛えようとすることはない。相手が「しごき」に耐えうるかどうかが判断出来ない指導者は、指導者としての能力が低いと判断されるからだ。日本の場合は、指導者の能力が低いという判断ではなく、指導される側の根性がないということが欠点とされることが問題だと僕は思う。死ぬまでしごいてしまう指導者は、その指導能力の低さを問題にすべきだろうと思う。「しごき」を有効に使うには、指導者の側に確かな目がなければならないのだが、幸か不幸か指導される側に根性があったりすると、間違った「しごき」でも一定の有効性を持つから、「しごき」に対する信仰はなかなかなくならない。次の南郷さんの指摘も見事なものだと思う。「先に、技は、その技を創る段階と、その技を使用する段階とに分けて考えねばならなうことを説いたが、この区別が出来ない人間にとっては、「しごき」がとても重宝に思われてくるものである。何故かというに、技は、いかにお粗末であっても、そのお粗末な技の限界ギリギリまでは、その技の使い方を巧みにすれば、まともな技を持っていながら、未だそのまともな技の使い方のお粗末なものよりも強さを発揮出来るものなのだからである。これが「ヤクザ剣法」が、甘っちょろい「道場剣法」より強い理由なのであるが、そればかりでなく、よりまともな技であればあるほど、その技を創ることも難しく、またその技の使用法に慣れることも難しいものである。」「しごき」によって鍛えたものは、表面的には、他のものよりもよくなったように見える。しかも、本質的に本物を身につけるのはたいへん難しいから、他の方法ではいくら努力しても成長・発達しなかったものが、少しでもよくなるように見えれば、それに飛びついてしまいたくなってくる。南郷さんは、この本の冒頭で、「しかし、明日の糧に困っている人々に、だから我々は飯に困らない社会を目指すのだとの原則論しか提示出来ないのでは指導者欠格であり、少なくとも人間的な指導者ではない。」と語っている。「代替案」のブログを運営している関さんのように、有効な代替案を提出することが指導者の責任でもあるだろう。「しごき」に代わる具体的で有効な代替案がなければ、「しごき」に流れる人々の心情を変えることは出来ない。だが、これは非常に難しい。このときに、代替案がないうちは、「しごき」にはわずかでも有効性があるのだから、その有効性を求めるのは仕方がないと考えるのか、あくまでもその害を重視して、たとえ代替案がなくても批判することが正しいのかは意見が分かれるところではないだろうか。「しごき」批判に対する反批判として、「それじゃ、何をすればいいのか具体的に語ってみろ」というのがあると思う。これは、ある意味では正しいと思うが、「だからしごきもやむを得ないのだ」と「しごき」を肯定する論理展開に向かうと、僕は間違いではないかと思う。代替案がなくとも、間違った「しごき」は否定しなければならない。有効な「しごき」があることをもって、「しごき」一般を肯定してしまうのは論理的な誤りだ。その肯定に対してはやはり批判することが正しいと思う。代替案がなければ批判することも許されないとするのは論理的な間違いだろう。本質的に難しい問題には、そう簡単に代替案が見つかるはずがない。だから、そういうものに対しては、確かに間違っていると考えられるものは厳しく批判すべきだと思う。戸塚ヨットスクールに対しても、死ぬまでしごくというやり方は絶対に批判されなければならない。南郷さんは、本書の冒頭で「肉体も精神も、単にもまれただけでは鍛えられないのである。苦しい思いをしただけで鍛えられるものであるならば、満員電車はさぞかし立派な鍛錬の場となっていることだろう。そこに欠けているものは積極的な働きかけ、つまり意志がないのである。」とも指摘している。この当たり前の感覚を持っていれば、意志を無視した「しごき」が間違っているということは判断出来るだろう。その間違いは、代替案の有無にかかわらず批判をしなければならないと思う。南郷さんは、「あらゆる方法が絶望的であるときは、最悪の方法が最良の方法である」という言葉を引いて、「どうやって上達させるものかを論理的に知らない人々にとっては、この最悪であるはずの「しごき」が最良の方法」となるとも指摘している。「「しごく」ほど楽なことはないからである。何しろ頭を使わなくてもいいのだ」と、まことに鋭い指摘もしている。間違った「しごき」を駆逐するには、正しい上達法が見つけられなければならない。それは、今では各方面で見つけられている。水泳の訓練法などは、ほとんど誰でもうまくなるように教えられるらしい。それは少しも「しごき」を使わなくても一定の水準に達するらしい。だから、最高の水準に達するためには、それなりの自覚をした人間だけに「しごき」をすればいいようになっているようだ。間違った「しごき」を駆逐するには、正しい上達法を積み上げていく努力をしなければならないが、それが難しいところではまだ間違った「しごき」が残り続けるだろう。それは、その間違いを批判することによって今のところは排除することが必要だと思う。少なくとも、死なせてしまうような事故を起こす人間に、「体罰も教育だ」というような間違った発言を許してはいけないと思う。
2006.05.18
コメント(0)
-
「権利」について考える
死刑廃止論の考察においては、「人権」という概念が非常に重要なものとして出てきた。その時に「権利」というものについても少し考えてみたのだが、この言葉は、僕の職業柄「教育を受ける権利」というものとして具体的に関わってくる。「人権」という言葉は、その「権利」を有する条件として「人間である」と言うことがあればいいものとして登場していた。「人間である」と言うことが証明されるなら、必ず「人権」というものが保障されるというのが人権の思想だ。SF的になるが、将来はロボットが人間であるかということが問題になるかも知れない。ロボットに人権があるかと言うことが論じられる時代が来るのは、SFの世界だけではなく現実になるかも知れない。この「権利」という言葉を考える上で役に立つものとして、中山千夏さんは英語の「right」を考えることが有効なのではないかと提案していた。「right」には「正しい」という意味があり、権利の行使の正当性は、その権利が存在することの「正しさ」に根拠を置いていると考えるわけだ。人間であれば、誰でも生きていたいと主張することは正しいと判断出来れば「生存権」というものが生まれてくる。何を思い・何を考えてもいいはずだと考えれば、思想・信条の自由が権利として生じてくる。これは、思ったり・考えたりするだけなら実質的な被害は起きないと言う判断から、その自由が存在することの正しさを帰結出来るからだと思う。また、実質的な被害が起きない限りにおいて表現の自由が存在するのも、権利として捉えることが出来る。この場合は、現実に被害が生じる場合もあるので、無制限の自由ではなくなるとは思うが。ウィキペディアでも「権利」と言う項目に、似たようなことが書かれている。次のようなものだ。「英語は別として、ヨーロッパにおいてはドイツ語の Recht、フランス語の droit、イタリア語の diritto など、法と権利は同一の言葉で表現されることが多く、区別する場合は「客観的」又は「主観的」という形容詞を付する。例えばドイツ語においては、objektives Recht は法の意味であるのに対し、subjektives Recht は権利の意味である。また、これらの語は正義をも意味し、法も権利も正義という観念が支えになっていることがうかがわれる。これに対し、英語の right は正義の意味はあっても法 (law) の意味はない。これは、ノルマン朝時代のイングランドにおいて、専制的な王が臣民に課した law に対立する臣民の right という意味合いで right という語が用いられるようになったことに由来するとされている。もっとも、その後、権利の章典に至り、law と right の対立が法の支配として克服される。」ここでは、「権利」として考えられている概念が、「正しい(正義)」ということのほかに、「法」の意味も併せ持っていることが語られている。これは、「権利」の主張が、その正しさに基礎をおいていて、しかも法によって主張が保障されるという関係にあるのだろうと思う。さて、もう少し「権利」について抽象的に考察していこうと思う。ウィキペディアでは、「権利の意味については様々な見解が唱えられているが、大まかに分類すると、伝統的には、法により保護された利益が権利であるとする見解(利益説)と、法により保障された意思又は意欲の力が権利であるとする見解(意思説)との対立がある。」と書かれていて、どちらの考えにも整合性を取れない場合が存在することが指摘されている。次のような場合だ。「金銭の借主が経済的に困窮している例にすると、このような場合にも貸主には借金を返してもらう権利はあるとされるが、そのことによる具体的な利益があるとは言い難い」「意思・意欲を期待することができない乳幼児は権利の主体になることはできないのかという問題を抱える」どちらか一方が正しいと考えると、それに反する場合との整合性を取れなくなると言うことは、この対象が弁証法性を持っていると言うことだ。だから、この対象を正しく捉えるには、どちらか一方の見解が正しいと結論するのではなく、一方の見解はどのような条件の時に正しくなるかという条件を吟味すると言うことが必要になるだろう。それが弁証法性を正しく捉えた考察になると思う。「権利」の問題は「義務」というものとも深い関わりを持つ。分かりやすい両者の関係は、それが二つの存在に分け持たれている場合だ。「教育を受ける権利」を持った個人がいた場合、その教育を受ける権利に関わる事柄でいろいろと保障されなければならないものがある。例えば学校を作ったり、学校でかかる費用の負担を背負ったりすることが必要になることがある。これらは、「教育を受ける権利」を保障する「義務」がどこかに存在することを意味する。それは、近代国家の場合は、国家が国民の教育を保障する義務を背負うと言うことになるだろう。学校のない地域に学校が必要なら、それを設置する義務を負うだろうし、経済的負担を背負えない個人に対しては、それを援助する義務を国家が負うことになる。「権利」と「義務」という対立した概念を背負う主体が二つある場合は、これは対立していても矛盾にはならない。それを背負うことに「正しさ」があるなら、それは「権利」として確立されるだろう。難しいのは、「権利」と「義務」の主体が同一の存在である場合だ。その時は、対立を背負う矛盾がそこに存在する。この弁証法性はどのように考えたらいいだろうか。これは俗論としてよく聞こえてくる、「権利ばかり主張して義務を果たさない人間には、権利そのものを与える必要はない」というような考え方とも関係してくるだろう。この考え方は、基本的な部分で間違っていると僕は思うのだが、すっきりと論理的に解決出来ないでいる。具体的に僕自身に関わってくる問題としては、学校というものを自分の都合に従って利用するだけで、学校における活動に対して協力する姿勢をあまり見せない人たちに対してどう接するかと言うことがある。このような人たちは、権利の行使はしているけれど、義務を果たしていないように見えるので問題が難しくなる。夜間中学と言うところは、その特殊性から、日本語の出来ない外国人に対して<日本語学級>というものが設置されている。夜間中学は、本来は<中学校>であるから、基本的には中学校課程の教育を保障するところだ。しかし、日本語がまったく出来ない人は、その中学校課程の学習を学ぶために日本語の教育が必要になってくる。だから、本来の目的である中学校課程の教育をする一つの手段として日本語教育が存在しているというのが、夜間中学校の本来のあり方だ。しかし、すでに働いている大人の生徒にとっては、日本の中学校課程の教育は、それほど日常生活で役に立つものではない。そうなると、日本語の学習は一生懸命やるが、中学校課程の学習には気持ちが向かないと言うことが起きてくる。これは本末転倒なことであり、そのような要求の生徒であれば、本来は日本語だけを教える教育機関へ行くべきだと僕も思う。しかし、日本には残念ながら、そのような要求を持つ人たちにふさわしい日本語教育機関がないので、多少の妥協をしながらも夜間中学校へ通う外国人は多い。我々夜間中学に勤める教員は、社会生活を営む人には誰にでも「教育を受ける権利」があるという前提で仕事をしている。ある意味では、日本で生活しているという条件さえあれば「教育を受ける権利」があると考えている。それが、中学校教育であると言うことは、また別の条件、例えば中学校課程を卒業していないと言うようなものがあるが、それをクリアしていれば「権利」としては存在していると考える。だが、生徒の方の姿勢が、日本語教育だけを要求していて、中学校課程の学習には見向きもしないと言うことがあると、その権利の行使に疑問を差し挟みたい気持ちになってくる。権利を認めながらも、権利を否定したくなると言う矛盾をどう処理したらいいかは、夜間中学で仕事をする教員にとっては現実的に深刻な問題だ。この問題の本質的解決は、日本語教育だけを求める人々に本当にふさわしい教育機関が出来ることだったり、中学校課程の学習が、日本での生活をする上で本当に役に立つものに変わっていくことだと思う。しかし、この両方の解決はすぐに出来るものではない。現実には、今あるリソースの中で解決を図るしかない。権利の存在が、その正当性から得られるものであるなら、夜間中学校にやってくる日本語教育を求める人々には、同時に中学校課程の学習も一生懸命やるという義務を持っているということが正しいかどうかを考えてみたいと思う。彼らの権利行使には、一生懸命やるという義務はないのかということも考えてみたい。彼らの出来る範囲でそれに応じればいいと言うことになるだろうか。これは、どちらが正しいか今の僕には結論が出せない。ただ、日本語教育と関係なく、普通の青少年の中学校教育を考えると、現在の中学校課程の学習を「一生懸命やる義務」というのは、それはないのではないかと思える。「一生懸命やってもいい」し、「一生懸命やらなくてもいい」という、どちらも許されるのではないだろうか。「一生懸命やらなければならない」という義務はないように感じる。これは、一昔前なら、一生懸命やることが当たり前で、ほとんど義務のように捉えられていたかも知れないが、中学校課程の学習そのものの価値に疑問が提出される時代になってから、そのような義務感はなくなってしまったのではないかと思われる。役に立つことだと思えるものなら、人間は、人から言われなくても一生懸命やるものだ。かつては、学校での学習はそのようなものとして捉えられていたのではないかと思う。今では、もはや学校での学習をそのように捉える子どもは少ないのではないだろうか。だから、いくら道徳教育を強化しても効果はないのだと思う。今の日本の状況では、一生懸命勉強することが義務だとはもはや言えなくなってきている。だから、問題の解決は、やはり中学校課程の教育を、本当の意味で役に立つものに変えなくてはならないのだろうと思う。それまでは、一生懸命やらないという態度が見えても、何とか人間的な信頼関係でそれを補って妥協していくしかないのかな、というのが今の僕の思いだ。一生懸命さがなくても仕方がない、教育を受ける権利は否定してはいけない、というのが今の僕の考えだろうか。権利と義務の問題は、道徳で解決出来る問題ではなく、ある種の妥協をしながら理想を実現していく過程を探らなければならないのだろうなと思う。
2006.05.17
コメント(2)
-
セクハラについて考える
僕は、昨日のエントリーで筆坂さんの『日本共産党』(新潮新書)を取り上げて考えてみたのだが、その中で、筆坂さんのセクハラ問題を「交通事故にあったようなもの」という比喩をした。この比喩は、かなり微妙な問題を含んでいるのを感じる。まず、日本におけるセクハラの定義だが、「セクハラ」によれば次のように書かれている。「セクハラとは、「性的いやがらせ」のことをいいますが、広くは、「相手方の望まない性的言動すべて」をいいます。 セクハラとなるかは、あくまで平均的な女性がその状況で、そのような言動を受 けた場合、不快と感じるかを基準に判断されます。 とはいっても、特に繊細で不快と感じやすい人の場合でも、不快な言動が続けられた 場合にはセクハラとされることもあり、快か不快かを決めるのはあくまで、そのよう な言動を受けている人ということになります。 」これはかなり問題のある定義だと思われる。この定義が一般的に「セクハラ」と言われるものを判断する基準になっているとしたら、これはかなり恣意的に判断される可能性を持っていると思う。第一の問題点は、「平均的な女性」という基準が曖昧で、何が平均的かを決められないと言うことだ。「快か不快かを決めるのはあくまで、そのよう な言動を受けている人」と言うことになってしまえば、極端なことを言えば「顔を見るだけでも不快」と言うような感情的な女性だったら、存在そのものがセクハラだと言われかねない。上の定義は、いわゆる「差別」の言動の規定とよく似ている。「差別」に関しても、そのような言動を受けた相手が「差別」と感じるかどうかに重点がおかれている。言動をした方には、まったく「差別」意識がなくても、それを受け取った方が「差別」だと感じれば糾弾されるという図式がこれまでもあった。三浦さんは、このような「差別語」の問題に関して、言語というものが元々対象の差異に応じて表現するものであることを指摘して、「すべての言語は差別語である」と言うことから、不当な「差別」になる規定を論じていた。すべての言語が差別語であるなら、どんな発言をしても相手によっては「差別」と受け取られてしまう。しかし、それでは社会的な判断としては成立しない。社会的な判断は、論理的・民主的な合意という妥当性をもっていなければならない。「差別」と受け取ることが、考えすぎの勘違いである場合は、それは「不当性」はないという判断をしなければならない。「セクハラ」の場合も同じような構造を持っていると思われる。セクハラの場合も、それを受ける側に判断の基準を持ってくれば、その判断は恣意的なものになり、どんな言動であってもセクハラになってしまう。それは社会的な判断としては間違っているのではないかと思う。三浦さんは「差別」というものを弁証法的な対象として考察した。同じような言動が、ある時は「差別」になり、ある時は「差別」にならない。これは、その言動がどのような状況の時になされたかによっている。条件の違いによって、真理の判断が違って来るというのが弁証法性の持つ特徴だ。セクハラも、現実に行われる行為であるから、これも極めて弁証法的な対象だろうと思う。同じ行為があるときはセクハラになり、ある時にはセクハラにならない。むしろ深い愛情の表現になる場合もあるだろう。その区別はどこでつけなければならないのか。難しい問題であるだけに、単にその行為を受ける方の感情だけで判断してはならないだろうと思う。勘違いと言うことも大いにあるのだから。筆坂さんの場合も、相手の女性が不快と感じるものをセクハラと判断するなら、これはセクハラと言うことになってしまうのだろう。しかし、筆坂さんの場合は、これまでそのような問題は何一つ出てこなかったと言うことを見ると、少なくともこのような意味での「セクハラ」の常習者ではないと思う。たまたま、あのときだけが、筆坂さんの勘違いで、親密さを表そうとした行為が、なぜか相手には不快に感じられてしまったと言うことなのかも知れない。そうではないかと僕は想像して、「交通事故にあったようなもの」かもしれないと思ったのだ。筆坂さんが、酒を飲んだときに、相手の感情を理解せずにいつでもべたべたしたような行為で相手に不快感を与えているような人間だったら、正しい意味での「セクハラ」だと判断されても仕方がないだろうと思う。しかし、報道を見る限りでは、筆坂さんのセクハラ問題はあの一件だけしか知らされていない。僕は、陰謀説まで主張する気はないが、何らかの勘違いがあったのではないかとする方が現実には理解しやすいと思う。筆坂さんが、共産党中央の権力の座にいたので、そこから追い落とそうとねらっていた人もいたかもしれないが、それは証明するのは難しいだろうと思う。もし筆坂さんが、相手に不快感を与えるという意味でのセクハラ常習者だったら、セクハラで告発されても仕方がないと思われるけれども、そうでないなら、セクハラで告発するのは酷なことだなと僕は感じる。一時の勘違い・過ちに過ぎないのではないだろうか。それも、取り返しのつく過ちだと僕には思える。これで議員辞職までするのは、ある意味では死刑宣告に近い重い刑罰だなと感じる。ただ、筆坂さん自身も、細かい事実を調べて精査するのを望まなかったのだろうと思う。これに対しても二通りの受け取り方があるだろう。セクハラが間違いなかったので観念したのだという受け取り方もある。議員辞職という重い責任の取り方をしたことがセクハラの証拠だという受け取り方だ。しかし僕は違う受け取り方をする。筆坂さんが、あくまでも事実で争うようなことをすれば、それは党に対するダメージがさらに大きくなったり、相手の女性ともかなり不愉快なやりとりをしなければならなくなっただろうと思う。そのようなことをしたくないという思いがあれば、過ちがあったというのは確かなので、何も弁解せずに処分を受けようということを考えたのではないかとも解釈出来る。セクハラの処分を受けたと言うことは、このように解釈すると、むしろ筆坂さんの誠実さを表しているとも受け取れる。以前にマル激にゲストで出ていた沖縄密約事件の西山元毎日新聞記者が、裁判で問題になった女性との関係に関することでは、一切弁解をしなかったということを語っていた。事実とは違うこともあったそうだが、それは何も弁解しなかったらしい。それは、新聞記者として取材源である人物を守りきれなかったという過ちをしてしまったことに対する責任の取り方だったと、西山さんは語っていた。そこでは、弁解をしなかったことは、その事実を認めたことになるのではなく、西山さんの誠実さを表しているのだと僕は感じたものだ。筆坂さんの沈黙にも僕はそのようなものを感じる。筆坂さんは、おそらくセクハラ問題に関しては、これからも細かい事実を語ることはないだろうと思う。だからそれが本当にセクハラだったかどうかは論じることは出来ないだろうと思う。これはある意味では仕方がないだろうと思う。筆坂さん自身がそれを論じることを望まないのだから。議員辞職という重い責任を取ったことで、この問題には一定のピリオドも打ったことになっていると思う。もし、筆坂さんのセクハラ問題を、セクハラとして問題にするのなら、それは筆坂さん自身ではなく、日本のセクハラ問題に疑問を持っている第三者が筆坂さんを応援するという形で提起しなければならなかっただろうと思う。しかし、共産党にはそのような方向でセクハラ問題を捉えている人はいなかったのだろう。僕は、日本におけるセクハラ問題は間違った方向へ行っていると思っている。判断基準を、セクハラを受けたという人間の方へすべて持っていくのは間違いだと思う。セクハラを受けたという告発は気軽に出来た方がいいと思うが、それが本当にセクハラかどうかは慎重に判断する第三者機関がなければならないと思う。当事者の言い分を聞いて即断してはいけないと思う。だいたいセクハラ問題のように難しい判断は、間違えることもたくさんあると自覚して判断すべきではないかと思う。そして、間違えたときの救済もあらかじめ考えておくべきだろう。告発された段階でもうセクハラをしたと決まってしまうのでは、容疑者の段階で犯人と決めつけるような犯罪報道に通じるものがある。セクハラ問題は、男にとっては極めて重大な問題だろうと思う。これを甘く見てくれと言うのではなく、正しく判断して欲しいと思う。そうでなければ、将来的に、男の大部分が女に対して愛情表現をすることを躊躇するような時代がやってきてしまうのではないか。本当の愛情表現なのか、単なるセクハラなのかを正しく区別して欲しいと思う。そして、愛情表現というものなら、女性の拒絶にもかかわらず強引に押し進めると言うことを躊躇する方向へ男の方も努力していくべきだろう。セクハラは、犯罪行為と愛情表現という、非常に広い範囲にわたる判断をする難しい判断があると言うことをもっとよく考えるべきではないかと思う。その典型例を正しく指摘していくことが必要だろう。そうでなければ、深いところで、男にとって反発を残すようなものになってしまうだろう。
2006.05.16
コメント(3)
-
日本共産党批判
日本共産党は左翼陣営にとって巨大な存在である。かつては左翼陣営を代表する社会党が、今では二大政党制としての民主党に吸収されてしまったので、おそらく、影響力の大きさで言えば、左翼陣営としては日本共産党が最大の存在になっただろうと思う。この共産党に、反対の陣営である右翼陣営から批判が集中するのはある意味では当然のことだと思う。むしろ、右翼に批判されないような左翼など、本物の左翼ではないとも言える。だが、日本共産党は、同じ左翼陣営からも強く批判がされてきた歴史を持つ。この批判は、右翼の批判とは違って、本物の左翼ではないという面が批判されてきたように思う。左翼性がまだ生ぬるいというような感じだろうか。僕が師と仰ぐ三浦つとむさんも、かつては共産党に所属していて、スターリン批判をきっかけに除名処分になった。その関係からか、三浦さんは、共産党のマルクス主義理論そのものを間違った理論として、「官許マルクス主義」と呼んで批判していた。障害児教育運動で影響を受けた津田道夫さんも除名処分を受けた人だった。除名処分を受けた人をいろいろ探してみると、各方面での優れた人間が多いように感じる。このように優れた人間が離れていってしまうような共産党の欠陥というものは、左翼陣営として一つの大きな支柱としての役割を担うべき存在としては残念なことだと思う。左翼と右翼というのは、科学的真理のように、どちらかが正しくてどちらかが間違っているというようなものではないと思う。これらがイデオロギーと呼ばれるのは、それが立場として選び取られるものであるからだろうと思う。死刑廃止の問題とよく似ていると思う。死刑廃止は、正しいからそれを選択するという問題ではなく、死刑廃止を選んだ上での社会の構築を目指すという、自己決定の問題として捉える問題ではないかと思う。左翼というイデオロギーも、その立場を選択した上で、自分の生き方をその基礎の上に築いていくというものになるのではないかと思う。もちろん、反対の右翼のイデオロギーを選んだものは、その基礎の上に自分の生き方を築いていくので、両者はイデオロギーと呼ばれているのだろう。左翼も右翼も、その立場が違うので、相手が間違っているという批判は当然のことだと思うが、よくある反共宣伝と呼ばれるようなものは、かつては左翼陣営だった人間が転向して激烈な攻撃を左翼陣営に行うというものが多い。これは、かなりの部分が感情的な攻撃に陥っていることが多い。それ故に、相手を罵って攻撃する分だけ、自己肯定を図っているように見えるので、そこから学ぶことはあまりない。セクハラ問題で議員を辞職し、共産党を離党した筆坂秀世さんが書いた『日本共産党』(新潮新書)という本も、形の上では、共産党に裏切られた恨みや辛みを綴った反共宣伝かも知れないという先入観を持たせるような本だ。しかし、この本はそのような本では全くなかった。筆坂さんは、基本的な思想としての共産主義への共感は捨ててはいないようだ。現実の共産党という組織については、いわば事故に遭ってしまったような感覚でセクハラ問題を受け止めているように感じる。そのような事故を起こすような組織に問題はあるけれども、「坊主憎けりゃ袈裟まで憎い」という感情的なことを綴った本ではなく、真の左翼陣営として、組織のあり方も正しいものであるべきだという提言を語ったもののように読めた。左翼陣営は権力を持たない方だから、すべての面において、正しい行動・行為によって、その正当性を示していく必要がある。そうでなければ多くの人に信頼を持ってもらうことは出来ないだろう。不透明で、不正な組織運営がされていれば、組織内での利権争いには勝てるかも知れないが、大衆運動的には勝てないと言うことは、三浦つとむさんの批判のポイントでもあった。三浦さんは、マルクス主義の理論的な正しさを確信していたし、僕も、三浦さんが語る弁証法を基礎にした理論には高い信頼を感じていた。それが左翼理論だというなら、僕も左翼理論の支持者だと言うことが出来る。しかし、どうも組織としての共産党を支持出来るかと言えば、三浦さんが批判していたこともあり、政治的な支持は出来ないでいた。筆坂さんは、党中央の中枢にいた人間であり、党の組織面を細かい部分までよく知っている人間だ。三浦さんは、学者として共産党にいただけで、政治的な地位は持っていない人だった。だから、その批判も理論的な面が強かったが、筆坂さんの批判は、現実の組織のあり方に関するものが多い。しかも、それは恨みを綴った悪口ではなく、的確にその欠陥を指摘したもののように見える。僕が抱いていた共産党組織への違和感が、この筆坂さんの本によってやはりそうだったかと言うことがよく分かった。民主集中制と呼ばれる共産党の組織原則は、民主的でありながら中央集権的な命令系統を確立するという矛盾を実現するものとして、理論的には正当性を持っている。党中央の方針は、下部組織で徹底的に討議され、それぞれの組織員が、自己決定的にその方針を選び取るという民主的手続きを経て、上部の命令に服従するという中央集権的なあり方の正当性を持たせている。民主的な手続きがなく、上部の命令に服従することを求めれば、上部の恣意的な命令に従うという個人の自由を否定することになってしまう。また、多くの人の力を集結しなければ、大きなこと(運動)も出来ないということから言えば、中央集権的なあり方の必要性も理解出来る。これらの両者を統合して達成するには、理論的には民主集中制という形を取るしかないだろう。これは、理論的には三浦さんも肯定していた。いわゆるプロレタリア独裁の必要性を、三浦さんも同意していたように僕は感じていた。しかし、この民主集中制は、理論的にはその正当性が理解出来るのだが、実際にそれに成功した組織はほとんどないというのが現実ではないかと感じる。日本共産党では、上部の指令を下部が検討するという形を取るものの、その指令の読了率というのは極めて低いそうだ。筆坂さんは、せいぜい3割程度と言っている。3割程度が指令を読んでいて、それで徹底的な議論が出来るとは思えないし、自己決定的にその指令を受け止めて活動するという組織原則が成立するのは無理があると思われる。さらに、末端の共産党員というのは、日常的な活動がたくさんあって、それに追われる生活になっているようだ。特に大きなものが、機関誌である『赤旗』の販売拡大という運動があるらしい。共産党が行う『赤旗』の販売拡大は、商業紙が行う販売拡大とは違うと思うのだが、筆坂さんの本を読んでいるとどうもそれほど変わらないような感じもする。商業紙の販売拡大は、その中身で取ってもらうと言うことはほとんど出来ないので、おまけを付けたり、購読料を下げて取ってもらったりしている。しかし、『赤旗』の場合は、その中身に共感して購読してもらわなければ、いくら部数が増えてもそれだけでは何にもならないのではないかと思う。一番重要なのは、その中身が、人々の要求を分かりやすく捉えて解説していたり、世の中の日々の出来事の中で、一般大衆の利害の問題として見えにくいものを見やすく解説したりして、「目から鱗が落ちる」というような体験をしてもらって、本当にいいことを書いていると言うことで購読してもらわなければならないのではないかと思う。それが、どうも大事なのは部数が増えることであって、セールスマンとしての能力に長けている人間が評価されているような感じもする。それは、まったく本来の思想的なものとは相容れない間違いではないかと僕は感じる。末端の共産党員というのは、非常に献身的で誠実な人が多いと思う。その人たちが、なかなか達成感を味わえずに、いつも追いかけられているような感じで活動をしているとしたら、その理想の高さに比べて、現実に得られる幸せが何と薄いことかと思う。末端で献身的に働く人々こそが満足出来る活動を実現するべきではないかと思う。そのようなことが出来る組織であれば、組織が発展し大きくなっていくだろうと思う。日本の組織というのは、どうして末端が幸せになれない構造になっているのだろうと思う。それとも、これは組織というものが持つどうしようもない属性なのだろうか。マルクスやエンゲルスが考えた抽象理論としてのマルクス主義は、僕は正しい理論だと思う。それが左翼理論だというなら、僕は左翼理論の支持者だ。しかし、僕は左翼組織というもので、支持出来るものに出会ったことがない。組織として支持出来ると思ったのは、仮説実験授業研究会という組織くらいだ。この組織は、完全に自由な自己決定的な組織だった。仮説実験授業研究会では、組織として何かを決定すると言うことは全くない。何かを、その組織の看板を掲げてやりたいとなったら、総会において立候補するだけでいい。しかし、それが認められたからといって、組織がそれを応援することはない。それは、手を挙げてやりたいと言った人間がやるべきもので、同じようにそれに賛同するやる気のある人間がそれをやればいいというふうに考える。もし、誰も賛同する人間がいなかったら、それは手を挙げた一人がやればいいということになる。そんなときに、組織として決定したのだから、決定したものは手伝うのが当然だというような道徳的な原理で動くことはない。もし、誰もそのことに関心を持たないなら、それは民主的な過程を経て消滅するのが正しいというのが、仮説実験授業研究会的な発想だ。民主集中制というのは、このように無関心という意思表明も民主的に受け止めるべきだろうと思う。そもそも読了率が3割程度しかないと言うことなら、それは民主的に否定されているのだと中央は受け止めるべきだ。『赤旗』の部数拡大が大事だというなら、それが大事だと主張する人間でまず頑張ってみるべきだろう。組織決定をしたのだから全員でやるべきだと主張するなら、それではその決定をした人間だけで組織を構成するべきだと言うことになる。そういう組織は、小さな団結しかできない組織になってしまうだろう。『赤旗』の販売拡大の活動はどうも苦手だししたくはないが、その他の大衆に奉仕する活動ならしたいという人間を吸収出来るような組織の方が、左翼陣営としては役に立つ組織なのではないだろうか。『赤旗』の販売拡大をすることが共産党の組織活動だというなら、僕はその組織とはたぶん未来永劫に関わりを持つことはないだろう。筆坂さんは、共産党という組織を離れて初めて見えてきたことがあったと語っている。それは本当だろうと思う。組織内にいると、考えるまでもなく当然だと感じてしまうことがたくさんあるだろうと思う。しかし、その当然のことが、実は組織の発展を阻んでいることもあるのだと思う。単なる罵詈雑言ではない、冷静な指摘が含まれている、この筆坂さんの本は、共産党にとっては自らを振り返る鏡として意義のあるものではないかと思う。
2006.05.15
コメント(0)
-
被害者感情への配慮
死刑廃止論は、被害者への感情の配慮が足りないと言う批判が言われるときがある。加害者に対する報復感情というものがある間は、凶悪犯罪に対して、その罪の重さに応じた死刑もやむを得ないとする考え方だ。しかし、犯罪被害者の遺族である原田正治さんは、たとえ加害者が死刑になろうとも、その感情的な鬱屈は少しも晴れることはないと言うことを伝えてくれている。やり場のない感情のはけ口は、死刑が執行されることでピリオドを打つわけではないのである。むしろそのような複雑な感情が、すべて報復感情で理解されることに原田さんは、被害者が少しも理解されず孤独の中で放っておかれているように感じていたようだ。死刑というもので一段落したのだから、その事件を忘れて新たな一歩を踏み出すものと周りに思われていたことに、原田さんは、自分が理解されていないと言うことを感じていたようだ。原田さんは、弟を殺されたのだが、最初はそれが交通事故として処理されて保険金が下りたらしい。ところが、それが殺人事件と言うことになり、保険金を返還しなければならなくなった。すでに、事故後の処理で使った部分もあり、まとまった金を都合するのにかなり苦労をしたらしい。しかし、そのような日常的な苦労は、報復感情のようには理解してもらえない。報復感情なら、誰もが同情して共感を寄せてくれるのに、そのような日常的な苦労は他人事として誰も助けてくれなかったそうだ。また、裁判の傍聴には毎回行っていたらしい。そのためには仕事を休んでいかなければならなくなる。誠実な原田さんは、出来るだけ仕事の上での迷惑をかけないように配慮して、休暇を取って傍聴に行く前日は、そのための準備に遅くまで仕事をしたようだ。そのような配慮をしていても、それが回数を重ねると、毎回行かなくてもいいじゃないかというような不満が同僚から出てくるらしい。最初の同情は、時間がたつに連れて薄れていき、ここでも、どうしても裁判の傍聴に行きたいという原田さんの気持ちはなかなか理解されなかった。死刑存続の意見を持つ人は、被害者遺族の感情の問題を大きな根拠とすることが多いが、その感情は、報復感情だけにとどまり、それ以外の感情は実はまったく配慮されていないのではないかとも感じる。中山千夏さんが指摘するように、報復感情というのは、実は被害者のものではなく、第三者が自分の中にあるものを被害者に投影して、被害者が報復感情を持つことを期待しているだけなのではないかと思う。中山千夏さんは『ヒットラーでも死刑にしないの?』の中で、本当の意味での被害者感情への配慮をいくつか語っている。僕もそれが本来の被害者感情への配慮のような感じがする。被害者感情へ、本当に深く配慮している人は、中山千夏さんのように死刑廃止を深く考えている人の方ではないかと思う。この本で、中山さんが提案している被害者感情への本当の配慮を考えてみたい。その最初のものは匿名報道だ。原田さんも、交通事故だと思った弟の死が殺人だと分かったとたんに、マスコミの激しい報道のあり方に振り回されたという。これは日常生活が破壊されることを意味する。原田さんは、そのことによって家庭にもひびが入り、家族の間の関係がおかしくなってしまったという。このような報道のあり方はまったく被害者感情を配慮していないものだが、マスコミは「知る権利」をタテにして、被害者の実名報道をやめようとはしない。一般の大衆にとって、実名であることはどれだけ報道価値があるというのだろうか。テレビにとっては、実名でなければ映像が流せないと言うことがあるのだろうが、映像を流すというのは、野次馬的な欲求を満足させるだけの、むしろ無視していい感情だ。映像がなければ視聴率が取れないのだろうが、視聴率を取るために被害者を傷つけると言うことが許されていいはずがない。大衆の側が、そのような下品な野次馬感情を満足させるだけのような報道を無視出来るだけの成熟度を持っていればいいのだが、残念なことに現実に視聴率を稼いでしまうので、そのような下品なワイドショー的な報道が罷り通るようになる。しかし、これは被害者感情を無視する配慮のない行動だ。また、匿名報道という点では、被疑者に対しても匿名を貫かなければならない。原田さんもその著書で書いているが、加害者の姉と息子が自殺しているらしい。加害者本人は、憎むべき犯罪を犯した人間かも知れないが、その家族には直接の責任はない。しかし、マスコミの憎しみを煽る感情的な報道は、その憎しみを家族に背負わせる。これは、形としては自殺だが、本質的にはマスコミが殺したようなものだ。そして、そのようなマスコミ報道を許している大衆は、その殺人に荷担していると言ってもいい。殺人を凶悪犯罪のように非難している人々が、自らそのような行為に荷担していることを自覚せず、善意から犯人を非難しているのだと思い込んでいることが、このような悲劇を生み出している。まさに「地獄への道は善意によって敷き詰められている」のだ。被害者感情を、本当に配慮するのなら、被害者はもちろんのこと、加害者に対しても匿名報道を貫くべきだろう。これは、優れたルポルタージュやノンフィクションが、仮名を使って事件を報告していたとしても、その事件の本質を伝えることが出来ることから、たとえ匿名報道であっても、その事件の本質を伝える報道が可能だということが言える。むしろ、センセーショナルに感情をあおる実名報道は、事件の本質とは関係ない、野次馬根性を満足させるだけだ。中山さんが次にあげる被害者感情への配慮は「補償」というものだ。これは、感情の問題をお金で解決するような不純なものというイメージを与えるかも知れないが、実際にはとても大事な配慮だと僕も思う。原田さんが保険金の返還でとても困ったように、被害者には、経済的な面で思いがけない苦労が舞い込むときがある。その時に、どこか相談出来るところがあれば、少し苦労したとしても被害者はとても助かるものだ。しかし、原田さんは、弁護士事務所や役所に相談に行っても、何ら有効な助言を得られず、結局は自分ですべて解決しなければならなかった。「補償」というのは、実際の金銭面での補償もさることながら、ちゃんとした相談の窓口があると言うことも大事なことだ。それがどこにもないと言うところに、この国は被害者に対して、報復感情以外の感情は何も配慮していない国だと言うことが分かる。中山さんがこの本であげている「補償」の意義は、まったくその通りだと賛同するものだ。次のようなものをあげている。「薬害や公害の被害者・遺族に、国や会社が行う補償には、こんな意味があるだろう。1、国や会社が加害者としての責任を認め、謝罪することの表明。2、被害による経済的損失を補い、被害者・遺族の生活、ひいては人権を守る。 そして、補償にはこんな効果がある。A、社会が被害者・遺族に無関心ではないことを示すことで、彼らを慰める効果がある。B、経済的な生活援助の効果がある。」本来は、こちらの方が報復感情を満足させることよりも大事だと僕は思う。しかし、こちらには誰も目を向けない。特に、統治権力はこのことを自ら主体的には考えようともしない。中山さんもこう語っている。「今、ごくわずかなお金を、厳しい基準に従って被害者に出すようになっているけれど、それはようやく1981年から始まった(犯罪被害者等給付金支給法)。しかも、この法律を作らせた原動力は、被害者遺族自身であった。彼らの熱心な運動によって、ようやく渋々貧弱な法律が出来た。それほどに、国会議員も私たちも、被害者や遺族に対する思いやりに欠けていたのだし、今もそうだから、その法律をもっと充実させようという声など巷にほとんどない。」被害者遺族の本当の感情的側面については、原田さんの『弟を殺した彼と、僕。』という本から、原田さんの率直な思いを読み取ってみたいと思う。当事者でない第三者が、いかにその感情を勘違いしていたかと言うことが分かるのではないかと思う。死刑によって報復感情が満足されるという考えも、実はそれは観客である第三者の感情が満足されるだけであるという中山さんの指摘がある。報復感情は、それが他人事である方がより満足される。そのような論理展開で中山さんはそれを批判している。それはまた、項を改めて考えたい問題だと思う。
2006.05.12
コメント(1)
-
亀井静香さんの死刑廃止論 2
亀井さんの第三の論点である冤罪の可能性について考えてみたいと思う。これは、死刑廃止論者が必ず取り上げるものであるが、亀井さんは元警察官僚だけに、その語り方にもリアリティを強く感じるものがある。実際に冤罪が作り出される現場にいたと言うことの重さを強く感じるものだ。まずは、事実の指摘として、次のようなものがある。「警察時代の私の経験から言いますと、被疑者が逮捕され娑婆(しゃば)と遮断された状態になり、縄手錠をされて引きずり回されるようなことになりますと、異常心理、いわゆる拘禁性ノイローゼになってしまうことが現実に非常に多いのです。 羞恥心も全部見透かされ、すべてを預けてしまうような心理状態です。まるで自分の子どものような心理状態と申しますか、取調官との関係が、王様と奴隷のような心理状態となり、すべて取調官のいいなりになってしまうのです。絶対的権力を握られてしまい、取調官の全くの言いなりになる被疑者がかなり多くいます。」拘禁性ノイローゼでなくても、権力関係にある人間の間には、「言いなりになる関係」というものが出来るだろうことは、自分の日常を振り返ってみてもそう感じられる。近代民主主義国家の市民意識を高めてきた人は、このような権力関係ではなく、対等で自由な関係こそが人間的だという思いを深めるだろうと思う。被疑者は、凶悪犯罪を犯したのだから仕方がないと感じる人もいるかも知れないが、被疑者は、まだ犯罪を犯したと決まったのではないのだ。疑いはかけられているが、それが本当かどうかは分からないと言う「推定無罪」の原則が、近代民主主義国家の取るべき姿勢でなければならない。逮捕されただけで犯罪者であると決まるわけではないのだ。権力関係によって言いなりになってしまうということを問題だと考えられるのは、この「推定無罪」の原則を持っているからだと思う。亀井さんについては、その保守主義のイデオロギーに反発する人もいるだろうが、死刑制度に関する限りでは、近代民主主義国家の市民意識を持っていると僕は思う。その意識が、すべてにわたって貫かれていないことが欠点だとしても、貫かれている死刑制度に関する考察は、非常に水準の高いものとして受け止めることが出来ると思う。死刑制度以前に、このような権力関係からの取り調べを問題にしなければならないだろうと思う。これが冤罪を生む温床になるからだ。冤罪を生む可能性がなければ死刑制度があってもかまわないと言うことではないが、冤罪を生む可能性があることが、死刑制度を否定する根拠になることは確かだ。死刑が執行された後に冤罪であることが分かっても取り返しがつかないからだ。間違いを修正する手段を残すために死刑制度を廃止するというのは、論理的に整合性のあるものだと思う。現実の冤罪の可能性について、亀井さんは次のようなことも指摘している。「今の刑事訴訟の立場からすれば、当事者対等・無罪推定の原則で公判廷に立って公平に行われているかと言えば、決してそうではありません。 しかも今の司法制度の下で、依然として自白が「証拠の王」と言うこと、これは変わりありません。 こうした実態の中では、あらゆる犯罪における捜査や判決には、常に冤罪の可能性があると言うことを我々は冷静に考えておく必要があります。 特に、死刑判決が下されるような重大犯罪においてはなおさらのことです。」この冤罪の存在については、冤罪で濡れ衣を着せられる人の感情を捨象して、一般論として「冤罪で死刑にされるのは、それは何万分の一の確率だから、社会防衛上仕方のないことではないかという人がいます」と亀井さんは語っている。しかし、「無実で処刑される人にとっては、それは自分の百パーセントの話なのであり、何万分の一の話でないのです」と、そのような考え方に反論している。僕は、この反論は正当なものだと思う。もし、確率的に仕方のないことだと主張するのなら、その人は、その論理を被害者の側にも使わなければならなくなる。論理というのは、一般化すれば一般的な対象にはすべて当てはめなければならないからだ。そうすると、社会に犯罪が起こる確率はゼロにはならないのだから、犯罪によって自分の家族が殺されても、それは確率的に低いことだから仕方がないと言わなければならない。冤罪者の存在を仕方がないと片づける人は、犯罪被害者についても、論理的には仕方がないと片づけてしまう人だ。冤罪があるがゆえに死刑廃止をしなければならないと考える、亀井さんのような死刑廃止論者は、加害者のことを考えるだけで、被害者のことを無視していると非難されることがある。しかし、冤罪の当事者は、加害者ではないのだ。むしろ被害者と言ってもいいような人だ。その被害を自分のことのように受け止めることが出来るのが死刑廃止論者なのである。だから、死刑廃止論者は、被害者を無視しているのではなく、被害者のことをも自分のことのように受け止めることが出来る人間だと僕は思う。犯罪による冤罪という被害もなくしたいと考えるのが死刑廃止論者なのだと思う。犯罪による直接の被害者の感情を考えると、死刑廃止に反対だとする人もいる。これは感情論として、もっとも強いものだろう。しかし、「加害者は許せない だけど死刑には反対です」という、犯罪被害者の遺族である原田正治さんのメッセージを読むと、被害者の感情というのが、単純な復讐感情だけではないことが分かる。原田さんの話を聞くと、むしろ被害者と加害者が向き合うことで、お互いを理解し合うことの中に、本当の意味での被害者感情の癒しというものがあるような気がする。アメリカなどでは、犯罪被害者と加害者が対話をするような制度があって、それによって癒される被害者が多いそうだ。日本でこのような努力をしている人々は、むしろ死刑廃止論者の方に多いと言うことを聞いたことがある。被害者感情を理由に死刑存続を望む人々は、復讐感情の方は考慮に入れてくれるが、それ以外のさまざまの複雑な感情に対してはほとんど配慮していないと言うのが実情ではないだろうか。そういう点が、中山千夏さんなどからは、復讐感情は本当の意味での被害者の感情ではなく、第三者が自分で抱いている感情を被害者に投影しているだけではないかと指摘されるのではないかと思う。亀井さんは、「何万分の一の確率だから、社会防衛のためだから、いいじゃないか」という感覚を、自分に損害がなければ他はどうなっても知らないと言う、連帯感のなさとして批判している。「自分さえよければ」という感覚につながることを問題にしている。他者のことを考慮に入れるというのは、道徳的な問題ではあるが、これは実は人間が生きていく上で必要な道徳ではないかと思われる。人間は、協力して、他者の労働によって自分の生活を補って生きていかなくてはならない。金さえ払えば、他者がどんな状態にいようが自分の権利を行使出来るという、社会全体とのつながりを欠いた意識は、人間にとっては危険ではないかと考えているようだ。僕もそう思う。「他人の犠牲で自分だけが幸せになるとか、安全でいたいなどと言う考えが世の中を覆ったら、この世の地獄が来ることは明らかです」という亀井さんの言葉は、単に道徳の押しつけだと受け止めるのではなく、パブリックマインドを語った正しい提言として受け止める必要があるのではないかと思う。他者の犠牲を見過ごしてはいけないのだ。自分がそのような立場に陥ったときに、それに納得がいかないことは、他者のこととして片づけるのではなく、自分のことのように受け止めないといけない。亀井さんのパブリックマインドをもっと感じさせる言葉を最後に引用しておこう。死刑を廃止するという問題が、どのようにもっと大きな問題に関わっていくかと言うことを語った言葉だ。それは、「共生」という言葉と関わっている。文化・習慣・考え方・価値観の違う人々が、いかに「共生」していくかという問題と死刑制度は深く関係があるという指摘だ。「さまざまに異なる民族や国家が一つの共通した価値観を持つことは、国と国とが戦争をしない、テロ行為を起こさせないための基本的な条件です。 そういう意味では、この地球から死刑というものを廃止していく一つの運動になっていくだろうと思うわけであります。 宗教も、歴史も、国家の発展段階も、民族も違う中で共有出来る一つの価値観、それが死刑廃止ではないかと思います。生きとし生けるものに対する共通の価値観、人間の尊厳についての基本的な考えの重なり合いと言ったものが、死刑廃止運動によって生まれてくるのではないでしょうか。 これは、ただ単に制度としての死刑を廃止すると言うだけにとどまらず、とても大きな意味あることだと思います。」実に格調高く素晴らしい言葉だと思う。このような大きな理想に支えられているからこそ死刑廃止を正しいと確信出来るのだろうと思う。これは、理想であるだけに現実に実現することは難しい。しかし、難しいからと言って理想そのものを捨ててしまえば、現実の現象を短絡的に捉えて、その場限りの行き当たりばったりの生き方になってしまうだろう。板倉聖宣さんが言うように、理想を持ちつつ妥協するという姿勢が大事だと思う。大きな理想を守るためには、理想以外の現実にはいくらでも妥協的に振る舞ってもかまわないという姿勢だ。戦争をしない、社会の中で人が殺し合ったりだましあったりしない、と言うことを理想と考えて、そのための努力をしていくということを考えたい。そのための中心に据えることが出来るのは、亀井さんが言うように、死刑廃止を考えると言うことかも知れない。これは簡単には実現出来ないだろうが、これを考え続けることによって理想を守ることが出来るのではないかと思う。
2006.05.11
コメント(0)
-
亀井静香さんの死刑廃止論 1
亀井静香さんの講演をまとめた『死刑廃止論』(花伝社)という本を買った。「死刑廃止 info! アムネスティ・インターナショナル・日本死刑廃止ネットワークセンター」というページに載せられている、「死刑制度の廃止を求める著名人メッセージ」の中の亀井さんの死刑廃止論に深く共感する部分があったので、それをもっと詳しく知りたいと思ってこの本を買った。この本を読んで思うのは、その主張がほとんど中山千夏さんと変わらないことだ。中山さんは、いわゆる革新派の議員で、亀井さんは保守本流の自民党議員だった。まったくイデオロギー的には違う二人が、死刑廃止論という点では見事に一致する。これは、死刑廃止論が、イデオロギーを超えた客観的な真理性を持っていると言うことではないかとも思う。少なくとも、抽象論のレベルでは、正しい論理展開をしていけば、同じ結論に到達するのではないかと思う。亀井さんの講演は、まず「人の命や自然環境を大事にしない社会は、健全な社会ではない」という社会観を表明する部分から始まる。この前提があるからこそ死刑廃止論という結論へ論理的に展開していくのだ。亀井さんは、南米の革命家であるゲバラを尊敬しているという。その心情が、この信念と結びついているのだろうと思う。僕も、「モーター・サイクル・ダイアリーズ」という映画を見て、ゲバラの魅力を知った。ゲバラの素晴らしさは、貧しい人や虐げられた人への共感能力の高さと、その共感を自らの行動に結びつける連帯の意識の高さだ。映画では、ハンセン氏病の施設でボランティア的な活動をするゲバラが、手袋をせずに素手で病人と接する姿が描かれていた。病理学的な知識によって感染しないことを確信しているとは言え、その時の世間の常識に従えば、手袋をしたとしても不思議ではないが、断固として素手で接しようという姿に、病気で苦しんでいる人々と本当の連帯をするのだというゲバラの決意が感じられた。ゲバラの連帯意識は、パブリックマインド(公共心)の最たるものだと思う。そのゲバラを尊敬している亀井さんは、やはり強いパブリックマインドの持ち主であろうと想像出来る。これは政治家にとってもっとも必要な資質だ。政治家を私腹を肥やすような仕事だと思っている人間は、いくら権力を握っても一流の政治家とは言えないが、パブリックマインドを持った人間は、たとえ選挙に敗れるようなことがあっても一流の政治家と言えるだろう。幸いなことに先の選挙で亀井さんは広島で当選した。ホリエモンと亀井さんを比べたとき、そのパブリックマインドの差は歴然としている。ブームに流されることなく亀井さんを選んだ広島の人々に大きな拍手を送りたいと思う。その亀井さんが語る死刑廃止論は、非常にわかりやすく、3つの論点をあげている。第一の論点は次のものだ。「国家権力が、犯罪者に、凶悪犯罪をやったと言うことで命を絶つ、国家権力が手足を縛って命を絶つと言うことは、近代国家においてやるべきではない。昔からやるべきでなかったとはもうしませんが、現在においてもそれを続けていると言うことは、日本民族の恥ではないかと、このように思っているわけです。」亀井さんも、国家の行為としての死刑を問題にしている。そして、近代国家においては、このような制度は廃止すべきだと主張している。近代以前の遅れた国家では、「人の命や環境」を第一に考えることが出来なかった。だから昔については仕方がなかったとも言えるが、日本が近代国家になったというのなら、これは廃止すべきだというのが亀井さんの主張だ。感情的な反発に対しては、「憎悪と報復の連鎖を断つ」のが、やはり近代国家の市民のあるべき姿ではないかという主張をしている。「憎悪と報復の連鎖」は、終わり無き殺し合いをもたらすだけであって、世界中のテロ行為を見れば、それがよく分かる。また、この「連鎖を断つ」ためには、「人間の心の中には、悪魔と天使と仏が同居している」という人間観を持つことが必要だという指摘も頷けるものだ。この人間観は、とても深い洞察を含んだもので、短絡的な感情に流されるのではなく、物事を総合的に深くつかんだ末に出てくるものだろうと思う。亀井さんのパブリックマインドの深さから来るものだと思う。「国家が悪魔を退治していく。これは極めて大切な仕事であります。しかし、同時に人間の中に宿っている仏の心と言いますか、天使の心を引っ張り出していく、そう言う努力を国家がやらなければならないのではないかと思います。悪いものを制裁するという国家だけであってはならないのではないか、私はこのように思っているのであります。」と語る亀井さんには感動的な共感を覚えるものだ。亀井さんに対する尊敬の念が高まってくる。このことを、そんなものは理想論だと切って捨てたい性悪説の人間観を持っている人がいるかもしれない。しかし、そう言う殺伐とした性悪説が、「人の命や自然環境」を大事にしないことは明らかだ。この前提を持つと言うことが、人間の心の中の天使や仏を信頼することを選択するという姿勢に結びついてくる。すべてはこの前提にかかってくることになるだろう。亀井さんの第二の論点は、「死刑に犯罪抑止力はない」と言うことだ。これは、元警察官僚だった亀井さんの言葉だけに、非常な重さを持った言葉だと思う。死刑があれば凶悪犯罪を犯さないと言う意識を人々は持つという主張に対して、亀井さんは次のように反論する。「死刑があるから犯罪を犯さず、死刑がなければどんどん人を殺してしまうと言うような、そのような理性的判断を元に犯罪を犯すというようなことは、ほとんど無いと思います。ごくわずかな例外はあるでしょうが、多くの人間にとっては、死刑制度の有無と、犯罪を犯す、犯さないと言うこととには関係がないと思います。」僕がこれに賛成するのは、多くの犯罪が、感情に流されて行われるものが多く、確信犯的に用意周到に計画されることは少ないと思うからだ。以前にも例として引いたが、イタリアの古い映画「刑事」では、こそ泥に入った青年が、そこの女主人の突然の帰宅に気が動転して、理性的な判断をすることなく殺人を犯してしまった。彼は、こそ泥さえしなければ、小心で善良な青年だった。マトモに働かず、人を殺して平然としているような極悪人ではなかった。確信犯的に殺人を犯しても平然としていられる人間は、推理小説の中にしかいないのではないだろうか。まともな人間だったら、感情に流されずに人を殺してしまうと言うことはないのではないだろうか。亀井さんが語るように、「生まれながらにして社会的に危険な人」は、「病理学の世界に属するごく一部」ではないのだろうか。人間が凶悪犯罪を犯すのは、「生まれ育った環境とか、社会の状況」というものが大きいという亀井さんの指摘は頷けるものだ。もし犯罪を犯した人間が、「まったく別の環境にあったとしたら、必ずしも凶悪犯罪を起こすことはありません」と亀井さんは語っている。これも、警察官僚として、多くの犯罪者を見てきた経験から、このような言葉が出てくるのだと思われる。社会は、このような犯罪者を抹殺することで犯罪者を一掃することは出来ない、と亀井さんは言う。社会に、犯罪者を生むような温床があれば、それは偶然そのような環境に陥った人を犯罪者にしてしまう可能性がいつも存在する。だから、社会全体のことを考えれば、そのような環境をこそ何とかしなければならないという結論が出てくる。これが、亀井さんが言う「人の命や自然環境を大事にする」と言うことだ。この前提は、社会全体のことを考えるという、高いパブリックマインドから出てくる前提なのだと思う。死刑に犯罪抑止力があると思っている人に対する次の具体的な事実の指摘は、一つの反例として正しいものだと思う。「よく、死刑制度は犯罪の抑止力になっているのではないかと言うことを言われます。 しかし、もしそうであれば、死刑制度を続けているアメリカや日本では凶悪犯罪がどんどん減らなければいかんわけです。 現実は逆で、激増しているわけであります。しかも、未だ経験したことの無いような、凶悪犯罪が、アメリカでも日本でも増え続けておるわけです。 また、では死刑制度を廃止した国々で、凶悪犯罪が増えているかと言えば、そう言うことも報告されておりません。 そうしたことも、死刑制度が抑止力になっているとは言えないことの客観的な証明になっていると思います。」犯罪の抑止には、死刑制度は直接的な影響はあまり与えていないと受け取るのが正しいと思う。むしろ、社会的な環境が大きいだろうことは、マイケル・ムーアの「ボウリング・フォオ・コロンバイン」などを見ていると感じるものだ。銃の所持が認められているアメリカとカナダを比べてみたとき、銃の使用による殺人は、カナダの方が圧倒的に少ない。この映画によれば、カナダの人はドアに鍵さえかけないとも報告されていた。社会的に、犯罪が極めて少ない環境にあるのだ。カナダは、ちなみに、1998年にすべての犯罪について死刑を廃止している。カナダの犯罪の少なさは、死刑との関わりではなく、社会的な環境との関連で理解した方が正しいだろうと思う。亀井さんの第三の論点は冤罪の可能性を論じるものだ。これは項を改めて考えてみたいと思う。
2006.05.10
コメント(5)
-
「自由」について考える
今週配信されたマル激には衆院議員の保坂展人さんが出ているのだが、保坂さんの話の中で非常に興味深いものがあった。それは、内申書裁判で有名な保坂さんが、教師との会話の中で聞いたというものだった。保坂さんは、非常に主体的な人間だったので、かなりの強い自己主張の持ち主だったと思う。その自己主張に対して、教師の側は、保坂さんが何を考え・何を思おうと、それ自体は保坂さんの自由だという。思想・信条の自由だというわけだ。しかし、それを表明して他の人間に影響を与えるのはいけないというのだ。ビラを配ったりする行為はいけないというのが、教師の主張だった。これは、教師である僕が言うのは変な感じもするが、この教師の「自由」に対する考え方はおかしいと思う。この教師は、心の内面としての思想・信条の自由は認めているけれども、それと深い関連を持っている「表現の自由」を認めていないからだ。「表現の自由」のない「思想・信条の自由」などと言うものが考えられるだろうか。保坂さんが語った教師の考えでは、表現すること自体がいけないという意味ではなく、表現することによって引き起こされる事態が「迷惑」だと言っているのだと思う。その「迷惑」は自分たちにとって困る事態だから、それはいけないと語っているのだと思う。しかし、それならば、その「迷惑」が禁止されるほどのものだと言うことをちゃんと証明する必要があるだろう。「迷惑」だと思うことは仕方がない。これは内面の問題だからだ。しかし、「迷惑」だと言うことで禁止するという、現実的な行動に結びつく場合は、その行動の正当性を証明しなければならない。教師の判断の方が正しく、保坂さんの判断が間違えていると言うことは、証明抜きに決まっていることではない。具体的な行為に沿った考察でそれは証明されなければならない。その考察なしに、教師の権威で保坂さんの行為を禁止していたように僕は感じたので、その教師の論理を変だと思ったのだ。このことは一般論として考えても面白いと思った。「表現の自由」には具体的な行動が伴う。その表現によって影響される人間が必ず出てくる。だから、そこでは、具体的な現象に対して、何らかの制限が必要になってくることも想像出来る。「表現の自由」は、無制限の自由ではなく、それが実際に実現されるときは、いつでも何らかの条件付きで実現されると考えなければならない。表現の自由があるからと言って、どんなことでも表現してもかまわないと言うわけではない。もっとも大きな制限は、プライバシーに関するものだろう。個人がプライバシーとして守りたいものは、他人が勝手に表現するわけにはいかない。この制限は論理的に納得出来るものだ。では、「思想・信条の自由」は、表現さえされなければ、心の中で思うだけだから、どんなことを思おうと自由だろうか。これは、他人に決して知られないものであれば、それを非難することも出来ないのであるから、原則的には自由だと言えるだろう。問題は、その内心の思いを知ることが出来たとき、どこまでを「自由」だと言えるかと言うことだろう。本人がことさらにそれを表現したいという意図を持っているなら、その表現することに伴う責任は生まれてくるだろう。この表現に対しては、実質的に影響が出た段階で責任を問うのか、それとも表現した時点ですでに責任を問うのかは難しい問題だ。ある種の表現に関しては、表現した時点で責任を問うというものが、今話題になっている共謀罪だろう。共謀罪は、「自由」に関する一般論とも関係していると思われる。凶悪犯罪に関しては、その意図を表現した時点で責任を問われるのは仕方がないことだろうか。例えば、殺人というような凶悪犯罪では、「殺してやる」というような言葉を吐いただけで、その人間は裁かれるべきだろうか。これは判断が難しいと思う。人間というのは、感情的な動物だから、「殺してやる」と思う感情はすぐに生まれてくるが、それを実際に実行する人間は少ない。感情が収まると、そのような気持ちが冷めてくるからだ。映画「12人の怒れる男」では、理詰めで追求してくる一人の男(ヘンリー・フォンダが演じていた)に対して、理屈ではなく感情で容疑者の少年を死刑にしたいと思っていた男(リー・J・コップが演じていた)が、激高して「殺してやる」と叫んでいた場面があった。その男は、もちろん、本当に殺すつもりはなかった。激高した感情が、そのように叫ばせてしまったのだ。もし、表現しただけで罪に問われるのであれば、感情に流される人間は、さまざまな場面で罪に問われそうな恐れが出てくるだろう。これは果たして正しいのか。もし、凶悪犯罪であると言うだけで、表現したとたんに罪に問われるのであれば、人間は感情的な表現をしてはいけないと言うことが、道徳ではなく法律で規制されると言うことになる。本来道徳的に規定すべきことを法律で規定してひどい結果になったというのは、すでに禁酒法や生類憐れみの令という歴史的な経験がある。それを繰り返すことになるのではないか。表現したとたんに罪に問われるというのは、もっと厳しい条件が必要だろう。それが表現されたと言うことだけで大きな影響を与えるのだと言うことが証明されなければならない。共謀罪は、機械的に4年以上の刑罰に及ぶものを対象にすると言うことではなく、本当に、それが表現の自由を制限してまでも規制する必要があるのだと言うことが納得出来るものに適用されなければならない。僕は、犯罪的な意図であっても、少しも実効的な準備をせずに、単に表現しただけであるなら、罰則の対象にしてはならないと思う。それは、まったく空想的なもので戯言と呼べるものかも知れないし、もしかしたらある種の芸術表現かも知れないのだ。実際の犯罪は恥ずべきものだが、推理小説における殺人は、芸術として楽しんでいるものになっている。表現するだけで罪に問われるのなら、このような推理小説的なものが許されるという根拠が無くなってしまう。実際に責任を問われるのは、考えただけのものではなく、表現されただけのものでもなく、具体的な準備をして実行に移そうという意図が明確に判断出来るものだと思う。その段階に至っているものなら、たとえ実行前であろうとも罪を問うことが出来るだろう。しかし、表現しただけのものは、罪に問えないと僕は思う。しかし、それでも、重大な犯罪については、その段階で見逃すのは手遅れになるのではないかと心配する人もいるだろう。だが、もし重大な犯罪を計画している人間がいたとしたら、彼らはそんなに簡単にその犯罪に対して表現をするだろうか。それが重大であればあるほど、外に対しては表現をしないのではないか。そのような重大な犯罪を未然に防ぐには、彼らの表現を見るのではなく、具体的に何をしているかという行動を見なければならないのではないか。もし、そうせずに、何を表現しているかに規制をかければ、犯罪的でない普通の人の行動に大きな規制をかけることになる。自由が失われていくことになる。普通の人の行動に規制をかけると言うことは、権力の側に大きな力を与えると言うことになる。自由に率直にものが言えなくなれば、権力批判などと言う危ないことを語る人間はいなくなる。かつて収容所国家などと呼ばれた旧ソビエトのように、反体制という思想だけで刑罰を与えられる国家になってしまうだろう。多くの人が非難する「北朝鮮」よりもひどいことになるのではないか。宮台真司氏は、「自由」というものを選択肢の問題として考えていた。選択肢が与えられていて、その選択肢のどれをも選ぶ可能性が与えられ、どの選択肢を選ぶのがもっとも最適かという判断能力があるときに、もっとも「自由」が実現された状態という風に見ていた。この「自由」が拡大することは、人間の文化の発展でもあると僕は思う。選択肢が増えることが望ましい。選択肢を減らし、「自由」を制限する方向に向かうのは、文化の発展の逆行だ。「表現の自由」を失うことは、やがて内面の自由である「思想・信条の自由」も失う方向へ行くだろう。規制され、選択肢が狭まれた表現の自由しかなければ、その狭められた範囲内で考えるしかなくなる。戦前・戦中の軍国主義下での生活を想像すると、その非人間的な姿が想像出来る。自由を失うことは人間でなくなることと一緒だ。権力の側は、現在における不安を煽って、安全の確保と引き替えに多少の自由を制限するのはやむを得ないという宣伝をしてくるだろう。アメリカは、それが今かなりひどい状況になっているらしい。共謀罪などというものが提出されている日本でも、その傾向が強く出ていると思われる。多少の自由の制限が、やがてはすべての自由の制限に結びついて来るという、軍国主義の経験は、すでに風化してしまっているのかも知れない。しかし今こそ敏感にならなければならない。今が不安が強い時代だということは確かだろう。しかし、それは自由を制限することで解消出来るものなのか。自由を制限しても、なおかつ安全が確保出来ないのではないか。それは、むしろ統治権力の民衆への監視を強めていくだけのことになるのではないか。実質的な安全の確保は、難しいだろうが、庶民にとっては連帯の意識を高めて、仲間だから傷つけてはいけないのだという道徳を復活させることで実現されるのではないかと僕は思う。庶民にとっては、連帯して助け合い、平和を確保して豊かさを分け合うことこそが、本当の安全の確保になるのではないか。
2006.05.09
コメント(0)
-
国家権力の暴走に対する「恐れ」の感覚
昨日は「人権感覚」というものを身につけることの難しさを考えたが、日本においては国家権力に対する感覚を磨くこともたいへん難しいものになっているように思われる。自由や民主主義を、国家権力との戦いによって勝ち取ってきた西欧なら、国家権力はよく監視していないと暴走するという感覚は普通のものだと思われる。しかし、日本では、水戸黄門に代表されるように、「お上」は正しい判断で民を救うものというイメージがあるせいだろうか、国家権力が暴走するという恐れよりも、正しい判断をお願いするという意識の方が強いのを感じる。死刑廃止論の抽象論の前提としては、死刑制度というような強大な権力を、その時の統治権力に与えることの恐れの感覚がある。統治権力が民衆のことを配慮して、その時のもっとも望ましい判断を常にしていると考えるのは幻想だ。むしろ、その時の利権が大きく影響して、もっとも強い力を持っているものに対して、その利益を誘導するような判断をするものだという理解が正しいと思う。このような理解は、近代民主主義ではごく当然だと思うのだが、日本ではこのような考えを持っただけで反体制派だというような受け取られ方をするだろう。しかし、時の統治権力を監視し、批判的にそれを見ることは、権力の暴走を防ぐという失敗に対する姿勢に過ぎない。時の統治権力を倒して、代わりの権力を打ち立てようと言うような考えではないのだ。それすらも許さないような空気を日本社会が持っているとしたら、日本はまだ近代民主主義国家になっていないと言うことになるだろう。今週配信されたマル激では、社民党衆議院議員の保坂展人氏を迎えて、最近国会に提出されている一連の新法案が議論されていた。話題になっている「共謀罪」なども語られていたが、これなどは、統治権力に対して実に強大な力を与える法律になっている。実行する前の段階で犯罪の取り締まりが出来ると言うことが、戦前・戦中の「治安維持法」によく似ている所なんだろうと思う。これを恣意的に適用されたら、統治権力にとって都合の悪い人間は全部犯罪者にすることが出来る。統治権力に対する暴走の恐れという感覚があれば、このことだけで「共謀罪」に反対する理由がある。しかし、それが薄いときは、かえって「共謀罪」を支持するような勘違いさえ起きてしまうかも知れない。オウム教団が行った、地下鉄サリン事件のような無差別殺人は、それが起こってしまってから対処するには、あまりにも犠牲が大きすぎる。だから、この種の犯罪に対しては、犯罪が起こる前に防止する必要がある、と言う論理は理解しやすい。確かに、この種の犯罪だけを取り締まるのであれば、「共謀罪」にも意義があると言えるだろう。だが、法律の適用というのは、ある意味では抽象的な普遍性を持っている。濫用の恐れがある場合は、正当に使われた場合のメリットと、濫用された場合のデメリットを比べて、どちらが民衆にとって結果的な利益になるかを判断しなければならない。その際に重要なのは、国家権力は暴走するという恐れの感覚だ。「共謀罪」の濫用でもっとも恐れなければならないのは、スパイを送り込んで陥れることが出来ると言うことだ。これが許されるなら、統治権力にとって都合の悪い人間を「共謀罪」で排除することが出来る。「共謀罪」は、本当の犯罪者を逮捕することも出来るだろうが、犯罪者ではない・統治権力にとって都合の悪い人間も逮捕出来てしまう。このような権力を与えることに対して恐れを感じることが民衆の側には必要だろうと思う。死刑廃止の問題も、感情論によって、廃止すべきではない・存続させるべきだと言うことが語られる。しかし、廃止しようと言う考えの基本にあるのは、これが国家にとって都合の悪い人間に使われる恐れが充分にあるという恐れの感覚だ。中山千夏さんの『ヒットラーでも死刑にしないの?』によれば、死刑になるような犯罪は次のようなものらしい。・内乱罪(の容疑者)…死刑または無期懲役・外患誘致罪(外国が日本に対して武力行使する元となるような活動をする罪)…死刑・外患援助罪(日本に対する外国の武力行使を手伝う罪)…死刑または無期もしくは2年以上の懲役・現住建造物放火罪…死刑または無期もしくは5年以上の懲役・建造物浸害(水を出して建物などに水害を及ぼす罪)…死刑または無期もしくは3年以上の懲役・汽車転覆罪(の致死)…死刑または無期懲役・往来危険罪(の致死)(汽車や電車の往来を妨害した結果、人を殺す)…死刑または無期懲役・水道毒物混入罪(の致死)…死刑または無期もしくは5年以上の懲役・爆発物使用罪(治安妨害や他人の殺傷を目的として、爆発物を使用、または使用させる罪)…死刑または無期もしくは7年以上の懲役または禁固個人の権利を脅かすものよりも、統治権力の権力的な側面を直接脅かすようなものが多いように感じる。個人の権利を脅かすものは、例えば「強姦致死罪」は、「明治時代から今日まで「無期または3年以下の懲役」のままだ」と中山さんは書いている。これを死刑にしろと言うことではないが、何を死刑にするかという判断において、統治権力にとってどのような意味を持つかという点が大きなものだというのを、ここからも感じることが出来る。統治権力に対する恐れの少なさが、逆に統治権力に対する「お上意識」となり、自分たちに何かをしてくれることを期待するメンタリティをつくる。これを、宮台氏は、「くれくれタコラ」と呼んでいた。統治権力に対して、何でも「してくれ」と要求するメンタリティだ。治安維持に対しても、監視カメラを増やしたりなどして、警察に何とかしてくれと要求する心情が強いのではないだろうか。警察が何とかしてくれる面があるには違いないが、それによって強大な権力も与えると言うことの恐れの面は薄い。自分は、その権力によって弾圧される側にはいないのだという素朴な思いが強いせいだろうか。しかし、弾圧されるかどうかは、一般庶民にとっては偶然の結果にしか過ぎない。本当に権力の近くにいる人間でない限り、弾圧される可能性は常に存在するのだ。被害者であるにもかかわらず、容疑者の疑いをかけられた河野義行さん(松本サリン事件被害者)は、権力によって弾圧された庶民だと僕は思う。権力にとっては、松本サリン事件という大きな事件に対しては、どうしても犯人が必要だったと思われる。このような大きな事件の犯人が見つけられないことは、統治権力の失態になってしまうからだ。河野さんは、たまたま化学の専門知識を持っていて、薬の調合が出来そうだということから疑いをかけられた。このような偶然から、国家権力ににらまれた場合弾圧される可能性が出てくる。幸いなことに、河野さんの場合は、オウム教団という真犯人が見つかったので冤罪であることがはっきりしたが、もし真犯人が見つからなかったら、冤罪のまま葬られていたかも知れない。これが、誰にでも起こりうるものなのか、自分には関係ないと思うか、それは、国家権力への感覚によって決まるのではないだろうか。アメリカでは、たまたま原爆製造者の関係者が親族にいたと言うことで、ローゼンバーグ夫妻は、国家権力の弾圧で死刑にされた。国家権力は、ローゼンバーグ夫妻が罪を認めれば死刑にはしないと言う取引もしてきたそうだ。それは、国家権力にとっては、どうしても犯人が必要だったと言うことを意味している。犯人になってくれるなら誰でもよかったのだ。偶然、その罪を押しつけられる存在としてローゼンバーグ夫妻が選ばれたに過ぎない。冤罪として訴えられている事件のほとんどは、誰かを犯人にする必要があった国家権力が、偶然疑いをかけられる相手を選んで弾圧しているのだと考えられるのではないかと思う。その偶然は、誰にでも訪れる偶然だと受け止めるのが、国家権力に対する暴走の「恐れ」ではないかと思う。和歌山毒カレー事件の林被告は、まだ冤罪だと決まったわけではないが、状況証拠ばかりで物証がないと言われている。もしも、この状況証拠だけで死刑判決が出されるようなら、僕は、これも国家権力による庶民への弾圧ではないかと感じる。たとえ、林被告がどれほど真犯人に見えようとも、状況証拠だけで死刑を出してはいけないと考えるのが、国家に対する「恐れ」の感覚ではないかと思う。中山千夏さんは、本当の意味で治安を確立させるためには、平和が必要だと主張している。正義のために人を殺すことを正当化するような戦争は、日常生活においても正義のための殺人を肯定してしまうだろうからだ。僕もその通りだと思う。そして、平和に加えて、豊かな生活を実現することが治安の基礎でもあると思う。犯罪の温床になるのは、鬱屈した不満というものだ。それを出来るだけ少なくしなければ、どれほど重罰化をして犯罪は減らないだろう。犯罪を減らすために警察権力を強めるという発想は、国家権力に対する「恐れ」の感覚が薄いと思う。それは、近代民主主義を支える市民が取るべき発想ではない。自らの自由を脅かし、国家の弾圧を容易にするような方向は、民主主義的な方向ではない。平和と繁栄と言うことが治安のための条件だと言うと、中山さんも言われたように、それは理想論で非現実的だという答が返ってくるだろう。確かに、これをすぐに実現することは難しい。しかし、それでは、これ以外にどのような現実的に実効性のある方法があるだろうか。警察権力を強める方向が実効性があるとしても、それは、将来きっと民主主義に危機をもたらす。民主主義を守る方向としては、平和と繁栄を求めて努力する以外にはないのではないだろうか。民主主義にも欠陥はあるし、平和と繁栄を求めるのも難しい。しかし、それは今のところ、他のどの道よりも健全な方向を向いているのではないかと思う。他にもっといいものが見つかるまでは、この方向を向いて努力するしかないのではないだろうか。だからこそ、今のところは死刑廃止が正しいと思うし、国家に対する「恐れ」の感覚を鋭く持ちたいと思うものだ。
2006.05.08
コメント(2)
-
「人権」について考える(続き)
さて、「人権」についてもう一つ大事なことが中山さんの本には書かれているので、それを考えてみたいと思う。それは「人権感覚」と呼ばれるものだ。「人権」というものを、その歴史的な成立過程を理解することで、人間であれば誰でも持っている当然の権利だと言うことを、その「正しさ」から導くことが出来た。「自由権」「参政権」「生存権」「社会権」などというものが正しいというのは、入れ替え可能性というものを想定することによって得られるのではないかと思う。もし、この諸権利が、「人権」として保障されていなかったとしたら、自分は、その権利を持たない状態にいたとして納得出来るだろうか。この諸権利を自分が持っていなかったら、社会生活を営む上で大きなハンディを持つことになるだろう。そのハンディは、ある種の条件の下であれば仕方がないとあきらめることの出来るハンディだろうか。これは、普通の状況であれば、ハンディを持たせることが不当になるだろう。このハンディを許さないという感覚が、人間が当然持っているはずの「人権」というものの感覚になるのではないだろうか。誰もが当然持っていると考えられる権利を、頭で理解しているだけではなく、身体でも実感出来ると言うことが「人権感覚」と呼ばれるものではないかと思われる。これはなかなか身につけることが難しい感覚だと思われる。自分の「人権」が犯されるという感覚は、自ら感じることの出来るものだから分かりやすい。しかし、ここで言う「人権感覚」というものは、他人の人権が侵されるときに、それを自分の人権が侵されるのと同じように感じられるかどうかという感覚になるからだ。死刑囚だから人権が侵されても仕方がないと思うような感覚では、人権感覚が身に付いているとは言えないだろう。たとえ死刑囚であろうとも、その人権が侵されていることを敏感に感じ取ることが出来たとき、人権感覚が身に付いていると言える。これは、「惻隠の情」で埋め合わせることが出来る感覚ではない。人権というものを、本当に深く理解したときにようやく身に付く感覚だ。中山さんも次のように語っている。「戦後に育った私たちも、基本的人権としての諸権利を、実感としてきちんと把握しているとは言えない。可哀相な人を助ける慈善の精神や、何か安っぽい人間中心主義と混同されているような感じさえある。」この人権感覚を身につけるのに邪魔になるのは、「けちな根性」だと中山さんは指摘する。けちな根性を持つ人は次のような考えを持つ。「私はこんなにたくさん税金を出している。隣のA氏は病気がちで働かないから、全然税金を出していない。それどころか、近所からものをもらったりお金を借りたりして生活している。そのA氏が私と同じように投票し、政治に口を出すのはおかしい。それでは、せっせと働いて税金を納めている私は損ではないか」このような考えは、「けちな根性」だと中山さんは言うのだ。その理由はこうだ。このお金持ち氏は、病気でもなくお金もあると言うことで、普段の生活ではA氏よりもずっと得をしていることになる。それを、ただ一点だけを見て「損」だというのなら、その生活をA氏と入れ替えることを提案してみるといいと中山さんは言う。本当に「損」であって、A氏の方が得だと思っているのなら入れ替える方を望むだろう。しかし、その提案には賛成しないだろう。結局、普段の得はそのままにしておいて、一点だけの損を埋め合わせたいとする欲は、「けちな根性」だと中山さんは言うわけだ。普段の損を埋め合わせるためにこそ、人権というものを保障して平等を確保しようと言うことを人間は歴史を刻むことで学んできたのだ。自分の欲を満たすことだけを考えて、他人が不幸になろうと知ったことではないと思っているなら、そのような金持ちは「けちな根性」の持ち主だと言われても仕方がないだろう。人間は、この「けちな根性」を克服して人権の考えを身につけたと中山さんは考える。次のように語っている。「人はみんな、さまざま違った条件を持って生まれ、時代や運に左右されて、得をしたり損をしたりする。それを運命だとあきらめていたのが、近代以前の人類だ。人権の考えはそれを変えた。人はみんな人として同じ、平等で自由であるべきだ、だから人の知恵で均せる損得、不平等は解消しよう、そう人々は考えついた。貧乏な人、元々損をしている人を政治参加させないのは、その人の運命的な損の上に、さらに損を法律が付け加えることである。その不平等を解消したのが、普通参政権の実現だった。」実に明快な人権の論理だ。金持ちが、「けちな根性」で自分の損を感情的に収めるのではなく、人権の考えとして平等を受け入れるなら、高貴な精神を持った人間として尊敬されることだろう。それが近代以後の市民というものだと思う。このような人権感覚を持たない人間は、近代以前の古くさい頭の持ち主だと言われても仕方がないだろう。人権感覚を身につけると福祉に対する考えも変わってくる。福祉というのは、金があるものが貧乏なものに対して施しを与えるようなものではないのだ。中山さんは次のように語っている。「人権による福祉は、これとは違う。人はみんな同じ、平等で自由であるべきだ。それが当然のこと、正しいこと、つまりライト(人権)だ。だから、人々はみんな等しく、衣食住に満足し自由に行動するのが、当然のこと、正しいこと、ライツ(諸権利)だ。従って、もし、身体的な条件や経済的な条件で衣食住に困り行動が不自由な人がいたら、その人が出来るだけみんなと等しい自由な暮らしが出来るように、社会は計らわなければならない。それが当然だ。と言うのが人権による福祉の感覚だ。ここには、福祉を受ける人のためになるかどうか、とか、受ける人の態度がいいかどうか、といった、する側の判断が入る予知はない。そこが慈善の福祉と大きく違う。」僕もまったくその通りだと思う。このようなことに対して「当然だ」「正しい」と思える感覚こそが「人権感覚」というものだろう。このような感覚が身に付くと、凶悪犯にも人権があるという感覚が違ってくる。人権に対しては、凶悪犯であろうと無かろうと、それは関係が無いという感覚を持たなければならない。だがそれは、まだ難しいだろうと中山さんも考えているようだ。その難しさを中山さんは次のように指摘する。「いやちょっと待て、確かに理屈ではそうだろうけれど、それはなんだか納得出来ない--多くの人々はそう思うのではないだろうか。正直なところ、私にもそんな気持ちがある。王様も奴隷も同じ人間だというのは、なるほどと納得出来るけれども、例えば幼女を強姦して殺害した男などを、善良な人と同じ人間と見なすことは、感覚的に難しいのが普通だと思う。」だが、中山さんは、この難しさは「単に私たちが人権感覚に慣れていないからだろう」とも語っている。そして次のような指摘をしている。「考えてみると、かつて、人権感覚に慣れない白人は、本国の人と植民地の人を同じ人間だと認めることは出来ても、黒人を同じに考えることはなかなか出来なかった。先住民インディアンを同じに考えることは、ようやく最近、始まった。女を男と同じ人間として考えることについても、まだ感覚的に反発のある人々が少なくない。 長い間、人種差別社会に生きてきて、人権感覚に慣れない白人は、黒人や先住民が選挙権を持ち、白人と同じ学校に通うことを、感覚的に納得出来ない。長い間、性差別社会に生きてきて、人権感覚に慣れないものは、女が選挙権を持ち、男と同じ仕事に就くことを、感覚的に納得出来ない。けれどもやがて、人権感覚が浸透して、黒人や先住民や女が、白人男性と同じ自由を行使することが、感覚的に普通になる。」人類の未来に希望を感じさせる、格調高い素晴らしい言葉だと思う。この指摘も、まったくその通りだと僕も思う。引用の連続になるが、次の言葉も素晴らしいのでそのまま引用する。「私たちは長い間、犯罪者を「人でなし」「鬼」と見て、そのように扱う社会で生きてきた。だから私たちは感覚的に、犯罪者をも同じ人と見なすことに抵抗があるのだ。人権感覚がよく浸透したところ、例えばスウェーデンの人々などは、私たちよりもずっと抵抗無く、犯罪者も同じ人間だと感じている。実際、犯罪者は重大な過ちを犯した「人間」なのだ。私たちも、人権感覚に慣れれば慣れるほど、そう感じるようになるだろう。 事実として無条件に、どんな人にもある、それが人権だ。だから、善良な人の人権は認めるけれども、凶悪な犯罪者の人権は認めない、というのは、人権を認めていることにならない。犯罪者にも一般人同様にある、それが人権なのだから。」「人権感覚」というものを深く感じるようになりたいものだと思う。また、自分だけがそれを感じるのではなく、多くの日本人にも感じてもらいたいものだと思う。それがおそらく、日本の近代化に大きく貢献するだろうと思うからだ。日本はまだ封建社会の残りかすを引きずっているような感じがするので、人権感覚を身につけた人々が、近代化の牽引車となっていくだろうと思う。近代国家の市民として必要な資質は、愛国心よりも、この人権感覚の方ではないかと思う。今の時代は、思いやりが育たないという指摘などもあるが、思いやりということの大切な側面は、他人になったつもりで考え・感じてみると言うことだ。そのような想像力を持つことが思いやりの心につながる。そういうものも、人権感覚を身につけることによって、他人の人権が侵されたときに、自分の人権が侵されたときと同じように感じることが出来れば、豊かな想像力として身に付くことになるのではないだろうか。死刑廃止について考えることは、それについて賛成する・反対するということにかかわらず、実に深い真理につながるものだなと思う。
2006.05.07
コメント(0)
-
「人権」について考える
死刑廃止の問題を考えるとき、「人権」というものが大きく関わってくる。死刑に反対することは、加害者の人権を守ることにはなるが、被害者の人権を無視しているのではないかという疑問が提出されることがあるからだ。このことに関しては、宮台真司氏なども的はずれな意見だと指摘していたが、中山千夏さんの『ヒットラーでも死刑にしないの?』という本では、この「人権」について詳しく論じている。「人権」というのは、辞書を引くと「人間が人間として当然に持っている権利」と書かれている。これは、分かったようで分からない定義だ。これは、同語反復のようにも見えるので分からない感じがする。「人権は人権だ」と言っているような感じがしてしまう。何を当然と考えればいいのかが分からないと、この定義は分からない。「人権」の内容をもっと具体的に考えるには、「基本的人権」という言葉を見た方がいいかも知れない。これは辞書によれば「人間が人間として当然もっている基本的な権利。近代初頭では、国家権力によっても制限されえない思想・信教の自由などの自由権を意味したが、二〇世紀になって、自由権を現実に保障するための参政権を、さらに国民がその生活を保障される生存権などの社会権をも含めていう場合が多い。日本国憲法は、侵すことのできない永久の権利としてこれを保障している。人権。基本権。」というふうに、かなり具体的に書かれている。「自由権」「参政権」「生存権」「社会権」というふうに書かれているものが、当然持っていなければならない権利と言うことになるのだろうか。しかし、この定義を読んだだけでは、これらの権利がなぜ「当然持っている」と判断されるのかはまだ分からない。「当然」だと信じられているだけでは、その理解が弱いと思う。なぜ「当然」なのかと言うことはどうしたら理解出来るだろうか。中山さんは、「権利」という言葉は「私には印象がよくなかった」と語っている。「権は権勢、権力の権、利は利益、利得の利。なんだかガメツイ感じがする」と言って、これが「当然」であると言うことがすんなりと納得出来なかったようだ。欧米では、権利の主張は、ごく当たり前のこととして誰もが認めているようにも感じるので、この感覚の違いがどこにあるかというのが、長い間の疑問だったそうだ。僕が関わっている「障害児の教育権を実現する会」では、障害児が、普通の地域の学校に行くか、それとも障害児学校である養護学校などに行くかは、障害児本人とその保護者の権利であって、彼らが決定すべきことだと考える。その決定を教育委員会などに指導してもらうと言うことは、権利であるという概念からは考えられない。そう言うふうに権利というものを捉えている。権利というのは、自己決定権を持っているもので、その権利を行使するかどうかも、権利の主体にゆだねられていると考えるのだ。障害を持っていなければ、地域の普通の学校に行けるというふうに、何かの資格を持っているから権利があるなどと言う考えには立たない。障害があろうと無かろうと、義務教育の就学権を持っていれば、その権利を行使出来ると考える。障害児の場合は、養護学校という別の選択肢があるからこそ、選択の権利があると考えるのだ。そこを選択するのも権利だし、選択しないのも権利だと考える。これは、極めて欧米的な権利意識だろう。権利としては、正統派の権利意識だと思う。しかし、日本ではこのような権利意識はしばしば非難の目で見られる。せっかく養護学校という配慮をしてくれているのに、無理に普通の学校を希望するのは、行きすぎた権利の主張だと見られることが多い。中山さんの気分にも、このような日本的な権利意識があったようだ。正面から権利を主張することに何らかのためらいを感じてしまったらしい。このためらいを解消するキッカケが、英語による「権利」の表現だったらしい。英語では権利を「Right」という。これは、「権利」の他に「正しい」という意味がある。「権利」の中にある「当然」だという感覚は、実は「正しい」と言うことから帰結する「当然」だったのだと言うことに中山さんは気づいたらしい。「権利」というのは、何か神から与えられた、無前提の信仰のような恩恵ではなく、その正しさが理解出来るものだからこそ、当然主張出来ることになると言うものだったのだ。そして、この「正しさ」は、歴史的に獲得されてきたものだ。それを理解することによって、「権利」の「当然」さは感覚的にも自分のものになるのである。かつて普通選挙が行われていなかった時代は、税金をたくさん納める人間が政治を司ることが当然だと思われていた。その時代の権利は、税金の額によって重さが違っていたわけだ。しかし、民主主義の思想が広まるに従って、財産の多さによって権利が違うと言うことが否定され、市民として同等であれば同じ権利を持つべきだという思想が正しいものと認識されるようになる。この正しさが普通選挙における参政権という権利につながる。しかし、女性が市民として同等だと思われなかった時代には、女性には市民としての参政権は与えられなかった。民主主義の思想がもっと育たなければ、女性を含んだ参政権の思想が「正しい」という判断まではいけなかったのだろう。しかし、それが正しいと判断されたとき、女性の参政権も、当然の権利として「人権」の中に含まれるようになったのだろう。権利が権利として機能するには、そこに「正しさ」がなければならない。そのように「権利」というものを理解すれば、それを主張するのは当然の行為だということも出てくるだろう。西欧的な「権利」の概念は、その主張の正当性をも支えている概念だと言うことが分かる。さて、「人権」というものをこのように理解すると、その中に入っている「生存権」というものも、それを主張することに正しさがあるというふうに理解しなければならない。それは、犯罪者であるかどうかで差別をしなければならないものではない。もし差別的に扱わなければならない「権利」だったら、「人権」と呼ばれる「基本的人権」にはならないと思われるからだ。たとえ犯罪者であろうとも、「人権」を認める立場に立つのなら、「生存権」を認めなければならない。そして、「生存権」という考えから死刑に反対する立場というものも、論理的な正当性を持つものとして受け止めなければならない。これが、たとえ感情的に受け入れがたいものであろうとも、前提である「人権を認める」と言うことに賛同するのであれば、この論理を受け入れなければならないのだ。もしどうしても受け入れられないと言うことであれば、「人権を認める」という前提も放棄しなければならないだろう。死刑囚に対しては「人権」を認めないという立場に立つことを宣言しなければならない。「人権」というものに対して例外を認めた場合、それがどのような影響を与えるかは抽象論の範囲でも考えることが出来る。死刑囚だという判断が100%正しく行えるのではないから、本来は人権を認めなければならない人の人権を認めないと言う間違った判断が起こる可能性が出てくる。この可能性があっても、あえて、死刑囚の「人権」は認めないという立場を堅持するかどうか。自分がそのような立場に立っても仕方がないとあきらめるのかどうか、そう言う選択すると言うことが、抽象的な問題として設定出来るだろう。僕は、それには耐えられないから、死刑囚といえども、「人権」の範囲の例外にすべきではないと思う。人間であれば、誰にでも認められる当然の権利として「人権」を受け止めるべきだろうと思う。さて、ここで冒頭の的はずれの疑問に戻ると、「人権」というのは、人間であれば誰でも持っている当然の・正しい権利なのだから、加害者にそれを認めて、そのために被害者のそれを無視すると言うことは、実は原理的に出来ないものなのである。加害者の「人権」を認めることが、被害者の「人権」を無視していることになるというのは、感情的にそう感じてしまうのかも知れないが、論理的にはあり得ないのだ。人権というのは、総量が決まっていて、誰かが一部を取ると、他の人の取り分が減るというものではないのだ。中山さんは、このような感情的な反発を、「コドモが駄々をこねるのと、いくらか似たところがある」と指摘して、次のように語る。「殺人が最大の人権蹂躙だというのは、正しい。しかし、言うまでもないことだけれど、死刑は、殺人事件が起こったあとで、その処理の一環として出てくる問題だ。心ない者によって、被害者の人権が根底から破壊されてしまった後に、死刑をするかしないか、という問題が出てくる。その時には、もはや被害者その人自体が存在しないので、その人の人権を守ろうにも、悲しいかな、私たちにはどうすることも出来ない。」殺人事件が起こった後で問題になるのは、加害者の「人権」の方であって、被害者の「人権」は、その時にはもう問題にすることが出来なくなっているのである。無視しているのではなく、問題にすることが出来ないので、語ることが出来ないのだ。もし、被害者の「人権」を考えるなら、被害者になる前に、被害者になる可能性を出来る限り減らす方向で「人権」を守るしかないだろう。それは、社会的な手だてを取れることは可能な限り努力をするという方向で考えるしかない。凶悪犯罪者を生まない豊かな社会の実現を目指すと言うことも一つの方法だ。小泉さんのネオリベ路線が、そのような方向になっているかどうかはよく考える価値があるだろう。もし、凶悪犯罪を生み出すような社会的背景を作り出しているようなところがあれば、それは被害者の「人権」を無視していることになるのだと思う。優勝劣敗の格差を生む社会が、凶悪犯罪を生む温床にならないかどうかは深く考えなければならないだろう。不幸にして犯罪が発生した場合でも、それが最悪の結果にならないように配慮することも社会的に行える「人権」の問題になるだろう。警察の治安の問題は、いろいろと複雑な問題が絡むので、なかなか単純な結論は出せないだろうが、市民を守ると言うことにおいて、「人権」の問題が考えられると思う。加害者の「人権」を守る方向を考えたからと言って、そのことが被害者の「人権」を無視することではない。むしろ、社会的に、犯罪を防ぐような手だてをしないことの方こそが、被害者の「人権」を無視していることになるのではないかと思う。
2006.05.07
コメント(0)
-
凶悪犯罪の加害者に対して死刑を望まない被害者遺族がいた
「ふらっと 人権情報ネットワーク」というページに「加害者は許せない だけど死刑には反対です」という、犯罪被害者の遺族である原田正治さんのメッセージがあった。これは、犯罪被害者の遺族の直接の声として、死刑廃止を考える人にとっては貴重な情報になるのではないかと思う。原田さんは、弟を保険金殺人で殺された犯罪被害者の遺族だ。加害者に対して、一審での裁判では「極刑以外には考えられません」と証言している。「殺してやりたいほど憎い」と思っていたそうだ。ここまでの感情の流れは、死刑を肯定する人々が語ることと重なる。被害者の遺族の感情としては、そうだろうと誰もが想像することが起きていた。しかし、原田さんはここからが違ってくる。確かに最初は、感情に流されて、誰もが想像するような対応になっていたが、時間とともにそれが変化していったのだ。変化の原因はいろいろなことが考えられる。興味本位で取材するマスコミにうんざりして、期待通りの行動をすることに疲れたということもあるかも知れない。原田さんは、犯罪被害者とその遺族に対する同情が、最初の一時期だけのもので、あとは何の公的なケアも受けられず、理解されない孤独の中で、家族関係もバラバラになっていくようになってしまったらしい。こんな風に記述されている。「自宅に押し寄せるマスコミ、一度は支払われた保険金の返還請求、会社を休んで裁判を傍聴することに冷ややかな会社との軋轢。同じ「被害者遺族」という立場でも、母親とも妻とも少しずつ事件の受け止め方は違う。家庭のなかで感じる孤独。お酒や遊びに逃げたこともあった。」「事件が発覚するとすぐマスコミが押しかけてきました。近くに住んでいたおふくろも当時小学生だった二人の子どもや妻もしばらく家から出られませんでした。僕はなんとか仕事には出ていましたが、帰宅すると物陰にひそんでいたマスコミの人が飛び出してきたりして、事件のことをゆっくり考える暇もありませんでした。 全国的に大きく報道されたほどですから、地方のちいさな町ではもう大事件です。自分の家を取り囲む空気をとても重たく感じましたし、友達との関係も変わりました。僕のひがみかもしれませんが、それまでよりも一歩ひいた感じで接してくるような。 返還を要求された保険金も葬式や法要の費用、弟の借金として長谷川君(明男さんの雇用主にして殺害を指示した人物)に支払ったりして(明男さんの借用証がなかったため、原田さんは嘘であろうと推測している)、すでに一部を使っていました。「返還しないと不当利益です」とまるでこちらがだまし取ったような言い方をされて腹が立ちましたが、すぐに返せる当てがなく困りました。行政や弁護士に相談してもきちんととりあってもらえません。おふくろや妻はそれぞれ自分の不安でいっぱいで、相談できる雰囲気ではない。「事件が明るみにならなければよかったのに」とすら思いました。みじめで悲しい思いをすることばかりで、孤独と社会への不信感でいっぱいでした。」マスコミや世間は、事件が起こった当初は、被害者とその遺族に対して同情的な姿勢を見せるのに、実質的な援助は何もしていないことが分かる。犯人を「吊せ」と叫ぶ人たちが、本当の意味では、被害者やその遺族のことを考えているのではなく、自分の感情を表出しているだけだという中山千夏さんの指摘は正しいのではないかと思われる。孤独の中で気持ちがすさみ、家庭も崩壊していった原田さんの救いになったのは、加害者の反省の態度だったという。その態度が、原田さんにとっては、本当の反省の姿のように見えたことが、原田さんの気持ちを変えてしまったという。加害者は、弁護士の影響からキリスト信者になり、原田さんに謝罪の手紙を送ってきたらしい。それに対して、原田さんには次のような変化があったという。「一方、原田さんは社会からひとり押し出されたような孤独感のなかで、「長谷川君」への憎しみを燃やし続けていた。送られてくる手紙は開封もせずに捨てていた。ところがある時、ふと好奇心がわいて読んだのをきっかけに目を通し始め、時には返事も書くように。そして事件から10年が過ぎた'93年、たった一人で「長谷川君」に面会に行く。憎しみや怒りが薄れたわけではない。むしろ持って行き場のない憎しみや怒りを直接ぶつけたい気持ちが強かった。しかし面会に来てくれたことを素直に喜ぶ「長谷川君」の表情に、フッと肩の力が抜けたという。」この手紙によって原田さんはかなり癒されたようだが、加害者と直接向き合うことによってさらに癒されることになったそうだ。最初の面会で、原田さんは、「彼が本当に「謝りたい」という気持ちをもっているということは感じられました」と語っている。「そして僕自身、彼から直接謝罪の言葉を聞くことで、誰のどんな慰めよりも癒されていくように思ったのです。長い間、孤独のなかで苦しみ続けてきた僕の気持ちを真正面から受け止めてくれる存在は長谷川君だけだと感じたのです。」と、その時の心境についてもこう語っている。この心境の変化は、死刑によって報復感情が癒されると主張するものに対して、必ずしもそうではないという反例になっているのではないだろうか。報復感情というものは、報復することによっては癒されないのではないか。むしろ、原田さんのように、加害者からの心からの謝罪を受けることによって、ようやく報復感情が癒されるのではないだろうか。原田さんの次の言葉は重いものとして、死刑肯定論者は受け止める必要があるのではないだろうか。「死刑制度を肯定する人たちは、よく「被害者の感情を考えれば、死刑も必要だ」と言います。確かに僕も一時は死刑を望みました。だけど怒りや混乱のなかで、死刑や死刑制度がどういうものなのかも考えたことも知識もなく、感情的になっていたのです。長谷川君と交流するうちに、彼から直接謝罪を受けることが何よりの癒しになることに気づいたから「死刑にするのは待ってほしい」と何度も法務省に申し入れたのですが聞き入られませんでした。 裁判所や法務省は死刑判決や死刑執行の際に「被害者感情を鑑みて」と言います。だけど「死刑は待ってほしい」と主張しても執行するなら、被害者感情など考慮していないということではないでしょうか。少なくとも僕はそう感じています。 死刑が執行されてもされなくても、僕の苦しんできたことは消えませんし、弟が生き返るわけでもありません。長谷川君がしたことへの怒りもなくなることはありません。「被害者感情」とは、そんな単純なものではないのです。」言葉では「被害者感情を鑑みて」と言いながら、「「死刑は待ってほしい」と主張しても執行するなら、被害者感情など考慮していないということではないでしょうか」という指摘は重いものとして受け止めなければならないだろう。また、この死刑は、さらに第二、第三の悲劇を生んでいる。ここには次のように書かれている。「「長谷川君」の死刑が確定してまもなく、彼の息子が自殺した。20歳という若さだった。その数年前には姉も自殺している。いずれも遺書は残されていなかったが、父であり弟である「長谷川君」のことで思い悩んだ末のことと原田さんは受け止めている。」この事実は、この国が、加害者の家族に対しても何の公的なケアもしない国だということを物語っているのではないかと思う。加害者の家族だから見捨ててもいいという人が多いとしたら、日本は何と冷たい国になったのだろうと思う。かつて、中国では、加害者である日本人の家族であっても残留孤児として、貧しい生活の中でも育ててくれた。日本には、そのような困ったときはお互い様という連帯はなくなってしまったのだろうか。原田さんは、このような現実から次のような考えを持つようになったようだ。「一番悪いのは、長谷川君や共犯者です。だけどそれだけじゃない。今の社会には「排除の構造」があり、いったん事件が起きると被害者も加害者も社会から排除されてしまう。そういう意味では加害者側の家族や親族も被害者だと思うのです。」このことが、犯罪被害者の遺族でありながら、死刑に反対するという気持ちを生んだのに違いない。そのような原田さんに対して、「「被害者のくせして」「被害者なのに」と非難する人も多い」らしい。しかし、その非難する人に対しての原田さんの次の言葉も重く響くものだ。「僕を非難する人に問いたい。「じゃああなたは僕が困っている時に手を差し伸べてくれましたか」「被害者の気持ちがわかるなら、その人たちのためにできることを考え、奔走しているんですか」と。」死刑存続の根拠を、被害者の感情に置く人々は、実際には、どれだけ「手を差し伸べてきた」のだろうか。原田さんにはまったく助けがなかったようだ。死刑廃止論者に対する非難として、被害者感情を無視しているということがよく言われるようだが、そう言っている死刑肯定論者は、果たして被害者感情をよく分かって配慮しているのだろうか。中山千夏さんが語るように、それは被害者感情ではなく、自分の感情を言っているだけなのではないか。原田さんの最後の言葉も、重いものとしてよく噛みしめなければならないだろう。次のようなものだ。「今、いろいろなところで話をさせてもらいます。すると死刑制度を支持しながら、ほとんど知識のない人が少なくありません。最低限の知識と、被害者が置かれている状況や気持ちをある程度は知ったうえで議論してほしいと思います。」原田さんのこの感想は正しいだろうと僕も思う。ネット上で検索出来る死刑肯定論を見ても、ほとんどが、自分の感情を語っているだけのもので、なかなか論評に値するものがないと思えるからだ。まったく「論」にはなっていないのだ。まともな論理で語っている死刑肯定論というのが、今のところは一つも見つからない。まともな論理を感じるのは、すべて死刑廃止論の方ばかりだ。だから、僕は、ますます死刑廃止論が正しいという確信を深めている。
2006.05.06
コメント(2)
-
死刑廃止に対する感情的反発にどう答えるか 2
感情の問題というのは、感情で判断することがふさわしいというものがあるだろうと思う。形容詞で表現されるような問題は、だいたい感情で判断してもそれほど間違いはないのではないかと思う。例えば好き・嫌いというものに関しては、何が好きでも、何が嫌いでもそれほど大した影響はない。自分の好みで選べばいいだけの話だ。好きなものは好きでしょうがないし、嫌いなものは嫌いでしょうがない。昨日は、知り合いとのある会話で日ハムの新庄が嫌いだという話題があった。あの目立ちたがり屋のところが嫌いらしい。僕などは、プロとしてインパクトのある行動で目を引くのは、ある意味ではプロ意識の現れだと思っているので、むしろ好感を持っていただけに、感覚の違いが面白いなと思った。だから僕が新庄が好きで、知人が新庄を嫌いでも、そのことはお互いの関係にはまったく関係がない。好みが違うのだなということを感じるだけだ。嬉しい・悲しいとか愛着・憎しみとかいう感情も、その感情だけの問題であれば、それを感じてしまうのは仕方がない。人間は感情の動物だから、その感情を抑えることは難しい。感じるものは仕方ないので、まずはその感覚の中で感情をいったんは開放しなければならないだろう。だが、その感情を、何らかの次の行為に結びつけることは、もはや感情の問題ではなく論理の問題になる。この行為を感情のゆえに正当化することは出来ない。その感情を抱いた人間が、論理を通過せずに、感情を行為に直結して失敗をしたという解釈は出来るかも知れないが、その感情のゆえにその行為を行ったのは正当だという主張は出来ないだろう。感情の問題と論理の問題は切り離して考えなければならない。死刑廃止論に対する感情的反発の問題も、報復感情のようなものから生まれた「吊せ」という行為の間に、いかに論理を挟んで考えるかということが解答になるのだと思う。その一つは、いかに凶悪な犯罪であろうとも、それを死刑に処することで、ふさわしい責任を取らせたことになるかということだった。むしろ、社会的な影響が大きい凶悪犯に対しては、死刑に処することよりも、生きて反省をしてもらうか、あるいは反省出来なくても束縛されたみじめな姿をさらす方が社会的な教育効果が大きいのではないかとも考えられる。中山さんが提出する別の問題としては、どの範囲までが死刑にふさわしいと考えるかという、程度の問題を考察するということがある。感情的に直結する判断では、情緒的に「吊せ」というふうに思った相手が死刑になってしまう。アメリカの西部劇でよく描かれる場面はこのようなものだ。この判断を情緒にまかせてしまえば、死刑にしたいものを死刑に出来るということになり、その間違いは明らかだろう。このような恣意的な判断を権力の側に許していけば、民衆はいくらでも弾圧出来る。それでは、どの範囲の人間が死刑にふさわしいかという限界は論理的に決定出来るだろうか。これは極めて難しいだろう。この論理は、いつでも行きすぎてしまうという傾向を持っているからだ。中山さんは、次のような流れで、このことの行きすぎる可能性を語っている。「ヒットラーを抹殺しなければナチズムは消せない ↓ ヒットラーに荷担したものも抹殺しなければならない ↓ 加担者の疑いがあるものはなるべく多く抹殺しなければ安心出来ない ↓ 無害な人も殺してしまう」死刑にふさわしい人間を決定する限界は、明確に・誰が判断しても同じものになるようには設定出来ない。それは、ある幅を持って判断しなければならないものになる。そうすれば、それはエスカレートせざるを得ない。だから、今度はそのエスカレートをいかにして防ぐかということが問題になってくる。エスカレートしたときに、エスカレートした人間を裁くことでこれを防ぐことが出来るだろうか。このことは、すべての体罰を禁止した学校教育法をアナロジーとして考えることが出来るような気がする。ワイドショーなどでは、戸塚ヨットスクールの校長である戸塚宏氏が刑期を終えて出所したニュースを伝えている。そして、戸塚氏の言葉で「体罰も教育である」というものに共感する人もいるように伝えている。この言葉が、結果的に体罰が教育効果を持つと解釈出来る場合もあるというのであれば、僕もそのようなことはあり得るだろうと思う。しかし、体罰を教育の一つとして認めろという主張だとしたら僕は反対だ。体罰は一度認めてしまうと必ずエスカレートする。そのエスカレートを許さないために、体罰においては、すべての体罰と思われる行為を禁止したのだというのが僕の考えだ。体罰にも教育効果がある場合が考えられるとしても、エスカレートを防ぐためには禁止しなければならないというのが論理だ。体罰は、禁止していてもそれが起こってしまうことがある。しかし、禁止しておけば、それが殺人に至るという最悪の事態は避けられる。これが、もしも許されるものになってしまえば、つい行きすぎて最悪の事態を迎えるということが頻繁に起こってくるのではないかと思う。体罰を行う人間が、常に教育的配慮でそれを行うと考えるのは、人間性に対する無知ではないかと思う。親が子供に与える体罰を考えればそのことは容易に想像出来る。ほとんどの体罰は、恣意的に感情的な判断で行われる。そして、体罰が許されるときは、他の教育手段を持たない人間は、容易に体罰を使うことに流れていってしまう。エスカレートして行きすぎるであろうとことは必然的なものに思われる。行儀の悪いコドモに対しては、殴るくらいのことは仕方がない、と感情に流れてしまえば、このエスカレートを防ぐことは出来ない。学校教育法という法制度は、感情的な判断で成立しているものではないので、このようなエスカレートを防ぐ制度として存在しているのだと僕は思う。死刑という制度は、ある意味ではもっとも重い体罰だとも言える。これを許してしまえば、それがエスカレートすることを防ぐことが出来ない。感情的に「吊せ」という声が挙がったときに、その間に論理を挟むことが出来なくなる。論理を挟むためにも、吊してはいけないのだと考えなければならない、というのが中山さんの死刑廃止論につながると思う。僕も論理的にはそう思う。死刑という制度は、殺される人間にとっては、感情と刑罰の間に論理を挟みにくいものになっている。なぜなら、それが間違いであることが後に分かったとしても、取り返しがつかないからだ。取り返しがつくようにしておいてこそ、間に論理を挟むことが出来るのだ。そのことを中山さんは次のように語っている。「ある政治勢力を抑えたり罰したりするのには、首謀者の禁固、懲役や、公職からの追放で充分だ。それを決めるのにも、やっぱり不公平や間違いはあるだろうけれど、間違って殺すのと、間違って監獄に閉じこめるのとでは、雲泥の差がある。間違いで捉えられた人は、いつか出られるかもしれないが、殺された人はどうすることも出来ない。」死刑廃止論に対する感情的な反発というものが、もしも感情だけのものであれば、死刑制度というものを考えるのは、感情の判断ではなく論理の判断こそがふさわしいということを主張することで足りるのではないかと思う。藤原正彦さんの『国家の品格』には、「情緒的判断の方が優れている」という主張があったが、それは、情緒的判断がふさわしい対象に対してのことであるという限定が必要だろうと思う。論理的判断がふさわしい対象に対してまで情緒的に判断をすれば、それはほとんどの場合間違える。死刑制度に関して、あくまでも感情的な判断を優先させて、論理などは二の次だとする人に対しては、中山さんが語るように、僕も、何を言っても無駄になってしまうと思う。だから、そういう人に対して話しかける言葉はもうないが、論理的には死刑廃止論を理解出来るけれども、何か引っかかりがある感情を持っている、という人とは語り合う何かがありそうな気がする。感情的判断はよくないと分かっていながら、どうしても感情的な判断が心に生まれてくるのを感じてしまうとき、その感情をどう処理するかが、本当の意味で「感情的反発に答える」ということになるのではないかと思う。感情的反発しか感じられない人に対しては、もっとオトナになることを待つしかないのかなと思う。そういう人間しか今の日本にいなかったら仕方がないけれど、サイレントマジョリティは、感情だけではなく、まともな論理を理解しようとしているのだと僕は信じたい。そういう人たちと「連帯」をして、感情と行為の間を埋める論理を発見したいものだと思う。
2006.05.06
コメント(0)
-
死刑廃止に対する感情的反発にどう答えるか 1
中山千夏さんは、第二章で「ヒットラーでも死刑にしないの?」ということを論じている。これは、本の題名にもなっていることなので、おそらく非常に重要なものと考えているのだと思う。死刑廃止論を、理屈では認めながらも、感情がそれを認めないという、感情の一つにこのようなものがあるに違いないからだ。中山さんの講演があったときに、話がこの死刑廃止論に向かうと、それに対して「深遠でない」つまりごく普通の話だといって不満を言ってくる人がいるらしい。その人の心理を分析した中山さんの次の言葉は、僕は鋭いところを突いているなと思う。「これは、オトナがコドモに対して、または男が女に対して、よく使うやり方である。その人の主張を聞きたくないとき、ものの言い方とか態度とかを批判して、主張そのものを無視するのだ。そして、そんなやり方をするのは、主張に対して反発があるのに、うまく簡単に反論出来そうにない、という時だ。」中山さんは、女だからこのような鋭い直感で相手を見抜くことが出来るのだろう。しかし、この中山さんの言葉が正しいからといって勘違いしてはならない。その言説が無視されても仕方がないほど水準が低いものであれば、無視されるのは仕方がない。むしろ、水準の低いものは無視するのが正しいと思う。それを無視せずに、的はずれの批判を撒き散らしていくような書き込みを見たりすると、この中山さんの言葉が正しいのだなと僕は改めて確認する。良心的な問題を扱っている女性のブログに、時として見当違いの書き込みをしていく人間は、「主張に対して反発があるのに、うまく簡単に反論出来そうにない」という感情を抱いているのだろうと思う。このような感情は、感情としてはどうしようもないので、何とかうまく対処しなければ死刑廃止を訴えることが難しくなる。中山さんはどうしているのだろうか。こう語っている。「ただし、私は、こうした人々を無理にも説得しようとは思わない。人権問題はたいていそうだけれど、個人の生活態度や人間関係の持ち方に大きな影響がある。例えば性差別についてどう考えるかは、たちまちツレアイとの人間関係にはね返る。そんなに直接的ではないけれど、死刑をどう考えるかも、自分自身にはね返る。もし、死刑が非人間的な不合理な刑罰だとしたら、それを認めてきた自分もまた、非人間的だということになる。自分でそう反省するならいいけれど、人から指摘されるのは、誰でもいい気持ちはしないものだ。 だから私は、性差別や死刑については、「どうも男女は不平等でよくない」と考えている人、「死刑にはなんだか抵抗がある」と考えている人、「だからもっとこの問題を考えてみたい」という人にしか、話をしても無駄だと思っている。「凶悪犯はどんどん死刑にすべきだ」と思い、そのことに何の疑問も持ったことがない人には、いくら声をからして説得しても、感情的な反応が返ってくるだけだろう。 ただ、面と向かえばそうであっても、一人で冷静になれば、考えが変わることはある。そのキッカケになれば、と願って、私は講演をしたり、こんな本を作ったりするわけなのでけれど。」とても素晴らしい考えだと思う。僕はほぼ全面的に賛成だ。結局、論理というものは「分かる人間にしか分からない」という側面を持っている。特に現実を語る論理は、その立ち位置や視点というものが論理の構造に大きな影響を与えている。それが弁証法性というものだ。だから、立ち位置や視点が違えば、まったく正反対の結論が、論理的に正しいものとして導けてしまう。そういう人に、いかに自分の立ち位置からの論理が正しいかを主張しても、それはある意味では「無駄」なものになってしまうだろう。感情的には、「人から指摘されるのは、誰でもいい気持ちはしないもの」だからだ。そんなことをするくらいなら、少しでも分かりそうな人に語りかけるということは、戦術としても正しいと思う。末梢的な揚げ足取りをして、的はずれのコメントを書いていく人間に、中山さんの爪の垢でも煎じて飲んでもらいたいものだと思う。もし、そういう人間が、本気で相手の考え方に影響を与えたいと思っているなら、それは全くの無駄であることを知らなければならない。もっとも、そのような的はずれのコメントを書く人間は、相手に働きかけるということよりも、自分の鬱憤を晴らすためにそうしていることが多いのではないかと思う。中山さんのように正しく考えられるのなら、そんなものは無視するのが正しいことが分かるだろう。むしろ、中山さんがやっているように、その言説を分かる人に向かって語りかけることで、副次的にそう考えもしなかった人に届いて、違う考えもあるのだなと気づくキッカケになってもらえばいいのだと捉えるべきだろう。それが正しい言説なら、いつかは考えを転換する人が増えるはずだからだ。板倉さんは、「真理は10年にして勝つ」という格言を語っている。どんなに正しいことであっても、革命的な斬新な真理は、今は非常識に見えるので、それが認められるには10年はかかると覚悟しておいた方がいいだろうということだ。さて、感情的な面への対処として中山さんが語ったことは、以外にも、感情的な面には対処しないということだった。それに無理に対応するよりも、分かる人に分かるように、論理的な面を押し出すべきだということになるだろうか。この対処の仕方も、僕は賛成だ。さて、感情的に死刑廃止に反発している人に感情面での対応はしないけれど、死刑廃止に対して賛成したいけれど感情面で賛成に踏み切れない人に対しては、中山さんは、論理によってそれに答えている。「ヒットラーでも死刑にしないの?」という問いに対しては、中山さんは次のような答をかつて咄嗟に考えてしたらしい。「今まで、そんな場合について考えたことがありませんでした。言われてみると本当に、ヒットラーも死刑にしないのは、なんだか割り切れない気がします。けれども、さっきお話ししたとおり、どんな人であれ、任意に殺す権利は誰にもない、と思います。ヒットラーは憎むべき存在ですけれど、それでもやっぱり、死刑にはしない方がいい、と私は思います。」これは、論理的には原則を守ると言うことだ。「殺人はいけない」という原則は、ヒットラーのように極悪人に見える人間にも適用されるべき重い原則だと言うことだ。しかし、そこまで原則的に考えられない人にとっては、まだ感情的な引っかかりが残るだろう。その人のために、中山さんは、「ヒットラー(のような独裁者)を死刑にしなかったら、どんな不都合があるだろうか?どうしても彼を死刑にしなければならない理由が、あるだろうか?」と問いかけてみる。そうすると、ある意味ではヒットラーのように極悪人と思われている人間は、かえって生きていた方がその後の世界にとってはいい影響を残したとも言えることに気づく。ヒットラーが生きていて、後の世界に対してもその思想が影響を与えるというのは、ヒットラーがまだ権力を握っているという前提があって言えることだ。権力の無くなったヒットラーは、むしろその存在によって、彼のそれまでの行為がいかに間違っていたかを示すことになるのではないか。宮台氏なども語っていたが、ヒットラーは、むしろ死ぬことによって永遠に英雄として心の中に生き続ける可能性を残してしまったのかも知れない。ヒットラー崇拝者にとっては、ヒットラーのみじめな姿を見ずに、その英雄的なイメージだけが残っていれば、ヒットラーはいつまでも英雄であり続けるだろう。東京裁判においては、日本軍中枢の人間たちが、すべて自分の責任を否定してみじめな姿をさらしたという。「生きて虜囚の辱めを受けてはならない」と教えた人間が、生き残って恥ずかしい姿をさらしたわけだ。東京裁判の目的の一つに、このようなみじめな姿をさらすということがあったのではないかと思う。これによって、日本人が抱いていた軍部への狂信的な忠誠心などというものはすべてなくなってしまっただろうと思う。イラクでは、フセイン元大統領のみじめな姿をさらして、フセイン支持者たちの気持ちをくじくことを考えていたようだが、最初の裁判で、フセインの方が立派な態度を見せてしまったので、その後の裁判はまったく報道されなくなってしまった。フセインがこのまま処刑されるようなことがあれば、フセインは、アラブの英雄として復活することがあるかも知れない。死刑には、そのような影響もある。これは、歴史に残るような大きな存在の人間が死刑になる場合には避けられない影響だろう。だから、そのような人間であれば、むしろ死刑にしない方がいいのではないかということも主張出来る。中山さんもそのようなことを論拠にして、「ヒットラーでも死刑にしない方がいい」と語っている。感情的にしっくり来ない人に対して、論理でもって説得をしようとしている。情緒に対して情緒を対置するのではなく、やはり論理で対処するのが僕も正しいと思う。そして、その論理が分かる相手には、それが必ず伝わるはずだ。情緒で考えて、論理を受け付けない人間に対しては、今のところは無視した方が正しい。歴史の流れを見れば、そのような人間はだんだんと少数派になってきている。死刑廃止論に賛成する立場としては、東京裁判における死刑判決についてもちょっと考えてみたいと思う。死刑廃止論からいえば、この死刑にも当然反対するのが当然だし、この死刑判決は間違いだと思う。だが、難しいのは、東京裁判が全体としてどのような正義を実現したかという評価と、死刑判決そのもの評価とは別だというところだ。東京裁判の正義を強調する人は、死刑になった戦犯たちを、当然の報いだと感じてしまうかも知れないが、死刑にしたのは間違いだったと考えなければならないと僕は思う。論理的には、死刑廃止論が正しいと思うからだ。東京裁判は、すべて正義だったわけではないし、まったく正義がなかったわけでもない。どこまでが正義で、どこからが正義でないかを正しく区別しなければならない。また、その正義も、どの立場からの正義であるかをはっきりさせなければ、全体としての東京裁判の評価は出来ないだろう。そして、その東京裁判でA級戦犯になった人が祭られている靖国神社が国際的な問題になっていることは、その正義が複雑な関係を持った正義になっていることを意味している。靖国参拝問題が、出口のない複雑な問題になっていることは、死刑廃止論の関係からも言えるのではないかと思う。感情的反発は、このほかにもさまざまなケースが考えられる。引き続き考えていこうと思う。
2006.05.05
コメント(2)
-
死刑は殺人か 2
中山千夏さんの死刑廃止論は、犯罪による殺人も死刑による殺人も同じものだと言うことを論拠に、犯罪による殺人が許されないものであるなら、同じように死刑による殺人も許されないことだという展開をする。これは、前提となる、「殺人」という点では両者は同じということを認めるなら、論理展開としては間違いがない。両者が同じ「殺人」であれば、一方が許されるなら他方も許されなければならないし、一方が許されないなら他方も許されないということで同じでなければならない。一方が許されない不当なもので、もう一方が許される正当なものであると主張するなら、その両者が同じものではないということをいわなければならない。そこで、前回は、法律によって正当な手続きが取られることが両者の違いだということを検討したが、これは、現在の段階ではそうであるが、法律を変えるなら正当な手続きそのものがなくなるので、行為としての両者の違いは、手続きの正当性からは導かれないということを見た。行為としての違いが言えなければ、行為としては同じになる。つまり、行為としては死刑に正当性はないと結論しなければならなくなる。さて、今回は、両者の違いをその主体の違いに見る視点を考察してみようと思う。行為の主体の違いが、その行為の正当性と不当性を区別する違いを反映したものになっているだろうか。犯罪においては、殺人の主体はあくまでも個人である。そして、その個人には他人を殺す権利はない。だから、いかなる殺人であろうとも、個人が行う殺人は正当性がなく、犯罪となる。それに対して、死刑の場合は、その行為の主体は国家という機関である。直接殺人を行うものは、国家の役割を分担する個人であるが、その個人は個人的な自分の意志で死刑を行うのではない。あくまでも仕事として行う。この違いに、死刑の正当性が含まれているだろうか。ちなみに、死刑の際に最後に命を奪うことになるスイッチを押すのは複数の人間で行うと聞いたことがある。これは、誰か特定の個人が死の責任を負わないように、誰が最後のスイッチを押したかが分からなくなるような工夫としてそのようにしているらしい。このことからも、死刑の主体が、個人ではなく国家という機関なのだということがうかがえる。さて、国家には、罪を犯した人間を死刑にする権利があるのだろうか。個人には、他人を死に至らしめる権利はなかった。それが、国家というものになると、その権利を持ちうるだろうか。それを論理的に整合的に説明することが出来るだろうか。この問題の解答の一つは、正義のための殺人は許されるとする考えだ。国家は死刑において正義を実現する。そのためであるなら、それは正当化され、許される殺人になるという論理だ。死刑廃止論者である中山さんは、この「正義のための殺人」に反対する。正義のためであっても殺してはいけないと主張する。これは、正義というものが、科学的真理のように、立場を越えて同意出来るものにならないからだ。国家にとって正義であるものでも、立場を変えれば正義ではなくなることがある。正義というのはあやふやなもので、そんなものを基礎にした判断は信用出来ないというわけだ。板倉聖宣さんは、正義というものはその時代の主流派の常識に過ぎないと語っていた。正義は多数決で決まってしまうのだ。このようなものに依拠して判断をすれば、それは時代や立場が違ったときに間違いになる。死刑を執行してしまったら、その間違いは取り返しがつかないのだから、正義を基にして死刑を許してしまってはいけないということになる。この正義というのは実にやっかいなもので、板倉さんは「いじめは正義から始まる」と指摘しているし、中山さんは「戦争は正義から始まる」と指摘している。攻撃的で相手を傷つける行為は、それが不正なものから発生している場合は、それほど大きく傷つかずにすむ。攻撃する方が悪いことが明らかだからだ。しかし、攻撃する方が、正義だと思ってやっていることは、下手をすると相手を徹底的に傷つける恐れがある。そのような弊害を持っている「正義のための殺人」は、間違えたときの影響の大きさを考えれば、やはり許してはいけないという結論を導くことが論理的な整合性があるのではないだろうか。現実の判断というのは、決して間違えないということがない。間違えたときに、取り返しのつかない結果を招くよりも、取り返しが出来るように配慮しておくことが、論理的には整合性があると思うのだ。ここで、中山さんは、百歩譲って国家が決して間違った判断をしないと仮定してさえも、正義のための殺人には反対するという。その正義が常に正しくても、そこから死刑による殺人の正当性を導くことは出来ないと主張するのだ。「それは、「どんな理由があろうと、殺人はいけない、やめよう」という私たちの大切なルールを弱める恐れがあるからだ」と中山さんは語る。最初から、このルールを大切なものと思わない人間だと困るのだが、一応これは大事なことだと思う人に対しては、「正義のための殺人」なら、やむを得ないこととして許されるという考えが、このルールを弱めるだろうことは想像出来る。「どんな場合でも」と語っているのに、この「特別の場合だけは」と考えれば、「どんな」ということが薄められるのは必然的だ。「どんな」は例外を許さないのに、例外を設定することになるからだ。この例外を許すことがどのようなものにつながってくるのかを想像しよう。この例外は、正義のためであれば殺人が許されるとするのだから、正義ということが確認された時点で、殺人が行われる可能性が出てきてしまう。例えば、相手が攻撃してくるかも知れない状況なら、相手を倒すことが正義になるので、その場合には相手を殺してもいいということになってしまう。相手が攻撃してくるかどうかがはっきりと分からなくても、攻撃してくると思い込んだら、相手を殺すことが正義によって許されてしまうことになる。これは、アメリカによるイラク攻撃の論理であり、イラクの危険性を語るアメリカの言説がほとんどでっち上げだったことを思うと、このような論理が誰の役に立って、誰の不利益になるかは明らかではないかと思う。また、国家ではなく個人的なレベルで同じようなことを考えると、かつてハロウィンの衣装で間違って射殺されてしまった日本人留学生のことが頭に浮かんでくる。彼は、銃を構えたアメリカ人に対して攻撃をする気は全くなかったにもかかわらず、射殺したアメリカ人は、彼からの攻撃を恐れて銃を撃って殺人を犯した。正義のための殺人が許されるという考えがなかったら、彼はいきなり射殺されるようなことはなかったのではないか。オウム真理教教団が行った地下鉄サリン事件なども、彼らにとっては正義の殺人だったことがいまでは知られている。それは、我々にとっては正義ではなかったが、オウム真理教信者にとっては正義だった。そして、彼らは、正義のために多くの人が犠牲になるような事件を起こした。どんな場合でも殺人はいけないということが、もしも常識として人々の中に強く存在していたら、このような事件の加害者は、いきなり殺人を犯すという動機は持たなかったのではないか。死刑というものが、正義のための殺人は許されるのだという前提を持っているとしたら、その前提こそ否定されなければ、殺人という悲劇は少なくならないのではないかとも思える。中山さんは次のように主張する。「「どんなに理由があっても、どんなに自分が正しくても、他人を傷つけたり殺したりしてはならない。それは人間として最低の行為だ」という考えが社会に強まれば強まるほど、殺人事件は抑制されるはずだ。 正義の殺人=死刑の存在は、私たちが殺人を根底から否定していないことの印である。そしてまた、個人が正義の殺人に走るときのお手本である。 私たちには、どんな理由があってもどんな正義があっても、他人を殺す権利はない。そのことをはっきり示すために、私たちの総体としての国家には、どんな殺人の権利も持たせてはならない、と私は思う。」僕もその通りだと思う。中山さんが語る死刑廃止論に強く共感するところだ。最後に、中山さんは、死刑という殺人は、制度として存在しているので、制度をなくしてしまえばなくすことが出来ると指摘する。どんな理由があっても殺人はいけないということを正しいとするなら、なくすことの出来る殺人である死刑を廃止することは、この正しさを守ることになる。また一方では、死刑ではない、犯罪としての殺人は、どのような努力をしてもなくすことは難しい、とも中山さんは語っている。人間はどうしても過ちを犯すからだ。死刑を廃止することは、この過ちを犯した人間を不当に許している甘い考えではないかと感じる人もいるかも知れないが、論理的にはそのような結びつきではなく、次のように考えるべきではないかと思う。どのような殺人であれ、殺人は許されるべきではない。だから、その許されない殺人の一部である、死刑による殺人は確実になくすことが出来る殺人だから、まずこれから先になくしていって、その後に犯罪としての殺人が減る方向に努力していこうというふうに考える。これは、決して犯罪を許しているのではなく、解決の方向として、その順番の方が有効ではないかと考えるということだ。死刑というものが、犯罪として行われる殺人と同じものである、と認めるなら抽象的には、死刑廃止という方向が正しいと結論出来るのではないかと思う。論理としてはこれが正しいと理解出来ても、何かすっきりしないところが残る人は、まだ感情の部分が納得していないのだと思われる。中山さんが語る各論として、その感情をどう受け止めるかということを次は考察してみようと思う。
2006.05.04
コメント(0)
-
死刑は殺人か 1
中山千夏さんの死刑廃止論である『ヒットラーでも死刑にしないの?』(築地書館)という本を読んでいる。僕は、総論としての抽象論である死刑廃止には賛成だ。抽象的な論理としての結論では、死刑は廃止する方向で考えることが、民衆としての立場としては正しいと思う。民主的に考えれば、これは多数の人の利益になることとして正しいと僕は思う。しかし、論理としては正しいと思っても、感情的な引っかかりがあるだろうことも理解出来る。そこで、中山さんが語る、この感情的な引っかかりの部分を考えてみようと思う。まず、第一章で語られているのは、死刑と殺人は同じものかというものだ。これに対しては、犯罪としての殺人は不正であり、死刑として凶悪犯を殺すのは、正義の実現として正しいのだと考える人がいるかもしれない。この感情の引っかかりを、論理でいかに埋めるかと言うことを、中山さんの文章をヒントに考えてみたいと思う。殺人を辞書で引いてみると、「人を殺すこと」と出ている。漢字を文字通り解釈した意味になっている。この定義に機械的に当てはめてみれば、死刑も、死刑囚を殺すのだから「人を殺すこと」であり、殺人だと言うことになる。しかし、この解釈では、現象を短絡的につなげただけで、本質を見ているとは言えないだろう。表面的には同じように見えながら、違う点が犯罪としての殺人と死刑の間にはある。だから、この違う点をまずは考察しなければならない。そして、それが違うように見えるにもかかわらず、本質においてはやはり同じだったと結論出来るなら、その結論は、短絡的な素朴な結論とは違ってくる。より深く本質を捉えた結論として回帰してくるのだ。これを弁証法では「否定の否定」という法則として捉えている。エンゲルスが、最初の素朴な見方が正しかった場合があとで確認されるときがあると語っていたような例に重なる認識だ。エンゲルスが語った例は、熱に関するもので、最初の素朴な見方というのは、摩擦によって熱が発生するという素朴な経験から来るものだ。これが後にフロギストン(熱素)というものとして考えられて、素朴な見方がいったんは否定される。しかし、後に運動エネルギーが熱エネルギーに転化するという本質的な見方が提出されて、最初の素朴な見方が、一段高いレベルで復帰した。認識の発展というのは、このように素朴な見方がだんだんと深まってレベルが上がっていくようになる。それが「否定の否定」と呼ばれる認識の法則になるのだが、これはいつでもそうなるとは限らない。最初の否定で終わってしまう場合もある。これは、素朴な見方が間違っていたという結論になるわけで、素朴だから正しいとは限らない。素朴な見方が、本質を捉えている、逆の意味で言えば、末梢的な部分を捉えられるほど発達していなかった(賢くなかった)おかげで本質だけが見えた場合に、後にそれが復帰してくる可能性があるのである。仮説実験授業をやっていると、もっとも難しい問題に関しては、非常に優秀な・対象について深く知っている生徒と、無駄な知識を持っていない・素朴な見方をする劣等生とが同じ正解を出すと言うことがある。これなどは、認識における「否定の否定」の法則が正しいことを示す実験のように僕は感じていた。さて、犯罪による殺人は不正で、死刑による殺人は正義の実現で正しいものだと考える人は、もしかしたら末梢的な部分にこだわって本質が見えなくなっているかも知れない、という視点でこのことを考えてみよう。中山さんが語る、両者の違いの一つは「手続きの正当性」というものだ。犯罪による殺人はもちろん許されているものではない。たとえどのような理由があろうとも、個人が行う殺人は許されない。正当防衛と言うこともあるだろうが、それも、最初から相手を殺すつもりで防衛をするのではなく、やむをえず相手を死に至らしめてしまったという場合になるだろう。犯罪による殺人には正当な手続きというものは無い。殺人はすべて犯罪として裁かれる。しかし、死刑の場合は、警察による逮捕から始まって、検察の側の証拠調べ、裁判を経て、正当だと思われる手続きによって死刑が決定される。だから、これはその正当性において違いがあるから、表面的には人が殺されるという共通点はあるものの、同じ「殺人」という言葉で語ることは出来ないと思う人がいるかもしれない。これは、なかなか反駁することが難しい論理構造だと思われる。しかし、手続きの正当性が、行為の正当性と同等かどうかということでこのことを考察出来るのではないだろうか。手続きの正当性が、そのまま行為の正当性を保障する場合もあるし、そうでない場合もあるのではないかと考えられる。この二つの場合を正しく区別出来れば、死刑の正当性を、その手続きの正当性で保障出来るかどうかも考えられるのではないかと思う。日本にいる外国人とつきあっていると、入国管理法というものが時にやっかいなものと感じられることがある。以前に荒川区で、タイから来た中学生が、この入国管理法によって一時帰国しなければならないと言われたときがあった。その中学生は、タイにはもう身寄りがなく、ただ一人の肉親である祖母を頼って日本に来ていた。そして、祖母は、その子を自分の養子として手続きをし、日本で生活出来るようにしてやりたいと思った。しかし、入国管理法によれば、日本での「定住権」が得られるのは、特別養子と呼ばれる制限がある子供だけで、この中学生の場合は、年齢の面で特別養子になれなかったようだ。そうすると、一定期間の後に、日本での滞在許可を取るために本国へ帰らなければならなくなる。しかし、現実的には、身寄りのない中学生を一人でタイに帰らせて、正当な手続きだけをしてこさせるというのはいかにも理不尽なことである。しかし、入国管理局の命令は、手続きとしては正当だから、この子だけを特別扱いすることは出来ないと言うことで、入国管理局の職員は、この命令を伝えざるを得ないだろうと思う。幸いなことに、法務大臣の判断で、この中学生は特別に滞在許可をもらったが、この特別措置が、正規の手続きの中に入っていなければ、同じような問題はまた生じてくるだろうと思う。現実には理不尽だと思われることでも、法律に明記してあれば、それは正当な手続きを経て執行されなければならない。その執行をサボることになれば、法律の効果というものがなくなり、社会の秩序が保てなくなる。ということは、法律に明記されている死刑についても、それが明記されていると言うことで、その正当性が保障されているように結論されてしまう。それでは、死刑は正当だと言うことになるのだろうか。これには一つの但し書きが必要だ。それは、現在の法律においては正当なのだという条件を付けなければならない。入国管理法に対しても、それが現在の形のものがあるから、タイの中学生のような問題が生じてしまうのであって、そのような問題に対処出来るように法律を変えれば、問題そのものはなくなってしまう。つまり、行為としては理不尽であっても、それに正当性を持たせることが出来てしまうのは、法律が現在の形を取っているせいなのである。法律は、その手続きの正当性の根拠は与えるが、行為の正当性は与えない。むしろ理不尽である行為を温存する働きを持つ。だから、行為そのものに対しては、それを理不尽であると判断するかどうかが重要になってくる。タイの中学生に関しては、法務大臣が特別許可を出した。つまり、法律に従った行為は、手続きとしては正しいが、行為としては理不尽だったと判断したわけだ。そして、行為としては理不尽だから、手続きが正当であっても、執行してはならないと言う判断を下したのだと考えられる。死刑の問題に関しても同じように考えられる。それが理不尽で不当な行為だと思うかどうかだ。行為そのものが理不尽で不当だと思えば、たとえ手続きが正当であっても、それを執行させてはならないと思うだろう。場合によっては手続きそのものを改めるという方向へ行く可能性もある。手続きが正しいから死刑に正当性があると考えるのは、論理の展開としては逆にならなければならない。死刑に正当性があるのなら、それを行う手続きを整備して、手続きにも正当性を持たせることで、死刑の正当性を損なわないようにしなければならない、と考えなければならないのだ。手続きの正当性とは別に死刑の正当性を主張する必要があるのだ。それでは、それはどこから言えるのだろうか。それが言えなければ、犯罪による殺人と死刑の違いはないということになり、最初の素朴な見方が正しいと言えるのだと思う。もう一つの正当性の主張に関わりがあるのは、殺人の主体の違いというものだと中山さんは考えているようだ。犯罪はあくまでも個人が行う。組織から命令された殺人であっても、直接手を下すのはあくまでも個人だ。そして、犯罪の責任は、実行犯と命令をしたものと別々に問われる。しかし、死刑の場合は、死刑囚の命を直接奪った人間に対して、殺人の責任を問うことはない。死刑における殺人の責任は、法律を制定し、それを遂行している国家にある。ここに違いを見て、国家が行うと言うことを根拠に、死刑の正当性を主張する論理が立てられるかも知れない。これに対しても、中山さんは反駁を用意しているのだが、それはまた項を改めて考えてみようと思う。
2006.05.04
コメント(0)
-
「普遍性」の認識
内田樹さんが「2006年05月02日 村上文学の世界性について」というエントリーを書いている。僕も村上春樹の小説が好きで、有名なものは一通り読んでいる。しかし、ファンを自認するほど読み込んではいない。もっとも好みに合うのは『ノルウェイの森』で、これを読んだのが最初だっただろうか。動機は、ビートルズの歌と同じ題名だと言うことだった。内田さんがここで書いていることは、村上文学の解説としても面白かったし、一応はそれを読んだことがあるので、書かれていることについてもなるほどと思えることだった。しかし僕には、文学の話ではなく、それをもっと一般化したものとして「存在するものは存在することによってすでに特殊であり、存在しないものだけが普遍的たりうる」という言葉が強く印象に残った。村上文学は、この「普遍性」を表現しているからこそ世界性を持つという解説も説得力あるものに感じた。僕がここから考えたのは「普遍性」というものの認識だ。三浦つとむさんの弁証法の話では、「特殊性」を「普遍性」と取り違える誤謬の話がよく取り上げられる。これは、両者が対立しているにもかかわらず、視点を変えて同じ対象を見たとき、「特殊性」として捉えられた部分が同時に「普遍性」としても捉えられることがあるからだ。つまり両者は弁証法的に統一されているのだ。このとき、対立を背負っている「特殊性」と「普遍性」を正しく理解するには、その視点を常に忘れずにいることが大事なことだ。自分はどの視点で対象を見ていることによって、その属性を「特殊性」として捉えているのか、あるいは「普遍性」として捉えているのかを忘れてはいけない。「特殊性」と「普遍性」の視点の違いの一つは、その認識の質の違いにあるだろうと僕は考えている。認識というのは、現実存在が人間の脳に反映したとき、それをどう捉えるかという働きのことを言う。視覚・聴覚・触覚などの感覚的に捉える部分と、それから得られた判断を結びつけてさらに立体的に捉える思考的な部分とがある。思考的な部分では、抽象と捨象という働きで対象を理解しようとするのだが、「特殊性」の認識は、より感覚に近いところでなされる分かりやすいものになるだろう。これは、他の存在との差異を見つけて区別がされればいいからだ。それに対して「普遍性」の認識は、ほとんど無限に多くの存在を想定して、それらから共通部分を抽象して来るという思考を経て得られる。「普遍性」は一つの対象を見ているだけでは見つからないが、そこに現象していることは確かなのだ。対象の全体性の把握と言うことがないと「普遍性」は分からない。「特殊性」は、比べる相手が一つあればそれを見つけることが出来る。そっくり同じでないところを見つければ、それが「特殊性」になる。しかし、「普遍性」は、同じではないにもかかわらず、同じだと言えるような抽象過程を経なければならない。同じでないところを、末梢的な部分として捨象するという思考をしなければならない。このような理解で、内田さんの言葉を眺めてみると、「存在するものは存在することによってすでに特殊であり」と言うことは、存在するものは、直接的に他の存在と比べることが出来るので差異を見つけることが出来ると解釈出来る。これは、現実に存在する二つのものは、決して同一のものではないということから来ている。現実存在には、 A=Aという等式はナンセンスになるということだ。何から何までそっくり同じであれば、両者を区別することが出来ないから、それは二つの対象とは考えられない。だから、現実存在について「A=A」という等式を立てても、それは対象については何も言っていないことになる。もし、現実存在に対して何かを言いたいのなら、 A=Bという等式を立てなければならない。これは、板倉さんが語ったように、存在としては違うものであるにもかかわらず、共通であるという視点を持って眺められる部分があるから等しいものとして表現される。この二つは、差異がある違うものであることを前提として、その上で同じものがあるという認識を持つことが出来たとき等式で表現されるのである。この有名な例として板倉さんも触れていたのが、マルクスの説明による、商品における「使用価値」と「交換価値」だ。商品はそれぞれ「使用価値」において差異を持っている。パソコンと、高級レストランでの食事は、存在としても・その使用目的もまったく違うものとして存在している。しかし、価格がついているというということで、その物差しで見るという視点では等式をつくることが出来る。 x量のパソコンの値段=y量の高級レストランの食事の値段この等式で表現されている、共通部分として等しいものこそが、商品の「交換価値」であるとマルクスは主張していた。パソコンがいろいろと便利に使える道具であり、高級レストランのうまい料理は「使用価値」として受け取ることは容易だろうと思う。それは感覚的に分かる「価値」だからだ。しかし、商品として一般化(普遍化)された対象に存在する「交換価値」は、やはり一般化(普遍化)されており、普遍性を表現している。これは直接感覚することが出来ない。ある商品が、なぜあれほどまでに高いのか、あるいは逆に安いものもあるのかということは、感覚的には分からない。それは抽象化されたものだから、抽象過程を経て認識されないと分からないのだ。そうすると、内田さんが語る言葉の後半部分「存在しないものだけが普遍的たりうる」ということの理解も次のようになるだろう。抽象された対象は、そのまま現実に存在するわけではないので、「普遍性」として認識されたものは、「存在しないもの」として捉えられる。そして、そういうものこそが「普遍性」を持つことが出来、「普遍的たり得る」のだという理解が出来る。現実存在にべったりと寄りかかって認識していたのでは、いつまでも「特殊性」から抜け出ることが出来ない。その現実存在から抽象化された対象が設定されたとき、その抽象化された対象において初めて「普遍性」を問題にすることが出来る。この抽象化の段階は、科学においては仮説が設定出来る段階であり、モデル理論ではモデルを設定する段階ではないかと思う。そして、仮説が証明され、モデルが現実のよい反映であることが証明されたとき、その仮説やモデルは「普遍性」を獲得して、一つの真理を表現しているのだと受け取られるのではないだろうか。「特殊性」から「普遍性」へ至る抽象の過程を理解するのは難しい。直接には見えない対象を見る「ノーミソの目」を鍛えないとならないからだ。内田さんは、「父なる存在」をこの「普遍性」を持った対象として説明している。これは、現実存在としての「父」ではないのだ。現実には存在しない抽象的な対象としての「父」であることが分かったとき、その「普遍性」を理解したと言える。「父なる存在」は、現実に父であろうと思われるものに現象している。その現象から本質を抜き出して抽象することによって「父なるもの」を考えることが出来る。しかし、「父なるもの」は科学の対象ではないので、万人が納得するような「普遍性」を抜き出すことは出来ない。これが「普遍性」ではないかというものを常に差し出す仮説のようなものしか提出することは出来ない。このようなものを表現するには、文学という芸術はまったくふさわしいものなのではないかと思う。文学は言葉の芸術だが、言葉というのはすでに言葉であることによってある種の抽象の過程を経ている。これは、言葉というのは、存在する対象を概念として捉えて、概念の部分を表現するものであるという三浦さんの指摘からそう考えることが出来る。「犬がいる」という言葉による表現は、目の前にいる特殊な犬を表現しているにもかかわらず、「犬」という種類を指す言葉で表現するという「普遍性」を持っている。絵画において抽象性を表現するのはたいへん難しいが、文学ならそれに比べれば表現可能ではないかと思われる。僕は、自分にはエディプス・コンプレックスがないのではないかと思っていた。自分は特殊な育ち方をしたのか、それとも、あの概念は日本人には当てはまらないのではないかと思っていた。僕は、現実に存在する父に対して、ライバル視をしたり乗り越えたいと願うという気持ちをほとんど抱かなかったからだ。一つの道を究めて歩んだプロとしての尊敬の気持ちを抱いていた。しかし、エディプス・コンプレックスが、現実の父ではなく「父なるもの」に対するものとしてあるのなら、それは「普遍性」を持った認識かも知れないと思える。人間の心にとって、絶対的基準を持った存在が必要だと言うことは分かるからだ。僕にとっては、おそらくそれが「論理」というものだったのだろうと思う。どんなに偉い人が言おうと、論理に反したことは僕は受け入れられない。論理こそが絶対的な基準になっている。内田さんは、このエントリーの最後に次のように語っている。「「善悪」の汎通的基準がない世界で「善」をなすこと。「正否」の絶対的基準がない世界で「正義」を行うこと。それが絶望的に困難な仕事であるかは誰にもわかる。けれども、この絶望的に困難な仕事に今自分は直面している・・・という感覚はおそらく世界の多くの人々に共有されている。」この困難な仕事は、確かに抽象の世界での仕事だと思う。それは、「普遍性」を捉えなければならないものであるからこそ困難なんだと思う。この「普遍性」を捉えようとした人に、何らかの考えるきっかけを与えてくれるのなら、村上文学が世界中の人々に読まれるようになるのは、確かに論理的に理解出来る、頷けることだと僕は思う。
2006.05.03
コメント(0)
-
連帯
昨日はメーデーに行って来た。主催者発表では約4万人ほどの人が集まっていたらしい。20年ほど前に初めて参加したときには、まだ組合の分裂前だったので10万人はいたのではないかと記憶している。僕は、その人の多さとエネルギーの大きさに感動したものだった。その場所にいるだけで強い「連帯感」を感じたものだった。しかし、昨日のメーデーにはそのように強いインパクトはなかった。年をとったせいもあるのだろうが、「連帯感」という感受性が弱くなっているのを感じる。宮台真司氏は、つい先日のフランスのデモやストに関して、世代を超えた「連帯」があるという見方を示していた。あそこでの反対の声は、直接的には若者の雇用政策に対するものだったが、それを、若者だけではなく年配者も支持していて、そこに「連帯」が存在していたという見方を語っていた。この「連帯」の基礎にあるのは、民主主義というものに対する不完全さの理解でもあると説明していた。民主主義は、利害の衝突を多数決によって調整していくものだ。当然、不満を持つものも出てくる。その不満が正しいか正しくないかは簡単に決定出来るものではない。だからこそ、不満の表明の手段は保障されなければならない、というのが民主主義の不完全性を埋めるものになるというわけだ。そのことを、社会を構成する「市民」の誰もが分かっているので、抗議の声をあげるということに関しては「連帯」が出来るのだという。ストやデモがあっても、それが日常生活の支障になる「迷惑」だという感覚はないと宮台氏は語っていた。それは当然の権利を行使しているのであって、自分の利益が損なわれたときに、自分が抗議の声をあげるということの正当性を担保しておくためにも、他者の抗議に対して寛容になることが民主主義社会に生きる「市民」感覚だというのだ。ところが、この一連のフランスのストやデモに関して、フランス在住が長いものでさえも、日本人の多くは「迷惑」だと受け取っていたらしい。日本では、久しくストは行われなくなっているが、もしどこかでストが行われたら、それは多くの日本人にとっては、社会生活を乱す「迷惑」だと感じるかも知れない。これは、日本社会における民主主義の成熟度が低い、つまり未熟だということだと思う。お上に対して抗議の声をあげることが正当な権利だという「市民」感覚が育っていないということがあるだろう。そして、またストを行う側の感覚も、それが市民社会にとっての利益だという感覚よりも、個別の組合の私的利益というエゴイズムの表現として出されているように感じられてしまう場合が多い。若者の雇用や賃金の問題なども、本当はフランスよりも日本の方がもっと深刻なものがあると思う。年金制度というものが、若者が年配者を支えるという基本構造を持っている限り、若者の雇用は、年配者の問題でもあるのだが、若者個人の問題として矮小化されてしまい社会的な問題だという視点が欠けているように僕には感じる。成功した若者は大金を稼ぎ勝ち組になるが、負け組になった若者は自己責任で、貧しい生活をしていても仕方がないのだというような考え方は、社会全体を見たときにはマイナスの方向への影響を持つだろう。マル激では、若者が学校を卒業したときには、社会でのデビューのための自己資金として一律数百万円単位で提供したらどうかというような話も出ていた。これに対して、いまの若者は理解出来ない考え方をするものもいるので、無駄に使われることがあるから、それはとんでもない提案だと感じる大人もいるだろうと語っていた。しかし、少数の成功者に金が集中しても、社会全体としてはその金はあまり回るものではなくなるが、多くの若者が金を持ってそれを使えば、金が回るという効果だけでも経済的には影響が出るだろう。金は天下の回りものだから、回ることが大事だと思えば、この提案もそれほど悪いものではないだろう。こういった提案は、若者世代と年配世代が断絶していて、若者の利益は年配者の利益にはならないと思ったら「連帯」は出来なくなる。利益につながりがあるという視点を持たなければならないだろう。「連帯」という問題では、耐震強度偽装問題で、価値のないマンションを所有することになってしまった人々との「連帯」が頭に浮かんできた。この被害者にとって、住むことも出来ない・売ることも出来ないマンションなど何の価値もないのだが、残りのローンだけを払い続けなければならないというのはいかにも理不尽なことだ。誰かが言っていたが、この借金をすべて銀行が引き受ければそれで被害者救済になるという提案は、僕はとても同感だと思ったものだが、その根拠に関してはあまりよく分からなかった。しかし、マル激を聞いていたら、住宅ローンの「担保」の問題というものが語られていて、それがヒントになって、このような論理的根拠を考えることが出来るのではないかとも感じた。それは、住宅ローンを貸し付けるときに、銀行は住宅というものを「担保」に貸し付けている面があるはずだ。ローンの債務者が、途中で借金を払えなくなったら、その担保にした住宅で借金を何とかするように考えるのではないだろうか。住宅を「担保」にするというのは、それがローンを貸し付けるに値する物件だという銀行の判断があるからではないだろうか。そうであれば、その物件が価値を失ったとき、所有者だけにその責任を押しつけるのは不公平ではないかと思う。所有者は、むしろ価値のなくなったマンションを手放して、残りのローンを帳消しにしてしまう道が選べるようにすべきではないだろうか。そのようなリスクがあれば、銀行は簡単にローンを貸し付けるのではなく、その物件が担保に値するものであるかを調べるようになるだろう。素人である所有者が調べきれないことも、仕事としてなら銀行はかなり細かく調べることが出来るのではないか。そのようにすれば、ローンはなかなかつかなくなる恐れはあるが、売り主の方はローンがつかなければ売ることが出来ないから、ローンがつくようにまともなマンションを建てるように努力するのではないだろうか。少なくとも耐震強度を偽装して建てようなどという業者は生き残れないはずだ。このような論理で被害者を救済するのであれば、僕は論理的にも納得出来る。しかも、このような救済であれば、不幸にも自分が被害者になったときに、その被害を正当な方法で回復することも出来るだろうと期待出来る。被害者との「連帯」を感じることも出来るのだ。「連帯」というのは、ある出来事を、他人事ではなく自分のこととして引き受けることでその感情が生まれてくる。これは、物事を突き放して見ようとする「論理」的な見方とはある意味では正反対の現象のように見える。しかし、論理をたどって納得すると「連帯感」が生まれてくると言うこともあるから不思議だ。顔の見える・よく知っている人間に感情移入して「連帯」するのと、顔の見えない・よく知らない人間と「連帯」するのとでは、その条件が違ってくるのだろうと思う。職場の仲間と「連帯」するのは、お互いによく知っている仲なので、感情的にも容易なものを感じる。だが、雇用が不安定な中で、将来の生活に不安を感じている若者一般との「連帯」を考えたり、直接には知らない相手である、耐震強度偽装問題の被害者と「連帯」しようと思ったら、感情移入だけの「連帯」は難しいかも知れない。それは、ある意味では「他人事」になってしまうからだ。その「他人事」が、よく考えてみると、自分にもつながりがあることだと理解するのは、「他人事」として突き放して見るという論理のおかげで分かる。かつて、仮説実験授業研究会の牧衷さんは、運動のスローガンが、個人の利益というエゴではなく、社会の利益という公共性を持ったとき、それは大きな支持を得ることが出来て成功への道を歩むと語っていた。松川事件と呼ばれるものに対する運動なども、不当な裁判を受けた個人の利害の問題であれば、人々の関心はあれほど高くはならなかったのではないかと牧さんは語っていた。司法制度の問題として、捏造された証拠で犯人にされてしまうということが、誰にでも関わりのある問題として、社会的な問題だと理解されたときに、人々は「連帯」をし、大きな力でその運動を推進していったのではないかと語っていた。メーデーは、元々、感情移入で「連帯」することが難しい大多数の人々の「連帯」をつくるものだった気がする。しかし、残念ながら、いまは顔見知りの「連帯」を超える「連帯」がなかなか生まれにくい。マスコミで大宣伝される人々は、直接知らなくても、ある意味よく知っていると言うことから感情的な「連帯」もしやすくなっているのではないか。いまのマスコミ状況で言うと、拉致被害者に対する「連帯」は比較的抱きやすいものではないだろうか。しかし、感情による「連帯」は、それが忘れられると「連帯」も消えてしまう。確かな論理的基礎を持った「連帯」はどのようなもので、どうすれば実現出来るだろうか。マルクスは、「階級」という言葉で多くの人の「連帯」を呼びかけたが、いまは「階級意識」も薄れてきている。「連帯」における感情と論理の問題というのを、改めて考えてみたいと思った。そんなことを思った昨日のメーデーだった。
2006.05.02
コメント(4)
全41件 (41件中 1-41件目)
1
-
-
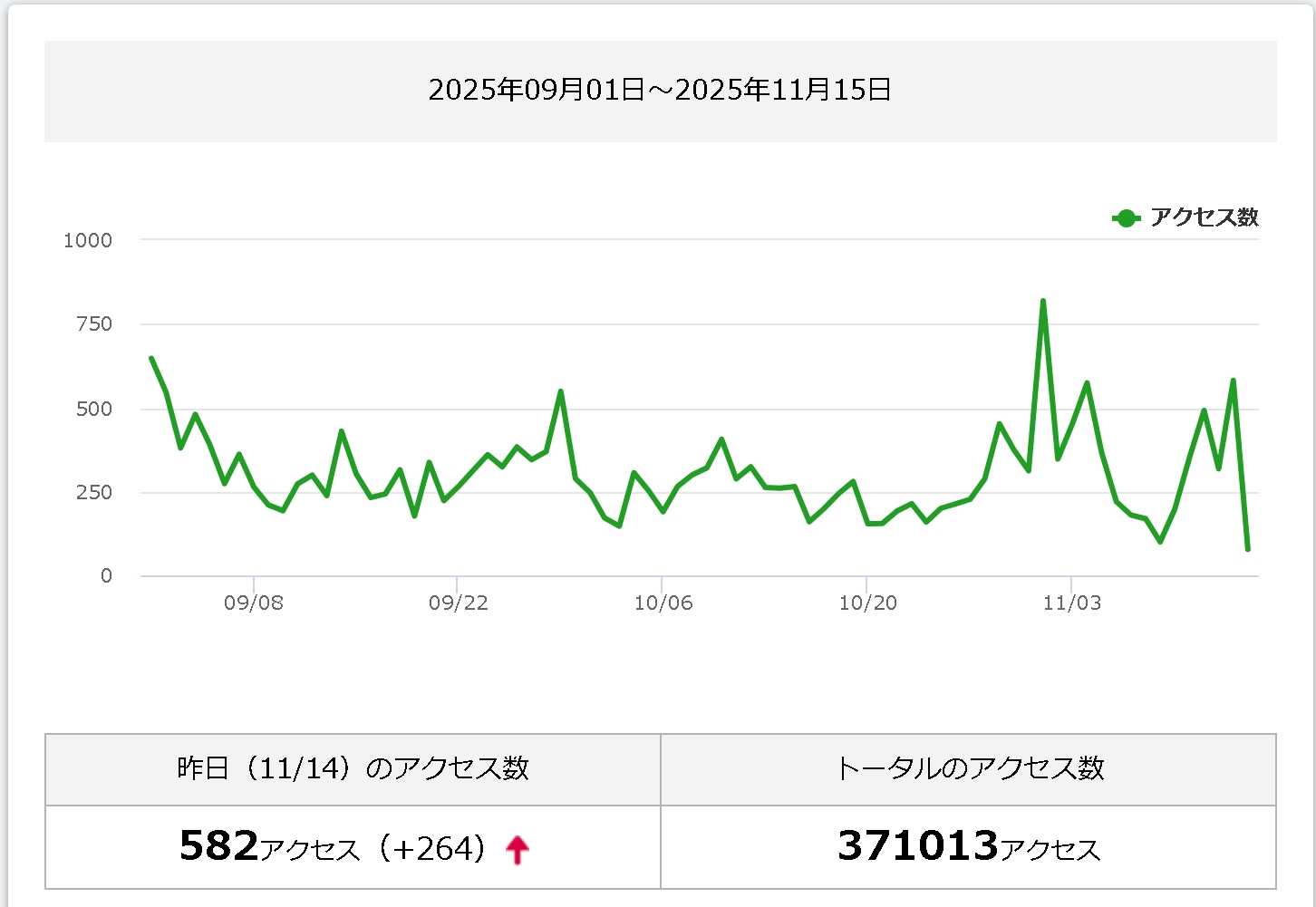
- つぶやき
- 結局変わんねぇなぁ~
- (2025-11-15 03:17:16)
-
-
-

- 避難所
- 【大人気】「エアーソファー」 で、…
- (2025-10-30 22:24:38)
-
-
-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…
- 【2025年11月15日の運勢】12星座占い…
- (2025-11-15 05:01:28)
-







