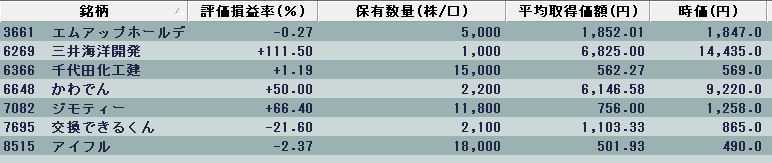2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2007年11月の記事
全9件 (9件中 1-9件目)
1
-
ウィトゲンシュタインの哲学の基本理解とその応用
僕は、ウィトゲンシュタインの哲学の理解に対して、直接ウィトゲンシュタインの著作から学ぶのではなく、野矢茂樹さんや橋爪大三郎さんの解説から間接的に学んでいる。それは、ウィトゲンシュタインの哲学というのは、直接その著作から学ぶには難しすぎるからだ。それは短い命題の羅列からなっているのだが、そこに含まれる内容は実に豊富なものがあり、その意味を理解するには予備知識が大量に必要になる。そのような予備知識の素養がなければ、ウィトゲンシュタインの文章を直接読んでも、何が書いてあるのかさっぱり分からない。これは、そのような素養を持っている人間の解説を頼りに少しずつ理解を進めていかなければならない。その解説者として信頼できる人が野矢さんと橋爪さんということになる。野矢さんは専門の哲学者であり、ウィトゲンシュタインに関する深い素養を元に、ウィトゲンシュタイン初心者にも分かるような解説を書いてくれる。橋爪さんは哲学者ではないが、社会学者としてウィトゲンシュタインの理論を応用するという面から示唆に富む解説を書いている。野矢さんと橋爪さんの解説によって、ウィトゲンシュタインの大雑把な全体像を作り、その全体像を元に直接著作を読み進んだときに、そこに書かれていることの整合性が納得できれば、野矢さんや橋爪さんの解説も、ウィトゲンシュタイン自身の理論展開も、ともに整合性のあるものとして論理的な理解が出来るようになるだろうと思う。そして、これらの人々が、その著作に直接書いていないことに自分の考えが及んだとき、それは基本的な理論の応用問題を僕が解いているのだということになるだろう。さて、橋爪さんは『言語ゲームと社会理論』(勁草書房)という本の中で、ウィトゲンシュタインの『論理哲学論考』の主張を次のように簡単にまとめている。1 世界は、分析的である(あるいは、分析可能である)。2 言語も、分析的である(あるいは、分析可能である)。3 世界と言語とは、写像関係にある(あるいは、同型対応している)。4 以上1~3の他は、言表不能=思考不能である。このまとめは非常に大雑把ではあるが、ウィトゲンシュタインの主張の全体像をつかむには分かりやすい。その細部については分からないところがたくさんあるが、全体が整合的であることを見るのは案外と易しい。分析的であるというのは、細部に分解できるということである。世界はまず全体的な印象として我々の目の前に現れるが、その部分に注目する視点から、全体とは別に細部を細かく見るということが出来る。これが分析的ということで、このことの整合性は経験からよく実感できるものだ。また、言語の分析というものも、言語表現が部分に分かれて考察できるということから理解できる。文法という学問が言語の分析を扱っているという経験からも、この主張の整合性がわかる。そして、言語が現実の世界を表現しているということから世界とのつながりが理解され、そのつながりが「写像関係」「同型対応」と呼ばれるものになっているということの整合性も理解できる。このまとめは解説として優れているのではないかと思う。だが、これはあくまでも大雑把な理解をするための全体像の解説であって、その細部に関しては語られていない。世界や言語が「分析的」であることは一般論として理解できるが、具体的な分析はどうされるのかについては橋爪さんの著書からは分からない。これは、橋爪さんの目的が応用にあるので、具体的な分析はその応用を見せることで示していると思われる。つまり、直接その分析はこういうものだというふうに、分析そのものを語ってはいない。だから、その応用の仕方を見て、「分析」をどうするかというのを自分の言葉で表現しなければならない。これはちょっと難しい。橋爪さんの応用が、社会学的なものなのでかなりの難しさを感じるからだ。この分析の具体的な方法については野矢さんの『『論理哲学論考』を読む』のほうが詳しい。野矢さんによれば世界の分析は、「事実を対象に解体する」と語られる。世界の現れは、まずは「事実」として目の前に現れる。この「事実」を構成する部分として「対象」というものが「事実」から引き出される。この展開を「解体」と呼んでいる。例えば我々の世界に「リンゴ」という物質があった場合、この「リンゴ」は単独で孤立的にそこにあるのではない。それは例えば「赤い」という属性を持っていて「リンゴが赤い」という「事実」として我々に認知される。「リンゴ」という実体だけ、あるいは「赤い」という属性だけがどこかに切り離されて浮かんでいることはない。この両者はくっつきあって現象する。それを引き剥がして別々のものとして考察の対象に出来るのは、「事実」から「対象」を「解体」するという分析を行っているからだ。「リンゴが丸い」という「事実」からは「丸い」という属性が対象として解体される。また、それが「冷蔵庫の中にある」という「事実」からは、空間的な位置関係が対象として解体される。野矢さんは、属性と関係を対象の中に含めているが、これには異論があるそうだ。しかし僕は、「事実」からの解体ということを考えると、属性や関係も解体されると考えるほうが整合性があると思うので、野矢さんの主張のほうを信用する。野矢さんは、「事実」から「対象」への解体についてはこのように語っているが、「事実」を「事実」として認識することについては語っていない。どこかで語っているのかもしれないが、この本を読む限りではそこには言及していないようだ。むしろ「事実」は、議論の出発点として所与のものとして前提しているようだ。それが「事実」であるかどうかは、ある意味では証明のしようがないということではないかと思われる。それが「事実」ではなく錯覚だったということは、錯覚をする根拠を見つけることによって分かる。だが、錯覚ではなく確かな「事実」だということは、水槽の中の脳の想像で考えたように、厳密には我々には区別がつかない。所与のものとして考えるしかないのだろう。だが解体される対象が単純なものか複雑なものかという区別は、対象の像としての言語を分析することによって得られる。そこで「事実」としては単純なものだけを選んで世界を構成することを考える。複合的な現象も、単純な現象へと分析されて「事実」として確立しようという発想だろう。これは、像として考えられている言語によって作られる「論理空間」というものの把握にとって、単純なものを基底(ベース)として、あとはそれを論理語(「ない(否定)」「かつ(連言)」「または(選言)」「ならば(仮言命題)」など)でつないで作ったものが「論理空間」だと考える方が把握しやすいという発想があるのではないかと思う。このような発想であれば、対象として選ばれるのは単純概念として写し取られるものになる。つまり実体的に存在する対象は、単純概念として言語に像を結ぶものだと考えられる。これは、直接野矢さんはそう書いていないようなので、野矢さんの理論展開を理解しての僕の応用ということになるかもしれない。なお現実の対象を眺めていただけでは、それが単純概念を持つ「対象」なのかどうかは分からない。それは、「対象」を像として写し取っている言語の中で「名」と呼ばれるものの分析をすることから判断される。ウィトゲンシュタインが、普通の文法のように、名詞や動詞や形容詞を区別せずに、「対象」を一括して「名」というもので呼んでいるのは、「事実」から解体される「対象」をすべて同等なものとして分析の対象にしているからではないかと思う。「名」というものを言語の中で設定して、「名」の分析によって「対象」の分析に代えるというのが、言語と世界の「同型対応」という考えから来るのではないかと思う。この「名」の分析は、我々の言語習慣・言語の使い方というものから判断される。野矢さんの表現を借りれば、「言語に慣れ親しんでいる」人間のみが、「名」の論理構造を理解し(つまり「名」の使われ方を理解し)、「名」を分析できるということになる。「名」を言語として分析することによって、それが単純概念であるかどうかが知られる。そして複合的な概念は、単純概念を論理語で結合したものとして再構成される。「名」による単純概念の表現で作られた命題が、所与の「事実」として世界の中に確認されれば、その命題は真理であるというような対応がされる。もし、「事実」としてその命題の主張が見つからなければ、それは可能性としてはあったが、現実性は否定されるものとして解釈される。そして、すべての可能性を尽くすことが出来れば、我々は思考の限界を知るということになる。このとき、「名」を単純概念に限らずに、複合的なものを含めて、とにかく命題表現が出来るものは「事実」として確認できるのだと考えると、所与のものとして前提されている「事実」が、その複合概念の定義の仕方によって異なってくる。例えば<虐殺>という概念が、<虐殺1>と<虐殺2>では、その構成する論理語のつながりが違うものであった場合、それに対応する存在は違うものになるだろう。そうすれば <虐殺1>はあった(存在した)。 <虐殺2>はなかった(存在しなかった)。という二つの命題は、違う概念を語っているのだから、当然両立してもかまわないものとなる。しかし、これを違う概念と考えずに、同じ「虐殺」という文字が使われているので同じものだと考えてしまうと、まったく正反対の主張が同時にされているように見えてくる。そうすると、どちらかが間違っているに違いないということになるわけだ。それは形式論理的な矛盾になってしまうからだ。<虐殺1>と<虐殺2>は、「虐殺」という言葉では同じでも、視点が違うのだから、判断が正反対でも両立しうると考えれば、これは弁証法的矛盾というものになる。複合概念の存在を考えると、そこには弁証法的矛盾が発生する可能性がある。これを形式論理的矛盾と勘違いすれば、そこには不毛な二項対立が発生することにもなる。永久に相手を納得させられない対立した主張が展開されることになる。所与の「事実」がこのようなあやふやなものになってしまえば、「事実」は個人によって違うものになり、世界の分析の客観性は失われる。所与の「事実」を安定した明確なものにするために、それが単純なものであるという規定はどうしても必要なのではないかと僕は思う。ただ、言語の概念における単純性の判断そのものは厳密に考えると難しいものもある。僕は「死んだ」という概念は「心臓が止まった」というものと同等だと考えると単純なものと感じるが、脳死の現場などでは、心臓が動いていても「死んだ」と考えようとしているので複合概念になってしまう。戦争において「死んだ」という判断は、「心臓が止まった」という単純概念で考えられると判断すれば単純概念になると思う。戦争において「虐殺された」という概念は僕は複合概念だと思う。だから、このことについて「事実」を求めようとするなら、単純概念に還元して存在を議論しなければならないのではないかと思う。その同意がたとえ困難であっても、そうしなければ不毛な二項対立になってしまうのではないだろうか。
2007.11.22
コメント(3)
-
応用問題について
算数・数学教育では、「応用問題」というものが課されることがある。これは、基本的な計算技術を学んだ後で、その計算を実際に応用して答えを求めようとするような問題を考えるものだ。計算して答えを出すだけなら、これには深い理解はいらない。アルゴリズムを記憶しておいて、その手順に従って数字を操作すればすむことだ。そこには主体的な思考というものがないので、コンピューターという機械にも出来る事柄になる。これに対し、応用問題を解くということは、実際の問題に対しその技術を適用することになる。このときも、いくつかの問題のパターンを公式化して、その公式に当てはめて計算をすることにすればある程度のアルゴリズムかが出来る。しかし、計算そのもののアルゴリズムと違い、どの公式が適用できるかという最初の判断においては、単に表面的な現象を見てすぐに決められるとは限らない。計算そのものであれば、そこにある数字を読んで、計算の記号を読むだけで次に何をするかが決まる。だが、応用問題のほうは、その問題が示している現実の構造を把握しないと、公式を適用するにしても、どの公式を当てはめるかという判断が決まらない。さらに、この応用問題が公式化されていない新しい問題であった場合は、いよいよその構造の把握が大切になってくる。応用問題を解くということは、その問題を、何らかのアルゴリズムが適用できる形に作り変えることだといってもいいかもしれない。我々が直面する問題は、実際には具体的な応用問題であり、一般論を学ぶのはその応用問題に適切な答えを出したいからだといえる。応用問題の現れが顕著である数学の場合を取っ掛かりとして、一般論を現実の問題に応用して解答を得るということについて考えてみたいと思う。小学校の四則計算の応用に「仕事算」と言うものがある。これは、一人が行う仕事の量を合計すれば、複数の人間ではその仕事が早く終わるという現実の構造を反映したものになっている。Aが行えば10日でその仕事が終わり、Bが行えば12日で終わるものだとすれば、それぞれ、Aは全仕事量の1/10、Bは全仕事量の1/12を1日に行うことになる。そうすれば、二人で協力して仕事をすれば、1日に全仕事量の11/60(=1/10+1/12)をこなすことになる。そうすればこの仕事は、二人でやれば6日目には完成する。これは分数の計算の応用問題になっているのだが、これはどんな仕事にも応用できるものではない。その仕事の現実の構造によっては、「仕事算」を仕事に応用できなくなる。なぜなら、「仕事算」では、仕事の内容という質的な面は捨象され、仕事の量的側面のみが計算の対象になっているからだ。だから質的側面が仕事の遂行に大きく関わってくるような仕事にはこの「仕事算」は応用できない。「仕事算」が計算できるのは、協力して行う複数の仕事が、同時並行的に行えるものという条件が必要だ。ある仕事が終わった後に次の仕事をしなければならないという順番が決まっているという「質」が問題になる時は、その量的側面だけを計算しても現実にはそぐわない結果が出てくる。実際に家を建てるなどという仕事を、量的な面だけを考えてみると、10人の大工が3ヶ月(90日)で行うとした場合、一人の大工の1日の仕事量は1/900になる。それでは、大工の数を900人に増やせば家は1日で建つかといえば、そんなことはあり得ない。家を建てる仕事はどれも同時並行的に出来るわけではないからだ。壁と屋根を同時に作るなどということは出来ない。空中に浮いた屋根などはないからだ。だがベルトコンベア的な仕事なら同時並行的に行える形に仕事の質を変えているので、人間を10倍に増やせば生産量も10倍になるという単純計算が出来る。「仕事算」が適用できるモデルケースともなるだろう。このような「仕事算」の適用の条件の問題は、「仕事算」の公式そのものには記述されていない。「仕事算」の公式は、平均化された仕事が、協働することによって足し算で計算されるのだということを語るだけだ。これを実際に応用する際は、公式に書かれていない部分としての、それを応用する現実の仕事の構造にまで考察を及ぼすという、より広い思考の展開が必要になる。このあたりに応用問題の難しさがある。論理というのは数学よりもさらに一般性の高いアルゴリズムなので、さまざまなところに応用されるが、応用する対象の構造を考えるときにも論理が使われるので、論理そのものを強く意識して対象の構造を捉えることがかえって難しくなる。自明だと思えることの正しさの根拠を論理で捉えることが出来なくなってしまう。例えば「弁証法」と呼ばれる論理は、次の3つの法則にまとめられると三浦つとむさんは指摘をしている。・否定の否定・量質転化・対立物の相互浸透この弁証法を現実の対象に応用するには、その対象が弁証法の応用にふさわしい構造を持っているという前提が必要なのだが、これはけっこう難しいのではないかと思う。「否定の否定」というのは、一度否定されたものが、それでなくなってしまうのではなく、形を変えて生き残り・発展した後に再び復活するので、もう一度否定されるというふうに解釈される。この「否定の否定」はどの現象にも必ず現れるというものではなく、その契機を失えば、最初の否定で全滅してしまう。「若いうちの苦労は買ってでもせよ」ということわざがあるが、これはその苦労のおかげで努力・学習することによって将来の成功がもたらされるという「否定の否定」の法則を語っている。しかし、その苦労が実りあるものに結びつかずに、背負いきれない重荷になって人間をつぶしてしまうこともある。過労死などの現象はそのようなものだろう。そこでは「否定の否定」の契機が失われてしまう。弁証法の論理が応用できる対象というのは、視点が違うところから見たときに正反対の異論がともに整合的に成立してしまうようなものでなければならない。誰が考えても同じ結論しか出てこないような現象は、弁証法の論理を適用する契機を失う。弁証法的な矛盾が見つからない対象に対して、無理やり矛盾を設定してしまえばそれは形式論理的な矛盾になってしまう。つまり現実には起こりえないことを主張することになる。そのような弁証法の応用は、ばかげた妄想を語ることになり、それによって弁証法は詭弁であるという評価を受けてしまう。「男である」という規定と「女である」という対立した規定を矛盾として設定して、それが総合されて、「男でもない女でもない、新しい人類」の形が生まれると考えるのは、それが頭の中で考えた想像の世界だけの話であれば、弁証法による詭弁になるだろう。現実に男の特性と女の特性の区別が消えていっているという現象に弁証法を応用するなら、現実からの規定で詭弁に陥るのを防ぐことが出来るが、現実を無視して弁証法の法則だけが一人歩きすると、やがては男女の区別がすべてなくなって、分業による社会さえも否定される方向に行きかねない。弁証法の法則は、男女の役割の固定化も否定するが、それが完全になくなるという主張も否定される。どのようにして弁証法的な矛盾を背負って発展していくかという展開を教えるのが弁証法の法則の応用になる。ウィトゲンシュタインが展開した哲学も、それを個人のものとして捉えずに、一般論として理解したときにはその応用というものが見出せる。それを、あくまでもウィトゲンシュタイン個人のものと見るのであれば、応用よりも、ウィトゲンシュタイン自身がどう考えたのかを正しく受け取ることに関心が行くだろう。その時は、ウィトゲンシュタイン自身が間違えたこともそのまま受け取るという姿勢になる。とにかく、ウィトゲンシュタインという個人が問題になる。だが、それを一般論として捉えると、ウィトゲンシュタイン自身が正しく考えた限りにおいてそれを受け取ることが関心の中心になる。それは、ウィトゲンシュタインが見ていたものと同じものを見て、そこから同じ判断が導かれるかということを考えることが中心になる。ウィトゲンシュタインがどう語っているか、どう考えているかというよりも、その見たものを忠実に再現して、そこから得られる判断がウィトゲンシュタインが語るものと同じものになるかが理解の中心になる。その意味で、僕は直接ウィトゲンシュタインに向かわずに、野矢茂樹さんが語るウィトゲンシュタインを元に考えを進めている。これは、ウィトゲンシュタインは、直接学ぶにはあまりに難しすぎて、知らなければならない予備知識が多すぎるということがある。野矢さんが語るウィトゲンシュタインなら、その予備知識を補ってくれるので理解がしやすくなる。また、僕にとっての関心は、ウィトゲンシュタインが何を語っているかという個人に関わるものではなく、ウィトゲンシュタインが捉えた一般的な真理の理解というものになっている。ウィトゲンシュタインが語ることが真理であるなら、それが真理であるということの理解をしたいと思うものだ。ウィトゲンシュタインに深く個人的にかかわっている思いや考えを捨象して、一般論として理解可能なところに考察を絞りたいと思う。それは、野矢さんの語ることを参考にした方が理解しやすいと思っている。その野矢さんは『『論理哲学論考』を読む』という本の中で、「ウィトゲンシュタインが「対象」と呼ぶものは事実の構成要素である個体、性質、関係に他ならない。つまり、単に個体だけではなく、性質と関係もまた、「対象」と呼ばれる」と書いている。これには、専門の哲学者からの異論もあるそうだ。異論があるということは、ウィトゲンシュタインが本当はどのような意図を持っていたのかはわからないということだ。これをウィトゲンシュタインに聞いてどちらかに決めるというのは、ウィトゲンシュタイン自身の伝記としては意味があるかもしれないが、哲学的な正しさとしてはあまり意味がないように思う。野矢さんのように考えたほうが整合性があるのか、その反対のほうが整合性があるのかを考えて、ウィトゲンシュタイン自身がどう考えようと、どちらが正しいのかを考えるほうが哲学的には意味があるのではないかと思う。そして、これはウィトゲンシュタイン自身が直接語っていないのであるから、ウィトゲンシュタインが展開した一般論の応用ということになるだろう。僕が展開した存在の問題に関しても、ウィトゲンシュタイン自身が直接言及しているかどうかは確かめていない。それは、ウィトゲンシュタインが展開した世界像と同じものを見ようとすれば、そう考えたほうが整合性があると僕が考えただけに過ぎない。存在を単純なものに限るというのは、少なくとも世界の出発点において合意できる部分の最低限のものを見出すということで整合性を持つのではないかと考えたからだ。複合概念の存在を考察すれば、それが「存在する」ということに関して合意が難しくなる。存在の合意が難しくなれば、それをア・プリオリの前提として展開する論理空間が個人によってまったく異なるものになり、世界は個人の数だけ存在するのだということになってしまう。これでは一般論を展開する余地がなくなる。一般的・普遍的真理を捉えるには、実体としての存在は単純なものに限るという考察が、僕の応用問題の捉え方なのだと思っている。
2007.11.21
コメント(0)
-
「猥褻行為」は存在するか
『社会学の基礎』(有斐閣Sシリーズ)という、大学の教科書として書かれた本の「行為と役割」という章を宮台真司氏が執筆している。ここでは行為の同一性に関して議論を展開しているのだが、二つの行為を比べてそれが同一であるか違うかという判断を3つのレベルにおいて考察している。その3つのレベルは、として捉えられている。それぞれのレベルは視点の違う見方になるので、では同一だがでは同一ではないという判断も成り立つ。つまり、弁証法的な意味での肯定と否定が同時に成り立つという矛盾が見られる。これは「行為」というものが単純なものではなく複雑なものであることを意味している。「行為」というものは、物理的に現れた現象にすべての属性が読み取れるのではなく、そこに人間が意味を与えることによって「行為」として受け取ることが出来る。つまり、物理的には同じように見えても、その意味が違うという受け取り方をすれば「行為」も違うという理解をするわけだ。この意味の問題に関連して「行為」は3つのレベルでの解釈が出来るものだと思われる。このように複雑な対象である「行為」に対して、それが「存在する」という言い方を考えてみたいと思う。結論を先に言ってしまえば、この場合の「存在する」という言い方は、僕は比喩的な表現だと思っている。文字通りそこに「行為」という言葉で指し示される何かが実体的に存在するのではなく、そこに存在する何かに関連させて、その意味がある「行為」だと解釈できるという判断が可能なとき、その何かの存在に「行為」の判断を重ねて、「存在する」という比喩的な言い方が成り立つのだと思う。これは、言葉の使い方にあまりにもこだわった考えのように聞こえるかもしれないが、「存在する」という言い方の真理性の強さが判断の間違いの反省を行うのを邪魔する気がするので、「存在する」という言い方にはこだわって考えたいと思う。一度「存在する」という判断をしてしまうと、その存在を前提とした思考において、前提そのものの存在を反省する契機がつかみにくいのではないかと思うからだ。存在はア・プリオリな前提として思考を強く支配する。その存在が前提されていると、そこから導かれる存在の属性は自明なものとして疑いを入れる余地が無くなる。真理をより確かなものにするための懐疑を忘れないためにも、思考の前提となる存在に関しては厳密に考えたいと思う。宮台氏は、猥褻行為に関して次のような記述をしている。「卑近な例だが、男の人が女の人の胸に触ったとしよう。これは猥褻行為だろうか?彼らの関係が恋人同士であれば、猥褻行為ではないかもしれない。しかしこれも、プライベート・ルームの中ならいざ知らず、電車の中で公衆の面前で行われたらどうだろう?また、赤の他人同士で行われたならば、猥褻行為だろうか?これも一概には言えない。男の人が医者であり女の人が患者であれば、猥褻行為ではないかもしれない。しかし、それも診療室の中で診療時間に行われたのではないとすると、どうなるか?」これは、「胸を触る」という物理的な現象が、「行為」としてはどう解釈されるかということを考えた記述になっている。つまりその現象の意味としての「行為」はどのように解釈できる可能性があるかを考えている。これは実にさまざまなものが考えられ、「猥褻行為である」という解釈と「猥褻行為ではない」という対立する解釈のどちらも成り立つ可能性があることが指摘されている。その解釈の違いは「文脈」と呼ばれるものの違いから生まれる。その現象が、どのような状況の下に現れているかという違いで「行為」の意味の受け取り方が違ってくるわけだ。このことは「行為」という概念が複合概念であり複雑なものであることを物語っている。「胸を触る」という現象が、猥褻行為ではないと判断するためには、次のような命題が真理であることが必要だ。 「二人が恋人同士である」かつ「それはプライベートな空間で行われた」実際には、これ以外にもいくつかの命題が論理語「かつ」という言葉で結ばれる必要があるだろう。また、ここで語っている「恋人同士」「プライベート」という言葉自体にも複雑さが含まれている可能性がある。これらをさらに分割して単純化しなければ複雑性を減らすことは出来ない。この複雑性はどこまでいってもきりがないということもあるだろう。どこでピリオドを打つかという難しい問題があるが、それは社会的合意の可能性というものにゆだねるしかないのではないかと思う。どの程度単純化すれば多くの人が合意できるかという地点を、実践的に探さなければならないのではないかと思う。複雑性を持った複合概念は、それが成り立つという判断が多くの条件が成立するという、その概念の定義によって異なってくる。その定義がそっくり同じものであっても、その条件が成り立っているかどうかで判断が違ってくるということもありうる。一般的に視点や立場が違えば、その総合判断は違ってくる。この違いをどう処理すればいいだろうか。どちらかが正しくて、どちらかが間違っているとして対立を解消できるだろうか。これが、もしも存在する物質の属性にかかわる考察であれば、どう見るかという視点の問題はかなり合意を得るところまで持っていける。それは客観的に、自分の意志とは独立して存在すると思えるので、自分ではない第三者的な一般的な視点を定めてもそれほどの違和感を感じないですむだろう。しかし、自分の生き方や思想・イデオロギーに関わった視点は、それを否定して他の視点を持つことが難しい。自分の存在意義そのものまで否定してしまうような感じになるからだ。複合的概念で語られているものが、もしも実体的に存在すると捉えられているならば、その視点は客観的なものであり、自分の意志と独立してあるのだと考えなければならない。そうすると、本来は自分の主観が大きく関わって視点が決まっているものであるのに、それこそが客観的で正しいものだという思いが強くなるだろう。マルクス主義的な唯物論が、多くの場合真理の押し付けになっていたのは、本来は存在として捉えるべきものではないものを、存在こそが基礎になるという唯物論を教条主義的に信じたために、存在から与えられた判断という観念に過ぎないものを押し付ける結果になったのではないかとも感じる。逆に、その判断が間違っていたと気づいたときに、反対の極に振れてしまうようなことも起きたのではないかと思う。判断が間違っていたというのは、解釈における誤謬なのであるから、どの存在の属性の解釈を間違えたかということを考えればいいのであるが、解釈ではなく存在の問題だと思っていれば、反対のものの存在を想定してしまうのではないかと思う。戦前・戦中において共産主義者の転向という問題が現れたようだが、これは、暴力による脅迫だけに帰するのではなく、本気で共産主義そのものが間違いだったと思った人もいたことだろう。そして、その信念が強ければ強いほど、それが間違いだったと感じた時は極端な否定になったのではないかと思う。複合的な概念に対して、その判断が極端に偏らず、多くの人の合意が得られるような形になる妥当性を持つようにするには、それを存在の問題にするのではなく、複合的な論理結合の問題として捉えるほうがいいのではないかと思う。存在の問題は、あくまでも単純な対象に限るということが、現実の世界においては「事実」という正しい命題の決定には重要ではないかと思う。ウィトゲンシュタインは、世界を「事実」の総体から出発させたが、「事実」を捉えるためにはそれが複合的であっては、それが「事実」であることが決定出来ず、考察の出発点である前提そのものが危ういものになってしまうのではないかと思う。ア・プリオリな前提として、所与のものとして「事実」があるのなら、それは合意可能な単純なものに限るというのは、整合性のある考え方ではないかと思う。「南京大虐殺」という文脈で語られる「虐殺」「残虐性」という概念も複雑な複合概念だと思われる。物理的には同じと見られるような現象であっても、文脈上は「虐殺」だと判断されない場合があるだろう。現実の条件にもよるだろうし、歴史的な文脈も関わってくるのではないかと思う。その当時においてはどの程度が「残虐性」として捉えられていたかが問題にもなるだろう。「南京事件」を語る時は、個々のディテールに関して、それが末梢的ではなく本質的なものを表しているかどうかをまず考えなければならない。そして、その行為が「虐殺」に値するかどうかが、複数の視点から語られなければならない。誰もが「虐殺」と認めるものだけを集めるのでもなく、一つの視点だけから「虐殺」と判断できるものだけを集めるのでもなく、あらゆる視点からの考察が必要だろう。そうすることによって、ある意味では「虐殺」というインパクトの強い言葉で語られるセンセーショナル性は薄められるだろう。それは、「虐殺」を告発する側からは利敵行為に映るかもしれない。しかし、何が正しいことなのかを考えるならば、現実の出来事というのは、解釈によって違うふうに見えるということを理解しなければならないのではないかと思う。それがたとえ自分の見方とは違うものであり、信念やイデオロギーに反するものであったとしても。「南京大虐殺」に関しては、多くの人がその「虐殺」という見方に疑問を抱いている。そう見る人々に対して、それは見方が間違っているのだと単純に切り捨てるのではなく、その見方にも一部の理があることを理解することが必要なのではないかと思う。逆に、「南京大虐殺」を否定する人々も、それを「大虐殺」だと解釈する見方にも整合性があることを理解すべきだろう。その上で、どちらの見方がより多くの人の合意が得られるかを考えるべきではないかと思う。立場やイデオロギーに関係なく、対象としての単純さを理解する範囲での合意を考えなければ、この対立は永久に不毛なものとして続くのではないかと思う。『言語ゲームと社会理論』(勁草書房)という本の中で著者の橋爪大三郎さんは、「我々は一方で、さまざまな私的体験をしており、体験の生じる場としての内面を持っている。また一方で、私的体験を表出する、形式化された振舞い(言語ゲーム)を持っている。両者は調和的に共存している。それでは、両者のどちらがいっそう、根本的なのか?前者だと考えると、収拾のつかない不合理をきたす。そこで、ウィトゲンシュタインは、躊躇なく後者だと考える。内面も各私的な主体も、実体としては存在しない。それらは、言語ゲームの与える、効果なのである。」と語っている。個別・具体的な体験で現れる存在は、言語で与えられる概念としては、単純なものでさえも「存在しない」と語っているようにも感じる。これはあまりにも極端な指摘なのでまだ理解が不十分だが、橋爪さんが語る「意図や、予想、願望、記憶、命令などは、いずれも、言語によって生み出される私的な出来事である」という指摘はよく考えてみたいものだと思う。「命令」というものは、実体として存在を議論できるものではなく、やはり解釈に属する概念なのかもしれない。だからこそ、「命令」の問題を存在の問題にしてしまえば、それは否定される運命になってしまうのではないかとも感じる。これは、それを解釈の問題にすることによって、それが「あった」という比喩的な表現の正当性を議論できるようになるのではないだろうか。
2007.11.19
コメント(0)
-
トートロジー(同語反復)という論理法則
カール・ポパーの「反証可能性」という言葉を、必要条件と十分条件という観点から考えてみようと思っている。「反証可能性」という概念は、その考察の対象が「科学である」ということに関して必要条件となるが十分条件ではないというようなことを考えている。ポパーの考察の対象は、科学を装ってはいるが科学ではないという、誤解と錯覚を与えるようなものだったので、「科学ではない」と結論できるような必要条件が問題となったのではないかと思われる。それに対し、板倉聖宣さんが提唱した仮説実験の論理(手順)は、「科学である」ということの十分条件を与えるものだと思われる。この違いが、科学の認識においてどのように関わってくるかを考えてみようかと思った。それで「反証可能性」に関する資料をいろいろと眺めていたら、論理学が科学ではないということの根拠にこの考察が役に立つと思った。特に、トートロジーと呼ばれるものは、論理的には絶対に正しいと考えられているものなのでまさに「反証可能性」は無いといえるものだ。論理における「反証可能性」の問題は、何か言い逃れをするようなごまかしではなく、絶対的に正しいものだから「反証可能性」が無いという特殊な面を持っている。それは似非科学を名乗っているのではなく、科学とは違う種類の真理を語っている。このトートロジーは、論理法則としては簡単なものだ。Aによって任意の命題を代表させれば、仮言命題 A →(ならば) Aという形で表現される。Aという同じ命題が繰り返されるので「同語反復」などと呼ばれている。Aとしては任意の命題を入れることが出来るので、明らかに間違っていると思われる命題でも入れることが出来る。例えば、「地球は太陽より大きい」という命題を入れると 「地球は太陽より大きい」ならば「地球は太陽より大きい」これは、Aとして考えている命題は明らかに事実に反する。しかし、この仮言命題全体は論理としては正しい。「地球は太陽より大きい」ということを仮定として設定すれば、そこから「地球は太陽より大きい」ということが結論として導かれるということが論理的な意味になっている。これは論理としては正しい。結論だけを取り上げて、それが事実と違うではないかといっても、この仮言命題全体を否定することは出来ない。「反証可能性」は無いのである。この仮言命題を否定するには、その仮定の元で結論が必ずしも成り立たないということを言わなければならないのだが、仮定と同じ結論を主張するトートロジーは、その仮定の成立を前提としたときに過程の命題が成り立たないと結論してしまえば、それは今度は矛盾律という論理法則に反することになってしまい、論理そのものが破綻してしまう。似非科学の代表例は心霊現象に関するものだが、ある種の心霊実験がうまくいかなかったときに、それは霊の運動を邪魔する人間がいたからだという理由がつけられる場合がある。これは実験の失敗という反証に対する言い逃れの代表的なものではないかと思う。このような言い逃れが許されるなら、心霊現象の真理性の確認は出来なくなり、「反証可能性」が無くなる。従ってそれは科学ではなく似非科学だということになる。しかしトートロジーは、論理的には正しいのでそれは似非科学のようなごまかしには見えない。しかも日常言語での表現によってトートロジーであることが分かりにくい表現になっている場合がある。このような時、その命題がトートロジーであって科学ではないということを理解するのはたいへん難しいのではないかと思う。それが論理的には正しいだけに、正しいことを言っているのだから、現実にも正しいのであり普遍性を持っている科学(信頼できる真理)だという認識に傾きやすい。「適者生存 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』」によれば「創造論者などは進化論への反論として「生き残った物が適者であり、適者が生き残る」と言う主張は循環論(あるいは同語反復、トートロジー)であり科学ではない、と主張する」と語られている。進化論が、科学と呼ばれる理論になっているかどうかは難しい問題をはらんでいるのだが、そこにはトートロジーの問題も深くかかわっているようだ。日常言語での主張には暗黙の前提というものが含まれている。「適者生存」ということを語るとき、その意味を、それに関して言及する前に確定しておけば論理的な意味でのトートロジーを見ることはた易い。数学などは、論理を展開する前にすべての用語の意味を確定する。そして、そこで確定した意味以外のものをまったく含ませることなく論理を展開する。その意味では数学は壮大なトートロジーの体系だと言っていいだろう。「適者」の概念が、もしも「生き残ったもの」というものであれば、「適者が生き残る」という「適者生存」の法則はトートロジーになる。 「適者」が生き残る(「適者」=「生き残ったもの」を代入) ↓ 「生き残ったもの」が生き残る ↓ 観察の対象が「生き残ったもの」 ならば それは「生き残ったもの」である日常言語を使っても、最後の言い方になればそれがトートロジー(同語反復)であることを見るのはた易いだろう。「適者生存」の法則は、「適者」の定義の仕方によってはトートロジーになる。それは反証可能性の無いものになり、科学ではないと結論できる。しかし、「適者」の定義として違うものを使えば、それはトートロジーにはならない。適者としてある種の能力を持ったものという定義をすれば、「適者生存」の法則は、ある種の能力を持ったものが生存する可能性が高いという言い方に変えることが出来る。そうすると、その能力を持っているにもかかわらず、結果的に生存出来なかった生物が存在する可能性がある。つまり反証可能性のある命題になるというわけで、科学である必要条件を持つことになる。後の考察は、その反例が仮説そのものを否定してしまうのか、それともその反例は特殊な例外であって、仮説そのものは維持されて一般化されていくかということを考えることになる。この一般化の過程で仮説実験の論理が成立するならば、それは普遍性を持った科学(真理)の資格を得ることになる。科学としての十分条件が満たされたと判断される。日常言語による表現では、それがトートロジーになるかどうかは、その言葉の定義に大きく依存している。議論の出発点において言葉の定義が明確にされているならば、それがトートロジーになることを見やすくなるが、暗黙の前提として辞書的な意味が立てられている時は、その解釈によって実はトートロジーの主張をしていることになってしまう場合がある。そのような時は、すでに結論の主張が前提の中に入り込んでいるので、主張している人間には自明のことのように感じてしまうが、同じ前提を共有していない人間は、単なる詭弁にしか聞こえなくなる。歴史的事実の「存在」に関しては、このようなトートロジーをめぐる議論のすれ違いがかなりあるのではないかという気がしている。例えば「南京大虐殺」と呼ばれる歴史的事実に関して、そこで何が「あった」かという「存在」の問題を考えると、「あった」と主張される事柄の定義によって、その「存在」の主張はトートロジーとなってしまう場合がある。そこで戦闘行為があったということはおそらく誰もが認める事実となるだろう。戦闘行為という言葉の定義に食い違いが生じる可能性は低いからだ。そして、戦闘行為の結果として死んだ人がいたことも事実だという同意が出来るだろう。これらは、現象面を捉えた単純な判断に還元できるからだ。そこには立場の違いなどはあまり関わってこない。ウィトゲンシュタインが、事実を単純なものに限ったのは、この同意が出来るという範囲が単純なものに限られるからではないかと思う。対象が論理語で結ばれるような複雑化したものになれば、立場の違いや観点の違いで同意できなくなり、それが事実として確定しなくなるのではないかと思う。「南京大虐殺」に関して、それが「あった」「なかった」とまったく正反対の主張がされるのは、どちらかが正しくて、どちらかが間違っているという単純な話ではないのではないかと思う。それが指し示す事実が単純なものではないので、まったく正反対の主張がどちらも成立してしまうのだと思う。それは、深く「虐殺」という言葉の定義によっているだろう。「虐殺」という言葉をどう定義するかという前提の中に、すでに「あった」という主張と「無かった」という主張のどれもが含まれているのだと思う。どのような定義を取るかでその主張が違ってくる。しかも、自分の定義が正しいと思えば、当然相手の主張が間違っているとしか思えない。だが、それはたぶん現実の事実の観察によっては決定出来ないトートロジーになっているだろうと思う。それが決着のつかない不毛な議論を生んでいるのだろうと思う。沖縄の集団自決に関しても、そこで多くの人が自死したという現象的な事実に限って考えれば、それが「あった」ということに反対する人はいないだろう。誰もが同意するに違いない。しかし、それが軍の命令で行われたということに関しては、「軍の命令」という言葉の定義をどうするかで判断が違ってくる。この定義が違えば、仮言命題の前提の違う論理の展開を考えることになるので、結論がまったく違っても論理としてはどちらも正当であるという場合もある。言葉の定義、特に日常言語の使用の場合においては、その定義を明確に意識して行うことは少ない。暗黙のうちに、自明だと前提していることを元に論理を展開している。そのような時は、実はトートロジーを語っているのに、それがトートロジーであることに気づくのは難しい。このトートロジーの問題は、仮言命題の全体としては正しいのだが、その前提が本当に正しいかどうかが決定出来なければ、結論の正しさが保証されないというところにある。「A→(ならば)B」という仮言命題の正しさが確認されても、それだけでは必ずしもBの正しさが得られないのである。Bが正しいことを言うには、同時にAが正しいことも語らなければならない。「A→(ならば)B」という命題は、その正しさを証明することが一般的には難しいので、簡単に結論の正しさを主張する人はいない。だが、「A→(ならば)A」という命題は、トートロジーであり、その正しさを示すのは容易である。そのため暗黙の前提に気づかないと、Aの正しさが自明ではないかという気分にもなる。我々が論理を展開するとき、特に日常言語によって論理を展開する時は、その言葉の定義に慎重にならなければならない。暗黙の前提を持っていれば、それはトートロジーという反証可能性の無い主張になっているかもしれない。そして、反証可能性の無い主張は、科学のような信頼性の高い真理を与えてはくれないのだということを自覚しなければならないだろう。勝手な思い込みである場合が多いのだ。
2007.11.16
コメント(0)
-
数は実在するか
以前のエントリーで、負の数を実体的に表す物質的存在はないという議論をいくつか展開したが、存在論というのは現実に対して何らかの考察をするときに前提となる重要なことではないかと思う。この存在論の発想が違ってくると、それを基礎にした論理展開も微妙にずれてくるように感じる。特に歴史的事実などの存在をめぐっては、「存在した」「存在しなかった」という判断は、存在論のあり方にかなり規定されるのではないかと思われる。僕にとって負の数は概念として創りあげたものというイメージが強かったので、そのままの形では実在しないというのはほぼ自明のことではないかとも感じていた。しかし、概念として捉えた物事が、そのままの形では実在しないと結論してしまうと、すべての概念はそのままの形では実在しないのだから、概念と実在との結びつきが考察できなくなってしまう。実際には、現実の存在から正しく抽象されてきた概念と、空想的に概念を結びつけて実在と関係なく創りあげた概念があるだろう。この両者をどのようにして区別するかということが問題になる。数に関して言えば、自然数というのは文字通り自然の対象に基礎を置いた数であり、実在する物質的存在を観察し抽象して創りあげた概念というものになる。それに対し負の数は、実在の対象の性質を概念として取り出し、その反対の概念と結びつけて新たに概念操作として創りあげた概念というものになる。ここに直接の実在と結びつかない契機が存在すると僕には思える。野矢茂樹さんのウィトゲンシュタインの解説を読んでいると、ウィトゲンシュタインは、存在というものを考察を進める前提としてア・プリオリに与えられたものと考えていたようだ。存在そのものを証明することは出来ないが、そのものについて何か考えられるというのは、それが存在しているという前提がなければ、観察による新たな発見も出来ず、考察そのものを進めることが出来ないと考えられる。思考の前提として、論理空間を構成する対象として存在はア・プリオリに前提されていると思われる。この存在は錯覚ということもありうる。存在していないものを存在しているように勘違いしていることもあるだろう。だが、その時はそれが錯覚であると分かるというところに、ア・プリオリな前提としての存在がなかったという判断ができるだろう。霊的現象だと思って観察したことが錯覚だと分かった時は、そこに何かが存在したことは確かなのだが、それを「霊的現象」と呼ぶのは間違いだということが結論される。逆に言えば、錯覚だと確認できない事柄に関しては、我々がそれを観察し、新たな事実を発見していけるのであれば、そこにはア・プリオリな存在が前提されていると言わざるを得ないだろう。このときには、新たな事実の発見という、ア・プリオリではない事柄が重要になる。もし、その考察が新たな発見から得られたものではなく、概念からの論理的考察で発見されたものであれば、そこにはア・プリオリな存在は前提する必要がなくなる。数学は、その出発点は、自然数のように実在から発想を借りているのだろうが、一度展開されてしまうともはや実在を必要とせず、論理のみによって新たな概念を作り出していけるようになる特殊な思考の産物ではないかと思われる。錯覚を考える上で面白いのは「水槽の中の脳」という想像だ。我々が感覚するものはすべて電気信号に過ぎず、本当に実在しているものは何もないという想像だ。これは、我々がもしそのような状態にあったとしても、我々にそれを確かめる方法はない。我々の観察が新しい発見を得ると感じるなら、我々はそこに未知なる存在、ア・プリオリに与えられた存在を感じるだけで、それが錯覚だということは確認のしようがない。それを確認できるのは、我々の世界を一段高いところから見ている、電気信号を与えている立場の者だけで、それは神と呼ばれるようなものなのかもしれない。いずれにしても、我々の観察の対象になるということがア・プリオリな存在の特徴になるだろう。それをウィトゲンシュタインは「対象」と名付けたのではないかと思う。また、この「対象」は、実在を確認できるものと考えるなら個別的・具体的な「個体」ではないかとも感じる。抽象して得られた概念は、論理操作の結果として得られるもので、個別的な「対象」として存在を前提できるものではないように感じる。実在というものを、観察の対象としてア・プリオリに与えられた「対象」と考える存在論で考えていこうと思う。そして概念を、この「対象」からの抽象で得られるものと、概念に対する論理操作で得られるものとに区別して考えたいと思う。このような考察から、概念の実在というものも、現実の個体から抽象される概念は実在するというふうに考えたいと思う。逆に言えば、概念の論理操作によって得られる概念は実在という存在の考察の対象にはならないと考える。それは、存在を議論するのではなく、解釈という判断の妥当性を議論すべきものだと僕は考える。さて自然数というものは、個体からの抽象によって得られるということは次のように考えると導かれる。現実存在の個体というのはさまざまの属性を持っているが、その個性を捨象(抽象)して同種というものでまとめることが出来る。その同種の個体を集めて一対一対応がつけられるものとしてまた個性を捨象(抽象)する。そのときに得られるのが自然数だと考えられる。リンゴ、犬、人間、星、そのほかさまざまのものが観察の対象として実在している。それらはそれぞれ違った属性(個性)を持っている。リンゴは丸い形をしていたり、甘酸っぱい味をしていたりする。犬は4本の足で歩くという性質を持っている。これらの属性はさまざま観察できるが、それらをすべて捨象して1対1対応という観点でのみこれらを観察する。そして1対1対応がつけられたとき、それは「同じ数」であるというような判断をする。ただ1個の存在に対して1対1対応がつけられたときに数の1が抽象される。そして、この1をさらに付け加えたものの1対1対応を考えることで数の2が抽象される。このような操作によって、自然数の列1,2,3,4,5……が得られる。これらは、観察によって得られる直接の概念であって、実在に基礎を持っていると考えられる。1そのものは抽象された概念であるから存在しないものの、1の基礎になる実在は個体として指摘することが出来る。何らかのものを一つ示すことはいつでも出来る。これに対して、負の数というのは、いったん捨象された質をもう一度考察の対象にして概念化することから得られる。例えば、温度計の0度を液体の水が固体の氷になるところだという規準を与えると、液体と個体という質に対応してプラスの温度とマイナスの温度が得られる。このとき実在するのは温度計の目盛りとしての、水銀やアルコールの長さというものになる。それは自然数を基礎にした数字になる。(分数や小数の問題はもう少し厳密な議論が必要なのだが、今は自然数からの連想で実在に基礎を置いたものと考える。)プラス10度であっても、マイナス10度であっても実在するのは0という目盛りからの距離が1度を基準として10個あるということだ。そこにはマイナス10が存在しているのではなく、マイナスという解釈を妥当にするような現象が存在しているだけだ。プラスというのは、直接実体を示すので名詞的なものだと書いてあるのを見た記憶がある。それに対してマイナスは形容詞的だと書いてあったようだ。形容詞というのは、実体に対する解釈であり、その属性の判断になる。「リンゴが赤い」というのは、リンゴに対する判断であり、「赤い」がどこかに実体として存在しているのではない。数学では借金をマイナスの例としてよく使うが、借金をプラスの例にすることはない。これはどうしてだろうか。数直線などで右をプラス、左をマイナスにするのは、習慣的なものもあり、また関数の変化を見るのに左から右に流れるように眺めたほうが見やすいということもあってそうするが、それは論理的必然性があってそうするのではない。偶然、我々の認識の仕方がそのほうが都合がいいというだけのことだ。便宜的なものである。だが、借金をプラスにして考えるのは、論理的な違和感を感じる。これはどこから生じる違和感だろうか。借金の反対の、財産と言おうか、お金の所有は実際に存在するお金という実在がある。この存在に対応させるという意味ではプラスがふさわしい。反対の借金では、例えば2万円の借金をしていると、目の前に2万円のお金があっても、それは無いものとして見なければならなくなる。目の前の事実をそのまま受け取るのではなく、ある種の解釈をして受け取らなければならなくなる。形容詞的な受け取り方になるのではないだろうか。借用書というものがあれば、借金も目の前の存在として実在するのではないかという疑問もあるかもしれない。しかし、その借用書が、例えば1枚が1万円の借金を表しているとしても、そこに実在するのは借用書が2枚(プラス2)存在するということでしかない。決してマイナス2万円があるという言い方は出来ない。それは比喩的な表現であり、実在を示した表現とはいえない。マイナスに関しては、それが形容詞的で、論理操作によって得られたという点を強く感じるが、自然数以外の小数・分数に関しても、実は概念操作という論理操作の結果ではないかということも感じている。そういう意味では0(ゼロ)もそうかもしれない。分数を有理数という自然数の対として捉える考え方をすれば、これは2つの自然数の組が分数だということになり、概念の組み合わせで新たな概念を作り出したことになり、実在するものを直接表現したとは言えなくなる。だが、分数に関しては、初期のエジプトでの発生の契機などを見ると、必ずしも概念操作の結果だけとは言えず、何らかの実在から求められているようにも見える。これは数学史を調べてもっとよく考えてみたいと思う。0に関しては、その量としての把握が、インド以外ではほとんど見られなかったということから、何らかの実在から導かれる概念では無いように感じる。「無い」という論理語による論理操作の結果得られたものと考えられるだろう。また、無理数に関してはさらに論理操作の結果であるという匂いを強く感じる。無理数は「有理数でない」という属性を持たせたものとして定義される。有理数が論理操作の結果であり、さらにそれを否定するという論理操作によって無理数が得られている。無理数の場合は、それが循環しない無限小数で表されるという性質についても、実在を捉えられないのではないかということを予想させる。もし無限に続く小数を把握できたと考えると、無限を数え上げるということが可能であることを主張しなければならなくなるのではないか。そうすると、ゼノンのパラドックスが現実化してしまう。無限を数え上げることが出来るなら、空間や時間を無限に分割することも可能になってしまう。だが、現実にはアキレスは亀に追いついてしまうのだから、ゼノンのパラドックスは現実化しない。このように考えると、実体としての「対象」とのつながりとして存在を考えることが出来るのは自然数だけではないかという気もしてくる。無理数の実在はかなり疑わしい。小数も分数も微妙なところがある。数学は、現実世界と無関係に数学的な世界を設定できるので、その世界ではこれらが存在すると言い切ってもかまわない気がするが、現実世界の存在との結びつきに関しては確実なのは自然数だけではないかという気がする。だからこそ、自然数以外の概念の獲得はそれなりの難しさがあるのだろう。
2007.11.12
コメント(0)
-
原則を貫く政治家としての小沢一郎氏 1
小沢一郎氏の辞任会見から始まった一連の混乱が収まりかけてきた今、改めてこの騒動は何だったのかということを整理してみたいと思う。小沢一郎氏は、僕自身は余り好きなタイプの人間ではなかったが、宮台真司氏が高く評価していることもあり、政治家としては優れている人物だろうとは思っていた。真のマキャベリストというような表現を宮台氏は使っていたが、理想の実現のためには、あえて不人気なことであろうとも実現していくというところが「豪腕」と呼ばれる所以なのだろうと思っていた。小沢一郎氏には、原則を貫くという政治家として最も大事な資質があると僕も感じている。だが、この一連の騒動においては、原則を貫くという面よりも、ある種の利害の計算で「大連立」を画策したというふうに、政治家ではなく「政治屋」として小沢氏を非難するようなニュースにあふれていた。報道に対する批判は、小沢氏自身も語っていたが、神保哲生氏も「小沢辞任会見を見て」というエントリーの中で「どうも報道されている内容とはちょっと趣が違うように私には聞こえました」と書いている。宮台氏も、このことを語ったマル激の中で、NHKの報道などはデタラメですということを語っていた。小沢氏が優れているという高い評価と、マスコミで報道されている小沢氏の姿が、どうしても整合性のとれた形で理解できないのを感じる。すべての間違いが小沢氏ただ一人に集中しているように語られている現状が果たして正しいものなのかというのを考えてみたいと思う。「ビデオニュース・ドットコム」では小沢一郎氏の辞任会見を見ることが出来る。神保氏は、この会見を見てから一連の報道を見直してほしいというようなことを書いていたが、この報道を見る限りでは論理的な齟齬を小沢氏の言葉からは感じない。原則を貫くという姿勢はここでも一貫している。小沢氏の主張の要約は「小沢氏辞任会見詳報(1)けじめをつけるに当たり」という記事に詳しい。それによると次の4つの点がポイントであると思われる。・1、国際平和協力に関する自衛隊の海外派遣は、国連安保理、もしくは国連総会の決議によって設立、あるいは認められた国連の活動に参加することに限る。したがって特定の国の軍事作戦については、わが国は支援活動をしない。2、新テロ特措法案は、できれば通してほしいが、両党が連立し、新しい協力態勢を確立することを最優先と考えているので、連立が成立するならば、あえてこの法案の成立にこだわることはしない。福田総理は、その2点を確約された。 これまでのわが国の無原則な安保政策を根本から転換し、国際平和協力の原則を確立するものであるだけに、私個人は、それだけでも政策協議を開始するに値すると判断した。・民主党は先の参院選で与えていただいた参院第一党の力を活用して、マニフェストで約束した年金改革、子育て支援、農業再生をはじめ、国民の生活が第一の政策を次々に法案化して、参院に提出しているが、衆院では依然、自民党が圧倒的多数を占めている現状では、これらの法案をいま成立させることはできない。逆にここで政策協議を行えば、その中で国民との約束を実行することが可能になると思う。・もちろん民主党にとって、次の衆院総選挙に勝利し、政権交代を実現して国民の生活が第一の政治を実行することが最終目標だ。私もそのために民主党代表として全力を挙げてきた。しかしながら民主党はいまださまざまな面で力量が不足しており、国民の皆様からも、自民党はダメだが、民主党も本当に政権担当能力があるのかという疑問が提起され続け、次期総選挙での勝利は大変厳しい情勢にあると考えている。 その国民みなさんの疑念を払拭(ふつしょく)するためにも政策協議を行い、そこでわれわれの生活第一の政策が取り入れられるならば、あえて民主党が政権の一翼を担い、参院選を通じて国民に約束した政策を実行し、同時に政権運営への実績も示すことが、国民の理解を得て民主党政権を実現する近道であると私は判断した。 また政権への参加は、私の悲願である政権交代可能な二大政党制の定着と矛盾するどころか、民主党政権実現を早めることによって、その定着を実現することができると考えている。・以上の考えに基づき、2日夜の民主党役員会において、福田総理の方針を説明し、政策協議を始めるべきではないかと提案をしたが、残念ながら認められなかった。それは私が民主党代表として選任した役員の皆様から不信任を受けたに等しいと考えている。よって多くの民主党議員、党員を主導する民主党代表として、また党首会談で誠実に対応してもらった福田総理に対し、ケジメをつける必要があると判断した。最初の点は、大連立と呼ばれるような政策協議に応じようとした判断の一番の根拠になるものだと思われる。安保政策の原則を国連の決議に置くというのは、小沢氏の長年の主張に重なるものであり、これを守りつづけるというところに、小沢氏の原則的な姿勢を見ることが出来る。また、この原則が実現できるなら、政権交代というもう一つの目標よりこちらのほうが優先されるという判断も、どちらがより原則的かという観点の違いによるものであるから、論理的にはまっとうでありご都合主義とはいえない。宮台氏も、これこそが最も重要な論点になるべきだったのに、マスコミの報道では、衆参両院での多数派の違いから法案が通らない状態を改善するために連立構想を立てたかのように末梢的な部分の報道がされていたと指摘していた。与党と野党のねじれ現象の国会運営を改善する政策の歩みよりは、この原則を確認した後に行われる妥協の産物であって、歩み寄ることを目的に政策協議をするわけではなかったのに、歩み寄るところばかりが強調されてしまったようだ。だから、自民党にノーを突きつけた参院選の民意を裏切ったかのように見えてしまったのではないだろうか。問題は、安全保障政策の原則に賛成できるかどうかということのはずだったのに。小沢氏の基本的な考えは、宮台氏が語るように、今までの無原則なアメリカ追従のやり方ではなく、国連決議というものを根拠に、アメリカの要求をただ飲むだけの安保政策からの転換を図るということが目的にあるものだと思う。国連決議さえあれば、どんどん自衛隊を海外派遣してもいいのだというような、戦争をしたいという意図のものではないと思う。むしろ、アメリカに要求されるままに自衛隊を派遣するという主体性のなさにピリオドを打つために原則を確立しようということだろうと思う。そうであれば、基本原則は考えるに値すると思う。また、この基本原則を打ち立てるなら、国連決議に従って国際貢献をするための軍隊の保持とその活動を憲法に明記する必要があるだろう。だからこそ、そのための改憲という問題も出てくるのだと思う。この改憲は、戦争が出来る国にするための改憲ではなく、無原則に戦争に巻き込まれることのないように、主体性を獲得するための改憲ということなら、これも議論に値するのではないかと思う。マスコミの報道では、小沢氏が民主党を「力量不足」だといったことが、まるで民主党を侮辱したかのように受け取られているが、これも曲解というものだろう。「力量不足」だと語っているのは、小沢氏ではなく、むしろマスコミのほうであり世論のほうである。小沢氏は、それはまだ政権を担当したことがないことから来るイメージによるものだと判断している。だからこそ政策実現のために政策協議を利用するということもありうると判断したのだろう。これは論理的には、そのように考えることにも一理ある。また、最後に語っているケジメの問題も、論理的には整合性のある判断だと思う。自分の主張が通らなかったから、わがままから仕事を放り出したというのではない。なぜかマスコミの報道のイメージでは、小沢氏に対してそのようなイメージを貼り付けたいような報道が、特にテレビなどで目立つようだが、自分の提案がほとんどの役員に否決されたということは、その役員を自分が任命したということで言えば「不信任を受けたに等しい」という判断をするのは正しいのではないかと思う。また、小沢氏は会見の中で、民主党のイメージを著しく落としたことについて、このまま代表を続けることでさらにそれが増幅することを心配していた。それは、ある意味では宮台氏が語るように、デタラメな報道をしているマスコミに責任の一端があることなのだが、小沢氏個人の力ではその流れを押し止めることが出来ないとすれば、辞任をすることで流れを止めようと考えるのは一つの考えだろうと思う。小沢氏が連立の提案を党に持ち帰って議論したことについて、世間ではなぜ持ち返ったのかと言っているようだが、それは民主的な手続きを踏んでいると神保氏は指摘していた。田中康夫氏も日本新党のWebラジオで同じようなことを語っていた。受けるにしろ受けないにしろ、独断的な判断を避けたということだ。この一連の騒動を改めてよく見てみると、小沢一郎という政治家は、非常に民主的で誠実な人ではないかと僕は思うようになった。今までのイメージでは、陰で総理を操るような黒幕的な人間という感じがして、権力者の中でも「悪」のイメージが強い人間のように見えたが、実は岡田斗司夫さんが言うような独裁者タイプの権力者なのかもしれない。独裁者タイプは、非常に有能で責任感の強いまじめタイプだと岡田さんは指摘していた。小沢さんの記者会見の言葉からは、有能・責任感・まじめという3つの言葉を強く感じるところがある。小沢さんの安保政策は、戦争をする国にしようという方向だと危惧する人が多いかもしれない。積極的に国際貢献をして行こうという方向が、どんどん戦争をしていくようなイメージを生み出しかねない。しかし、記者会見での言葉を見る限りでは、平和のために必要最低限の武力活動がなくてはならない、というような発想のように感じた。もしその最低限の武力活動さえも否定してしまえば、囚人のジレンマのようにもっと悲惨な結果が待っているという考えではないかと感じた。戦争をしたいというのではなく、戦争を避けるためにこそ武力が必要だという発想のように見える。ただ、この発想はすぐに賛成できない人が多いだろうとも思う。異論が噴出する問題だろう。だがそれだけに、この問題を中心に据えてこそ、本当の意味での日本の未来の方向の選択が決まるといえるかもしれない。今のように烏合の衆のような2大政党ではなく、基本的な考え方の違いから主張が異なるという2大政党制こそが小沢氏の目指すものではないかとも思える。小沢氏のマスコミ批判には、政府与党の側の情報を一方的に垂れ流すマスコミに対してのものがあった。政府与党が何を言っているかということを書くことも必要だろうが、それならば、異なる側の小沢氏が何を言っているかもあわせて書くべきだという批判だ。読売の記事は、政府与党の側の話だけで、小沢氏とその周辺に対してはまったく取材がなかったそうだ。これは、ジャーナリズムとしては片手落ちということになるだろう。一方の側の情報だけを垂れ流す報道は、かつての大本営発表と同じで、かつての間違った歴史を繰り返すのではないかという主張も会見では語られていた。敗戦の歴史を間違ったものと認識しているところを見ても、小沢氏は、単なる感情に流される保守主義者ではなく、何が守られるべきかということを冷徹に判断できる保守主義者ではないかとも感じる。コメント欄に続く
2007.11.11
コメント(7)
-
囚人のジレンマ--信頼への裏切りがもっとも利益になるという皮肉な判断
ゲーム理論で有名なものの一つに「囚人のジレンマ」と呼ばれるものがある。これは詳しくは「囚人のジレンマ 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』」で紹介されているが、簡単に要約すると次のようになるだろうか。共犯だと思われる二人の被疑者AとBの取調べにおいて、二人において次のような条件が提示されたとする。・A,B二人とも黙秘し、自白しなければ少ない物証によって二人は懲役2年の刑になる。・どちらか一人が自白し、もう一人が黙秘した場合は、自白したほうは情状酌量されて反省の意を示したと受け取られ懲役1年に減刑される。しかしもう一方は、反省の意を示していないと判断され、懲役15年の厳罰に処される。・A,Bどちらも自白したなら反省の意を示したという情状を考慮して、その罪に応じた処罰として懲役10年が言い渡される。このとき、二人の囚人AとBはどのような戦略を立てることが利益を最も大きくするか(あるいは損害を最も少なくするか)ということを考えるのがゲーム理論の問題となる。ゲーム理論のもたらす結論は、相手を裏切って自白することが最も利益となる(最も損害を少なくする)というものだ。論理の流れとしては次のとおりだ。まずは、相手の行為を「自白する」か「自白しない」かのどちらかだというふうに場合分けする。これは、形式論理における「排中律」を認めるなら、これですべての場合を尽くしていることになる。さらに、それぞれの場合において自分が「自白する」か「自白しない」か、どの行為を選ぶほうが利益になるかを考える。それは次のようになるだろう。・相手が自白した場合 自分が自白すれば、懲役10年の刑になる。 自分が自白しなければ(黙秘すれば)懲役15年の刑になる。 自白したほうが利益が大きい(損害が小さい)。・相手が自白しない(黙秘した)場合 自分が自白すれば、懲役1年の刑になる。 自分が自白しなければ(黙秘すれば)懲役2年の刑になる。 自白したほうが利益が大きい(損害が小さい)。いずれの場合においても、自白するという行為のほうが利益が大きくなる。したがってゲーム理論においては「自白する」という戦略が理論的には選ばれるということになる。だがこの結果は皮肉なものとして現実化する。上の思考は、一方だけに当てはまるのではなく、両者に同じように当てはまる。だから、A、B二人とも、お互いを裏切ることが最適の戦略になってしまう。そうすると、お互いを信頼していれば懲役2年で終わったものが、実際には懲役10年の刑を食らうことになって、理論的には最適な選択とはいえ何か損をしているような気分になってしまう。このあたりが「ジレンマ」と呼ばれることにつながってくる。この囚人のジレンマは、設定としては無理やりにこのような場面を作り出して考察しているので、その無理が何かジレンマを生じさせてしまっているようにも感じる。もし、二人の囚人が本当に罪を犯しているのなら、自白することによって反省の意を示すことで懲役10年に落ち着くのは合理的であるようにも感じる。しかし、もし冤罪であるなら、そもそも懲役刑になること自体が間違っているともいえる。だから、問題は冤罪であるか、本当に罪を犯しているのかを正しく判断することにあるようにも見えるのだが、これは現実にはたいへん難しい問題になる。完全な物証があれば自白などは必要ないわけだが、それがない時は自白がかなり大きな決め手になる。もし一人が冤罪で、もう一人が真犯人であった場合は、これは最も悲惨な結果をもたらしてしまう。冤罪の方はあくまでも犯行を否認して自白しない態度を貫くであろうが、真犯人のほうは、そのままでも懲役10年の刑には値してしまうのであるから、自白してそれが懲役1年になればたいへんな儲けものという感じになる。したがって、真犯人のほうが懲役1年になり、冤罪のほうが懲役15年を食らうという結果が起こってしまうだろう。ゲーム理論の設定では、この二人は共犯ということになっているので、冤罪と真犯人というケースは除外されていると思うが、現実にはそういうケースが起こる可能性はある。また共犯の場合も、この二人がお互いに信頼を保ちつづけられるかという問題が、現実の問題として生じてくる。それは、さまざまの実験によればかなり難しいことが確かめられているらしい。人間は、信頼を持ちつづけるよりも、疑心暗鬼になって相手を疑うことが多いらしい。そうすると囚人のジレンマの状態にいる人間は、自らの利益のために相手を裏切るという行為に傾くことがかなりあるようだ。囚人のジレンマは、ゲーム理論の対象としても面白いと思うが、それ以上に、人間における信頼関係のもろさというものを教えてくれるのではないかと思う。囚人という設定ではないが、ある利害関係を持った相手がいた場合に、お互いを信頼し合えば現実的には利益となるのに、自分が信頼しているときに相手に裏切られるときの損害の大きさに疑心暗鬼になり、お互いを裏切って、信頼していた状態よりも利益を損なうというケースが出てくる。この皮肉なジレンマが人間社会においてはたくさん見られるようだ。上記のウィキペディアでは「「囚人」という言葉にこだわらなければ、現実での例はいくらでもある。「価格破壊競争」など、例えばA社とB社があり、A社が販売価格を下げれば、B社のシェアを奪う事が出来るが、B社も販売価格を下げた場合、A社のシェアは変わらず、利益のみが下がる事になる。恐怖の均衡にも似たところがある。」という例が語られている。米ソの冷戦時代などにも、核兵器の使用という点で、先に使ったほうがより損害が少なく出来るという理論的な結果が導かれたそうだ。バートランド・ラッセルのような平和主義者でさえも、理論的にはそう主張したということをどこかで読んだ記憶がある。核兵器をお互いに使うことがなければ、つまりお互いが使わないという信頼を持っていれば、核兵器による悲惨な殺戮は避けられる。しかし、この信頼をもし相手が裏切るなら、先に核兵器を使って相手を屈服させてしまったほうが利益が大きくなる。相手に対する信頼が崩れ、疑心暗鬼を抱けばそう結論せざるを得なくなる。しかし、その思考は相手も同じなので、お互いに核兵器を使用してそれに見合うだけの悲惨な殺戮が行われるということになってしまう。それは、相手に一方的にやられる場合に比べれば損害の程度が少しは軽くなるかもしれないが、大きな損害を受けることは確かだ。信頼していれば受けなくてすむ被害が、信頼がなくなったときには、最適の戦略を選んだ場合でさえも大きな損害を受ける。幸いなことに、冷戦時代には米ソどちらも先に核兵器を使って相手に先んじようとすることがなかった。核兵器の場合は、下手をすれば自分も全滅してしまうかもしれないという大きなリスクがあるので、その決断を下せなかったということもあるのだろう。理論どおりにいかなかったのを幸いだと思うだけだ。だが、これはお互いの信頼の上に安定して平和が保たれていたようにも見えない。果たして、平和というのは信頼関係の基礎のうえに築くことが出来るものだろうか。囚人のジレンマに寄れば、それはたいへん難しいのだといっているように聞こえる。日本国憲法では、その前文に「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」という文章がある。日本国憲法の平和の理念は、「平和を愛する諸国民の公正と信義」への信頼を基礎に置いている。囚人のジレンマ的な発想で言えば、この信頼が崩れない限りにおいて、現実的には最も利益となる方向を選択していることになる。だが、もし信頼が裏切られれば、日本は最も損害が大きくなるというリスクを背負っている。現実には、日本は自衛隊という軍隊を持ち、日米安保条約によって世界一強大な軍隊の庇護の元にいるという、いわば日本国憲法でうたわれているような「信頼」を裏切る存在となっている。日本国憲法は、その前文において空文化しているわけだ。だが、この空文化はゲーム理論的にいえば正しい選択だといえるものになるだろう。国家における軍隊の問題も、囚人のジレンマ的な側面を持っているように思われる。もし軍隊に使うだけの金を他のところにつぎ込めるなら、国家としての経済的な利益は計り知れないものになるだろう。しかし、軍隊を持たないということは、外国が侵略してこないということを信頼することでもある。この信頼は、たいていの場合は裏切られる。地下資源を豊かに持っている国は、侵略される危険をかなり考慮しなければならないだろう。Kさんが「存在の問題の難しさ--その弁証法性」というエントリーのコメント欄でコスタリカについて語っているが、コスタリカはかなり特殊なケースとして考える必要があるのではないかと感じる。コスタリカにおける軍隊の放棄は、自らの国が、侵略されるあるいは侵略するという行為からは遠くはなれているという特殊な状況における結果だと考えたほうがいいのではないかと感じる。それは一般化できるケースではなく、特殊な例外的な存在だというふうに僕には感じる。コスタリカは、自らが原因で国際紛争を起こすことは考えにくい。他国の状況に巻き込まれるという危険性が最も高い。だから、他国の紛争の調停への努力というのは、コスタリカという国の存続をかけた仕事になるようだ。その調停のためには、強大な軍隊を持つ必要はないし、むしろ軍隊を持たない、戦争行為の心配のない国だということをアピールしたほうが有利だろう。コスタリカという国の特殊性が、軍隊を持たないという選択を合理的なものとしているように思われる。果たして、その他の国でも、平和を実現するために軍隊を持たないほうが利益となるのだということを一般化できるだろうか。これは理論的には僕には確信が持てない。囚人のジレンマが信頼を揺さぶるのではないかと思われるからだ。核兵器を使用しないという点では、我々は結果的にその囚人のジレンマを解決してきたように見える。米ソは核兵器を使わなかった。この成功を軍隊一般にも広げることが出来るだろうか。もし出来るなら、未来において軍隊のない平和な世界を想像(創造も)することが出来るだろう。しかし囚人のジレンマが残りつづけるなら、未来に渡っても国家が存続する限り軍隊も存続するということになるのではないかと思う。国家にとって軍隊は必然的な存在になるかどうか、萱野稔人さんの国家論などを参考にして今一度考えてみたいと思う。
2007.11.09
コメント(0)
-
自己実現幻想の弊害--いつまでも子どもから脱しきれない若者たち
内田樹さんが「人生はミスマッチ」というエントリーでたいへん面白い文章を書いている。このエントリーの冒頭で内田さんは次のように書いている。「リクルートの出している「RT」という冊子の取材が来て、「高校の先生に言いたいこと」を訊かれる。中高の現場の先生には基本的に「がんばってね」というエールを送ることにしている。現場の教師の士気を低下させることで、子どもたちの学力や道徳心が向上するということはありえないからである。現場の教師のみなさんには、できるかぎり機嫌良くお仕事をしていただきたいと私は願っている。人間は機嫌良く仕事をしているひとのそばにいると、自分も機嫌良く何かをしたくなるからである。だから、学校の先生がすることは畢竟すればひとつだけでよい。それは「心身がアクティヴであることは、気持ちがいい」ということを自分自身を素材にして子どもたちに伝えることである。」学校という現場にいる人間として、たいへんありがたい応援の言葉をもらったようで嬉しく感じるし、その基本的な発想に共感するものだ。教師という職業の人間に出来ることは高が知れている。その中で何を一番大事にしなければならないかという発想で、内田さんが語る「「心身がアクティヴであることは、気持ちがいい」ということを自分自身を素材にして子どもたちに伝えることである。」ということは、たいへん共感できることだ。この教育観も共感できる面白いことだったのだが、それ以上に印象に残ったのが若者の自己実現幻想の弊害を指摘した次の部分だ。「大学三年生相手の就職セミナーでリクルートの営業はまず最初に「みなさんは自分の適性に合った仕事を探し当てることがもっとも重要です」と獅子吼する。その瞬間に若者たちは「この広い世界のどこかに自分の適性にぴったり合ったたった一つの仕事が存在する」という信憑を刷り込まれる。もちろん、そのような仕事は存在しない。だから、「自分の適性にぴったり合ったたった一つの仕事」を探して若者たちは終わりのない長い放浪の旅に出ることになる。」この主張は、宮台真司氏などがマル激でよく語ることと重なるところがまた面白いと思った。内田さんは、以前の文章などで、宮台氏がどうやら嫌いらしいということが書かれていたのだが、嫌いという感情を抱いていても、その語る結論が重なってしまうというのは、それが合理的な思考の結果であることを物語っているような感じがする。どこかに自分にぴったり合った職業があるはずだという考えは、仕事によって自己実現を図るということに通じる。そして、そのような仕事を求めて自分探しの旅に出るような放浪を求めるようになる。しかし、それはどこかに探し求めるものが存在するのではないという指摘を、宮台氏も内田さんもしているように見える。それはチルチルとミチルが求めた青い鳥のようなものだろう。それは、どこかに始めから存在しているものではなく、生きていく中で創りあげ、発見していくものなのだろうと思う。だからこそ、青い鳥は、実はすぐ近くにあったのだということになるのだと思う。自己実現幻想も、それが幻想である所以は、自分にぴったり合った職業などというものが、どこかに始めからあるという思い込みだ。そんなものはないのである。もしぴったり合ったと思えるときが来るとしたら、それはまず仕事を始めてから後に分かるのであって、仕事をする前に分かることではない。さらに言えることは、人間は活動をすることで変化し成長するということだ。はじめは何気なく始めた仕事が、その仕事をすることで成長をし、いつしか天職のようにその仕事で才能を発揮するということがある。むしろ、最初から使命感を抱いてその職業に飛び込んだ人間は、こんなはずではないという幻滅のほうが強くて、最初の志がだんだんしぼんでいってしまうことのほうが多いのではないだろうか。本多勝一さんは、地元に帰って家業を継ぐのがいやで、たまたま就職してしまった新聞記者という仕事が天職のようになったとどこかで語っていた。それもきっかけは、察回り(警察情報の聞き取り)という定型的な仕事のつまらなさと矛盾に気が付いたことがその転換点だったという。そして、元探検部という特性を生かした秘境のルポルタージュがヒットしたので、本来やりたかったことに手が出せるようになったという。仕事をする中で、その特性と才能が花開いて、自身の成長ということが結果的に仕事での自己実現をもたらしたという感じがする。本多さんのような有名人と自分自身を比べるつもりはないのだが、僕自身も教員になったきっかけは、卒業後も学問を続けるだけの時間的余裕がほしかったというのが一番の理由だった。学問そのものを職業にすることが出来なかったので、せめて生活の糧を稼ぐ仕事の合間に学問をするだけの余裕がほしかったというのが、教員という職業を選んだ理由だった。いわば、「教員にでもなるか」という感じの「でも教師」だった。子どもが好きだとか、教育に使命感を感じて教師になったということではなかった。しかしそれでも憧れの教師像というのは持っていた。それは児童文学者の灰谷健次郎さんがかつてそうだっただろうと思えるような教師であり、灰谷さんと対談をして、「人間について」という授業実践をしていた林竹二さんが、いわば僕の理想の教師像だった。しかし学校現場で実際に仕事をしてみると、この理想はすぐに崩れていった。とてもじゃないが、自分にはこの二人の真似すらできないという思いが強かった。自分には教師の資質が欠けているというか、教師は自分に適した仕事ではないという思いをすぐに感じたものだった。自分の進むべき道は二つしかないように感じていた。一つは、適正を欠く教員という仕事をやめて、もっと自分に適した仕事を求める道だ。そしてもう一つは、教員という仕事を、生活の糧を得るための仕事と割り切って、給料分の仕事をしてすごせればいいと思うことだ。これは、適性がないと思える教師の仕事に慣れることで対処しようというものだ。不思議なもので、適性がないと感じたところですぐに辞められないと、ちょっと長く仕事を続けると、この仕事に慣れが出てくる。1年を過ぎたところで迷いながらも続けていた仕事が、3年も勤めてしまうと、それなりに大過なく過ごせるようになり、これならこの先何年でも慣れと経験だけでやっていけそうな感じもしてしまった。転機が訪れたのは、4年目に養護学校に転勤したことだった。そこでの仕事には迷いもなく、ある意味ではこんなに楽しんで仕事をしてもいいのだろうかと思うくらい、仕事に没頭することが出来た。ここでようやく適正を感じる仕事にめぐり合ったという感じだろうか。養護学校での仕事は、当時は余り希望する人はなく、会う人ごとに「たいへんですね」と声をかけられたものだが、僕にはそういう思いはまったくなかった。むしろ、楽しさのほうが大きく、楽しいがゆえにここでの仕事は楽だという思いが強かった。そのように感じることが出来たとき、その仕事に適正を見出すことが出来るのかもしれない。ただ、楽しい仕事は四六時中あるのではなく、つまらない仕事が大部分ではあるけれど、その中にいくつかの楽しい時があることが、その仕事への意欲を継続させてくれているという感じがする。仕事での自己実現というのは、そういうものではないかと思う。どんな仕事をするかというのは、かなり偶然の結果であることが多い。その偶然に取り組んだ仕事で自己実現が出来るかどうかは、その仕事のどこかに適正を感じる部分を見つけることで成し遂げられるのではないかと思う。決して、どこかに適正がぴったりする仕事があって、それが待ってくれているのではなく、偶然見つけてしまうものなのだろう。その偶然見つけるきっかけとしては、内田さんが語る「人生はミスマッチである。私たちは学校の選択を間違え、就職先を間違え、配偶者の選択を間違う。それでもけっこう幸福に生きることができる。チェーホフの『可愛い女』はどんな配偶者とでもそこそこ幸福になることのできる「可愛い女」のキュートな生涯を描いている。チェーホフが看破したとおり、私たちには誰でもどのような環境でもけっこう楽しく暮らせる能力が備わっているのである。それでいいじゃないか。」という文章の中の「可愛い女」の感性が役に立つのではないかと思う。どんな相手ともそこそこうまく付き合えるというのは、どんな相手とも相性のいい部分を見つける技術と能力を持っているということではないかと思う。どこかに自分にぴったりあう唯一の相手がいるのではない。どんな相手とも、相性の合う部分は必ずあるのであり、それを見つけることが出来るかどうかで幸福になれるかどうかが決まる。このような考え方は、板倉聖宣さんが語る「どっちに転んでもシメタ」という発想にも似ている。現在の状況というのは、視点を変えることによって最悪の状態だという思いを転換できるということだ。それは、無理やりにそう思い込んで自分を慰めるのではなく、客観的にそういう視点が必ず見つかるというのが、いわば弁証法的な現実の法則性だといってもいいものになっている。「ものは考えよう」ということわざに通じるものだろうか。ただ、この弁証法性は、弁証法性であるから常に正しいとは限らない。いつも「ものは考えよう」と思っていると、もしかすると不当な扱いを受けているのに、それに気づかないで我慢しているだけということもあるかもしれない。だが、それの裏返しとしての、民衆は常にだまされて搾取されていると考えるのも、極端な非弁証法的な発想になるだろう。問題は「程度の問題」なのではないかと思う。人間はたいていどんな相手ともうまくやっていけるだけの社会性を持っている。しかし、特別の相手とはどうやってもうまくいかないということもある。そこに「程度の問題」が存在するだろう。仕事に関しても同じではないかと思う。どんな仕事でもそれなりにやることは出来る。生活の糧を得るためだと割り切れば、少しでも効率のいい給料の高い仕事を探すというのが第一に大切なことになる。特別に自分に相性の合わない仕事だけができないという判断になるだろう。だが、自己実現が出来なければ自分とは相性が合わないのだという基準を持っていると、大部分の仕事は自分と相性が合わなくなってくる。自己実現幻想を持つことは、仕事をするという社会性を育てる上で大きな弊害となって今現れているのではないかと感じる。自己実現は、目的として存在するのではなく、結果としてそのようになったように解釈できるという現象なのではないかと思う。そう思えたとき、人は少し大人になったと感じるのではないだろうか。苦い現実を謙虚に受け止められるようになるのだと思う。
2007.11.08
コメント(0)
-
支配という現象の論理的考察
今週配信されているマル激のゲストは岡田斗司夫さんで、ダイエット問題から入ったその話はたいへん面白いものだった。岡田さんは、100キロ以上あった体重を50キロも減らしたダイエットで有名になったが、その方法論がたいへん論理的で説得力のあるものだった。岡田さんという人は、その話の展開が非常に論理的な説得力を持った展開をする人だと感じた。さっそく岡田さんの本を求めて読んでみようと思って本屋へ行ったのだが、ダイエット関係の本は売り切れていて手に入らなかった。代わりに『「世界征服」は可能か?』(ちくまプリマー新書)という本を手に入れた。これがたいへん面白かった。論理的な書き方をしているのでたいへん分かりやすく、そこにちりばめられたユーモアたっぷりな表現が、飽きさせずに最後まで読ませるという効果を生んでいた。面白おかしく軽く読ませるこの本だったが、そこに書かれている内容は決して軽いものではなく、「支配」という現象の本質をついているものではないかと感じた。「世界征服」などというものは、空想的な物語の中にしか登場しないから、笑い飛ばしてしまえるようなものだが、現実に「侵略」と呼ばれているような「悪」は、この「世界征服」という喜劇に近いものがあるように感じる。「世界征服」なら非現実的な、ある種のユーモアを感じて笑い飛ばせるものが、「侵略」という現実は悲惨でまじめに向かい合わなければならないものになる。しかしその本質はかなりよく似ている。「侵略」という現実を笑い飛ばそうという不謹慎な意図はないが、目じりを吊り上げてそれを糾弾するという反対の極の対応も何か違和感を感じる。「侵略」のように見える現実も、「世界征服」としてフィクションの中に描かれる荒唐無稽さの勘違いが含まれているのではないかという感じもする。結果的に「侵略」になってしまった行為の責任を問われたとき、その行為者はほとんど「侵略の意図はなかった」というような言い訳をするのではないかと思う。これは結果としての「侵略」を認めないごまかしのように受け取る場合が多いが、実は本気で「その意図はなかった」と当事者は思っているのではないかということが、岡田さんの本を読んでいると感じられるようになった。世界征服を企てるような「侵略者」は、極悪非道な人間ではなく、むしろまじめで正義感が強いタイプの人間が多いのではないかとも感じる。いじめの問題において、正義感がいじめを生むという指摘をしていたのは、仮説実験授業の提唱者の板倉聖宣さんだった。「争いの元に正義あり」というような格言のようなものもよく語っていた。この正義は、被害者からは勝手な言い分のように聞こえるが、論理的にはそのような正義があるからこそ悲惨な結末に向かって事態が展開してしまうのではないかと思う。この正義は、それを単に否定するだけでは、現実には消えていかないのではないかと思う。その実体を正確に捉えて、その正義の間違いがどのような方向へ進むかという法則性を認識しなければならないのではないかと思う。それを岡田さんの本は、ユーモアたっぷりに面白く教えてくれるのではないかと思う。この本では支配者を4つのタイプに分けて考えているのだが、それぞれに支配者が、単なる悪人ではなくそれなりに理解と共感が可能になるようなタイプとして考察されている。「征服」や「支配」という現象は、結果的には虐殺などの悲惨な出来事を生む場合があるとはいえ、その意図に関しては決して「悪」だけではないという理解が出来る。この理解は、「征服」や「支配」を容認するということではなく、意図が悪くなければその事を押し進めていいのだという勘違いをしないために、「征服」や「支配」の意図が本来は悪いものではなかったというのを理解することが大切ではないかと思う。悪意を持たなくても悲惨な結果をもたらしてしまうというのを、社会の法則性として認識することが大事だと思う。アメリカという国を考えるとき、岡田さんが語るタイプの一つにそれがよく当てはまるのを感じる。アメリカの行為は、ベトナム戦争においても、イラク戦争においても結果的には「侵略行為」になっている。しかしアメリカ自身(アメリカ人自身というべきだろうか)は、自らの行為を決して「侵略」だなどと思ってはいない。それはむしろ正義の実現だと思っているだろう。アメリカの正義感の強さが結果としての悲惨な「侵略」を生んでいる。この「侵略」は、結果を指摘して非難するだけでは、当のアメリカ自身がそれを理解することはないのではないか。日本における第二次世界大戦の結果としての「侵略行為」も、その当事者である旧日本軍の関係者にしてみれば、自らの努力と正義を一方的に否定されているように感じるのではないかと思う。日本では、「勝てば官軍」ということばがあり、「負ければ賊軍」という言葉もある。結局戦争の結果で非難されるのは負けたからではないかという思いが強くなるだろう。負けたのがいけなかったので、勝ちさえすれば自分たちの正義は証明されるという受け取り方にもなるのではないかと思う。右翼といわれた故黛敏郎さんなどは、そのような考えを公言していた。僕は、勝ち負けよりも、正義の思想を一方的に押し付けようとした「支配」に問題があるのだと思う。その勘違いを深く認識しなければ戦争責任の問題も多くの人が納得するようなものが提出できないのではないかと思う。正義の思想を押し付けて実現しようとする「支配」や「征服」は、その実現の達成のためには実に効率の悪い方法であることが岡田さんによって指摘されている。これはたいへん説得力のある指摘だ。実に論理的にすっきりしている。このような認識を多くの人が持てば、戦争責任に関する不毛な議論のいくつかは解消されるのではないかとも期待できる。結果だけをぶつけ合って、その結果の解釈の違いを議論するような不毛な議論を、そこに至る過程の正しい理解の上で、その失敗の過程を繰り返さないような教訓として歴史を学ぶという議論にしていけるのではないかと思う。さて岡田さんは、支配者のタイプを次の4つに分けて考えている。 A:魔王タイプ …「正しい」価値観ですべてを支配したい B:独裁者タイプ…責任感が強く、働き者 C:王様タイプ …自分が大好きで、贅沢が好き D:黒幕タイプ …人目に触れず、悪の魅力に溺れたいこれはとても面白い発想だ。このうち、Aの魔王タイプとCの王様タイプの支配者は、現実にはそのモデルを探すのが難しい。フィクションの中のヒーローと戦う「悪」にこの種のタイプが描かれることがほとんどではないかと思われる。魔王タイプの支配者は、自らの価値観から来る正義の観念が強すぎて、ほとんどすべての人間が許せないものになってしまう。このタイプの支配者は、従って人類絶滅を意図するような「悪」として描かれることが多い。しかし、支配者が、支配しようとする人類を絶滅させてしまうということは、支配という言葉の意味に反した行為になってしまう。だから、現実にはこのようなタイプは成立しにくいだろう。だがこの魔王タイプの人間がもしいたならば、現実にはもっとも危険な存在になる。魔王タイプは、自分以外は信用できないと考える孤立した存在になる。自分以外の人間は、正しい価値観を持っているとは思えないのだ。そういう相手は、生きている価値がないという判断をする可能性があり、相手を殺すことをためらわない心性を持つ可能性がある。「正義」というものが、誰にも当てはまる普遍性を持っているものではないので、このように強すぎる正義感を持った人間は、社会にとって非常に危険な存在だといえるだろう。救いは、この種のタイプは孤立しているので、強大な権力を持って社会を脅かすという可能性が低い点だろうか。王様タイプも現実には可能性の低い支配者タイプだ。これは、王様タイプのように自己中心的でわがままな人間は、それを支える人間に恵まれるということが考えられず、能力のある人間に利用されるか、利用価値がなくなれば、その支配者のほうが抹殺されてしまうということになるからだ。岡田さんによれば、このタイプの支配者は現実には「北朝鮮」の金正日くらいしか見当たらないそうだ。現実に存在する支配者としては、Bの独裁者かDの黒幕かということになる。これは実際のモデルを発見するのも容易ではないかと思う。ヒトラーは典型的な独裁者タイプの支配者だが、岡田さんによれば、このタイプの支配者は、有能すぎて過労死にいたるという。とにかく、すべての判断を自分がした方が正しい判断になってしまうので、四六時中支配することに身を捧げていなければならなくなる。また、支配されるほうの人間たちも、常に有能な独裁者に指示を仰ぐようになる。この独裁者タイプは、それに心酔するような支持者も生むので、「支配」や「征服」という言葉の正しい定義にもかなうのではないかと思う。しかしそこには確かに「支配」という現象が見られるが、独裁者の立場から見てみると、それは「支配」と呼ぶよりも、未熟なものたちを「指導」しているという感じに見えてくる。恣意的に自分の意図が実現されるのではなく、有能であるがゆえに、これが正しいと見通したことが実現されるだけのことになりそうだ。「支配」という現象の弁証法性がここには見られるのではないかと思う。この独裁者タイプは、権力を持つまでの過程では、ほとんど正しい判断をすることが出来て大衆の支持を得て権力を確立する。しかし、常に正しいことを行えるかどうかということが、現実の人間の行動の難しさだ。独裁者が、もし判断を間違えたとしても、それを指摘できるだけの人間は、権力を確立した後にはもはや側近にはそのような人間はいなくなるだろう。たった一つの失敗のきっかけが独裁者の権力を消し去るのに働くだろう。歴史はそのようなことを物語っている感じがする。板倉聖宣さんも、社会主義国家が崩壊したときに、その国の独裁者について、社会主義国家が発足した当時はもっとも有能でいい人だったに違いないということを語っていた。独裁者というのは、そういうタイプの支配者ではないかと僕も思う。しかし、有能であるがゆえにすべてを自分で背負って判断することに疲れ、やがてその判断に間違いがもたらされるだろう事も予想できる。独裁者は、ある一時期にはたいへん効率的な面を見せるが、それが長く続けば効率が悪くなるのではないかと思う。どんなときに独裁を許すかということの考察が大切になってくるだろう。黒幕タイプというのは、いかにも悪いやつの代表みたいなイメージがあるが、これもなかなか難しい問題を含んでいるのではないかと思う。社会というのは建前だけでは回らない部分をどうしても持っているのではないかと感じるところがあるからだ。建前だけでは回らない部分を、陰の機能として引き受ける黒幕という存在があったほうが、社会が安定するということもあるだろうと思うからだ。ただ、陰の存在は、あくまでも陰として引っ込んでいてもらわないとならない。これが表に出てくるようになるとまた問題が生じてくるだろう。この黒幕の存在は、必要悪としてどのような整合性を持たせるかが難しいだろう。明治のころの日本は、自らが植民地化されるのを防ぐために、当時遅れていたアジア諸国を進歩させるために指導するという意識を強く持っていたように感じる。その意識が、明治の日本の急速な発展をもたらしたようにも感じる。だからこそ明治は明るい時代としてイメージされるのではないかとも思う。だが、その明治がやがては「侵略」という結果を生む昭和の時代になってしまう。このボタンの掛け違いはどこから生まれるのだろうか。岡田さんの考察がそれを考えるためのヒントを与えてくれるような感じもする。岡田さんのこの本は、面白おかしい軽い読み物になっているが、そのような深い内容を同時に持っているという稀有な優れた本ではないかと感じた。
2007.11.01
コメント(0)
全9件 (9件中 1-9件目)
1