2013年08月の記事
全8件 (8件中 1-8件目)
1
-

ロンドン(London) 10 (テンプル教会 2 Banker)
カテゴリーを「建築物・教会・墓地・墓石」から「お金」に変更しました。ロンドン、シティにあるテンプル教会は建物もさる事ながら、ロンドンを金融の街にした礎そのものだからです。テンプル騎士団とテンプル教会があったからこそ、金融の街ができあがった理由を紹介。案外今のシティの人達も知らないかもしれません。ロンドン(London) 10 (テンプル教会 2 Banker)シティ・オブ・ロンドンがなぜ金融の街になったのか?それはテンプル教会のロンドン拠点がそこにあったからに他なりません。結論から言えば、シティにあったテンプルそのものが巨大な銀行として存在していたからです。十字軍とテンプル教会偉大なるヘンリー2世とヘンリー2世の失敗シテイの礎を造ったテンプル教会Bankers to Europeちょっとおさらい・・十字軍とテンプル教会キリストの聖地を取り戻す為に教皇の公認の元に誓願(せいがん)を立てて「十字章」をつけた戦士が十字軍(crusade)です。注・・ 「十字章」は1095年11月28日フランスのクレルモンでの教皇演説の時に志願者に配られたワッペンのようなものです。その十字章より十字軍と呼ばれる訳です。1099年、聖地を奪還するもイスラムとの戦いは続く、そんな中に結成された修道誓願を立てたたった9人のグループは巡礼者が安全にエルサレムに辿りつけるようボランティアで巡礼路の警護を始める。その戦士の一団はやがて、かつてソロモン神殿のあった場所に拠を置く事を許された教皇公認の騎士修道会に認定(1129年)。それがテンプル(神殿)騎士修道会(Knights Templar)であり、この教会のルーツです。シティにあるテンプル教会何度も修復され、最初の姿はほとんど無いそうですが存在に意義のある教会です。テンプル騎士はすぐにロンドンにオフィスを作ったようですが、1160年の始めに現在のシテイに移転。ここはイングランドにおけるテンプル騎士団の本部となり、騎士や教会の財産管理をする本部事務所に発展。因みに最初の教会はホルボーン(Holborn)のリンカーン法曹院の東隣(現在のSouthampton Building) にOld Templeがあったと言う。「The New Temple' in London(ロンドンの新しいテンプル)」の創設は1185年。時の総長は10代目ジェラール・ド・リドフォール(Gérard de Ridefort)(1185年~1189年)と推定。欧州にかなりの土地の寄贈を受けていた事が解っているので寄進の受け口としてのオフィスや騎士募集の為の教会が必要だったのは確かですし、拡大する教団にかかわる諸々の事業者の事を考慮するとホルボーン(Holborn)は手狭になったのかもしれません。円形堂内部教会は無料で一般公開されています。円形の堂下には中世の騎士の墓。ダ・ヴィンチ・コード(The Da Vinci Code)ではこの堂内部で銃撃があります。遺物にあたったらどうするのだ? 実はここは先の大戦で空爆(1941年)されドームが崩れ破壊されここにあるのはレプリカのよう。偉大なるヘンリー2世とヘンリー2世の失敗教会移転の頃(1160年~1185年)はヘンリー2世(Henry II)(1133年~1189年)の時代です。ヘンリー2世と言えばコモン・ロー(common law)が確率したばかりのイングランドでさらに司法制度、裁判システムを創設(1154年)。現在に続く英国の司法の諸制度のほとんどは彼の時代に確立されたと言う。しかし、訴訟が国王裁判所に集中した為、王の権限はUPしたものの仕事は増えた。つまり、マグナ・カルタ(Magna Carta)以前のイングランドの王は国王裁判所と政務を取る宮殿との間を往復する忙しい生活だった・・と言うわけです。そんな頃、トマス・ベケット(Thomas Becket)(1118年~1170年)暗殺事件が起きる。ヘンリー2世は腹心の部下であり友、トマス・ベケットをカンタベリー大司教に推薦し、イングランドの総司教座にまで着かせた(1162年)が、教会の立場に立って王とことごとく対立。ヘンリー2世の部下にカンタベリー大聖堂で暗殺された時、トマス・ベケットは司教であった為、王はマズイ立場に・・。ローマ教皇に睨まれ、十字軍遠征を約束させられる。テンプル騎士団に騎士200人分の費用など資金援助し、彼らのバックアップをする関係が生まれた。因みにヘンリー2世は聖地に行けなかったが、腹心の側近、騎士のウィリアム・マーシャルが戦地におもむいているし、リチャードの十字軍、Richard the Lionheart(リチャード獅子心王)はヘンリー2世の3男リチャード(Richard I)の事である。イングランド王家とテンプルの密接な関係はこうしてでできあがった。テンプル・バーの中には、国王が滞在する為の建物や、貯蔵庫、厩舎なども建造され、王はよくそこに滞在していたと言われている。シテイの礎を造ったテンプル教会シティの街はテンプル騎士修道会が解散した後も発展をとげた。もともと戦地に送る鎧甲など軍需品の会社などいろんな業種の会社が集まって来ていた事もあるだろう。法曹界も債権や権利書など銀行に付随するものとして当時からテンプル周辺に集まって来ていた事もある。しかし、金融センターとしてニューヨークのウォール街と共に世界経済を先導してきたシティの基礎はテンプル騎士修道会の莫大な遺産と金融のノウハウだった事は間違いない。騎士修道会と銀行が結びつくとはとうてい考えられないでしょうが、当時最も崇敬されていた彼らの本部には莫大な献金があった。テンプル騎士団はその誕生から100年後にはエルサレムで最大の土地所有者になり、ヨーロッパ各地に広大な土地を所有。テンプルの事務局では、領地を売り払い債権にして遠征に参加した者達の銀行代わりもしたし、領地を寄進した貴族や経済状況が悪くて領地をテンプルに買い取ってもらいたい領主の面倒もみた。つまり資産運用と同時に預貯金業務も行っていたのである。円形ドームの壁は特殊な装飾が・・。奇妙な顔のレリーフが続くグロテスクな顔がたさん。魔除けか?Bankers to Europe(銀行家はヨーロッパへ)どんどんふくれあがる資産。潤沢な資金はエルサレムにいる者だけでなく、周辺の領主やヨーロッパの商人やヨーロッパ各国の王侯貴族にまで貸し付け。表看板は騎士修道会でありながら資産運用のサイドビジネスが成功し、独自の財務システムを発達させ銀行のような金融団体に成長してしまった。ではテンプル(神殿)騎士修道会が解散してその莫大な資産はどうなったのか?基本的にはテンプルの資産は聖ヨハネ騎士団が引き継ぐ事になっていたが、フランスだけは全てフィリップ4世が没収。イングランドではいったん王の管理下に入り、聖ヨハネ騎士団に資産が移るまで25年かかっている。テンプル(神殿)騎士修道会が解散させられた理由はやはりフランス王フィリップ4世(Philipe IV)(1268年~1314年)の資産ねらいだったと言うのが真実のよう。当時フランスの財政は逼迫していたし、かなりのお金をテンプルから借りていた? 借金踏み倒しだったのかも・・。イングランドではこのテンプルの資産が凍結されると王は王族や貴族の預金を抜き取ったと記録されている。それはまさに銀行の破綻前の行動?しかしテンプル(神殿)騎士修道会が解散後も彼らの事務機関は生き残りシティに息づいた。それは突然破綻させられたわけではなく、イングランド王の元に管理されて今まで通り運営されたから? なのかもしれない。それにしても聖ヨハネ騎士団に資産が移るまで25年の利子は誰の手に?※ 騎士修道会については以下に紹介。テンプル(神殿)騎士修道会(Knights Templar)の末路については「騎士修道会 2 (聖ヨハネ騎士修道会)」の中で紹介。リンク 騎士修道会 1 (テンプル(神殿) 騎士修道会)リンク 騎士修道会 2 (聖ヨハネ騎士修道会)リンク 騎士修道会 3 (ロードスの騎士)ロンドンシリーズ Back numberリンク ロンドン(London) 1 (テムズ川)リンク ロンドン(London) 2 (テムズ川に架かる橋 1)リンク ロンドン(London) 3 (テムズ川に架かる橋 2)リンク ロンドン(London) 4 (タワー・ブリッジ 1)リンク ロンドン(London) 5 (タワー・ブリッジ 2リンク ロンドン(London) 6 (バトラーズ・ワーフ)リンク ロンドン(London) 7 (シャッド・テムズのカフェレストラン)リンク ロンドン(London) 8 (シティの紋章)リンク ロンドン(London) 9 (テンプル教会 1)ロンドン(London) 10 (テンプル教会 2 Banker)リンク ロンドン(London) 11 (テンプル教会 3 中世の騎士)リンク ケルト(Celt) のドラゴン リンク シティのパブ The Edgar Wallace リンク ロンドン(London) の地下鉄(Underground)リンク ビクトリア& アルバート博物館 のカフェテリアリンク ユーロスター(Eurostar)リンク 英国のEU離脱の失敗 ・ ウェストミンスター宮殿
2013年08月31日
コメント(0)
-

新 騎士修道会 3 (ロードスの騎士)
ウイーンのマルタ教会の他、ロードスの写真も入れ変え中身も多少追加しました。書き換えたのでお約束。「新 騎士修道会 3 (ロードスの騎士)」にしました。今回はテンプル騎士団の紹介が目的だったので The First Crusade(第一次十字軍)から騎士修道会設立までのいきさつををメインに紹介しました。十字軍についてはその後も何度かの遠征があり、欧州の諸王達も利権をかけた隊を派遣しているので複雑な歴史がたくさん続きます。が、それはまたどこかで関連してきたら取り上げる事にしてとりあえず聖ヨハネ騎士修道会の最後を簡略に紹介して終わります。新 騎士修道会 3 (ロードスの騎士)アトリビュート(attribute)「キリストを現す獅子」流れ流れて・・聖ヨハネ騎士修道会は?ロードス島(Rhodes)ロードスの騎士(Knights of Rhodes)ロードスの騎士からマルタの騎士にウイーンのマルタ教会(Maltese Church)現在の聖ヨハネ騎士修道会正式名称アトリビュート(attribute)「キリストを現す獅子」マルタ教会の天井のクロッシングに付いていたライオンの彫物。これの意味がわかりました。通常ライオンと言えば福音書記者マルコのシンボルでありアトリビュートとなる物と連想してしまうが、ここでは全く別の意味で使われていた。ライオンは中世にはすでに百獣の王と認識されていた事から「全人の王キリスト」にもなぞられていたらしい。また、ライオンは眠っている間もまぶたを閉じ無い動物と考えられていた? 悪魔が「主の羊(人間)」を盗む事が無いよう常にキリストが見守っている。と言う考えからもキリスト自身になぞられる存在らしい。図は、子ライオンと共に描かれている。生まれて間もく目を開かない子ライオンに向い吠えて蘇(よみがえ)らそうとしている光景らしい。その行為もまたキリストが死して神の声に蘇った事が掛けられていると言う。因みに羊は人民一般を現すアイテムです。キリスト教におけるアトリビュート(attribute)とは、その物が何か別の意味を持って表現されている。と解釈される存在です。例えば聖人が何かを持っているとすると、その持ち物で誰かわかるような象徴的なアイテムがアトリビュートと言えます。以前紹介した使徒ペテロのアトリビュートは鍵(かぎ)。それは彼が天国の門の鍵をキリストから預かった人だからです。キリスト教では、いろんなアイテムがアトリビュートとして使われています。解説の本も出ているくらい数が多いし、一つのアイテムで幾つも意味を持つ場合もあるのでややこしいのです。おそらく時代の認識も違ったからかもしれません。さて、今回はロードス島へ渡ってロードスの騎士となった聖ヨハネ騎士団です。エルサレム(Jerusalem) → アッコ(Acre) → キプロス島(Cyprus) → ロードス島(Rhodes) → マルタ島(Malta) 流れ流れて・・聖ヨハネ騎士修道会は?一時は聖地を奪還したものの、やがで再び聖地はイスラムの手に落ちてしまう。エルサレムにいた十字軍の騎士修道士はエルサレムが陥落すると、王国の首都を北のアッコ(Acre)に移動。1291年、そのアッコ(Acre)も陥落。十字軍国家は中東の拠点を失い地中海の島に逃れてイスラム勢力と戦う事になる。テンプル騎士団もヨハネ騎士団もキプロス島(Cyprus)に待避。※ ルアド島に逃げて立てこもったテンプル騎士もいたが1312年テンプル騎士団は解散。キプロス(Cyprus)島はイングランドのリチャード1世がたまたま占領してエルサレム王が買い取った場所であり、一応十字軍国家の属州であった。が、キプロスに逃げた段階でテンプルは主要騎士を失っていたので(事務職ばかり?) ほとんど機能していなかったようだ。一方、聖ヨハネ騎士団はキプロス王国の内紛に巻き込まれ島を出る。そして当時東ローマ帝国(ビザンツ帝国)領であったロードス島(Rhodes)に渡るのである。1309年、聖ヨハネ騎士団はロードス島を占拠してそこに本拠を移すと名前もロードス騎士団(Knights of Rhodes)と呼ばれるようになる。ロードス島(Rhodes)現在はギリシャ共和国の所領となったロードス島は極めてアナトリア半島に近いドデカネス諸島にあり、ロードス・シティは島の北端に位置。ホメロースの詩にも謳われる古代都市だったロードス・シティはBC408年に建設された街。14世紀から15世紀にかけて聖ヨハネ騎士団が街を占領中に城塞を築き街そのものを要塞化した。城壁の上から撮影した市街同じく城壁の上から撮影。大型客船が多数寄港している。聖ヨハネ騎士修道会の遺構はどこよりもこのロードス島に多い。ロードス・シティの旧市街はそれ自体がこの島の一番の観光名所になっている。中世の城塞都市の特質が最も良く残された場所として1988年「Medieval City of Rhodes(ロードスの中世都市)」ユネスコの世界文化遺産に登録。11の門と何層にもかさなる厚い城壁まるで万里の長城のように延々続く城壁は、その上を歩いて回る事ができる。ロードスの騎士(Knights of Rhodes)聖ヨハネ騎士団がロードス島に本拠を移す(1309年)と1522年オスマン軍によりロードスを追われるまでの200年ちょっとの間に彼らはここにテンプル騎士団の財産を使って鉄壁な要塞を築くのである。もともと巡礼者の病院として発展した彼らは病院としての慈善事業を進めながら戦士として戦ってきたが、ここに来て海軍力も保持する事になる。ロドス・シティは高い城壁で囲われた街である。その城壁は区分毎に郷土別に部隊が守備していた。Langue(ラーング・舌)部隊フランス(仏北部)、オーヴェルニュ(仏中部)、プロヴァンス(後の仏)、アラゴン(後のスペイン)、カステーリャ(後のスペイン)、イタリア、ドイツ、イギリスもともと騎士団は寄り集まりの為、言語もバラバラ。その為に戦時は言語により部隊が分けられた。全体にはフランス出身者が多かったので第1公用語はフランス語。第2公用語はイタリア語。騎士団通りには、Langue(ラーング・言語?)部隊毎に館が建ち並んでいる。騎士団長の館1856年に火薬庫の爆発事故で崩壊。1937年にイタリア人によって再建されるも歴史的な正当性を欠いたリノベーションになったと言う。ロードスの騎士からマルタの騎士に1522年、オスマン帝国の第10代皇帝スレイマン1世の軍勢の前にロードスは陥落。ロードスを追われた聖ヨハネ騎士団(ロードス騎士団)はしばらく流浪の民となり、1530年に神聖ローマ皇帝カール5世よりマルタ島の賃貸契約が締結。賃貸料・・・鷹一羽マルタ島に渡ってさらなるイスラムからの攻撃を受ける。キリスト教徒側からするとイスラム勢力と一括りにしているが、実は十字軍が戦ったイスラムは一つではない。ルイ9世を捕虜として捕らえ十字軍を撃退したのはマムルーク朝であったが、騎士団が地中海に出てから戦うイスラムはオスマン帝国になる。オスマン朝(1299年建国?)はアナトリアの小国から発したイスラム王朝であるが、やがてバルカン半島のキリスト教圏や、同じイスラムのマムルークの所領など西アジア、北アフリカのイスラム教国を征服して地中海の過半を覆う大帝国に発展。そんな勢いのある軍隊の前にもはや島一つの騎士団はそれほど相手にされず、むしろ台頭してきたモンゴル帝国の方が驚異だったようだ。1565年の「マルタ包囲戦」はかろうじて撃退するも1798年6月13日敵はオスマン帝国でなく、ナポレオンの艦隊にあっさり降伏してマルタをあけ渡す。マルタ騎士団はここに終わる?しかし聖ヨハネ騎士修道会はなぜか今も生き残っている。居所を失った聖ヨハネ騎士団は、ロシアに助けを求める。1801年にロシア皇帝パーヴェル1世を騎士団総長にして生き延びるのだ。1834年に本拠はローマに移り慈善団体として、現在世界の約94か国と外交関係を持ち、在外公館を設置。国際連合にオブザーバーとして参加する国際組織になっているのである。(⌒▽⌒;) オッドロキー ウイーンのマルタ教会(Maltese Church)正式名は洗礼者ヨハネ教会(Church of Saint John the Baptist)聖ヨハネ騎士団をルーツとする教会です。教会は、カールスプラッツ駅からオペラ座の横を通りシュテファン大聖堂に至るケルントナー通り (Kärntner Straße) 沿いで偶然発見。最初は聖ヨハネ騎士団の後方支援の事務所として1217年頃に建てられた場所らしい。現在の建物は15世紀半ばに建立? さらに1806年に再建された。第一次世界大戦後、財政難で一度手放され、1960年に買い戻されたと言う。下は、エントランス上部とパイプオルガン1730年、祭壇画はJohann Georg Schmidtにより描かれた。現在の聖ヨハネ騎士修道会正式名称エルサレムの聖ヨハネ病院の騎士団 (Hospital of Saint John)はその過程からいろんな呼び方がされてきた。ロードス騎士団(Knights of Rhodes)マルタ騎士団(Knights of Malta)聖騎士団 ジョン(Saint John)現在の正式名称はKNIGHTS HOSPITALLERS OF THE SOVEREIGN ORDER OF SAINT JOHN OF JERUSALEM KNIGHTS OF MALTAロードスおよびマルタにおけるエルサレムの聖ヨハネ病院独立騎士修道会騎士修道会おわり騎士修道会バックナンバーリンク 騎士修道会 1 (テンプル(神殿) 騎士修道会)リンク 騎士修道会 2 (聖ヨハネ騎士修道会)リンク 十字軍(The crusade)と聖墳墓教会(The Church of the Holy Sepulchre) 1リンク 十字軍(The crusade)と聖墳墓教会 2 (キリストの墓)
2013年08月25日
コメント(0)
-

騎士修道会 2 (聖ヨハネ騎士修道会)
写真の入れ替えをしました。聖地から地中海に分散した聖ヨハネ騎士修道会は、ロードス島ではロードスの騎士団(Knights of Rhodes)と呼ばれマルタ島ではマルタ騎士団(Knights of Malta)と呼ばれたのです。他にも聖騎士団 ジョン(Saint John)とも呼ばれています。ウイーンにマルタ教会があり、これを書いた後に訪問して写真を撮っていたので次回のロードス騎士団の方にマルタ教会の写真追加します。リンク 騎士修道会 3 (ロードスの騎士)さて、欧州の歴史は宗教と一体化して成り立っている。キリスト教が理解できなければ真実にはたどりつけない。常々そう思ってきたが、十字軍は宗教だけではなく、正義と騎士道が大きく作用していたのだ・・。修道騎士は修道中に子孫を作る行為は許されない。それ故、数百年続いた紛争中の聖地に新しい生命が生まれるはずはなく、戦士が死ねば、新しい戦士を外部から補充しなければならなかった。常に「前線で戦う騎士募集中」だったと言う事だ。何だか虚しいような事実であるが、これを彼らは正義で貫いていたのだから凄すぎる。騎士修道会 2 (聖ヨハネ騎士修道会)修道院が軍事化した理由テンプル(神殿)騎士修道会(Knights Templar)の末路聖ヨハネ騎士修道会(Knights Hospitallers)成り立ちクレルヴォーの修道士ベルナールの肝入りで人気を博したテンプル騎士団にはお金も人もあふれるほど増えた。1129年のトロワの宗教会議で公認される前後から寄進が始まり、アラゴン、カステーリャ、イングランド、フランスに支部が造られユーグド・バイヤンが亡くなる1136年には西ヨーロッパにかなりの土地を所有する程になっていたと言う。テンプルはもはや貧しき騎士ではなくなり、中世最もお金を持った教団に成長する。この頃、そんなテンプルを真似て仕事幅を拡大。修道会の中に軍事力を持ったのが巡礼病院だった聖ヨハネのホスピタルである。彼らは傭兵を雇い騎士修道会にシフトして行くのである。赤字に白い十字は聖ヨハネ騎士修道会のマークステンドグラスはウイーンのマルタ教会(Maltese Church)のもの。正式名は「洗礼者聖ヨハネ教会」。今回紹介している聖ヨハネ騎士修道会のウイーンにおかれた教会で創建は1217年。ウイーンのマルタ教会は次回に写真追加します。第1回十字軍 アンティオキア攻囲戦 (1097年10月~1098年6月)ウィキメディアコモンズより作品は後年1474年に描かれたもの。アンテオキアの鉄壁の城壁は、かつてユスティニアヌスが築いたもの。一時はイスラムの元にあった街を再び十字軍が取り戻す為の攻防戦である。絵画には聖ヨハネ騎士団の十字の旗が描かれているが、聖ヨハネ騎士団が成立するのは1136年以降のはず。因みにテンプル騎士団もまだ無い。正確に言うならアンテオキア戦闘の段階では、各国の寄せ集めの軍隊による戦いであるし、甲冑を身に付けた戦士も少数だったはず。確実にこんな劇的な戦いではなかった修道院が軍事化した理由聖地が奪還されたから終わりだ。・・と思うのは浅はかだ。力で奪った物は奪い返される可能性がある。ましてそこは異教徒の中の小島に近い場所。さらにそこはろくに作物も育たない痩せた土地で食料を確保する必要があった。巡礼者ばかりか、あらゆる巡礼物資が欧州側より船で届けられることになる。当然彼らは安全に物資が届く為の港の確保を必要とする。防衛上その対象はシリアやパレスチナの海岸線1000km。当初十字軍が確保した港は2つだけ、その後近隣の港街を落とす為に戦いが始まる。しかし主要部隊は聖地を奪還するとほとんどが国に帰ってしまった。戦士はいくらでも必要であったのに・・。1291年 アッコ包囲戦(The Siege of Acre)十字軍が建国したイェルサレム王国の首都アッコがイスラム勢に襲われている所。作品は1840年に描かれた作品。抵抗しているのは聖ヨハネ騎士団とテンプル騎士団。1291年陥落。生き残りの騎士団らはキプロス島に逃げ延びる。ウィキメディアコモンズより攻める側から攻められる側に・・。後にその立場が逆転。十字軍は聖地エルサレムを奪われ、、アッコを奪われキプロスやロードスに逃れて縮小されていくのである。テンプル(神殿)騎士修道会(Knights Templar)の末路1305年、フランス王フィリップ4世(Philipe IV)(1268年~1314年)によりテンプル騎士団に対して執拗なまでの攻撃が始まる。でっち上げの異端告発や風評をも操ったのだ。問題だったのは「アヴィニョン捕囚」と呼ばれる当時ローマ教皇自体か特殊な状況下におかれていた事である。教皇は次々亡くなりフィリップ4世におされて教皇クレメンス5世が即位。教皇庁はローマでなくアヴィニョンにおかれ、教皇権は完全にフランス王の強い影響のもとに置かれていた時代である。かくしてフィリップ4世の思惑のままにテンプル騎士団は弾圧されて1307年にテンプル騎士団の総長ジャック・ド・モレー始め騎士団全員捕らえられ財産が没収。拷問の後に異端審問にかけられた。1312年テンプル騎士団は解散。1313年総長ジャック・ド・モレーはフランスでフィリップ4世により火刑にされる。しかし、酷かったのはフランスだけである。他の国はむしろ同情的だったようだ。このフィリップ4世は教会にも負けず君主権を確立した王であるが、かなりブラックな王のようだ。テンプル(神殿)騎士修道会が壊滅させられた本当の理由は、フィリップ4世のしかけた財産狙い・・と言うのが真相のようだ。注:テンプルの資産についてはテンプル教会で・・。リンク ロンドン(London) 10 (テンプル教会 2 Banker)14世紀のイラスト(テンプル教会の冊子より)火刑にされるテンプル騎士聖ヨハネ騎士修道会(Knights Hospitallers)成り立ち第一次十次軍以前に破壊されたエルサレムの巡礼病院再築の為にイタリア、アマルフィの商人が「洗礼者聖ヨハネ修道院」の跡地に建てた病院が始まりである。ジェラード修道士(Blessed Gerard Thom)(1040年~1120年)が1099年~1120年初代総長になる。当初は祈りと戦いと病人と貧者の為の看護団体として宿泊所も兼ねた巡礼病院であったが、先述のように1136年頃から傭兵を雇い1160年には祈りから完全に軍事化され戦う教団に変貌。(修道会としては一番古いが軍事化するのはテンプル騎士団の後)ところで、ジェラード修道士がどこ系の修道会かは解りませんが「洗礼者聖ヨハネ修道院」の跡地に建設された巡礼病院の後ろ盾はベネデイクト修道士会だったようです。ベネデイクト会バックの聖ヨハネ騎士団とベネデイクト会から分派したシトー会バックのテンプル騎士団は事ある毎に何かともめて対立。が、ライバルのテンプル騎士団が1308年に異端審問で捕らえられると軍事面の主力部隊が聖ヨハネ騎士団に移り、テンプルの遺産も舞い込んで来る。1113年に聖ヨハネ看護団体として認可された時は聖墳墓教会に隣接した場所に所在していた。偶然撮影したこの門が聖ヨハネ看護団体の本拠だったかどうか確証はないが、信徒の巡礼病院か、宿泊施設であったのは間違いなさそう。右:十字・・・マルタ十字の形状を持つこの印はKnights Hospitallers 時代の印 ?左:鷲・・・福音書記者ヨハネの象徴のワシ(騎士団のヨハネは洗礼者ヨハネなのだが・・)中:羊・・・・正確には「勝利の旗を持って立っている小羊」旧約時代にはイスラエルの民を表し、キリスト時代になると洗礼を受けた信者を表す羊であるが、ここでは勝利の旗を掲げた傷ついていない羊の姿をとっている。これはヨハネによる黙示録の傷ついた羊とは対照する健康な羊を表現?シンプルに考えたら杖を持つ羊全部が洗礼者ヨハネを現すアトリビュートかな? ところで私は長らく誤解をしていました。聖ヨハネ騎士修道会は福音所記者のヨハネであると・・。本当はキリストを洗礼した洗礼者のヨハネ(John the Baptist)のヨハネ由来だったようです。洗礼者のヨハネはサロメに首を落とされ殉教するヨハネと同一人物で、旧約の登場人物ですが、キリストの洗礼者だけあって、カトリックや正教会でも聖人として扱われています。ビィザンティン時代のイコン、デイシス(Deisis)ではキリスト、聖母と共に居るのがこのヨハネですが、西方教会での扱いはほとんど無い気がします。さて、中東を追われ、落ち武者になった聖ヨハネ騎士団はキプロスを経てロードス島に身を寄せます。ロードスの旧市街ははまさに聖ヨハネ騎士団が要塞化した街そのものなのです。次回「騎士修道会 3 」「ロードスの騎士」で関連写真紹介。今回はおまけです。ロードス島 ロドス・シティの要塞とグランドマスターの城館今や世界的リゾート地になったロードス島には大型客船が多数出入りする。歴史は紀元前7世紀に遡る。カステーリャの守備した城壁St Ag Nicholas 聖アギオス・ニコラス要塞ロドス・シティ Marine Gate2回で終わらず m(_ _)m ゴメンナサイ リンク 騎士修道会 1 (テンプル(神殿) 騎士修道会)リンク 騎士修道会 3 (ロードスの騎士)
2013年08月21日
コメント(0)
-

ビクトリア& アルバート博物館 のカフェテリア
値段が一部わかったので追加Break Time (一休み)ビクトリア& アルバート博物館 のカフェテリア実は昨日ちょっとした手術をしてきました。だから昨晩は痛み止めで眠くて眠くて・・。足の爪が陥入して化膿したり腫れたりで2か月つらい思いをしていました。さかのぼれば1月にささやかな深爪だけだったのに、爪3ミリばかりサイドを切り落とされ引っこ抜かれてしまったのです。それが根っこの処理がされていない為に生えかわってきた爪が食い込む食い込む。伸びれば終わる・・と我慢していたのですが、腫れて歩くのにも支障が出てきたのでついに病院に・・。もちろん違う病院を探しました。陥入爪や巻き爪は外科の専門になるようです。外科と言っても知識のある先生でないとうまく対応してくれないのでなかなか病院を決めるのに時間がかかりました。結局ひどくなっていたので伸びかけた爪を再び切って引っこ抜いて、根元を科学的処理して2度とはえないようにしてもらいました。もっともこの方法はまだ完全には確立されていないのだそうです。2度も怖い思いをして今年も散々な年になりました (хх。) イタイさて、V&Aの略称でおなじみロンドンにあるVictoria and Albert Museum(ビクトリア& アルバート博物館)ですが、そこのカフェが美術館としてはなかなか素敵なカフェテリアでした。これから行く方はお茶だけでなくそちらで軽食をとるのもお勧めです。ビクトリア& アルバート博物館 のカフェテリアイギリスはとにかく物価が高くて驚きました。観光客泣かせの場所です。しかし、公営の美術館だけはたいてい無料です。(個人の所は別)※ 無料でも一応善意の献金が必要。ビクトリア& アルバート博物館正面玄関Sir Aston Webb(1849年~1930年)設計1851年のロンドン万国博覧会をきっかけに誕生した美術デザイン博物館です。当初は工業製品博物館と呼ばれ、マルバラ・ハウスに展示されていたそうです。1857年作品はサウス・ケジントンのプロンプトン・ボイラーズに収蔵。1899年創立者であるヴィクトリア女王と夫君アルバート公を讃えて名称を変更。下・・正面入り口左・・地下鉄連絡通路からの入り口グリーン・・中庭 その上の建物が下のルネッサンス・スタイルの建物でカフェはそこにある。Francis Fowke(1823年~1865年)設計 Morris Gamble Poynter Rooms破風(gable)の装飾はヴイクトリア女王に工芸品を献上する為に来る各国の人々イタリア、フランス、オランダなど国名が記されている。(アメリカは入っているが日本はない)Morris Gamble Poynter Roomsの中をそのまま利用した一部カフェ近代的な方が好きな方はこの向こう側にデリのお店が数軒並び、精算は1カ所のレジで行う。サラダ専門店や、肉類をメインにしたお店、パン屋系はサンドイッチ、ワインなど飲み物のお店も。Giant Meringue肉まんではない。これは卵白を泡立てた巨大なメレンゲのお菓子である。サラダを多く扱うお店でメインにスモークサーモンをチョイス。サブは3種まで選べた。レシートが見つからないが1200円くらいだったかな?スモーク・サーモンは北欧だと思っていたけどロンドンではあちこち出たし、とても油が乗っておいしいサーモンでした。因みにイギリスには歴史的な事情でインド人がものすごく多い。だからカレー味は結構多いです。付け合わせのサラダはカリフラワーのカレー味です。ミートパイ(ビーフシチューのポッドにパイがかぶせてある。)ここが一番高いブース。ミートパイ 9.95ポンド 付け合わせ2種 3.10ポンド 税込みTotal 13.05ポンド (約2000円)このお店がオープンするまで待った待った。何しろ寒い日だったからね。思っていたより高かった。この値段なら市内のパブのが安いですね。でもオープンしてからは人だかりで撮影ができなかったけど・・。イングリッシュ・スコーンスコーンにジャムとバターで2.95ポンドクロテッド・クリーム0.90ポンドおいしいスコーンでした。でも二人でちょうどかな?席数はあるほうですが、ランチだけ来る人もいるので早めに行かないと席がなくなります。何しろ美術館は無料で入れるので・・。今回いろいろ美術館のカフェには入りましたが、品揃えは一番。味も一番だったかな?ロンドンのレストランリンク シティのパブ The Edgar Wallaceリンク ロンドン(London) 7 (シャッド・テムズのカフェレストラン)
2013年08月20日
コメント(0)
-

騎士修道会 1 (テンプル(神殿) 騎士修道会)
Mail (armour)のリンク先追加しました。今回写真は神殿の丘から尚、本筋のロンドンのテンプル教会では、テンプルの資金と騎士ウィリアム・マーシャルを紹介する予定です。騎士修道会 1 (テンプル(神殿) 騎士修道会)騎士修道会(Knights of Christ)テンプル(神殿) 騎士修道会(Knights Templar)ソロモン王の神殿(Solomon's Temple)シトー会と聖ベルナール騎士修道会(Knights of Christ)十字軍時代に大活躍したのが騎士と修道会である。中でも修道会を軸とする修道騎士で作られたコミュニティーは、負傷兵や巡礼者の病院の役割ばかりでなく、巡礼者を保護したり、イスラムとの戦いにおいては戦闘集団にもなった。そんな志を同じくする騎士の集まりはローマ教皇に認可された騎士修道会となる。十字軍時代騎士修道会は8つほど発足したと言われるが、その中でも代表的な騎士団は3つ。聖ヨハネ騎士修道会(Knights Hospitallers)テンプル(神殿)騎士修道会(Knights Templar)ドイツ修道会のチュートン騎士団(Teutonic Knights)当時騎士団に入る事はとても栄誉な事であり、非常に人気があったようだ。最初に認可された聖ヨハネ騎士修道会には欧州の身分の高い貴族の子息がこぞって参加したとされる。下、白装束に赤い十字はテンプル(神殿)騎士修道会の騎士彼らは修道士か? 騎士か? どんな身分の者も入団には修道請願をたてる必要があり、修道士としての規律を守る必要があった。それ故、団員のほとんどは臨時の修道士だった・・と言う事になり、聖戦において、戦士が僧侶になった・・と言うのが騎士修道会の実態である。十字軍時代の発足当初の「騎士修道会」とはKnights of Christ(キリストの騎士)と言う存在だったのだろう。が、後半の騎士修道会は十字軍国家の防衛の主力となり、祈りよりも戦力。キリストの騎士と言うよりは国の防衛の為だけに戦ったただの戦士となっていた。聖ヨハネ騎士団だけで2つの大要塞と140の砦を守る任務があてられたと言う。テンプル(神殿)騎士修道会(Knights Templar)治安の悪かった巡礼路において、巡礼者を守る為に活動を始めたのがテンプル騎士団の創始理由です。創始者のユーグ・ド・パイヤン他8名で始まった警護は個人のボランティア? だったのか?ユーグ・ド・パイヤン(Hugues de Payens)(1070年~1136年)は1104年聖地での現状を聞いた後に聖地に出かけ1108年まで逗留。再び聖地に(1114年~1116年)次に帰国した時には資産を整理して1118年、3度目の聖地入に親類と仲間と共に入り活動を始めたとされる。神殿の丘は後にシオンの丘と呼ばれている。右の金色のドームが岩のドームで、左端にある銀色のドームがエル・アクサ・モスクテンプル(神殿)騎士と呼ばれるようになった理由最初は俗人の服を身につけ、信徒が与える施しにより生活。貧しさに耐え。報いられる事も世に認められる事も望まず。黙々として危険に身を呈していた彼らに対して、エルサレムの指導者達は深い感銘を受け、3代目国王ボードワンII(1118年~1131年)は主の神殿のそばにある王宮内に彼らの事務所と住居を与えたと言う。以降彼らはテンプル(神殿)騎士(Knights Templar)と呼ばれるのであるが、それが1118年~1120年の間とされている事からもしかしたらユーグ・ド・パイヤンは前の聖地入りの時からすでに活動を始めていたのではないか? と言う推察もできる。また、彼らが突然スターダムにのし上がるのはクレルヴォーの修道士ベルナール(1090年~1153年)の熱烈な支持があったからである。※ ベルナール (仏 Bernard de Clairvaux) ベルナルドゥス (ラテン語 Bernardus Claraevallensis)「新しき戦士を讃えて」の小雑誌では騎士の精神を忘れて世俗化した騎士を批判し、テンプル騎士団の清貧と熱意を賞賛。貧しき神殿の騎士を正式な騎士団に昇格する努力を彼は惜しまなかった。かくして豊かな寄付が彼らに寄せられるようになり、入団希望者は押しかけ、1129年のトロワの宗教会議では、テンプル騎士団の創設が決定された。ボードワンIIがユーグ・ド・パイヤンにソロモン神殿を譲る図 13世紀頃ウィキメディア・コモンズよりソロモン王の神殿(Solomon's Temple)主の神殿とは、ソロモン王が造ったとされるエルサレム神殿の事である。ソロモン王の神殿は紀元前960年頃の話であり、この当時すでに城壁の一部しか存在しておらず、神殿の上にはイスラムの建てた岩のドーム(The Mosque of Omar)(690年)とエル・アクサ・モスク(Mosque of El Aksa)(710年)があった。十字軍は岩のドームが契約の箱を納めた場所だと特定。アル・アクサ・モスクはソロモンの宮殿と呼ばれ十字軍のエルサレム王国の王宮として使用されていた。岩のドーム(The Mosque of Omar)(690年)アブラハムが生け贄(息子イサク)をささげようとした場所であり、ダビデ王やソロモン王が祈り、契約の箱を祀った場所である。イスラム教徒にとっても聖地。ここはマホメットが昇天した場所でもある。エル・アクサ・モスク(Mosque of El Aksa)(710年)エルサレム王国の王宮として使用され、テンプル(神殿)騎士修道会の本拠が置かれた。十字軍時代ここが至聖所の一画と考えられていたからでもある。テンプル騎士のフィギュア左の騎士の持つ白と黒に赤い十字の盾(たて)が1147年以降のテンプル騎士団の印。見えないが、白いマントの左胸に赤い十字のマークもテンプルの印。衣装の白装束は当初、テンプル騎士達がシトー会の聖ベネディクトの戒律を遵守していた事による。トロワ公会議の後にテンプル独自の戒律はできるが、衣装はそのままで、鎖帷子(くさりかたびら)の上に白い衣を着てマントをはおるのがテンプル(神殿)騎士修道会(Knights Templar)風として定着。以前テムズの橋のところでドミニコ会系の修道士をBlackfriars(黒衣の修道士)と書いたが、逆に「白衣の修道士」と言うのが存在する。それがベネディクト会改革運動から分派したシトー修道会の装束である。シトー会と聖ベルナールシトー会は1098年、ディジョン南東の森の中シトーに「巡礼病院」として認可‥修道服の白色は自己犠牲、清貧、福音主義などの改革精神を象徴する色。前述、フォンテーヌの城主ベルナールの入会によりクローズアップされる修道会である。ベルナールの名演説で2回目の十字軍を募り後に彼は聖人に認定。神秘思想家にして政治、社会問題まで幅広い調停をこなすベルナールは当時欧州で最も影響ある人物であった。鎖帷子(くさりかたびら)ニットのように見えるが、薄い鉄板を輪切りにしたり、鉄の細糸を輪にしてつなぎ止めた防具。それ故Chain mail と呼ばれる。以前「西洋の甲冑 2 (Armour Clothing Mail)」でMail (armour)について紹介しています。リンク 西洋の甲冑 2 (Armour Clothing Mail)後年、書いた続編(甲冑の歴史)でも詳しく出ています。リンク 西洋の甲冑 4 ハプスブルグ家の甲冑嘆きの壁(The Wailing Wall)ヘロデ大王時代のエルサレム神殿の西の外壁跡「嘆きの壁」はユダヤ人にとっての最も聖なる場所。つづくリンク 騎士修道会 2 (聖ヨハネ騎士修道会)リンク 騎士修道会 3 (ロードスの騎士)リンク ロンドン(London) 9 (テンプル教会 1)リンク ロンドン(London) 10 (テンプル教会 2 Banker)リンク ロンドン(London) 11 (テンプル教会 3 中世の騎士)
2013年08月14日
コメント(0)
-
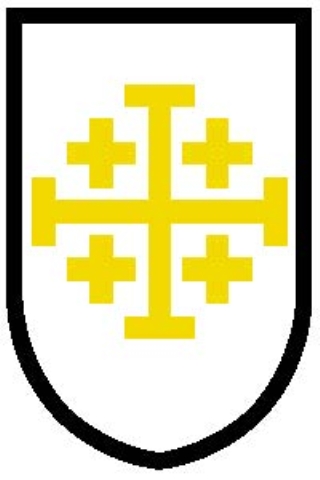
十字軍(The crusade)と聖墳墓教会 2 (キリストの墓)
今回紹介している聖墳墓教会は2008年に撮影したものです。十字軍(The crusade)と聖墳墓教会 2 (キリストの墓)ウトラメール(Outremer)エルサレム王国聖墳墓教会(The Church of the Holy Sepulchre)キリストの墓テンプル(神殿)騎士団のルーツウトラメール(Outremer)ヨーロッパではない外地レバント、シリア地方、パレスチナなど東地中海の海岸沿いの地方にできた国を指す総称で、特に十字軍派遣の副産物。騎士が造った4つの王国(アンティオキア公国、エデッサ伯国、エルサレム王国、トリポリ伯国)を指した言葉だそうです。1096年8月から順次出発した公式部隊は、エルサレムまでの道中で幾度もの激戦をし進軍。翌年1097年5月までには東ローマのビザンティンに到着。ところが公式特使の部隊でさえ、以降エルサレムに向かうまでに陥落した街を自分の所有にし、聖地に行くのを止めた部隊もあり初心通り聖地にたどりついた部隊はわずか2万ほど。シリアの中心アンティオキアを陥落後に君主になったのはイタリア軍の指揮官ボヘムント。タルソスとエデッサを陥落して君主になったのはブローニュ伯ボードワン。1099年1月やっとトゥールズ伯レイモンとブイヨン卿ゴドフロワがアンティオキアを出発してから聖地に到着したのはその年の6月の事。当時の戦闘は城壁を越えるまでの攻防があり、城内に入れば勝ち・・と言うもの。公式の第一次十字軍によるエルサレム陥落は1099年7月13日夜半。騎士500人、兵卒2万人ほど。街の住人はイスラム教徒もユダヤ人も全く無差別に殺され、通りは彼らの血で真っ赤に染まったと言う。聖地エルサレムは話し合いによりロレーヌのゴドフロワ・ド・ブイヨン(Godefroy de Bouillon)がエルサレム王国の君主に決まった。トゥールズ伯レイモン(Raymond IV de Toulouse)の方は数年後に北アフリカのトリポリに自分の国を造る事になる。エルサレム王国初代君主、ゴドフロワ・ド・ブイヨン(Godefroy de Bouillon)(1060年頃~1100年)しかし、彼は君主と呼ばれる事を拒否。 聖墓守護者でありたかったようだ。正式に王と呼ばれるのは2代目のエデッサ伯ボードゥアン1世(Baudouin I)(初代ゴドフロワ・ド・ブイヨンの弟)である。征服した1099年から始まり、セルジューク・トルコのサラディンに攻め落とされる1187年までエルサレムに存在。エルサレム陥落後、王国の首都はアッコに移り、マムルーク朝スルタンのアシュラフ・ハリールにアッコが攻め落とされる1291年まで存続。第一次十字軍で残留した兵士は土地をもらい領主になったが、そのほとんどはフランス人だった為に公用語はフランス語だったと言う。エルサレム王国の紋章(ウィキメディア・コモンズより)聖墳墓教会(The Church of the Holy Sepulchre)巡礼ポイント ゴルゴタ(Golgotha)の丘Aポイントがキリストが磔になったゴルゴタの丘。Bポイントは「キリストの墓とされる場所。聖墳墓教会はそれらの上を覆うようにして連結して教会堂を建てられている。つまり、ヴィア・ドロローサ(Via Dolorosa)悲しみの道の10~14ステーションがこの教会の中にある。聖堂はキリストの墓所のあるアナスタシス(anastasis・復活聖堂)とマルチュリオン(martyrion ・殉教聖堂)。それに地下の聖ヘレナ聖堂からなっている。ギリシャ正教会の聖堂ここはキリストが十字架にかけられ亡くなった・・とされるゴルゴタ(Golgotha)の丘。その祭壇の下、十字架が建てられた穴の場所アナスタシス(anastasis・復活聖堂)キリストの墓ドームの下には完全なるサンクチュアリ(sanctuary・聖域)である囲われた建物がある。ここはキリストが葬られ、かつ復活を果たした岩の洞窟跡を囲った墓所とされている。福音書マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネともにキリストの死の章の内容にはずいぶん差がある。十字架に付けられて亡くなったのはどれも同じであるが、槍に突かれ亡くなった・・との記載はない。唯一イエスの脇腹を刺した・・の箇所はヨハネの福音書のみで、それも死後の確認の為であった。世間に有名なキリストを刺した聖槍であるロンギヌス(Longinus )の槍はこの一点からのみ誕生している。また、槍で突いた事による出血の血を受け取った聖杯伝説もここに由来している。福音書マタイ、マルコ、ルカではキリストが十字架上につけられていた時に起きた奇跡の現象が描かれ、特別な人だった・・との印象を示している。ヨハネにはそれが無い。翌日が安息日の為に罪人はすみやかに十字架から降ろされた。遺骸を引き取ったのは議員で、アリマタヤ出身のヨセフ。彼は遺骸を亜麻布で包み、ほど近い園の新しい墓にキリストを安置した。それぞれ異なるのは、香油と没薬のくだりである。いずれも翌日が安息日の為に慌てていた様子がある。安息日の翌日墓に行くと墓を塞いでいた石のふたが開いていた。マタイ、マルコ、ルカでは天使が現れている。ヨハネの方は普通にキリストが消え亜麻布が残されていた。と言う現実的なもの。つまり埋葬された墓から3日目にはキリストの遺骸は消えていたので「復活された」・・と解釈。墓は墓でもそこにキリストの骨一つさえ無い・・と言う事である。イスラエルの第二神殿時代、金持ちの墓は岩を真横にくり抜いて造られていたと言う。入り口を入るとさらに入り口が・・。そして祭壇テンプル(神殿)騎士団のルーツテンプル騎士修道会の正式認可は第1次十字軍(1096年)遠征後1120年頃の事です。イスラム教徒からキリスト教の聖地エルサレムを奪還したものの騎士はその後の国の防衛にあたり、エルサレムを除けばほぼイスラム勢力圏内で、巡礼路は相変わらず危険地帯だったそうです。巡礼者を守る為の仕事を最初にかって出たのがシャンパーニュの騎士、ユーグ・ド・パイヤン(Hugues de Payens)(1070年~1136年)とジョフロワ・ド・サントメーら当初9人。彼らは巡礼者が上陸するパレスチナ港ヤッファからエルサレムまでの警護を始めたと言う。それが後に騎士団に正式に認められるのである。続きはテンプル騎士団で・・。back numberリンク 十字軍(The crusade)と聖墳墓教会 1 リンク 騎士修道会 1 (テンプル(神殿) 騎士修道会)リンク 騎士修道会 2 (聖ヨハネ騎士修道会)リンク 騎士修道会 3 (ロードスの騎士)
2013年08月09日
コメント(0)
-

十字軍(The crusade)と聖墳墓教会 1
用語解説の意味でもどうしてもテンプル騎士団より先に紹介しておきたかったので差し込みました (;^_^A 突然ですが、ロンドンを離れて中東に・・。写真はエルサレムの聖墳墓教会(The Church of the Holy Sepulchre)から。十字軍が何を守ったか? テンプル(神殿)騎士修道会のルーツがここにあります。聖墳墓教会のレアな写真もあるので全2回ものになりそうです。十字軍(The crusade)と聖墳墓教会(The Church of the Holy Sepulchre) 1十字軍とはどんな軍隊か? その目的は?そもそもなぜ十字軍なるものが誕生したのか?どんな人達が十字軍に参加したか?巡礼の地エルサレム十字軍とはどんな軍隊か? その目的は?イスラム教徒からキリスト教徒の聖地であるエルサレムを奪還する為に教皇の名の下に各国の王侯に聖地奪還の為の軍隊派遣を要請。それを受けて組織された討伐軍隊が十字軍(crusade)です。十字軍の出陣は時期や出立の場所などさまざまあり、何回かの十字軍(crusade)を数えますが、最初の趣旨で言えば、教皇のお墨付きによる地元領主と共に聖地を目指したきちんとした団体のみが十字軍(crusade)と数えられるでしょう。なぜなら聖地奪還ではなく、異教徒討伐や略奪的進軍に変わり、真の目的を失っているものもたくさんあるからです。※今回は敢えて回数には踏み込まず、十字軍が何だったか・・だけ紹介します。エルサレム旧市街 神殿の丘オリーブ山から撮影岩のドーム(右手前)と聖墳墓教会(左奧のドームと尖塔)そもそもなぜ十字軍なるものが誕生したのか?発端は1095年に東ローマ、ビザンツ帝国の皇帝アレクシウス2世が西のローマの教皇に助けを求めた書簡。ビザンツ帝国の皇帝アレクシウス2世は1071年の戦いでセルジューク朝トルコに奪われた土地を取り返す為の軍隊を要請。彼らは聖地の支配者でもあったのでセルジューク朝トルコを打倒して欲しい・・と言う所が本音。しかし、ローマの教皇ウルバヌス2世は想定外の方向に動いた。1095年11月28日フランスのクレルモンでの教皇演説では「東方のキリスト教徒の救援に出かけ、聖地を奪還しよう。・・それは天上の栄光を勝ち得るチャンス。巡礼であると同時に聖戦であり、何よりも贖罪となる。と言うような内容。参加志願者が我先に十字軍のバッジを受け取ったのは免罪のキップを手に入れたような熱狂だったのでは? と推察できる。そして翌年から幾多の団体が聖地に向かって出かけた。第一次十字軍(The First Crusade)1096年~1099年ここはラテン語でVia Dolorosa(苦難の道)イスラエルのエルサレム、旧市街、イエスが十字架を担ぎ3度目に倒れた場所。ゴルゴダの丘の一歩手前。見える聖墳墓教会はキリストの磔刑の場所であるゴルゴダの丘の跡に326年コンスタンティヌスの母ヘレナが巡礼と聖遺物収拾に出かけたおりにここを断定。ヴィーナス神殿を取り壊し、聖墳墓教会(The Church of the Holy Sepulchre)が建設されたの336年。(ゴルゴタの丘の所在については、今更・・だが実は異論がある。)聖墳墓教会(The Church of the Holy Sepulchre)どんな人達が十字軍に参加したか? 全ての参加者が軍人(騎士)ではなかった。完全に戦闘モードの軍隊は全体の1/6程度。それに非戦闘要員を足すと数万人単位の団体だったようです。諸侯は自分の周りに騎士を随行。(唯一の本物の戦力)お付きの従者や戦えない聖職者もいたし、農閑期の村人など半武装の者もいた。(ここまでは教皇も想定内)しかし免罪キップとなる巡礼ついでに一山あてたい者もいたし、出稼ぎ気分で随行した者の他に貧困から脱出して新天地に行きたかっただけの足手まといとなる参加者の方が多かったようだ。その為にわずかな騎士は大勢の武器を持たない者達を守る役目もしなければならず本末転倒。なかなか聖地にたどりつけず疲弊。1101年に20万人の十字軍一団が出立しているのですが、聖地にたどりついた者はわずか1%。(それ故「第二次」と言う称号も付かず忘れられた。)特にトルコ経由の西ルートは危険だらけだったと言う。聖墳墓教会入り口現在の教会はビザンティン時代、十字軍時代と19世紀に建てられているらしい。ローマ・カトリック、ギリシャ正教、アルメニア教会の聖地の為に勢力とすみわけができているそうです。でも、教会の扉を開けるのはそれらキリスト教徒でない者がわざわざ選ばれている・・とか・・。巡礼の地 エルサレム313年、ローマ帝国皇帝コンスタンティヌス1世によりミラノ勅令が発布。これは全帝国民の信教の自由を認めた内容である。これより今まで迫害されていたキリスト教徒は自由を得、キリストの生誕の地や十字架に架けられたゴルゴダの丘のあるエルサレムは熱狂的信者の巡礼の地となった。キリスト教が公認されて真っ先に聖地に巡礼し聖遺物を持ち帰ったのがコンスタンティヌス1世の母ヘレナ(Helena)(246年/250年~330年)である。先に述べたように、ヘレナは場所を特定してそこに教会をたてたばかりか、いくつかの重要な聖遺物を発見している・・とされる伝説がある。キリストの脇腹を刺したロンギヌスの槍(Lance of Longinus)など・・。しかし聖地は638年イスラムの街となる。イスラム帝国、第2代正統カリフ(634年~644年)の時代である。それから十字軍がエルサレムに乗り込むまでイスラムの王朝が支配。しかし、イスラムの街になった後もキリスト教徒の巡礼は続いた。心が広かったのはイスラムの国の方だった。イスラムの国(アッバース朝、アイユーブ朝時代)はそれなりに関係を保っていたので、聖地にはいつでも巡礼に訪れる事ができたと言う。それ故に本当は聖地奪還の必要はなかった。(エジプトのファーティマ朝時代、カリフ、ハキムの時代に不具合はあったらしいが、彼の死後再び巡礼は保護されていた。)実際十字軍の派遣直前1026年にはノルマンディー公リシャール2世が700人を引き連れて巡礼に出かけているし、1065年には12000人以上のゲルマン人が巡礼に出かけていたと言う。セルジューク朝トルコはイスラムの中でも問題児ではあったが、その時代さえ聖地の巡礼を拒む事はなかったと言う。ただ、そこに至る巡礼路には盗賊がいて巡礼は大変危険だったようだ。しかし、キリスト教徒にとって巡礼はその道程が含まれる。特定の信仰を持たない日本人にはちょっと解りかねないカトリック信者の死生観がそこにあったと思う。ゴルゴタ(Golgotha)の丘は現在、聖墳墓教会の中に含まれている。ゴルゴタとは髑髏(されこうべ)の意。いわゆる行灯の下には大理石の石の板が・・。これが磔(はりつけ)にされたキリストが下ろされて寝かされた場所だと言う。それにしても十字軍の功罪は、聖地にいた者をほぼ皆殺しにし、略奪の限りをつくしたと言う事だ。その中にはイスラム教徒だけでなくキリスト教徒も沢山いたと言う。それ故、奪われたものを取り戻す為の彼らイスラムの反撃が始まるのは必然であった。十字軍と聖墳墓教会・・・つづくリンク 十字軍(The crusade)と聖墳墓教会 2 (キリストの墓)リンク 騎士修道会 1 (テンプル(神殿) 騎士修道会)リンク 騎士修道会 2 (聖ヨハネ騎士修道会)リンク 騎士修道会 3 (ロードスの騎士)リンク ロンドン(London) 9 (テンプル教会 1)リンク ロンドン(London) 10 (テンプル教会 2 Banker)リンク ロンドン(London) 11 (テンプル教会 3 中世の騎士)
2013年08月05日
コメント(0)
-

ロンドン(London) の地下鉄(Underground)
Break Time(一休み)テンプル教会を紹介する為には、テンプル(神殿)騎士修道会の話をしなければなりません。が、その騎士修道会の話をする為にはどうしても十字軍の話から入らなければならないのです。それらはどれも簡単に説明できるものではなく、特集に持ち込みたいネタですが、今回はできるだけシンプルに流れを紹介して・・と思っています。が、新たに本を数冊読んでいるので今回は別ネタです (;^_^Aロンドン(London) の地下鉄(Underground)世界初の地下鉄は蒸気機関車が牽引1863年1月9日。世界初の地下鉄がロンドンで開通した日である。区間はパディントン駅からファーリントン・ストリート(約6km)。まだ日本が江戸幕府14代将軍の頃の話である。ロンドン市内はすでに建物が密集し、地上に鉄道用地を確保できなかった為に地下を掘ったそうだ。その為か? ロンドン地下鉄はSubwayと言うよりUndergroundと呼ばれている。一目で地下鉄駅だと認識できるような工夫がわざとされていると言う。Piccadilly Circus Station 入り口世界初の地下鉄は蒸気機関車が牽引1863年の開業初日に3万人の乗客があり、初年度950万人の人を運んだと言う。しかし、この時の地下鉄は蒸気機関が牽引し、しかもガス灯を灯した木造客車の上にさらに屋根が無かったと言うのだから驚き。 シェー 「( ̄□ ̄;)」駅は換気の為に吹き抜け構造となり、トンネル内に排出される煤煙と熱を抑える構造がとられていたようです。また全てが地下トンネルではなく、路線の一部は土地を切り開いて掘る掘割(ほりわり)が多かったようですし、パディントン駅からキング・クロスはそのほとんどが開削工法(オープンカット工法)で行われたと言います。そこに排煙だけでなく、技術的問題もあったのでしょう。それにしても蒸気機関では、さぞ体に悪かったろうし、すすで真っ黒に汚れたであろう・・。ロンドンの地下鉄が電化されるのは1905年。地下鉄として世界で最初に電化路線になったのは、1896年5月2日に開業したブダペスト(ハンガリー)の地下鉄。ピカデリー線 (Piccadilly Line) は地表から深い位置を走るタイプの路線だそうです。ロンドン地下鉄の路線では3番目に利用客が多いとか・・。Piccadilly Circus Station思ったよりかなり綺麗だったので驚きました。もしかしたら昨年のオリンピックで綺麗にしたのかも・・。トンネルの掘削の関係で列車もこじんまり創られているので日本の地下鉄よりずっと狭いです。当時、すでにシティに徒歩で通勤している人は一日20万人に達していたとか・・。鉄道は1850年までにロンドン中心に7つの鉄道のターミナル駅が存在し、営業効率のいい郊外へ路線をのばしていたと言いますが、それら路線もバラバラ。地下鉄同士も当然接続されていなかった為に一度地上にでないと乗り換えができない不便さもあったそうです。ロンドンの地下鉄が統合されるのは1933年以降です。まとめて警報があるのは良いアイデアですね。駅構内の広告はどこも一緒。広告と言えば、電車丸ごとラッピングされている日本の地下鉄を見たらさぞ驚くだろうな。副都心線の地下鉄は電車自体が丸ごと広告でラッピングされている事が多く楽しいですし、何より広告のインパクトがあります。電車の形状が、本当にトンネルの形のよう。ところで、ロンドン最初の地下鉄を運営していたのがメトロポリタン鉄道(Metropolitan Railway)ですが、1900年パリ万博に合わせて開通したパリの地下鉄は、メトロポリタン鉄道の名からメトロ(Métro)の呼称をつけたと言われています。今や「メトロ」はフランス語の「地下鉄」の意味になりましたが、本当は都市交通の総称なのだそうです。
2013年08月01日
コメント(0)
全8件 (8件中 1-8件目)
1










