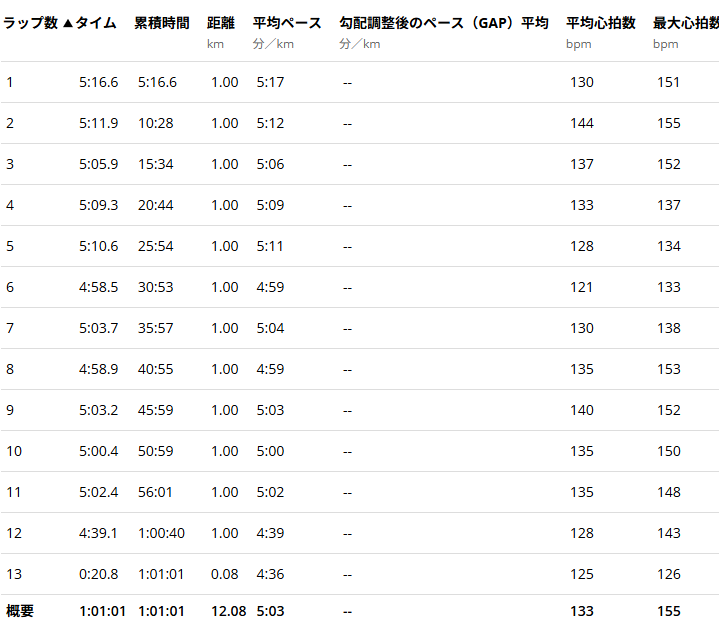『橋の下の彼女』(22)
1999年7月6日(火)
フィリピン・アレン
まだ八時前だというのに、太陽に焼かれた地面からはむせ返るような熱気が立ち上っているが、昨日とはうってかわって、錆びの浮いたトタン屋根と、高さの不ぞろいなブロック壁に囲まれた加工場には、新学期の初日のような、初々しい雰囲気が漂っていた。
二十四名の新人たちは、期待と不安と緊張が入り混った表情で加工場の壁際に立ち、アルバートやイボンが鮮魚や氷の入った大バケツを運び入れるのをじっと見るめている。そんな彼らを前にして、将人はふと、学生時代に部活で新入部員を迎えたときのういういしさを思い出した。
辰三は基本となるオペレーションの流れをリンドンに説明した。
まず朝一番で、冷蔵庫に保存している鮮魚の魚種別の鮮度と在庫量を確認する。同じ魚種、同じ保管方法でも、固体別に相当の差が出るので、データで一括管理せず、必ず自分の目で見て触って確かめること――。
次に、その日に加工する魚種と加工法と目標数量を決めるが、痛んでいるもの、鮮度落ちの激しいものを優先し、日持ちしそうなものは後回しにして、在庫ロスが出ないよう気をつけること。どのテーブルで何人にどの加工を担当させるか、などという割り当ても始業前に考えておかなければならない。作業が開始したら、製品ごとの製造スピードや在庫数、干物の場合は天候による乾きの早さ遅さなども考慮しながら、生産数も種類も偏ることのないよう、随時生産調整していく――。
加工を終えた魚は、生産性を落とすことがないよう、加工係でなく梱包係がそれぞれのテーブルをまわって回収する。魚は厚手のビニールパックに並べて詰め、急速冷凍用の金属製のトレイに間隔を空けて並べる。トレイがいっぱいになったら、計量所に運び、重量を記録して、白いリーファーコンテナの急速冷凍庫に運び入れる。パック詰めした製品の急速冷凍が完了したら、緑のリーファーコンテナに移し、マイナス十度の庫内で出荷用のきれいなダンボールに梱包していく――。
「そうやって、まるの魚が、サンパブロへ出荷できる製品になるわけだ」辰三はそそくさとメモを取り続けているリンドンのせなかをポンとたたいた。「まあまま、書くのも大事だけどよ、まずはやってみることだ」
それから、辰三はリンドンを引き連れ、白いリーファーコンテナに保存されている鮮魚を見てまわった。アジの鮮度が落ちていたので、アジを優先して加工することになった。鮮度の良いものはフライ用、鮮度が落ちて身が柔らかくなってしまったものは干物用の具材にする。フライ用は頭を落として背骨を抜き取る工程が難しいので、昨日の試験の成績で上位から四名をひとつのテーブルに集めて作業させることになった。辰三は、その四人を〈選抜組〉と命名した。その中に、あの〈太っちょさん〉も含まれている。
残りの加工係たちには、干物用を加工させる。
「干物用もフライ用も、試験での連中の腕を見る限り心配はいらねぇよ」メモを復唱しながら工程を確認しているリンドンに辰三が言った。「フライ用はそのままパックに詰めて冷凍するだけだ。干物用はな、醤油を入れたバケツに一時間くれぇ漬け込んだあと、そうだな、三十分から四十分くれぇ天日で干す。こっちの日差しは強ぇから、場合によっちゃもっと短くていいかもしれねぇが、まあそれはやってみるまでわからねぇな。だからまだメモするのは早ぇぞ、リンドン」
しょうゆ漬けされたヒラキを干し網に並べていく役目は、「あのヌンチャク野郎がいい」という辰三の希望でなぜかノノイに決まった。
加工場に呼び出されたノノイは、ハンサムな顔で嬉しそうに微笑んだ。
「ぜんぜんかまわないさ。こっちのほうが、おんなのこがたくさんいるし、たのしそうだなとおもってたから」
「丁寧に扱うんだぞ、女を扱うようにな」
レックスがからかうように言った。
「それなら、とくいです」
ノノイが胸を張って答えた。
リンドンは今日も用意周到で、首にはホイッスル、手にはストップウォッチを持って加工場に仁王立ちした。
トトがテーブルに出刃を配り終え、新しい従業員たちが配置についた。
「それでは、作業開始!」
八時きっかりに、リンドンは鼓膜が破れそうなほどけたたましくホイッスルを吹き鳴らした。
加工係たちは、ミナモト水産の大バケツの中に手を突っ込んで数匹の鮮魚を取り上げ天板の中央に置くと、指示されたとおり、常温にさらされているあいだに痛むことのないよう、フレークアイスで覆っていく。そして、その氷の山から一匹を手元に引き寄せると、ためらいもなく出刃を動かし始めた。
「おいおい、勢いがいいのは認めるが、そんなにせかつくとミスするって――」
辰三が慌ててテーブルに駆け寄っていく。
フライ用具材担当のテーブルに首を突っ込んで「ちょっと、いったん手を休めて俺の話を聞け」と辰三は大声で言ったが、作業を中断した加工係たちの手元に視線を落としすなり、押し黙ってしまった。
「どうかしました?」
将人は聞いた。
「いや、その――」辰三が引きつった笑いを浮かべる。「――できてるんだよ。昨日ちょっと教えただけだってのに」
背骨を抜き取るとき、ほんのわずかだけ身を削りすぎてしまっている者がいて、辰三は身振り手振りで注意したが、もちろん「欲を言えば」というレベルの話だという。
一匹仕上げるたびに、「これで良いか?」と辰三のところまでヒラキを見せに来る従業員も何人かいて、そのたびに辰三はよりきれいに加工するコツをうれしそうに教えていた。
いつのまにか、加工係全員が、一匹仕上げるごとに辰三の評価をうかがいにやって来るようになった。全員の質問に答え切れない辰三の代わりに、途中からトトも加工係たちの質問に答えるようになった。
「あいつら、今日だけで腹開きが完璧になるかもしれねぇな」辰三が心底、感心したように頷いた。「器用なだけじゃなくて、物覚えもやたら早えからよ」
レックスが近づいてきて「どんな具合です?」と聞いた。
辰三は何も言わず、ただにやけて肩をすくめただけなので、レックスはそれをどうとらえて良いのかわからない様子だ。
「ショウ、タツミさんは何か困ってるのか?」
「困っていますよ――」将人も辰三を真似て肩をすくめて見せる。「――彼らがあまりに優秀すぎるからです」
レックスは表情を緩めると、新しく雇い入れた者たちを見渡しながら、「そうか、それは確かに困ったことだ」と満足げに頷いた。
リンドンが十時きっかりにホイッスルを吹き鳴らした。あまりに強く吹いたためか、途中でホイッスルが口から吹き飛んだ。
従業員たちから控えめな笑いが起こった。
「十分間の休憩を取ります。十時十分に作業再開するので、くれぐれも自宅へ戻ったりしないように」
フィリピンでも、日本のように、十時に十分間の休憩を取るというのが何だか意外だった。
中年の女性従業員たちは、加工場の壁際に置かれたベンチ――知らぬ間にブノンが作ったようだ――に腰掛けておしゃべりを始めたが、若い男の加工係たちは、休憩のあいだも、もっとやらせろ、と言わんばかりの勢いで持ち場を離れず出刃を動かし続けている。そんな彼らをリンドンが一人ずつ諭してまわり、一人、また一人と、名残り惜しそうにテーブルから離れていった。
アルバートが将人と辰三にビンのコーラを二本持ってきた。リーファーコンテナの中で冷やしていたのか、飲むと舌が痛くなるほど冷えている。
「おばちゃんたちはよ、家でも同じことやってるわけだから、ここでの仕事は、まあ家事の続きみてぇなもんだろうが、ああいう若い連中にとっちゃさ、それこそ新しいゲームみてぇなもんに感じるもんだ。どれだけ上手に、どれだけきれいに魚をさばけるかって、仲間うちで競うゲームさ。おまけに金までもらえるんだから、あんなふうにむきになっちまうもんなんだよ」
言って、辰三はストローでコーラをすすりながら、感慨深げに目を細めた。
四つのテーブルで加工が進められている干物用のヒラキは、梱包係たちが集めてノノイのところに運んでくる。五十枚集まったところで、ノノイは醤油を満たした大バケツに投入し、腕時計で漬け時間を計り始めた。
数十分して、「そろそろ干してみるか」と辰三が言うと、バケツとにらめっこしていたノノイが嬉しそうに立ち上がった。
「やっと、しごとができるよ」
辰三がノノイと梱包係の四人を干し台の前に呼び寄せた。逃げ出したくなるような強烈な直射日光の下でも、彼女たちは身じろぎすらせず、どうやってしょうゆ漬けしたヒラキを干し網に並べるかという辰三の指導をじっと聞いている。
醤油で手がかぶれるかもしれないということで、リンドンがゴム手袋を用意していた。ノノイがそれをはめて、漬け込んだ魚をバケツからつまみあげ、干し台の上に並べて置いた干し網の上に、どさりと山にして置く。辰三がそれをきれいに列にして並べ始めると、梱包係もそれに続く――アマリア、クリスティ、イザベラ、それにあともうひとり、名前がわからないが、他の三人に引けを取らない整った顔立ちをした背の低い女の子――。
アレンで美人コンテストを開催したら、この梱包係の四人が上位を独占するのではないか、と将人は思った。
そんな彼女たち相手でも、ノノイはまるで昔ながらの知り合いであるかのように、親しげに会話している。ノノイが彼女たちに接する態度には、まるで下心が感じられず、むしろ彼女たちの方が、彼に興味を抱き始めているのが見ていて伝わってくる。中学校のころ、放課後の教室で、人気者の男子を数人の女子が取り囲んでいるのを見たときに感じた羨望と嫉妬を、将人は場違いに思い出し、思わず微笑んでいた。
「あんなもの、ノノイひとりでやらせればいいんだよ。女の子たちまで手伝う必要はないじゃないか」
振り返ると、発電機と冷凍装置の調整と燃費記録で大忙しのはずのアルマンが、みるからに不機嫌な顔で隣に立っていた。
「なんだアルマン、ノノイにやきもちかい?」
将人はからかった。
「僕は仕事の能率のことを言っているんだよ。あんな仕事に五人もいらないだろ」
「辰三さんが干し方を五人にまとめて指導してるんだ。それよりアマリアを見てよ、とても楽しそうじゃないか。さすがノノイだね、女性をリラックスさせるのが上手いよ、僕も見習いたいくらいだ」
「わかってないんだなショウは」アルマンが不自然に甲高い声で笑った。「いいかい、ノノイみたいな筋肉男が女に受けるのは最初のうちだけさ。女というものは本来、頭の良い男が好きなんだ。例えば、みんなが知らないような、難しい機械のこともで、すぐに理解できるインテリ――つまり最終的には、僕みたいな技術者のところへなびいてくるってわけ」
それからしばらくうんちくをたれて気が済んだらしいアルマンは、そそくさと発電機の方へ戻っていった。
ノノイと梱包係たちが要領をつかんだところで、辰三は「まったく日なたは暑くてたまらねぇよ」と逃げるように加工場へ戻った。
「しかしアレだな、あのねえちゃんたち、さすがに暑さには強えな、びっくりだ」言いながら、辰三はじっとりとにじんだ額の汗を拭った。「それにしても、汚れる仕事だってわかってるはずなのによ、なんでこいつら、毎日毎日、あんな洒落た服を着てくるんだろうな」
それは将人も気になっていた。梱包係の四人だけでなく、加工係たち全員が、昨日の採用試験のときと似たり寄ったりの、まるでレストランか社交パーティにでも出かけるかような小ぎれいな服装をしている。上着には魚のうろこや血や内臓が点々と跳ね飛び、ズボンやスカートにはテーブルから滴り落ちた汚水が転々と落ちている。ゆったりとした白いシャツを着ている女性など、テーブルの縁に触れる部分がべっとりと赤茶色に染まってしまっている。
リンドンにわけを聞くと、彼は肩をすくめて呆れたように首を振った。
「昨日、彼らにはしっかり伝えたんだよ。『明日からは汚れてもかまわない服装で来い』とね。でもさ、彼らにとては、日系企業のブエナスエルテ社に出勤するときこそ、持っている服の中で一番良い物を着てくる場合なんだ。そもそも、あんな服を着ていく場所も用事も、ここサマールの人たちにはほとんどないんだから」
将人が通訳すると、辰三は苦笑いを浮かべながら、リンドンに言った。
「なあ、エプロンを全員に用意してやってくれねぇか? 費用はミナモト水産でもつからよ」
一瞬だけ驚いた顔になったが、リンドンは「ご心配はご無用です」とすぐに答えた。
「今、ライアンが町にエプロンを買いに行っています。アレンですからビニール製の安いものしか手に入らないでしょういが、人数分は揃えられるでしょう」
辰三はほっとした顔で「頼りになるよ」とリンドンに言った。
加工場の柱に取り付けられた掛け時計の秒針を目で追いながら、リンドンは十二時ぴったりに昼休みを告げるホイッスルを吹いた。
加工係たちは、加工途中のものは最後まで仕上げてから出刃を置いた。テーブルの上でフレークアイスに包まれていた加工前の魚は、氷水の入った大バケツに戻される。
片付けを終えると、加工場の従業員たちは、昨日のようにいくつかの仲良しグループになって木陰で弁当を広げた。家が近い者たちは自宅で昼食を取るらしく、リンドンに断ってからそそくさと加工場から去っていく。
今日から昼食は社宅で取る、と将人はライアンから告げられた。理由をたずねると「一介の従業員たちと同じ場所で食事はできないよ」という返事が返ってきた。
パジェロに乗り込むとき、アマリアたちと木陰に座っていたクリスティが、こちらに向けて小さく手を振っているのに気付いた。自分に向けられたものかもわからないのに、将人は大きく手を振り返した。
社宅に戻ると、ちょうどサンがダイニングテーブルに料理を並べ終えたところだった。分厚い豚肉の煮込み、ハーブとスパイスがたっぷりかかったミルクフィッシュのグリル、具のたくさん入ったピラフ。どれもおいしくて、毎度のことながら、将人はついつい食べ過ぎてしまう。
将人は、こうして毎日、同じ時間に同じ仲間と昼食を共にしていることが嬉しくて仕方なかった。この仕事が決まる前は、用がなければ昼まで寝ているのが常で、昼に家でひとり飯を食べながら、世間から隔離されたような、寂しくて情けない気分を味わっていたのだ。
「ショウ、何をまたにやにやしてるんだ? あ、わかったぞ、クリスティのこと考えてたんだな。手を振ってもらっただけで顔を真っ赤にするなんて、君もまだまだ幼いな」
アルマンがしたり顔で言った。
「見てたの?」将人は苦笑いした。「だけどそういう君だって、暇さえあればアマリアを見つめてるじゃないか」
「彼女が先に僕を見つめてくるから、僕も見つめ返しただけの話さ」
やれやれ、と将人は首を振った。
「何だ、またアマリアの話か?」
辰三が身を乗り出してきた。アマリアの名が会話に出ると、辰三が妙に過敏に反応する。
「アルマンがノノイにやきもちを焼いているんです。一緒に干物を干してるから」
辰三が「ばかだなぁ」と大笑いすると、アルマンが将人の胸に指を付き立てた。
「ちょっとショウ、タツミさんに何を話したんだ? 日本語は禁止だぞ、このテーブルでは今日から日本語禁止!」
「そんなこと言ったら、ショウがタツミさんに通訳できなくなるだろ」
ライアンが笑いながら指摘する。
アルマンは不満そうに「それはそうだけど」と答えた。
「庫内温度は安定しているのか?」
何の脈略もなく、レックスがそう聞いた。
アルマンがさっと背筋を伸ばして答える。
「開け閉めの回数が多くなると、二度から三度上昇しますが、おおむね安定しています。送風ファンの霜つきもありません」
それを聞いて、辰三もほっとした顔になった。
「タツミさん、お願いがあるんですが――」アルマンは辰三に頭を下げてから、将人に、通訳してくれ、というように目配せしてきた。「冷凍装置と発電機の管理が僕の仕事ですが、今は両方とも少しくらいなら目を離しても良いくらいに安定しています。もし加工場の作業でお手伝いできることがあったら、ぜひやらせていただけませんか? 例えばその、干物を干すとか――」
「だったら、フレークアイスを運んでるアルバートを手伝ってやれよ」
ライアンはそう言ってから大笑いした。
「僕は力がないから足手まといになるだけだよ。やっぱりそういう力仕事こそ、ノノイにやらせるべきで――」
「それなら加工係に混ざって出刃の使い方を覚えたらどうだ。君は自分がAMPミナモトの社員だってことを忘れたわけではあるまい? サンパブロでは、UPで経営学を専攻していたカルロが、日本食の調理法を必死で学んでいるんだ。君だって、機械以外に何かしら鮮魚加工の知識を身につけるべきだと思うが」
レックスが、真剣にもおどけているようにも見える顔で言った。
「そうですよレックスさん、僕の言いたいのはまさにそれなんです。つまり、まずは干物の干し方から学んでみようと思ったんです」
言って、アルマンはしてやったり、という顔になった。辰三は大笑いしてから、あきれるように首を振った。
「でもなぁ、もしアルマンに作業を手伝わせてるのが関内さんにバレたら、俺やレックスが怒られるんだぞ」
「絶対に内緒にしますから!」
アルマンが必死の形相で訴えた。
ライアンはもはや腹を抱えて笑っている。
「やっぱり手伝わせるわけにはいきませんよ。アルマンはセキウチさんのスパイだということを、今の今まですっかり忘れていました」
レックスが言うと、テーブルにいた全員が大笑いした。
昼食を済ませると、五人はリビングのソファーに座って、チャンネルが古いダイヤル式の、ノイズだらけのテレビで、陽気なバラエティー番組を見て過ごした。司会者の若い男二人組は、タガログ語と英語を場面によって使い分けている。
CMに入る前に、司会者と観客が、『ペラ・オ・バヨン』と声を合わせて言うところが、日本の『いいとも』にそっくりだった。
番組中の会話はほとんどがタガログ語なので、将人にはまったく理解できなかったが、たくさんの水着の女性が、これでもか、というほど腰を振ったりするので、映像を見ているだけでも面白かった。辰三も、まんざらでもないといった顔で画面に見入っていた。
加工場の午後の作業も順調に進んだ。ライアンが買ってきた透明ビニールのエプロンが、加工係と梱包係の全員に各一枚ずつ配られた。そのおかげかはわからないが、生産スピードが午前中よりも向上した。
干し台の上に並んで置かれた干し網の上には、ヒラキがぎっしりと敷き詰められている。すでに二百枚ほどが袋詰めにされた。
予想をはるかに超える作業効率に、辰三は「いやぁ、びっくりだ」と感心しきりだ。
フライ用を担当している〈選抜組〉のスピードもかなりのもので、一パック十八匹入りのビニールパックが十二個で一ロットだが、午後も早い時間にそれが二ロットできた。
辰三の後ろで加工場の作業風景をじっと見つめていたレックスが、将人を呼んで肩に手をかけた。
「やはり日本の加工法は繊細だよ。干物はフィリピンでも作るんだが、塩をたっぷりと振って、二日でも三日でも干し続けるんだ。雨が降れば、味が薄まらないようにとまた塩をどっさり振りかけたまま、また太陽が出るまでそのままにしておく。フィリピンの干し網は干し代と一体化しているから、雨が降ったからといって簡単には取り込めないんだ。それに比べて、タツミさんの設計したあの干し網は、台から取り外すことができるだろ。あれなら、雨が降ったら網ごと簡単に屋内へ取り込めるし、干し終わったものは網ごと入れ替えられるから干すのと取り込みが同時に出来る。生産性は倍になるんだ。まったく、〈ジャパニーズ・スタンダード〉というやつには、つくづく感心させられるよ」
将人がレックスの言葉を伝えると、辰三が照れくさそうに微笑んだ。
「俺だって、フィリピン人の真面目で、もの覚えが早くて、器用なとろこには、とことんびっくりさせられたよ。今日なんて、こうしてぼおっとながめてるだけで、口出す必要がねぇもの」
「タツミさんの技術と、この従業員たち、そしてブエナスエルテ社は、そう遠くない未来に、フィリピン中に名の知れ渡る存在になるかもしれませんよ」
レックスが差し出した手を、辰三が強く握り返した。
五時になり、終業のホイッスルが鳴り響いた。
リンドンは、加工係と梱包係に一人ずつ声をかけながら、名簿にしるしをつけた。さしずめ、手書きのタイムカード、といったところだろう。
八時間も立ちっぱなしで魚をさばき続けていたというのに、加工係たちの誰ひとり疲れた顔をしている者はいなかった。みな、洗い場で手を洗い、汚れたビニールエプロンを水で流し、サンダル履きの者は足もすすぎ、血やうろこで汚れてしまった服のことなど気にする様子もなく、にこやかに加工場から去っていく。男たちの中には、加工場から表の道路まで、全速力でかけっこする者すらいた。
「あのおばちゃんたち、どこまで帰るんだろうな」
辰三は、アレンの目抜き通りとアジアンハイウェイが交差する三叉路のバス停に向かって歩いていく数人の女性加工係たちを見ていた。
ちょうど通りかかったライアンにその疑問をぶつけてみた。
「彼女たちは、ここから三十キロくらい離れた町から通ってるんだ。求人広告の看板を出したなかで一番遠い町だよ」
「そんなに遠くから毎日通うんじゃ大変だね」
「五時半に家を出て、ジープニーかトライシクルをつかまえるって話だよ。でも日系企業で働けることになって、きっと町中でも羨望の的だろうから、きっと早起きも苦にならないはずさ」
将人はラウルの言葉を思い出した――妻や息子たちは、私が日本人社長の運転手をしていることを、誇りに思っています――。
言われてみれば、加工作業にはまるで場違いな彼女たちの服装は、この仕事に対する誇りの表れなのかもしれない。
「ところでさ、加工場の従業員の給料っていくらなんだ?」
辰三が聞いた。
「百五十ペソだよ」ライアンは笑いながら答えた。「一日で百五十ペソ。彼女たちは、たぶん交通費に三十ペソは使うだろうから、手取りは百ペソちょっとになってしまうけど、それでもサマールの住民にしたらずいぶんな額だよ」
百五十ペソ、と聞いて将人が思い出したのは、〈ランドマーク〉の地下のスーパーで買った、ピーナッツのはちみつ漬けだった。あの菓子がひと瓶、百五十ペソだった。
辰三も、嘘だろ、というように首を振っている。
「サマールの標準な日給が百五十ペソなのです。しかしブエナスエルテ社の雇用条件が桁違いに優れているのは、彼らに長期雇用を約束していることなんですよ。つい先週まで、サマールの田舎町で、その日暮らしの生活を送っていた彼らが、これからは毎月、安定した収入を得るんです。彼らの金銭感覚も大きく変わるでしょうね」
その通りだな、と将人は納得した。不安定な収入がどれほど生活に制限をもたらすか、またその逆がどれほど生活を豊かにするか、将人は身に沁みて知っている。
「だから、もし仮にタツミさんが愛人を作ろうと思えば――」ライアンが、アジアンハイウェイを南に向って歩いていくアマリア、クリスティ、イザベラの三人の背中に向けて、思わせぶりに顎をしゃくった。「――それほど難しいことではないんですよ」
将人がためらいがちに通訳すると、辰三はアマリアの背中を見つめて腕組みし「そういうもんなのか」と真顔で漏らした。
「ショウも同じさ」
ライアンが言った。
「何が?」
「クリスティだよ」
「クリスティがどうしたって?」
「まったくもう」ライアンが苦笑いしながら首を振った。「君の収入があれば、彼女を愛人にできる、ってことさ」
とんでもない、と言いかけて、将人ははっと気づいた。愛人ということはつまり――。
「彼女、結婚してるの?」
「既婚で子供もいるよ」
将人はがっかりした気持ちが顔に出ないように努めた。
「でもね、例えば背がものすごく高くてハンサムな日本人のショウから『愛人になってくれ』と二千ペソ、ぽんと渡されたとする。彼女は一日八時間働いても百五十ペソだろ。彼女が果たしてその誘惑に勝てると思うかい?」
勝てるに決まってるだろ、と言い返しながらも、将人は、一糸まとわぬ姿でベッドに横たわり、体をすり寄せてくるクリスティを想像して、体中が火照るのを感じた。
「いいかいショウ、サマールでは十代で子供を産むのは決してめずらしい事じゃないんだ。ちなみに、アマリアには三歳の男の子、クリスティには五歳の男の子と二歳の女の子、それにイザベラには二歳の――」
「イザベラまで?」
将人は目を瞬いた。イザベラは確か二十歳だと聞いた。
ライアンが大笑いした。
「そう、イザベラにも二歳の男の子がいるよ。先進国日本から来たショウがショックを受けるのもわかるけど、これがありのままのフィリピンの姿なんだ。アルマンを見てごらんよ、アマリアに子供がいることを気にするどころか、旦那がいないと聞いて最高のチャンスだと大喜びしているくらいなんだから」
アマリアのどことなく悲しげな表情に比べて、クリスティとイザベラの、柔らかく暖かい微笑みは、彼女たちが幸せな家庭を築いている何よりの証拠だと将人は思った。いずれにせよ、クリスティに対して抱き始めていた淡い恋心は、すぐにも吹き消さねばならない。
「金で誰かの心を買ったりするのは好きじゃないんだ」
将人は言った。
ライアンが肩をすくめた。
「ショウがそう言うのなら仕方がないね。そういえば、今夜、ブエナスエルテ社からショウに給料が支払われるんだけどさ」
「給料?」
「聞いてるでしょ、一万ペソ。うちの会社から支給するって」
ライアンの言う給料とは、つまり現地手当てのことだと将人は思い至った。雇用契約にあった現地手当ての一万ペソというのは、辰三からときおり渡される交友費と同じなのだと思い込んでいた。
「関内さんからならともかく、まさかブエナスエルテ社から給料をもらうとは、考えてもみなかったよ」
「社宅の家賃、サンの給料、食事代なんかも、全部、関内さんとの取り決めで、うちの会社が負担しているんだ」
将人は、レックスが関内に抱く不満のひとつが理解できた気がした。ブエナスエルテ社が約一ヶ月と見込んで予算を組み、手配した辰三のサマール滞在が、関内が辰三をサンパブロに引き止めたために、一週間ほど短縮されてしまったのだ。辰三は本来、到着日と帰国日を除いてサンパブロに滞在する予定はなかったと言っていた。つまり、関内はAMPミナモトで辰三に調理指導させるために、日程を勝手に――もしかすると確信犯的に――変更したのだ。
マカティのオフィスで、辰三の滞在予定の詳細を決めたとき、レックスが異様に不機嫌だったのも、おそらくそのせいなのだろう。ひょっとすると、フィリピンへの出発日がなかなか決まらず、一ヶ月近く引き伸ばされたのも、TTCの社員食堂での試験販売に辰三を引っ張り出すための策略だったのではないか、とすら思えてくる。
「ショウ、そんな難しい顔しないでよ。君にとっては、一ヶ月で一万ペソというのは少ないかもしれないけど、僕らにしたらすごい大金なんだからさ」
「あ、違う違う、そういう意味じゃなくて――」はっと我に返り、将人は慌てて笑みを繕った。「――ブエナスエルテ社から給料をもらうのは複雑な気持ちなんだよ。僕は君たちも、君たちの会社も好きだからさ」
ライアンが将人の肩に手をかけた。
「ショウにはそれだけの価値があるんだ。僕も、父さんも、君には喜んで給料を払うよ」
レックスも、将人に向けて「そうだとも」と頷いて見せた。
夕食が終わった後、将人はライアンから、千ペソ札が十枚入った封筒を受け取った。
「ショウは大金持ちだ、女もたくさん寄ってくるぞ、くそ、うらやましいな」
言って、アルマンは疲れた顔でため息をついた。
「金持ちなんていわれたのは生まれて初めてだよ。僕が日本でどんな生活してるのか、君に見せられないのが悔しいね」
将人は言い返したが、アルマンはうなだれたままだった。
「僕ですらこんなにもらってないよ」
ライアンがおどけるように言った。
「ブエナスエルテ社のお金だから、大切に使うつもりさ。できれば使わずに日本円に両替して、帰国してからの生活費の足しにしたいな」言いながら、将人はふと思いついた。「そうだ、いっそのこと、ブエナスエルテ社が僕を雇ってくれればいいじゃないか。月給がいくらだろうと、僕は喜んで働かせてもらうよ」
「それは良い考えかもしれない。ショウがうちの会社にいれば、ミナモト水産と直接やりとりができる。でもセキウチさんが黙っていないだろうね。また機会を見て父さんに話してみるよ」
冗談のつもりで言ったが、よくよく考えてみれば、帰国した後、もしミナモト水産から正社員登用の話がなければ、また憂鬱な仕事探しの日々が続くことになる。今回の海外派遣通訳で、履歴書の職務経歴欄が多少にぎやかになるとはいえ、それが何かの保障になるわけではない。それならば、たとえ月給一万ペソでも、このまま何年かサマールで働くのも悪くないなと将人は本気で思った。フィリピンの現地企業で数年間働いたという経歴は、将来、東南アジアと取引のある日本企業に求職する際に相当なアピール材料になるだろうし、二年もあれば、タガログ語も日常会話程度まではしゃべれるようになるだろうと思えた。
「君たちとこれからもずっと一緒に働けたら、きっと楽しいだろうな」
将人は言って微笑んだ。
ライアンも、アルマンも、にこやかに頷いた。
将人は、フィリピンにやってくる前の自分を思い出した――無職同然、恋人とは別れたばかり、実家暮らしで生活費は親に頼る始末、用事といえばバスケサークルの練習だけ――。
人生を転換させるとすれば、これほど良い時期がほかにあるだろうか。ミナモト水産が、ブエナスエルテ社またはAMPミナモトの現地駐在員として、将来的に将人を雇うということも考えられる。そうなれば、加工係たちと同様、将人も今までの不安定な生活に最高のピリオドを打てるだろう。フリーの通訳としての夢はいったんあきらめることになるが、この場合、それは前向きな決断で、決して妥協の産物というわけではない。
「一万ペソあったら、アマリアと、彼女の息子まで養ってやれるのになあ」
アルマンが、将人の手にした封筒を見つめてつぶやいた。
将人は頭の中で大まかに計算してみた。ミナモト水産から支払われる月給十万円と、ブエナスエルテ社から支払われる現地手当一万ペソを合わせて、約四万ペソ。
一日八時間、週休一日で働く加工係たちの月収が、約三千六百ペソ。
つまり将人は、彼らのざっと十一倍の収入があることになる。
〈サマールでは、僕は金持ちらしい〉
その日の日記を、将人はその言葉で締めくくった。
次へ
トップへ
© Rakuten Group, Inc.