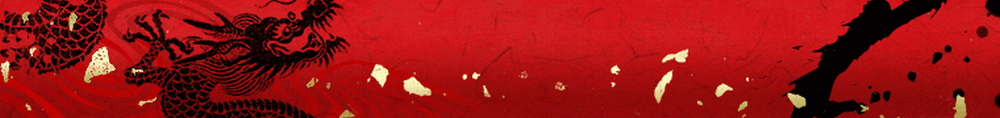『橋の下の彼女』(46)-1
1999年7月31日(土)フィリピン・アンティポロ――サンパブロ
サマール島を離れてから、今日が三日目になる。
夕暮れ時に蚊や蚋に刺されることも、真夜中にゴキブリが顔の上をはうこともなくなった。シャワーは湯が出るし、トイレには水桶などなくロール紙が常備されている。食事は朝昼晩と日本食で、ティーバッグとはいえ、緑茶も添えられる。朝出した洗濯物は、夕方にはアイロンがけされて戻ってくる。
サンパブロでは、それがごく当たり前の生活だった。
将人は、四人掛けのテーブルにひとりで座り、カフェテリアのオープンテラスの先に広がる、良く手入れされた緑の芝を眺めていた。テーブルの上には、二百ペソもするベーコンエッグの乗った皿がある。これでも、メニューの中から一番安いものを選んだのだ。
Gショックを見た。午後二時五十分。意味も無く、〈G〉のボタンを押して液晶を青色に光らせる。あと十分すれば、加工場は三時の休憩だ。昨日のアルマンの定時連絡によれば、加工場の作業は、辰三抜きでも滞りなく進んでいるという。明日は日曜、週に一度の休みだ。みな、張り切って出刃を動かしているに違いない。
そういえば、伝言少年にさよならを言えなかった。娼婦に首っ丈になった背の高い日本人が、また何か用を頼むかもしれないと、今日もブエナスエルテ社の表の道路をうろついているかもしれない。
将人は今、〈バレー・ゴルフクラブ〉というゴルフ場にいる。昨日の晩、「一緒にやるかね」と関内に誘われたが、即答で断った。その報復かどうかはわからないが、今日はラウルと一緒に買い物に行く自由は与えられず、代わりに、ゴルフ場のクラブハウスで一日を過ごすという自由を――もしくは罰を――与えられた。
朝から七時間以上、将人はテラスの同じ席に座りっぱなしだった。気の毒そうな顔でミネラルウォーターを運んでくる給仕の顔も何度か入れ替わった。関内から好きなだけ飲み食いして良いと言われてはいたが、加工場の従業員たちの日給よりもずっと高い料理を、何品も頼む気にはとてもなれなかった。
朝八時に関内と辰三がコースに出て行くと、彼らが十八ホール回って帰って来るまで何をして過ごせばいいかと、初めのうちは途方に暮れていた。しかし、手持ち無沙汰から広げた手帳のカレンダーとにらめっこしているうちに、日付けと曜日を照らし合わせると、それぞれの日に何が起きたかを、鮮明に思い出せることに気が付いた。昔から、将人は記憶力がひと一倍良かった。
それならばと、しばらく書いていなかった日記を、一日ずつ思い出しながら、遡って書いてみることにした。結果は上出来だった。目の前のスクリーンに映し出されたものを、ただ文章にしていくだけで良かった。書き上がったものは、誰が読んでも、毎日欠かさず日記をつけていたと思うに違いないというほどの出来ばえだった。
ただ、サンパブロに戻ってからのことは、到着した日の長い晩酌のことを書いている途中で、書く気を失った。伝えたい、書き残したい、という気持ちが、まるで起きなかったのだ。
日記を書き終えて書類カバンにしまったときには、十二時を過ぎていた。辰三たちはどこか別の場所で昼食を取ったのか、昼にも姿を見せることはなかった。
午後になって、将人はあたりをうかがいながら、茶色の大型封筒をそっと書類カバンから取り出した。中には、関内の資金不正流用の全容がびっしりと記された五枚の文書のほか、領収証や入金伝票、銀行口座利用明細、納税証明書などのコピーが十枚ほど入っている。とても手書きで翻訳できる量ではないので、本格的な翻訳は日本に帰ってからワープロソフトを使って行うことにして、フィリピンにいる間に、使われている専門用語で意味がわからないものをざっと書き出しておくことにした。
日本の出資者たちから集めた資金がGFCにどう流れていったか、そして、その過程でどんな偽装工作が行われていたのか、ざっと目を通して、おおよそは理解できた。だが、持ち株会社、合弁会社、共同出資などの違い、また、出資金の所有権が現在誰にあるのか、どこからどこまでがプロジェクトの範囲で、どこからが不正流用または横領と見なすべき行為なのかという根拠を説明した部分はかなり難しく、しかしそれこそが、レックスが日本の出資者たちに伝えようとしている、告発の核となる部分だった。
思い込みで偏った翻訳をすれば、逆に関内から名誉毀損で訴えられることにもなりかねない。将人が手にしている書類は、訴訟が起こされれば、裁判所に提出される証拠になりうる類のものなのだ。
帰国したら、さっそく初心者向けの株や投資に関する参考書を買い込んで、証拠書類の内容を十分に理解した上で翻訳を始めようと、将人は決めていた。
大型封筒をカバンに戻し、まだ手をつけていなかったベーコンエッグにナイフを入れ、半分に切った。百ペソの価値がある半切れにフォークを突き刺し、口の中に放り込む。タタイ・アナックのハンガーガーがいくらだったか、はっきりと思い出せなかったが――一ひとつだけ買ったことはなかったからだ――あっちの方がよっぽど美味いと思った。確か、二十ペソか三十ペソ、ひょっとすると十五ペソくらいだったかもしれない。日本でも地方によって物価にばらつきはあるが、フィリピンのそれは比較にならないほど極端だ。ゲストハウスのダイニングテーブルの上に置いてある、ピーナッツのはちみつ漬けのボトルが百五十ペソ。工場の従業員たちの日給と同じ額だ。
実際、〈ミツオカプロジェクト〉は、日本基準の品質で既存商品と差別化を図るというよりも、フィリピン国内の賃金格差を利用して成り立っていると言えるのかもしれない。将人が頬張っているベーコンエッグの料金二百ペソを払うのは関内だが、その金が、あのブエナスエルテ社の従業員たちからもたらされたものかもしれないと考えると、胃をえぐるような空腹感は鈍痛に変わり、食欲は消え失せる。
給仕を呼んで、ミネラルウォーターを頼んだ。コップに入った水には料金がかからないことは、朝一番で確認してあった。
サマールからサンパブロに戻って以来、将人の頭の中に、今までの人生では考えたことも無いような数々の疑問が渦巻くようになった。
人を雇い、雇われるとはどういうことなのか。賃金とは何か。仕事とは何か。金とは何か。
加工場の裏手に広がる水田の先に茂っているヤシ林は、どう見ても原生林だった。そこに育つ膨大な数のヤシの実の全てが、マニラかどこかの都市にいる一人の地主の所有物だと、従業員の誰かが言っていた。アレンで生まれ、アレンに住み、アレンで死んでいくあの人々たちは、しかしその原生林が育んだ果実を、金を支払わなければ食することができない。
アレンの人々は、生きるために、トライシクルをこぎ、ジープニーを走らせ、服を売り、料理し、洗濯し、魚をさばき――あるいは体を売って――わずかな金を稼ぐ。
所有とは何なのか。一生かかっても消費できないほどのものを、それが自然によって生み出されたにもかかわらず、たったひとりの人間が、なぜ自分のものだと主張することができるのか。また、それに正当性を与えているものは何なのか。人はなぜ、そこまで強欲になれるのか――。
「お待たせしました、サー」すっかり顔なじみになった給仕が、ミネラルウォーターの入ったグラスを持ってきた。「今日はいつもより長いですね。もう三時ですから、ミスター・セキウチもそろそろホールアウトされるとは思いますが」
この若い男の給仕に限らず、どの給仕も、みな将人が関内の連れであることを、告げる前から知っていた。
「関内さんはよくここに来るの?」
「そうですね、私は毎日働いているわけではないのですが、それでも最近は週に三日はお見かけしますよ。どれだけ働いても、私にはそんな優雅な暮らし、一生できないでしょう。うらやましい限りです」
給仕は額に手を当てて首を振った。グラスをテーブルに置くと、ごゆっくり、と言って去っていった。
フィリピンの国土の半分以上が、たった数十人の地主のものだと聞いた。そんな上層階級の支配を武力で打ち倒そうとする革命組織が今でもいくつか存在していると、日本を発つ前に読んだ本に書いてあった。ホセ・リサールはスペインからの独立運動を主導して処刑された。彼は今でも、フィリピンで英雄視されている。
だが、今のフィリピンはどうだろう。スペイン、日本、アメリカの植民地支配を退けて独立を勝ち取ってきたこの国は、結局、追い出した外国人から取り上げた富や地位は、上層階級のごく一部の人々に移っただけで、国としての構造は、植民地時代と何ら変わらないのではないだろうか。いや、むしろ同国民が同じフィリピン人たちから植民地同様に搾取するのだから、さらに悪くなった、と言うべきなのかもしれない。
ブルジョワジー、プロレタリアート、階級闘争、暴力革命――。
そんな時代遅れの言葉が、続けざまに頭に浮かんでくる。まるで、どこかの大学の校舎の屋上から、機動隊に向って火炎瓶を投げる団魂世代の共産主義者になったような気分がして、将人は慌ててかぶりを振った。少なくとも食い物には困らなかったあの時代の日本で、そんな革命運動の真似事をしていた連中は、単に金持ちがうらやましかっただけだとしか思えない。
だが、フィリピンには本物の貧困がある。
越えられない階級の壁が、今も確かに存在している。
それこそ、暴力革命でもおこさない限りは崩せない壁が――。
たった一ヶ月ほどの滞在で、将人はそれを、身をもって感じ取っていた。
「おう、待たせたな」
はっと振り返ると、辰三が立っていた。シャワーを浴びてきたらしく、タオルで濡れた髪を拭っている。
「そんな風にぼけっと考え事なんてしてねぇで、酒でも飲んでりゃよかったのに。あ、そうかそうか、さてはアレンの彼女のことでも考えてたんだな。そんなに好きなら、電話の一本でもかけてやりゃいい――おっと、そういやあっちには電話がなかったな、こりゃしっけい」
そんなことを言いながら、辰三は給仕を呼び寄せてサンミゲルを頼んだ。
ティサイは今、何をしているんだろう――そう考えたら、なんだか彼女を置き去りにしてきたような気がして、胸が締め付けられるように痛んだ。
「関内さんはどうしたんです?」
「まだシャワー浴びてるよ。いい年して、けっこうきれい好きなんだな、あの人は。体洗う暇があったら、ゴルフの腕前をあげて欲しいもんだ」
どうやら今日のコンペは辰三が勝ったようだ。
給仕が、水滴をまとったサンミゲルのビンとグラスを二つ運んできた。
「いよいよ明日だな」
辰三はサンミゲルをビンのまますすり上げた。
「明日ですね」
将人たちは、明日の日曜、午後四時三十分発の飛行機で、日本へ帰国することになっている。
「いよいよフィリピン、いよいよサマール、いよいよサンパブロ。いよいよを何度も繰り返したけど、そんな〈いよいよ〉も、これで最後だな」
言って、辰三は大笑いした。将人もつられて笑った。
「長い長い晩酌も、今夜で〈いよいよ〉最後ですよ」
「その〈いよいよ〉が、一番嬉しいかもしれねぇな」
笑おうとしたところで、濡れた白髪をタオルで拭いながら、こちらに歩いてくる関内の姿が目に入った。
席に着くと、関内はここでも、将人を無視して辰三と話しを始めた。話題がアレンでのことになると、辰三はときおり、将人を指差しながら、「それがこいつったらさ――」などと思い出話を面白おかしく語ったり、「よくやってましたよ、こいつは」などと褒めてくれるのだが、関内はそのたびに、将人を一瞥して、「へえ、そうなんだ」とまったく感情のこもっていない口調で言っては、すぐ話題を変えた。
関内のそんな態度にいい加減うんざりして、トイレに立ったあと、将人は別の空いているテーブルにひとりで座った。
それから関内は一時間ほども、昨晩の晩酌で聞いたのとまったく同じ話を、辰三相手に数回繰り返した。
「あっちのテーブルは、あの彼が払うから」
ようやく席を立った関内が給仕にそう言ったのが聞こえた。
テーブルを移ってから、将人はミネラルウォーターしか飲んでいなかった。だが、給仕はだいたいの状況を把握していたらしく、気を使って〈0ペソ〉と書かれた伝票を持ってきてくれた。
給仕に十ペソのチップを渡して握手を交わしたとき、関内の舌打ちが聞こえた。
次へ
トップへ
© Rakuten Group, Inc.