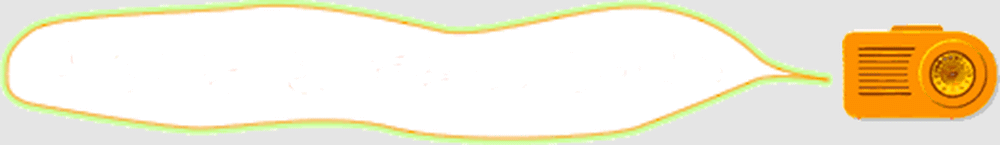映画の品格~硫黄島からの手紙
お年を召した夫婦連れが目立つ中、僕も開演を待つ列に並んだ。
映画は、「父親たちの星条旗」と同じく、静かに始まる。
だが、「父親たちの星条旗」が、戦後の視点から戦争の意味を問い直す構成になっていたのとは逆に、この映画では、篭城のための準備から悲惨な敗北までストレートに進んでゆく。モグラのように潜むトンネルの中で、兵士たちの想いは家族へ、あるいは戦いの意味へと広がってゆくのである。
「父親たちの星条旗」におけるアメリカ軍上陸の大物量に対して、なんと悲惨なことであろう。僕たちはすでに、第一部によって、どれほどの戦車が、アメリカ兵が、押し寄せてくるのかを知っている。とても相手になるまいに、けなげに塹壕を掘っている日本兵たちの姿に涙が出てきた。
まず賞賛されるべきは、二宮和也の演技であろう。
僕はこの童顔の青年のことはよく知らない。
もちろん「嵐」の一員であることは知っているが、この人の演技など観た事もないし興味もない。
公開記念の記者会見でも、ひとりリラックスしていて、なんだかいい感じを持っていなかった。
ところが、観てみなければわからないもので、栗林(渡辺謙)・西(伊原剛志)という二人の仕官が、あまりにもりっぱに描かれていて(実際りっぱだったんだろうと思う)やや違和感を持つが、この、妻と生まれたばかりの子供を持つパン屋職人こそが、この大作に肉体と心を与えている。
誰のために戦い、死んでいこうとしているのか。国のためか家族のためか、それとも戦争で死んでゆくことなど何の意味もないのか。妻と子供のことだけを心配しているこの頼りない日本兵・西郷こそが、この映画のテーマを具現する。
僕はもう一度、「父親たちの星条旗」を観ようと思う。
雨あられと撃ち込まれる擂鉢山への砲撃。あの山肌のどこかに、西郷や清水(加瀬亮)が息を潜めて震えているのだと考えると、僕の胸は切り裂かれるにちがいない。
戦争の意味を、戦闘をまるごと描くことによって映し出そうという試みは、キューブリックが「突撃」で、コッポラが「地獄の黙示録」でやろうとして失敗した。
「トラ・トラ・トラ」や「史上最大の作戦」や「プライベート・ライアン」は、実際の戦争における1エピソードを再現してみせるスペクタクルである(映画が見世物でもある以上、もちろんそういう趣旨の映画にも意味はある)。「プライベート・ライアン」もそういう趣旨で作られていると僕は理解する。
そしてこの映画は、ついに「戦争」を描く事に成功したのではないかという満足感を与えてくれる。
ついに読まれることのなかった手紙の数々から、多くの呟きがあふれ出るラストシーン(涙を止めることができない)に続き、DIRECTED BY CLINT EASTWOOD とタイトルが出る。そうなのだ。観ている間は忘れているが、この映画はアメリカ映画であり、クリント・イーストウッドという、アメリカ人が撮った映画なのだ。
「天皇陛下、万歳」と戦争映画の中で叫ばれる時、そこにはいつも恥ずかしさがつきまとう。「トラ・トラ・トラ」では、アメリカ版ではカットされたはずだ。
しかしこの映画の中での、しぼりだすような「天皇陛下、万歳」は悲痛だ。初めて聞いた悲痛な「天皇陛下、万歳」が、クリント・イーストウッドという、自分が好きで好きでたまらない監督の映画であったことに僕は感動する。
戦争はゲームではないことを、この偏見という言葉を持たない監督は知っている。勝ち負けなどどうでもいいのだ。「硫黄島」というちっぽけな島を奪い合うことに意味はないが、そこに流された多くの血には意味がある。意味があったことを忘れてはならない。そうイーストウッドは言いたいのだろう。だからこそ、「父親たちの星条旗」も「硫黄島からの手紙」も、オープニングは現在なのである。
初めて「品格」を持った戦争映画に出会えて僕は幸せだ。
映画における「品格」については、明日また書きたいと思う。
若い人たちも多く観にきていた。
なんだかとても嬉しいことであった。
© Rakuten Group, Inc.