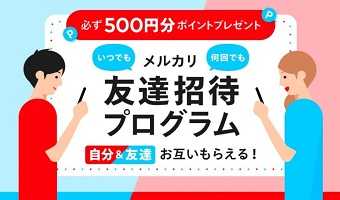藤井聡先生の犬のしつけ教室
2004年2月11日
保健所主催「犬のしつけ教室」に参加しました。無料。
スライドでの講演で、ここには映像がないのであくまで覚書です。聞き取りメモなので誤解もあるかもしれません。正確には先生の著書を文末に載せます。
『スーコールマンの絵。「狼とインディアン。」』
インディアンの村にのどに大きな骨を詰まらせた犬がやせ細ってやってきた。村人はその骨をとってあげた。犬は、何食わぬ顔で去っていった。そして冬が来た。雪が降り、村に食べ物がなく、村人が餓死寸前に見舞われたとき、その犬がやってきて、殺したトナカイのところに案内したという神話の絵である。この神話の話は現実に有ったのではないか。人と動物の絆というのはそういうものである。
『縄文時代の犬骨』
この骨の横に人骨もあった。犬は人と一緒に埋葬されていた。決して、貝塚に犬の骨は捨ててない。この時代は一緒に狩猟。人間との絆があった。
その縄文犬とその時代に大陸から来た犬が日本犬の祖先となった。弥生時代には入り狩猟せず、権力戦いの時代になって犬との絆が薄まってきた。
『補助犬のステッカー』
現在、補助犬入場可のステッカーが各地で張られている。法律で認められた。
『2002年12月21日号の科学雑誌サイエンスの表紙を犬が飾る。』
その日の朝刊にも「サイエンスの表紙に犬」と1面の隅に載った。
それは犬のルーツについて。世界中の犬の遺伝子配列を調べた研究。その結果、共通の遺伝子が見つかる。犬のルーツは15000年前。東アジア。
そして、犬は間違いなく狼。
『公認犬種を10のグループにわけ5グループはすべて日本原産。』
スピッツアンドプリミティルという項目がある。(原始的)日本の犬は狼に近い。
『犬の各時期』
新生時期 生後~2週間
過渡期 2週間~
社会化期 4週間~12週例
○○期(聞き逃しました。)
新生時期・・・母親は股の間をなめて排泄を促す。人と犬の違いはここからある。母がなめて処理する。食糞。当たり前。しかし食糞するには原因がある。
過度期・・・まだ、お尻をなめる。母親はとても面倒を見る。母犬のおっぱい+フード
社会化期・・・脳発達と順応性の時期
シェパード50-60日に耳に刺青。シェパードはしないと血統書登録できない。耳に穴、墨を刷り込む。繁殖者が分かり、飼い主が分かる。災害が有ろうと、無事に戻れる。耳をひっくり返さないと見れないのでよその人が見れる犬にしつけておくのも大事。
『where is john?』 というポスターがある。
世界中共通のマイクロチップを皮下に埋め込む。すぐに愛犬が見つかる。
日本では4分間で一頭が処分されている。ジャパンケンネルクラブに入れるには必要。
『社会化環境順次』
70日目子犬の時期にいかに数多くの人間に接するかが大事。
ユニクロのバックの中に先生の犬「ポチ」
500円のユニクロバックに入れいろんなところに連れて行く。犬にとっては窮屈ではない。むしろ安心。車でも連れて行く。音に慣れる。社会化環境期である。犬にも面会、バックに入れたままでいい。触れなくても見えるだけでよい。
不快なもの恐怖なものにあってもパニックにならない。怖いものになれさせる。
『ペットボトルのカーテン』(しつけ教室の特別なもの)
光ってすごく怖い。飼い主を馬鹿にしている犬の前で飼い主がくぐる。見直す。また、その訓練をする中で少しの刺激にも騒がなくなる。
子どもを見ると追いかける。小さな子どもと早くから接触させておく必要がある。はじめ、じたばたする。そのうち抱きかかえホールドスティール。後ろから体を抱えられると犬は不安。それができる。従属のしるし。子ども順次。子どもになれさせる。
猫順次40日ぐらいの子犬に入れる。しかし猫が犬に順次していないとだめ。そのためには順応しやすい子犬のうちから飼うことが大事。先住者猫。猫の方が上。
『ベルギーの訓練競技会の一場面』
競技を見ている女の子の横に50日くらいの犬が伏せている。何かに気をとられて立ち上がった。すかさずその女の子は子犬をひっくり返して抑える。10秒抑える。何事もなかったように立ち上がって競技を見ている。どうも後ろで女の子の母が指示はしていたようだ。しかしヨーロッパの飼い方。子どもにも教育されている。
日本人社会は、まあいいじゃないか、子どものくせにかわいそうとか。
ヨーローッパではあたり前にしつけ教育している。伝統的に教育。ヨーロッパ人と日本人社会の違い。
『室内で犬の居場所を規制する。』
自由を勝ち取った子犬は好き勝手。規制管理をして始めて犬になる。好き勝手は野生・狼と一緒。
『ユニクロのバックがハウス。』
人間とオラウータンはエサを分ける。しかし、居場所を規制すること大事。食事をしていても、ユニクロバックの中で待っている。
よく病気ですか?なんでじっとしている?と聞かれる。
居場所に安心ができる。
『ハウス』
出てくるので蓋ができるもの。出れなくする。ハウスという習慣が身につく。
『クレートレーニングと排泄管理』
なぜ放し飼いにするか?放し飼いにするから、いろんな悪さ。排泄もあちこちでする。規制の管理をしないから。
『犬とかまくら』のスライド。
犬はかまくらに喜んで入る。なぜか?祖先は横穴。机の下にもぐる。囲まれて安全な居場所が犬は落ち着く。ドイツの訓練場の見学。スライド。見学いすのスタンドの下にもぐりこむ。窮屈でかわいそうではない。犬にとって落ち着ける場所。日中はハウスにしまう練習。トイレのときハウスから出し、排泄する習慣にする。
『しつけハウス』
仕切り板があり、成長とともに面積を広げていく。狭いから動き回らず排泄をしない。ハウスの中は誰も入ってこない。守られるプライベートルーム。散歩とトイレは切り離す。散歩はなぜ行くの?散歩に行かないとストレスがたまると思っている。ちがう。
『犬は習慣性の動物。時間覚を持っている。』
その習慣が取れないときワーワー吼える。そこで従属者的な対応になると「尽くして当たり前」、「要求すれば当たり前」になってしまう。すべて不定期に対応することが必要。
『じっとしてたが動くから排泄したくなる。』
ハウスから出してトイレに定期的に出すと排泄する。えさを食べたら出す。繰り返す。管理しなければ絶対にトイレを覚えない。
『外のトイレ』
洗い流せてよい。しかし、周りから見えないようにする。フェンスの中にさらにフェンスに囲むと安心できるので吼えない。
『一定の居場所から出し入れする。』出されたら排泄の習慣。
『網つきトイレ』下におしっこが落ちる。犬はきれい好き。うんこはすぐにとる。
すべて自由を与えてきた結果、飼い主が困る。
散歩に出たときくらいと甘やかす。綱を張ると余計張る。
≪マーキング≫:相手の尿に尿を引っ掛ける。トイレは自分の家で排泄。一回でもやったら途中で散歩をやめて帰る。そうすると犬は分かる。トイレに行ってから散歩に行く。
≪塀もない玄関前にフェンスのみで犬を飼う。≫
吼えてくれといっているようなもの。家の裏でいい。観葉植物じゃないから、日があたらなくてよい。安心できる場所におくことが大事。
≪分離不安症候群≫
「いってくるね。」は孤独の宣告。宣告しない。分離不安のストレスは大きい。人の出入りに敏感。家族に「ただいま」などの挨拶をし、犬が足元でじゃれても無視。
≪甘ガミ≫
子犬同士はじゃれて、互いに甘ガミ。兄弟で順位を決めている。人の足元を甘ガミ。一ヵ月後にはかじる。そのうち飛びついて支配。家族みんなが怪我。
≪小型犬と枕を共にする場合≫
同じ高さにいるというのは同等の扱い。犬に同等はない。高さで差をつける。ベッドの下で寝かす方がよい。
『先生の犬「あずき」』
いつもは、ベットの下で寝る。時々ベットの上にバスタオルを敷き寝かせる。犬同士の順位がある、優先的に対応。年取ってくると下位の犬がのざばるときがある。あずきも年をとってきた。あずきだけが先生のベットで寝ることができる。あずきの方が上。さすがとほかの犬に分からせる。そのために寝かせる。
『犬に与えられなければならない権利』
1、 犬にはよりよい環境が与えられなければならない。
2、 犬にはよりよい栄養が与えられなければならない。
3、 犬にはよりよい教育が与えられなければならない。
4、 犬にはよりよい繁殖が与えられなければならない。
≪実演≫
公演中ずーと横に座っていたポチ。ゲージに入れた途端に排尿。
訓練校の生徒さんと4匹のワンちゃんモデル登場。人間が右、犬が左側にいる。
犬とウォーキング。人間が止まったら座わる。→この際黙って歩く。座ったらほめる。犬を見ない。しゃべらない。服従の行動が取れたら見る。ほめる。
* 命令しなくても自発的にするようになる。ゆっくり歩くとゆっくり。小走りすると小走り。止まると座る。命令してしゃべればしゃべるほど馬鹿にする。
前に出たがる犬は左回りにまわると常に人間が前になる。人間より遅い犬は右回りに回ると追いついてくる。リードは張らない。張れば張るほど犬はリードを引っ張る。もし張ったら緩める。飼い主は颯爽と歩く。

強制のしつけはしない。叩いたり、力で強制すると仕方なく回避するために服従。強いものには従うが弱いものには従わなくなる。強制的には教えないほうがよい。
『オペラント法』・・・座ったら食べることができる。(ここではレバーのおやつ)念仏のように命令してはいけない。犬が迷う。無言で黙ってやることで集中でき、冷静になれる。伏せたくなる位置にご褒美を持ってくる。
『待て』・・・ご褒美を差し出しては人間がすばやく下がり、犬が動く前に犬の前にもどる。ご褒美をやる。だんだん離れていく。犬は戻ってきてエサをくれる行動を学習し、待っていればご褒美をもらえることを自分の頭で考える。犬が分かってきたら「待て」と声を掛ける。
『ご褒美』・・・最初はご褒美で、分かってきたら「よしよし」だけにする。いつかは食べることできる。と期待する。「そろそろたべれるか?」と。「エーくれないの?」と動きそうなときにご褒美をやる。その時間をだんだん長くする。
『ホールディング』・・・犬は後ろから抱かれるのは不安。マズルコントロールし「天井」「した」「左」「右」「ぐるっと回す」両足を持ってバンザイさせ伏せのポーズ。タッチングへ

『マズルコントロール』・・・獲物を捕まえて、食べる口。犬にとって口は生命線。薬を飲むときも口をあけて薬をいれ、マズルを押さえればごっくんしてしまう。エサに薬を混ぜても嗅覚のよい犬ははじいてしまう。ちゃんと薬を飲んで命を守るためにも必要。
『タッチング』・・・耳・前足・爪の先・尻尾・股の間も触る。耳は掃除もしなくてはならない。爪も切らなくては、足も拭かなくてはならない。苦手なところを触る。こういう犬は診察台に乗っても素直。素直ならよく先生に見てもらえる。長生きできる。

* 注意事項:途中でやめない。家族がいて、お客が来ても電話がかかっても出なくてよい時に行う。気持ちよくて眠くなるくらい落ち着いて行う。途中でやめると「終わること」を期待してしまう。
* 徐々に元に戻す。伏せ・お座りの姿勢。そして人が犬より先に立ちあがる。
Q&A
・ なでる手をかもうとする。→下あごを一瞬ロックする。のどを絞めると余計もがく。
・ シャンプー後ドライヤーをかけたら隅っこにおびえるようになった→音に敏感。ほかの部屋でドライヤーを鳴らし少しづつ音に慣らす。楽しい事にすりかえる。
・ 去勢は?→繁殖は専門家へ。オスは片足上げるようになる前に去勢。健康で長生きするために去勢。性的ストレスから解放させる。1回でも交配すると余計かわいそう。ストレスは寿命に関係。リーダーに立つものは短命。ペーペーの方が長生き。
・ ワンと吼えたら名を呼び違うことに気を向けさせる。それでもだめならあとは天罰。酢と水を半々割って霧吹きで吹く。クシュン。「こら」っと行動対処の「罰」としてやってはだめ。何気なくやる。吼えると嫌な感じになる。と犬に考えさせる。
・ 排泄。飼い主と便の取り合いに→エサを上げたらトイレへ。どうしてもだったらリードをつけておく。定期的に管理し、ハウスから出されたときにする習慣をつける。犬はきれい好き。自分のおしっこの上にはしない。よく、おしっこのにおいを置いておくというがだめ。自分の尿の上にしたくない。目くじら立てない。肛門にマッチ棒1センチ入れると出る。目くじら立てないことが大事。
まったく、目から鱗の講習会でした。
講師:藤井 聡先生
(日本訓練士養成学校教頭。オールドッグセンター全犬種訓練学校責任者。ジャパンケンネルクラブ公認訓練範士、日本警察犬協会公認一等訓練士。日本シェパード犬登録協会公認準師範)
*オールドッグセンター 全犬種訓練学校 日本訓練士養成学校 聴導犬訓練所〒356-0051 埼玉県入間郡大井町亀久保2202
電話0492-62-2201 Fax0492-62-2210
著書:
成美堂書店 『子犬の育て方』780円
青春出版社『しつけの仕方で犬はどんどん賢くなる』
青春出版社『愛犬の困ったカンタン解決する裏ワザ77』
青春出版社『犬がどんどん飼い主を好きになる本』
© Rakuten Group, Inc.