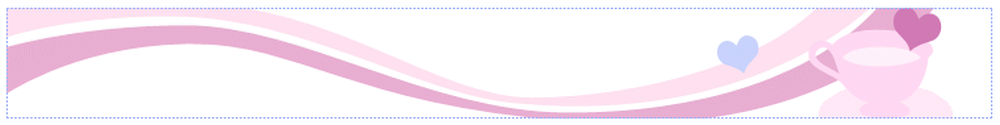2025年06月の記事
全2件 (2件中 1-2件目)
1
-
Why your fingers wrinkle in water (and what it can reveal about your health)
The skin on our fingertips and toes shrivels like prunes when soaked for a few minutes in water. But is this an adaptation that occurred to help us in our evolutionary past? And what can it reveal about your health today?Spend more than a few minutes soaking in a bath or paddling around a swimming pool and your fingers will undergo a dramatic transformation. Where there were once delicate whorls of lightly ridged epidermis, engorged folds of ugly pruned skin will now be found. (BBC News)*****shriel(縮んで皺がよる)prune(~から余分なものを取り除く)*****「脂肪と人類」(イェンヌ・ダムベリ著・久山葉子訳)を読みました。原始の祖先たちは脂肪を求めて狩りをしていた。脂肪は生きるに欠かせぬ存在、命そのものだった。脂肪を欲し求めたことで今のような人間に進化できた。他の霊長類より脂の多い食事だったからこそヒトの脳はこれほど成長できた。昔は脂こそが手に入れたいもので初期の宗教でも神への捧げものだった。今の食肉業界では解体した肉の脂肪含有量を測定し脂肪が多いほど安値がつく。生き延びるために狩りをしていた時代と脂肪のステータスが真逆だ。縄文時代の人が好んだ海洋性脂肪、墓にあった壺の中身は大半が動物性で日常生活の場での発見物は植物性のものが多かった。脂肪はチーズの味にも大きく作用する。脂肪がどれほど大事かは低脂肪のチーズを食べればはっきり感じる。チーズは乳脂肪と水を乳化させたものでたんぱく質が網の様につながっている。肉の場合は脂肪の分布が味や食感を大きく左右する。味わいは脂肪粒子の分布具合によって決まる。脂肪は命を与える、その一方私たちを殺しもする。20世紀贅沢による新しい病気が広まった。脂肪は身体における最も強力な燃料。リパーゼと言う酵素によって分解され脂肪酸とグリセロールに変換され血液に送られる。大豆油は四千年前にはすでに中国で生産されていた。日本や韓国、インドネシアの食文化でも大豆をベースにした食品が欠かせない。たんぱく質と脂肪を高レベルに含むなどと脂肪のことを色々知った。
2025年06月20日
コメント(2)
-
'A home for trees and birds, and also humans': How high-rise forests can transform city life – and make us happier
It's been 10 years since the creation of the first vertical forest, Milan's Bosco Verticale. How has it inspired other buildings – and affected their residents' happiness and health?In 2007, Italian architect Stefano Boeri witnessed the frantic construction of a city in the Dubai desert dominated by energy-wasting skyscrapers covered in glass, ceramic and metal. All these materials, he tells the BBC, "reflected sunlight, generating heat in the air and especially on the urban ground, where pedestrians walked". (BBC News)*****frantic(ものすごい、すばらしい)dominate(~にそびえたつ)*****「20のテーマでよみとく日本建築史」(海野聡著)を読みました。平安時代の建築の変化についてみると寝殿造りについては平安京の貴族邸宅の発掘調査が増加した事で奈良時代の貴族邸宅の特徴を受け継ぎつつ発展していった。寺院建築に関しては浄土教の流行にともなって阿弥陀堂が多く建立された。1180年南都焼き討ちによって東大寺・興福寺の伽藍が灰燼に帰し東大寺の再興で大仏様という新しい様式が持ち込まれた。それ以前からの形式を和様という。禅宋寺院の造営では禅宋様と言う技術が用いられた。和様は奈良時代の律令造営宮司の系譜にあるといえる。和様と名乗りつつも淵源は唐にある。懸造、舞台造などと呼ばれる手法で立てられた清水寺の舞台は有名、懸造は高低差のある地形や崖壁に取りつくように建物が建つ。柱が一貫して通し柱となっている。三仏寺投入堂は平安時代後期、鰐淵寺蔵王堂がある。谷崎潤一郎の陰翳礼讃は建築界では必読本の一冊、書籍内では厠の存在が強調されている。谷崎は日本の建築の中で一番風流に出来ているのは厠であるとも言えなくはないと。京都や奈良の寺院へ行って昔風の薄暗いそして掃除の行き届いた厠へ案内される毎につくづく日本の有難みを感じると。大正ロマンの街並み銀山温泉は三階建ての木造旅館群がガス灯によって照らされる街並みは大正ロマンといわれ明治大正のノスタルジーを感じる。円仁が見た唐の都市の事も書かれている。平安宮において唐の制度を学び取っただけでなく唐長安の含元殿を手本とした建築が二つも存在するなどと色々進化して行ったことを思った。
2025年06月13日
コメント(2)
全2件 (2件中 1-2件目)
1