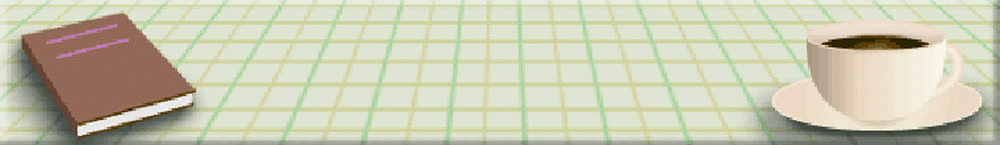時空剣劇ファイターズ(その三)
突然、三人の後方で、内臓が痺れるような振動と共に強烈な閃光が走った。あっと思ったときは、先ほど乗ってきた空飛ぶ円盤は跡形もなく、そこには畳数十枚を跳ね除けてぼっかりと空いた巨大な穴が残っているだけである。
「間違いない、俺たちは囮だ」
杉本の声が聞こえているのか聞こえていないのか、里中は立ち尽くすばかりだった。
その間にも、刀や槍を手にしたサムライたちが、里中らにじわじわとにじり寄ってくる。群れは塊になって、今にも孤軍の三人を津波のように飲み尽くそうとしていた。
「どうします、ってか、どうなっちゃうんですか、僕たち。ひょっとして死ぬの?」と、井吹。
「まあ、どう考えてもそういう運命みたいだな」
「最近、斬られ役してないから、死に方わからないですよ」
会話のピントがずれまくっていた。圧倒的な恐怖を前にして、杉本は茫然自失に近いが、井吹のほうは静かに精神を狂わせているようだった。
井吹は自分の腹をさかんに摩っている。
「こんな野蛮人たちの餌食になるぐらいなら、もはや切腹しかないかも」
「アルミの刀でか?」
と、杉本が突っ込んだところに、突然、舞台でたたらを踏んで見得を切る歌舞伎役者のような形相で、里中が叫んだ。
「うろたえるな、格さん、助さん」
その目はすでに常軌を逸している。
「控えよ!」
と、さらに大音声をあげた。
サムライたちは、その威嚇に一瞬ひるんだ。
「おぬしら、頭が高いのじゃ!」
里中は、ついに人格のコントロールが限界点を越えたようだった。現実の境が吹っ飛んで、役者としての虚構だけが噴出してきたのだろう。
つまり、開き直りだな、と杉本は思った。ならば、長い付き合い。お互いに、職業意識も共通だ。
「ええい、控えおろう、このお方をどなたと心得おる」
杉本も、思わず助さんになりきった。役者本能としての無意識がそうさせた。活路はそこにしかない。
ところが、次の言葉に詰まった。
「水戸黄門はこの時代にはまだ子供ですよ」と、井吹が横で口を挟んだからだ。
歴史の薀蓄はわかるが、利口者の愚直さとしかいいようがない。杉本も本来は、小心者である。その一言で一気に萎えた。
「おぬしら何者だ」
と、群れの中からドスの効いた声が響いた。
あの、その、といっている暇はないのである。
その瞬間に、「……(むにゃむにゃ)である」と、里中が言葉を濁した。群れの端々まで通る声量でありながら、曖昧な発音をする技術はまさに役者の力だとしかいいようがない。
「何者だ」
と、再び相手。
「二度も誰何(すいか)するとは礼を知らぬか」
「しかし……」
「武士に二言はない。とにかくこれ以上、おぬしら雑兵を相手にできぬ」
と、強引に押し通してしまった。
「まず、責任者をここへ呼べ」
「……せき…忍者?」
サムライたちは変な顔をした。
「誰が、忍者と申した、責任者と……?」
「そりゃ、ご隠居。現代人の言葉」
「まさか、彼らダジャレかましてるわけではないでしょうね」
「当たり前じゃないか」
と、里中の後ろで井吹の言葉に杉本は小声で答えた。
「ええい、うっとうしい、責任者でわからねば、家康を呼べと申しておるのだ」
里中はさらに殿中も震えるばかりの大声である。さすがに里中新三郎。時代劇役者は、声と顔面が大きくなければならないという基本を完璧に備えている。助さんと格さん(杉本と井吹)は、自らの危険も忘れ、先輩の芝居に見惚れた。
ひょっとしたら、このまま何とかなるかもしれない。
そういう甘い期待が沸いてきた。
が、それも刹那の希望。里中は少し調子に乗りすぎたかもしれない。
「どけい。わしは家康に用がある。いく手を阻むものは斬り捨てるぞ」
と、サムライの群れを掻き分けようとしたとき、なら、斬ってみよと数人が前へ出てきたのである。
役者など所詮、うわべだけの嘘ぱち。たちまちのうちに三人の化けの皮がはがれた。本気で命のやり取りになると、自然、目の中に恐怖の色が浮かぶ。本来の弱さが出てくるのを止めようがない。
「この狼藉者め」
「ほ、本気でかかってくるつもりか……な…っ」
声が裏返った。
武士とは多くの言葉を操らないもの。腰をかがめ刀を振りかぶった態度で、それが「つもり」ではないことは明瞭だった。
「死ぬかも……」
三人は再び、そう確信した。「助けて」と叫びそうになった。
が、それをしてしまうと、緊張感の糸が完全に切れる。あとは殺戮の波に飲み込まれてしまうだけだ。もっとも、今ここで誰かが助けに来てくれるような状況ではない。
「助さん、格さん。どうやら、これまでじゃな」
「ご隠居!」
「長い間、ありがとう」
里中はいやいや模擬刀を構え、相手を見据えながら呟くようにいった。
井吹は泣いていた。
杉本は真っ赤な顔をして、鼻の穴を膨らました。怒ったように里中を見た。
「最後に里中さんにいいたかったんだが、次に生まれてくるときはサヤカさんを俺にください」
「娘と……? まさか、君」
「キムユウ(木村祐樹…人気トレンディ俳優で杉本とは同期)に彼女を渡してしまったこと、今さら悔やんでも悔やみ足りない。俺、いつも勝負を逃げてた。正々堂々と彼女に気持ちを告げるべきだったんだ」
「そうだったのか、近くにいながら気づかぬ私もいけなかった」
実は里中も、サヤカの夫、木村祐樹にはいい感情を抱いていない。杉本が息子になったらどうだろうか、長年の共演者だけになんだかくすぐったい気持ちがする。
しかし、我が子ながら、あの娘と結婚すると、きっとお前苦労するぞ、といいかけてやめた。
「お父さん……と、呼んでもいいすか」
「いや」
「お父さん」
「嫌じゃといっておろう。今は水戸の隠居じゃ」
と、照れた。
「じゃ、お父上」
「だから、そういう問題ではないっ!」
「てか、今、そんなに和やかに会話している時ですか?」
と、井吹が鼻をすすりながら、間を割った。
そのときだった。
気の荒いサムライのひとりが、裂ぱくの気合と共に一歩踏み込んできた。ままよとばかりに、一太刀を浴びせ掛けてきたのだ。
驚く間も、呆然とする間もなかった。
あっと思ったときには、里中の体が半身に開き、ぎゃわわんという金物の弾ける音が甲高く響いた。模擬刀とはいえ、本物志向の特別製である。人は切れないが、真剣でさえ弾き飛ばす程度の強度があった。
「あ、危ないじゃないか」
何ごとが起こったのか、里中本人でさえ気付いていない。彼は、間一髪、その第一激を避けていたのである。体が空気の動きに反応して、勝手に動いた。そうとしか考えられない出来事だった。
格さんと助さんも唖然と里中の動きを見ている暇はなかった。その一太刀を皮切りに、周囲の数人がどっと斬り込んで来たのである。
ふたりは、相手が放つ袈裟斬り、突きなどの連続的攻撃を、無意識のうちに右に左によけながら、少しずつ後退していた。
「ごめんなさい、ごめんなさい」
井吹など、そう泣き喚きつつ、刀を振るって相手の剣撃をことごとく受けた。だが、多勢に無勢、剣先を交わすのがやっとのふたりだったが、そのままでは後がない。
「いやあ!」と突然叫んだのは、杉本である。
やけくそになって、前へ出た。同時に来た相手の斬り込みを、模擬刀で側面に受け流し、続けざまに面を打った。
「ぎゃっ!」という悲鳴で三人は我に帰った。
たちまち時間が止まったように、全員の動きが凝固した。
杉本の正面撃ちが相手の鬢の真中、綺麗に剃り上げた前頭部の中心に食い込んだまま、ぴくりともしない。ニセモノとはいえ、もろに喰らえば痛いだろう。そっと刀を引くと、見事なみみず腫れが、脳天から額にかけて出来上がっていた。
相手はそのまま気絶し、膝から崩れるように倒れ込んだ。
誰もが感歎の声を上げた。
敵とはいえ、あっぱれな武技でござる。
サムライたちの目は、そういって三人の不敵な男を賞賛しているように見えた。
沈黙はまだ続いている。サムライたちは、これは迂闊に踏み込めないと、次の攻め手に躊躇しているようだった。
「ひょっとして、俺たち強い?」
杉本は、ふたりの仲間を振り返った。
「まさかね」
杉本は念を押した。「でも、何だかとても強っぽい気分だ」
「いや、強いはずはないでしょう。僕たち、ただの俳優ですよ」
と、井吹が首をかしげながら答えた。
「しかし」
と、里中はいった。「私はこの道に入って、三十年。来る日も来る日も、殺陣を研鑚してきた。時代劇の中で、斬った人数は数千、数万をくだらないだろう」
「俺だって、時代劇役者になって、チャンバラばかりの毎日。真剣を持った立会いなら、そこらへんにいる剣道の有段者ごときには負けないかも、と思っていた」
「へ?」
井吹は涙でぐしょぐしょになった頬を袖でぬぐい、ずり落ちためがねをかけなおしながら、自らの刀を目の高さに掲げた。この刀はニセモノとはいえ、まるで、自分の体の一部のようだと、改めて思う。収録の続いた毎日、何時間も振り続けてきた刀である。そう思えても当然かもしれない。
「て、ことは、僕たち知らず知らずのうちに、本当に強くなっていたというわけですか」
今まさに力を取り戻したように、レンズの奥の井吹の目が、きらりんと光った。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- これまでに読んだ漫画コミック
- モジャ公
- (2025-12-01 07:13:27)
-
-
-

- 今日どんな本をよみましたか?
- 【いちばん大事なことは霊的進歩、神…
- (2025-12-01 07:05:04)
-
-
-

- ★ おすすめのビジネス書は何ですか!…
- ウィニング勝利の経営 =4章 発言権と…
- (2025-11-29 00:36:41)
-
© Rakuten Group, Inc.