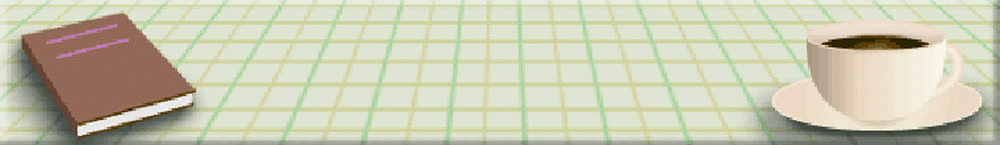時空剣劇ファイターズ(その四)
調子づいた井吹は、サムライたちの群れの中に飛び込み、斬りに斬った。里中も杉本も、その勢いに釣られ、われを忘れて暴れた。
三人にとって、チャンバラは日常である。水を得た魚のように、体が自然に動いた。彼らが刻むチャンバラのリズムに、周りのサムライたちは魅せられたように呼応し引き寄せられた。お互いに、斬り役と斬られ役として、見事にシンクロしていた。
もちろん得物は模擬刀であるから、斬ってもその肉を断つことはできない。だが、相手はサムライだ。たとえ傷は受けなくても、斬られたことによる精神的ダメージが相当のものなのか、模擬刀が触れるとそれだけで戦闘意欲をなくし、たちまち凝然として動かなくなる。やっていることはいつも通りの時代劇の殺陣と変わらなかった。
時代は戦国を終え、安定期に入ったところ。サムライはすでに平穏に慣れ、武技の衰退は著しい。里中たちの技が、彼らをはるかに凌いでいたのは驚きだが、理解できないことではなかった。
さらに落ち着いて観察すれば、いかめしい大顔のわりには、相手は皆子供のような体格である。簡単にいうと、五頭身の漫画キャラクターのような体型だった。栄養事情にも格段に差があるだろう。このときの日本は、平均寿命が三十代に過ぎない時代。現代人との体格と膂力の違いは歴然としていた。
あまりにも相手が弱すぎるせいか、井吹など、
「おらおらおら」などという気合で、少しばかり品性のない殺陣をしている。学識があることと剣術の格は別物らしい、と、里中は、剣撃の間も眉をしかめざるを得なかった。車の運転と同じで、斬撃の快感は人を変えてしまうようだ。
その点、杉本は里中の一番弟子として申し分のない殺陣をしていた。迷いのない剣筋には無駄がなく、幾何学模様を描くような様式美がある。
その間にも、相手は向かってくる。互いの剣術を確認し評価する余裕があったのは、ほんのわずかの間で、里中など年のせいかすぐに息が上がってきた。相手の剣戟を受ける手が重くなる。もちろんこれは杉本とて同じだった。
「きりがないですね」
「まったくだ。ただまあ、斬ったら二度と向かってこないのがいい」
「これってどういうルールですかね? ま、こっちは都合良いけど」
「サムライの身の処し方とは、実に不思議なものだ」
といいながら、里中は肩で息をする。そろそろ休憩を取りたいと思う。だが、ここには「カット」の声も、カチンコの音もない。
「おらおらあ」
が、井吹は若いだけに元気がいい。
「あっ」と、相手の切っ先が頬に触れ、井吹の顔面を血塗らしている。それがますます彼を逆上させて、バカ働きに働かせているようだった。
もっとも、三人が鬼神のように応戦している間に、サムライの群れの方も押したり引いたりと徐々に変化し、その勢いが少しずつ削がれていくようだった。とうてい敵わないと、全体的に逃げ腰になってきたのがわかる。そのうち、群れの中にわずかに突破口が見えてきた。
「あっちだ」
と杉本が、敵陣の密度が薄くなっている部分を目ざとく見つけて叫んだ。
「逃げましょう」
「よし」
活路を見つけた三人は、怒涛のような勢いで突進した。彼らの突き出した刀の先端から、サムライの群れが幕が割れるように左右に分かれた。そこから渡り廊下に突出し、転がるように庭に飛び出した。
「待たれい」
と、さらに追いすがる者がいる。
杉本は、その声の鋭さに驚き、振り返った。
まるで鬼瓦のような顔をしたサムライがひとり、廊下から三人を追って屋外に降り立っている。その鬼瓦に制された人数たちは、すでに彼の背景に過ぎない。
「お主たちを逃がすわけにはいかん。このままでは武士の一分が立たぬ」
「俺たちは何もしない。このまま逃がしてください」
杉本は心から懇願した。どんなに武技で勝っていようと多勢に無勢。しかも相手は真剣である。どのみち、このままでは三人の命が危ういのは目に見えていた。
「お主らは何者なのだ」
「ただの役者ですよ。人を斬るのが仕事じゃありません」
数歩前に走っていた里中と井吹が立ち止まり、杉本の横に戻ってきた。
「逃がしてくだされ」
と、里中も口を揃えた。
が、鬼瓦はするりと刀を抜いている。正眼に構えた姿は、これまでにない迫力がある。
「本物だ」
と、杉本は戦慄した。今までのその他大勢、十把一からげとはまったく違う。
「まず、勝負」
「勝負などしたくない。逃がしてくれ」
「馬鹿をいうな。それでも武士か」
「役者です」
里中が落ち着いた声で同じことを繰り返した。
「これにはいろいろと事情がありまして……」
「いや」と、里中の胸を片手で後に押し下げながら、井吹が一歩前に出た。
「僕が相手しましょう」
頭に乗っている、と、杉本は思った。今や井吹はいっぱしの剣豪きどりだが、このままでは本当に斬られる。ここは彼にはまかせられない。
「格さん(井吹)、君は後に下がっていろ。調子にのらない方がいい」
「しかし、助さん(杉本)、僕は戦えますよ。本当をいうと、まだ逃げなくてもいいぐらい、元気一杯です」
里中も困った顔をした。
「君は、どうやら人を殺すことをたしなんでいるようだな」
「相手、死んでないし……」
「とにかく」と、杉本がいいかけた間に横をすり抜けて、井吹は勝手に前に出た。
「勝負だ、かかってこい」
相手も納得したらしい。無言のまま、そのするどい視線を、井吹だけに集中している。もうこうなっては、間を割るわけにもいかない。がんばれよ、と、里中と杉本はうしろに下がった。
サムライたちの群れも動きを止め、息を殺して二人を見つめている。その多勢を背にして、鬼瓦も一歩前に出た。
「いざ」
「いざ、勝負!」
あっ、と声を出す暇もなかった。
鬼瓦の一閃が井吹の手元に伸びたのように見えたが、あまりにも速過ぎて定かではない。少なくとも、井吹の姿勢に変化はなかった。
変化は、わずかに井吹の手元にあった。
ぬるりと手をすべらし、刀を落したのである。何事かと思って、顔の前に手をかざして驚いた。
両手が鮮血でべとべとになっている。右手の人差し指が根元からなくなっていたのだ。
それを見た井吹は、まず指先から力が抜け、肩が落ち、全身の筋肉があっという間に弛緩した。
「指が……僕の指が!」
と、半泣きになって、なよなよと座り込んだ。
「参る」
といいながら、上段に振りかぶる鬼瓦の前に、やっとの思いで杉本が飛び出した。
「ま、待って。勝負ありだ。あんたの勝ちだ」
「僕の指を探して、どこかにいったよ、僕の……」
杉本は鬼瓦から視線を外さないように踏ん張りながら、無様に喚く井吹をなんとか抱き起こした。杉本には、それ見たことか、という気持ちも少しある。
「だから調子に乗るなといっただろう。今さら、指などどうしようもない」
「でも、切れた指があれば、手術でくっつける事ができるじゃないですか」
「だめだ。ここには医者はいないよ」
井吹は大声を上げて泣き出した。
「今度は、お主が相手か」
相手は容赦ない。
杉本は慌てた。こんな化け物と試合えば、命はいくらあっても足りない。だが、
「まあ、待て。まず、あんたの名を聞こうか」
と、何とか言葉を返した。一方で窮地を乗り切るための時間稼ぎのつもりだった。ところが、この質問が彼らのただならぬ状況をさらに証明するはめになった。
「柳生但馬」
と、鬼瓦が平然と答えたのである。杉本は思わず、げえっ、と唸り、井吹を抱える手を放した。
地面に投げ落とされた井吹でさえ、一瞬凍りついて泣き喚く声を止めた。
いくら歴史に疎いとはいえ、時代劇でこれほどのビッグネームを知らない役者はいないだろう。
里中はただ青ざめて天を仰いでいる。「ボケ老人」という演技のシェルターの中に閉じこもっているのに違いない。おそらくそれが、里中の最後の保身術なのだろう。
杉本だけが状況を把握しようとし、なんとか助かる道はないかと懸命に頭を働かせていた。もはや剣術で切り抜けることができるとは思えなかった。
その杉本を相手に、鬼瓦はにやりと笑う。
「お主も名を名乗るのが礼であろう」
「名乗るも何も」
と、歯の根も合わないほどたどたどしい口調で杉本はやっと答えた。
「私どもは、一介の旅芸人、河原乞食でございます」
「名を名乗れと申しておる」
さすがに歴史上の人物ともなると、恫喝も有無をいわさない迫力があった。
「さ、佐々木助三郎でござる。助さんと呼ばれてござる。ひっくり返せば、三助で……」
結局、ボケボケ作戦しかないと踏んでおどけてみたが、笑いを誘うまでには到らない。刃物の下をくぐるような緊張感は依然解けそうもなかった。
「ふうむ、豊臣の残党か、それとも真田の放った忍びかな」
さらに柳生鬼瓦は、後に向かって、
「服部をここへ」と呼ばわった。
もはや万事休す。服部といえば、服部半蔵に違いない。この状況で、伊賀忍者まで相手にできるはずがないではないか。
ところが、まさにその時だった。
突然、空間が歪んだかと思うほどの、大量の光が三人の目の前を白くした。
なんということだろうか。
空飛ぶ円盤だ。
江戸城の庭園の中空に止まっている。ビイイ~ンという安っぽい振動音が辺りに響き、居合わせた全員が嫌悪感から耳を塞いだ。
ここで考えている暇はない。
「助けてくれ」
三人は口をそろえて叫び、円盤に向かって一目散に駈けた。
「助さん(杉本)、僕の指……」
「そんな暇ないよ」
杉本は吐き捨てるようにいって、井吹の尻を叩いた。
「とにかく逃げろ!」
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- ★ おすすめのビジネス書は何ですか!…
- ウィニング勝利の経営 =4章 発言権と…
- (2025-11-29 00:36:41)
-
-
-

- これまでに読んだ漫画コミック
- モジャ公
- (2025-12-01 07:13:27)
-
-
-

- 連載小説を書いてみようv
- 63 花祭り
- (2025-12-01 06:34:57)
-
© Rakuten Group, Inc.