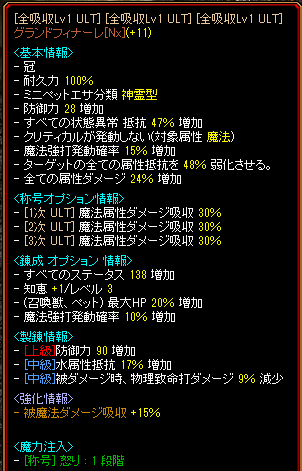第19章
前進両者の牽制が続く中、先手で動いたのはブラッドの方だった。右腕を後方に下げた、一撃必殺の構えで突撃してくる。単純で真っ直ぐな動きだ。一見して何の変哲もない攻撃だが、ゼロはブッラドがその右腕を繰り出す直前に彼の真横ほどまで大きく回避行動を取った。
「な?!」
その拳によって起きた現象に、レイが目を疑い、驚愕の声を上げる。
拳が繰り出された方向に在った大木が、幹の途中をくり抜かれたかのようになり、音を立てて倒れていく。拳圧だけで、この威力だ。
おそらくこれほどの威力だとゼロが予想していなかったら、決着は付いていただろう。全身を粉々になるほどの圧力を受け、即死したに違いない。
しかし、紛れも無くゼロはここまでを予測し避けたのだ。天才としか思えない、勘の良さだ。
「どれくらい鍛えりゃ、そんな攻撃が出来るようになるんだ?」
冷や汗一つ流すことなく、ゼロがブラッドに尋ねる。それに対しこの大男は苦笑しただけだった。だがなんとなくゼロには答えが伝わってくる。彼にはきっと不可能だ。先天的に与えられた遺伝子レベルまで突き詰めれば理論的な答えは返ってくるのだろうが。
「じゃあ、次は俺の番だな」
その言葉とともに、ゼロの姿が消える。何となく気配が動いているのは感知出来るが、それがどこにいるのか、レイには判断できなかった。
―――なんちゅー速さや……!
しかもゼロはただブラッドを撹乱しているだけではない、小さいが、確実に彼の表皮が薄く裂かれ、血が滲み出している。ほとんど感じられてはいないだろうが、不快さを煽る攻撃だ。
「はあ!!」
そして、ゼロの殺気が極端に膨らんだ刹那、ブラッドも強烈な気を発した。彼もゼロの居場所を判明できなかったためであろう、彼の身体を中心に全方位へ気を発している。その攻撃に、ゼロがかなりの間合いを置いて姿を現す。ゼロが小さく舌打ちしたのが見えた。
必殺の一撃を止められたのだ。仕留め損ねた、という意識は強いのだろう。
「大したものだ」
「どーいたしまして」
激しくぶつかり合っている二人にしか分からない空気が二人を包む。どちらともなく、獰猛で不敵な笑みを浮かべていた。
改めて構え直し、両者は再度攻撃の機を探った。
「ぬおおぉぉぉ!!」
シーナの斬撃を受けつつも、ヴァリスは得物の鎌を振り回しシーナを牽制した。心臓に達するであろうと思われた彼の刀を紙一重で後退し、“死”を免れはしたものの、大ダメージには相違ないだろう。右わき腹から左肩へ抜けるように、真っ赤な線がヴァリスの身体上に引かれている。流血は、収まりそうには見えなかった。
いくらヴァリスが強いと言っても、これほどの傷を負ってはもはや敗北、死は決定的であろう。
自身の肉体を支えきれず、ついにヴァリスが地に膝をつく。
「流石……これが、最強、というもの、か……」
息も絶え絶えにヴァリスが言葉を洩らす。それに対し、シーナは冷たい視線を送るだけだった。
「悪いが、俺に慈悲はない」
刀がヴァリスの真正面で振り上げられる。
「来世に期待しろ」
こうして、中央最凶と謳われた“神魔団”のリーダー、ヴァリス・レアーは、その激動の生に終止符を打った。
―――なんやこの空気、全く、全く先が見えへん……。
蛇に睨まれた蛙の如く、レイは固唾を飲んで戦いの次の瞬間を見守っていた。ブラッドにやられた彼自身の負傷は落ち着いてきたが、どうしてもゼロと同等に動ける自信が湧いてこなかった。事実、先ほどからゼロが見せている動きは、以前にゴーストと戦った時とは比較にならない。これが、東西南北最強と謳われる“死神ゼロ”の本当の実力なのだろうか。
ふと、ゼロが口元に小さな笑みを浮かべているのに気付く。この激しい命の削りあいの中で、何が可笑しいのだろうか。レイには、到底分かりそうになかった。
―――強いオーラが一つ消えた……。シーナ・ロード、もう倒したってのか。
ブラッドとの戦いの最中、ゼロはシーナとヴァリスの戦いの決着を感づいた。遠くに巨大な存在感を2つ感じていたのだが、今は1つだけ、それも憎たらしいほどに余裕を持ったものだ。
―――俺も、さっさとこいつ程度倒さなきゃな。
そう決めた瞬間、ゼロが刀身を鞘に収めたまま、一気にブラッドに迫る。
シャァァァン、と何か擦れるような甲高い音が響くのと、ブラッドが大きく後退したのは、ほぼ同時だった。いや、ただ後退したのではない、改めて彼を見れば、とある大きな事実に誰もが気付くであろう。
「なんだ今の技は?」
脂汗を浮かべながら、ブラッドが右腕を、右腕の二の腕が付いていたはずの場所を押さえながらゼロに問いた。だらだらと止め処なく血が滴り落ちている。
「必殺技さ」
ゼロの放ったのは単純かつ超高度な“居合い”という技だった。鞘から刀を抜刀し、目標へ斬撃を加えた後、また鞘へ戻すという、流れだけ見れば単純な技。しかし、達人がそれを行う場合、それは単純を越え、最強の名を冠するに疑いないほどのものとなる。攻撃の余韻を残すことなく、次の攻撃態勢に入れるという利点を持つが、高速の動きの中、小さな鞘の入り口に寸分狂わず刀を戻せる者がどれほどいるだろうか。まさしく刀を熟知し、熟練の技術の下に行われる技なのである。
ゼロが今見せた攻撃を、ブラッドは目で捉えることが出来なかった。いつ斬られたのか分からなかった。抜刀から納刀まで、目にも止まらぬ速さで行うからこそ意味を成す技、それがゼロの必殺技の一つ、居合いだ。しかし、攻撃するその一瞬は、防御を無視し攻撃だけに全神経を集中させるため、防がれたときには無防備な瞬間が生まれるため、諸刃の剣ともいえるのもまた真理なのだが。
ブラッドが右腕の付け根の当たりを力いっぱい握る。段々と右腕の血行が悪くなっていき、血が止まった。それは、見ていて気持ちいいものではなかったが。
「大した攻撃だ!」
吐き捨てる様にそう言った直後、今度はブラッドが一気にゼロへ接近する。その速さは焦りが混ざったもののためか、速いのだが、どこか単純な速さだった。そんな動きに対し、今のゼロが対応できないわけもなく、なんなく、といった風にひらりと身かわす。先ほどのような全力の拳ではなく、利き腕でもないため、拳圧も然程ではない。
しかし、ブラッドの攻撃に休むところはなく、単純な攻撃にも関わらずゼロは反撃に転じることができなかった。体格の違いから当然ゼロとブラッドとではリーチが違う上に、攻撃する際にダメージを負わせうるために使用する筋肉の加減も違う。速さと見切りで圧倒するとはいえ、やはりゼロには幾らかの不利があるのだ。
―――もしかして、これはチャンスやないか?
ブラッドが執拗にゼロを狙う光景を見て、レイははっと気がついた。先ほどからずっと傍観に徹していたが、逆に言えばブラッドの意識から自分の存在が消えている可能性があるのだ。それに気付いたとなれば、取るべき選択は一つ。
タイミングを見計らってレイが剣を構え、二人の様子を窺う。だが、信じられないことに突如ゼロの足が止まり、ゼロはブラッドの筋骨隆々とした左腕によるボディブローをまともに受け、後方へ大きく吹き飛ばされた。
「ゼロ?!」
頭で命令を下す前に、身体が動いた。
追撃を加えようとしたブラッドとゼロの間に割ってはいる。拳を振り上げたブラッドが踏みとどまり、3歩ほど後退する。
「ゼロ! 大丈夫か?!」
ゴホゴホと咳き込んでいるから、生きているのだろう。それだけにはホッとした。だが、今生きているからといって、油断はできない。内臓を痛めていた場合、激しい苦痛が襲ってくることもあるのだ。
「ああ、問題ない」
若干苦しそうだが、レイの予想していた以上にゼロの声はピンピンしていた。普段通りのクールさを兼ね揃えた美声。
血が混じった唾を吐き捨て、ゼロがレイの隣に並ぶ。
傍に立って初めて分かったが、やはり呼吸が少しおかしい。やはり問題ないわけはないようだ。
「何故、何故そう立っていられる?」
ブラッドが信じられないといった表情でゼロに尋ねる。彼も大量に血を失ったために、顔色が悪い。
「お前には幻覚を見せて、俺の存在を意識の外へ飛ばさせたはずだ。ノーガードで俺の攻撃を食らい、お前は死んでいるはずだ」
そう、ゼロの足が突然止まったのはブラッドのアビリティ“幻覚”を受けたからのようだ。シーナから助言はもらっていたものの、先ほどの場面では到底瞼を閉じさせるなど間に合わなかった。
「お前の拳が俺に触れた瞬間、お前の視線が俺から外れた。そこで気付いたのさ。意識の繋がりが若干おかしいってな。受け流すことは流石に出来なかったが、俺自身も後ろへ飛べば、多少なりともダメージは軽減できるだろ?」
半分以上は本能がなしえた動き。尋常ならざる反射神経。だが、彼のアビリティを知っていなければきっと避けることはできなかっただろう。やはりシーナの助言はこの戦いに大きく関わったようだ。
「何故、俺のアビリティを?」
「シーナ・ロードが教えてくれたんや」
レイの答えに、ブラッドがなるほど、といった表情を見せる。
「それならば、仕方ない、か。だが俺は独りでは逝かん。悪いが冥府まで付き合ってもらうぞ」
改めてブラッドが二人に攻撃をしかけてくる。二人はそれを冷静な視線で分析した。既にブラッドはその戦闘力の大半を失っている。最早、負ける要素はない。
ブラッドの拳はゼロを狙っていた。やはり、自身の負傷の大部分が彼に負わされたものだからだろうか。だが、万全の状態であったならば、彼らに脅威を与えたブラッドの拳も、既に大した攻撃ではない。さっと避け、ブラッドの右側を取る。
「悪いが、これ以上立ち止まっているつもりはないんだ!」
一瞬だけ、ゼロの瞳が憂いを帯びた。だが、それもすぐに消え、ゼロの刀がブラッドの身体を一閃する。
手ごたえがあった。懐かしい、と言えば嘘にはならない。統一戦争の際は、必然的に味わっていた。人を、刀で斬る感覚。
改めてブラッドを見る。ゼロの感覚には狂いなく、既に彼は絶命していた。しかし彼に苦悶の表情はない。戦いの中、己の信念を貫き通して死んだ者が見せる、どこか満足げな顔だった。
刀を鞘に収め、ゼロは自分の手のひらを見つめた。目には見えない“赤”が見える、そんな気がした。
「しんどい戦いやったな~」
レイがゼロの頭をぽんと叩き、にっこりとゼロに笑いかけていた。彼からすれば、これは自分にとって大きな勝利なのだ。いや、レイだけではない、ゼロにとっても、大きな勝利。表面上は、ゼロも笑ってみせる。だが自分でもはっきりと分かるほど、ぎこちない笑みのような気がした。
「ぼろぼろだな」
と、そこで無感情な声が二人の耳に訪れる。その声の主を見て、二人は驚きを隠せなかった。
「ん? どうかしたか?」
「嫌味か……」
「そうみたいやな……」
満身創痍の二人とは対照的に、シーナはまるで無傷。二人と彼を比べると、まるで彼がキラキラと輝いているような錯覚を覚えてしまう。
「悪いな、強くて」
二人のコソコソ話にも的確に嫌味を入れる。ある意味完璧だ。
「しかも地獄耳かい……」
「な、イヤな奴だろ?」
「そやな……。俺もちょっと嫌になってきたわ」
げんなりする二人。
「しかしまぁ、よくブラッドを倒せたものだ」
ぐったりしていた二人の耳に、予想外の言葉が届く。まさかここまで嫌味を言っておいて、今さら賞賛するとは。何かの間違いではないのかと二人は耳を疑った。
「俺がヴァリス相手にここまで余裕で勝てたのは当然実力もあるが、正直言ってあいつが俺に持っていた先入観のほうが強いな」
確かに“中央最強”と謳われるほどの人物だ。多少なりとも、もしかしたら自分には勝てないかもしれない、というイメージは持たせることができたかもしれない。
「それに対してお前らは、ブラッドに勝てないかもしれないと思わせる要素がない。ヴァリスだったら驕って油断したりしたかもしれないが、ブラッドは弱者に対しても容赦ない男だ。よく勝てたものだ」
その褒め言葉を、ゼロは正面から受け取ることが出来なかった。どこか不満そうな顔で。
「あんたの助言があったから、勝てたようなもんだ」
顔だけでなく、声も不満そうだ。それに対してシーナが「ほお」とゼロに視線を向ける。
「あんたの助言がなきゃ、俺は死んでたよ」
「なら俺に感謝するがいい」
まさかの彼の言葉に、ゼロはもちろんレイまでもが目を細めた。
「あんた、無償で受け取れとか言ってたじゃねえかよ」
「ほお、西王とあろうものが間接的にせよ命を救った恩人に礼の一つも言えんのか」
「前言撤回! あんたの助言がなくてもやっぱ俺が――」
と、そこでゼロの言葉が強制的に途切れさせられる。大した量ではなかったが、ゼロは二人の前で吐血した。
「ゼロ?!」
戦闘が終わり、身体の緊張が解け、アドレナリンの分泌が収まったのだろうか、急に全身が悲鳴を上げ始める。
ふらついたゼロの身体を、すっとシーナが支えた。二人の距離は2、3メートルほどあったはずなのだが、レイには彼の動きはまったく見えなかった。
「ほら見ろ、ぼろぼろじゃねえか」
「う、うるさい……」
自分の足で直立しようにも、いかんせん力が入らない。蓄積されたダメージと疲労がピークに達しようとしているらしい。
それ以上に、ゼロにとってシーナの胸を借りて身体を支えているということが嫌だった。だが、触れた彼の胸の鼓動が聞こえ、少しだけゼロの考えは変わった。
心臓の鼓動が、少し早い。
―――心配して、くれてんのか……?
もちろんそれは確かなことでもないし、ゼロの幻聴だったかもしれない。彼に支えられることが嫌なことには変わりないが、さっきまでよりは心のとげとげしさはなくなっていた。
「とりあえず、よく頑張ったな」
その言葉はまるで二人の兄のようで。
その言葉に改めて自分たちの勝利を実感する。
そして実感するとともに、段々と眠くなってきた。
レイが何か言っているように聞こえたが、ゼロの耳にはよく聞こえず、そこで彼の意識は途絶えた。
どうやら傍で誰かが話しているらしい。内容まではよく聞こえないが、なんとなく声が聞こえてくる。
どうやら自分はどこに横になっているようだ。シーナに支えられていたところまでは記憶があるのだが。
ゼロはゆっくりと瞼を開く。視界いっぱいに真白な光を受け、ゼロは目を細めた。
「ゼロ!」
女性の声に呼ばれ、声のした方へゼロが顔を動かす。若干泣き目になっている青い髪の可愛らしい女性が視界に入った。
「……ミュアン?」
見間違えるはずもない。ブラッドの戦いに行く前に、自分とレイを見送った女性だ。中央における、数少ないゼロが知己とする存在。
「どこも痛くない?」
そう言われて改めてゼロは自分の身体を見てぎょっとする。
「右足靭帯損傷、肋骨骨折5本、左肩脱臼……折れた骨が肺を傷つけてて、まぁ折れた骨が肺に刺さらんかっただけマシみたいやけど、ほんまぼろぼろだったようやで?」
レイの説明を聞いて若干ゼロの顔色が青くなる。腹部には包帯が巻かれ、右足と左腕は固定されている。絶対安静、といった状態のようだ。
「お前は、大丈夫なのか?」
ゼロの隣のベッドに横になっているレイに顔を向ける。彼も左腕を固定されている。
「俺は左上腕骨折と、肋骨にヒビが入っとるだけや」
上半身を起こし、ベッドに腰掛けるようにレイが移動した。“だけ”とは言うものの、あまり無事には見えない。ゼロから比べたら、マシかもしれないが。
「レイくん! まだ安静にしてろって言われたでしょ!」
起き上がった彼に向かって、ミュアンが怒鳴る。すると慌ててレイがまた横になった。その様が滑稽で、ゼロは思わず笑ってしまう。
「あいつが、運んでくれたのか?」
ゼロがそう言うと、レイが頷いた。
「あの後ゼロが気絶してもうたからな、何も言わずに運んでくれたで。今回ばかしは、ほら、俺の腕も折れとったさかい」
本当に、何も言わずに? 正直信じられず、そんな疑問が浮かんだが、とりあえずは信じることにしよう。シーナ・ロードが律儀に自分を病院まで運んでくれたのは間違いないだろう。これは、借りを作ったということか。
「そう、か」
ゼロが一人苦笑する。その意味は二人には察することはできなかった。しかし、確かなことがある。
「ホント、生きて戻ってきてくれてよかったよ」
“無事に”と言わない辺りが彼女らしいか。そんなことを考えながらも、ゼロとレイは笑顔を浮かべた。
そう、見事に彼らは“神魔団”を滅ぼしたのだ。
着実な進展を実感し、ゼロはぎゅっと拳を握り締めた。
「おかえり!」
砦に戻ったシーナを、活発な方のフィエルが迎える。「ああ」と小さく答えたシーナは出迎えてくれた彼女の横を通り過ぎ、椅子に腰を下ろした。
「どうだった?」
「見れば分かるだろうが」
シーナにこれといった負傷はない。確かに見れば分かることだが。
「そうじゃなくて!」
フィエルが急かすようにシーナに問い詰める。目だけで「どういうことだ?」と問うと。
「アリオーシュたちの方だよ! シーナのことぐらい私だって見ればわかるって!」
「ああ、あいつらか」
あえてシーナが表情を暗くしてみせた。それを見てフィエルがまさか、といった不安そうな顔を見せる。
「冗談だ。そんなに露骨に反応するな」
「シーナ!」
今ここにゼロがいれば間違いなく「嫌味な奴だな……」とツッコミを入れただろう。根っから、こういう性格なのかもしれない。
「なかなかに負傷していたが、二人とも生きて勝利を収めたよ。しかも、アリオーシュの方は“直系にのみ許された第二の扉”を開ける手前まで辿り着きそうだ」
「本当ですか?!」
突然フィエルの口調が変わる。気付く余裕もなく人格の変わった彼女に、シーナが視線を向ける。
「ああ。イシュタルの直系の俺でさえ23年かかったというのに、大したセンスだよ」
「しかしそれが本当ならば、貴方の力と彼の力で、彼女を救うことができるかもしれません」
「……だといいがな」
フィエルのプラス思考な考えに賛同しながらも、シーナは別のことを考えていた。
―――“最強”の名も、危ういかもな……。
“直系にのみ許された第二の扉”を開けることとはいったいなんであるのか。そしてそれによって救うことができるかもしれないこととは。
シーナの気持ちも露知らず、フィエルには、うっすらとだが、光明が見えてきたような気がしていた。
© Rakuten Group, Inc.