第26章
純粋――この感じ、久々だな。
ゼロの脳内に直接声が響く。アノンの憑依状態は、およそ2年ぶりだ。
――そうだな。最初から全力でいくぞ。俺たちの想い、あの頭でっかちにぶつけてやる!
先ほど身体を貫くほどの一撃を食らったというのに、ゼロ・アリオーシュは再び立ち上がった。
「ゼロ!」
彼の傍らには、目を真っ赤にして喜ぶ女性が。
「心配かけたな。この戦い、一気に終わらせるぞ」
「まだ刀の使い方は覚えているか?」
何度か攻撃をしかけ、一度エルフから距離を取ってシーナはレリムに声をかけた。
「も、もちろん! 兄さんの教えを忘れたりはしません」
「ふ……使え」
彼女の答えを聞き、彼は自分の刀を差しだした。
「え?」
「俺はイシュタルの直系だぞ?」
その言葉の意味が彼女にはすぐ分かった。刀を受け取ると、シーナの手が輝いていく。
「奴が神槍ならば……これで勝負だ」
彼の手が握るのは、今までの刀とは違う少し大ぶりな剣だった。
「神剣デュランダルか……イシュタルめ、味な真似を」
エルフが再び迫る。その攻撃をシーナは正面から受け止めた。
今までなら大ダメージだった雷撃が、来ない。
「イシュタルに創造の力を授けたお前の責任だ」
力比べになれば相手の肉体はあのフィエルだ。シーナに分があるようだ。
「遠慮はいらん!殺す気でいけ!」
鍔迫り合いのような拮抗状態を好機と見、シーナがレリムに命じる。彼とフィエルの関係は十分承知しているつもりだ。その彼が殺すという言葉を彼女に対して使うということは、並大抵の覚悟ではない。ここで手加減しては、彼に対して失礼だ。
「はぁっ!!」
シーナを飛び越え、エルフの頭上から一気に刀を振り下ろす。だが。
「身の程を……わきまえろ!」
今までは手からしか出していなかった衝撃波を全身から放出する。シーナとレリムの身体はいとも容易く吹き飛ばされた。
だが薄々と感じる。エルフに余裕がなくなってきていること。
絶対的な存在の神が、揺らぐ。
「自分のやりたいようにやって、創りたいように創って、どこまで傲慢なんだかね」
死地から帰ってきた男の姿に、エルフが僅かに眉をひそめた。
「俺たちにはかけがえのない仲間ってのがいる。築いてきた信頼がある。俺の帰る場所を、お前何かに壊させやしない!」
ゼロがエルフに向かって突撃する。
「アリオーシュの力、俺たちの想い、受けてみろ!」
ゼロの一撃をエルフの槍が受け止める。今までなら考えられなかった。だが、確実にゼロの一撃はエルフに効いていた。
「くっ……」
エルフがよろめく。
「何だ貴様の攻撃は……?」
エルフの中で何かが暴れる。
「フィエル! いい加減起きろ! いつまで寝てるつもりだ!!」
そこにシーナが追い打ちをかける。エルフの中で眠る、フィエル・エルフへ。
「あああああ!!」
エルフが頭を抱え喚く。彼女の中で、神エルフとフィエルの両者がぶつかっているのだろう。
「何なのだ、貴様らの想いとは……!」
「想いをストレートにぶつける。純粋な想いであればあるほど、直接届く。それがアリオーシュの力らしいぜ」
そのアリオーシュの力を使い、ゼロはエルフを揺さぶった、ということだろう。
――想いを力に、か……。ここじゃない、向こうでゼロを待っている人がいる。その人の所へ帰ろうと願う想いを力にしたのかなぁ。
そう思うとミュアンの胸に寂寞の思いが募った。
「後ひと押しだな」
「一気に行くか」
フィエルを斬るのではなく、エルフという存在を斬るのだ。アリオーシュの力が使える今ならば、出来るはず。
ゼロとシーナが剣先を呻くエルフへと向ける。そして同時に、動いた。
一瞬の閃光が辺りを包んだ。
そして。
「馬鹿な……! ヴォルクツォイク如きの貴様らに、この私が、敗れる、だと……?」
フィエルの身体には傷一つない。だが彼女から発せられていたエルフの気配が離れていく。
「俺たちの行く末、もう少し見守ってくれよ」
「争い、平和を壊すのも確かに俺たちエルフだが、その平和を築くのも俺たちだ」
ゼロが見つめるのは、平和な東西南北、シーナが見つめるのは、平和な中央。
そしていずれは、森全体としての平和を。
二人の男が想う未来が、希望が、理想が、神に届く。
「いいだろう……この森の行く末、今しばらく見守ろう……。弱きものたちよ……」
最後の言葉を残し、エルフの気配が消える。力無くフィエルが倒れそうになったのを、シーナが支えた。ゆっくりと息はしている。気絶か睡眠状態のようだ。
「無事で良かった……」
その呟きは誰にも聞こえないほど小さいものだった。
「……勝ったのですか? 神に……」
いまいち実感は湧かないが、レリムが誰にでもなく尋ねる。アノンが憑依状態を解き、姿を現した。
「そう願いたいな」
誰しもが何も言えなくなった。信じられないような出来事だったのだ。まさか、神と戦うことになるとは、誰も思うまい。
呆然としばらく立ち尽くす5人。
「さて、余計な邪魔が入っちまったが」
「本番といくか」
「え?」
沈黙を破ったのは、二人の最強だった。信じられずミュアンが力ない声を出す。
疲れていないわけがない。むしろあの二人が一番疲れているはずだ。ゼロに至っては死の一歩手前までいったばかりだというのに。
「前哨戦にしちゃあ長すぎたな」
「バテたのか? ウォーミングアップには丁度いいくらいだったろう?」
どこか楽しそうな表情で二人は睨み合った。
「兄さん、闘うならこれでしょう?」
こうなっては止められない。レリムは小さくため息をついて、だが嬉しそうにシーナに刀を返した。無言でそれを受け取り、今まで持っていた剣を消す。
「兄さん……?」
レリムの言葉を理解出来ず、ミュアンが聞き返す。だがそれに答えてくれる者はいなかった。
「よし、アノン、いくぞ。こいつを倒して、城暮らしに戻るんだ」
「分かった」
ハチャメチャだ。この二人には常識が通用しないのだろう。そしてそれについていくレリムとアノンも。ミュアンの常識を超えている。
だが、これでいいとも思う。好きな男のやりたいようにやらせる。彼が楽しそうならそれでいいのだ。
気が付くと笑っていた。彼女が信じるのはゼロの勝利ただ一つ。
「……がぁんばれ」
聞こえなくてもいい、ただ応援したくなる乙女心なのだ。
「いくぞ」
先手を打ったのはシーナだった。正面頭上から一刀両断の構えで攻めてくる。バックステップでその攻撃を避けるゼロに、着地と同時に踏み込んだシーナが迫る。避けられる速さではなく、ゼロも刀を振るう。甲高い音が月夜に響いた。
一度間合いが開く。今度はゼロから仕掛けた。鞘に刀を入れた状態のまま突撃する。そしてギリギリのタイミングで抜刀、納刀。だがその攻撃はシーナを捉える事はなかった。さらに広く距離を取って対峙する二人。
今度は二人同時に動いた。両者の中心地点にて激突。肉薄する鍔迫り合いの状況で二人は不敵に笑っていた。
「疲れてんのか? 攻撃にキレがないぜ」
「そういうお前こそ何ださっきの居合は。欠伸がでる」
最早二人を支えるのは己の信念と、男の意地くらいなものだった。体力の限界はとうに超えている。それでも皮肉を止めないのは二人だからこそか。
真の最強の名を賭けた戦いとはこういうものなのかもしれない。先ほどまで共闘していた二人による最後の対決。
互角の戦いがしばらく続いた。
ミュアンもレリムも何も喋らず、ただ二人を見守る。
静かな森に、金属がぶつかり合う音が響く。
半刻ほど戦いが続き、最後に立っていたのは。
「俺の勝ちだな!」
肩で息をしながらゼロが吠える。一滴の血も流さずに、地面に仰向けに倒れ伏せたシーナは小さく舌打ちをしたが、どこか満足げな表情を浮かべていた。
「あぁ……俺の負けだ。最強の名は、お前にくれてやる」
「よっしゃ、終わっ……た……!」
シーナの宣言を聞き終えると、ゼロも大地にその身を預けた。ミュアンとレリムが駆け寄ってくる。アノンも憑依を解き、ゼロに寄り添う。
「お疲れ様。勝っちゃったんだね、シーナ・ロード……シーナ・イシュタルに」
ゼロに肩を貸し、立たせる。今ばかりはゼロもミュアンに甘えた。シーナ・ロードがレリムの兄だったということには驚きだったが、彼女の姿、視線を見ていては信じないわけにはいかなかった。どことなく、自分のゼロへの視線と似ている気がしたのだが。
「そうだな……。これで終わったんだ」
「うん!」
心の中の寂しさを隠し、ミュアンは笑顔を保ち続けた。
「お疲れ様です」
シーナに寄り添ったレリムが声をかける。
「最強の名は失った。イシュタル家の掟は、もう廃れたのかもな……」
そう呟くシーナの口元には悲しみはなく、少しだけ、ほんの少しだけ寂しそうな笑みが浮かんでいた。一族殺しの汚名を継承する時代は終わったのだ。
「兄さんは私を生かしてくれた。その優しさがイシュタルの最強を退けたんですよ、きっと」
「それも悪くない、か」
その囁きはレリムにすら聞こえなかった。だが、彼は確実にそう呟いた。
ゆっくりと立ち上がり、ゼロの方へと近づく。
「向こうに帰る前に、もう一度この神殿へ立ち寄れ。アノン・アリオーシュをヴォルクツォイクに転成させられるよう試してみる」
――今、名前で呼んだのか……?
ずっとアレやソレ呼ばわりだったアノンに対して、彼がゼロの妹としての呼び名を使ったことに対してゼロは驚きを隠せなかった。だが、嬉しく思う。
「分かった」
「後継者の砦にも寄ってくださいね? 感謝したいことがたくさんありますから」
「悪いがそれは遠慮させてもらうよ。覇権はレリムに譲る、後のごたごたと一緒にな」
「そうですか、残念です」
どことなくその答えを予想していたのだろう。統一戦争を終え、すぐに帰らなかったことが招いたのが今回の一件だ。今回こそは早く帰りたいのだろう。
「よし、帰るか」
「ん」
ミュアンとアノンを連れ歩き出す。シーナとレリムはその姿を見送っていた。
夜が明け、朝日が森を照らし始めた。
レイの借り家は暗く、人気がなかった。どうやら彼は不在らしい。
「レイくん、いないの?」
「そうみたいだな……」
戦いは終わったというのに、まだ消えない不穏感。信じたくないことを想像し、ゼロの表情は曇っていた。
翌日、ゼロはアノンを連れたって昨日の決戦の地へと赴いた。シーナの言葉を信じれば、彼女を本当の意味で妹的存在に出来る。
普通の、エルフに。
背負わされた業からの解放を。
「だまってりゃただのエルフなんだけどな」
彼女の頭をぽんぽんと叩きながらそんなことを洩らす。
「私が仮にも元神の一人だったということを忘れているな?」
「あー、そういや」
「北の崇める公正と慈愛の神ジャスティの妹、アノン。それが矛となる前の私だ」
彼女の表情があまり明るくないことに気が付く。確かに少しだけ、声が暗いような気もした。
「ジャスティの妹であったほどだ。その力は彼に勝るとも劣らず、戦姫の異名を取るほどだった。そんな存在を誰が殺したと思う?」
答えにくい問いだった。数千年も過去の話といえど、思い出してしまった以上彼女にとっては忘れることのできない記憶なのだ。これ以上のこの話をしたくないのが本音だった。
「今ではこう侮蔑されているはずだ、偽神リューゲとな」
聞いたことのない名前だった。少なくともその名を持つ貴族を彼は知らない。
「奴は私の側近だった。ジャスティの信頼した腹心だったからこそ、私の護衛として側近としたのだ。だが停戦協定の話が出た辺りでアシモフが交戦の道を選んだ直後だった。おそらくアシモフに惹かれたのであろう。奴は彼の下へ行く手土産として、私を殺した。……正確には死んでいないのだがな」
アノンの無表情が、ゼロにとって苦痛だった。これを語る彼女の覚悟が伝わってくる。認めたのだ、この真実を。
「私は奴を本当に信頼していたのだがな……。まぁ、おかげで私はアリオーシュに出会えた。そして今貴方の側にいられる。これで良かったのかもしれない、そう思える。これは幸せと考えてもいいものだろうか?」
彼女が顔を上げ、儚げに微笑む。過去を切り捨て、今へ。これからの彼女が歩く道は、神など関係ない普通の人生。だから。
「俺もお前に会えて良かった。だから、良しとするか」
彼女の髪を撫でてやる。アノンはアノン。ジャスティの妹ではない、ゼロ・アリオーシュの妹だ。
彼女のために出来ること、それをするために二人はまたやって来た。創造と破壊の神イシュタルの末裔、シーナの所へ。
「フィエルの具合はどうなんだ?」
シーナへの確認もなしに部屋に入る。彼ならば気配で分かるだろう、という予測の元だが。
「変わる気配はないな」
昨日の戦いが終わっても、彼女は目を覚まさなかった。心臓は動いているし、呼吸もしている。だが、目を覚まさないのだ。
「おそらくこいつの中でエルフと戦ってるんだろう。馬鹿だからな、それくらいしか罪滅ぼしが浮かばないんだろうな」
彼の様子は普段と変わらない。だがゼロは昨日のシーナを見てしまった。エルフが目覚め、フィエルの身体と戦うことになった時の動揺も、戦いに勝って彼女が生きていた時の安堵も。
きっと彼ならば彼女が目覚めるまでずっと側にいてやるだろう。そんな予感がする。
「それは置いといて、本題に入るか。ついて来い」
フィエルが眠る部屋を出て、斜め向かいの部屋に入る。ほとんど何も置いていない、殺風景な部屋だった。
だが見覚えがある。確かここはアノンが眠っていた部屋だ。
「俺自身生物に対してイシュタルの力を使ったことはない。だからどうなるか分からん。だが方法はこれしかあるまい。それでもいいな?」
改めて確認されると、すぐには返答出来なかった。
「構わない」
だが、アノンがすっと答える。彼女にしか出来ない即答だった。
「アリオーシュも同意見か?」
「……こいつがそう言うんだ。一緒だよ」
これしか方法がないのなら、こうするしかあるまい。そう自分に結論付ける。
彼女の辿ってきた道を思うと、自分は何と平坦な道を歩いてきたのだろうかと思う。だから、これからは彼女も一緒に平坦な道を歩ければいい、切にそう願う。
「手順は簡単だ。お前がアリオーシュの力を使い、こいつにどうなって欲しいかという想いとやらぶつけろ。そこで生じるであろう存在の隙間を俺がイシュタルの力でこじ開け、存在を書き換える。理論的かも分からんが、俺に浮かんだのはこれくらいだ。……アリオーシュの想いの力とやらを使う段階で妖しいもんだが、そういう非科学的なもののほうが意外と上手くいくものだろ」
言われてみれば昨日神を、エルフを倒したのに使ったのも非科学的な想いの力だ。信じないわけにはいかない。
「分かった。やってみよう」
ゼロがすっと目を閉じる。アノンも少し緊張した様子で目を閉じた。これから自分がどうなるか分からないという不安は打ち消せられるものではないだろう。
――お前に課せられた運命は、もう十分役目を果たした。
――だからもうお前は自由に生きていいはずなんだ。
――矛なんかいらない。一エルフとして、お前が必要なんだ。
――アノン・アリオーシュとして生き、過ごし、アノン・アリオーシュとして死の時を迎える。それでいい。
――これからがアノンの本当の人生なんだ!
ゼロの想いが溢れる。その波動にアノンだけでなく、部屋全体が衝撃を受けたように思われた。ゼロの想いがダイレクトに伝わった彼女の目からは、涙が溢れる。
『想像せよ、汝はアノン・アリオーシュ。ヴォルクツォイクが一人ゼロ・アリオーシュの妹アノン・アリオーシュ。汝が望むように、我創造せり』
そしてシーナが彼女に触れる。その手から伝わる言葉に彼女の想いが溢れる。
――私は……!
普通に生きてほしいという、兄としてのゼロの想い。
出来るならば、彼の妹としての生を歩みたいアノンの想い。
この二つをシーナのイシュタルの力で融合させる。
眩い光が空間を包み込んだ。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- ◆パチンコ◆スロット◆
- 大阪府羽曳野市 低貸スロット(2.5…
- (2025-12-02 00:00:10)
-
-
-
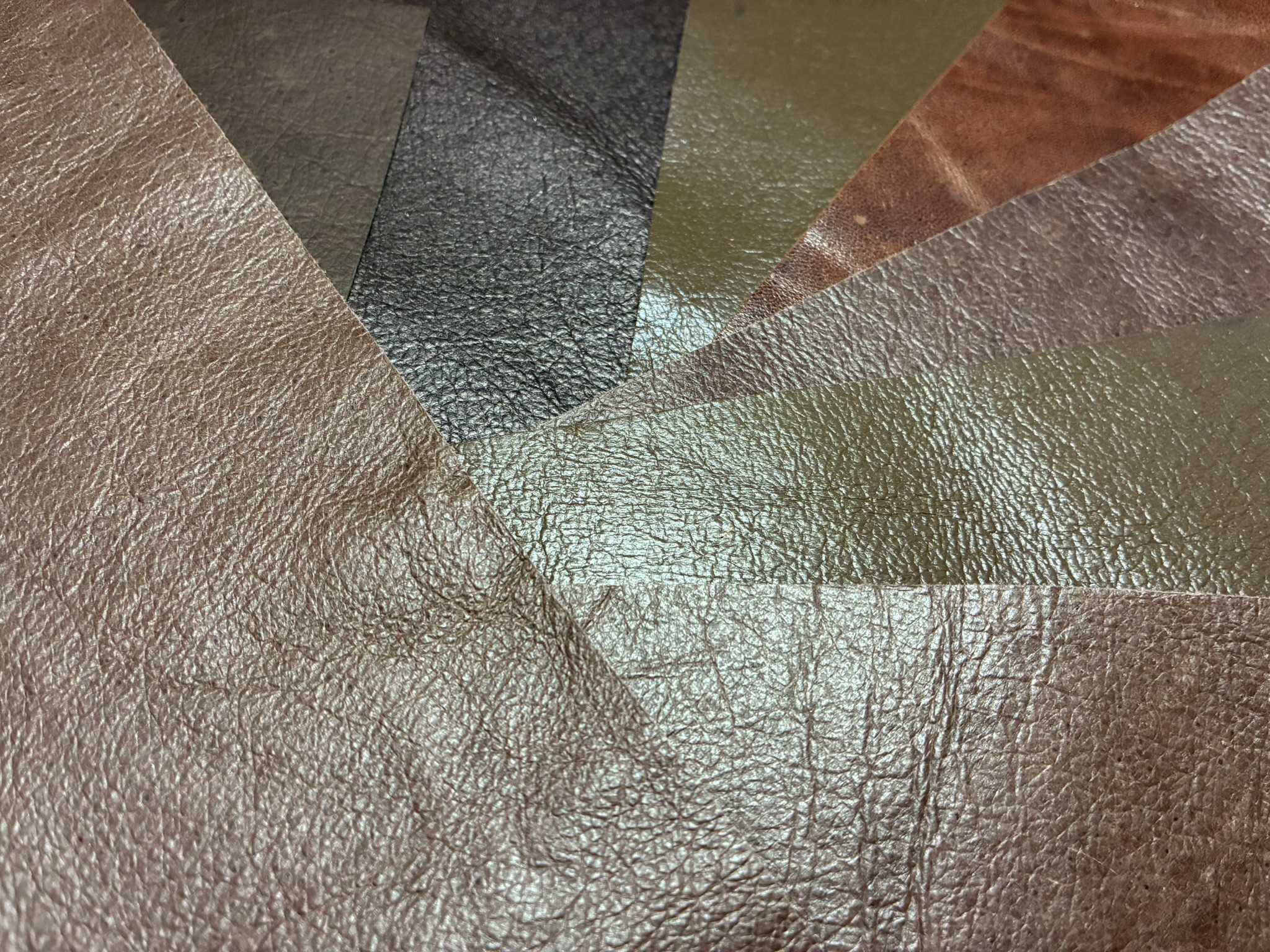
- 何か手作りしてますか?
- カードケースを作る その1
- (2025-12-01 20:08:13)
-
-
-

- 妖怪ウォッチのグッズいろいろ
- 今日もよろしくお願いします。
- (2023-08-09 06:50:06)
-
© Rakuten Group, Inc.



