第3章
始まりの事件南王の結婚式で森が幸せムードを迎えていた2週間後のことだった。
その事件は西の旧コールグレイ領で起こった。
「キャーーー!!」
女性の甲高い悲鳴が商店街に響く。
白昼の商店街には多くの人が溢れていたが、彼らの視線は一か所に集中していた。
路上では3人が、血を流しながら倒れている。まだ呻けるだけの体力を持った者もいるようだが、2人は既にピクリとも動いていない。
そしてその倒れた者らの中心に、赤い液体を滴らせるナイフを持った男がいた。
足元はおぼついておらず、まるで酔っているような歩行。
その瞳に光はなく、人に嫌悪感を抱かせるような笑みを浮かべている。
凍りついた空気に、人々は恐怖からか足を動かせなくなっていた。
「真っ昼間から犯罪とは大した度胸だな」
凍りついた群衆の中から割って出るように2人の騎士が現れる。商店街で帯剣を許されているのは騎士団関係者と自警団関係者の者か、貴族とその護衛だけと法により決められており、簡素ながら鎧を着ていることから彼らが騎士であることが理解できた。
「シィアリア、背後に回れ」
命令を下す青年は銀髪を長く伸ばした、冷たい瞳をした端正な顔立ちの青年だった。この事態にもうろたえた様子はなく、騎士の本分を果たすことだけしか考えていないような雰囲気を感じた。
「りょーかい」
その命令に答えるのは黒髪を肩まで伸ばした女性だった。少しだけ気だるげな雰囲気を醸し出しているが、ナイフ男の背後へ動く足捌きには精錬されたものがあった。こちらも整った顔立ちだ。
「“パターンF”の可能性もある。殺すなよ」
「分かってますよ!」
先に男性の方が仕掛ける。真正面から鞘に剣を入れたまま振り下ろす。斬撃ではなく打撃で相手を気絶させようという寸法だろう。だがその鞘は男のナイフで止められた。頭上から振り下ろされた打撃に対し、慣性を無視したかのようにナイフはビクともしなかった。
その異常に男性騎士の表情が一瞬曇る。
「隙ありぃ!」
一方の攻撃を止めているという無防備な脇腹に、シィアリアと呼ばれた女性騎士が先ほどの男性騎士と同じように鞘に剣を入れたまま一撃を放つ。男性の剣より細身の型だが、それでもまともに受けたならば骨折はしそうな一撃だった。
2人の騎士ともに鍛え抜かれた戦闘技術を持っているようだった。
「ぐふっ」
これには流石のナイフ男も苦悶の表情を浮かべる。
「テミス!」
「待ってました!」
男性騎士の呼び声に答えて、群衆の中で一人の青年が高らかに返事をする。振り上げた右腕から光が飛び出し、ナイフ男の体を拘束する。網状系の拘束魔法のようだ。商店街で魔法が使われる場面などそうそうないだろう。
この一連の戦闘に群衆から歓声が上がる。歓声に応える間も置かず、今しがた魔法を使ったばかりの青年はまだ息のある市民へ駆け寄った。簡単ながら治癒魔法を使う。身体の細胞を活性化させ、生命維持活動を促進させるのだ。そして止血を行うことも忘れない。腹部からの出血だったが、一命は取り留めそうだった。手慣れたものである。
「誰か早くこの人を病院に!」
その言葉に群衆も我に返りワタワタと動き出す。体格のいい男性二人が負傷者を運んで行った。
残念ながら他の2名は既に事切れていたようだった。
「オルフェリアスさん、僕は自警団に連絡取って埋葬の手配をしてきますね」
オルフェリアスと呼ばれた青年騎士は、ナイフ男のナイフを奪い、実物の縄で男を拘束しながらその言葉に頷いた。
「ああ、頼んだ」
彼の返事を聞くまでもなくまたもや駆け出していくテミスと呼ばれた青年を見送る。
「これきっと“パターンF”ですね」
「場所が場所だけに、確定だろうな。ついに西でも始まってしまったか……」
通り魔事件の犯人を犯罪者の留置所へと連行しながら、オルフェリアスとシィアリアは深いため息をついた。
この事件が全ての始まりへと繋がっていくことを、その時はまだ誰も気づいてすらいなかった。
場所は移りホールヴァインズ城、事件のあった頃から既に日が暮れる時間まで時計の針は進んでいた。
先ほどまで夕暮れの日差しが執務室の窓から侵入してきていたというのに、気づけば灯りを点けねばならないようだった。
ランプに火を灯そうとしている時に執務室の扉がノックされた。
「ゼロ様、マリメル様の……終わったみたいです」
少しだけ言葉を濁しながらそう報告に来たのはアーファだった。
「何かわかったのか?」
「はい、ですが色々と報告あるようで、円卓での会議を希望されるとのことです」
円卓での会議、それは西の重鎮全員を集めた会議、相当に重要な事態であるということを意味する。元諜報部団長で抜群の判断力を持つマリメルを持ってしても決めかねた内容ということは余程のことなのだろう。
「分かった。とりあえずすぐ集まれる者だけでも召集してくれ」
「はい!」
手早に先ほどまで相手をしていた書類を整理し、すぐさま会議室へ向かう。円卓を希望したのがマリメルならば、彼女はもう既に待機しているだろう。
それは案の定であった。
他の者への召集は今アーファが大至急行っている最中であるから、まだマリメルと諜報部団長のマチュアしか部屋の中にはいなかった。
「“FT”だったんだよな?」
「残念ながら」
彼女が円卓を希望した時点でそれしかないとは思っていたが、案の定の答えに少しだけため息が出てしまった。いずれ必ず西にも回ってくるとは思っていたが、いざ使用者が現れ、こういった事件を起こしたとなると複雑な気持ちになるのは当然のことだろう。
罪もない民が傷つけられたことへの憤りは大きい。
「留置所から地下牢への移送中、ずっと『天使が泣いている』と呟いていました」
「犯人の身元は分かったのか?」
「どうやら貿易行商人だったようです。まだ駆け出しのようでしたが、主に東の商人を相手にしていたようで、きっとそこから回ってきたのでしょう」
マチュアが淡々と種類の内容を報告してくる。
「ふむ」
東が一番FTの被害を被っている、ということは一番流通しているということだ。今回のような事件が頻発しているのかと考えると東王の気苦労が知れていたたまれない気持ちになる。
――ライトさんも大変だな……。
「貿易商に対して検問を設けるかねぇ」
「早期対処で大きくいくのは、ちょっと難しいかな」
割って入ったのはゼロ以外の男声だった。
「早かったな」
この場において今のような口調で発言出来る者は円卓において男女各1名ずつのみ。男性であったということから、姿を見ずとも宰相ベイト・ネイロスであると予想は出来た。
改めて入口を振り返ると同時に何人かの重鎮たちの姿が見えた。
ベイトを筆頭に自分の席へと座っていく。法務大臣のアオガ、商務大臣のクェフィル、外務大臣のアーナンド、内務大臣のネア、親衛隊隊長のテッセン、近衛騎士団長のエキュアがやってきたようだ。
「僕らはたまたま城の中にいただけだよ」
勤務の定時は既に越えているが、今日ばかりはみな“パターンF”、FT関連の事件が起きたためかまだ残っていたのだろう。
「東との貿易をメインに生活していた男、なんですよね」
一応話は聞いていたのだろうが、確認のためかアオガがマリメルに話しかけた。
「そのようです」
淡々とマリメルが質問に答える。その答えに表情を難しくするのは各大臣たちだった。
「東との通商に検問を設置するには証拠も足りませんし、王立騎士団と自警団に警備を強化してもらうのが最良でしょうか」
商務担当として商人の反発は極力避けたいのがクェフィルの本音なのだろう。
「警備の強化なら大丈夫ッスよ」
「自警団は人員的にちょい厳しいな」
まだ来ていなかった4人が同時にやってくる。財務大臣のミシェリラーナン、王立騎士団長のアドルフ、自警団団長のライダー、そして王妃のユフィだ。
「親衛隊だって警備に回りますよ。まさか城内でFT使用者が出ることもないでしょうし、外の警備を拡大するのが最善でしょう」
「でも警備だと常に後手にしか回れませんよね……」
騎士団長たちは警備の強化に前向きだったが、ネアの発言に対しては反論出来なかった。根本的に警備増加による取り締まりでは、事件発生自体は防げず、事件の鎮圧スピードを上げるのと、事件の拡大を防ぐに過ぎない。
「検問も何も、FTの入手ルートを特定しないと対処のしようはありませんわよ」
「ちなみに今回のFTの入手ルートは東との通商で確定なの?」
ユフィの質問が尋問を行ったマリメルへと投げかけられる。
「おそらくそうだとは思われるのですが、ウェフォール家とジオレイル家という名前もでてきており、両貴族が仲介に入った可能性も否定できません」
その情報は全員にとって初耳だった。
「両方北の貴族ですね」
アーナンドがすぐに反応する。北が原産地ということは既によく知れていることだ。となるとその両貴族が畑を管理しているという可能性が一気に高くなる。
「マリメル、尋問内容を書面に起こしてくれ」
ゼロの命令は淡々としていた。
「マリメルが書き終えたら、悪いが至急北のフーラー家に届けてくれるか? マチュア」
「了解です!」
命令を下した時のゼロの視線は誰も見ていなかった。ただ下を向いている。
「今回の件から明日以降は警備を強化する。夜間の警備も、だ」
「夜間は王立騎士団にお任せあれ」
「親衛隊の方にも通達を回します」
「自警団も了解だ」
ゼロの命令に警備担当部署となるメンバーが了解する。
「とりあえず内政面ではまだ対応は取らないでおこう。北から何か通達があればそれに従おう。……そんなところか」
そこでやっとゼロが顔を上げる。
「そうね、1件起きたからって浮き足立たないように気をつけることが1番だね」
最後にユフィが言葉を付け加える。円卓メンバーも同様に頷き、仕事が増えた各騎士団長たちが出ていく。
「夜間の警備の拡大の予算は?」
ゼロの横に立つミシェリラーナンが険しい表情で尋ねる。小さい身体でも発するプレッシャーは強い。
「森の外へ続く街道整備に当てた財源を使うよ。ヒュームとの貿易はまだ始動には至らないなら大丈夫だろう」
むぅ、とミシェリラーナンが黙り込む。彼女もそこを削るしかないと考えていたのだろう。自分の仕事を取られたようで彼女はムッとした表情で会議室から出ていく。
「法整備もまだ必要はなさそうですし、後手後手に回らなければならないのは残念ですが、今は王妃の言うように浮き足立てないようにしましょう。我々の不安は市民に悪影響ですし」
アオガも当面自分の担当が出てこないと確認すると会議室を後にした。勤務の定時は大きく過ぎている。彼らにも本来のスケジュールがあったのだろう。
「東と北相手には多少強気に出てもいいでしょう。何かあれば私が当たるのでお申し付けください」
文官である外務担当のアーナンドの言葉は頼もしい。
ひとしきり大臣たちが退室した後、ライダーがゼロの隣へやってきた。
「ウェフォール家っていやあ、シアラんちだろ?」
その言葉にゼロだけでなく、ユフィやベイトも反応を示す。
シアラ、シアラ・ウェフォールと言えば貴族学校時代のゼロたちの同世代の女性で、ゼロやベイト、ライダーら武術専攻クラスの中で1番の美女だった女性だ。彼らの世代で、第5学年の途中から第6学年の途中まで彼女とゼロが交際していたことを知らない者はまずいないと考えて間違いないだろう。
その名前を聞いてユフィがどことなく不機嫌な表情を浮かべ、ベイトも苦笑を浮かべた。その理由が分からず、アーファとネアが困惑していた。
「関係ない。まぁ、あいつが関わってなければいいな、って思うしかないだろ」
ゼロの表情からその言葉に隠された彼の真意は読み取れなかった。
「ま、シレンだったら何とか計らってくれるよ」
ベイトが言葉を補う。北の諜報部を統べる男、シレン・フーラーもまたゼロたちと同世代の青年だ。
FT関連の尻尾をつかんだ。それだけで今回の事件は大収穫なのだ。
会議室から出たアドルフは地下牢に向かっていった。事件で逮捕された男を見張っているであろう騎士団員を労うためだ。
地下牢への階段を下り、入口の鉄の扉の前に騎士団員が立っていた。
「ご苦労さん。中の男はどうしてる?」
「え、いや……」
言葉を濁す理由が分からずとりあえず中へと入る。尋問室は地下牢に入ってすぐ左手の部屋だ。尋問室というよりも、場合によっては拷問室と言った方が適切な場合の多いのだが。
尋問室の前にも一人の騎士が立っていた。
「オルフェリアスじゃねえか、どうした?」
今日の昼の事件を沈めたチームのリーダーであるオルフェリアス・トギノヤはアドルフと同い年の元虎狼騎士だ。彼の表情は暗かった。
「男の身元から家族なども割り出した。その確認をしようと思ったのだが、これじゃどうしようもない」
その言葉を聞いて嫌な予感がした。恐る恐る尋問室の扉を開けた瞬間に襲い来る錆びた鉄の臭い。久しく忘れていた嫌悪感がよみがえる。戦場でもここまでの臭いを嗅ぐことはなかなかあるまい。
「確かに、これじゃあどうしようもないか」
手枷と足枷で拘束された男の目に光はなかった。目だけではない、右手と右足も身体から離れ、床に転がっている。身体に残った手足もあり得ない方向に曲がっており、どのような尋問、拷問が行われたのかなど考えたくもなかった。
「殺してやったほうが幸せだろうな……」
オルフェリアスが隣に立ってそう漏らす。
「ここまでやるかね、暗部は」
「全ては陛下のため、なんだろうな」
いつもは軽い調子のアドルフも表情に影を落とす。
「陛下の指示とは思えない、思いたくない……つーかここまでやったって陛下が知ったら、どんな顔するっつーんだよ……」
尋問室の扉を閉めたアドルフの表情は、ゼロへ絶対の忠誠を誓う人物への嫌悪感で溢れていた。
執務室へ戻るゼロにユフィも続く。何となく彼女の話したいことは予測がついたが、自分からその話をふる気にはなれなかった。
「シアラさんのこと助けに行かなくていいの?」
「俺の出番はないよ」
部屋に入りすぐに明かりを点ける。もうすっかり月が高くなっている。今日の分としていた書類がまだ残っているため、ゼロは再び執務室の椅子に座った。机を挟んで体面する形でユフィが話を続ける。
「FTに関わってたら、ただじゃ済まないでしょ……」
ゼロの元彼女、ゼロの初めての彼女であったシアラ・ウェフォールのことをよくは思えない。だが話したことがないわけではないので気がかりなのだ、彼女としても。
「関わってたらその罪は償わなきゃいけない。その裁量を下すのはローファサニさんだし、関わってなかったならシレンが巧くやってくれるさ」
「心配なくせに」
先ほどからあえて冷たく振る舞っているようにしか、ユフィは見えなかった。ずっと彼を見てきているからこそ分かる、ゼロの動揺だ。
「心配じゃないと言えば嘘になるけど、俺の感情であいつだけ便宜を図るわけにはいかないさ。四王としての立場ってのがあるし」
その答えは本音だったのだろう。言ってしまった、という表情をゼロが浮かべる。
だが彼の言い分はもっともだ。悪いことをしたら裁かれる、これが秩序というものだとは子どもでもわかる。
「北の諜報部なら正しい答えを出してくれるさ。上手くいきゃ大元の組織に結び付けてくれるだろうに」
根本の解決のためにはFTを扱っている大元を叩かなくてはならないのだ。
ゼロはこれから忙しくなるであろう北の親友に期待を込めた。
――シレン、頼んだぞ。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- ゲーム日記
- 12周年イベント 黒き導き、白き目覚…
- (2025-12-01 23:23:27)
-
-
-

- 気になる売れ筋おもちゃ・ホビー・ゲ…
- [楽天市場]「カレンダー」 検索結…
- (2025-12-01 20:36:11)
-
-
-
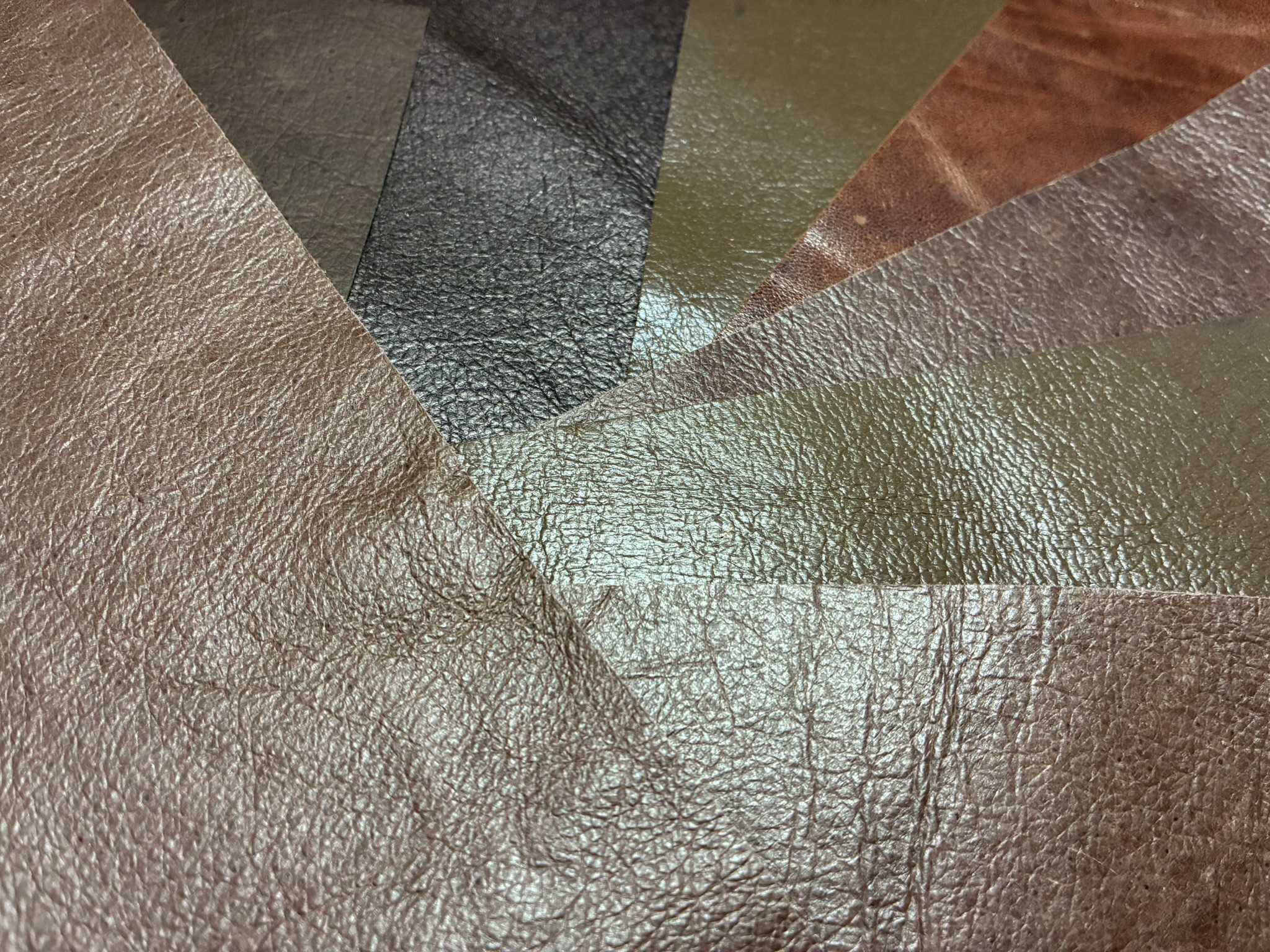
- 何か手作りしてますか?
- カードケースを作る その1
- (2025-12-01 20:08:13)
-
© Rakuten Group, Inc.



