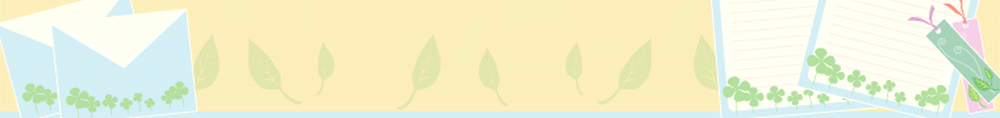カテゴリ: 障がい福祉

図解でわかる障害福祉サービス [ 二本柳 覚 ]

【ふるさと納税】消防ホースリメイクバッグ | 愛知県 愛知 豊田市 豊田 楽天ふるさと 納税 返礼品 支援品 支援 名産品 特産品 バッグ リメイク バック かばん 鞄 カバン ファッショングッズ 日本 お土産 リサイクル エコ ファッション 消防 雑貨 おしゃれ 小物 消防ホース
障害福祉サービスとは?種類・対象者・費用・利用方法などを解説
障害福祉サービスは、障害のある方の生活や就労をサポートするためのサービスです。障害の状態や受けたい支援内容に合わせて、様々なサービスが用意されています。
サービスには介護給付と訓練等給付があり、全部で18種類に分かれています。
障害福祉サービスの種類や利用料、利用の流れなどについて詳しくご紹介します
障害福祉サービスとは?サービス概要や対象者について
障害福祉サービスとは、障害のある方が日常生活・社会生活を送るために必要な支援を提供する公的支援サービスです。
障害者総合支援法で規定されており、日常生活における課題のサポートを目的とした介護給付と、自立や就労を目的とした訓練等給付の2種類があります。
介護給付・訓練等給付を合わせて18種類のサービスがあり、大きく「生活系、入所系、自立・就労系」に分けることができます。
障害福祉サービスの種類
介護給付
(日常生活の課題をサポート) 訓練等給付
(自立や就労をサポート)
・居宅介護 ・自立訓練(機能訓練)
・重度訪問介護 ・自立訓練(生活訓練)
・同行援護 ・宿泊型自立訓練
・行動援護 ・就労移行支援
・療養介護 ・就労継続支援A型
・生活介護 ・就労継続支援B型
・短期入所(ショートステイ) ・就労定着支援
・重度障害者等包括支援 ・自立生活援助
・施設入所支援 ・共同生活援助(グループホーム)
福祉サービスの種類
前述の通り、障害福祉サービスは生活系、入所系、自立・就労系に分けられます。それぞれのサービスについて見ていきましょう。
生活系
日常生活での困難を抱える人に向けたサービスです。
居宅介護
ホームヘルパーが自宅に訪問し、生活全般のサポートを行うサービスです。
利用対象者は、18歳以上の身体・知的・精神に障害のある方で障害支援区分1以上と認定された方、または18歳未満のこれに相当する障害児になります。
居宅介護の主な類型とサービス内容は以下の通りです。
居宅介護の主な類型とサービス内容
サービスの類型 サービス内容
身体介護 利用者さんの身体に直接触れて行う介助サービスで、入浴・排泄・家事などの介助を行います。
家事援助 身体介護以外の日常生活を援助するサービスで、調理・洗濯・掃除・買い物などを行います。
通院等介助 利用者さんが医療機関に行くまでの準備や移動を介助するサービスで、車両の乗り降り・受診手続きなどを行います。
その他 生活全般に関する相談、助言、援助など。
重度訪問介護
障害が重度な方を対象とした居宅訪問型のサービスです。
ホームヘルパーが自宅や入院先、入所先へ訪問して、食事・入浴の介助や相談・助言、意思疎通などのサポートを行います。
自宅に訪問して介護を行うという点では居宅介護と同じサービスに思えるかもしれませんが、両者には以下のような違いがあります。
居宅介護と重度訪問介護の主な違い
居宅介護 重度訪問介護
対象者 18歳以上の身体・知的・精神に障害のある方で障害支援区分1以上と認定された方、または18歳未満のこれに相当する障害児 障害支援区分4以上で、二肢以上に麻痺等があり、歩行・移乗・排尿・排便のいずれもが「支援が不要」以外に認定されている方
サービス内容 ・身体介護、家事援助 ・身体介護、家事援助
・コミュニケーション支援、見守り支援
対象者については、重度訪問介護の障害区分は4以上となっており、居宅介護に比べるとより重度な精神障害や知的障害または肢体不自由者が対象となっています。
また、重度訪問介護のサービスには、日常生活におけるコミュニケーション支援や見守り支援などが含れるため、事前に決めた支援計画と異なるサービスが提供できない居宅介護に比べ、突発的な事に対しても柔軟に対処・支援してくれるのが特徴です。
同行援護
視覚障害のある方が外出する際に危険にさらされないように行動するための情報を提供したり、行動時のサポートを行うサービスです。
行動援護
知的障害・精神障害を持った方の外出時、危険を避けるため、食事や排泄などをサポートするサービスです。
療養介護
医療処置や医師の管理下での介護・看護が必要な障害がある方を対象としたサービスです。機能訓練、日常生活の介助、医療的ケアが行われます。
生活介護
身体障害者や知的障害者、精神障害者などが利用する各施設などにおいて、障害者の自立支援を行います。
日中における、入浴や食事などの介助や、創作活動や身体機能の維持・向上に関するサポートを受けられます。
重度障害者等包括支援
重度の障害を持ち、意思疎通や行動に大きな困難を抱えている方に対する、全般的な支援を提供するサービスです。
生活介護や行動援護など、様々な障害福祉サービスを組み合わせて、その方に合わせたサポートを行います。
入所系
障害のある方が自宅を離れ、環境が整った施設に入所してサポートを受けるサービスです。
短期入所(ショートステイ)
一緒に暮らしている家族の病気療養中など、短期間のみ施設に入所し、介助(支援)を受けながら生活を送ることのできるサービスです。
施設入所支援
施設に入所している障害がある方に向けた、夜間の支援サービスです。
日中の生活介護と同様に、食事や入浴、着替えなどの身体介助や、生活を送るうえでの相談・助言を行います。
共同生活援助(グループホーム)
他の障害がある方と共同で生活を送る中で、夜間や日中の相談、介助(支援)を受けながら暮らすことができるサービスです。
グループホームに入所して共同生活を送る形のほか、グループホーム近くのアパート等で暮らし、必要な時にグループホームの世話人・支援員のサポートを受けられる、一人暮らしに近いサービスも用意されています。
自立・就労系
障害のある方が自立して生活を送るための支援や、就労するための訓練を受けられます。
就労移行支援
就職を目的として、障害を持った方が一般就労に必要な職業訓練を積むことのできるサービスです。障害を持った方の中で、18歳以上65歳未満の一般就労が見込まれる方が利用できます。
生活リズムの安定や、ビジネスマナーの習得、自分の障害についての理解など、障害を持った方が働く上での幅広い訓練を受けることが可能で、利用期間は最大2年間です。
就労継続支援A型
一般就労には課題のある障害者が、事業所と雇用契約を結び、障害に配慮した作業を行いながら最低賃金を得られるサービスです。
就労継続支援B型
一般就労には課題があるが、利用回数・利用時間など自分のペースで働きたい障害者に対し、障害に配慮した働く場を提供するサービスです。
就労継続支援A型との違いは、雇用契約を結ばないことで賃金の代わりに工賃を得ることができます。
就労定着支援
就労移行支援・就労継続支援・自立訓練・生活介護などのサービスを利用して一般企業での就職に結びついた方が働き続けることを目的としたサービスです。
就労定着支援員が、仕事をしていると出てくる様々な困りごとに対して助言を行ったり、必要に応じて企業との環境調整を行ったりします。就労後半年経過後から最大3年間、利用することができます。
就労定着支援だけを単体で利用することはできず、あくまで前述の就労支援サービスなどから一般就労に至った方だけが利用できるサービスです。
自立生活援助
障害者がひとり暮らしをしている、または始めるにあたり、定期的な巡回や助言などを行って安心・安全な暮らしをサポートするためのサービスです。
対象者は以下のように定められています。
自立生活援助では、支援員が定期的に利用者さんの居宅を訪問することになっており、下記のような項目を確認のうえ、必要に応じて助言や他の福祉サービスとの調整などを行います。
自立訓練(機能訓練)
身体的な生活能力の向上を目指して、リハビリテーションなどの機能訓練や、生活上必要な助言・相談などのサービスを行います。
自立訓練(生活訓練)
生活能力の向上を目指して、食事や入浴、金銭管理やコミュニケーションの取り方などについて、日常生活に必要な訓練・相談、助言を行います。
宿泊型自立訓練
自立した社会生活に向けて、一定期間施設の中で暮らし、生活に必要な様々なこと(家事、金銭管理、身の回りの世話など)を自身で行えるように訓練するサービスです。
障害福祉サービスの対象となる人
障害福祉サービスの対象となるのは、身体障害、知的障害、精神障害、難病患者のいずれかに当てはまる方です。
18歳未満の障害児の場合は、障害福祉サービスの他に児童福祉法に基づくサービスを受けることもできます。また、65歳以上の方は、原則、介護保険サービスの利用が求められます。
ただし、これまで利用していた障害者向けのサービスが介護保険になかったり、介護保険で提供されるサービスを利用するだけでは日常生活に支障をきたす場合など、65歳以上であっても障害福祉サービスを利用できるケースが多くあります。
また、各障害福祉サービスには障害支援区分によって利用できないサービスがあります。
例えば居宅介護の場合、対象者は障害支援区分1以上と定められており、他のサービスにも以下のような要件があります。
このように、障害の程度により利用できるサービスも変わってくるため、詳しくはお住まいの地域にある役所の障害福祉担当課窓口にお問い合わせください。
障害福祉サービスを利用するには?
障害福祉サービスの利用には、市区町村が発行する障害福祉サービス受給者証(※通称:受給者証)が必要になります。
受給者証には氏名、生年月日、住所、サービスの種類、支給量・期間などが記載されており、障害福祉サービス利用のための資格証のようなイメージで捉えていただくと分かりやすいかと思います。
受給者証取得のためには、必要書類を市区町村へ提出し、障害福祉サービスの必要性を判断するための面談などが行われた後、受給者証を発行してもらうことができます。
受給者証取得の流れについては、利用の流れと一緒にご紹介します。
障害福祉サービスの利用料
障害福祉サービスを利用する時の自己負担額は1割です。例えば5,000円のサービスを利用する場合の負担額は500円で、わずかな金額負担だけでサービスを利用できる仕組みになっています。
障害福祉サービスの利用料は、世帯所得によって額が定められています。
B型事業所の利用者負担上限月額
区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯(注1) 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満※注2)
入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く(注3) 9,300円
一般2 上記以外 37,200円
(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象
(注2)所得が概ね670万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」
例えば、自己負担上限月額が9,300円の場合、1ヵ月の支払額は次のようになります。
1ヵ月の自己負担額8,000円→8,000円の支払い
1ヵ月の自己負担額10,000円→9,300円の支払い
自己負担上限月額を超えた部分については、国と自治体が負担をしてくれます。そのため、負担上限月額を超えて費用の支払いが必要になることはありません。
ただ、食費や光熱費、グループホームの家賃などはこの月額に含まれないため、別途支払いが必要になります。
また、利用料の区分の対象となるのは前年度の世帯所得となります。居住している市区町村によって条件などが異なることもありますが、就労センターでは多くの利用者さんが自己負担なしで通われています。
利用料の軽減制度
サービスによっては、利用料や食費、光熱費などの軽減制度が設けられているものもあります。
2つ以上の障害福祉サービスを利用している方の場合は、自己負担額が基準額を超えてしまうことがあるため、自己負担額を超えないよう利用事業所が調整してくれる「上限額管理」という仕組みがあったり、同一世帯に複数名、障害福祉サービス利用している方がいる場合も、負担が大きくなるため、払戻しの対象となる事があります。
また、18歳未満の障害がある児童が障害福祉サービスと併用して、児童福祉法に基づくサービスを利用する場合、利用料やその他かかる費用が軽減される措置もあります。
兄弟で利用するなど、同一世帯に複数の障害福祉サービスを利用する場合も、負担額が一世帯分となるよう調整されます。
その他、食費や光熱費などについても、減免制度や給付制度が使える場合があります。
障害福祉サービスご利用の流れ
障害福祉サービスを利用するためには、お住まいの地域にある役所の障害福祉担当課窓口に行き、必要書類を提出して申請をする必要があります。
手続きの流れ
障害福祉窓口に相談・申請
役所の障害福祉担当課窓口で「障害福祉サービスを利用したい」と相談し、申請の流れや必要な書類について説明を受け、必要な書類をそろえて提出します。
利用したいサービスや事業所が決まっていない時には、案内を受けることも可能です。また、障害福祉サービスの相談窓口が分からない場合には、総合案内で教えてもらうことができます。
STEP2
障害支援区分の決定 ※主に介護給付で実施
居宅への訪問や聞き取り、医師の意見などを踏まえて、障害の程度がどの支援区分に該当するのかを決定します。(※認定調査という)
通常、本人やその家族と市区町村担当者のみで行われることが多いですが、自治体によっては、利用予定の事業所の支援員同席が求められる場合もあります。
また、訓練等給付では障害支援区分を認定する必要がないため、認定調査の有無は自治体により様々です。
STEP3
サービス等利用計画案の作成
サービスを利用する目的や内容について記載した計画案を作成します。
相談支援事業所に所属する相談支援専門員が無料で作成してくれる事が多くなっておりますが、自治体やサービスにより、相談支援事業所を利用せずに自身で計画を作成する「セルフプラン」が認められる場合もあります。


サービス担当者会議
必ず実施されるわけではありませんが、障害福祉サービスを利用してどのように生活していくのか決めるため、本人、相談支援専門員、利用予定の障害福祉サービス事業所支援員などで話し合う場を設ける事があります。
支給決定
サービス等利用計画等を踏まえて支給が必要と自治体に認められれば、支給決定となります。
申請から支給決定までの期間は、申請時期や障害の状況、自治体により様々ですが、おおむね1~2か月で決定されることが多いです。
利用開始
障害福祉サービス事業所と契約をして利用が開始されます。この後も、相談支援事業所で作成したサービス利用計画は定期的に見直され、適切にサービスを受けられているか確認していきます。
必要な書類
障害福祉サービス利用にあたり求められる書類は自治体によって異なりますが、次の6点は求められる場合が多いです。
すでに自立支援医療などを利用している場合、医師の診断書が免除される場合もあります。
また、用意に時間がかかるものもあるため、早めにお住まいの地域にある役所の障害福祉担当課窓口に必要な書類を確認し、揃えておくと手続きがスムーズに進みます。
困ったときの相談窓口
障害福祉サービスの利用は、初めての方にとっては聞きなじみのない言葉も多く、手続きが難しく感じる方もいるかと思います。そんな時には次の3つの窓口に相談してみると良いでしょう。
まず、「ひとりで申請するのに不安がある、自分にどんなサービスが合っているのか分からない」など、サービスの利用にあたって全般的な不安がある方は、お近くの「相談支援事業所」へ相談することをおすすめします。
相談支援事業所では、障害福祉サービスについての情報提供や利用にあたっての計画策定などを行ってもらえます。
次に「使いたいサービスはある程度決まっているけれど申請の仕方に不安がある、どんな書類が必要か分からない」という方は自治体の障害福祉窓口に相談すると良いでしょう。
自治体によって必要な書類や申請方法、給付までの期間は異なるため、使いたいサービスが決まり次第できるだけ早めに相談することをおすすめします。
また、すでに利用したいサービスも事業所も決めている方は、その事業所に相談する方法もあります。
事業所職員から自治体に連絡を取り、手続きをサポートしてもらえる場合もあるため、見学や体験などの際に確認してみてください。
障害福祉サービスには多くのメリットがある
生活する上でのメリット
障害福祉サービスを利用することにより、必要なサポートを受けながら地域活動への参加ができ、安心して将来を歩める可能性が高まります。
生活する上でのメリット
相談できる場所が増える
社会とのつながりを持てる
特性に合わせたサポートが受けられる
生活リズムを整えることができる
配慮が整った環境で安心して生活できる
本人や家族だけで抱え込まなくてよくなる
働く上でのメリット
障害福祉サービスを利用することで、自分のペースで社会復帰や就労を目指すことができるようになります。
働く上でのメリット
収入を確保することができる
自分のペースで社会復帰ができる
自立に向けてサポートを受けながら働ける
最適な職場を見つけるためのサポートを受けられる
働き続けるためのサポートが受けられる
自分に合う障害福祉サービスを探すには?
自分に合う障害福祉サービスを探すためには、重視するポイントを決めた上で、いくつかの事業所を見学・体験することをおすすめします。複数の事業所を比較する中で、一番自分に合っている事業所を選ぶのが良いでしょう。
事業所を比較するときのポイントもご紹介します。
事業所を比較するときのポイント
作業や訓練内容が自分に合っているか
事業所・職員さんの雰囲気
利用日数・利用時間
送迎や食事の有無
落着ける空間かどうか
例えば、「お金に困っている場合」は、送迎ありや食事無料の事業所を選ぶと満足度が高くなるでしょう。
また、作業内容や訓練内容が自分に合っているかどうかも大切なポイントです。
パソコン作業をしたいのに軽作業しかない就労継続支援B型事業所に通ってしまうと、ミスマッチが生じて通い続けることが難しくなってしまうかもしれません。
何を重視するのか考えたうえで見学・体験に臨むことで、より自分に合ったサービスを選択することが可能です。
自分の得意・不得意や体力に合わせて作業をしながら自分のペースで働きたい希望をお持ちでしたら、就労センターへご相談ください。
就労センターでは、様々な企業からお仕事の依頼を受けており、パソコン作業や軽作業など豊富な種類の作業をご用意しています。
その中で、利用者さん一人ひとりの作業適性を見ながらお仕事を提供しているため、自分に合った作業を自分のペースで行えます。
また、昼食の無料提供やご自宅までの無料送迎も行っています。通所リズムもその方に合わせて、昼まで利用や昼から利用も可能で、週1日から始められるため、無理なく自分のペースで通っていただけます。
本記事では障害福祉サービスの内容と利用方法についてご紹介しました。
障害福祉サービスとは、障害のある方が地域で当たり前に暮らせるように、生活や自立・就労をサポートするものです。利用することで専門的な支援を受けながら安心して生活を送れたり、自分に合った就労ができたりします。
色々な事業所を見学・体験して、自分に合った内容や雰囲気の場所を見つけることで、より納得してサービスを受けることができるはずです。
今回の記事で、障害福祉サービスの利用を検討したいと思われた方は、お住まいの地域にある役所の障害福祉担当課窓口へお問い合わせください。
この記事が障害福祉サービスを利用する一助となっていただければ幸いです。最後までお読みいただきありがとうございました。
#障害者 #ピアカウンセラー #パソコンインストラクター #出張 #福祉用品 #ニュース今日の報告です
☆----------------------------------------------------------------☆
悩み事や福祉制度の相談、パソコンサポートのご依頼の方は
ogayasu(☆)gaia.eonet.ne.jpへ
※(☆)は@に打ち変えてください
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[障がい福祉] カテゴリの最新記事
-
【今年の障害年金ニュース3選】支給件数の… 2025年11月26日
-
ウェルビーイングとは?意味や働き方改革… 2025年11月25日
-
透析続けながら8時間勤務 テレワーク用い… 2025年11月25日
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.