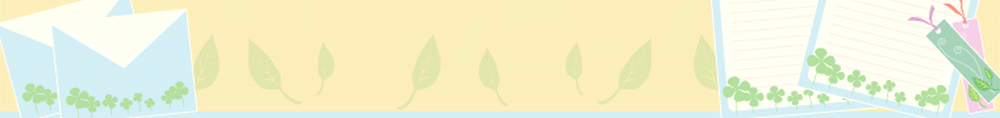カテゴリ: 障がい福祉

☆7月 誕生石 ブレスレットパワーストーン ブレスレット カーネリアン サンストーン 【幸運 目標達成】パワーストーン ブレスレット レディース ハワイ 送料無料

【クーポンで10%OFF】ライトニングクォーツ 原石 産地 ブラジル Lightning Quartz 雷水晶 稲妻水晶 マスタークリスタル 天然石 鉱物 1点もの 現品撮影 LNC-154
メリット①目標を達成しやすくなる
行動力があると、考えて悩む時間や労力を短縮できるので、目標が達成しやすくなります。
「ああなったらどうしよう」「細かく計画を立てないと」と考えていると、いつの間にか行動できなくなってしまいますよね。
周りよりも先に行動できる人は、失敗した際のリカバリーも人より早く行えます。
人よりも先に失敗を経験し、すぐに対策法を考え、行動すれば目標達成までも早いですよね。
目標達成までが早くなることが、行動力を磨くメリットです。
考えすぎをやめたい人は、以下をご覧ください。
なぜ考えすぎてしまうのか、5つのタイプ別にみていきましょう。
・タイプ①完璧を目指すあまり考えすぎる
・タイプ②周りの評価や意見を気にするあまり考えすぎる
・タイプ③不安を感じて先のことを考えすぎる
・タイプ④過去の出来事に囚われて繰り返し考えてしまう
・タイプ⑤一人で解決しようとして抱え込んでしまう
タイプ①完璧を目指すあまり考えすぎる
完璧を目指す人は、絶対に間違った選択をしたくないと考えます。
そのため「もっといい選択肢があるのではないか」「これを選んだ場合、こうなってしまうのではないか?」と不安が強くなり、考えすぎてしまうのです。
完璧を目指す人は、失敗しないためにはどうすればいいのかを考えすぎるため、すぐに行動に移せません。
しっかりと計画を立てて進めていきたいといった完璧主義な人や、真面目な人に多く見られます。
タイプ②周りの評価や意見を気にするあまり考えすぎる
周りの評価や意見を気にしてしまうがゆえに、考えすぎてしまうタイプもあります。
自己肯定感が低い人に多くみられ、自分自身や行動に自信がないため、決断できず考えてばかりになってしまう状態です。
たとえば「あの人がこう言ったから」「●●さんが」など、決断をする際に人に流されている人は注意しましょう。
いざ自分で決めようとすると、自分の意見が他の人からどう評価されるのかが気になり、考えるだけで終わってしまう可能性があるからです。
タイプ③不安を感じて先のことを考えすぎる
考えすぎる人は、先のことに対して過剰な不安を持ったり、未来に対して悪いイメージを持ったりします。
たとえば地震が起こったらどうしようと不安になるあまり、あらゆることを想定しすぎて防災用品が多くなってしまうのもこのタイプです。
感受性が強く敏感な人や、心配性の人に多く見られます。
不安を感じることは社会的に必要なことなのです。
しかし「ああなったらどうしよう」「こうしておかなくては」と考えている内に、行動できるタイミングを逃してしまいます。
タイプ④過去の出来事に囚われて繰り返し考えてしまう
過去の出来事に囚われて、繰り返し考えてしまうタイプもあります。
以前自分がした選択や行動に対して、後悔や自己責任を感じて繰り返し考えてしまうのです。
「あの時どうしてこんな言い方をしてしまったんだろう」「このことをしておけば失敗しなかったのに」と、気持ちの切り替えが苦手な人に多くみられます。
過去の自分と上手く折り合いがつけられていないため、記憶の中で同じことを反芻してしまうタイプです。
タイプ⑤一人で解決しようとして抱え込んでしまう
一人で解決しようとするため抱え込んで考えすぎてしまう人もいます。
責任感が強い人や、コミュニケーションが苦手な人に多く見られるタイプです。
親に甘えられない環境で育った場合や、相手との信頼関係がなくコミュニケーションが上手くできないで抱え込んでしまう場合もあります。
考えすぎをやめたい人におすすめの7つの方法
ここからは、考えすぎをやめるための方法を7つ紹介します。
どれも気軽にできる方法なので、気になったものからぜひ取り入れてみてください。
考えすぎる自分から抜け出していきましょう。
・方法①自分の思考パターンを理解する
・方法②考えていることを紙に書きだす
・方法③まずは行動してみる
・方法④考える時間を制限する
・方法⑤別のことに集中する
・方法⑥他の人からアドバイスをもらう
・方法⑦マインドフルネスを取り入れる
方法①自分の思考パターンを理解する
自分の思考の癖を理解することで、結論を出しやすくなります。
地図を見るように一歩引いて見ることができれば、別の解決策を考えやすくなるからです。
たとえば思考の癖を理解している人は「自分はこのパターンを選んで失敗したから、次はこのパターンでやってみよう」と早く切り替えられます。
自分の癖がわかれば、いつの間にか考えすぎることもやめられるでしょう。
方法②考えていることを紙に書きだす
考えていることを紙に書き出すのもおすすめの方法です。
というのも、頭のなかで思っているだけでは、考えがまとまらないからです。
何か物事を考えているとき、実は同じところをぐるぐると回っているだけで進んでいない場合があります。
なので、考えていることを一度、紙に書き出してみましょう。
たとえば、下記の方法は重複している言葉や同じつながりと思える事柄、派生している単語が明確になるのでおすすめです。
・フローチャート
・マインドマップ
・リスト
自分が今何に困ったり悩んだりしているのかを整理するために、頭のなかの問題や頭をよぎることはすべて書き出してみましょう。
方法③まずは行動してみる
案ずるより産むがやすしということわざがあります。
リスクやこれから起こることを考えすぎる前に、少しずつでもいいので思い切って行動してみましょう。
実際のところ、行動してみないとわからないことや気づかないことが多くあるからです。
たとえば自転車にはじめて挑戦したとき、どうやれば成功するか何日も考えてから乗った人は少ないでしょう。
実際にやってみると、自分が考えていた通りに進まないことも多々ありますが、考えてばかりいても何も経験を積めないままになってしまいます。
自転車のときと同じように、まずは乗って漕いでみること、考えるより先に行動してみることも大切です。
方法④考える時間を制限する
人は制約の多い状況に置かれると創造する力が向上する、といわれています。
なので考える時間を制限すると、考えすぎを予防できるでしょう。
ビジネスのアイデアを出すときにも、時間制限はよく使われますよね。
「5分だけ」「通勤時間だけ」「寝る前の10分」など考える時間を決め、決めた時間内は考えることに集中します。
つい長い時間悩んでしまうという習慣を区切ることで、上手く切り替えができるようになりますよ。
気がついたらずっと考えている人は、身近にあるスマホのタイマー設定を使ってあらかじめこの時間だけ考える、と自分に制限をかけてみましょう。
方法⑤別のことに集中する
別のことに集中することも、考えすぎることをやめる方法です。
人間は基本的に、同時に2つのことを考えられないといわれているからです。
考えすぎているなと感じたら、散歩やサイクリングをするなど他のことに集中できる環境に身を置いてみましょう。
特に運動は体を動かすことに意識が向くため、心が無の状態になりやすくなります。
趣味のことに集中したり、別の環境に身を置くのもおすすめです。
別のことに集中すると、頭のなかで考えていた問題が、少しずつ自分のなかで受け流しやすくなります。
物理的に考えている時間もなくなり、考えていた問題との距離がうまく取れるでしょう。
方法⑥他の人からアドバイスをもらう
人を頼ることも、考えすぎることをやめる方法です。
自分ひとりで考えていても同じことを繰り返し考えてしまったり、結論がでないことがありますよね。
他の人に相談してアドバイスをもらうことで、「そんな見方があったのか!」と自分のなかにはない考えや解決法を見つけられます。
あなたが今抱えている考えや悩みは他の人も悩んだ経験があるものです。
一人で悩まずに、他の人に「これってどう思う?」と相談してみてください。
きっと相談するとこれまで持っていた荷物が降ろせたように、心が楽になっていることでしょう。
方法⑦マインドフルネスを取り入れる
マインドフルネスを取り入れることも、考えすぎないための方法です。
マインドフルネスは今に集中できるような状態を作ることで、瞑想方法のひとつとして有名になっていますよね。
考えすぎで思考が行き詰まった時は、マインドフルネスを取り入れて自律神経を整えたり、心身ともにリラックスさせる習慣をつけましょう。
考えすぎによるデメリットとは?
・決断力が鈍る
・ストレスの増加
・時間の浪費
・パフォーマンスの低下
・コミュニケーションに障害が生じる
・クリエイティブな能力の低下
何かを良くするために考えているつもりでも、考えすぎることで結果的に何も行動できなくなったり、心配や不安が生じて新しいアイデアも出にくくなります。
結論が出ないと考えた時間が無駄になり、得られるはずの経験も得られないなど、チャンスを逃してしまうでしょう。
ある程度考えることは大切です。
しかし、行き過ぎてしまうと生活面や心理面にマイナスに働いてしまいます。
マイナスだけじゃない!深く考えることのメリットとは?
・リスクを回避できる
・解決策を発見できる
・計画を詳細に考えられる
・多角的な視点が持てる
・他の人が見落としがちな細やかなところに気づける
・人の気持ちを考えられることから相手を尊重できる
全員が効率だけを考えていると、誤った方向に行っていても気づかないことがあります。
考えることができる人は、「●●のリスクがあるのではないか」とストップをかけられるので、チームが冷静になる時間が生れます。
失敗しないようにとコミュニケーションを取ろうとするため、ミスにも早く気づけるでしょう。
考えすぎることは一概に悪いことではなく、他の人にはない大きな強みにもなるのです。
※
考えすぎをやめる方法を紹介しました。
今回、お伝えしてきたことをまとめます。
考えすぎる人にもタイプがある
考えすぎることをやめるには思考の癖を理解して、頭のなかを整理することが大切
時間を制限したり、違うことに集中したりすると、考えがリセットできる
考えすぎることで決断力が鈍くなったり、時間の浪費につながったりするのがデメリット
考えすぎることでリスクの回避ができたり、細やかに計画を立てられたりするメリットもある
考えてばかりいることで次第に心が疲弊してしまったり、決断できない自分に落ち込んでしまう人もいるでしょう。
ぜひ今回紹介した方法を使って、少しずつでもいいので状況を変えていってください。
いつの間にか「考えすぎる性質」が「行動に移せる自分」になって自信につながってきますよ。
メリット②良好な人間関係を築ける
行動力を高めると、周りとの関係も変わってきます。
自分が行動することで、周りに協力してもらうことや助言をもらう機会が増えるからです。
今まで関係がなかった人と連絡を取ったり、良い影響がある人とより親密なコミュニケーションをとったりすることが多くなるでしょう。
行動力を磨くことで、今までとは違った人間関係を構築できます。
メリット③ビジネスチャンスが広がる
行動力を磨くことで、これまで以上にビジネスチャンスが広がります。
というのも、多くの場所に出向く機会が増え、新しい人脈ができるからです。
出会い以外にも、成功体験や失敗体験など多くの経験を積むことができるでしょう。
行動した経験から知識や学びを得られれば、仕事の精度をさらに高めることができ、自身のできる仕事の幅が広がります。
新しいビジネスのヒントを得たり、仕事の質を高めたりできることが、行動力を磨くことのメリットです。
行動力を鍛える6つの方法
冒頭でお伝えしたように、行動力は特別なスキルではありません。
行動力は今からでも身につけることができますよ。
ここでは、行動力を鍛える6つの方法を紹介するので、ぜひできることからチャレンジしてください。
・方法①行動する目的を明確にする
・方法②簡単なことから始めてみる
・方法③期日を設定する
・方法④自分で考えて自主的に動く
・方法⑤選択肢を多く持つ
・方法⑥上手くいっている人から学ぶ
方法①行動する目的を明確にする
行動力を鍛えるなら、具体的な目標や目的をはっきりとさせておきましょう。
他の行動に流れたり、目移りしたりすることなく、目的に添った行動がしやすくなるからです。
大切なのは、何をやるべきかが明確に自分でわかることです。
「いつもギリギリでやっている営業資料作りを余裕をもってやれるようになりたい」なら、「毎日5分早く出社して、気持ちを仕事に切り替える時間を作る」「先輩に仕事量の調整を相談する」とやるべきことが見えてきますね。
綿密な計画は必要ありませんが、理由や目的がしっかりがあると、人は行動しやすくなります。
方法②簡単なことから始めてみる
行動力を磨こうと考えた際は、簡単なことから始めてみましょう。
いきなり大きなことに取り掛かろうとすると、ハードルが高すぎて行動できなくなるからです。
初めは「実際に今すぐできる」くらいの、小さな挑戦をしてみてください。
最初は簡単なことから取り掛かると、次第に行動力がついて、すぐにできる自分になっていきます。
方法③期日を設定する
行動力を鍛えるためには、期日を設定する方法もあります。
先延ばしをする癖があるという人は、「これまでにこうしよう」と期日を設定しましょう。
人は流されやすい性質があるため、行動したいと思っていても面倒になったり、後回しをしたりするからです。
スケジュール帳に書く、メモを貼っておくなど、期日は目で見れるところに書いておくのがおすすめです。
ぼんやりと「あれはあの日までに」と記憶しているだけでは、忘れるリスクがあります。
いつまでにやるべきことなのか、小さなことでも締切を決めると、行動力を高められます。
方法④自分で考えて自主的に動く
他の人からの指示を待っていたり、人に流されていては行動力はつきません。
なぜ人に流されやすいのか?影響されやすい性格の直し方
・人に流されやすい人の特徴は?
自分の意見を言える人になりたい!
流されやすい性格と合った仕事はある?
行動力を磨くなら、目の前のことに対して、何ができるか自分で考えて自分から行動しましょう。
たとえば、「これは先輩に聞かないとわからない仕事だからやらない」と行動することを諦めてはいけません。
マニュアルに書かれている内容はないか、無理のない範囲で進められる部分はないか確認するなど、諦める前に自分ができることは多くあるからです。
受け身の仕事をしていると、行動できる自分の像からは遠ざかってしまうでしょう。
自主的に動いていけると自分を信頼できるようになり、行動力を高めることができます。
なぜ人に流されやすいのか?影響されやすい性格の直し方
・人に流されやすい人の特徴は?
・自分の意見を言える人になりたい!
・流されやすい性格と合った仕事はある?
人の意見に流されてばかりで嫌になることはありませんか。
「わたしは人に流されやすい性格だから仕方ない」と諦めてしまってはもったいないです。
その場では流していても、自分の本当に思っていることをずっと言えていない状態のため次第にストレスが溜まってしまいます。
そこで、この記事では、人に流されやすい性格の直し方を紹介します。
流されやすい人の特徴や、性格を活かした仕事もまとめました。
ぜひ記事を読んで、流されやすい性格から脱し、自分らしさを磨いていきましょう。
なぜ人に流されやすいのか?流されやすい人の特徴5つ
コミュニケーションを円滑にすることを優先しすぎて、自分を後回しにすると人に流されていると判断されてしまいます。
誰しも他人との距離感やコミュニケーションには悩むものですよね。
どういった人が流されやすい人なのか、より詳しく5つの特徴を見ていきましょう。
・特徴①周りからの見られ方が気になる
・特徴②自分に自信がない
・特徴③面倒くさいことが嫌い
・特徴④相手の気持ちを考えすぎる
・特徴⑤流行りに敏感
特徴①周りからの見られ方が気になる
流されやすい人は、周りの人と意見を合わせることで安心したいと考える傾向があります。
会議で自分の意見があるのにも関わらず、周りが何もいわないので仕方なく話を合わせることはありませんか。
周りからの視線が気になりすぎる人は守りの姿勢になってしまい、結局は他の人の意見に同調してしまいます。
同じ意見や考えを持つことで周りから浮かないようにしたり、他人から嫌われないようにしたりするのが、流されやすい性格の特徴です。
特徴②自分に自信がない
他の人の意見に流されてしまう性格は、自分に自信がない人によく見られます。
「これについてどう思う?」と聞かれても、自分の意見に自信がないため、他の人に同調した答えを出してしまいます。
自信がない原因は責任を負うことを怖れていることや、判断できるほどの情報や知識を持っていないことなどが考えられるでしょう。
他の人にどうしたらいいのか判断を委ねてしまうのも、人に流されやすい特徴のひとつです。
特徴③面倒くさいことが嫌い
面倒くさいことが嫌いなために、自分の意見を通さない人もいます。
自分の意思で、他の意見に同調しているパターンです。
たとえば同じ方向に行くとみんなが言っているのに、自分が違う方向に行きたいと主張すると、意見の衝突や周りの人を説得する必要がでてきますよね。
反対の意見を通すためには相手が納得できる落としどころを探して、自分がどう思っているかを伝えてと、通常よりも時間や考えることが増えます。
なかには無意識のうちに、人に流されることで面倒なコミュニケーションを省いている人もいるでしょう。
面倒だからといって「これでいいんじゃない」と同調してばかりになると、いい加減な性格、自分で考えない人と見られてしまいます。
特徴④相手の気持ちを考えすぎる
相手の気持ちを考えすぎることで、自分の意見がいえない人もいます。
相手の希望や意見に合わせて、いい人だと思われたい、相手に嫌われたくないという気持ちから話を合わせてしまうのが特徴です。
会議でどう思うか問われているのに「他の人は賛同してほしいだろう」と、何も意見を言わない人は、相手の気持ちを考えすぎて流されてしまっているので注意しましょう。
ポジティブな思考もやりすぎると、流されやすい性格になってしまいます。
サービス精神が旺盛で目の前の人に喜んでほしいと思うがゆえに、自分の気持ちを伝えられない人もいるでしょう。
ネガティブな思考、ポジティブな思考どちらにも、人に流されやすい特徴があります。
特徴⑤流行りに敏感
流行に敏感なことも、流されやすい人の特徴です。
流行りに敏感なことは、悪いことではありません。
周りと同じことをすることで、不安や孤立感を感じないよさもあるでしょう。
しかし流行っているからという理由だけで行動や考えを変え、大きな流れに逆らわず生きることが普通になると、人に流されている性格になってしまいます。
流行を理由に決断する人は、「流されやすいよね」といわれてしまうこともあるでしょう。
影響されやすい性格の直し方!克服するための6つの方法
流されやすい性格を直すにはどこまでが他人の意見を聞いていいか、自分で譲れない部分はどこかなど、自分で線引きすることが大切です。
今回は人に流されやすい性格を直す6つの方法を紹介します。
・方法①小さな成功体験を積み重ねる
・方法②自分の意見を持つ重要性を理解する
・方法③自分の本当の気持ちを伝える
・方法④アサーションスキルを身につける
・方法⑤一人で考える時間を設ける
・方法⑥知識やスキルを習得する
方法①小さな成功体験を積み重ねる
人に流されやすい性格を直すには、自信をつけることが大切です。
というのも、自信を持てるようになれば、自分の考えや意見にも価値があると感じられるからです。
小さな成功を自分で積んでいくことで、自信へと変えていきましょう。
「今日も朝、予定していた時間に起きられた」「朝ご飯を食べることができた」など、日常のなかでできていることも小さな成功体験になります。
小さなことでも「できた!」という成功体験を積み重ねることで、ポジティブな自己イメージを持てます。
肯定感が高まり、いい意味で他人を気にしなくなるので、人に流されなくなるでしょう。
方法②自分の意見を持つ重要性を理解する
「自分の意見なんて価値がない」と、考えたことや湧いてきた感情に蓋をしていませんか。
自分の意見を持つ重要性を理解することも、流されやすい性格を直すためには大切です。
他の人の意見に価値があるのと同じように、自分の意見にも価値があります。
たとえ相手とは反対の意見だとしても、現在の状況をより良くするために、自分の意見を伝えてみてください。
伝える際は相手を尊重して、お互いが納得できる落としどころを探すと、関係を壊さずコミュニケーションができるでしょう。
気持ちを伝えたことが自己肯定感につながり、周りの意見に左右されない自分を作っていくことができます。
方法③自分の本当の気持ちを伝える
流されやすい性格を直すためには、自分の本当の気持ちを伝えましょう。
周りの意見に合わせることは、その場を和ませるために必要と思っていたかもしれません。
しかし意見がぶつかっても、ポジティブに話を進めることはできます。
たとえば参加者がうなづいてばかりの会議より、意見を出し合う会議の方が早く終わり、計画もまとまりやすかったことはありませんか。
みんなが意見を言わないでいた場合、結局は何も伝わらず時間の浪費になってしまいます。
会議や会話であなたが他人を尊重するように、他人もあなたを尊重してくれます。
「自分はこう思う」と本当に思っていることを伝えても、円滑なコミュニケーションができるのです。
本音が言える関係性を作れれば、人に流されなくなるでしょう。
方法④アサーションスキルを身につける
人の意見に流されずに、自分の意見を出す方法としてアサーションスキルを身につけましょう。
アサーションスキルとは、相手を傷つけずに、しっかりと主張を行うというコミュニケーションスキルのことです。
アサーションスキルで使えるのは「I(私)メッセージ」や「DESC法」です。
「I(私)メッセージ」を使うと、「私は~~思う」「私は~~で悲しい」と自分の感情を伝えつつ、相手を否定しないで意見が言えます。
DESC法は、「Describe(描写する)」「Express(説明する)」「Suggest(提案する)」「Choose(選択する)」の4つのステップで会話を進める方法です。
たとえば、このように会話を進めていきます。
「相手:このA商品の資料を、明日までにまとめてもらえるかな?
あなた:この書類の整理が15時までに終われば、明日の午後にはA商品の資料を提出できますよ。(描写)
相手:できれば明日の午前中には欲しい資料なんだけど・・無理かな?
あなた:早めに提出できれば良いんですが、明日の午前中は難しいです。(説明)
相手:そっか・・・
あなた:お昼ごろになら提出できると思いますが、それでは間に合いませんか?(提案)
相手:ん~そうだな。会議が午後イチだから、午前中がいいんだよな・・・
あなた:どうしても午前中までということでしたら、書類整理を代わってもらえないか確認してみます。(選択)」
アサーションスキルが身についてくると、自分の意見を言っても相手を傷つけないことが次第にわかってきます。
相手に自分の気持ちを伝えることも楽になるため、人に流されなくなるでしょう。
方法⑤一人で考える時間を設ける
流されやすい性格の人には、ひとりで考える時間を設けることをおすすめします。
流されやすい性格の人は、他人のことばかり考えているからです。
会社にいる場合は会社、家庭に戻ったら家庭での役割、恋人と一緒のときにも恋人に気を遣うなど、自分の気持ちを理解してあげる時間が少ない傾向があります。
ひとりだけの時間を持ったり、眠る前に日記をつけるなど、自分を優先する時間を作りましょう。
身の回りにあった事実や、考えたことを振り返ることで「自分ってこの時こう考えていたんだ」と自己理解が深まります。
思い込みや周りの意見は絶対に正解ではないことにも気づけるでしょう。
自分の思いと相手の意見を客観的に見ることができ、人の意見に流されない自分になっていきます。
方法⑥知識やスキルを習得する
人の意見に流されないようにするには、自分で意見を言えるほど知識やスキルを手に入れることが大切です。
客観的な判断を下すことができ、「情報ではこうだけれど、こちらから見るとこういう視点ではこうだ」と他人とは違う意見が出しやすくなるからです。
・会社内での情報
・家庭での会話
・本
・勉強会
・資格の取得
このように、さまざまなことから見識を増やしていきましょう。
物事をさまざまな角度から見られる広い視野を持つことで、意見を求められやすい人材にもなれます。
知識やスキルが身につくことでも、人の意見に流されない自分になれるでしょう。
ブレない自分になることで得られるメリット
・自分を信頼して自分に自信が持てるようになる
・目標を達成し、自分自身に新たな可能性を見出すことができる
・状況が困難になった時にも自分軸を元に冷静に対処できる
・心身ともに健康でいられる
周りに影響されない人は、自分のやりたいことや理想の姿をしっかりを見つめられます。
なりたい自分がわかれば、理想の実現に向けて行動しやすくなります。
自己成長も早くなり、自己肯定感を育みやすくなりますね。
影響されやすい性格の長所とは?流されやすい人に向いてる仕事
影響されやすい性格の人の長所は素直さや、柔軟性、協調性などです。
下記のような仕事で長所を活かせるでしょう。
・カスタマーセンターなどのサポート業務
・事務などのアシスタント業務
・手順や作業工程などマニュアルがしっかりとしている仕事
上記にある以外にも「あなたに話を聞いてもらうとホッとする」など言われた経験のある人はカウンセラー向きかもしれません。
感性が鋭い特性があればアーティスト向きの人もいるでしょう。
人に流されやすい性格を活かすというよりは、自分の特性を見つめて、自分の特徴と合っている仕事を探すことが大切です。
探していく中で「この仕事なら楽しい!」と思える適職がきっと見つかるはずですよ。
◎
流されやすい性格の直し方を紹介しました。
これまで紹介してきたことをまとめてみましょう。
・流されやすい人は周囲の目を気にしすぎている傾向がある
・自分に自信がないことも、人に流されやすい性格の特徴
・小さな成功体験を重ねると自分に自信をつけられ、人に流されなくなる
・相手を尊重しつつ自分の意見を言うには、アサーションスキルを身につけることが大切
・自分の意見にも価値があることを理解すると、人に流されない軸を持てる
※流されやすい性格について、短所ばかりではなく長所もあります。
「自分自身を変えたい!」と考えたら、今回紹介した方法を参考に、目指す姿に少しずつ近づいていきましょう。
あなた自身が生き生きとしてくる環境に身を置けるよう、さまざまな方法を試していってくださいね。
方法⑤選択肢を多く持つ
行動力を鍛えるなら、全てのことに対してアクションする必要はありません。
行動すること、行動しないこと、どちらも選択肢だからです。
行動力を高めるなら、選択肢を多く持つことが大切ですよ。
先ほどあげた、先輩に聞かないとわからない仕事について考えてみましょう。
自分でできることをしっかり確認して、独断でやるべきではないとわかったから「やらない」のであれば実行していませんが、行動力はありますね。
「リスクや不安を考慮したうえでやらない」といった選択肢を持つこと、リスク管理ができる人は行動力のある人です。
多くの選択肢を持つことを意識すると、行動力も鍛えられますよ。
方法⑥上手くいっている人から学ぶ
成果を上げている人や実際に行動力のある人は、上手くいく習慣が身についています。
仕事の優先順位のつけ方や関係者へ連絡を取るタイミングなど見よう見まねでいいので、真似をしましょう。
行動できる人の真似をする内に、自然と自分自身も行動力のある人に近づくことができますよ。
自分が真似したいと思える人に焦点を当て、その人の仕事のこなし方などを観察しましょう。
なりたい人の真似をするべき理由を、以下で詳しく紹介してるので、ぜひご覧ください。
◎
なりたい人の真似をするべき3つの理由!真似のやり方も紹介
・なぜなりたい人の真似をするべきなの?
・理想の人の真似をするとどんな影響がある?
・なりたい自分になる方法が知りたい!
なりたい自分になるには、なりたい人の真似をするのが近道です。
しかし、人の真似をしていては自分らしさが失われてしまい、むしろなりたい自分からは遠ざかってしまうと不安になる人もいますよね。
人の真似という言葉になんとなくネガティブなイメージがつきまとっていて、躊躇してしまう人もいるでしょう。
そこで今回は、なりたい人の真似をするべき理由や、理想の人の真似をすることで得られる影響を詳しく紹介します。
本記事を読めば、なりたい人の真似が、なりたい自分になるための近道であるとわかります。
なりたい人の真似をしつつも、なりたい自分になるための一歩を踏み出してみましょう。
なりたい人の真似をするのが良いと言われる3つの理由
真似という言葉を調べてみると、『形だけ似た動作をすること』と辞書に書いてあります。
世間一般的に真似をすることに対してネガティブなイメージがついているのは、こうした意味合いから、真似は上っ面だけ似ていて中身は伴っていないという認識があるからでしょう。
しかし、人はこの世に生まれたとき、真似をしながら成長していきます。
言葉は親や周りの人たちから、文字はお手本の真似をして覚えましたよね。
つまり真似をすることはネガティブなことばかりではなく、ポジティングなこともあるのです。
なりたい人の真似をするのが良い理由には次の3つがあるので、それぞれを詳しく見てみましょう。
・理由①目標を設定しやすい
・理由②成功までの本質がわかる
・理由③失敗しないための基本
理由①目標を設定しやすい
自分が目指すべき人物像がイメージしやすいことが、なりたい人の真似が良いとされる理由です。
憧れの対象が同じでも人によって何に憧れるかは違います。
尊敬している部分の違いによって目標は変わりますね。
たとえば、モデルのCさんに対してAさんはスレンダーな体型に、Bさんは日々努力を続けるCさんのストイックさを尊敬しているとしましょう。
Aさん:Cさんが行っている運動や食事管理を真似する
Bさん:Cさんの言動や書籍などから生き方や考え方を学ぶ
このように憧れの対象は同じでも、人によって目標が違うので行動が変わってきます。
なりたい人がいて、なりたい人の何を真似したいのかが見えていると、なりたい人に近づくために何をすべきかがわかりやすくなります。
理由②成功までの本質がわかる
あなたがなりたい人の真似をすると「理想としている人が過去にどのような努力をしてきたのか」その過程を知ることができ、あなた自身も成功への道筋や本質がわかりやすくなります。
あなたがなりたい人も、過去には憧れを抱いて誰かの真似をしています。
今の姿は、一夜にして手に入れたものではありません。
本人は意識していなかったとしても、人は周囲の他人に影響を受けながら、今の自分を作っているのです。
なりたい人の真似をすることで成功の要因や失敗したときの対処法、経験値の積み方や役立つ資格など、自分の理想の叶え方がわかるでしょう。
理由③失敗しないための基本
ビジネスにおいて真似をするのは、効率的に事業を行う上での基本です。
世の中には、同じ商品が同じ売り方で販売されていますよね。
ポテトチップスはどのメーカーも袋に入れて販売している
販売されている歯磨き粉のほとんどがチューブ型
ポテトチップスが袋に入って売られているのは、窒素を入れて膨らませることで、空気に触れにくくして酸化を防いでいるからです。
歯磨き粉は粉とあるように元々は粉でしたが、現在主流の練り歯磨きが売られるようになると、ペースト状の中身を出しやすいように日本のライオン株式会社がチューブを開発しました。
どちらも世界各国で採用されている売り方ですよね。
つまり今ある商品の売り方は試行錯誤の結果、それが売れるとわかっているものなので、真似すれば失敗する可能性を低くできます。
ただし、真似をするだけではただの二番煎じとなってしまい、他社との差別化が図れません。
似たように見える商品でも、それぞれ個性やオリジナリティで勝負しています。
なりたい人を真似する場合も、そっくりそのまま真似をするのではなく、あなたらしさを失わないように意識することが大切です。
なりたい人の真似で変わる5つの良い影響とは?
なりたい人を真似するのは、理想や憧れの人に自分を近づけるだけではありません。
次の5つの良い影響を、自分に与えることができます。
・影響①客観的な視点を持てる
・影響②ポジティブ思考になれる
・影響③辞めるべきことがわかる
・影響④スキルを習得できる
・影響⑤周りの環境が変わる
影響①客観的な視点を持てる
トラブルや悩みに直面したとき、多くの人はそれまでの自身の経験や価値観などから「どうするべきか」「何をしたらよいのか」を考えます。
しかし、なりたい人がいると、「あの人ならどう考えるだろうか」というまったく別の視点で物事を捉えられるようになります。
同時に、自分自身を外から見つめる機会も得られるので、自分の考えが凝り固まってしまっていると気づくことがあるでしょう。
新しい視点から得られた気づきは、新しいことにチャレンジする意欲をくれたり、逆に行動力にブレーキをかけたりします。
これまでとは違う習慣を取り入れることに躊躇する気持ちを和らげてくれるでしょう。
なりたい人の真似をすることで自分とは違う考えや視点など、冷静に判断や選択するための材料が増えます。
影響②ポジティブ思考になれる
誰かの真似をしたいと思うとき、その人の良い面や明るい部分を自分も取り入れたいと思うものです。
嫌な面や暗い部分を真似したいとは思いませんよね。
つまり、なりたい人の真似をする時点で、真似をしたい人のポジティブな思考が加わり、真似をしている自分も自然とポジティブ思考になっていきます。
思考が変われば振る舞いや行動が変わるので、理想の自分へと近づいているという実感によってモチベーションが上がり、継続する力も身についていきます。
影響③辞めるべきことがわかる
なりたい人の真似をすることで、今まで「何となくそう感じる」と信じてきた価値観が、理想の自分になるためには不要なものだったと気づけます。
なりたい人の真似をする際には、理想とする人が「やらないこと」にも目を向けるからです。
たとえば、あなたは1人でも多くの人脈を持つことが仕事の成功につながり、理想の自分の実現には欠かせないと信じているとしましょう。
そのため、飲み会の声がかかったら面子に関係なく、必ず参加していたとします。
しかし、あなたがなりたい人は、名刺を交換するだけの時間を過ごすくらいなら仕事をしたほうが効率的だと考えているので、浅い関係の人との飲み会には一切参加しません。
あなたとは真逆の考え方です。
なりたい人の真似をしていると、理想の自分になるために足りていないものがわかるだけではなく、今の自分が持っている不必要なものもわかるようになります。
影響④スキルを習得できる
最初からホームランを打てるバッターはいません。
初めて描いた絵が、プロ顔負けのセンスを持ち合わせていることもありません。
ホームランを打つためにホームランを打っている選手のフォームを研究したり、プロのイラストをトレースしてテクニックを自分に取り入れていく必要があります。
人の真似をせず、0から積み上げたほうが自分の力になることもありますが、膨大な時間がかかりますよね。
誰かの真似をするということは、その人が長年をかけて培ってきたスキルを短期間で利用させてもらう、ということにもなります。
0から1になるスピードが速ければ、2,3と積み上がっていくスピードも上がりますね。
空いた時間を有効に使えるので、その人以外のスキルも併せて取り入れていけばより多くのスキルを得られるようになります。
なりたい人の真似をすることは0ではなく1からのスタートなので、スキル習得が早く、より深くできるでしょう。
影響⑤周りの環境が変わる
自分を変えたいと思っていても、これまでは周囲にいる自分と似たような人から、「変わるはずがない」とネガティブなことをいわれて諦めていたのではないでしょうか。
そこから脱するには、環境を大きく変えるのが一番の近道です。
あなたがなりたい人が自分とはかけ離れた人の場合、あなたは今までとはまったく違う環境に身を置くことになります。
当然ながら交流する人も変化するので最初は少し戸惑うかもしれませんが、あなたがなりたい人の周辺には、なりたい人に似たポジティブ思考の人がたくさんいます。
自分を変えたいといったら、「きっとできるよ」と前向きに応援してくれるでしょう。
自分を変えることを肯定的に捉えられるので、自分らしくいられるようになります。
なりたい人を真似する5ステップ
なりたい人の真似をするといっても、具体的に何をしたらよいのかよくわからない人は多いでしょう。
なりたい人を真似するには、次の5つのステップを行います。
・ステップ①なりたい人物像を設定する
・ステップ②外的要素を真似する
・ステップ③内的要素を真似する
・ステップ④自分の型に落とし込む
・ステップ⑤考えるよりまずは行動する
ステップ①なりたい人物像を設定する
なりたい人を真似するには、なりたい人が必要です。
まずは、「こんな人になりたい」と憧れる人を選びましょう。
なりたい人は身近な存在でも、芸能人のような身近な存在ではない人でも構いません。
もっといえば、現在は亡くなっている偉人でも、実在しないキャラクターでも良いでしょう。
身近な存在の場合、積極的にコミュニケーションをとったり一緒に行動する時間を多くすればその分観察することができるので、なりたい人から得られるものは多くなります。
芸能人や偉人、キャラクターであれば、過去のインタビューや書籍などを読み、なりたい人の思考や行動を分析してみましょう。
ステップ②外的要素を真似する
なりたい人物像を設定したら、外的要素を真似していきましょう。
外的要素とは、たとえば次のようなものです。
行動
仕草
呼吸
間合い
話し方や意見の言い方
声のトーン
表情
なりたい人の話し方は耳に届きやすく、説得力もあると感じるのであれば、その話し方を真似できればあなたの話も多く人を納得させられるものになりますよね。
とはいえ、ただ声のトーンや間合いを真似しても、それは単なる真似にすぎません。
行動や仕草のひとつひとつについて、なりたい人が何を伝えたいのか分析することがとても大切です。
ステップ③内的要素を真似する
内的要素とは、行動に至る原因となる性格や思考を指します。
内的要素を真似するには、なりたい人の行動を真似し、なぜその行動をとるのか考えてみるのがよいでしょう。
行動は外的要素にも含まれていますが、内的要素の場合は行動そのものに注目するのではなく、行動に至る考え方に重きが置かれます。
なぜなら、人の行動には潜在意識が深く関わっているからです。
潜在意識とは、人の脳のなかで意識できていない領域を指すものです。
潜在意識は過去の経験や価値観などによって形成されているため、その人の本質の部分であるといえます。
つまり、なりたい人が無自覚で行っている行動を観察し、行動に至る考え方を習慣づけられるようになると、あなた自身の潜在意識がなりたい人の潜在意識と近くなります。
それによって、同じ行動や考え方が自然とできるようになるでしょう。
ステップ④自分の型に落とし込む
なりたい人を選び、その人の外的・内的要素を真似するのは、なりたい人を真似してなりたい自分を作るための「ベース」部分です。
ここまでの作業であれば、それはなりたい人に似たような人ができただけですよね。
ここから、あなたらしさを取り入れて「自分」という唯一無二のモデルを完成させましょう。
積極的に行動する憧れの人を真似しつつ、心配性である自分の慎重さも大切にして、「適切に素早く判断できる人になる」のように自分らしさも取り入れてみてください。
ステップ⑤考えるよりまずは行動する
最後に深く考え込まずに、とにかく真似をしてみましょう。
人の真似をするのは、思っている以上に難しいですよね。
人の話し方や行動、思考などを真似するということは、それまでのあなたの生き方や価値観を否定する形にもなります。
真似をする真意をしっかりと掴みモチベーションを保ちながら、考えすぎる前に行動してみましょう。
※
なりたい人を真似するべき理由や、真似をする方法を紹介しました。
最後に、これまでの内容を簡単にまとめます。
なりたい人を真似すると目標や道筋がわかりやすい
真似によって自分以外の視点や価値観が加わる
ポジティブ思考になれる
なりたい人を選び、外的・内的要素を真似することから始めてみる
なりたい人の真似をベースに個性を出す
真似は、人が成長する上でもビジネスでも成功の基本となるものです。
素敵な人を見つけたら、真似したい部分はどんどん吸収し、自分の強みに変えていきましょう。
【注意点】行動力を高める際に覚えておくべきこと
行動力を高める際は、リスクも考えてください。
特に周りや会社に迷惑がかかるケースでは、行動力よりも実行力を身に付けたほうがいいでしょう。
毎回「行動力が必要だから」と一か八かで賭けにでるような仕事では、会社としての損失が大きくなってしまいますよね。
あなたの任された仕事は、すぐに行動すればビジネスチャンスを掴めるでしょうか。
行動力を高めて大胆に攻めるとき、計画性や慎重さも考慮するときなど、シーンで使い分けることが大切です。
※
これまで行動力を持った際のメリットや行動力を鍛える方法、注意すべきことを紹介してきました。
これまでのことをまとめてみましょう。
・行動力を高めることで目標達成もしやすく、他者との関係も良くなる
・やろうと思っていることの期日を決めると行動力が鍛えられる
・行動しないことでも、行動力は鍛えられる
・上手くいっている人の真似をして行動できるコツを身につける
・ケースバイケースで行動力や実行力を使い分けることが大切
行動するハードルが高すぎるのなら、超えられそうな部分を見つけ実際にやってみましょう。
行動するか、しないかを決めているのは自分自身なので、行動できない悩みを変えられるのも自分だけです。
習慣や生活、仕事など、始められるところから行動力を鍛えていきましょう。
#障害者 #ピアカウンセラー #パソコンインストラクター #出張 #福祉用品 #ニュース今日の報告です
☆----------------------------------------------------------------☆
悩み事や福祉制度の相談、パソコンサポートのご依頼の方は
ogayasu☆gaia.eonet.ne.jpへ
※直接入力の際は(☆)は(@)に打ち変えてください
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[障がい福祉] カテゴリの最新記事
-
透析続けながら8時間勤務 テレワーク用い… 2025年11月24日
-
考えすぎる性格を直したい!何でも深刻に… 2025年11月23日
-
苦手だらけの場所で大興奮! 自閉症の娘と… 2025年11月23日
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.