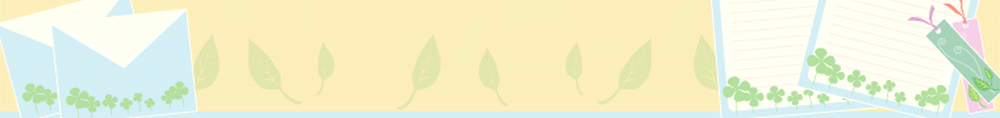カテゴリ: 障がい福祉

お試し価格で大変お買い得!「ペットクリーンお試しセット」(スプレー+詰替え) 粗相 ペット臭 トイレ 犬 猫 小動物 うさぎ おしっこ うんち 臭い 多頭飼い 複数飼い ペット臭 アンモニア臭 ブラッシング 次亜塩素酸 消臭除菌水

立体型アイマスク 安眠マスク ブラック 3D ブラック 黒 安心 安眠 圧迫感なし 3D構造 目隠し 遮光マスク メガネの上から着用可 メイク中もOK
「成長したいですか?」
そうきかれたら、あなたはなんと答えるでしょうか?
※
「もちろん!」
があなたの答えなら、
※
「コンフォートゾーン」について知っておくといいかもしれません。
「自分に変化を起こしたい」「もっと成長したい」と感じている方は、ぜひ読んでみてください。
※
日本では、3つの円(コンフォートゾーン、ストレッチゾーン、パニックゾーン)で表されるモデルがよく知られていますが、この記事では、少し異なる視点から4つのステップに分けたモデルを紹介します。
安心の領域(コンフォートゾーン)とは?
コーチングや心理学でよく使われる
※
「コンフォートゾーン(安心の領域)」
とは、私たちが
※
「自分のコントロール下にある」
と感じられる空間を指しています。
昔々、私たちが野山に暮らしていた頃。住んでいる洞窟は安全な場所で、その外側、狩りにでる森や草原は敵がいる危ない場所でした。
「ここにいると安心」
そういう空間を、私たちは昔から知っていたように思います。
安心の領域(安全と感じるコントロール下にある)→恐れの領域→学びの領域→成長の領域
例えば、
※
いつものお店や道、なじみの人々に決まったやり方。
コンフォートゾーンは、私たちが生きるうえで大切な役割を果たしています。
※
心理的な安全が保たれる
ことで、心の健康を守り、無意識にルーティン化できるため、効率も高まるのです。
人は「変化を好まない」生き物だと言われていますが、それは
※
変わらないこと=安心できる
ことだから。たとえば「早起きできない」「転職に踏み切れない」といった悩みも、変わるより同じ場所にとどまる方が脳にとっては安全だと感じるためです。
その一方で、コンフォートゾーンは、
※
人の成長を阻む
ことがあります。同じことを繰り返すだけのこの領域には、「変化」がありません。
※
成長とは、変化していくこと
ー安心な場所にとどまり続けているかぎり、私たちは成長することができないのです。
これから、コンフォートゾーンを越えた先に続く、成長のステップを一緒に見ていきましょう。
恐れの領域(フィアーゾーン)
コンフォートゾーンを抜けて最初に出会うのは、
※
「フィアーゾーン(恐れの領域)」
です。その名の通り、私たちが恐れや不安を感じる空間です。
生まれたときから、一度も洞窟を出たことがない人にとって、洞窟の外は、未知と恐怖に満ちた世界だったことでしょう。どこで水が手に入るのかもわからない。何日も食べ物にありつけないかもしれないという不安。
勇気を出して一歩踏み出してみても、聞いたことのない獣の咆哮に恐れおののいて、結局、洞窟へと駆け戻ったかもしれません。
安心の領域→恐れの領域(言い訳を探す 他者の意見に影響を受ける 自信がない)→学びの領域→成長の領域
社会人になったり、転職したり、起業したり。
※
何か新しいことを始めるとき、私たちは不安になったり、自信を失ったりします。
慣れ親しんだものから離れ、知らない世界に飛び込むのは、誰にとっても居心地が悪いものです。
このフィアーゾーンにいるとき、私たちはつい、
※
コンフォートゾーンに戻るための言い訳を探してしまいます。
「どうせ無理だからやめておこう」「まだ早いからまた今度にしよう」
そんな頭の声が、ささやき始めるのです。
さらに、
※
周囲の意見にも敏感になりがち
です。「~したほうがいい」「~すべきではない」といった声に揺さぶられ、知らない世界へ進む勇気を失いかけることもあります。
※
大切なのは、このフィアーゾーンは一時的な場所だということ。
怖れに向き合い、小さな一歩を積み重ねていけば、やがて次の領域へと自然にたどり着くはずです。
学びの領域(ラーニングゾーン)
フィアーゾーンの外側にある「ラーニングゾーン(学びの領域)」は、私たちが、新しい学びや経験を得られる空間です。
少しずつ洞窟の外に慣れ、世界を探求する余裕が生まれると、目の前に新しい風景が広がりはじめます。どこに水場があるのか。どこで果物が採れるのか。どうやって狩りをするのか。未知だったことが少しずつ、「知っていること」へと変わっていきます。
「どうしたら、より大きな獲物を仕留められるのか」など新たな課題は次々に現れても、それはもう、洞窟の中で怯えていた頃の悩みとはまったく違うものになっているでしょう。
※
安心の領域→恐れの領域→学びの領域(新しいチャレンジや問題を扱う コンフォートゾーンを広げる)→成長の領域
ラーニングゾーンではとにかく、「やってみる」→「フィードバックを手に入れる」→「学びや気づきに変える」のプロセスが繰り返されることになります。新しい仕事のやり方でも、プライベートの新たな活動でも、自分なりのやり方を構築していくステージです。
分からなかったことに慣れていくうちに、それらはやがて、コンフォートゾーンに変わっていきます。輪の境界線が広がるように、安心できる領域が外へと大きくなっていくのです。
もちろん、ラーニングゾーンの中でも新たな課題は現れます。コンフォートゾーンが広がるたび、その外側にはまたフィアーゾーンが生まれるからです。それでも、
※
「これまでも、わたしは境界線を越えてきた」
という経験と確かな自信が、次の一歩を後押しする勇気になってくれることでしょう。
成長の領域(グロウスゾーン)
成長のプロセスの最終段階は、
◎
「グロウスゾーン(成長の領域)」
です。挑戦と学びを繰り返すうちに、人は自然とこの領域へと足を踏み入れ、新たな夢や目標へと意識が向かうようになります。
大昔の人々がこんな思いを馳せていたかは分かりませんが、「私もいつかマンモスを仕留める」「いつかこの大きな水たまりの向こうの大陸に行きたい」のような夢を抱いていたとしたら、なんだかつい微笑んでしまいます。自分なりの明確な目標を持って日々を暮らすとき、それはとてもワクワクする充実した時間だったのではないでしょうか。
※
安心の領域→恐れの領域→学びの領域→成長の領域(目標を達成する 新たなゴールを設定する 自分の目標を見つける 夢を実現させる→自信や信念がある)
グロウスゾーンでは、人はとても自由です。
※
「自分は何のためにこれをやっているのか」
という目的をしっかりと認識し、失敗やリスクを恐れず、自分の限界に果敢にチャレンジする力があります。少し難しい課題にも積極的に踏み出し、さらなる学びと成長の機会を自ら作り出していきます。
組織で言うならば、上から与えられた目標をこなすだけではありません。「こんなチームにしたい」「こんなことを実現したい」といった自分なりのビジョンを掲げ、その実現に向けて
※
挑み続ける主体性
も育まれていることでしょう。
コンフォートゾーンを出るかどうかで何が変わるのか?
他者の学びや成長のサポートをしている私のコーチとしての性質上、つい「コンフォートゾーンを出ようぜ!」みたいなノリになっちゃうのですが、じゃあ
※
「コンフォートゾーンは出るべきなのか?」
という問いについては
※
「場合による」
と思ってます。
特に今メンタルが落ちている状態の人にとっては、無理にコンフォートゾーンを出ようとするとかえって苦しくなっちゃうこともあるんじゃないかなと。
ただ「このヒドイ咳の原因は、洞窟の中に生えてるキノコだった」みたいなケースはあるかなと思うんです。つまり今いる環境が、自分の状態にかなりの負の影響を与えている場合。そういう時には「洞窟を出て冒険!」みたいなことにチャレンジしないまでも、
※
「他の洞窟を探す」
ことが助けになることもあるかもしれないですね。
で、ここからは心身ともに健康だけど「前ほど仕事にやりがいを感じられない」「最近ちょっと飽きを感じている」みたいな方にお話ししたいのですが、コンフォートゾーンを出るかどうかって、けっこう大きな違いが日常に生まれるんじゃないかと感じています。
創造性のスイッチ、新たなチャンスとの出会い、成長と学び。今の枠から出ることで得られるものはとても多いので、以下で紹介しています。もっと深めてみたい方は、こちらもどうぞ。
※
コンフォートゾーンを出るかどうかは、私たちにどんな影響を及ぼすのか
安心の領域とも呼ばれる「コンフォートゾーン」は、私たちが誰でも持っているもの。「コンフォートゾーンと成長の領域」にも書いたのですが、そこを出るかどうかは「個人の判断」に委ねられていると思っています。人生には色々なことが起こりますし、それぞれのタイミングがあると思うので。
一方で、自分がコンフォートゾーンを出るのを阻む外的要因は何も無くて、自分の心ひとつでどちらにも行けるという場合。コンフォートゾーンを出ることを選ぶか、出ないことを選ぶか(変化を起こそうとするかどうか)で、どんな違いが生まれてくるのでしょうか?
私自身にとって「人生で一番大きな変化」は、16年やっていた職人から個人起業したとき。しかも職業をコーチに変えていますから、ダブルでインパクトのある変化でした。この記事では、その経験の中で感じたことも織り交ぜながら「コンフォートゾーンを出るかどうかが与える影響」について、それぞれのケースについて考えてみたいと思います。
コンフォートゾーンを出ないことで起こりうる影響
現状を変えたいという思いがあるにも関わらず「コンフォートゾーンを出ない」ことを選んでいる場合、以下のようなことが起こりうるかもしれません。
成長の停止
植物を鉢植えで育てる時、小さな鉢を使うとある一定以上の大きさには育たなくなります。コンフォートゾーンの中に留まり続ける、それは言葉を変えると
◎
「成長が止まってしまう(又は非常にゆっくりになる)」
ことを意味するかも。コンフォートゾーンとは「いつもの〇〇」であり、そこには変化がありません。何も変えなくても普通に生きていけるため、キャリアや個人的な成長が遅れてしまうことがあります。
自信の欠如
やってみたいことがあるにも関わらず、チャレンジしない状態を続けていると、
◎
自分に自信が持てなかったり自己肯定感が低くなりやすいかもしれません。
というのも、その際頭の中で「私には出来ない」「私はダメな人間だ」などのセルフトークが起こり、自己評価を低くする連鎖になりやすいから。
コンフォートゾーンの中に留まることを「洞窟」に例える時、それは洞窟から全く出ずに生きることを意味します。外の世界を知らないということは、聞こえてくる生き物の咆哮や天気の移り変わり、様々なことが
※
「見えない」「分からない」
という状態ですから、漠然とした不安を抱えやすかったり、ちょっとした変化に対してもストレスを感じやすいかもしれません。
ルーティン化による飽き
「いつもの〇〇」の良さは、考えないで済む&決断の回数が減ることによる、効率性や居心地の良さです。一方で、同じことをずっと繰り返していると、全てがルーティン化され飽きやすくなる可能性があります。コンフォートゾーンの中に留まることを(無意識にでも)選んでいると、もしかすると色んなことについて「面倒くさい」と感じやすくなるかもしれません。
また見ている世界が限定的になりやすいため、様々な視点から物事を捉えようとするのではなく、(自分でも気づかないうちに)ある一点からの物の見方を「正しい」と信じやすいかも。
機会の損失
人生を将棋やチェスに例える時、ある一つの駒を動かすことによって、様々な可能性の扉が開いたということはよく起こります。コンフォートゾーンの中に留まるとは、
※
駒を動かさずに現状維持する
ということ。それによって、様々な機会が失われる可能性があります。例えば新たな学びや経験を積むための機会、自分に刺激を与えてくれるような人と知り合う機会、異なる視点を手に入れる機会、人としてもっと成長する機会などです。
モチベーションの低下
幸せホルモンとも呼ばれる「ドーパミン」は新しいことや困難なことに取り組むことで、分泌されます。このドーパミンが出ているかどうかは、私たちのモチベーションを大きく左右するそうです。コンフォートゾーンの中ではこのドーパミンが出る機会が少ないため、
※
モチベーションが低下しやすくなります。
またモチベーションが高いとは、ある特定の物事に自分のエネルギーが集中している状態です。コンフォートゾーンの中では特に注意を向けなくても出来てしまうことが多く、エネルギーを注ぐべき「明確な対象(目標)」が無いため、
※
やりがいや達成感を感じにくい
という側面もあるかもしれません。
自分の職人時代を思い返してみると、不思議と「自信の欠如」や「機会の損失」はあまり感じたことがありませんでした。で、よくよく考えてみると、「成長を感じられない」「飽きてきた」「モチベーションが上がらない」みたいな状況になると、私いつも転職をしていたんですよね。
トータル16年この世界で働いていましたが、最長でも3年までしか同じ企業に所属したことが無く。内半分ぐらいは海外二か国にいましたから、おそらく私の場合は性分として「現状維持が嫌い」というのがあるのかも。
仕事の種類にもよると思うのですが、一年いると全体の流れは大体見える。二年目はそれを「より良く」することを楽しめるのですが、三年目あたりになってくると段々飽きが生じてきて、、、もちろん新しいメニューを開発するとか、小さな「新しいこと」は生み出せるんですけど、職業柄部署を変えるのも難しかったので、新しい会社で出来ないことが出来るようになっていく達成感に比べると、どうしても成長を感じにくかったんですよね。
以前は一社で長く働けない自分を「どうなんだろうなー」と思っていた時期もありました。ただ、転職回数が人より多い分「新しい環境に早く溶け込む」というのが得意にもなり、色んな働き方、考え方、に触れられる良い経験が出来たと今では思っています。会社の文化としての「当たり前」って、気づかないうちに自分の思考パターンやビリーフ(信念)にも影響していて、内側にいるとその視点が固定されていることに、自分では気づきにくいので。
と、ちょっと話がそれちゃいましたが、、、コンフォートゾーンを出ないことを選んでいる場合、安心や心地良さと引き換えに、やりがいや達成感、成長などを手放すことになるのかもしれません。
コンフォートゾーンを出ることで起こりうる影響
コンフォートゾーンを出ることで起こりうることは、基本的に上に書いたことの逆を考えてみるといいのかなと。具体的には以下の5つです。
成長と学習の促進
近年変化の速い状況下でも使えるフレームワークとして
※
「OODAループ」
が注目されています。これは「観察する(Observe)」→「方向づける(Orient)」→「意志決定(Decide)」→「行動(Action)」の頭文字を取ったもの。コンフォートゾーンを出る時、人は自分の目と耳で聴き主体的に意思決定をして動くことを頻繁に求められます。そのためこのOODAループを回しやすく、成長と学習のスピードが速くなります。
またチャレンジをするということは、現状の自分のままでは成し遂げられないことに挑んでいくということ。自分の限界をストレッチさせることによって、
※
潜在ポテンシャルが発揮されやすくなり、
大きな自己成長へと繋がります。
自信の向上
新たなチャレンジをする時、そこには失敗やリスクが当然あります。それでも自分が目指す目的地へ向かって進もうとすることによって、困難を乗り越えていく力や粘り強さが育まれ、
※
自分への信頼が増し、自己肯定感が向上します。
また目指す目的地に辿りつくために、新しい能力やスキルを身につける機会も増えます。これはただ「知識を学ぶ」のとは違って実践の中で
※
「自分のものになる」
ことが多く、またそのプロセスで他者からの肯定的なフィードバックをもらうチャンスも増えるため、必然的に自信の向上へと繋がります。
コンフォートゾーンを出るということは
※
「自分自身と向き合う旅」
でもありますから、自己理解が深まり、より客観的に自分を見られるようになるのも大きな特徴のひとつでしょう。
創造性の向上
人の脳が最も創造的になれるのは、完全に自由な時やリラックスしている時よりも、一定の制限がある時だと言われています。コンフォートゾーンを出ると様々な壁にぶつかることになり、
※
脳が本来持っているクリエイティビティが活性化されやすくなります。
新しい世界では新しいものに出会う機会も増えるため、好奇心がかき立てられることで様々なインスピレーションも得やすくなるでしょう。
因みに私はこの状態を
※
「気づき体質になる」
と呼んでいるのですが、思考が世界に対してとてもオープンな状態になることで、様々な物事が繋がりやすくなり、気づきの瞬間が多くなるように感じています。
機会の拡大
コンフォートゾーンを出ると、自分の世界が広がります。色んな人や考えに出会うことで視点の数が増えたり、視座が上がって、世界をより俯瞰して見ることができるようになります。それによって、これまでには気づいていなかったチャンスを掴めることもありますし、「学びや成長」の機会も必然的に増えていきます。
※
「類は友を呼ぶ」
という言葉がありますが、自分の夢に向かって頑張っていると、同じようにチャレンジし続けている人にも遭遇しやすくなります。そういった出会いも含めて、
※
自分の人生をより良くできる機会
は広がるだろうと思います。
モチベーションの向上
モチベーションは
※
「フロー状態(Flow)」
と密接な関係があります。フローとは、スポーツなどでは「ゾーンに入る」という表現もされる、超集中した状態です。フローを提唱したチクセントミハイによれば、この状態に入るための条件には7つあるのですが、そのうち少なくとも次の3つを満たす必要があると言われています。
①目標が明確であり、何のために自分がそれをやるのか分かっている
②自分の行動に対するフィードバックがある(目標に近づいているか、遠ざかっているか分かる)
③自分の能力よりも少しだけ高いレベルの挑戦である
コンフォートゾーンを出る、
特に
※
「成長の領域」
まで行けた場合には、これらの条件を非常に満たしやすくなり、モチベーションを保ち続けることが容易くなります。
コンフォートゾーンを出るとき助けになるもの
成長のプロセスにおいて、私たちの多くが最もつまづきやすいのは、
※
「恐れのゾーン」を抜ける最初の一歩
でしょう。小中学校の進学や社会人への移行など、これまでの変化は多くが「外的な要因」によってもたらされたものでした。つまり「コンフォートゾーンを出る」以外の選択肢は無かったわけです。
一方、大人になってからの挑戦——たとえば転職や起業など——は、コンフォートゾーンを「出るか出ないか」を自分で選べます。
※
選択の自由があり、主体性を求められるからこそ、行動に移すのが難しく感じる
のかもしれません。
それでも「成長のために一歩踏み出したい」と思うなら、次の3つのヒントを参考にしてみてください。
※
1「とても小さな変化を設定する」
チャレンジしようとしていることが大きければ大きいほど、私たちはより大きな恐れを感じます。夢や目標を細かくして、小さなマイルストーンを設定しましょう。進んでいる実感を得やすくなり、小さな成功体験を繰り返すことで自信にも繋がります。
2「誰と一緒にいるかを選ぶ」
変化を避ける人に囲まれていると、自分が「異質」に感じられ、最初の一歩を踏み出すのはとても勇気がいるはずです。挑戦や成長を楽しんでいる人と、繋がる時間を持つようにしましょう。モチベーションが保ちやすくなり、諦めそうになっても「仲間」の存在が自分を奮い立たせてくれます。
3「他者のサポートを得る」
第三者の視点は、自分では気づけない盲点を照らしてくれます。また自分との約束は守れなくても、人との約束なら原動力になるという人も多いのでは。自分のニーズに合わせて、専門家も含めたサポートを得ることは、前進するための有効な術のひとつとなるでしょう。
ちなみに「コーチング」は、このコンフォートゾーンを少しずつ広げて、成長していくのをサポートしてくれる心強い手段です。次のパートでは、「コーチングって実際どんなふうに役立つの?」というところを、もう少しわかりやすく紹介していきますね。
コンフォートゾーンとコーチングの関係性
転職や起業など目に見える変化(外側のコンフォートゾーンの突破)のサポートのイメージが強いコーチングですが、実は
※
「内面的なコンフォートゾーンの書き換え」
こそが、コーチングの醍醐味。例えば「他人にどう思われるか気にしすぎる」「人に頼るのが苦手」「完璧主義」な自分から脱却出来たら、あなたの人生にどんな変化が起こると思いますか?
こういった思考から行動へと繋がるパターンを変えることは、目には見えにくいものの、
※
「生き方の自由度」
が爆発的に広がります。コーチとの対話ではこういった「無意識に繰り返されるパターン」にも光を当て、今のあなたにふさわしい形へと変えていくプロセスを共に歩みます。
また少し逆説的に聞こえるかもしれませんが、「コンフォートゾーン=悪」ではありません。新たな挑戦をするとき、それは安心したり、充電したり、創造性を育てるための
※
「基地」
にもなり得ます。「留まる or 出る」の話よりも、自由に出入りできる自分になることのほうが大切なのですね。
コーチと定期的に話す空間自体がその「基地」にもなり得るでしょうし、コーチング以外の場所で本当に心地よいと感じられる「基地」を増やしていくことも、成長のプロセスのひとつです。コーチはそんな自己成長の旅の中で、あなたが自分自身の力を思い出し、新たな視点や可能性に火を灯すのを支える、お供のような存在なのです。
※
自分のコンフォートゾーンを知るヒント
ストレングスファインダー
」は、コーチングや人材育成で活用される“才能の地図”のようなツール。才能を「無意識の思考・感情・行動のパターン」と定義しているため、自分のコンフォートゾーンを客観的に捉える手がかりにもなります。「いつもの自分」は、変化を妨げることもあれば助けることもあります。自分という旅人のクセと強みを知ることで、成長の旅はもっとしなやかで自由なものになっていくでしょう。
#障害者 #ピアカウンセラー #パソコンインストラクター #出張 #福祉用品 #ニュース今日の報告です
☆----------------------------------------------------------------☆
悩み事や福祉制度の相談、パソコンサポートのご依頼の方は
ogayasu☆gaia.eonet.ne.jpへ
※直接入力の際は(☆)は(@)に打ち変えてください
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[障がい福祉] カテゴリの最新記事
-
透析続けながら8時間勤務 テレワーク用い… 2025年11月24日
-
考えすぎる性格を直したい!何でも深刻に… 2025年11月23日
-
苦手だらけの場所で大興奮! 自閉症の娘と… 2025年11月23日
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.