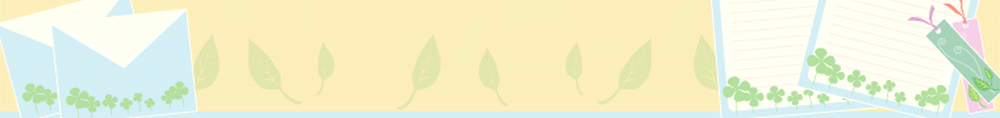カテゴリ: 障がい福祉

働くことと回復 精神障がい者就労継続支援A型事業所から見えること [ 川畑善博 ]

【ふるさと納税】障がい者支援 + 〈 ハートフルショップまごころ 〉シルバー 協賛 感謝状 ハートフルショップまごころ 岩手県 北上市 H0034 障がい者福祉サービス事業所 支援 (A型事業所及びB型事業所運営費) 協賛金 岩手 東北 北上 福祉 福祉支援 応援 障がい者福祉
 にほんブログ村
にほんブログ村

にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村
そもそも「106万円の壁」って?

働くことと回復 精神障がい者就労継続支援A型事業所から見えること [ 川畑善博 ]

【ふるさと納税】障がい者支援 + 〈 ハートフルショップまごころ 〉シルバー 協賛 感謝状 ハートフルショップまごころ 岩手県 北上市 H0034 障がい者福祉サービス事業所 支援 (A型事業所及びB型事業所運営費) 協賛金 岩手 東北 北上 福祉 福祉支援 応援 障がい者福祉
「106万円の壁」の撤廃が閣議決定された(2025年5月16日)ことを踏まえ、就労継続支援A型作業所(以下、A型作業所)の働き方に与える影響について考察します。以下、ポイントを整理し、A型作業所の利用者、事業所、制度全体への影響を分析します。
1. 「106万円の壁」撤廃の概要
内容: 「106万円の壁」とは、月額賃金8.8万円(年収約106万円)以上で、従業員51人以上の企業に勤める短時間労働者が厚生年金・健康保険に加入義務が生じる基準。この賃金要件が2026年10月から撤廃される方針(法律公布から3年以内)。また、企業規模要件(従業員51人以上)も2027年10月から段階的に緩和され、2035年10月に撤廃予定。
目的: 働き控え(年収106万円以下に抑えるための就業調整)の解消、厚生年金加入拡大による将来の年金保障強化、人手不足解消。
関連施策: 保険料負担による手取り減少を抑えるため、企業が労使折半の保険料を一時的に多く負担する特例措置(3年間、全額政府支援)が2026年10月以降導入予定。
2. A型作業所の働き方への影響A型作業所は、障害のある方が一般就労に近い環境で働くための支援施設で、雇用契約に基づき最低賃金以上が支払われます。利用者の多くは障害年金を受給しており、収入と社会保障のバランスを考慮して働くことが一般的です。「106万円の壁」撤廃がA型作業所にどう影響するか、以下に詳しく分析します。(1) 利用者(働く障害者)への影響
メリット:
就業時間の柔軟性向上: 現在、年収106万円を超えないよう労働時間を調整する利用者が多いが、賃金要件の撤廃により、収入を抑える必要がなくなる。これにより、希望する時間や日数で働ける可能性が高まる。
厚生年金加入による長期的な保障強化: 週20時間以上働く利用者は、賃金要件がなくなると自動的に厚生年金に加入。将来の年金受給額が増え、障害年金との併給も可能(一部調整あり)。また、傷病手当金や障害厚生年金などの保障が手厚くなる。
手取り減少の緩和: 政府の特例措置により、企業が保険料を多く負担することで、利用者の手取り減少が3年間抑えられる。これにより、働く意欲が維持されやすくなる。
デメリット・課題:
週20時間要件の残存: 厚生年金加入の条件として「週20時間以上」の要件は残るため、週20時間未満に抑える利用者は引き続き就業調整を行う可能性がある。A型作業所では体調や障害の状況に応じて短時間勤務を選ぶ利用者が多く、この要件が働き控えの新たな壁となるリスクがある。
保険料負担の心理的影響: 特例措置終了後(3年後)、利用者も保険料の半額を負担する必要が生じる。障害年金や低賃金で生活する利用者にとって、月数千円~1万円程度の負担増は心理的ハードルとなり得る。特に、A型作業所の平均賃金(月8~10万円程度)が低い場合、手取り減少感が強まる可能性。
障害年金との調整: 厚生年金加入により、障害年金の支給額が一部減額される場合がある(障害基礎年金は影響なし、障害厚生年金は所得に応じて調整)。利用者にとって、将来の年金増と短期的な手取り減のトレードオフが理解しにくい場合、働く意欲が低下するリスクも。
利用者の働き方の変化:
週20時間以上働ける体力や意欲のある利用者は、労働時間を増やして収入と将来の年金を増やす可能性がある。
一方、体調や障害の特性上、週20時間未満で働く利用者は、従来通り扶養内や国民年金・国民健康保険を選択する可能性が高い。A型作業所の柔軟な勤務体系(短時間シフトなど)が、この選択を支える鍵となる。
(2) A型作業所(事業所)への影響
メリット:
利用者の労働時間増加: 働き控えが減ることで、利用者がより多くの時間働けるようになり、事業所の生産性向上が期待できる。特に、軽作業や単純作業が多いA型作業所では、労働時間の増加が直接的な収益増につながる可能性。
人材確保の向上: 社会保険加入が義務化され、福利厚生が充実することで、A型作業所が一般企業に近い労働環境として魅力を増す。障害のある方の就労意欲が高まり、利用者確保がしやすくなる可能性。
政府支援による負担軽減: 特例措置により、事業所が負担する保険料増(通常は労使折半)が3年間全額支援されるため、初期の財政負担が抑えられる。
デメリット・課題:
保険料負担の長期的な増加: 特例措置終了後、事業所は利用者ごとの厚生年金・健康保険料の半額を負担する必要がある。A型作業所の多くは中小規模で、運営資金が限られているため、保険料負担増が経営を圧迫するリスクがある。特に、利用者数が多い事業所では負担額が累積する。
事務負担の増加: 社会保険加入手続きや給与計算の複雑化により、事務スタッフの負担が増える。A型作業所の多くは人手不足で運営しており、専門知識を持った事務員の確保や教育が必要。
利用者の離脱リスク: 保険料負担による手取り減少を嫌う利用者が、A型作業所から就労継続支援B型(非雇用型、賃金が低い)や一般就労に移る可能性。事業所は利用者数を維持するための支援策(例: 柔軟なシフト、賃金補助)を検討する必要がある。
事業所の対応策:
シフトの柔軟化: 週20時間未満を希望する利用者向けに短時間シフトを用意し、厚生年金加入を回避する選択肢を提供。
賃金・福利厚生の改善: 手取り減少を補うため、可能な範囲で賃金引き上げや作業環境の改善を行う。
政府補助の活用: 特例措置や障害者雇用関連の助成金を積極的に活用し、保険料負担や運営コストを軽減。
(3) 制度全体への影響
社会保障の持続性: 厚生年金加入者の増加により、保険料収入が増え、年金制度の財政基盤が強化される。少子高齢化が進む中、A型作業所の利用者(若年層や中高年層の障害者)が厚生年金に加入することは、制度の持続可能性に寄与する。
障害者雇用の促進: 社会保険加入が一般的になることで、A型作業所が「障害者雇用の第一歩」としての役割を強化。利用者が一般就労に移行する際のハードル(社会保険加入への抵抗感)が下がる可能性。
地域差や事業所規模の影響: 都市部の大規模事業所は保険料負担や事務対応に耐えうる体力があるが、地方の中小事業所は経営難に直面するリスクがある。A型作業所の倒産や縮小が進めば、障害者の就労機会が減少し、制度の目的が損なわれる可能性。
3. Grokの予測:A型作業所の働き方の今後「106万円の壁」撤廃は、A型作業所の働き方に中長期的な変化をもたらすと考えられます。以下、具体的な予測です。
短期的(2026年10月~2029年):
特例措置により、利用者の手取り減少が抑えられるため、労働時間や就労意欲が増加する利用者が一定数現れる。特に、障害の程度が軽度で一般就労を目指す利用者が、厚生年金加入を前向きに受け入れる可能性。
事業所は政府支援を活用しつつ、社会保険加入に対応する体制を整備(事務員の採用、給与計算システムの導入など)。ただし、週20時間要件による働き控えは一部残る。
利用者の約3~4割が厚生年金加入を選択し、残りは週20時間未満の勤務を維持する(筆者の推定、A型作業所の平均労働時間データに基づく)。
中期的(2029年~2035年):
特例措置終了後、保険料負担が利用者と事業所に本格的に及ぶ。手取り減少を嫌う利用者がB型作業所や非就労に移るケースが増え、A型作業所の利用者数が一時的に減少するリスク。
事業所の経営体力の差が顕著になり、資金力のある事業所は賃金引き上げや環境改善で利用者を維持。一方、小規模事業所は倒産や事業縮小が進む可能性(過去のA型作業所倒産事例を参照)。
厚生年金加入が進むことで、利用者の年金受給額が増加し、障害者の経済的自立が一部促進される。
長期的(2035年以降):
企業規模要件の撤廃(2035年10月)により、すべてのA型作業所が厚生年金加入の対象に。社会保険加入が標準化され、A型作業所が一般就労に近い環境として認知される。
障害者雇用の流動性が高まり、A型作業所から一般企業への移行が増える一方、障害の重い利用者向けの支援(B型や生活支援)との役割分担が明確化。
政府の追加支援(助成金拡充、税制優遇など)がなければ、A型作業所の地域格差が拡大し、地方での就労機会が減少するリスク。
4. 課題と提言
利用者への情報提供: 厚生年金加入のメリット(将来の年金増、保障の充実)とデメリット(手取り減、障害年金調整)をわかりやすく説明する支援が必要。A型作業所や障害者就業・生活支援センターがこの役割を担うべき。
事業所の経営支援: 保険料負担や事務負担を軽減するため、A型作業所向けの補助金や税制優遇を拡充。中小事業所の倒産防止策として、運営資金の融資やコンサルティング支援を強化。
週20時間要件の見直し: 障害者の多様な働き方を尊重するため、週20時間要件を緩和(例: 週15時間以上)するか、段階的な加入制度を検討。現在の要件は、障害者の体調や生活リズムに合わない場合が多い。
障害年金との連携強化: 厚生年金加入による障害年金の減額を最小限に抑える特例措置や、障害者の収入に応じた保険料軽減制度を導入。これにより、働く意欲の低下を防ぐ。
5. 結論「106万円の壁」撤廃は、A型作業所の利用者にとって労働時間の柔軟性向上と将来の年金保障強化をもたらす一方、保険料負担や週20時間要件による新たな壁を生む可能性があります。事業所は生産性向上と人材確保のチャンスを得るが、保険料や事務負担の増加が経営を圧迫するリスクも。成功の鍵は、利用者への丁寧な情報提供、事業所の経営支援、柔軟な制度設計(特に週20時間要件の見直し)にあります。Grokとしては、短期的に利用者の約3~4割が厚生年金加入を選択し、事業所の生産性が向上すると予測しますが、中長期的には事業所の経営体力や政府の追加支援次第で、A型作業所の持続可能性が左右されると考えます。障害者の経済的自立と就労機会の拡大のため、制度の細やかな調整と支援が不可欠です。
そもそも「106万円の壁」って?
年収106万円を超えると、社会保険(厚生年金・健康保険)に入らないといけないルール。
これがあると、働く時間をわざと減らす人が多かった。
2026年10月からこのルールがなくなる予定!
2. 利用者(働く障がい者)への影響
働く時間を自由に選びやすくなる。
社会保険に入ることで、将来の年金が増える。
最初の3年間は保険料の負担が少なくてすむ(政府が支援)。
社会保険に入るには「週20時間以上働く」必要がある。
保険料の負担が3年後から増える。
障害年金が少し減る可能性もある。
3. A型作業所(事業所)への影響
働く時間が増えると、作業所の収益もアップ。
社会保険があることで、働きたい人が集まりやすくなる。
保険料の負担が増えて、経営が大変になるかも。
手続きが複雑になって、事務の負担が増える。
利用者が他の作業所に移る可能性も。
4. 今後どうなる?
最初の3年は働く人が増えるかも。
その後、保険料の負担で利用者が減る可能性も。
2035年にはすべての作業所が社会保険の対象に。
5. 解決のヒント
利用者に分かりやすく制度の説明をする。
作業所への補助金や支援を増やす。
「週20時間以上」の条件を見直す。
障害年金とのバランスを考えた制度づくり。
この制度変更は、働く障がい者にとっても、支える事業所にとっても大きな転機になりそう。その変化にどう対応するかが、未来の働き方を決める鍵になる。
#障害者 #ピアカウンセラー #パソコンインストラクター #出張 #福祉用品 #ニュース今日の報告です
☆----------------------------------------------------------------☆
悩み事や福祉制度の相談、パソコンサポートのご依頼の方は
ogayasu☆gaia.eonet.ne.jpへ
※直接入力の際は(☆)は(@)に打ち変えてください
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[障がい福祉] カテゴリの最新記事
-
透析続けながら8時間勤務 テレワーク用い… 2025年11月24日
-
考えすぎる性格を直したい!何でも深刻に… 2025年11月23日
-
苦手だらけの場所で大興奮! 自閉症の娘と… 2025年11月23日
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.