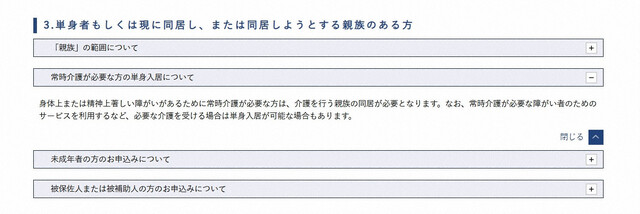ホタル(Sストーリー)モルBさんからです。
僕の案内で1人の人物が部屋の中央にあるパイプ椅子に腰掛ける。
僕はストップ・ウォッチを押す。
パイプ椅子に腰掛けた人物は白い壁をじっと見つめる。
時間が来る。
僕は「お疲れ様でした」と言ってその人物を隣の部屋に誘導する。
それでおしまい。
しばらく待って逆側のドアに移動して外にいる次の人に声をかける
「次の方、お入り下さい」
そして机の上にあるリストにチェックをして
椅子に座るように告げる。
僕はまたストップ・ウォッチを押す。
同じ事の繰り返し。
1993年の夏の日の出来事だ。
僕がこの事を思い出したのはほんの些細な偶然の出会いからだった。
いつだって些細な事の集積がひとつの結論を導き出す。
それが、名も無いちっぽけな記憶だったとしても例外などではない。
そして、その記憶もまた些細な事の集積の一部となってゆく。
*
「その中の一人に私がいたのよ」
友人の結婚式でたまたま隣り合わせになった女の子が僕に言った。
どういう話の成り行きでそんな話に行き着いたのかはっきり思い出せない。
でも、僕たちは10年前のその日、同じ場所にいた。
「まさか」僕は言う。
「本当、まさかね」彼女は笑う。
僕らは些細な物事を順序良くこなしていった。
そして10年前の記憶に辿り着いた。
ひとつ欠けてしまってもここに辿り着く事は出来ない。
それほどデリケートな工程を経て
今、目の前にいる女の子と10年前の女の子が
僕の記憶の中でひとつになる。
そう、全ての知覚とはすでに記憶なのだ。
僕は今という最新版の過去に生きている。
そう考えると僕の気持ちは少し落ち着きを取り戻す。
*
10年前の僕はその白い壁を見つめている。
最初は真っ白な壁にゆっくりと、非常にゆっくりと影が浮かびあがる。
いや、本当は何も写っていないのかもしれない。
それくらいささやかな影だ。
でも、僕にはその影がジョン・F・ケネディの様に見えた。
「ねぇその時、壁にジョン・F・ケネディみたいな影が映ってなかった?」
僕は彼女に訊いてみる。
「覚えてないわ」
「うっすらだけど、確かにジョン・F・ケネディみたいだったんだよ」
「ケネディの顔が良く思い出せないの」彼女は笑った。
「じゃ、とにかく男の人の顔」
「10年も前の事よ」
「うん。でも本当に覚えてないかな」
「ごめんなさい、本当に覚えてないの」
僕はジョン・F・ケネディのことはあきらめる事にした。
*
彼女は新婦の友人で名前は涼子と言った。
涼子は以前、僕が好きだった女性にそっくりだった。
容姿はもちろん、声や話し方から服装から何から何まで。
僕は誰にでもすぐに親近感を覚えるわけではない。
でも涼子に対してはそういう訳ですぐに親近感を覚えることが出来た。
僕らはその後、店を変えて飲みなおすことにした。
適当に通りを歩いて適当に目に付いたバーを選んだ。
重い扉を押し中に入る。
こじんまりとした店内をざっと見渡す。
数人の客がゆっくりと時間を過ごしていた。
店内にはビル・エヴァンスのワルツ・フォー・デビィが流れている。
そこにいる誰もが居心地のよさを感じているようだった。
「ここ良いかな?」僕はカウンターを指差す。
「もちろん」若いバーテンダーは微笑みながら答える。
若いバーテンダーはスマートで顔立ちの整った青年という印象。
そしてどこと無く女性的な美しさを持っている。
シャツから覗く透き通るような白く細い手首が
その印象に拍車をかける。
僕らはカウンターに並んで座った。
バーテンダーに注文を告げる。
僕はビールで涼子がモスコミュール。
どちらとも無く僕らは話を始めた。
僕らは初対面とは思えないほど不思議なくらいうまく話が合った。
まるで古くからの知り合いの様な感覚さえ覚えた。
お互いの考えてる事は同じとまでは言えなかったが
涼子の言葉は僕の中にしっかりと刻み込まれた。
僕は彼女の話し方に好感と信頼を抱く事ができた。
その日は僕が今まで経験したどの1日よりも短い1日だった。
同時に僕の人生の中で特別な意味を持つ1日ともなった。
*
僕が涼子の死を知ったのはその数日後だった。
*
僕は涼子の死を警察の事情聴取で知った。
刑事の話によると彼女が自殺したのは
僕らが会った日の翌日だった。
その日、彼女は朝からどこにも出かけていなかったようなので
最後に彼女に会った人物が僕だったのだ。
刑事は僕に「彼女に何か変わったところは?」と訊いた。
「さぁ、分かりません」僕は答えた。
そしてその夜、彼女を抱いたかを訊かれた。
僕は「いいえ」と答えた。
刑事は間を置いた後、
「いいですか、正直に」と再び念を押す。
彼には彼の思い描いた状況があり、
僕がその状況に沿った答えを口にするのを期待していた。
少なくとも僕にはそう思えた。
その瞬間から僕はこの事情徴収がどうでも良くなってしまった。
このやりとり自体がまるで意味の無いセレモニーの様に思えたのだ。
その後、僕は全ての質問に一言で答え続けた。
「そうですね」「分かりません」「あるいは」「時として」
そんな具合に僕は質問をクリアしていく。
彼にとって僕はとても不真面目に写ったのかも知れない。
でも、それは仕方が無い事だと思った。
ある意味ではきっとそれは正しい判断だからだ。
一通りの質問の後、彼は調書を読み上げる。
全くひどい文章だった。
僕が代わりに書こうとも思ったがやめた。
そんな事はきっとするべきではないからだ。
僕はその調書の最後に住所と名前を書いて拇印を押す。
彼は「何か思い出したらここに電話するように」と
電話番号と担当である彼の名前の書かれたメモを僕に差し出す。
僕はそれを二つ折りにしてポケットにしまった。
そして町に出た。
得体の知れない喪失感が僕を包み込む。
もちろんこの喪失感には特別な意味など無い。
でも僕は誰とでも良いから話をしたい気分になった。
携帯を取り出し、何人かに当たってみる。
でも、誰1人として電話に出るものはいない。
僕は途方にくれる。
再び得体の知れない喪失感が僕を包み込む。
僕はふと「アンナ・カレーニナ」の1節を思い出す。
「幸福はどれも似たようなものだが
不幸はいずれもそれぞれに不幸なものである」
*
しばらく歩き回った後、僕は1軒のバーの前で足を止める。
ここは彼女と最初に来たあのバーだ。
中に入る。店内に客は1人もいない。
店内にはキャノンボール・アダレイの「サムシング・エルス」が流れている。
僕は以前座った席に座り、ビールを注文する。
「今日はお1人なんですか?」
バーテンダーがビールを僕の目の前に置く。
「色々とあってね」僕は答える。
彼は軽くうなずくと僕の前に灰皿を置く。
「ありがとう」僕はビールを流し込む。
*
しばらくして1人の女性客が入ってきた。
彼女は慣れた雰囲気でカウンターの逆はじに腰掛けた。
そして柔らかい口調でバーテンダーに話しかけている。
何を話しているか僕には全く聞き取れない。
もちろん、聞き取る気も無い。
僕は気にせず文庫本に目を通す。
バーテンダーは僕の灰皿を交換しながら言った。
「僕の郷里には蛍がたくさんいたんですよ」
バーテンダーは確かにそう言った。
もちろん、僕に向かって言った訳ではない。
話の流れはよく分からなかったが
その一言だけが僕の耳に飛び込んできたのだ。
彼には郷里があって、そこにはホタルがたくさんいた。
それ以上のこともそれ以下の事も僕には分からない。
でも、僕はその一言がどうしても気になってしまう。
ホタルの話から何故か僕は涼子の事をリアルに思い出す。
それはきっと単なる偶然かも知れないし
一種の同時存在的正当性なのかも知れない。
ホタルの淡い光が命のはかなさと重なったのかも知れないし
あの、10年前のぼんやりと浮かんだ光の中の影が
オーヴァー・ラップしたのかも知れない。
いや、そんな事は今となってはどちらでも良い。
彼の郷里にはホタルがいて、僕は涼子の事を思い出した。
ただそれだけの事だ。
*
*
*
あれから2年経った今、
僕はようやく涼子の事を冷静に振り返れるようになった。
それでも涼子の事をこうして文章にした事が
正しい事だったのかは正直よく分からない。
あの日からホタルという言葉を耳にする度
決まって僕は想像上のバーテンダーの郷里と涼子の事を思い出す。
彼女とホタルの間には何の関係もないのにも関わらずだ。
現実は時として奇妙な手触りだけを人の心に残してゆく。
きっと、僕はそれを書き残したかった。
そしてこの文章が生きて行くかぎり何度も何度も繰り返されてゆく
この得体の知れない奇妙な感情への手がかりになれば良いと思っている。
そう、何かの手がかりになれば良いと。
**********************
大好きなそしてリスペクトするモルB兄さんがアナザーストーリーを
書いてくれました。とても感動。そして感謝。
© Rakuten Group, Inc.