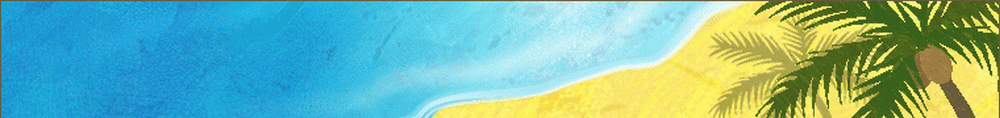苦い苦い恋のはなし
缶コーヒーがまだ百円玉一枚で変えた頃の話だ。
夕暮れは雨を連れてやってきた。
北国に降る冬の雨は、時として雪よりも怖いということを知っていた僕は
なんとも憂鬱な気持ちのまま駅のホームに降り立った。
この雨が夜の寒さで凍りついてしまうと
明日の朝は自転車で家を出ることは不可能に近い。
三月の雨は霧のように辺りを舞い
無人駅の階段はいつもよりやけに寂しく見えた。
「さて、どうしようかな・・・傘も持ってこなかったし」
さっきまで肩にかけていたショルダーバッグが濡れないように
胸元に抱えなおした僕は
小さな屋根のかかる自動販売機の下でほっとため息をついた。
そのとき、低いモーター音を出しながら佇む、背中の自動販売機から
あの頃の声が聞こえた気がした。
「ねぇ、いっしょに帰ろうか」
ハッとして振り向いた僕は急いで彼女の姿を探したが
そこにあるのは雨だけが静かに降り続く空間だけ。
「・・・もういいかげん忘れたらどうだ」
胸の奥がパキッと音を立てたようなせつなさが、僕の唇を真一文字に結ばせた。
1ヶ月前、そこの空間には確かに彼女の姿があった。
そう、ちょうど今日のような雨の降る夕暮れはいつだって
彼女は学校帰りの制服のまま、薄いベージュ色の傘をさし、僕の帰りを待っていてくれた。
そう、彼女はいつもいつも笑っていた。
二人とも部活のせいで帰るのが遅くなってしまうおかげで始まった恋だった。
中学の頃はお互い好きになるなんて思ってもいなかったのに、
寄り道のような出会いは、いつしか大切な恋に変わっていった。
薄暗くなった駅の小さなベンチ。
パチパチとたまに点滅する接続の悪い電灯。
錆びて赤茶けた二つのごみ箱。
僕達はその田舎の何もないけど静かに澄んだ夜の空気の中で
いつも缶コーヒーを飲みながら笑っていた。
百円玉一枚で買えた恋の時間。
「ブラックなんてよく飲めるね」
彼女は少しハスキーな、それでも合唱部で鍛えた張りのある声でクルクルと笑った。
「お前こそ、そんな甘ったるいやつ、よく飲めるよなぁ」
僕はそう言いながら、本当はまったく飲めないその苦さをグイッと飲み込んだ。
そう、彼女の前では少しでも大人でいたかったから。
バレンタインの日。
彼女の前でだけブラックが好きになってしまう僕のため
彼女はわざわざビター味のチョコレートをくれた。
「ビター味のチョコ、探すのけっこう大変だったんだからね」
そう言ってまたクルクル笑う彼女に
ちょっとだけかっこつけたことを心の中で謝りながら
僕はとても嬉しい気持ちになっていた。
そして僕たちがキスをするとき、決まって甘さと苦さが溶け合った恋の味がした。
それからしばらくして缶コーヒーが百十円になった頃、僕達は別れた。
きっと十円玉をポケットから探しているうちに
二人の距離も離れてしまったのだろう。
入れたてのコーヒーの香りが、時とともにしだいに薄れていくように
僕の隣から彼女の香りも遠ざかっていった。
「しょうがないな、走って帰るか」
寒さでかじかんだ指で、やっと百十円を取り出した僕は
あの頃と同じように無糖のコーヒーを選んだ。
彼女といっしょに飲んでいたコーヒーはもうすでに新しいものに変わっていたけど
僕の中の彼女はいつまでもあの頃のままだ。
ゴクッと飲み込んだ一瞬。
恋の終りのブラックコーヒーは本当に苦かった。
© Rakuten Group, Inc.