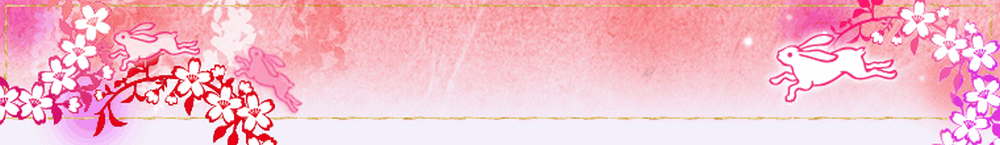小説
小説 ☆ある日の出来事☆
長い眠りから覚め、ふと列車の窓から外を眺めた。
黄泉(よみ)の国へ来てしまった!一瞬、心臓の鼓動が停止した。
再び脈打ち始めたのは、車内販売の売り子が、大きな声で叫びながら
通っていった時だった。
闇の中に、ロウソクの火がポツンポツンと灯る。
赤や青や緑やオレンジや黄色・・・色とりどりの灯りの数は、
時間が経つにつれてみるみる増えてきた。
巨大な四角い箱の中に整然と並んだ灯りたちが出迎えてくれた。
黒い河を黄色とオレンジと赤の灯籠が止めどなく流れていく。
高くそびえる塔の先に輝くルビー・・・。
私には、確かにそんなふうに見えたのだ。
いつの間にか乗客は、私ひとりになっていた。
次の駅で降りなければ・・・そう思いながらも終着駅まで、
行ってみたい衝動にかられる。
静まり返った車内に、突然、子供の笑い声が響いた。
5、6歳の男の子と女の子が隣の車両からかけだしてきた。
天使を思わせるほどそのふたりは色が白くふっくらして、
黒い瞳は、月夜の海のようにやさしさをたたえていた。
ふたりで、ふざけあいながら通路を走り去っていく。
私は慌てて呼び止めた。「待ってくれ、ボウヤ!」
子供はピタッと止まるとゆっくり振り向いた。
「おじさん、僕たちが見えるの?」
男の子は、目をパチクリさせながら不思議そうに私の顔を見た。
「おじさん、だめだよ、どうしてひとつ前の駅で降りなかったの?」
「私たちが見える人は、まだ行っちゃいけないのよ。」
「なぜ!?」私は思わず立ち上がって子供達にたずねた。
その時、ガクンゴゴゴゴーと激しく列車が揺れた。
私はよろけて座席に叩きつけられた。
列車がみるみる加速していくのがわかる。
窓から見える無数の灯りは光の帯へと変わった。もう形が判別できない。
私は夢中で叫んだ。「教えてくれ、いったいこの先には何があるんだ!」
もうすでにそこには、子供達の姿はなかった。
「次の停車駅は、マイン、マイン、ただ今から超光速運転に入ります。
切符をお持ちでない方は、次の停車駅マインにてお降りください。」
「切符、切符!」慌ててポケットというポケットを探したが出てこない。
それもそのはず、いつ列車に乗ったのか記憶がないではないか!
私は途方に暮れてしまった。ここまで来てしまった以上、
終着駅まで行ってみようではないか。
「そうだ切符を買わなくては、車掌はどこだ!?」
私は隣の車両へと走った。「いない!?」
その隣の車両にも、そのまた隣の車両にも、ひとっこひとりいない車内を走り回る。
燃えさかるロウソクから滴ったロウのような粘っこい熱い汗が頭から流れ出す。
息せき切ってたどり着いたのは、運転室の扉の前だった。
一歩、二歩と前へ進む、その足がやけにぎこちなかった。
きれいに磨かれた銀色のレバーに、鉛のように重く感じられる手を乗せた。
カチャッ、かすかな音と共に扉が開いた。私はゆっくりゆっくりと扉を押した。
自分の呼吸の音が耳に響いてきて、うるさく感じられる。
私の心臓は今にも風船のようにパアンと割れるのではないかと思うほど
高鳴っている。
その中はとても列車の運転室とは思えないほど、たくさんの計器がびっしり
埋め込まれ、まるで宇宙船のコクピットのようだ。
一通り見回した私の目は、きっとまんまるくなっていたはずだ。
中央に背もたれの高い大きな椅子がある。
そこに運転手が座っているようなのだが、こちらからは見えない。
「困りますなぁ、お客さん、ここへ入ってこられては。」
運転手の声におずおずと頭を下げた。
「すみません、車掌がみつからなかったものですから・・・。」
途切れ、途切れに言葉が出てくる。ドギマギしているのが自分でもわかった。
「切符、切符を売っていただきたいのです。」
そういう私の声をじっと聞いていた運転手は困ったというようなうなり声をあげた。
「お客さん、切符も持たずに乗車なさるとは、いけませんなぁ。
どうしてマインのひとつ手前で他の方とごいっしょに降りられなかったのですか?
この列車がどこへ行くかご存じないのですか?
あいにくですが、終着駅までの切符は列車の中では売っていないのです。
後5分程で、マインに到着致します。どうしてもその先へ行きたいとおっしゃるの
でしたら、マインのオレンジの窓口で切符を購入してください。
ただしこの列車は、3分停車した後、発車致します。客席へお戻りください。」
白い手袋をした運転手の手だけが少し見えた。
上に上げられたその手は、邪魔者を追い払うように、ゆっくり前後に振られた。
仕方なく、私はペコリと頭を下げ、運転室を出て客席へもどった。
列車のスピードが少しずつ落ちてきた。
薄暗い中にボンヤリと入り江らしきものが見える。
「海だ!」黒々とうねり、時折、波がかすかな光を反射し光る。
不気味に見えるその海が、なぜか懐かしい気がしたのはどうしてだろう。
無数に点在する灯りが見えてきた。あれがマインという駅なのだろう。
3分の停車時間の間に切符を買わなくてはならない。
自分でもなぜこれ程まで、終着駅へ行ってみたいと思うのかわからない。
好奇心という言葉は、私の中でとっくに死語になっていると思っていた。
すでに頭は白髪まじりだし、顔は油ぎっている。女子高生などは、きっと
「イヤァ~ン!」とでも言って逃げていくだろう。
これでもかつては、なかなかの美男子だったんだがなぁ・・・。
窓に映る自分の顔をしげしげと見て苦笑いした。
「マイン、マイン、お出口は右側です。」
「おっと、こうしちゃおれん!」私は慌てて出口へ走った。
ホームへ飛び降りるとオレンジの窓口とやらを探した。
結構広い駅なのだ、見つからない。
海の上に、にゅーっと頭を出して周囲をうかがう潜望鏡のように
私は首を長くして見回した。
「あった!」オレンジ色のライトの看板が見えた。「あれだ!」
小学校の運動会の時でさえ、こんなに一生懸命走ったことはなかった。
窓口に駆け寄ると「切符、切符を!」息を切らしながら言った。
「どちらまでですか?」
「えっ!」行き先の名前は知らないのだ。
苦し紛れに、「終点まで。」
「終点までと言われましても・・・たくさんあるのです。」
「えっ、終着駅はひとつじゃないのか!?」
私の顔はきっとみるみる赤くなったに違いない。汗が吹き出る。
ズボンのポケットからハンカチを取り出すと、額の汗をぬぐった。
時計を見るともう3分経っているではないか!?
私はサァーっと血の気が引いた。振り返ると列車はまだ発車していない。
私を待っているのか・・・!?
「ご安心ください、この駅では、3分というのは、15分のことですから。
お客様のお持ちになっている切符によって終着駅は変わるのです。
行き先をおっしゃっていただかないことには、切符を売りたくても
売ることができないのです。」
どこかに駅名が書かれていないものかと探してみてもマインという駅名以外
書いていない。
「おじさん!」小さな声と共にズボンがつまんでチョンチョン引っ張られた。
「おじさん、速くしないと列車行っちゃうよ。あの列車行っちゃったら、
今度は十年後じゃないと次の列車来ないんだよ。」
いつの間に来たのか、もう片方の脚に女の子がしがみついていた。
「この駅にはね、ホテルも何もないの。この切符売りのお姉さんだけよ、
ここにいるのは・・・。」
「本当かね!?」私は切符売りに聞いた。
「はい、ですから、ここで次の列車を待って十年暮らすのは無理です。
ここにはマインの駅以外何もありませんから・・・二十年前にお一人
とうとう行き先を決めかねて、列車に乗れずここに残り、飢えに苦しんだ
あげく、海に飛び込まれた方がいましたわ。」
「それならば、君だってここで暮らせないではないか!?」
私は、多少声が大きくなっていたと思う。売り子は顔色ひとつ変えずに言った。
「あら、私は食べなくても死にませんから。」
私は、水槽の中の金魚のように口をパクパクさせるだけで、
言葉がなかなか出てこなかった。
「食べなくても死なないって・・・君はいったい!?」
売り子は、私の顔をまっすぐに見つめるとこう答えた。
「私は、このマインの駅で、永久に切符売りをやることを志願したのです。
鉄道局から給料代わりに永遠の命をいただきました。」
「淋しくはないかね、こんなところにひとりきりで・・・?」
「淋しいと言えば、淋しいですわ。けれど、周りにいくら大勢人がいても
淋しい時はあるでしょう?」
そう言われてみればそうかもしれない・・・。
私だって、いつもひとりで6畳分のスペースの一室で書類整理に追われて
いるのだから・・・。
書類という言葉が、頭に浮かんでハッとした。
そうだ、18日までに仕上げなくてはならない書類が山程残っているでは
ないか!私は、売り子に聞いた。「いったい、今日は何日だね?」
「16日ですわ。」売り子は、つんとすまして答えた。
「何時だね、16日の何時だね、今は!?」
私は、窓口から顔を突き出した。売り子は少し後ずさりすると時計を見た。
「もう4分ほどで、17日です。列車の発車時刻は0時ジャストですから。」
「おじさん、速く、速く!」子供達が急き立てる。
こんな所に残って十年も次の列車を待つなんて、まっぴらだ!
ましてや食べ物もないというのだから、乗り遅れたら自分に待っているのは、
死という一文字だ!
「お客様もここに残って、切符売りをなさろうと思っても無駄ですわ。
ここの職員の定員は1名ですから。」売り子は、つんとすました。
「あぁ、ここの仕事は君にしかできやしない、私は遠慮するよ。
ところで、切符をくれないか!?」
売り子は、急にパアーッとひまわりのように明るい顔を輝かせて身を乗り出した。
「どちらまで!?」
「東京!」
「東京ですね、千円になります。」
私は、胸ポケットから財布を出すと、売り子の前に千円札を差し出した。
そこには、夏目漱石ではなく、虚ろな顔をした私の肖像が描かれていた。
売り子は、名刺大ほどの切符を置いた。「ありがとうございます。」
切符を受け取った私は、子供達に急き立てられながら走りに走った。
発車のベルが鳴る。「おじさん、速く!」「エイッ!」
飛び乗った私の背後で扉がシュルシュルガッコーンと閉じた。
振り向いて窓からホームを見ると、子供達が手を振っていた。
「フー・・・。」私は、体の中にある空気を全部吐き出した。
「そういえば、あの子達は、あそこに残って大丈夫なのだろうか・・・?」
「お客様。」いつの間に現れたのか、後ろに車掌が立っていた。
「切符を拝見致します。」私は、言われるまま切符を渡した。
「東京までですね、かしこまりました。危ないですから、速く席へお着きください。」
車掌はそう言うと運転室のあるほうへと立ち去った。
私は、気怠い身体を引きずって客席へ戻った。窓から外を見る。
なんと!海の上を幾千ものレールが枝分かれして、四方に伸びているではないか!
もうすぐこの列車は、その切り返しの所に差し掛かる。
売り子が、終着駅は、ひとつではないと言った意味がやっと判った。
一組のレールが、何千ものレールに分かれていく。
まるで、ほうきを思わせる。今ちょうど、ほうきの杖の所を列車は
走っている。
これより光速運転に入ります。ガクンゴゴゴゴォー!
再び、窓の外の景色は、光の帯へと変わった。
やがて、闇の中に入り、何も見えなくなった。
いつの間にか眠り込んでしまったらしい・・・。
目覚めた私の頭の中は、どんより曇っている。
虚ろな目の中に大勢の人影が飛び込んできた。
次第に、私の耳にざわざわとざわめきが蘇ってきた。
窓の外を見ると、無数のネオンが灯り、家々の明かり、街灯が輝いている。
道路には、車が長い列をなして流れていく。相変わらずの混雑ぶりだ。
川辺には、巨大なマンションが建ち並ぶ・・・。
高くそびえ立つビルも見えてきた。今もなお次々と建設されているビル。
大きなクレーンの先の赤いランプが点滅を繰り返す。
「都会か・・・。」窓の外の景色は、いつも見慣れていたものに変わった。
「東京、東京・・・。」
駅のホームに降り立つと、人の波に飲まれて身動きできなくなった。
まるで、海に漂うくらげのように、私は、力無く流れるままに任せていた。
書類の整理をすっかり終えて、気晴らしに外へ散歩に出掛けた。
公園のベンチにどっかと腰を下ろして、しばらく通り過ぎる人を眺めていた。
緑の木々をバックに、突然、ふわふわとオレンジの丸いものが現れた。
男の子が走ってきた。空へ向かって上へ上へと旅立っていく風船を、
男の子は、ちょっぴり悲しそうな表情で見送っていた。
上を見上げていた男の子の顔が、ヒョイと私のほうへ向けられた。
「おじさん、スーパーマンに変身して、取ってきて、僕の三時のおやつを
あげるから・・・。」
私を見送ってくれたあの男の子と姿がダブった。
小さな子にしては、おもしろいことを言う。
「あいにくだが、おじさんは、スーパーマンじゃないんだよ。」
すると、男の子は、首を左右に振り、私の腹のへそのあたりを指差した。
「スーパーマンのマークだもん。」
どうやら、男の子の言うスーパーマンのマークというのは、
このベルトのバックルの模様のことらしい・・・。
言われてみれば、あのスーパーマンの胸のマークと似ている。
ひょっとして、あの行き先を聞かれた時、スーパーマンになれる国とでも
言っていたら・・・そんな国へ行けたんだろうか?
もしかしたら、私は、滅多にないチャンスを棒に振ってしまったんじゃないだろうか?
結局、私は、ありきたりな日常の中へ戻ってきてしまった・・・。
「おじさん、おじさん。」男の子の呼び声にハッとした。
「ごめん、ごめん。」私は、男の子の頭を二、三度なでた。
見ると、風船を売っている人がいる。
「ようし、新しい風船を買ってあげよう。」
「ほんと!?」男の子は、嬉しそうにピョンピョン跳ねた。
「風船を、ひとつ・・・。」そう言って、風船売りの顔を見た私は、
ぎょっとした。なんとあのマイン駅の売り子にそっくりではないか!?
風船売りは、ポカンとしている私を、怪訝そうに見たが、
「何色ですか?」
「あっ、あぁ・・・ボウヤ、何色の風船がいいかな?」
「う~ん、青!」
私は、売り子から風船を受け取ると、ボウヤに渡した。
「今度は、飛ばすんじゃないよ。」
「うん、ありがとう!」
男の子は、手を振りながら元気に走っていった。
その後ろ姿を見送って、もう一度風船売りを見たら、
あのマインの売り子とは、全然違う顔だった。
「私の見間違いか・・・。」
風が、さわやかに吹いていく・・・。
私は、なんだかスキップでも踏みたいような気分だった。
~おわり~
著作・ピョンコ
-
-

- 妖怪ウォッチのグッズいろいろ
- 今日もよろしくお願いします。
- (2023-08-09 06:50:06)
-
-
-

- GUNの世界
- COMMANDER CUSTOM【DX】/ ウェスタン…
- (2024-12-02 15:29:20)
-
-
-

- フィギュア好き集まれ~
- 【中古】[FIG]SNK美少女 不知火舞(し…
- (2024-12-02 16:00:45)
-