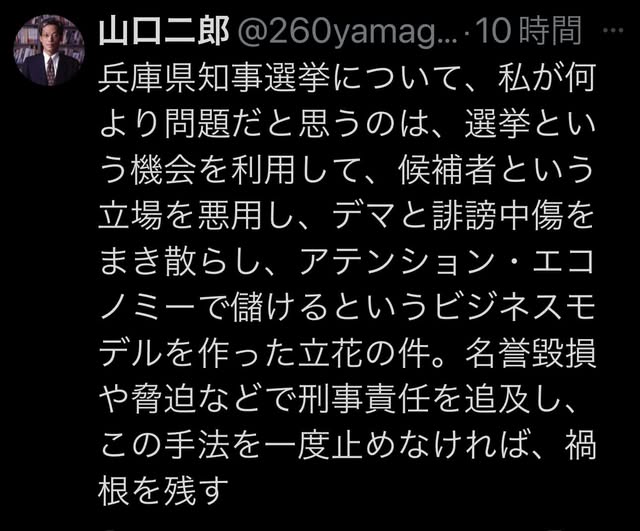第二章 発生
「僕もどう分析すればいいか迷うほど、これはイレギュラーですよ」
「そうですね。私も、ちょっとこんなタイプの物はアメリカでも見たことがありません」
話しているのは、田島と、助手の千代田だった。松野サラも報告を受けて、呼ばれていたのだった。
「もしかしたら一種の地下茎の植物ではないのですか」
「ふむ。まだ解明はつかない。というのはどこまでが茎なのかまだはっきりと断定しかねる状況だ。君の言うとおり、根だけの特徴を見ると地下茎にも見えるが、実際には根は繋がっておらん。松尾君はどう思ったかね」
「採取した感じでは地下茎とは言い難かったのですが、隣の花の根と絡んでいて。傷つけずに採取するのが手間でしたが、根は丈夫でした。これが、生態に関わる何か重要なヒントかもしれませんね」
「根が絡む? 確かにデータにある密度を考えると、そういう風に想像もできなくはないですけど。本当ですか?」
「本当です。複雑に絡んでるわけではなかったのですけど、はがすのが大変でした」
「そういう生態なんでしょうか。まさか、全ての花が絡んでいるとか?」
「確認はしてませんが、それはどうでしょう。その動機付けも説明する材料もまだありませんしね」
「ふむ……」
田島は首を傾げた。確かに判断材料はあまりにも乏しい。研究はまだ始まったばかりだった。千代田は好奇心が強く、なかなかいい着眼点をしている。まだ若いのだが研究熱心でもあるので、田島はよく千代田を重用していた。
「そもそも、どうしてここまで密集するのでしょうか」
「肥沃ではない土地で、絡むくらい密集していたら互いに成長が阻まれてしまう」
高山は養分がどうしても痩せる。過度に密集するのは、あまりに効率が悪い。
「それに、中心の赤い花。これがどうも謎なのだ」
「赤い花だけ、少し大株ですね」
「赤い花も、同じように絡んでいたんですよね?」
「そう言えば……。赤い花だけ広く場所をとっていた気がします。その時は気をつけて考えませんでしたけど」
サラは採取したときのことを思い出そうとした。
あの花を採取するときは、他の花が感情を持っているように攻撃的な気がした。もちろん、植物が人を襲うはずもないのだから錯覚だ。集中できなかったのは確かだったかもしれない。
あの時は別のことに気が散っていた。忌まわしい事件が再来せぬように、そのことで神経をすり減らしての作業だった。
田島が、サラの考えてることを察したのか、僅かに首を左右に振って、何も言わなくていいと合図した。それを受けて、サラは目で頷いた。
「この花の生態は謎だらけですね。どうしてこんなに不思議なのでしょうか。我々が知る法則の多くを無視した花です」
そのことは誰もが知っている。だが、本当はもっと恐ろしく凶悪な花なのだ。その片鱗に勘づいて危惧していたのは、この場では田島とサラだけだった。
「千代田君、私の研究室の棚に先週まとめた資料があっただろう。持ってきてくれないか」
「はい」
田島は千代田に鍵を渡した。
「松野君、木田君が疑っておる。気をつけたまえ」
千代田を見送ってから、田島はそう言った。
「わかってます。私はあまりよく思われていませんね。彼だけからではなく」
「しかし、皆は事の重大さを理解しておらんからな。だが、これは研究員にも伏せておかねばならぬ」
「何も知らないのは、私たちも一緒ですけどね」
「ふむ……」
田島は頭をゆっくり振りながら丸い目で下の方を見た。
こうして短い間考えるのは田島のクセだった。
「フロリダからは新しい報告はないようだが?」
「あっちも忙しいようです。あの事件が身に染みてますから。それよりこの件は国に漏れるとよくないので、博士は口にしないで下さい」
「そうはいかん。私も他人事ではないのだ」
オアシスフラワーの災厄を知る者はまだ少ない。だが、二人はその驚異をよく知っていた。
© Rakuten Group, Inc.