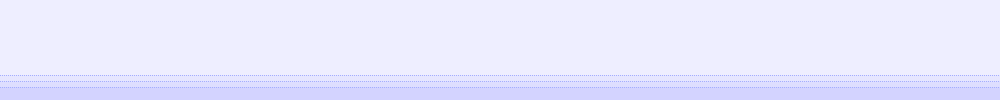冬の国の王女No.4
王さまはそう言うと王女の体をいつまでも抱きしめていました。 けれども掟を破ることはできません。 王さまとお妃はどうしても出かけなければならないのです。 それが冬の国に生まれたものの使命だからです。
「さようなら私の娘よ。 私たちはもう行かなければならない。 どうか良い子でいておくれ。 この仕事が終わったらこれからはずっといっしょにいられるのだからね。」
王さまはとてもなごりおしそうでした。
「さようなら。 こんど会うときはあなたにかわいい秋の花を一りん持ってきますよ。 それはそれは色鮮やかな花をですよ。 それまで待っていてちょうだいね。」
お妃はなぜかわきあがる暗い考えを押しのけるようにして言いました。 こうして二人は去って行きました。
「もう、行ってしまわれたんだわ。」
王女はくもの車に乗って北風に運ばれていく二人の姿が見えなくなるまで立っていました。 それから王女は力なくベッドにこし掛けました。 頭の痛みはもうかなり良くなっていましたが、かわりに胸のあたりがもっと痛みはじめています。 王女はいたむ胸を押さえながらベッドに横たわりました。
「なんだかとっても疲れたわ…。」
王女はぐったりとして目をつぶりました。
王女が目を閉じるとふしぎなことに国ざかいの山が見えました。 その天をつくほど高い山のふもとに、あの、小さな男の子がたった一人で行きだおれています。 男の子のうえでは吹雪が狂ったようにはげしく舞い上がり、みるみる男の子を雪の中にうずめて行きました。
そのつぎに王女が見たのは北の国の豊かな秋でした。 なだらかな丘にすこしずつ違った色がまじる美しい秋です。 黄金色の畑が風にそよぎ、風は冬の国とは違ってふんわりと命あるものをつつむように流れて行くのです。 そこにもあの小さな男の子が立っていました。 見ると男の子の顔は悲しみでくもっています。 そして北の空がすこしずつどんよりした暗い色に変わって行くのを見て男の子はなみだを流すのでした。
やがて北の国の空は今までなかったほど暗い色になりました。 鳥はさえずるのを止めて巣にもどり、風さえピタリと止みました。 すると北の空からヒューンとうなる音がして北風が一気に押しよせてきました。
北風は北の国に雪を運び、寒さで凍らせ、霜を降らせて、はげしく国中をゆさぶりました。 もう北の国には秋のおもかげなどどこにもありません。 ただはてしなく広がる雪の草原を、あの小さな男の子が秋を追いかけるかのように
「おーい、おーい!」
と叫びながら走りつづけているのです。 やがて秋を追いかける男の子は力つきて倒れました。 その男の子に吹雪が猛然とおそいかかります。 王女はあわてて荒れ狂う吹雪のまえにたちました。
「だめ! 冬の国に帰って! 王の娘のことばを聞きなさい。」
けれども王女の言葉をあざ笑うかのように吹雪は王女のわきをすり抜け男の子を襲いました。 男の子は王女の目のまえでみるみる雪の中にうずもれて行きます。
「だめよ! やめなさい! やめて!」
王女は声をかぎりに叫びました。
そのとき王女ははっとして目を覚ましました。 王女の体は汗でびっしょりになっています。 王女はいつのまにか夢を見ていたのです。 でもそれは本当に夢だと言えるのでしょうか? これが王女のしたことだとしたら…。 王女はぞっとするほどの不安にかられて、氷の馬を探しました。
しばらく氷の草原を歩いていると、遠くに馬の群れが見えました。 王女は必死になって手をふると氷の馬を呼びました。 氷の馬はすぐに王女のもとにやってきました。 氷の馬は王女を見るとびっくりして言いました。
「いったいどうなさったのですか、王女さま? お顔の色が悪うごさいますよ。」
王女はそれを聞くと、氷の馬の首に顔をうずめて泣きました。
「ああ、氷の馬よ。 私はどうしたらいいのでしょう? 私は北の国を冬に変えてしまったのです。 そのせいで作物がみんなだめになりました。 人間はもう、食べ物が手に入れられなくなったはずです。 ぜんぶ私のせいなのです。」
「王女さま・・・。 あなたさまは何もごぞんじではなかったのです。 どうしてそれがあなたさまのせいだと言えるでしょうか? もう気に病むことはございません。 昔から冬がうまく来れなかったことがなんどもあって、そのたびに人間はそれを乗り越えてたくましく生きてきたのです。 こんどのことも人間たちが何とかするはずです。 どうかもう、これ以上お苦しみにならないで下さい。」
「でも、」
王女ははげしくかぶりを振りました。
「でも、私のせいでたくさんの人が死ぬかも知れません。 私はそのことを考えると、いてもたってもいられなくなるのです。」
王女は力なくうなだれました。 長い沈黙がながれました。 氷の馬はそのあいだも王女をじっと見つめていました。
しばらくして王女が目を上げました。 見るとその目はきらきらと輝いています。
「そうだわ! 今から冬の国の実を北の国に運んだらどうかしら。 そうすればみんなが助かるわ。 おねがい、氷の馬よ、木の実を運ぶのをてつだって。」
氷の馬はおどろいて目をみはりました。
「なんと言うことをおっしゃるのです! この前もあなたさまは倒れておしまいになったというのに、こんどあの国に行ったらあなたさまはそれこそ無事ではいられませんよ。 どうか、王さまとお妃さまがお戻りになるまでお待ち下さい。」
「いいえ! お父さまとお母さまは世界中の冬が終わるまではお戻りになりません。 人間が春にまく種を食いつくす前に、どうか私を北の国につれていってください。」
王女のくちびるはかたく結ばれ、目には赤く燃える炎が宿っていました。 それを見ただけで王女の決意がどれほどのものか、氷の馬にもわかりました。 が、それでも氷の馬はうんということができません。
「お願い、お願いです。」
そう言う王女のくちびるははげしく震え、目からは涙がぽろぽろとこぼれ落ちました。 それを見ると、氷の馬の心はひどくかき乱されました。
「わかりました。 王女さまのお手伝いをいたしましょう。 きっとここの木の実は北の国でも役にたつはずです。」
氷の馬はひどく疲れた声で言いました。
「ありがとう。」
王女は馬の首を抱きしめると、ほっとしたようすで言いました。 けれども氷の馬は心配でたまりません。 それでも氷の馬は王女の願いをことわることが出来ませんでした。 こうして二人は氷の木の実を集めはじめました。
冬の国の木の実はとてもふしぎです。 その実の形はりんごによくにていたのですが、味がずいぶん違っています。 その実は甘くてみずみずしいのにミントのすっとした香りとさわやかさがあるのです。 それにこの実を食べると体に栄養がいきわたり、長くお腹がすきません。 そして食べたものの体を健康でじょうぶなものにしました。 この命にあふれた氷の木の実なら、北の国でも持ちこたえられる、と王女は思いました。
やがて王女がかかえきれないほどの木の実をかごに集めると、氷の馬はそれを自分のせなかに乗せました。 そして王女がかごをしっかりだきしめると氷の馬は飛ぶように走り出しました。
氷の馬はどんなに険しい山でもかるがると越えられる素晴らしい足を持っています。 そのうえ氷の馬の足のひとけりひとけりは力強く、たくましく、やくどう感がありました。 それに山のどんなに険しい斜面でも、氷の馬はひるむことなくかかんに駆けあがり、そして駆け下りて行きました。 やがてひとつの山を越えました。 またひとつ、またひとつ、氷の馬は休むことなく走りつづけました。 こうして氷の馬はあっというまに北の国につきました。
北の国はもうすでに冬一色です。 ゆたかだった秋の色はとうに消えて冬のくすんだ色があたりを支配しています。 かつては黄金色にかがやいた畑の穂の実も熟さないまま枯れはてて、力なく北風にひき倒されています。 そしていんきな風が葉を落とした枝をカチカチ鳴らして、気まぐれにかわいた落ち葉を吹きあげていました。
「これがあのときとおなじ北の国とはとても思えないわ。」
王女は悲しくなりました。 これらのことはすべて王女の持つ冬の力が作り出したものだったからです。 だからといって悲しんでばかりしているわけにはいきません。 この国の暖かさは冬の国のものにはとても危険だったからです。 王女はさっそく木の実を配りはじめました。
配りはじめるとかごの木のみはすぐになくなりました。 そのために王女と氷の馬はなんども冬の国と北の国のあいだを行き来しなければなりませんでした。 とにかく急がなければなりません。 残された時間はあとわずかしかないからです。
「なんてここは暖かいのかしら。」
王女は重い腕をあげて、ひたいの汗をぬぐいました。 それからかたわらの氷の馬を見ると氷の馬は暖かさにあえぎ、足も重くなっているようでした。 そのうえ全身からは汗がふきだし、息づかいも荒く、いかにも苦しげです。
「氷の馬よ。 だいじょうぶですか?」
王女がたずねると氷の馬は
「心配はございませんよ、王女さま。」
と短く答えました。
氷の馬はあきらかに無理をしていました。 王女にもそれがわかりましたが、あとすこしで木の実を配りおえるのです。 そのことを思うと、王女もだるく熱をおびた体をのろのろと動かしはじめました。
北の国の人々は苦しげに顔をゆがませ、すっかり希望をうしなっていました。 これから来るききんを思い、長くゆううつなひもじい日々を思うと、彼らの心はふさぎました。 そしてなによりも愛する家族をうしなうのではないかという恐れが、彼らの生きる力をうばって行ったのです。 人々は力を落とし顔を上げるものもいませんでした。
その姿は見ているものの心も、暗くつらいものに変えてしまいました。 だからこそ王女は力をふりしぼらなければならないのです。
氷の馬はそんな王女のためにあえぎながらもけんめいに働きました。
「すこし息を吹きかけてあげましょう。 あなたはほんとに疲れているようだから。」
そう言うと王女は馬の背なかからとびおりました。
「とんでもありません。」
氷の馬はあわてて首をふりました。
「そんなことをしたらあなたさまの命が危なくなってしまいます。 あなたさまのほうこそ弱ってらっしゃるというのに。 私はだいじょうぶです。 さあ、もういちど私のせなかにお乗り下さい。」
こうして王女と氷の馬はぜんぶの家をまわりました。
「ああ、これでぜんぶ終わったわ。 これで私たちも帰れます。 さあ、いますぐ帰りましょう。」
そういって王女が氷の馬をふりかえったとたん、ズン!という音がして氷の馬が地面に倒れました。
「どうしたの!」
王女は悲鳴をあげました。
「しっかりして! お願い、死なないで!」
王女は氷の馬にすがりつきました。 氷の馬は苦しそうに全身をふるわせ、口からあわを吹いています。
「王女さま。 どうかご心配なさらず冬の国におもどりください。 私はすこし休んでからまいりますから。」
氷の馬はそう言ってけんめいに首をもたげようとしました。 けれども氷の馬はすぐに力つきてガクリと首を落としました。
「ああ、どうしたらいいの? このままではおまえは死んでしまう。」
王女は西の空にしずむかすかな日の光でさえ、氷の馬の命をむしばんでいくのを感じました。 もう、一刻のゆうよもありません。
「氷の馬よ。 いままで私のためにつくしてくれてほんとうにありがとう。 私はそのことをけして忘れません。 おまえは私のたったひとりの友達です。 だからおまえだけはけして死なせません。」
そういうと王女は立ちあがりました。 そして静かに目をとじると大きく息をすって胸をふくらませました。 それとどうじに王女の胸にさすような痛みが走り、体じゅうの血がいっせいにわきたちました。 王女はそのあまりの熱気に気を失ってしまいそうになりました。
けれども王女はけんめいに意識を集中させました。 そうやって王女は自分の冬の力を自分の息の中にとじ込めたのです。
「おやめ下さい。 王女さま…。」
氷の馬は苦しい息の中で、けんめいに王女に呼びかけました。 けれども王女はまったく耳を貸しません。
と、つぎのしゅんかん、王女は氷の馬に冷たい息を吹きました。
フーッ!
それは、冷たい息でした。 その冷たさは空気さえもまたたくまに凍らせてしまうほどでした。 それには冬を作り出すものの命が込められていたからです。
こうして命の息を吹きかけられると、氷の馬はすぐさま立ちあがりました。 もうすでに体のほてりはおさまり、足には力強さとやくどう感がもどっています。 それを見ると王女はまんぞくそうに笑いました。
「王女さま。」
氷の馬が口をひらいたとたん、笑ったままの王女の体は砂のようにくずれおちました。
「ああ、なんと言うことをなさったのです…。」
氷の馬は何とかして王女の体をせなかに乗せようと試みました。 けれども王女の腕はだらりとたれ下がったままぴくりとも動きません。 氷の馬はあわてて冬の国に駆けもどりました。 いそがないともう時間がありません。 氷の馬の心は不安でかきむしられてしまいそうでした。
「北風よ、今すぐ王女をつれもどしてくれ。 たのむ。 早く!」
氷の馬は空をつんざく叫びを上げました。 その声を聞いてあわてて北風がやってきました。
「さあ、急ぐんだ!」
氷の馬は北風のまえを風よりも早く走り出しました。 こうしているあいだにも王女の小さな命はいつ、つきるか知れないのです。
「王女さま!」
氷の馬は絶望と後悔に押しつぶされてしまいそうになりました。 そのうえ気が狂いそうなほどの悲しみが波のうねりのようにいくどもおしよせて来るのです。
「ああ、あの時なんとしてもおとめするんだった。 ああ!!」
氷の馬は狂ったように叫び声を上げました。
やがて王女の姿が見えました。 その王女の姿はいつもよりほんのわずか小さく感じられます。 氷の馬はそれを見るとはっとしてその場に立ちすくみました。 もうどうしていいのか分かりません。
「さあ、王女さまをお連れするんだ!」
北風が雲を集めて王女の体をふわりと浮かしました。 氷の馬はあわてて王女のそばによりました。
「どうかしっかりなさってください。」
氷の馬はけんめいに王女に語りかけました。 王女はうっすらと目を開けると小さくうなずきました。 その目には沈んで行く太陽の光が赤々とうつしだされています。 その燃えるような赤い色は王女に死の影をおとしていました。
「急げ! 急ぐんだ!」
王女を乗せた北風はぐんぐん飛んで北の国をあとにしました。 けれども王女の命はもう消えかかっていたのです。
「王女さま、冬の国が見えてまいりました。 もう少しのしんぼうでございますよ。」
氷の馬は必死になって言いました。
「ありがとう…。」
王女はかすかに唇をうごかしました。 そしてやさしいほほ笑みを浮かべると静かに目をとじました。
「王女さま! 王女さま!」
氷の馬がいくら呼んでも王女の目は開きません。 王女は死んでしまったのです。
「うおおお!」
氷の馬は空にむかって叫びを上げました。 けれども空も大地も氷の馬にこたえてはくれません。 それらのものはいつものようにただ、静かに存在し、氷の馬の叫びを吸いとって行くだけでした。
やがて、亡くなった王女の体はつゆが朝日に消えて行くように西日の中にすっと消えて行きました。 あんなに美しかった王女の姿はもうどこにもありません。
「王女さま! ああ、何てことだ!」
残された氷の馬は、王女が消えた空を北風に乗って狂ったようにかけまわりました。
「王女さま! 王女さま!」
空はすこしずつ暗くなり、やがてまっくらな闇があたりをおおいました。 その闇の中にひとつ、またひとつと小さな光がまたたきました。
「もしかしたら王女さまは星になってしまわれたのだろうか?」
氷の馬はその光のまたたきの中に消えてしまった王女の姿を見つけ出そうと、なおも走りつづけました。 けれども王女のひとみほどやさしく輝く光はどこにもありません。
その日、北の国の人たちは戸口にある冬の国の木の実を見つけました。 その実は一口食べるとひんやりすずしい冬の味がしました。 それなのに食べた後にはほんのりと甘くやさしい感触が広がり、かめばかむほど包みこむようなさわやかなかおりただよいました。 またのどを通るとすぐにひもじさを忘れられます。
「なんてふしぎな木の実だろう。」
「それにこの実のおいしいことといったら!」
「これはきっと神様の贈り物にちがいないよ。」
その喜びの声は国じゅうに広がって、西の空でなきさけぶ氷の馬の声をかき消してしまいました。
ところが空を見上げていたあの小さな男の子は、ひげの父親を呼んで言いました。
「ねえ、お父さん。なんだか空がとっても悲しそうだよ。」
男は窓から広がる空と星をながめました。
「ほんとうだね。 なんだか空を見ているとだれかが泣いているように見えるね。」
「うん、それにどうしてだか僕の大切なひとがいなくなったように感じるんだよ。」
男は息子をだきあげるともういちど空を見上げました。 自分がおなじ気持ちなのをふしぎに思いながら。
© Rakuten Group, Inc.